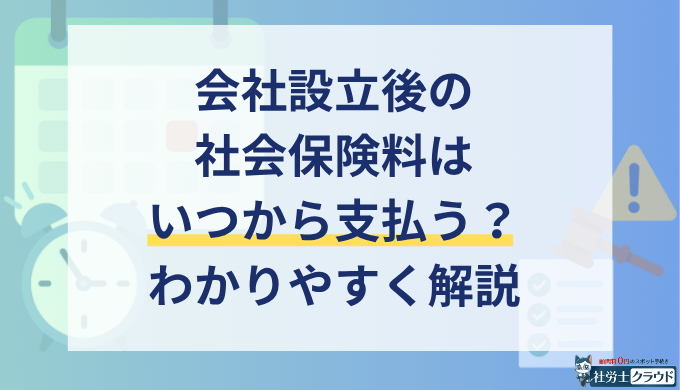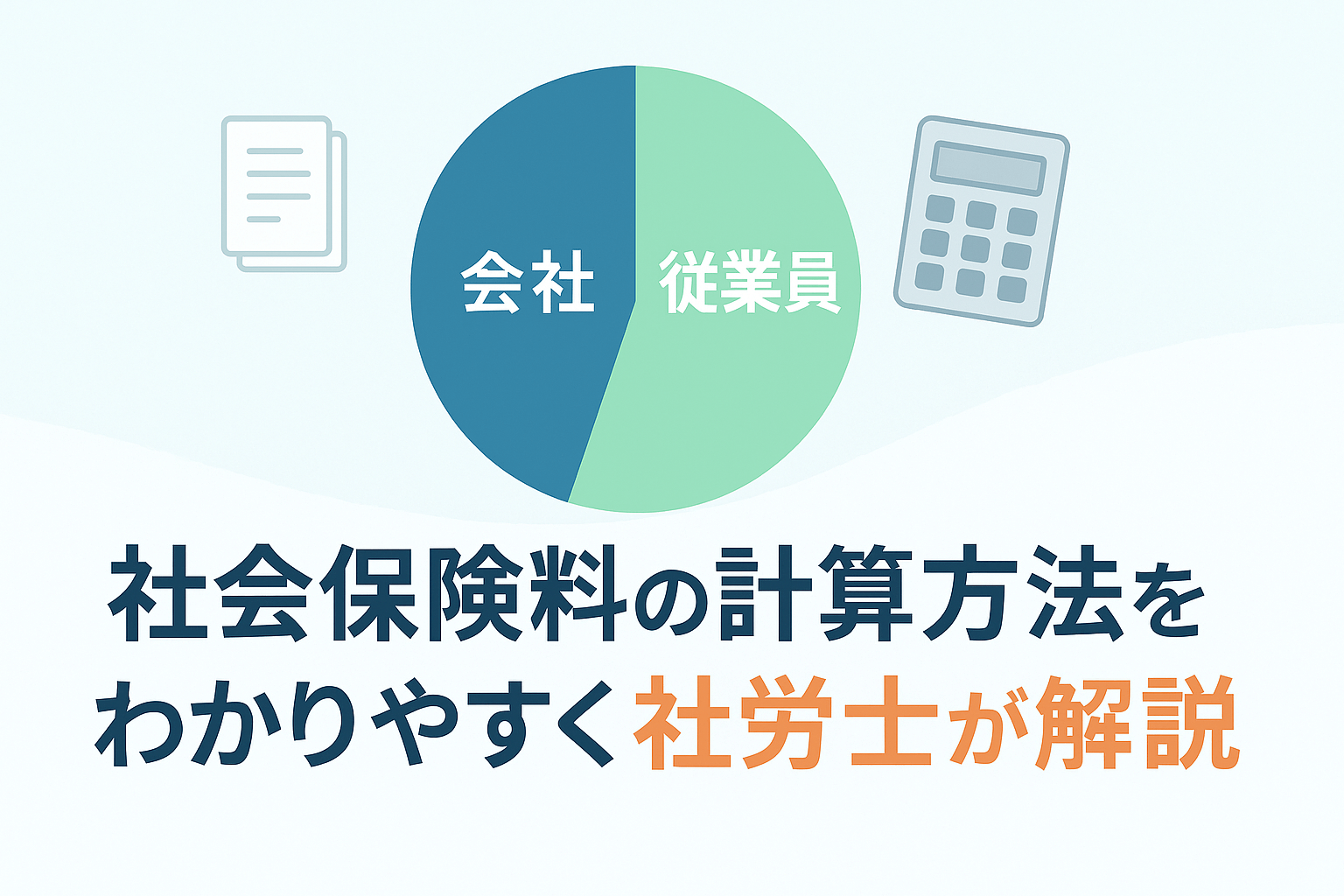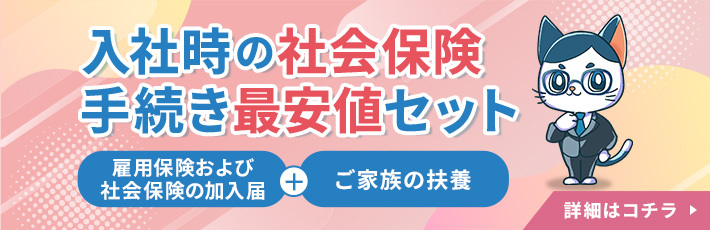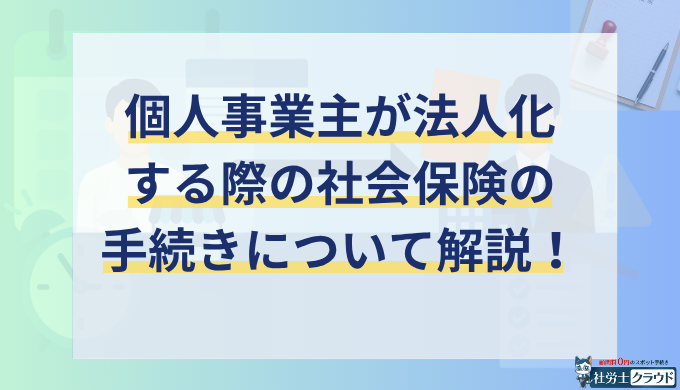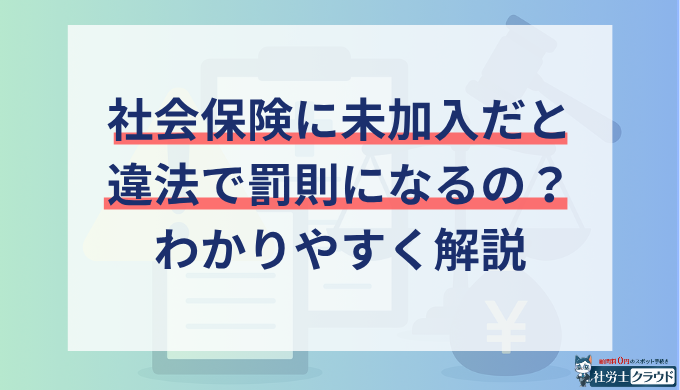会社を設立すると、たとえ社長一人の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入と保険料の納付が法律で義務付けられます。
では、その社会保険料は具体的にいつから支払いが始まるのでしょうか?
原則として、社会保険料は会社を設立した「設立月」から満額発生し、その月の保険料を「翌月末日」までに納付するのが基本ルールです。
ただし、設立初月は注意が必要です。「①保険料の発生(当月)」、「②会社から国への納付(翌月末)」、「③給与からの天引き(多くは翌月支給の給与)」という3つのタイミングがずれるため、資金繰りの管理が非常に重要になります。
この記事では、会社設立後の社会保険料について、「いつから発生し、いつ支払うのか」という基本ルールから、初回納付の流れ、給与からの天引きパターン、そして設立時に注意すべきポイントまで、分かりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
社会保険料は会社を設立したその「月」から1か月分が満額発生します。日割りはなく、月単位での計算です。
そして、その月に発生した保険料を、会社が「翌月の末日」までに年金事務所へ納付するのが基本ルールです。
例えば、4月に会社を設立したら、4月分の保険料が発生し、それを5月末日までに納付します。
ここで設立者が注意すべき最も重要な点は、「①保険料の発生(設立月)」、「②会社から国への納付(翌月末)」、「③従業員給与からの控除(多くは翌月支給の給与)」という3つのタイミングがズレることです。
設立初月は、会社が保険料を納付する時期と、従業員から天引きできる時期が必ずしも一致しないため、設立直後のキャッシュフロー(資金繰り)に影響します。
ここでは、この「発生」「日割り」「納付」の3つのポイントについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。
社会保険料は社会保険に加入した「月」から1か月分が発生する
社会保険料の支払いが始まるのは、原則として社会保険に加入した日が属する「月」からです。
法律上、この設立日が社会保険の「資格取得日」とみなされ、「被保険者の資格を取得した日の属する月」から保険料が計算されるルールになっているためです。
具体例を挙げると、もし4月10日に会社を設立した場合、資格を取得したのは「4月」ということになります。その結果、会社は4月分の保険料から支払い義務を負います。
このルールは、たとえ社長が1人しかいない会社であっても、例外ではありません。
法人は、設立した日から社会保険に加入することが義務付けられている「強制適用事業所」となります。
社長(役員)が会社から報酬を受け取って働く実態があれば、社長本人の資格取得によって会社全体が社会保険の適用事業所となるため、設立したその月から社会保険料が発生します。
[補足]法人は社長1人(役員1名)であっても、報酬を受けて使用される実態があれば、設立日から社会保険の強制適用事業所となり、加入義務があります。 一人社長の社会保険加入について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
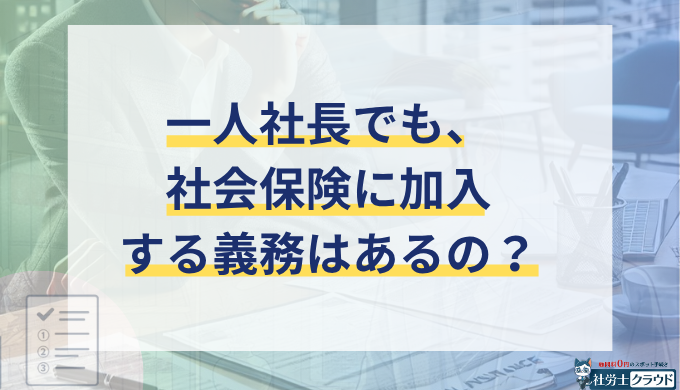 一人社長でも社会保険の加入は義務?会社設立した時の手続きと必要書類をわかりやすく解説
一人社長でも社会保険の加入は義務?会社設立した時の手続きと必要書類をわかりやすく解説
社会保険料は日割り計算されない
社会保険料を計算する上で最も重要な注意点は、日割り計算の仕組みがないことです。保険料は常に月単位で計算されます。これは法律(健康保険法・厚生年金保険法)で、資格を取得した「月」単位で計算されると定められているためです。
そのため、例えば4月1日に会社を設立した場合でも、4月30日に設立した場合でも、どちらも「4月」に資格を取得したことに変わりはなく、「4月分」として1ヶ月分の保険料が満額発生します。
この「月単位」の仕組みを誤解していると、「月末加入だから負担は軽いはず」と考えてしまい、設立直後の資金計画にズレが生じるため注意が必要です。
特に設立日を4月30日にすると、実質的にはたった1日の加入で1ヶ月分の保険料を支払うことになります。
【実務上のコツ】
もし設立日の日程に自由度があるなら、登記申請を1日ずらして5月1日設立にすることも検討の価値があります。こうすることで4月分の保険料負担をまるごと回避でき、初回の支払いは5月分から(納付は6月末から)にできます。
設立初期のキャッシュフローを温存する有効な選択肢ですが、事業計画や許認可の都合など、他の日程との兼ね合いも見て総合的に判断することが大切です。
会社は「翌月末日」までに年金事務所へ納付する
設立月(資格取得月)に発生した社会保険料は、翌月の末日(納付期限)までに会社が納付します。
例えば、4月に設立した場合、4月分の保険料は5月31日が納付期限となります。
ここから逆算して、初めての納付は以下の流れで進みます。
【初回納付の主な流れ】
1.手続き(設立から5日以内)
会社を設立したら5日以内に、管轄の年金事務所へ「新規適用届」や「被保険者資格取得届」といった書類を提出します。
2.納付書の到着(翌月中旬)
書類が処理されると、翌月の中旬(15日〜20日頃)になって、年金事務所から「保険料決定通知書」と「納入告知書(納付書)」が会社に郵送されてきます。
3.納付(翌月末まで)
会社はその納付書を使って、記載されている金額(会社負担分と本人負担分の合計額)を、納付期限(翌月末)までに金融機関やPay-easy(ペイジー)で支払います。
初回の納付は、この納付書で行うのが前提です。
便利な口座振替の手続きも並行して申請できますが、手続きが完了するまでに1〜2ヶ月かかるため、初回納付には間に合わない前提で準備してください。
納付が期限を過ぎると延滞金が発生するため、必ず期限内に納付しましょう。
特に設立初月は、「保険料の発生(帳簿上の負債)」と「実際の納付(現金の支払い)」に1ヶ月のズレが生じます。このズレを設立初期の資金繰り表にしっかり反映しておくと安全です。
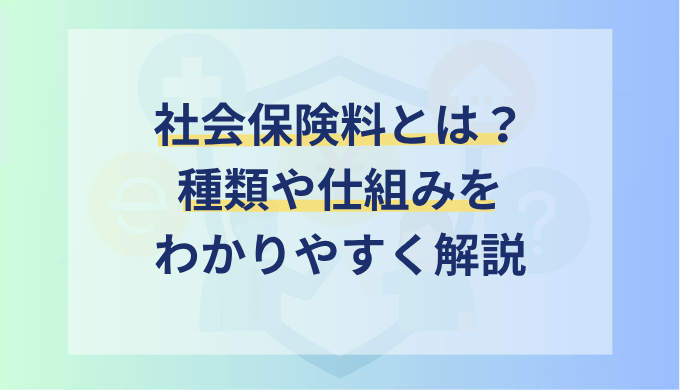 社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
社会保険料の給与からの天引き開始時期は法律で「この日」と一律には決まっておらず、会社の給与ルール(締日・支払日・控除方法)で定めることになります。
実務上、方法は「翌月徴収」と「当月徴収」の2つがあります。
「翌月徴収」は、4月分の保険料を、5月に支給する給与から天引きする方法です。「当月徴収」は、4月分の保険料を4月支給の給与から天引きします。
創業期の管理のしやすさと計算の誤差の少なさを考えると、「翌月徴収」を強くおすすめします。
なぜなら、会社の納付タイミング(4月分を5月末に納付)と、給与からの天引きタイミング(5月支給の給与)が一致し、管理が非常にしやすいからです。
一方で「当月徴収」を採用する場合は、就業規則や給与規程にその旨を明記し、従業員へ周知する必要があります。
ただし、設立初月は保険料の正確な金額が給与計算に間に合わない(確定が遅れる)ことが多く、概算で天引きして後日精算するといった手間が発生しやすい点に注意が必要です。
創業直後は、この納付と控除の「ズレ」が資金繰りに直接影響します。自社の給与サイクルに合わせて、どちらのルールを採用するかを明確に決めておくことが重要です。
具体的な給与サイクル別に、いつから天引きが始まるのかをケースごとに解説します。
ケース1:月末締め・翌月25日払い(翌月徴収)の場合
「月末で締めて、翌月の25日に支払う」会社が、「翌月徴収」を採用しているケースです。これは、最も一般的で管理がしやすい給与サイクルです。
前提として、4月10日に会社を設立し、社長(または従業員)が同日入社したとします。
5月25日の給与は4月1日〜4月30日勤務分の支払いであり、この給与から初めて4月分の社会保険料(本人負担分)を控除します。
会社は、控除した本人負担分と会社負担分を合算し、5月末日までに年金事務所へ納付します。
この方式は、控除(5月給与)と納付(5月末)が同じ月にそろうため、差額の立替や精算が少なく、仕訳や資金繰りの管理が簡単です。
創業初月は現金の出入りをシンプルに保つことが重要です。
給与明細には「4月分 社会保険料」と控除対象月を明示し、入社月の従業員にもズレの仕組みをわかりやすく説明しておくと、問い合わせ対応の負担を減らせます。
ケース2:20日締め・当月末払い(翌月徴収)の場合
次に、給与の締日と支払日が同じ月内に収まるサイクル(例:20日締め、当月末払い)の会社が、「翌月徴収」を採用しているケースです。
前提として、4月10日に会社を設立し、入社したとします。
4月30日支給の給与は4月10日〜4月20日の短い期間の支払いですが、翌月徴収のためこの給与からは社会保険料を控除しません(0円)。
翌月の5月31日支給給与(4月21日〜5月20日勤務分)で、初めて4月分の社会保険料(本人負担分)を控除します。
設立直後の最初の給与に控除が無いことで「手続き漏れでは?」と不安になりがちです。しかし、翌月徴収のルールに沿った正常な処理です。
会社側は「初回控除は翌月給与から」「会社は4月分を5月末に納付」という2点を事前に周知します。この方式でも、控除(5月給与)と納付(5月末)は同月にそろい、管理は安定します。
ケース3:20日締め・当月25日払い(当月徴収)の場合
最後に、実務上はあまりおすすめできない「当月徴収」を採用した場合のケースです。給与サイクルは「20日締め、当月25日払い」とします。
前提として、4月10日に会社を設立し、入社したとします。 4月25日には、4月10日〜4月20日勤務分の給与が支払われます。
「当月徴収」ルールでは、この4月25日に支払う給与から、4月分の社会保険料(本人負担分)を天引きすることになります。
しかし、この方法は設立時にはおすすめできません。
なぜなら、給与計算を行う時点(例えば4月21日頃)では、年金事務所での手続き(資格や標準報酬月額の確定)が完了しておらず、会社は4月分の正確な保険料額をまだ把握できていないことが多いからです。
保険料額が未確定のままでは、見込み額(概算)で天引きし、後日(翌月以降)に確定額との差額を精算する、という非常に面倒な作業が発生します。
これは給与計算のミスを引き起こす大きな原因となり、創業直後の人的・時間的余裕が少ない時期には大きな負担となります。
もし当月徴収を運用する場合は、①給与規程に明記すること、②概算控除と確定後の精算方法、③退職・休職時の精算手順などを、文書でしっかり整備しておく必要があります。
[補足ケース4] 月末締め・当月末払いの場合
給与サイクルが「月末締め・当月末払い」という会社もあります。この場合、徴収ルールによって以下のような違いが出ます。
◯翌月徴収(前月分を控除)の場合
初回(4月末)の給与では控除できません(前月がないため)。会社は4月分の保険料(本人負担分含む)を5月末に立替えて納付し、翌月(5月末)の給与から4月分を天引きすることになります。従業員の退職時には、最後の月の保険料を忘れずに精算する必要があります。
◯当月徴収(当月分を控除)の場合
初回(4月末)の給与から4月分を天引きします。ただし、上記のケース3と同様に、給与計算の時点(4月末)までに正確な保険料額が確定していないリスクがあり、実務が難しくなります。
会社設立の直後は、保険料の「発生月」「納付期限」「給与からの控除開始」がずれやすく、迷いやすい場面が続きます。
とくに月末設立や、従業員の入社日がずれたとき、役員報酬をどう設定するかで取り扱いが変わります。
ここでは、会社を設立する方が特に疑問に思う、判断の拠り所と実務上の注意点をまとめました。 読みながら、自社の給与サイクルや就業開始日、役員報酬の金額設定を具体的に当てはめて確認してください。
月末(4月30日)に設立しても、4月分の保険料が全額かかりますか?
社会保険料は、会社設立が月末であっても全額(1ヶ月分)かかります。社会保険料は月単位で計算されるため、日割り計算の仕組みはありません。
法律上のルールとして、資格取得日(=会社設立日)が4月30日の場合、「4月」に資格を取得したことになります。そのため、たとえ加入期間が1日だけであっても、4月分の保険料が満額徴収されます。
もし設立日の調整が可能であれば、登記申請を1日ずらして5月1日に設立すると、4月分の保険料は発生せず、保険料の支払いは5月分から(納付は6月末から)となります。これは設立初期の資金繰りを少し楽にする方法の一つです。
従業員の入社が設立日とズレた場合、いつから加入ですか?
従業員の社会保険料は、その従業員の「入社日(=雇用契約開始日)」が属する月から発生します。
社会保険の加入資格は、社長(役員)と従業員、それぞれ個人ごとに判定されます。社長の資格取得日(=設立日)と、従業員の資格取得日(=入社日)は別々に考えます。
具体例で見てみましょう。
ケース①: 会社設立が4月10日、従業員Aさんの入社日も4月10日の場合
→ Aさんの社会保険料は、入社日が属する「4月」分から発生します。
ケース②: 会社設立が4月10日、従業員Bさんの入社日が5月1日の場合
→ Bさんの社会保険料は、入社日が属する「5月」分から発生します(4月分はかかりません)。
このように、従業員の入社時期が設立日と異なる場合、社会保険料が発生する月や、給与から天引きを開始するタイミングが人によってズレることになります。そのため、従業員ごとの資格取得日を正確に管理することが重要です。
役員報酬を0円にしたら、保険料はかかりませんか?
実態によりますが、恒常的に報酬0円で勤務実態もほとんどない場合、そもそも社会保険の加入要件を満たさず「加入不可」となり、保険料は発生しません。
これはよく誤解される点ですが、社会保険の被保険者となる前提は「適用事業所に使用され、報酬を受ける者」であることです。
そのため、恒常的に(常に)役員報酬が0円で、役員としての勤務実態もほとんどないような場合は、この「報酬を受ける」という要件を満たさないと判断され、原則として社会保険の資格を取得できません(または資格を喪失します)。
この場合、社長個人は国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ただし、注意点があります。
一時的に役員報酬が0円になっただけで、会社には在籍し続けている場合や、報酬額が非常に低い(例えば月額3万円など)場合は異なります。
この場合は、「資格喪失届」を年金事務所に提出しない限り、社会保険の資格は継続します。
資格が継続する場合、保険料は健康保険・厚生年金の最低等級に基づいて計算され、発生し続けます。 報酬が0円または極端に低い場合、給与から本人負担分の保険料を天引きできません。
その結果、会社が本人負担分も立て替えて年金事務所へ納付し、後で本人から回収する(会社から役員への貸付金として管理する)という、非常に複雑な処理(債権管理)が発生します。
役員報酬の設定については、社会保険への影響も含めて慎重に検討する必要があります。
特に報酬を見直す際は、実際の勤務実態と報酬額(標準報酬月額)の整合性を確認し、取締役会での決議や役員報酬規程での明確化といった会社法上の手続きも適切に行うようにしましょう。
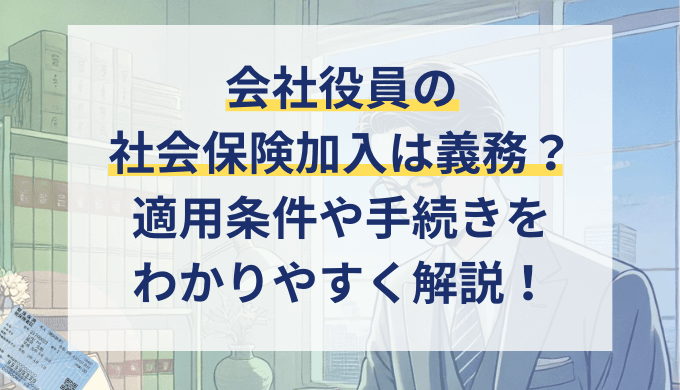 会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
会社設立時の社会保険料の費用はいくら?
設立時の社会保険料は、設立時に届け出る役員報酬(月給)を「標準報酬月額等級表」に当てはめて決まり、その金額を会社と本人(役員・従業員)で半分ずつ(折半して)負担します。
会社設立後、最初に提出する「被保険者資格取得届」には、役員や従業員の報酬月額を記載します。年金事務所は、この届け出た報酬月額を「標準報酬月額等級表」という表に当てはめて、その人の社会保険料の基準額(標準報酬月額)を決定します。この最初の決定方法を「資格取得時決定」と呼びます。
決定された標準報酬月額に、健康保険料率と厚生年金保険料率を掛けて保険料が計算されます。
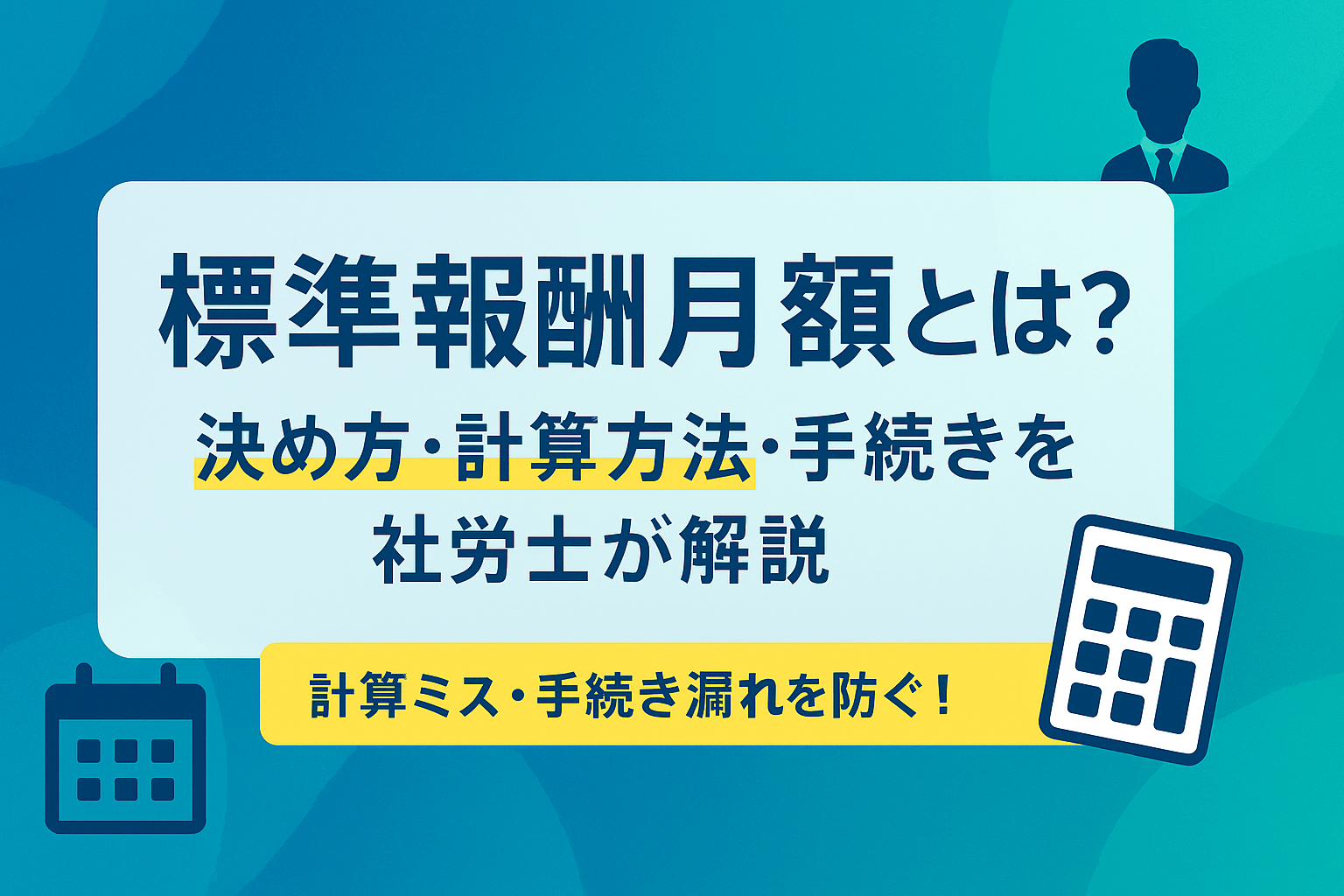 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
【具体例:役員報酬30万円の場合】 (東京都・40歳未満・令和7年度の保険料率で計算)
- 役員報酬(月額):300,000円
- 標準報酬月額:300,000円
- 健康保険料(9.91%):29,940円
- 厚生年金保険料(18.300%):54,900円
- 合計保険料(月額):84,630円
この合計額84,63円を、会社と本人が半分ずつ負担します。
- 本人負担額:約42,315円 (←給与から天引きされる額)
- 会社負担額:約42,315円 (←会社の経費(法定福利費)となる額)
つまり、会社としては毎月84,630円弱の社会保険料を納付する必要があります。
※健康保険料率は都道府県によって異なります。 ※40歳以上65歳未満の場合は、上記に加えて介護保険料(令和7年度は1.59%)が上乗せされます。
正確な保険料額は、加入する健康保険組合(多くは協会けんぽ)のウェブサイトで確認できます。
参考)令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
また、具体的な計算方法やシミュレーションについては、以下の記事やツールも参考にしてください。
なお、ここで解説した「資格取得時決定」は設立時のルールです。翌年以降の社会保険料は、原則として毎年4月から6月の給与に基づいて見直されます(定時決定)。
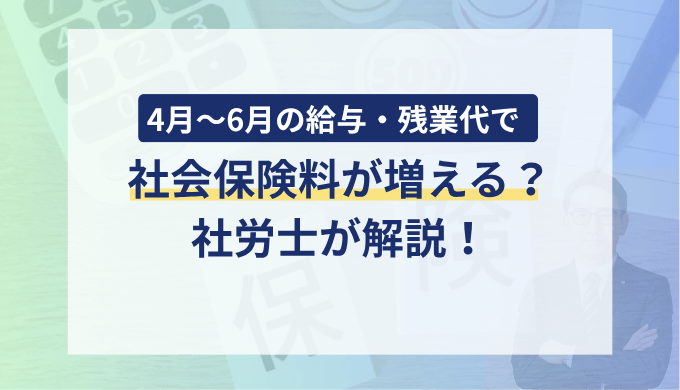 社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説
社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説
会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きが必要です。
設立後(登記後)原則5日以内に、管轄の年金事務所へ「新規適用届」などの書類を提出する義務があります。 この「5日以内」という期限は非常に短いため、注意が必要です。
もし手続きが遅れると、年金事務所から指摘を受けたり、過去にさかのぼって保険料を支払うよう求められたり(遡及請求)、延滞金が発生したりする可能性があります。 設立準備の段階から、必要な手続きと書類を把握し、計画的に進めることが大切です。
手続きは、会社の所在地を管轄する「年金事務所」または「事務センター」で行います。 会社設立後5日以内に提出が必要な主な社会保険の届出・書類は、主に次の3つです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
これらの届出書の内容と、主な添付書類は以下の表の通りです。
| 届出書 | 書類の内容 | 添付書類 |
| 社会保険 新規適用届 | 法人が社会保険に加入するために必要な書類 | ・法人登記事項証明書 ・法人番号指定通知書(のコピー) など |
| 社会保険 被保険者資格取得届 | 法人の代表や従業員が個別に社会保険へ加入する際に必要な書類 | (基礎年金番号が不明な場合などに追加書類が必要なケースあり) |
| 被扶養者異動届 | 家族を扶養に入れる際に必要な書類 | 被扶養者の認定に必要な書類 ・続柄確認書類(住民票など) ・収入確認書類(課税証明書など)が必要な場合あり |
(※参考リンク 「会社設立 社会保険の手続き」記事への内部リンクをここに配置)
補足:従業員を雇用する場合は労働保険(雇用保険・労災保険)も必須
会社設立時の手続きとして忘れてはならないのが、「労働保険」です。 従業員(パート・アルバイト含む)を一人でも雇う場合は、これまで説明してきた社会保険とは別に、労働保険への加入手続きも法律で義務付けられています。
「労働保険」とは、「労災保険」(仕事中や通勤中のケガなどに対する保険)と「雇用保険」(失業した場合の給付金など)の総称です。
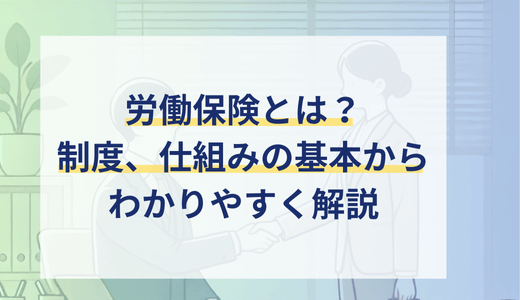 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
手続きは社会保険とは異なり、以下の2つの役所で行います。
1.労働基準監督署 での手続き(主に労災保険)
| 書類名 | 提出時期 | 提出方法 |
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した翌日から50日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
※労災保険料は全額会社負担です。
2.ハローワーク での手続き(主に雇用保険)
| 届出書 | 書類の内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用を受けるための事務所の設置を届け出る書類 | 雇用した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の被保険者資格を取得したことを届け出る書類 | 雇用した月の翌月10日まで |
社会保険の手続き(年金事務所)とは別に、労働保険の手続き(労働基準監督署、ハローワーク)も必要になる、という点をしっかり覚えておきましょう。
なお、社長一人だけの会社(役員のみ)の場合は、原則として労働保険の加入対象外となります。
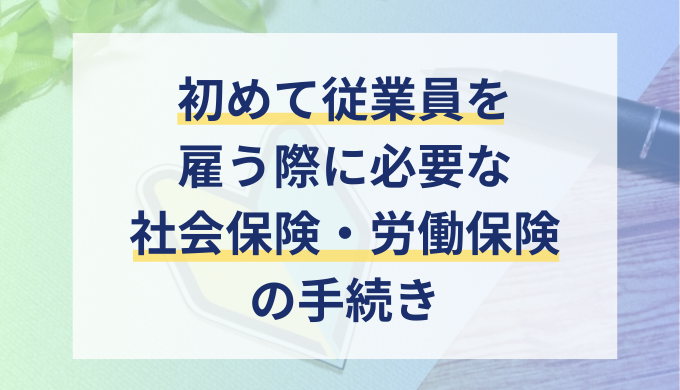 初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
会社設立後の社会保険料は、設立した月から1か月分が満額発生します。月の途中で設立しても日割り計算はなく、月末に設立した場合でも1か月分まるごと発生する点に注意が必要です。
会社は、発生した月の保険料を翌月の末日までに納付します。
特に設立初月は、「保険料の発生(設立月)」、「会社から国への納付(翌月末)」、「給与からの天引き(多くは翌月支給の給与)」という3つのタイミングがずれることを理解しておくことが重要です。
この“ズレ”を前提に、設立日から逆算して早めに手続きを進めることが大切です。初回の納付は納付書での支払いになるため、あらかじめその分の資金を確保しておくと安心です。
また、給与からの天引きルール(翌月徴収か当月徴収か)を給与規程などで明確にし、納付期限などを社内でしっかり管理することで、設立初月のミスを防ぐことができます。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。
社会保険の「新規適用届」「被保険者資格取得届」など、会社設立直後に必要な手続きをオンラインでスムーズに進められます。
▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由
1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)
2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)
3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)
社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。
まずは、お気軽にご相談ください。 「設立時の手続き、具体的に何から始めればいい?」 「期限(5日以内)が迫っているけど間に合う?」 「うちの場合、初回の社会保険料はいつ、いくら払うことになる?」 といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。
複雑な手続きや保険料の管理は専門家に任せて、安心して事業のスタート準備に集中しませんか。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|