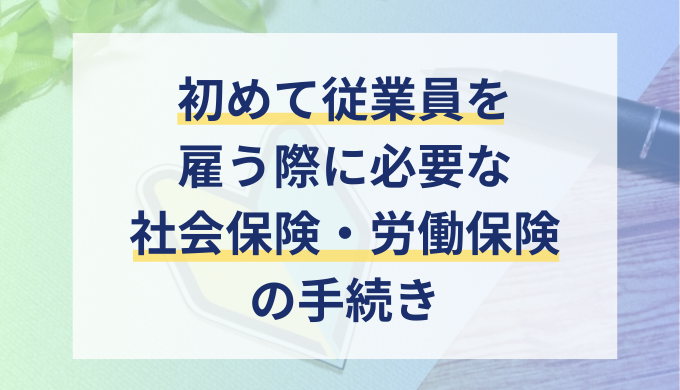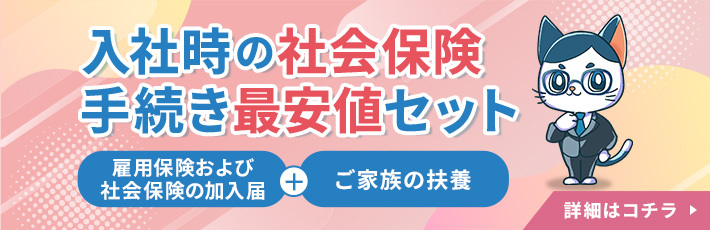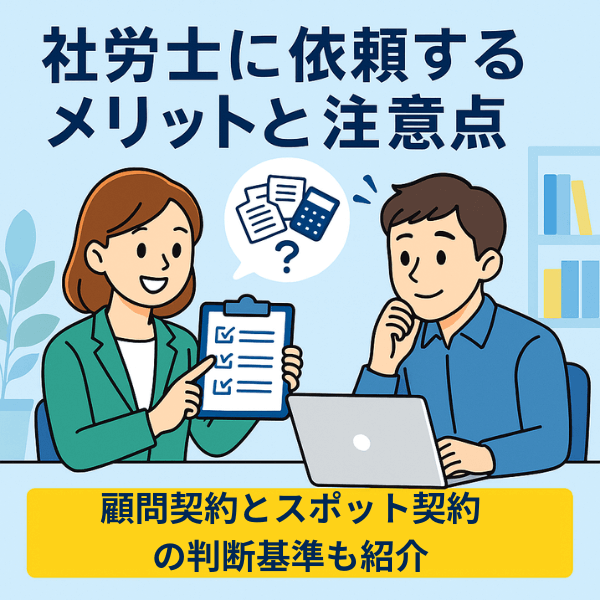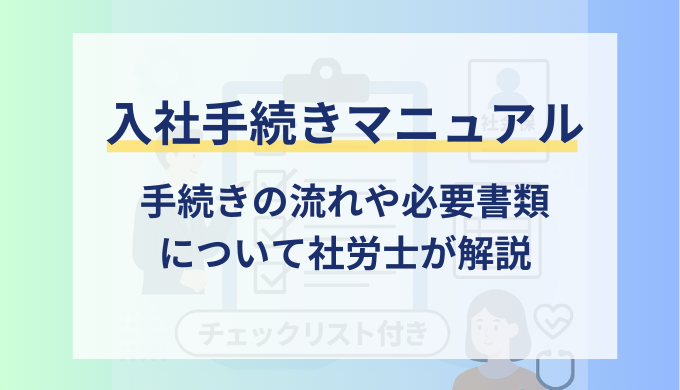初めて従業員を雇うとき、「社会保険や雇用保険、何から手を付ければいいのか」「提出先や期限を間違えないか」といった不安で、本来注力すべき事業の準備が滞ってしまうことは少なくありません。
人を雇用する際には、社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(労災・雇用保険)への加入手続きが法律で義務付けられています。加入手続きには厳格な期限があり、もし遅れると罰則だけでなく、従業員の保険証が発行されず医療費が自己負担になるなど、深刻な事態を招きかねません。
本記事では、初めて従業員を雇用した会社が行うべき社会保険・労働保険の手続きを、提出書類から正しい流れ、注意点まで社労士が分かりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
YouTubeでも従業員の入社時に会社側が行う社会保険と労働保険の手続きについて詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
従業員を一人でも雇用した場合、会社には社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きを行う法律上の義務があります。
社会保険・労働保険の手続きは種類が多く、提出先や期限もバラバラなため、難しく感じるかもしれません。しかし、最初に全体の流れと必要な書類を把握すれば、一つひとつ着実に対応できます。
重要なのは、届出書の作成に取り掛かる前に、法的な土台となる準備を済ませておくことです。届出書を作成する前に、次の3つの準備を済ませておきましょう。
- 労働契約の締結
- 法定三帳簿の整備
- 従業員からの情報収集
従業員を雇用する上で前提となる労働契約の締結や法定三帳簿の整備については、下の記事で詳しく解説しています。
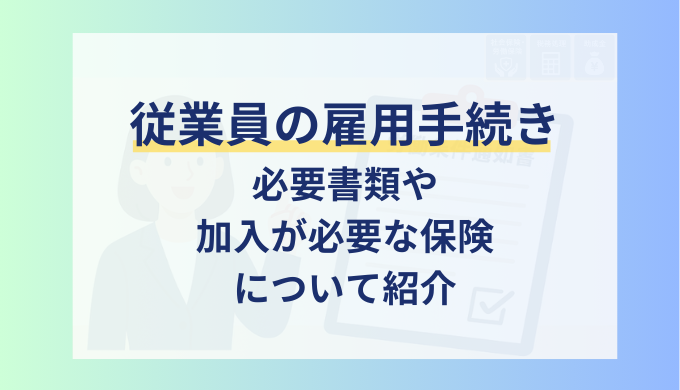 従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
準備が整ったら、チェックリストに沿って手続きを進めていきましょう。
| 届出名 | 目的 | 提出先と期限 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 社会保険新規適用届 | 会社自体が社会保険の適用事業所になるための届出 | 提出先: 年金事務所 期限: 事実発生から5日以内 | 法人設立時に提出済みの場合が多い。 |
| 被保険者資格取得届 | 従業員を健康保険・厚生年金に加入させるための届出 | 提出先: 年金事務所 期限: 雇用開始から5日以内 | 健康保険証の発行に関わるため、最優先で対応する。 |
| 被扶養者(異動)届 | 従業員の扶養家族を健康保険に加入させるための届出 | 提出先: 年金事務所 期限: 資格取得届と同時 | 扶養に入れるには収入などの厳格な要件がある。 |
| 保険関係成立届 | 会社が労働保険の適用事業所になるための最初の届出 | 提出先: 労働基準監督署 期限: 雇用日の翌日から10日以内 | 全ての手続きの起点。この届出で労働保険番号が決まる。 |
| 適用事業報告 | 事業場が労働基準法の適用対象であることを報告 | 提出先: 労働基準監督署 期限: 遅滞なく | 事業場(店舗・支店)ごとに提出が必要。 |
| 労働保険の概算保険料申告書 | その年度の労働保険料を概算で前払いするための申告・納付 | 提出先: 労働基準監督署、金融機関など 期限: 成立日の翌日から50日以内 | 申告と納付の両方が必要。 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 会社を雇用保険の適用事業所として登録するための届出 | 提出先: ハローワーク 期限: 設置日の翌日から10日以内 | 労基署で受け取った保険関係成立届の控えが必要。 |
| 被保険者資格取得届 | 従業員を雇用保険に加入させるための届出 | 提出先: ハローワーク 期限: 雇用した月の翌月10日まで | 設置届と同時に提出することが多い。 |
手続きの流れを整理すると、基本的には次の3ステップで進めるとスムーズです。
という順番です。この流れを守ることで、各制度が正しく連携し、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
社会保険に加入する際は、年金事務所へ複数の届出を提出する必要があります。
この手続きの特徴は、提出期限が「5日以内」と非常に短いことです。これは、従業員とその家族が早急に健康保険証を受け取り、医療を安心して利用できるようにするために定められています。
期限を守るためにも、これから紹介する3つの届出の内容を事前に理解しておくことが大切です。
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
会社が「社会保険新規適用届」を提出して社会保険の適用事業所となったら、次に役員や従業員を社会保険に加入させる手続きとして、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出します。
この届出を行うことで、従業員はマイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」が使えるようになります。2024年12月2日以降、従来のカード型の健康保険証は新規発行が停止されたため、この手続きが保険証利用の前提となります。
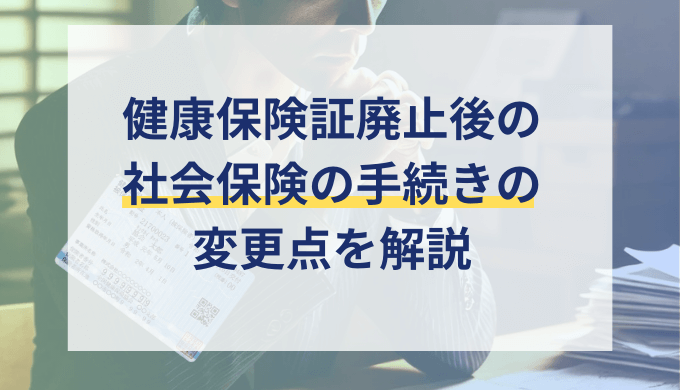 健康保険証の廃止で2024年12月2日から社会保険手続きはどう変わった?マイナ保険証についても解説
健康保険証の廃止で2024年12月2日から社会保険手続きはどう変わった?マイナ保険証についても解説
提出期限は従業員を雇用した日(資格取得日)から5日以内で、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届け出ます。届出書には、従業員の基礎年金番号又はマイナンバーの記入が必須となるため、事前に確認しておきましょう。
電子申請を利用した場合、審査期間はおよそ2週間程度です。その後、従業員の資格情報に関するお知らせは事業所の登録住所に送付されます。会社は、届いた情報を速やかに従業員に伝える役割を担います。
会社がこの手続きを怠ると、従業員は保険診療を受けることができず、医療費を全額自己負担しなければならなくなるため、迅速かつ正確な対応が求められます。
マイナンバーカードを持っていない、または保険証としての利用登録を行っていない従業員には、申請に基づいて「資格確認書」が発行されます。
この資格確認書は、従来の健康保険証の代わりとなる書類です。事業主は「資格取得届」を提出する際に、新様式に設けられる「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れることで、従業員に資格確認書が交付されるよう手続きできます。
健康保険被扶養者(異動)届
採用した従業員に、生計を共にしている配偶者やお子さんなどの扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要です。
この届によって家族が健康保険に加入でき、国民年金では「第3号被保険者」として扱われ、保険料の納付が免除されます。
一般的に、従業員の資格取得届と同時に提出します。
被扶養者として認定されるには、年間収入が130万円未満であるなど厳格な収入要件があります。場合によっては、続柄や収入状況を証明する書類の添付を求められる場合もあるため、従業員から事前に必要な資料を集めておきましょう。
社会保険新規適用届(未加入の場合)
会社自体がまだ社会保険の適用事業所として登録されていない場合、まず「社会保険新規適用届」を提出し、会社そのものを社会保険に加入させる必要があります。従業員が加入するための、大前提となる手続きです。
法律上、社会保険への加入が義務付けられた事業所を「強制適用事業所」と呼びます。
株式会社や合同会社といった法人の事業所は、業種や従業員数に関わらず、すべてこの強制適用事業所に該当します。役員報酬を受けている社長が一人しかいない、いわゆる「一人社長」の会社であっても加入義務がある点には特に注意が必要です。
また、個人事業所であっても、常時5人以上の従業員を雇用する場合(農林水産業やサービス業などの一部を除く)は、強制適用事業所となります。
多くの法人は会社設立登記の際に手続きを済ませていますが、もし未加入の場合は、適用事業所となった日から5日以内に、法人登記簿謄本などを添付して管轄の年事務所へ提出しなければなりません。
この手続きが遅れると、将来、年金事務所の調査が入った際に過去に遡って社会保険料を支払う必要が生じるため、迅速な対応が不可欠です。
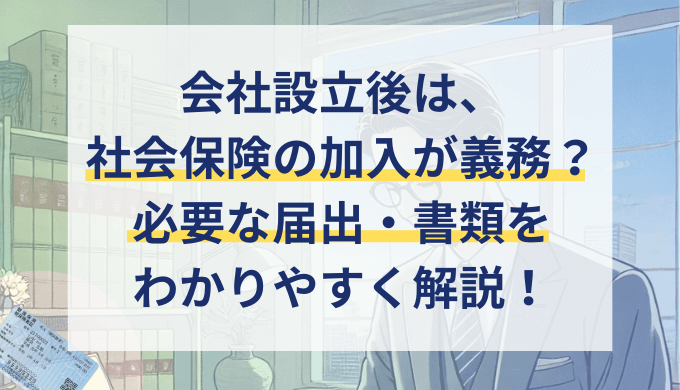 会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説
会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説
労働保険に関する手続きは、「①労働基準監督署 → ②ハローワーク」という順番で進める必要があります。
これは、最初に労働基準監督署へ届出をすることで、国に対して会社としてのマスター登録を行い、労働保険番号というマスターIDが発行されます(①)。その後にそのマスターIDを使って、ハローワークへ届出をすることで、その会社がどこで事業を行うのかという、より具体的な拠点情報を登録する、という階層構造になっているからです。
この流れを理解しておくと、なぜハローワークで労働基準監督署の受付印が必要になるのかが分かり、手続きをスムーズに進められます。
ここでは、労働基準監督署とハローワーク、それぞれの窓口に提出する書類を順番に解説します。
保険関係成立届
「保険関係成立届」は、会社が労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所となるために、最初に行う最も重要な手続きです。
従業員を一人でも雇用した場合、パートやアルバイトであっても、事業主にはこの届出を提出する法律上の義務があります。
重要なのは、事業主が手続きをしたかどうかに関わらず、労働者を雇用したその日に、法律上、労働保険の関係は自動的に成立しているという点です。万が一、手続きを怠っている期間に従業員が業務中に怪我をした場合でも、それは「労働災害」として扱われます。
提出期限は、従業員を雇用した日(保険関係が成立した日)の翌日から10日以内です。管轄の労働基準監督署へ提出します。この届出により労働保険番号が付与され、以降の労働保険手続きでこの番号を使用します。
手続きを怠ると、保険料の遡及請求だけでなく、労災給付にかかった費用を請求されるなどの重いペナルティが課される可能性があるため、必ず期限内に提出しましょう。
労働基準監督署への適用事業報告
労働保険の手続きとは別に、従業員を雇用して事業を開始したら「適用事業報告」を、遅滞なく管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
これは、その事業場が労働基準法の適用対象であることを、行政へ明確に報告するための手続きです。一般的には、一つ前に解説した「保険関係成立届」と同時に提出します。
ここで最も注意すべき点は、労働基準法が「企業単位」ではなく「事業場単位」で適用されるという考え方です。例えば、複数の店舗や支店を運営する場合には、その場所ごと(事業場ごと)に適用事業報告を提出しなければなりません。
この「事業場単位」の考え方は、社会保険手続きとは異なる労働法特有のルールのため、特に意識して対応しましょう。
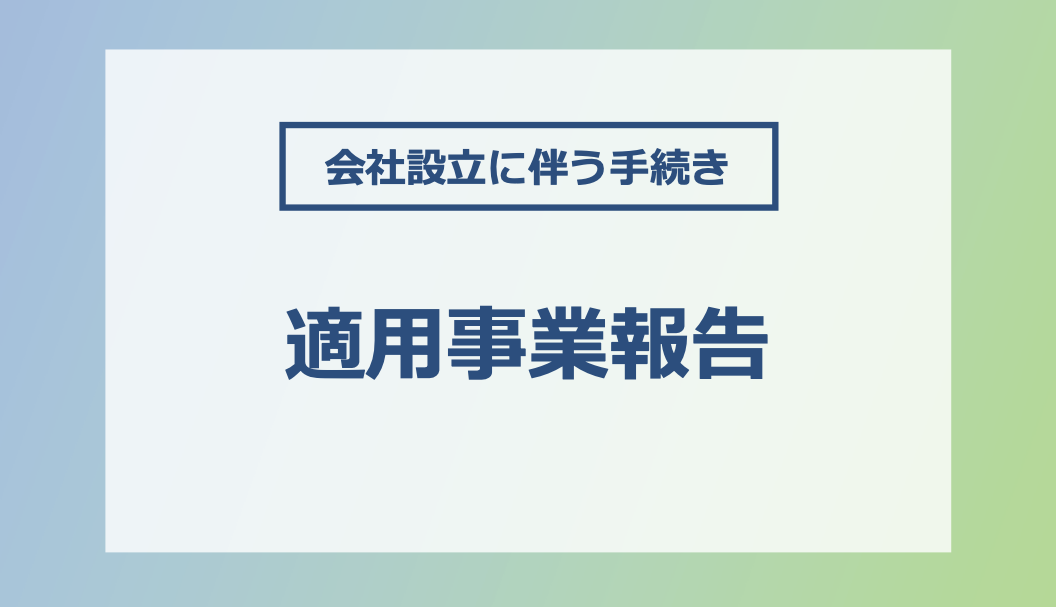 適用事業報告の手続き内容|スポット(単発)の社会保険手続き代行
適用事業報告の手続き内容|スポット(単発)の社会保険手続き代行
労働保険の概算保険料申告書
「労働保険の概算保険料申告書」は、その年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払う労働保険料を、概算で前払いするための申告書です。
そもそも労働保険料とは、以下の2つを合わせたものです。
1.労災保険料
業務中の怪我などに備える保険。全額を事業主が負担します。事業内容によって労災の発生リスクが異なるため、業種ごとに保険料率が細かく設定されています。
2.雇用保険料
失業などに備える保険。事業主と従業員の双方が負担します。
労働保険料は、まず年度の初めに概算の金額で申告・納付し、翌年度の初めに確定した賃金総額をもとに過不足を精算する、という仕組みになっています。
提出と納付の期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。ただし実務上は、労働基準監督署での手続きを一度で済ませるため、「保険関係成立届」と同時に提出することが一般的です。
申告書は労働基準監督署へ提出し、保険料は銀行などの金融機関、または電子納付で納めます。
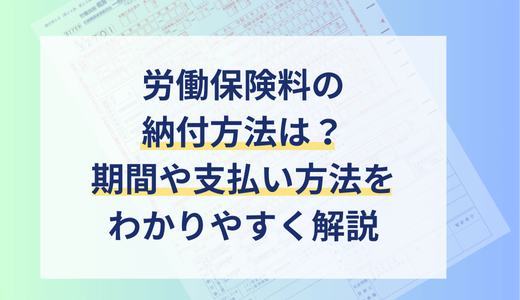 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
雇用保険適用事業所設置届
「雇用保険適用事業所設置届」は、あなたの会社を雇用保険の手続きを行う事業所として、ハローワークに登録するための届出です。
この届出によって、従業員が失業した場合などに給付手続きを行う行政拠点(窓口)が正式に決まります。
提出期限は、事業所を設置した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出します。この際、労働基準監督署の受付印がある「保険関係成立届」の控えを添付する必要があります。
これが、労働基準監督署の手続きを先に済ませなければならない明確な理由です。
雇用保険被保険者資格取得届
個々の従業員を雇用保険制度に登録するための最終的な手続きが、「雇用保険被保険者資格取得届」です。
この届出が受理されることで、従業員は正式に雇用保険の被保険者となり、失業手当や育児休業給付金、介護休業給付金など、様々な給付を受けられる資格を得ます。
提出期限は、従業員を雇用した月の翌月10日までです。
一つ前に解説した「適用事業所設置届」と同時に提出することも可能であり、初めて従業員を雇用する場合は、一連の流れの中でまとめて手続きを行うのが効率的でおすすめです。
従業員を雇用した場合、誰を社会保険や労働保険に加入させるべきかを正しく判断することが重要です。
正社員はもちろん、役員やパート・アルバイトなども対象となる場合がありますが、その基準は制度ごとに異なります。特に非正規雇用の取り扱いは複雑で、事業主が誤解しやすい部分でもあります。
ここでは、加入対象の判断基準を整理して解説します。
【正社員・役員】原則すべての人が対象
正社員として採用した従業員は、条件を満たせば全員が社会保険と労働保険に加入させる必要があります。また、法人の役員についても、定期的に役員報酬を受け取っている場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務があります。
ただし、役員は法律上「労働者」には当たらないため、雇用保険や労災保険といった労働保険の対象には原則として含まれません。この違いを理解しておくことが大切です。
労災保険はすべての労働者が対象です。
保険の種類の中でも、労災保険は特に適用範囲が広く、パートやアルバイト、日雇いの方であっても、事業所で1分でも働けば加入対象となります。労働時間や日数に関わらず、すべての労働者を守るための保険であると覚えておきましょう。
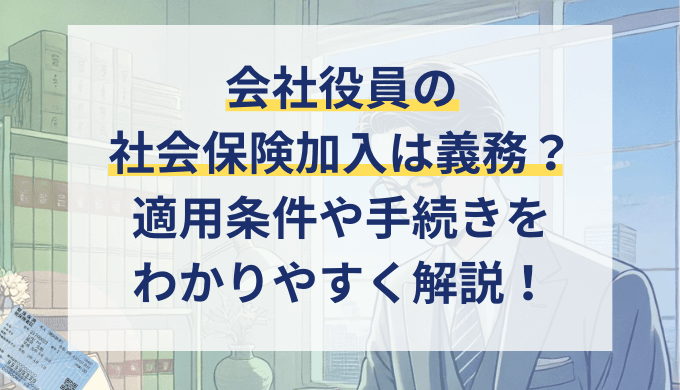 会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
パート・アルバイトの加入条件
パートやアルバイトの従業員については、社会保険と雇用保険で基準が異なるため、それぞれ確認が必要です。
社会保険の加入には、まず「4分の3基準」が適用されます。これは、週の所定労働時間や月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入するというルールです。 例えば、正社員が週40時間勤務の事業所で、パートの方が週30時間勤務する場合、この方は社会保険の加入が必要になります。
雇用保険については、以下の2つの条件を両方満たす場合に加入させなければなりません。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
【注意】有期契約に関する誤解
「2ヶ月以内の有期契約だから社会保険は不要」と考えるのは誤解です。当初の契約が2ヶ月以内でも、その後契約を延長した場合はその日から加入が必要です。また、試用期間などで当初から長期雇用が見込まれる場合は、最初の雇用日から加入させる必要があります。
従業員51人以上の企業は適用範囲がさらに拡大
2024年10月からは、法改正により従業員数51人以上の企業(※)において、パート・アルバイトの社会保険加入範囲がさらに拡大しました。 (※厚生年金の被保険者数が51人以上の企業を指します)
これにより、4分の3基準を満たしていなくても、以下の4要件をすべて満たす場合には社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8.8万円以上であること(残業代・賞与・通勤手当は除く)
- 雇用が2か月を超えて見込まれること
- 学生でないこと
事業主は、従業員の労働条件をこれまで以上に丁寧に確認する必要があります。
社会保険や労働保険への加入は、従業員を守ると同時に事業主自身を守るための法的義務です。
未加入のまま放置すると、行政からの是正指導にとどまらず、事業の継続そのものに大きなリスクを及ぼす重大なコンプライアンス違反として、厳しいペナルティが課せられます。
ここでは、未加入が発覚した場合に企業が直面する具体的なリスクと罰則について解説します。
最大で過去2年分の保険料を遡って徴収
年金事務所などの調査で未加入が発覚した場合、最大で過去2年分に遡って保険料を一括で請求されます。徴収権の時効が2年とされているためです。
会社は自社負担分だけでなく、本来従業員が負担すべき保険料についても、まずは全額を立て替えて納付する義務があります。すでに退職した従業員分も対象になるため、金額は想像以上に大きくなる可能性があります。
延滞金や、悪質な場合は懲役刑の可能性も
遡及された保険料には、最大で年8.7%という高率の延滞金が課されます。
さらに、度重なる指導に従わないなど悪質と判断された場合は、健康保険法第208条などの規定に基づき「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることもあります。
加えて労働保険では、未加入期間中に労災事故が発生すると、給付額の40〜100%を企業が負担する追徴金が課され、数千万円単位に達するケースもあります。これは中小企業にとって致命的な打撃となります。
ハローワークに求人が出せず採用活動に支障が出る
社会保険や労働保険の加入義務を果たしていない企業は、法令を守っていないとみなされます。その結果、ハローワークに求人を申し込むことができなくなります。
特に中小企業にとって、ハローワークは重要な採用チャネルの一つです。利用できない状態が続けば、人材確保が難しくなり、事業の成長や存続に深刻な支障をきたします。
ここでは、初めて従業員を雇用する事業主の方が抱きがちな疑問について、専門家の視点からQ&A形式で分かりやすく回答します。
従業員が50人以下の会社は社会保険に加入しなくていい?
法人の場合、従業員数に関わらず社会保険への加入義務があります。
「51人以上」という基準は、あくまでパート・アルバイトの方の社会保険の適用範囲が拡大される条件の一つです。会社自体の加入義務とは全く関係ありません。
株式会社や合同会社といった法人は、社長一人であっても社会保険に加入する義務があります。この点を混同しないように注意してください。
1週間だけ残業で20時間超えた場合、雇用保険はどうなる?
雇用保険の加入対象にはなりません。
加入の判断基準となるのは、残業時間を含まない、雇用契約書で定められた「所定労働時間」だからです。
そのため、基本の契約が週20時間未満であれば、一時的に残業で労働時間が20時間を超えたとしても、ただちに加入義務は発生しません。
ただし、毎週のように残業が常態化し、常に20時間以上働いているような実態がある場合は、雇用契約そのものを見直した上で、雇用保険に加入させる必要があります。
週の労働時間が月によって変動する場合はどうなりますか?
1ヶ月など、一定期間の平均の所定労働時間で判断します。
例えば、雇用契約で「1ヶ月の所定労働時間を80時間」と定めている場合、月の日数に関わらず、1ヶ月を平均4週間として計算し、「週20時間労働(80時間 ÷ 4週)」と判断します。この場合、雇用保険の加入対象となります。
特定の週だけを見て判断するのではなく、契約全体での平均労働時間で考えるのが基本です。
従業員から「家族の扶養から外れたくない」と言われたら?
従業員の希望に関わらず、加入要件を満たした場合は加入させなければなりません。
社会保険への加入は、事業主と従業員の双方に課せられた法律上の義務です。従業員個人が、加入するかどうかを選択できるものではありません。
もし加入させなかった場合、その責任を問われ、罰則の対象となるのは事業主です。
従業員には、法律上の義務であることを丁寧に説明すると同時に、将来の年金額が増えたり、病気や怪我で休んだ際に傷病手当金が受けられたりするなど、本人にとってのメリットも伝え、理解を求めることが重要です。
社会保険料の会社の負担割合は?
従業員と会社で、およそ半分ずつを負担します。
社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(40歳以上の場合)などを合計したものです。この総額を、従業員と会社(事業主)が折半して負担する「労使折半」が原則です。
厳密には、保険の種類によって労使の負担率はわずかに異なりますが、事業主は**「従業員の給与から天引きする保険料と、ほぼ同額を会社も負担している」**と理解しておくとよいでしょう。これは会社の資金繰りにも関わる重要なコストです。
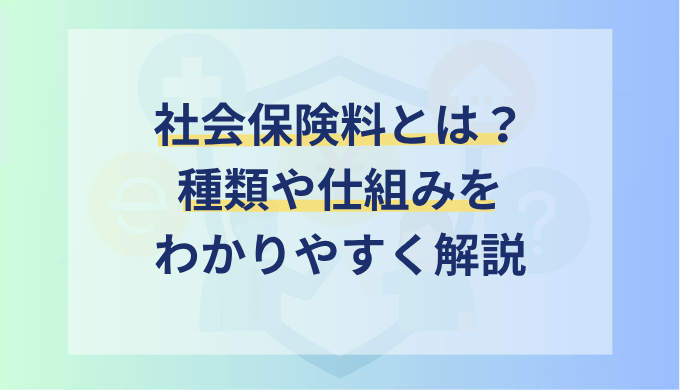 社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
個人事業主も従業員を雇用した場合は、社会保険に加入する必要はある?
常時5人以上の従業員を雇用した場合は、原則として加入義務があります。
個人事業主の事業所であっても、常時5人以上の従業員がいる場合は、法律上、社会保険の「強制適用事業所」となります。
ただし、飲食店や理・美容業といったサービス業、農業、漁業などは、5人以上の従業員がいても強制適用の対象外です。その場合でも、従業員の半数以上の同意などを得れば、任意で社会保険に加入する「任意適用」を選択することも可能です。
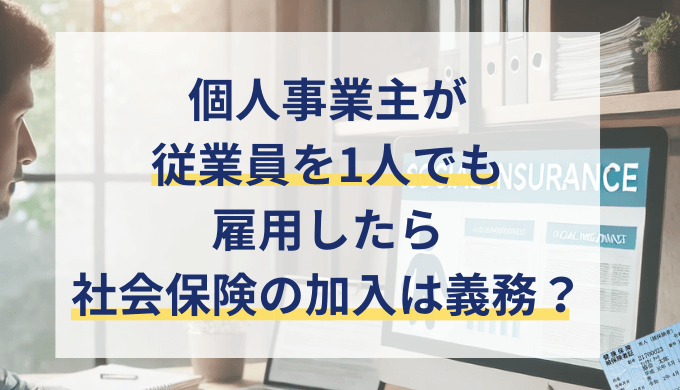 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
社会保険・労働保険の手続きは準備と正確さが大切
初めて従業員を雇用する際の社会保険・労働保険の手続きは、提出先が複数あり、期限も短いため、複雑に感じるかもしれません。
しかし、手続きをスムーズに進めるために最も大切なことは、届出書を書き始める前に、その土台となる「労働契約の締結」や「法定三帳簿の整備」といった準備をしっかりと済ませておくことです。
そもそも社会保険・労働保険とは、「ルールを守るからこそ、事業主と従業員の双方がルールに守られる」という仕組みです。万が一の労災事故の際には従業員に手厚い補償がなされ、コロナ禍で注目された雇用調整助成金のように、事業主が助成金を受給できるセーフティネットでもあります。
逆に、手続きを怠った場合のリスクは、保険料の遡及徴収や罰則だけではありません。コンプライアンス意識が高まる現代では、取引先からの契約解除や従業員の離職といった事態を招き、事業経営そのものを危うくする可能性もはらんでいます。
こうした複雑な手続きを効率化するには、電子申請システム「e-Gov」の活用が有効です。また、手続きの漏れやミスといったリスクを根本からなくしたい場合は、専門家である社労士に依頼することも検討しましょう。
従業員の雇用は、事業成長の大きな一歩です。本記事を参考に、必要な手続きを漏れなく進め、従業員と事業主、双方が安心して働ける環境を整えましょう。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
社会保険や労働保険の手続きは複雑で、提出先も複数に分かれているため、初めて従業員を雇用する事業主にとって大きな負担になりがちです。少しの記入ミスや提出遅れが、従業員の保険証発行や給付に影響する可能性もあり、正確さと迅速さが強く求められます。
こうした不安を解消する方法として、専門家である社会保険労務士に依頼するのは非常に有効です。手続き漏れのリスクを確実に防ぐことができ、事業主は本来の事業運営や経営に集中できます。特に、初めての手続きで戸惑う小規模事業主にとっては、専門家に任せることが最も合理的な選択といえます。
「社労士クラウド」では、顧問契約を結ぶ必要がなく、必要なときにだけ依頼できるスポット申請代行サービスを提供しています。初めて従業員を雇用する事業主が抱える不安に寄り添い、安心と確実性をもってサポートしています。まずは無料相談から始めることで、自社の状況に合わせた最適な対応が可能です。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|