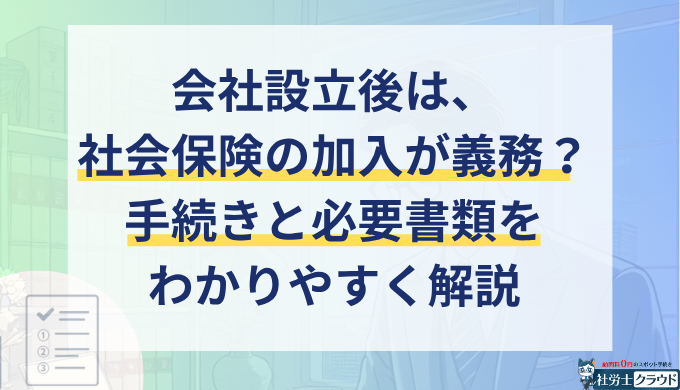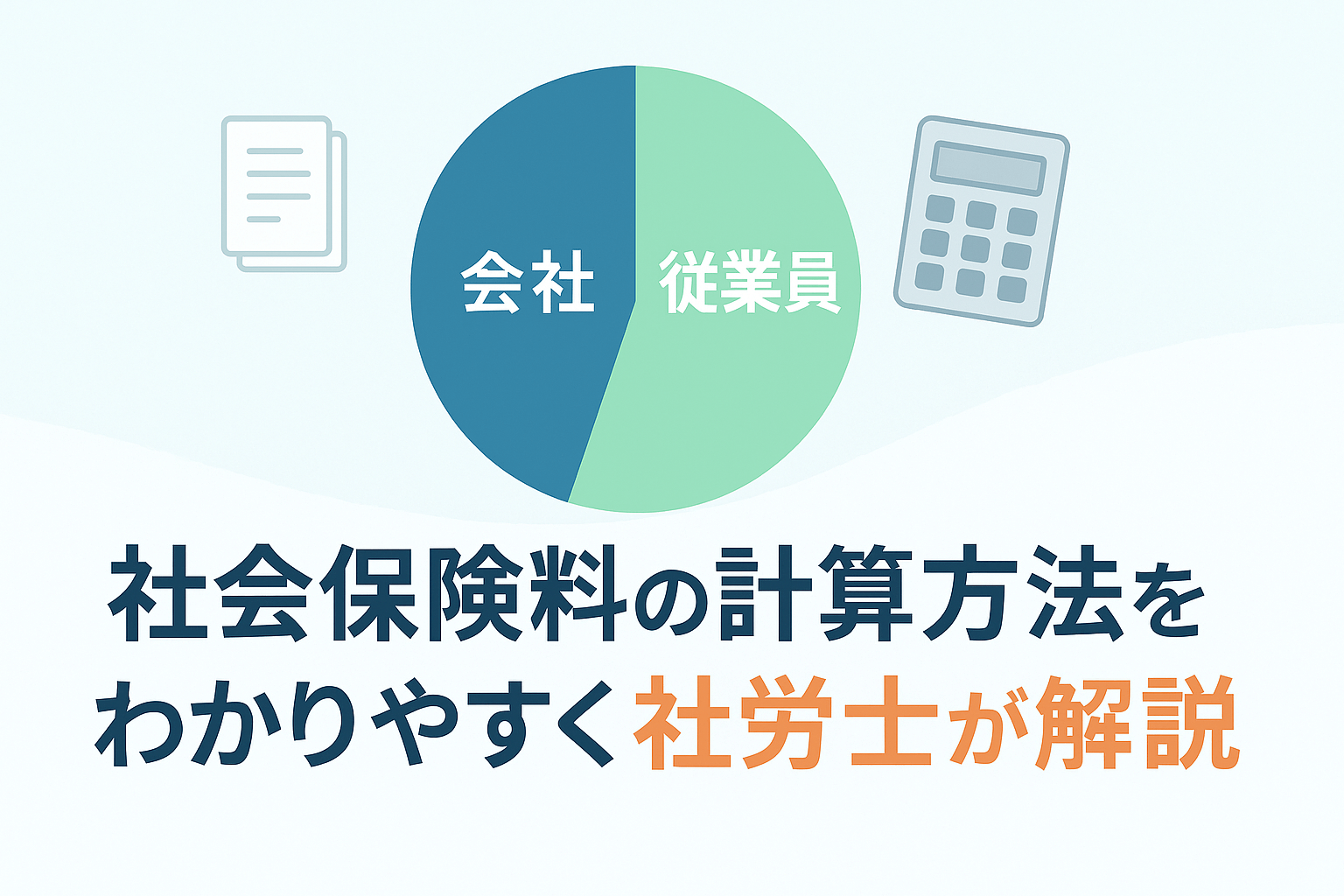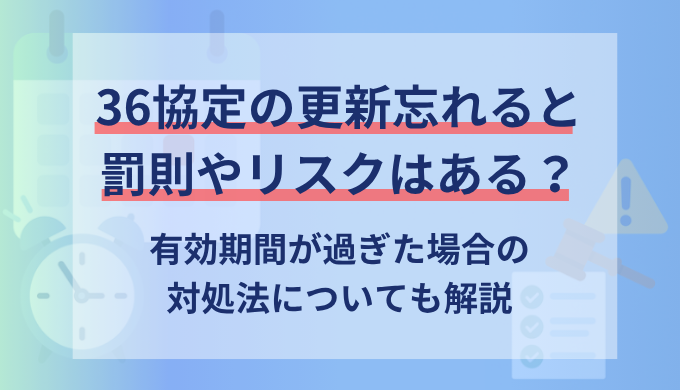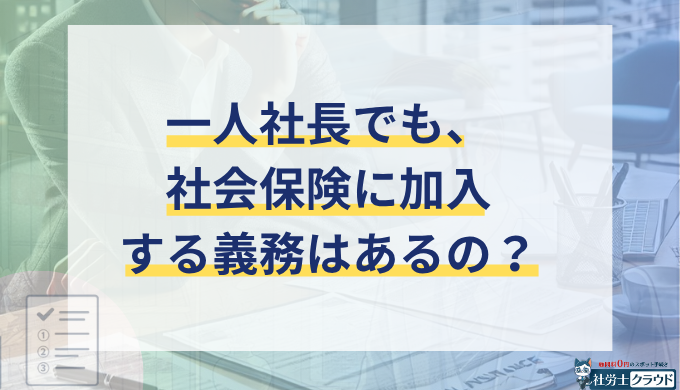会社設立後は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きを速やかに進める必要があります。法人であれば、たとえ社長一人の会社でも原則として加入が義務です。
また、従業員を雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要になります。
ただし、設立直後は登記や銀行口座の開設、税務の準備などで多忙なため、社会保険の届出が後回しになってしまうケースも少なくありません。
しかし、手続きが遅れると罰則を受けたり、過去分の保険料を請求されたりするリスクがあるため注意が必要です。
「手続きが複雑そう」「費用負担が心配」と感じる方も多いかもしれませんが、正しく対応しなければ法律違反となる可能性もあります。
この記事では、会社設立時に必要な社会保険・労働保険の加入手続きや提出書類、未加入のリスクについて詳しく解説します。
設立直後の忙しい時期でもやるべきことを整理し、効率的かつ確実に手続きを進めていきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
YouTubeでも会社設立時の社会保険の手続きについて詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
会社を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則として義務です。
株式会社や合同会社など、法人として登記された会社は、法律上「従業員の人数に関係なく社会保険に入らなければならない事業所(=強制適用事業所)」として扱われます。
つまり、社長1人だけの会社であっても、会社そのものが社会保険の加入対象になります。

会社設立時に対応すべき保険の手続きは、2つのグループに分けられ、それぞれ加入が必要になるタイミングが異なります。
1.社会保険(健康保険・厚生年金)
2.労働保険(労災・雇用)
1の社会保険は、「法人の設立(登記)」が加入のタイミングです。 2の労働保険は、「従業員を初めて雇った時」が加入のタイミングです。会社設立と同時に従業員を雇用しない場合は、この時点での手続きは必要ありません。
「一人社長」で従業員がいない場合でも、会社(事業所)としては社会保険の適用対象です。
ただし、社長本人が社会保険に加入できるかどうかは、役員報酬を受け取っているか、実際に業務に従事しているかによって判断されます。
社会保険に加入しないまま放置すると、後から罰則や過去分の保険料を請求されるリスクがあります。
手続きは複雑で期限も短いため、少しでも不安がある場合は、早めに社会保険の専門家(社労士)へ相談するのが確実です。
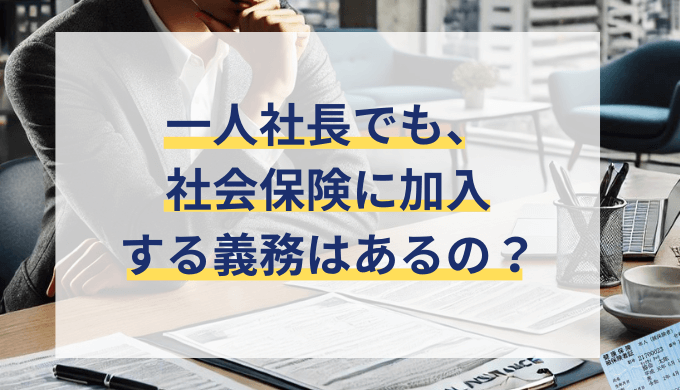 一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説
一人社長でも社会保険加入の義務がある?法人化した時の手続きを解説
例外的に社会保険に加入できない(不要な)ケースがある
会社を設立した場合、原則として社会保険への加入は必須ですが、一部の例外では加入が不要、またはできないケースがあります。

社会保険料は役員や従業員の「報酬額」をもとに計算されるため、報酬の支給状況によっては社会保険の加入資格が発生しないことがあります。 代表的なケースは次のとおりです。
◯役員報酬がゼロ(0円)の場合
報酬がなければ保険料を算定できないため、社会保険には加入できません。 この場合、社長個人は「国民健康保険」と「国民年金」に加入する必要があります。健康保険(協会けんぽ)の給付(例:傷病手当金など)とは保障内容が異なる点に注意が必要です。
◯役員報酬が著しく低額な場合
報酬額が健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の最低等級に満たない場合、加入対象外(不該当)となる可能性があります。
◯非常勤役員の場合
名義上は役員でも、実際に出社していない・指揮監督を行っていないなど勤務の実態がない場合は、加入対象外です。 ただし、会議出席や業務指示などを継続的に行っており、実質的に常勤とみなされる場合は、後から社会保険料を遡って請求されるリスクがあります。
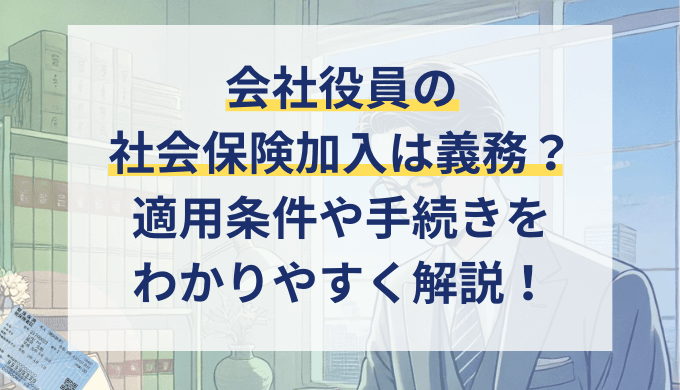 会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
社会保険に未加入のままだと罰則の可能性がある
もし社会保険に未加入のまま放置した場合、法律に基づく罰則の対象になる場合があります。
健康保険法第208条や厚生年金保険法第102条には、度重なる加入指導に従わないなど悪質なケースに対し、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されると定められています。
労災保険や雇用保険の未加入についても、同様に罰則が設けられています。
最も直接的なリスクは、金銭的なものです。未加入が発覚した場合、最大で過去2年分の保険料を遡って(遡及徴収)請求されるのに加え、延滞金も加算されます。
この時、従業員が負担すべき分も含めて、まずは会社が全額を立て替えて納付する必要があります。
さらに、経営上のデメリットも多く存在します。
- 国の助成金・補助金の対象外になる
- 金融機関の融資審査で「法令遵守に問題あり」と判断されるおそれがある
- ハローワークで求人募集が受理されない
- 従業員や取引先からの信用低下につながる
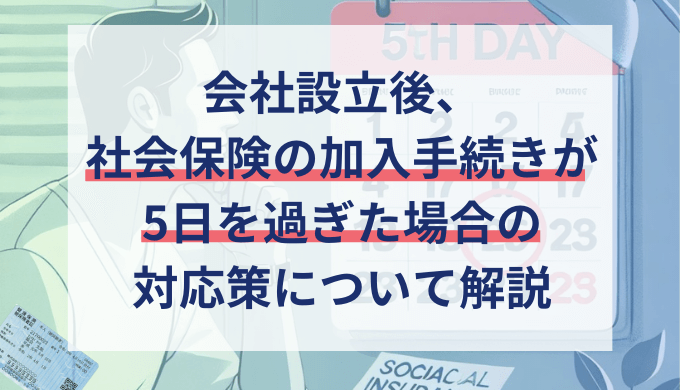 会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
会社設立(登記)が完了したら、健康保険と厚生年金の加入手続きは、会社が社会保険の適用事業所として認められた日から5日以内に行う必要があります。
手続きは、会社の所在地を管轄する「年金事務所」または「事務センター」で行います。 会社設立後5日以内に提出が必要な主な社会保険の届出・書類は次の3つです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
各届出の書類の内容と主な添付書類は以下のとおりです。
| 届出書 | 書類の内容 | 添付書類 | 提出先 |
| 社会保険 新規適用届 | 法人が社会保険に加入するために必要な書類 | ・法人登記簿謄本 ・法人番号指定通知書 | 年金事務所 |
| 社会保険 被保険者資格取得届 | 法人の代表や従業員が個別に社会保険へ加入する際に必要な書類 | 国民年金第3号被保険者関係届(事業所が協会けんぽに加入している場合) | 年金事務所 |
| 被扶養者異動届 | 家族を扶養に入れる際に必要な書類 | 被扶養者の認定に必要な書類 | 年金事務所 |
以下で、それぞれの手続きについて詳しく説明します。
健康保険・厚生年金新規適用届
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、法人が社会保険に加入するために必須の手続きです。設立後5日以内に、管轄の年金事務所または日本年金機構に提出する必要があります。
提出に必要な主な添付書類は以下の通りです。
届提出に必要な添付書類
届提出に必要な添付書類
- 法人(商業)登記簿謄本 (法人設立を証明するための書類で、発行から90日以内の原本が必要)
- 法人番号指定通知書のコピー
さらに、会社の登記所在地と事業所所在地が異なる場合は、以下の補足書類も必要です。
- 賃貸借契約書のコピー:事業所所在地を証明する書類。
- 公共料金の領収書:事業所所在地の実在を確認するための書類。
申請方法は、年金事務所の窓口への持参、郵送、または政府の電子申請窓口「e-Gov」の利用が可能です。電子申請は、無料で取得できる「GビズID」を使うと24時間手続きができ、役所へ行く時間や手間を削減できます。
また、手続きの際には、今後の保険料の納付漏れを防ぐために「保険料口座振替納付申出書」も同時に提出しておくことを強くおすすめします。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、社長(代表取締役)や常勤役員、加入対象となる従業員を、社会保険の被保険者として登録するための書類です。この届出によって、健康保険証が発行されます。
この書類も「新規適用届」とあわせて、登記日から5日以内に提出する必要があります。
書類には、主に以下の情報を記入します。
- 事業所の整理記号・番号(新規適用届と同時提出の場合は空欄でよい場合もあります)
- 被保険者となる個人の基本情報(氏名、生年月日、マイナンバー、基礎年金番号など)
- 資格取得日(設立日や入社日)
- 給与情報(報酬月額)
会社設立直後で役員報酬がまだ正式に確定していない場合でも、「報酬月額」の欄は役員報酬の見込み額を記入して申請することが可能です。
もし扶養家族がいる場合は、次の見出しで説明する「被扶養者(異動)届」も、この書類とあわせて提出します。
「被扶養者(異動)届」(扶養家族がいる場合のみ)
もし、社会保険に加入する社長や従業員に、扶養する家族(配偶者や子など)がいる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。
この届出により、扶養家族も健康保険の対象となり、家族分の健康保険証が発行されます。
ただし、扶養家族として認められるには、収入要件(例えば、年間の収入見込みが130万円未満であることなど)を。満たす必要があります。
提出の際には、扶養の事実や収入状況を確認するため、所得証明書や、続柄を確認するための住民票などの添付を求められる場合があります。扶養する家族がいる場合は、この書類も「被保険者資格取得届」と一緒に提出しましょう。
従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇った場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要になります。 なお、これらの労働保険は原則として従業員のための制度であり、社長や役員といった事業主は加入対象外です。
書類提出の順番は「労働基準監督署 → ハローワーク」です。 まずは労災保険の加入手続きを行い、交付される「保険関係成立届(控)」をもって雇用保険の手続きを行います。
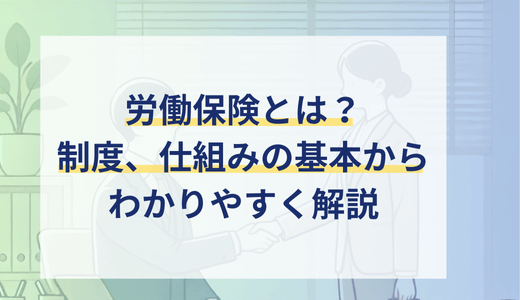 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労災保険の加入手続きと必要書類
従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇ったら、まずは「労災保険」の手続きを行います。これは、従業員が業務中や通勤中にケガをした場合などに備える保険です。
手続きは、会社の所在地を管轄する「労働基準監督署」で行います。 この手続きで主に提出が必要な書類は、「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」の2つです。
それぞれの提出先と期限の概要は、以下の表の通りです。
| 書類名 | 提出先 | 提出時期 | 提出方法 |
| 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した翌日から50日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
労災保険の保険料は、全額を会社が負担するのが特徴です。 以下で、それぞれの書類について詳しく説明します。
「保険関係成立届」は、労働保険(労災保険と雇用保険)の適用を会社として開始するために、労働基準監督署へ最初に提出する基本書類です。提出期限は、従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内です。
提出に必要な主な添付書類は以下の通りです。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)のコピー
- 事業所の所在地が確認できる書類(賃貸借契約書のコピーなど)
注意点として、この書類は複写式になっていることが多いため、基本的には労働基準監督署の窓口で直接入手するのが確実です。
この届出が受理されると、会社に「労働保険番号」が割り当てられ、「受付印付きの控え」が交付されます。
この控えは、次のステップであるハローワークでの雇用保険手続きで必須となるため、大切に保管してください。
「労働保険概算保険料申告書」は、その年度末(3月31日まで)に従業員に支払う賃金総額の見込み額を計算し、それに基づいて概算の労働保険料(労災保険料と雇用保険料の合計)を申告・納付するための書類です。
この書類には、前のステップ(保険関係成立届)の提出によって発行された「労働保険番号」を記載する必要があります。
法律上の提出期限は、保険関係が成立した日(従業員を雇った日)の翌日から50日以内とされています。
しかし、実際の手続きでは、「保険関係成立届」を労働基準監督署に提出する際に、この「概算保険料申告書」も同時に提出し、その場で保険料を納付するのが一般的です。
別々に手続きすると二度手間になるため、一緒に準備しておきましょう。
労働保険料の詳しい納付方法や分割納付については、下記の記事で詳しく解説しています。
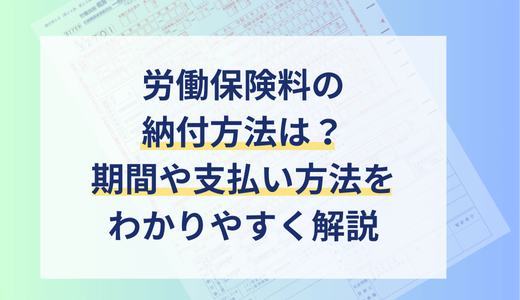 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
雇用保険の加入手続きと必要書類
労働基準監督署での労災保険の手続きが完了したら、次に、管轄の「ハローワーク(公共職業安定所)」で雇用保険の手続きを行います。
ここで最も注意すべきポイントは、手続きの順番(依存関係)です。雇用保険の手続きは、必ず労働基準監督署での手続きを終えてから行ってください。
なぜなら、ハローワークでの申請時に、「労働基準監督署の受付印が押された『保険関係成立届(控)』」の提示が必須だからです。
この順番を誤って、先にハローワークに行ってしまうと、書類不備で受け付けてもらえず、再訪が必要になるなど二度手間になります。
必ず「労基署 → ハローワーク」の順で進めましょう。
雇用保険の手続きで提出が必要な主な書類は、以下の2つです。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
以下で、それぞれの書類の内容・添付書類・提出先をまとめます。
| 届出書 | 書類の内容 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用を受けるための事務所の設置を届け出る書類 | ハローワーク | 雇用した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の被保険者資格を取得したことを届け出る書類 | ハローワーク | 雇用した月の翌月10日まで |
以下では、雇用保険の手続きに必要な届出・書類とその概要について詳しく解説します。
「雇用保険適用事業所設置届」は、会社が雇用保険の適用事業所であることをハローワークに届け出るための書類です。
従業員を1人でも雇用する場合、この手続きが法律で義務付けられています。この届出を行うことで、従業員が失業した際などに雇用保険の給付(失業給付や育児休業給付など)を受けられるようになります。
提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
期限を過ぎると、従業員が給付を受けられない期間が生じたり、事業主に指導が入ることもあるため注意が必要です。
- 保険関係成立届(控)
労働基準監督署で受け取る「受付印のある控え」を添付します。 - 登記事項証明書(コピー可)
会社の法人情報を確認するために必要です。 - 事業所の実在を確認できる書類(いずれか1点)
・法人名義の賃貸契約書のコピー
・法人名義の公共料金の領収書(発行から6か月以内) - 事業の実態を確認できる書類(いずれか1点)
・会社の営業許可証のコピー
・取引先との契約書や納品書、請求書など
この届出が受理されると、会社に「雇用保険の事業所番号」が割り当てられます。
この番号は、今後従業員を雇用した際の「被保険者資格取得届」など、雇用保険関係のすべての手続きで必要となる重要な情報です。
「雇用保険被保険者資格取得届」は、雇用保険の加入条件を満たした従業員を被保険者として登録するための書類です。この届出を行うことで、従業員が失業した場合などに失業給付や育児休業給付などを受けられるようになります。
従業員全員が対象となるわけではなく、主に以下の要件を満たす場合に提出が必要です。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
提出期限は、対象となる従業員を雇用した月の翌月10日までです。「適用事業所設置届」と同時に提出することが一般的です。
ハローワークの窓口では、従業員が上記の加入要件を満たしているかなどを確認するため、以下の書類の提示を求められることが一般的です。あらかじめ準備しておくと手続きがスムーズです。
- 労働条件通知書 または 雇用契約書
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード)など
届出が受理されると、従業員ごとに「雇用保険被保険者番号」が発行されます。この番号は、将来的に従業員が転職・退職した際にも引き継がれるため、正確に管理しておきましょう。
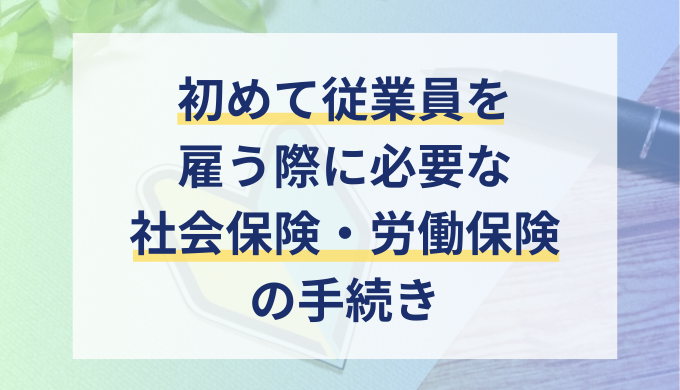 初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
会社設立後の社会保険手続きは、提出先が複数あったり、期限が短かったりと、初めて行う方にとっては戸惑う点も多いかもしれません。ここでは、特に注意しておきたいポイントを2つ解説します。
社会保険の加入手続きは法人登記後5日以内にする
会社設立後の手続きで、最も注意すべきなのが「期限」です。特に、健康保険・厚生年金保険の加入手続き(「新規適用届」と「被保険者資格取得届」の提出)は、法人登記が完了した日から起算して5日以内に行う必要があります。
この「5日」という期限は、土日祝日を含めてカウントされるため、非常にタイトなスケジュールです。法人登記が完了したら、すぐに準備に取り掛かり、速やかに提出することが重要です。
万が一、この期限を過ぎてしまった場合でも、加入できなくなるわけではありません。「遡及適用」といって、設立日に遡って加入する手続きが可能です。 期限を過ぎたことに気づいたら、放置せず、できるだけ早く管轄の年金事務所へ電話などで連絡し、状況を説明して指示に従ってください。
他の法人で社会保険に加入している場合は、二以上事業所勤務届を提出する
本業で会社員(サラリーマン)として働きながら、副業で自分の会社を設立した場合など、複数の会社から役員報酬や給与を受け取り、それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たすケースがあります。
このように、2ヶ所以上の事業所で社会保険の対象となる場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を年金事務所に提出する必要があります。
この届出を行うことで、主たる事業所(通常は報酬が高い方)を選択し、すべての事業所からの報酬額を合算した上で、毎月の社会保険料が計算され、各社に按分されることになります。
注意点として、この手続きを行うと、保険料の計算結果などが本業の会社にも通知されるため、それによって副業(別会社での就労)が本業の会社に伝わる可能性があります。副業に関する規定は会社によって異なるため、事前に本業の就業規則などを確認しておくと安心です。
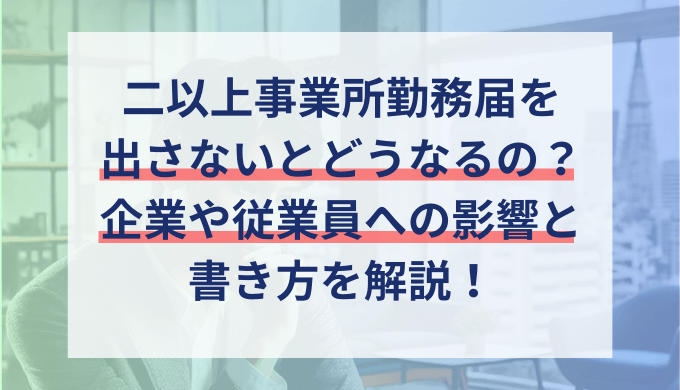 二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説
二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説
ここでは、会社設立時の社会保険手続きに関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。手続きを進める上での不安解消にお役立てください。
社会保険料はいつから支払いが始まる?
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、加入した月(資格を取得した月)から発生します。月の途中で会社を設立したり、従業員が入社したりした場合でも、日割り計算はなく1ヶ月分の保険料が必要です。
納付期限は、加入した月の翌月末日となります。例えば、4月10日に会社を設立(資格取得)した場合、4月分の保険料が発生し、その納付期限は5月末日です。
最初の支払いは、手続き後に日本年金機構から送られてくる納付書(納入告知書)を使って金融機関で支払うことが多いです。納付忘れを防ぎ、毎月の手間を省くためにも、加入手続きの際に「保険料口座振替納付申出書」を提出し、口座振替にしておくことをおすすめします。
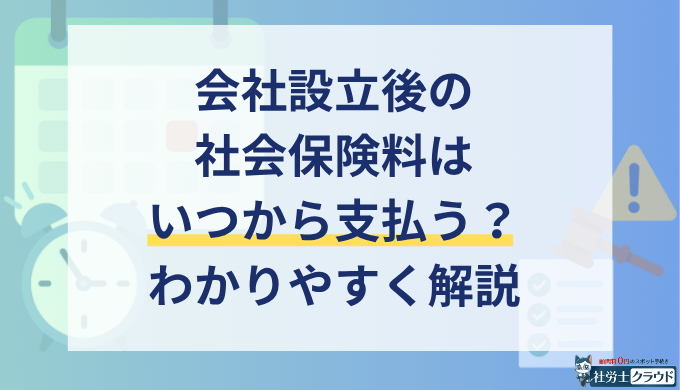 会社設立後の社会保険料はいつから支払う?発生・納付・給与天引きの時期を解説
会社設立後の社会保険料はいつから支払う?発生・納付・給与天引きの時期を解説
社会保険料の費用はいくら?
健康保険料と厚生年金保険料の合計額は、役員や従業員の給与(役員報酬)を「標準報酬月額」という区分(等級)に当てはめて計算されます。
保険料率は、厚生年金保険料が全国一律(現在18.3%)、健康保険料は加入する健康保険組合や都道府県(協会けんぽの場合)によって異なります。計算された保険料は、会社と本人(役員・従業員)が約半分ずつ(折半)で負担します。
例えば、役員報酬が月額30万円(40歳未満、東京都在住で協会けんぽ加入)の場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計は約8万5千円〜9万円程度となり、会社負担分と本人負担分はそれぞれ約4万数千円ずつとなります。
正確な金額は、加入する健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトで公開されている最新の「保険料額表」で確認できます。また、おおよその金額を手軽に知りたい場合は、社会保険料の計算ツールを利用するのも便利です。
株式会社と合同会社で手続きに違いはある?
手続きに違いは一切ありません。
社会保険の加入義務は、株式会社か合同会社かといった「会社の種類」ではなく、「法人であるかどうか」で決まります。株式会社も合同会社も同じ「法人」ですので、社会保険への加入義務や、その手続き(提出先、期限、必要書類)は全く同じです。
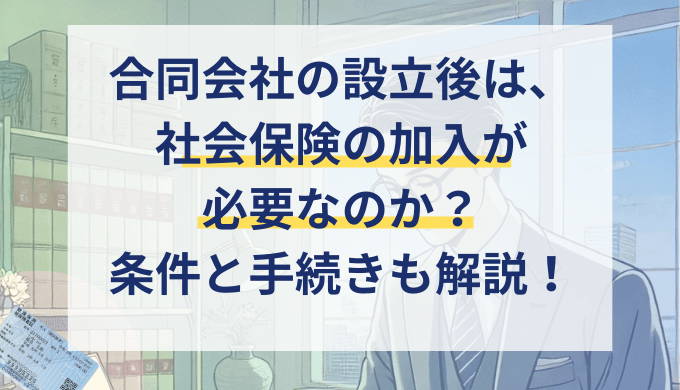 合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
自分でできる?社労士に頼むべき?
社会保険の加入手続きは、ご自身(会社)で行うことも可能です。書類は年金事務所などの窓口で入手できるほか、ウェブサイトからダウンロードして郵送や電子申請(e-Gov)で提出することもできます。
ただし、設立直後は非常に忙しく、書類の作成や添付書類の準備には専門的な知識も必要です。特に健康保険・厚生年金の手続きは「登記後5日以内」と期限が非常に短いため、記入ミスや添付漏れ、期限超過のリスクも考えられます。
もし、手続きの正確性を確保したい、期限内に確実に完了させたい、あるいは本業に集中したいという場合は、社労士に設立時の手続きだけを依頼する(スポット依頼)のも有効な選択肢です。
専門家に任せることで、時間と手間を節約し、安心して事業を開始できます。
 社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説
社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説
従業員を採用する前にやるべきことは?
従業員を採用してハローワークで求人募集を行いたいと考えている場合、注意が必要です。原則として、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していない会社は、ハローワークで求人を受理してもらえません。
そのため、従業員の採用活動を本格的に始める前に、まず自社の社会保険の「新規適用届」を年金事務所に提出し、加入手続きを済ませておく必要があります。 (※設立時に役員報酬ゼロで社会保険に加入していない場合は、報酬の支払い開始と同時に手続きする旨などを、事前にハローワークに相談しておくとスムーズです。)
遅れてしまった…どうすればいい?
健康保険・厚生年金の手続き期限(登記後5日以内)を過ぎてしまった場合でも、加入できなくなるわけではありません。
気づいた時点ですぐに管轄の年金事務所へ電話などで連絡し、正直に状況を説明して、指示に従ってください。通常は、設立日に遡って加入する「遡及適用」という形で処理されます。
ただし、60日を超えるなど、手続きの遅れが長期間にわたる場合は、通常の書類に加えて「遅延理由書」や、その間の給与支払い状況がわかる賃金台帳などの提出を求められることがあります。
いずれにしても、放置せずに速やかに行動することが重要です。
会社を設立したら、まず最優先で行うべきは「登記後5日以内」に年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きを済ませることです。
その後、従業員を雇用した場合は、「労働基準監督署 → ハローワーク」の順で労災保険・雇用保険の手続きを行います。これらの手続きは法律で定められた義務であり、期限や必要書類を正確に守る必要があります。
少しでも手続きが遅れると、過去分の保険料を遡って請求されたり、罰則を受けたりするリスクがあります。また、「一人社長」や「役員報酬ゼロ」などの例外的なケースでは、加入義務の判断を誤ると後から経営上の不利益を受ける可能性もあります。
近年は、政府の電子申請システム「e-Gov」と「GビズID」を活用することで、窓口に行かずにオンラインで手続きを完結させることも可能です。時間や手間を省きつつ、正確な申請を行うためにも活用を検討してみてください。
とはいえ、設立直後は登記・銀行・税務など他の手続きも重なり、社会保険の届出が後回しになりがちです。期限や書類作成に不安がある場合は、無理せず専門家である社労士へ相談、依頼するのが確実です。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。
1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)
2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)
3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)
社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。
まずは、ご相談ください。
「設立時の手続き、具体的に何から始めればいい?」 「期限(5日以内)が迫っているけど間に合う?」
といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。複雑な手続きは専門家に任せて、安心して事業のスタート準備に集中しませんか。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|