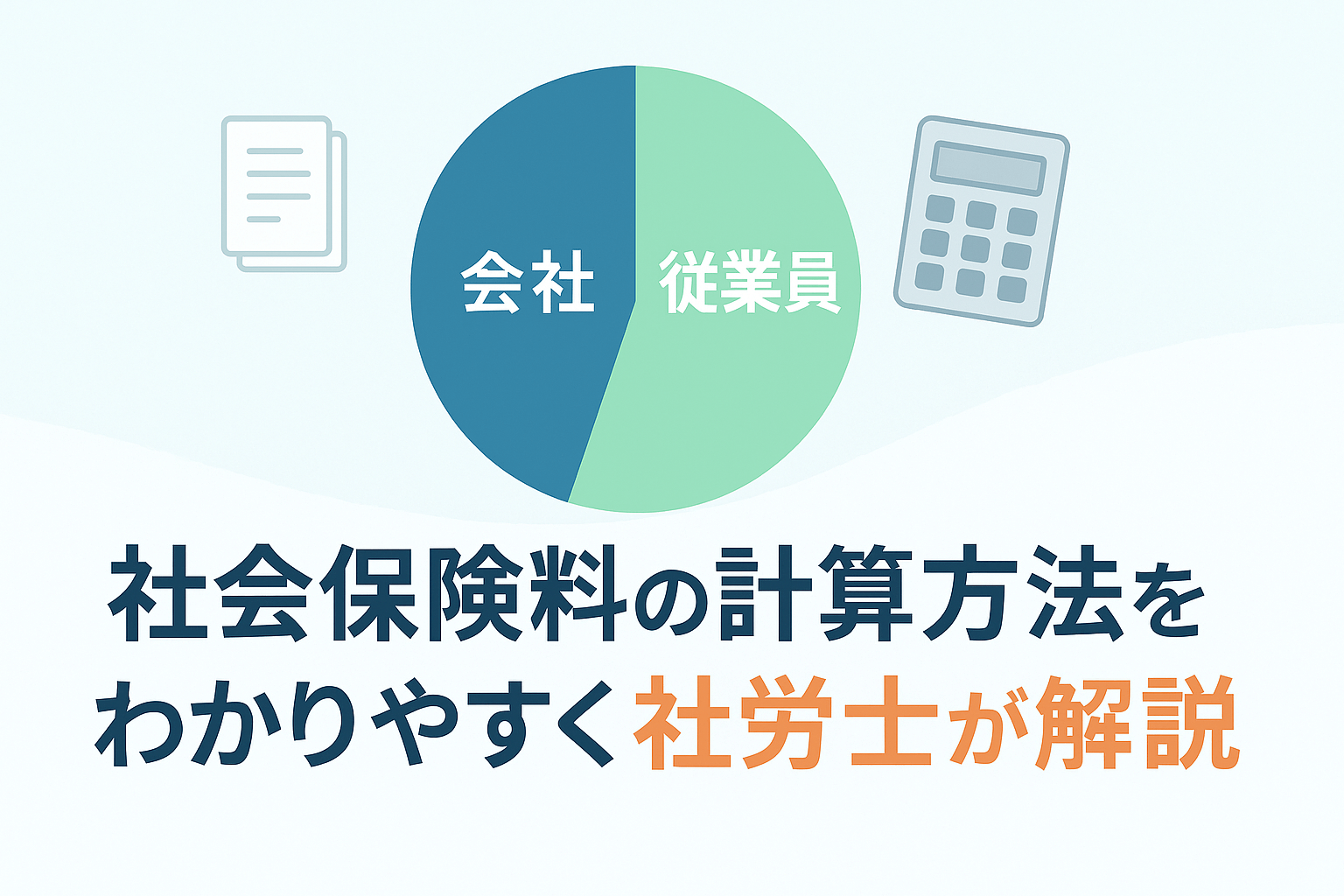健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料など、企業が毎月対応すべき社会保険料は多岐にわたり、その計算方法は種類によって異なります。従業員との負担割合や納付タイミングもそれぞれ異なるため、給与計算や労務手続きを担当される方にとっては、正確な知識と細心の注意が求められる業務でしょう。
特に、多くの社会保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」の決定や、年に一度の算定基礎届、給与変動時の月額変更届といった関連手続きは専門知識を要し、「どうやって決まるの?」「どの手当が含まれる?」といった疑問やその複雑さから、多くの担当者様を悩ませるポイントではないでしょうか。
社会保険料の計算や手続きに誤りがあると、保険料の追徴が発生するだけでなく、従業員の将来の年金額にも影響を及ぼす可能性があるため、正確な理解とミスのない運用が不可欠です。
この記事では、毎月の給与や賞与に関わる社会保険料の計算方法についてわかりやすく解説しています。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
労働保険の年度更新や算定基礎届など、労働保険・社会保険の手続きは、1年のうちで決まったタイミングで発生するものと、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きが必要なもの、また生年月日に応じて必要な必須の手続きがあります。
⇒社会保険・労働保険手続きの年間スケジュール(PDF)を無料ダウンロード
社会保険料とは、病気やケガ、失業、労働災害、老齢、介護といった様々なリスクに備えるために、法律に基づいて国や地方自治体が運営する公的な保険制度へ支払う掛け金のことです。
会社(事業主)は、従業員を雇用する際に、原則として社会保険に加入させ、発生する社会保険料を従業員と会社で分担して納付する義務を負います。
社会保険には、健康保険や厚生年金保険だけでなく、労働保険(雇用保険・労災保険)も含まれます。それぞれの保険で目的や保険料の計算方法、会社が負担する割合が異なります。
2024年10月からは社会保険の適用拡大により、条件を満たすパートやアルバイトの方も社会保険の適用対象となっています。
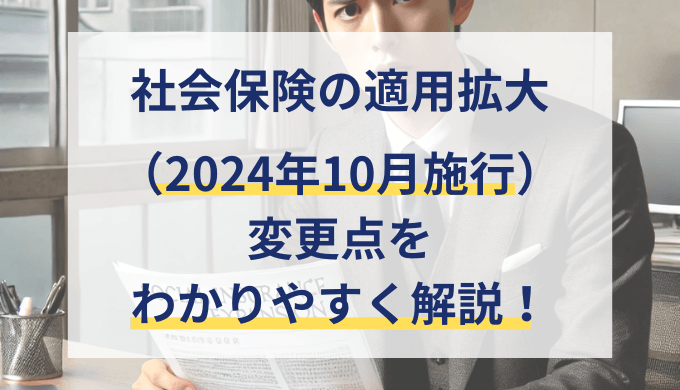 2024年10月〜パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大!企業が取るべき対応と影響を解説
2024年10月〜パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大!企業が取るべき対応と影響を解説
社会保険の種類と保険料の企業負担
会社が関わる主な社会保険は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類です。この5つの保険料は、労災保険を除き、会社(事業主)と従業員双方で負担します。
それぞれの保険の概要と、会社(企業)が負担する保険料の基本的な考え方は以下の通りです。
【保険の種類と企業の負担割合】
| 保険の種類 | 主な目的 | 負担割合 |
| 健康保険 | 業務外の病気・ケガ等の医療給付 | 会社と従業員で50%ずつ |
| 厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡時の年金給付 | 会社と従業員で50%ずつ |
| 介護保険 | 介護が必要となった場合の介護サービス給付 | 会社と従業員で50%ずつ(従業員が40歳以上65歳未満) |
| 雇用保険 | 失業時の給付、育児・介護休業時の給付など | 事業の種類によって事業主と従業員の負担割合が異なる。 |
| 労災保険 | 業務上・通勤中の災害に対する給付 | 全額事業主負担 |
社会保険の種類によって会社が負担する保険料の有無や割合が異なります。
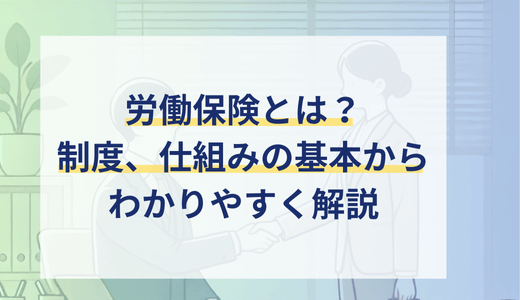 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
会社が社会保険料を納付するタイミング
会社が社会保険料を納付するタイミングは、法律で定められており、原則として対象月の翌月末日です。従業員の給与から天引きした保険料と、会社負担分の保険料を合わせて納付しなければなりません。
具体的には、以下のようになります。
毎月の従業員の給与から前月分の保険料を徴収(天引き)し、当月の給与から当月分の保険料を徴収する「当月徴収・翌月納付」または、当月の給与から前月分の保険料を徴収する「翌月徴収・翌月納付」のいずれかの方法で従業員負担分を徴収します。
どちらを採用するかは会社の規定によりますが、納付義務は対象月の翌月末日となります。
例えば、4月分の社会保険料(3月に支給する給与から天引き、または4月に支給する給与から天引き)は、5月末日までに日本年金機構へ納付します。
労働保険料は、原則として年に一度、概算で申告・納付し、翌年度に確定申告して過不足を精算する「年度更新」という手続きを行います。
年度更新の期間は、毎年6月1日から7月10日までです。ただし、雇用保険料の従業員負担分については、毎月の給与から会社が徴収(天引き)します。
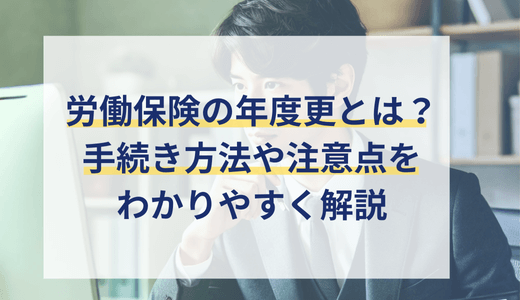 【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
社会保険料の納付が遅れると、延滞金が発生する場合がありますので、納付期限を正確に把握し、計画的に納付することが重要です。特に設立当初は資金繰りが厳しい場合もありますが、社会保険料の納付は法的な義務であることを認識しておきましょう。
毎月の給与から天引きされる社会保険料は、従業員の生活にも会社経営にも関わる重要なものです。ここでは、各社会保険料がどのように計算されるのか、具体的な計算式と計算例を交えながら、会社負担分も含めて解説します。
社会保険料の計算の基礎となるのは、主に「標準報酬月額」または「賃金総額」です。「標準報酬月額」とは、社会保険料の計算を簡便にするために、従業員の月々の給与を一定の幅で区分したものです。詳細は後述の「社会保険料の計算で必要になる標準報酬月額・標準賞与額」で解説します。
それぞれの保険料の特性を理解し、正確な給与計算につなげましょう。
健康保険料の計算方法
健康保険料は、従業員が受け取る毎月の給与(より正確には、その給与を基に決定される「標準報酬月額」)に「健康保険料率」を乗じて算出され、その金額を会社と従業員が原則として半分ずつ負担(労使折半)します。
| ■健康保険料の計算式 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 |
「健康保険料率」は、会社が加入している健康保険の種類によって異なります。主な健康保険には、大企業などが独自に設立・運営する「健康保険組合(組合健保)」と、主に中小企業の従業員が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類があります。
協会けんぽに加入している場合は、適用事業所の所在地によって保険料率が異なります。
【計算例(令和7年度 東京都 協会けんぽ料率を使用)】
東京都に事業所があり、協会けんぽに加入している会社に勤務する従業員(35歳、介護保険第2号被保険者に該当しない)の標準報酬月額が30万円の場合の健康保険料を計算してみましょう。
- 健康保険料(総額): 300,000円 × 9.91% = 29,730円
- 従業員負担額: 29,730円 ÷ 2 = 14,865円
- 会社負担額: 29,730円 ÷ 2 = 14,865円
◯計算に用いた保険料率(令和7年度 東京都 協会けんぽの場合)
- 介護保険第2号被保険者に該当しない場合(40歳未満の方など):9.91%
- 介護保険第2号被保険者に該当する場合(40歳以上65歳未満の方):11.50% (内訳:健康保険料率9.91% + 介護保険料率1.59%)
参照:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
【注意点】
- 従業員が40歳以上65歳未満の場合(介護保険第2号被保険者)は、上記の健康保険料率に介護保険料率が上乗せされた料率(東京都の令和7年度協会けんぽの場合は11.50%)で計算します。
- 他の都道府県の協会けんぽの保険料率や、ご加入の健康保険組合が定める保険料率は、ここで示した東京都の例とは異なります。必ず自社が加入している保険者の最新の保険料率を確認し、それに基づいて正確に計算してください。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は、従業員の老後の生活などを支えるための重要な社会保険料であり、その計算は「標準報酬月額」に基づいて行われます。算出された保険料は、会社(事業主)と従業員(被保険者)が半分ずつ負担する労使折半が原則です。
| ■厚生年金保険料の計算式 厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 |
「厚生年金保険料率」は、全国一律で18.3%と定められています。この料率は平成29年9月以降固定されており、令和7年度においても変更の予定はありません。
【計算例】
標準報酬月額が30万円の従業員の場合の厚生年金保険料を計算してみましょう。
- 厚生年金保険料(総額): 300,000円(標準報酬月額) × 18.3%(厚生年金保険料率) = 54,900円
- 従業員負担額: 54,900円 ÷ 2 = 27,450円
- 会社負担額: 54,900円 ÷ 2 = 27,450円
このように、厚生年金保険料の計算は、標準報酬月額に全国共通の保険料率を乗じ、その結果を会社と従業員で折半することで求められます。
会社としては、従業員負担分を給与から適切に天引きするとともに、会社負担分と合わせて日本年金機構へ納付する義務があります。
介護保険料の計算方法(40歳以上65歳未満の被保険者)
介護保険料は、40歳以上65歳未満の健康保険に加入している従業員(介護保険第2号被保険者)が負担する保険料です。「標準報酬月額」に「介護保険料率」を乗じて算出され、その金額を会社と従業員で半分ずつ負担します。協会けんぽの場合、健康保険料と合わせて徴収される点に留意しましょう。
| ■介護保険料の計算式 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 |
従業員(45歳、介護保険第2号被保険者に該当)の標準報酬月額が30万円の場合の介護保険料は、以下の通りです。
- 介護保険料(総額): 300,000円(標準報酬月額) × 1.59%(介護保険料率) = 4,770円
- 従業員負担額: 4,770円 ÷ 2 = 2,385円
- 会社負担額: 4,770円 ÷ 2 = 2,385円
なお、健康保険料と合わせて徴収される場合、東京都の協会けんぽの令和7年度の料率では、健康保険料率9.91%と介護保険料率1.59%を合計した11.50%で計算された保険料総額(この例では34,500円)から、それぞれの負担額が按分されます。
65歳になると、従業員は介護保険第1号被保険者となり、原則として市区町村から直接介護保険料を納付する形に変わるため、給与からの天引きはなくなります。
雇用保険の計算方法
雇用保険料は、従業員に支払われる毎月の「賃金総額」に「雇用保険料率」を乗じて算出され、会社と従業員の双方が負担する仕組みです。ただし、その負担割合は会社と従業員で異なります。
他の社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)が「標準報酬月額」を基に計算されるのに対し、雇用保険料は、毎月の賃金総額(基本給のほか、残業手当や通勤手当など、税金や社会保険料が引かれる前の総支給額すべて)を計算の基礎とします。
| ■雇用保険料の計算式 雇用保険料(月額) = 賃金総額 × 雇用保険料率 |
「雇用保険料率」は、国によって毎年度見直され、会社の事業の種類によって異なります。令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の雇用保険料率は以下の通りです。
- 一般の事業:1.45%
- 農林水産・清酒製造の事業:1.65%
- 建設の事業:1.75%
◯負担割合(一般の事業の場合、令和7年度)
- 従業員(労働者)負担:0.55% (5.5/1,000)
- 会社(事業主)負担:0.9% (9.0/1,000)
(事業主負担の内訳:失業等給付・育児休業給付の保険料率 0.55% + 雇用保険二事業の保険料率 0.35%)
参照:厚生労働省「令和7年度の雇用保険料率について」
【計算例(令和7年度 一般の事業の料率を使用)】
一般の事業を行う会社に勤務する従業員の、ある月の賃金総額が30万円だった場合の雇用保険料は、以下のように計算されます。
- 雇用保険料(総額): 300,000円(賃金総額) × 1.45%(一般の事業の雇用保険料率) = 4,350円
- 従業員負担額: 300,000円 × 0.55%(労働者負担率) = 1,650円
- 会社負担額: 300,000円 × 0.9%(事業主負担率) = 2,700円
雇用保険料率は毎年度変更される可能性があるため、必ず毎年4月からの新しい料率を厚生労働省のウェブサイトなどで確認するようにしてください。また、農林水産・清酒製造の事業や建設の事業に従事している場合は、適用される料率が一般の事業と異なる点にも注意が必要です。
労災保険の計算方法(全額事業主負担)
労災保険料は、従業員の業務中や通勤中のケガや病気に備えるための保険であり、その保険料は全額を会社(事業主)が負担します。従業員の給与から天引きされることはありません。
労災保険料の計算は、従業員に支払われる年間の「賃金総額」(原則として4月1日から翌年3月31日までに支払われる賃金の合計)に、事業の種類ごとに定められた「労災保険料率」を乗じて算出します。
| ■労災保険料の計算式 労災保険料(年間) = 年間の賃金総額 × 労災保険料率 |
「労災保険料率」は、会社の事業内容によって異なり、その事業の過去の労働災害の発生状況などを考慮して細かく定められています。料率は数年ごとに見直されることがあります。
例えば、令和6年度の料率では、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」の場合は3/1,000(0.3%)、「運輸業、郵便業」の場合は6/1,000(0.6%)などと設定されています。
参照:令和7年度の労災保険率等(厚生労働省)
【計算例(令和7年度料率を使用)】
卸売業(労災保険料率0.3%と仮定)を営む会社に勤務する従業員の年間賃金総額が400万円の場合の労災保険料(会社負担額)は、以下のように計算されます。
労災保険料(会社負担額): 400,0000円(年間の賃金総額) × 0.3%(仮の労災保険料率) = 12,000円
労災保険料率は、事業の種類によって数十種類に分類されており、自社の事業がどの料率区分に該当するのかを正確に把握することが非常に重要です。誤った料率で申告・納付すると、後日、追加徴収や還付の手続きが必要になる場合があります。
労災保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度とし、その年度の初めに概算の保険料を申告・納付し、翌年度の初めに確定した賃金総額に基づいて確定保険料を計算し、過不足を精算する「年度更新」という手続きによって納付します。
毎月の給与計算において直接従業員から徴収するものではありませんが、会社が負担する重要なコストの一つとして正しく理解しておきましょう。計算方法や料率について不明な点があれば、所轄の労働基準監督署や労働局、または社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
【関連記事】
> 社会保険料の計算シミュレーション!自動計算ツールと早見表【2025年版】
従業員に賞与(ボーナス)を支給する場合も、毎月の給与と同様に社会保険料が徴収されます。ただし、計算の基礎となるものが「標準報酬月額」ではなく「標準賞与額」となる点や、対象となる保険の種類に注意が必要です。
ここでは、賞与から引かれる社会保険料の種類と、それぞれの計算方法、会社負担額について具体的に解説します。
まず、賞与から徴収される主な社会保険料は以下の通りです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上65歳未満の被保険者の場合)
- 雇用保険料
労災保険料は、賞与からも毎月の給与からも直接徴収されるものではなく、年度末に年間の賃金総額で計算されるため、ここでは割愛します。
標準賞与額とは?
賞与にかかる健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料を計算する際の基礎となるのが「標準賞与額」です。 標準賞与額は、実際に支給された賞与の額面金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額となります。
標準賞与額には上限が設けられています。
- 健康保険:年度の累計額で573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計)
- 厚生年金保険:1ヶ月あたり150万円(同じ月に複数回支給された場合は合算して判断)
上限を超える賞与が支給された場合でも、保険料計算に用いる標準賞与額は上記の上限額となります。
【各社会保険料の計算方法と計算例】
ここでは、従業員(45歳、東京都の協会けんぽに加入)に賞与555,500円が支給された場合の社会保険料を計算してみましょう。
1. 標準賞与額の決定
支給額555,500円の1,000円未満を切り捨てて、標準賞与額は555,000円となります。
2. 健康保険料の計算 (料率:9.91% + 1.59% = 11.50%)
- 健康保険料(総額):555,000円 × 11.50% = 63,825円
- 従業員負担額:63,825円 ÷ 2 = 31,912.5円 → 31,913円(※)
- 会社負担額:63,825円 ÷ 2 = 31,912.5円 → 31,912円(※)
- ※端数処理については、後述のQ&Aで解説しますが、一般的に従業員負担分を切り上げ、会社負担分を切り捨てることがあります(労使協定等による)。ここではその例で計算しています。
3. 厚生年金保険料の計算 (料率:18.3%)
- 厚生年金保険料(総額):555,000円 × 18.3% = 101,565円
- 従業員負担額:101,565円 ÷ 2 = 50,782.5円 → 50,783円(※)
- 会社負担額:101,565円 ÷ 2 = 50,782.5円 → 50,782円(※)
4. 雇用保険料の計算 雇用保険料は、標準賞与額ではなく、実際に支給された賞与の額面金額(555,500円)に雇用保険料率を乗じて計算します。
- 雇用保険料(総額):555,500円 × 1.45% = 8,054.75円 → 8,054円(1円未満切り捨て)
- 従業員負担額:555,500円 × 0.55% = 3,055.25円 → 3,055円(1円未満切り捨て)
- 会社負担額:555,500円 × 0.9% = 4,999.5円 → 4,999円(1円未満切り捨て)
【賞与支給時の注意点】
◯賞与支払届の提出
賞与を支給した場合は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります。
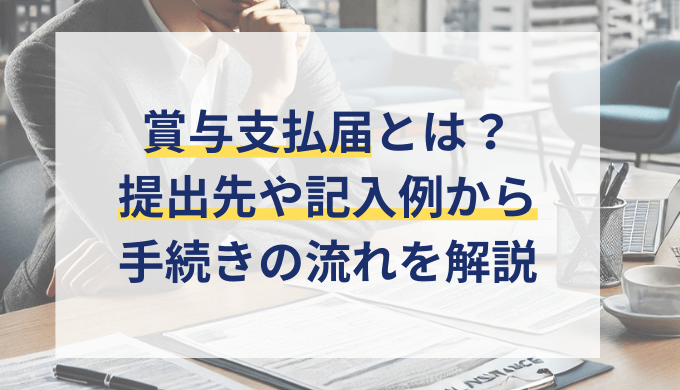 賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
◯年4回以上の賞与の扱い
年に4回以上支給される賞与は、社会保険上は「報酬」とみなされ、標準報酬月額の算定基礎に含まれます。この場合、標準賞与額としての取り扱いではなく、毎月の給与と同様に標準報酬月額を決定し、それに基づいて保険料が計算されます。
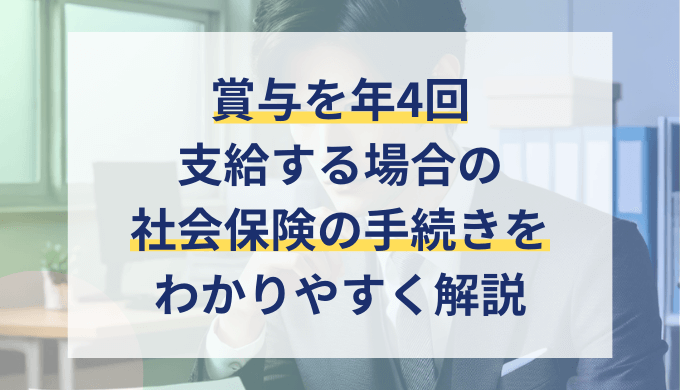 賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
賞与からの社会保険料計算も、毎月の給与計算と同様に正確に行うことが求められます。特に標準賞与額の決定ルールや上限額、届出の義務をしっかりと理解しておきましょう。
健康保険料、厚生年金保険料、そして40歳以上65歳未満の方の介護保険料を計算する上で、最も基本となるのが「標準報酬月額」と「標準賞与額」です。
社会保険料の計算に給与額や賞与額そのものではなく、「標準額」を用いる理由は、毎月の給与が残業手当などで変動するたびに保険料を計算し直すのは非常に煩雑になるため、計算事務を簡略化し、保険料額を一定期間安定させる目的があるからです。
ここでは、標準報酬月額と標準賞与額がそれぞれ何を指し、どのように社会保険料計算に関わってくるのかを解説します。
【標準報酬月額と標準賞与額の概要】
| 項目 | 標準報酬月額 | 標準賞与額 |
| 定義 | 従業員が受け取る月々の給与(報酬)を、保険料計算のために一定の区切り(等級)に当てはめたもの。 | 従業員に支給される賞与(ボーナス)から、保険料計算のために1,000円未満の端数を切り捨てたもの。 |
| 対象となるもの | 基本給、役付手当、職階手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当など、名称を問わず労働の対償として経常的に支払われるもの全て。現物支給(食事、社宅など)も含む。 | 税引前の賞与額。ただし、年3回以下の支給に限る(年4回以上支給される賞与は標準報酬月額の対象となる)。 |
| 決定・改定 | 従業員の入社時(資格取得時)、毎年1回の定時決定(算定基礎届)、給与が大幅に変動した際の随時改定(月額変更届)、育児休業等終了時改定など。 | 賞与が支給される都度、その支給額に基づいて決定。 |
| 主な用途 | 毎月の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算。傷病手当金や出産手当金、将来の年金額の計算基礎にもなる。 | 賞与支給時の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の計算。 |
標準報酬月額は、毎月の給与計算における社会保険料の天引き額を決定するだけでなく、従業員が病気やケガで休業した際に支給される傷病手当金や、出産時に支給される出産手当金の額、さらには将来受け取る厚生年金の額にも影響を与える非常に重要な金額です。
一方、標準賞与額は、賞与から天引きする社会保険料を計算するために用いられます。
これらの標準額がどのように決定・改定されるのか、そのタイミングを次に見ていきましょう。
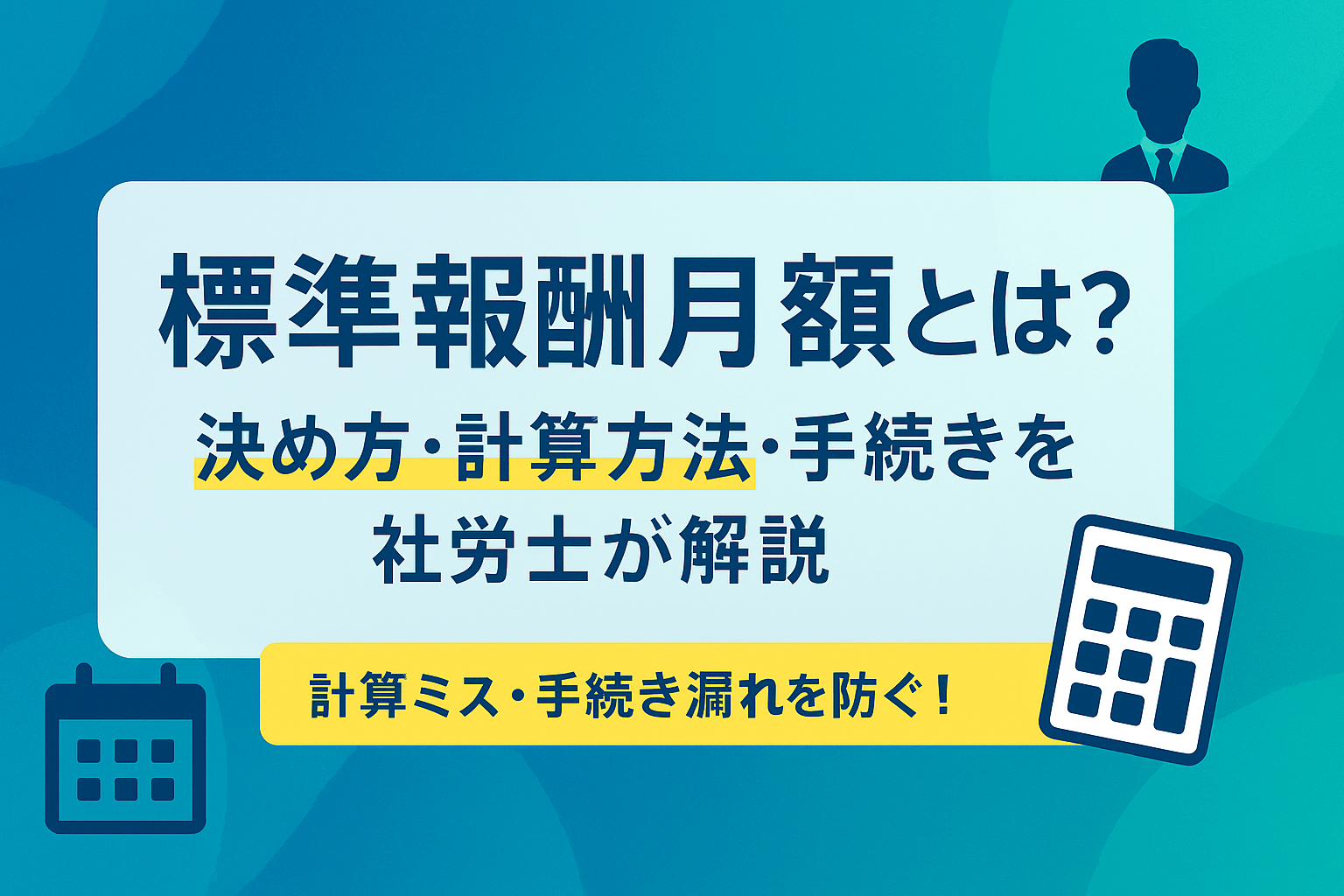 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
標準報酬月額が改定されるタイミング
従業員の給与(報酬)に大きな変動があった場合など、特定のタイミングで見直し(改定)が行われます。会社の人事労務担当者は、これらの改定タイミングを正確に把握し、適切な手続きを行う必要があります。
主な改定のタイミングは以下の通りです。
- 資格取得時決定: 新たに従業員を雇用し、社会保険に加入する際
- 定時決定: 年に一度、全被保険者を対象に行う定期的な見直し
- 随時改定: 昇給や降給などにより、月々の給与が大幅に変動した際
- 育児休業等終了時改定: 育児休業などを終えて復職した際
これらのうち、特に実務で頻繁に関わるのが「定時決定」と「随時改定」です。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
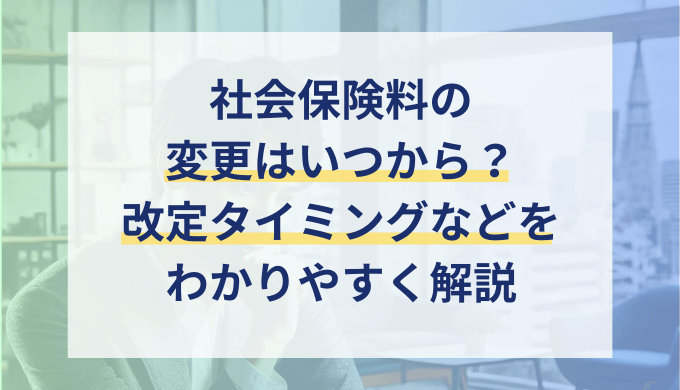 社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
定時決定とは、毎年1回、会社が全ての被保険者について、その年の4月、5月、6月に支払った給与(報酬)の平均額を基に新しい標準報酬月額を決定し、日本年金機構および健康保険組合に届け出る手続きのことです。この手続きで提出する書類が「被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)」であるため、一般的に「算定(さんてい)」とも呼ばれます。
算定基礎届を提出する目的は、従業員が実際に受け取る給与額と、社会保険料計算の基礎となる標準報酬月額との間に大きなズレが生じないように、年に一度見直しを行うことで、保険料負担の公平性を保つためです。
変更された標準報酬月額は9月から適用され、健康保険料などの天引きは翌月の給与から行われるため(翌月徴収の場合)、新たな標準報酬月額が反映された保険料は、一般的に10月支給の給与から控除されます。
この定時決定は、社会保険事務の中でも特に重要な手続きの一つです。算定基礎届の作成・提出を誤ると、従業員の保険料額や将来の年金額に影響が出る可能性があるため、慎重な対応が求められます。対象となる報酬の範囲や支払基礎日数の考え方を正しく理解し、手続きを進めることが重要です。
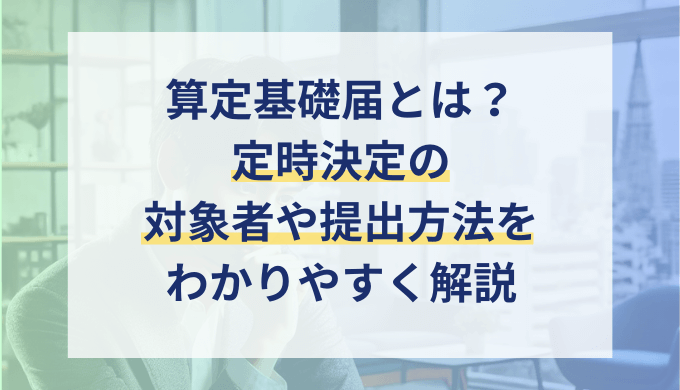 算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
随時改定とは、昇給や降給、あるいは給与体系の変更などにより、従業員の月々の固定的賃金に大幅な変動があり、その結果、標準報酬月額の等級が大きく変わる場合に、次の定時決定を待たずして標準報酬月額を見直す手続きのことです。「月額変更」とも呼ばれます。
月額変更届を提出する目的は、実際の給与と標準報酬月額との間に著しい差が生じた状態が長期間続くことを避け、より実態に即した保険料負担とするためです。
随時改定(月額変更)が行われるのは、主に以下の3つの条件をすべて満たした場合です。
- 固定的賃金の変動があったこと
- 変動月以後継続した3ヶ月間の支払基礎日数がすべて17日以上あること
- 変動月以後継続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額に基づく標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
決定される新しい標準報酬月額の適用期間は、原則として、固定的賃金の変動があった月から数えて4ヶ月目から、次の定時決定(通常は8月)までとなります。
上記の3つの条件をすべて満たした場合は、事業主は速やかに「被保険者報酬月額変更届」を管轄の年金事務所または事務センター(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合にも)へ提出しなければなりません。
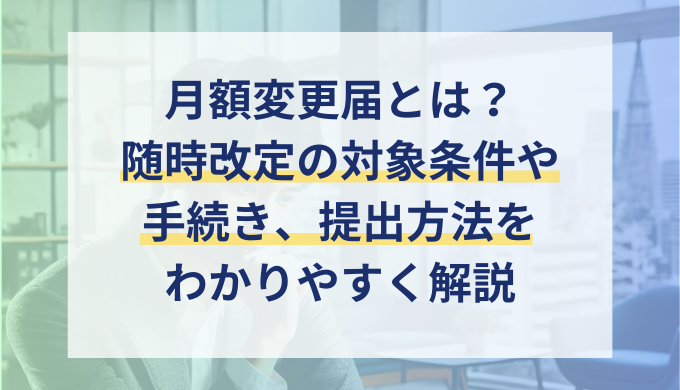 社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
社会保険料の計算は、毎月の給与計算や賞与計算において避けて通れない重要な業務です。計算方法を理解するだけでなく、実務で間違いやすいポイントや、法改正などにより注意すべき点を押さえておくことが、正確な処理とコンプライアンス遵守につながります。
ここでは、社会保険料を計算する上で特に注意しておきたい点を5つ解説します。
社会保険料率は改定されることがある
健康保険料率や介護保険料率、雇用保険料率は、毎年度見直しが行われ、改定されることがあります。特に協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年3月分(4月納付分)から新しい料率が適用されるのが一般的です。 厚生年金保険料率は現在18.3%で固定されていますが、将来的に変更がないとは限りません。
労災保険料率も事業の種類ごとに定められており、数年ごとに見直されることがあります。
【実務上のチェックポイント】
◯最新料率の確認時期
毎年2月~3月頃には、協会けんぽや厚生労働省のウェブサイトで翌年度の保険料率が公表されるため、必ず確認しましょう。
◯給与計算システムへの反映
給与計算ソフトを使用している場合でも、新しい料率が正しくシステムに設定されているかを確認することが不可欠です。手動で設定変更が必要な場合もあります。
◯社内周知
保険料率の変更は、従業員の手取り額にも影響するため、変更がある場合は事前に従業員へ周知することが望ましいでしょう。
古い料率で計算してしまうと、保険料の徴収不足や過払いが発生し、後日の訂正や精算業務が非常に煩雑になります。常に最新の情報を確認する習慣をつけましょう。
産休・育休中は条件を満たせば社会保険料が免除になる
従業員が産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得する期間中は、一定の要件を満たせば、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料(該当者のみ)が、従業員負担分だけでなく会社負担分も共に免除されます。
対象となる保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料です。
この免除制度は、休業中の従業員と会社の経済的負担を軽減する重要な制度です。手続き漏れがないよう、従業員から産休・育休の申し出があった際には速やかに対応しましょう。
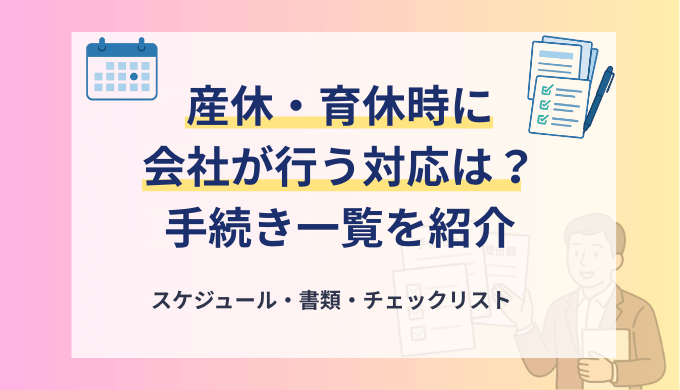 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
雇用保険料以外は日割計算がない
社会保険料の計算において、月の途中で入社したり退職したりした場合の取り扱いは、保険の種類によって異なります。特に、日割り計算の有無は重要なポイントです。
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、月単位で計算され、日割り計算は行われません。
資格取得日(入社日など)が月の途中であっても、その月1ヶ月分の保険料が発生します。資格喪失日(退職日の翌日など)が月の途中である場合、資格喪失日が属する月の前月分までの保険料が発生し、資格喪失月分の保険料は発生しません。
例)5月15日に入社した場合
5月分の保険料から発生します。5月20日に退職した場合(資格喪失日は5月21日)、4月分の保険料までが発生し、5月分の保険料は発生しません。ただし、同月内に資格取得と資格喪失があった場合は、1ヶ月分の保険料が発生します。
雇用保険料は、その月に支払われた賃金総額を基に計算されるため、月の途中で入退社し、支払われる賃金額が少なければ、それに応じて保険料も少なくなります。実質的に日割り計算に近い考え方です。
この日割り計算の有無を誤ると、保険料の徴収額に過不足が生じるため、正確に理解しておく必要があります。
月の途中で入退社した場合の計算
従業員が月の途中で入社したり退職したりした場合の社会保険料の計算は、特に注意が必要です。前述の「雇用保険料以外は日割計算がない」という原則と、資格取得日・喪失日の考え方を正確に理解しておく必要があります。
【入社時の社会保険料】
資格取得日は、原則として入社した日です。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、資格取得日が月の途中であっても、その月1ヶ月分の保険料が発生します。日割り計算はされません。
| 例:5月15日に入社した場合5月分の保険料全額が徴収対象 |
徴収タイミングは会社の規定によりますが、入社月の給与から徴収するか、翌月の給与から徴収するケースが一般的です。
雇用保険料は、入社月に支払われる賃金総額に対して、所定の保険料率を乗じて計算します。
【退職時の社会保険料】
資格喪失日は、原則として退職した日の翌日。健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、資格喪失日が属する月の保険料は発生しません。 その前月分までの保険料が徴収対象となります。
| 例:5月20日に退職した場合資格喪失日:5月21日この場合、5月分の保険料は発生せず、4月分の保険料までが徴収対象となります。 |
| 【例外:月末退職】月末(例:5月31日)に退職した場合資格喪失日は翌月の1日(例:6月1日)この場合、退職月(5月)分の保険料まで発生します。 |
徴収タイミングは、最終給与から控除するのが一般的ですが、退職日によっては調整が必要になる場合があります。
雇用保険料は、退職月に支払われる賃金総額に対して、所定の保険料率を乗じて計算します。
月の途中での入退社は、給与計算の中でも特に間違いやすいポイントです。資格取得日と喪失日の正確な把握、そして各保険料の徴収ルールをしっかりと確認し、適切な処理を行いましょう。
社会保険料の対象とならない支払いもある
毎月の給与や賞与に含まれるすべての支払いが、社会保険料の計算基礎となる「報酬」や「賃金総額」に該当するわけではありません。社会保険料の対象とならない支払い(報酬に含めないもの)を正しく区別することが重要です。
【社会保険料(標準報酬月額・標準賞与額の算定)の対象とならない主な支払い例】
| 臨時に受けるもの | ・結婚祝金、弔慰金、災害見舞金 ・大入袋(おおぶくろ)など、恩恵的に支給されるもの |
| 実費弁償的なもの | ・出張旅費、赴任旅費(実費精算分) ・業務遂行に必要な作業着代や工具代の会社負担分 |
| その他 | ・退職金、解雇予告手当・会社が負担する財形貯蓄の奨励金(一部例外あり) ・傷病手当金、出産手当金、労災保険からの給付など、社会保険制度から支給されるもの |
報酬の範囲を誤って解釈すると、標準報酬月額や標準賞与額が不正確になり、結果として保険料の計算ミスにつながります。判断に迷う手当や支払いがある場合は、日本年金機構のガイドラインを確認するか、社会保険労務士に相談しましょう。
社会保険料の計算は複雑で、実務では様々な疑問が生じることがあります。ここでは、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。日々の業務の参考にしてください。
4月~6月の残業が多いと、社会保険料は高くなりますか?
4月、5月、6月に残業が多いと社会保険料が高くなる可能性があります。
これは、毎年7月に行われる「定時決定(算定基礎届の提出)」という手続きで、4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額に基づいて新しい標準報酬月額が決定されるためです。この3ヶ月間の報酬には、基本給だけでなく残業手当も含まれます。
したがって、この期間に残業が多く、支払われた報酬総額が増加すると、標準報酬月額の等級が上がり、結果として9月以降の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料。従業員負担分および会社負担分)が増加することがあります。
社会保険料の計算における端数、小数点以下の処理は?
社会保険料の計算過程で発生する端数(1円未満の数値)の処理方法は、法律や通達で定められています。原則として、従業員負担分の保険料に50銭以下の端数が生じた場合は切り捨て、50銭を超える端数が生じた場合は切り上げて1円とします。
具体的には以下の通りです。
◯健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(従業員負担分)
- 計算結果の1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て。
- 計算結果の1円未満の端数が50銭を超える場合は切り上げて1円とする。
例)従業員負担分の計算結果が14,865.50円であれば14,865円に、14,865.51円であれば14,866円になります。
◯会社(事業主)負担分の端数処理
法律上、会社負担分の端数処理について明確な規定はありません。そのため、上記の従業員負担分と同じ処理(50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ)をするか、あるいは労使間の取り決め(就業規則や労働協約など)によって、例えば「会社負担分は切り捨て」とすることも可能です。実務上は、保険料総額から従業員負担分を差し引いた残額を会社負担分とするケースが多いです。
◯雇用保険料(従業員負担分)
- 計算結果の1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て。
- 計算結果の1円未満の端数が50銭を超える場合は切り上げて1円とする。
ただし、慣習として、賃金総額に労働者負担率を乗じて算出した額の1円未満を切り捨てている事業所も多く見られます。どちらの処理とするかは、会社の規定やこれまでの慣例に従うことになりますが、一貫した処理が必要です。
◯保険料率の小数点以下の扱い
健康保険料率や雇用保険料率は、通常「〇〇/1,000」や「〇.〇〇〇%」のように小数点以下第2位または第3位まで設定されています。計算時には、この公表されている料率をそのまま用いて計算します。
端数処理は、わずかな金額の違いであっても、毎月の積み重ねや従業員数によっては大きな影響となる場合があります。法令に基づいた正しい処理方法を理解し、社内で統一したルールで運用することが重要です。
不明な点があれば、管轄の年金事務所やハローワーク、または社労士に確認しましょう。
本記事では、事業主や人事労務担当者の皆様が社会保険料の計算方法を正しく理解し、実務に役立てていただけるよう、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険といった各種社会保険料の計算方法について、会社負担分も含めて具体的な計算例を交えながら解説してきました。
社会保険料の計算は、一見複雑に感じるかもしれませんが、本記事で解説した一つひとつのルールや計算のステップを正しく理解し、手順に沿って処理すれば、決して難しいものではありません。
特に、給与計算ソフトを導入されていない小規模事業所の経営者様やご担当者様にとっては、ご自身で計算の仕組みを把握し、その正確性を確認できることは、日々の業務における大きな安心感につながるはずです。
社会保険料計算の多くは「標準報酬月額」を基礎としており、この標準報酬月額は実際の給与を等級に当てはめた「みなし報酬月額」です。給与の額面や手取り額とは異なる点を理解しておく必要があります。また、標準報酬月額は、年に一度の定時決定(算定基礎届)や、昇給・降給などがあった場合の随時改定(月額変更届)などで見直されるため、それぞれのケースで適切な手続きを期限内に行うことが不可欠です。
計算ミスや届出漏れは、追徴金や延滞金といったリスクを伴います。さらに、健康保険料率や介護保険料率、雇用保険料率は毎年度改定される可能性があり、法改正などによってパート・アルバイトの方などの加入対象者も変動するため、常に最新の情報を収集し、正しい保険料を計算できるようにすることが大切です。
特に、年に一度の定時決定や、随時改定の要件判断は、多くの情報を整理し確認する必要があるため、担当者の方にとっては大きな負担となり、専門的な知識も求められます。
正確かつ効率的な手続きのためには専門家である社労士に相談、申請代行することも検討しましょう。
社労士クラウドのスポット申請代行サービス
「社会保険料の計算方法が複雑でよくわからない…」「標準報酬月額の算定や、それに基づく算定基礎届・月額変更届の作成が毎年大変…」「計算ミスによる追徴金のリスクが心配…」
このような、社会保険料の計算に関するお悩みをお持ちではありませんか?
社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の決定は、専門知識が必要で複雑です。誤った計算は、追徴金や従業員の不信感にも繋がりかねません。
そのような社会保険料計算に関するお悩みを解決するのが、「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスです。
当サービスでは、社会保険料計算に不可欠な標準報酬月額に関わる算定基礎届や月額変更届の作成・提出代行をはじめ、関連する社会保険手続きを必要な業務だけスポット(単発)でご依頼いただけます。
顧問契約は不要ですので、費用を抑えつつ、専門家である社会保険労務士のサポートを受けることが可能です。社労士が最新の法令に基づき、正確かつ迅速に手続きを代行することで、お客様は面倒な社会保険料計算や手続きから解放され、コア業務に集中いただけます。オンラインで全国どこからでもご依頼可能です。
社会保険料の計算や手続きでお困りの際は、ぜひ一度「社労士クラウド」のスポット代行サービスをご検討ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 1,800社以上の社会保険手続き実績|

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|