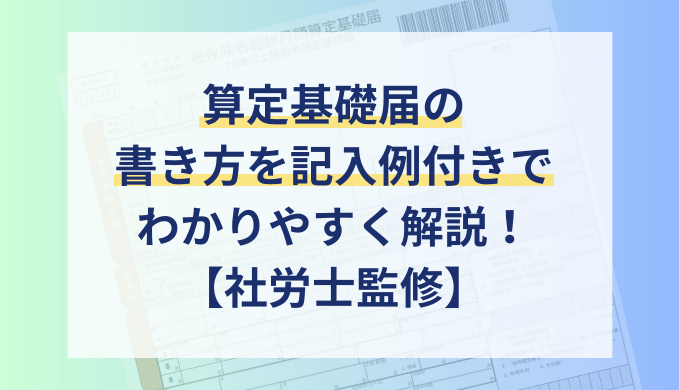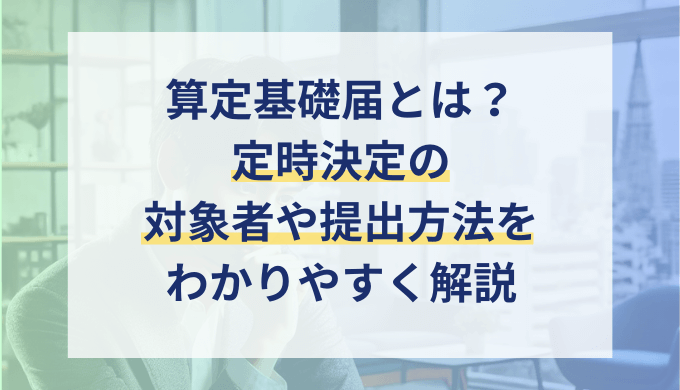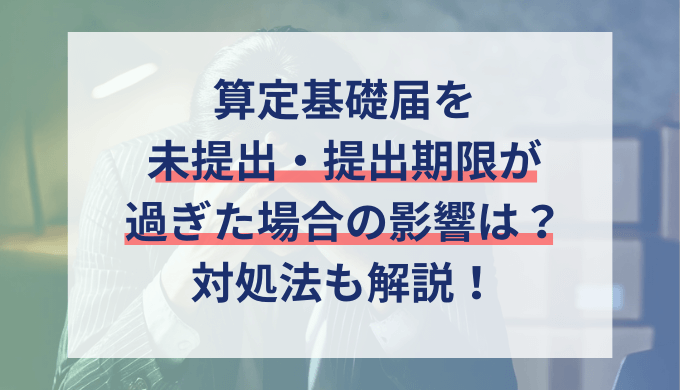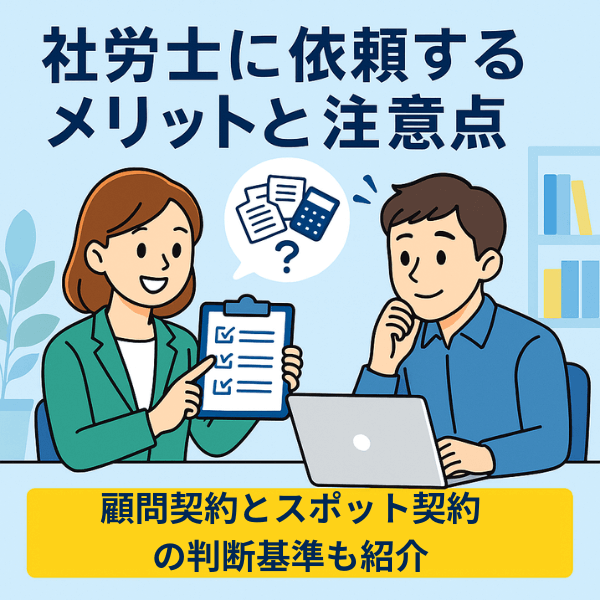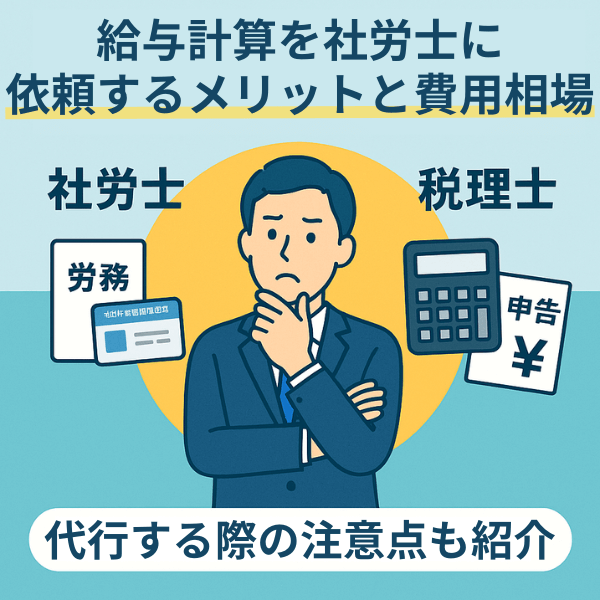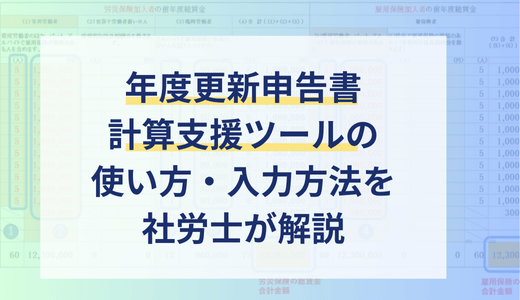社会保険に加入している事業所にとって、毎年7月の「算定基礎届」の提出は、避けて通れない重要な業務です。この届出は、従業員の健康保険と厚生年金保険の保険料、さらには将来の年金受給額を計算する上で基となる「標準報酬月額」を決定するために不可欠な手続きなのです。
しかし、算定基礎届の記載する支払基礎日数や報酬額の算出は複雑で、頭を悩ませている労務担当者の方も多いのではないでしょうか?
特に、途中入社や退職者がいる場合、休職や昇給があった場合、また、短時間労働者の扱いなど、イレギュラーなケースでは判断に迷うこともあるでしょう。
この記事では、算定基礎届の基本的な書き方を記入例付きでわかりやすく解説します。さらに、支払基礎日数に17日未満の月がある場合や、短時間就労者(パートタイマー)、短時間労働者のケース別の書き方や、イレギュラーなケースでの手続きについても詳しく紹介しています。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
労働保険の年度更新や算定基礎届など、労働保険・社会保険の手続きは、1年のうちで決まったタイミングで発生するものと、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きが必要なもの、また生年月日に応じて必要な必須の手続きがあります。
⇒社会保険・労働保険手続きの年間スケジュール(PDF)を無料ダウンロード
算定基礎届とは、健康保険と厚生年金保険に加入している従業員(被保険者および70歳以上被用者)の標準報酬月額を決定するために、事業主が毎年4月から6月に支払った報酬月額を日本年金機構または健康保険組合に届け出る書類です。
以下は実際の算定基礎届の見本です。「事業所・事業主情報」「対象者の基本情報」「対象者の報酬情報」「備考」を記入する欄があります。記入項目と書き方については、後ほど詳しく説明します。
この手続きは「定時決定」と呼ばれており、実際の給与と標準報酬月額に大きな差が生じないように、毎年1回見直しが行われます。そして、決定された標準報酬月額に基づいて、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が算出され、適用されます。
算定基礎届の提出は、健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条で定められた事業主の義務です。毎年、提出期限が設けられており、7月1日から7月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、日本年金機構または健康保険組合へ提出する必要があります。
提出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので注意が必要です。
算定基礎届の作成から提出までの流れは、次の3つのステップで進めます。
- 算定基礎届を書くために必要な事前準備
対象者を確認し、4月・5月・6月に支払った報酬額を集計・計算します。 - 算定基礎届の作成と提出
事前準備で算出したデータをもとに届出書を記入し、期限内に提出します。 - 標準報酬月額決定通知書の送付
標準月額の決定通知書が日本年金機構から送付されてきます。
標準報酬月額の決定後、実際の社会保険料はいつから変更されるのか気になる方も多いでしょう。
この点については、以下の記事で詳しく解説しています。
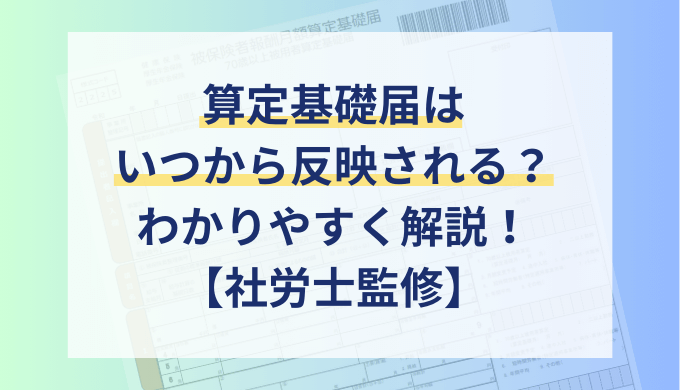 算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説
算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説
算定基礎届には、次の3つを算出し記載する必要があるため事前に計算して準備する必要があります。
- 対象となる従業員を確認する
- 4月・5月・6月に支払った報酬額を集計・計算
算定基礎届の提出が必要な従業員
算定基礎届の提出が必要なのは、原則として、7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている全ての従業員です。具体的には、以下の条件に当てはまる従業員が提出対象となります。
- 7月1日時点で在職中の全ての被保険者(正社員、契約社員、パート、アルバイト等、社会保険加入者全員)
- 産前産後休業中、育児・介護休業中の従業員(休業中も社会保険に加入している方)
- 70歳以上の従業員(健康保険被保険者または厚生年金70歳以上被用者)
- 出向中の従業員
また、個人事業主でも、常時5名以上の従業員を雇用したり、任意適用など社会保険の適用事業所になっている場合は、算定基礎届の提出が必要です。
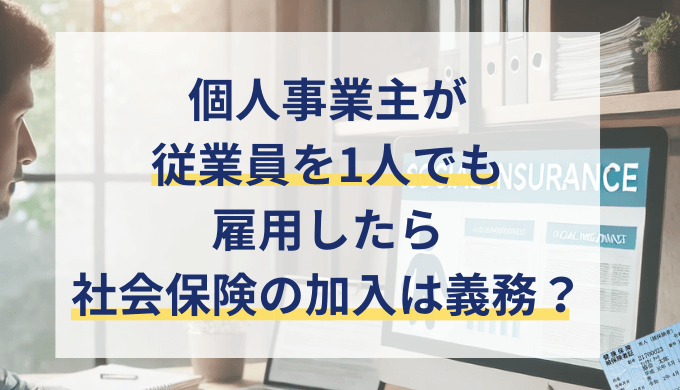 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
4月・5月・6月に支払った報酬額を集計・計算
算定基礎届を作成するためには、まず対象となる従業員の4月、5月、6月の報酬額を正確に集計・計算する必要があります。ここでいう報酬額には、基本給だけでなく、各種手当(役職手当、通勤手当、残業手当など)や現物給与も含まれます。注意点として、賞与は含めないことを忘れないようにしましょう。
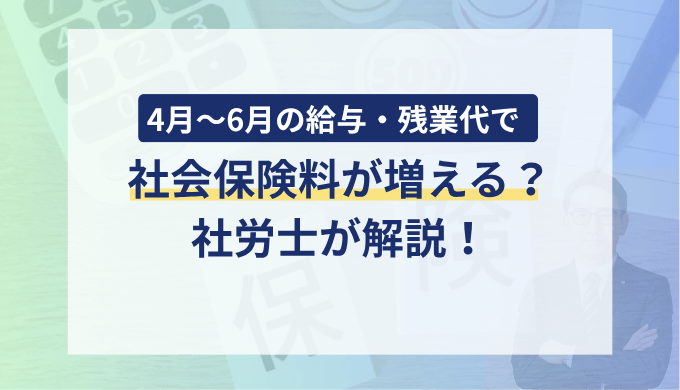 社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説
社会保険料は4から6月の給与で決まる!仕組みと注意点を社労士が解説
具体的な流れは以下のとおりです。
3か月分の総支給額を合計し、3で割った金額を求めます。これが「報酬月額」となり、標準報酬月額の決定基準になります。
対象となる従業員ごとに、4月、5月、6月に支払った給与明細を準備します。
各月の総支給額(課税対象となる額)を計算します。控除後の手取り額ではなく、支給総額である点に注意してください。
- 現物給与の扱い
会社が従業員に支給する住宅や食事などの現物給与がある場合、それも報酬に含めます。 - 締日と支払日のずれ
報酬は「支払基準」でカウントするため、締日が3月分でも4月に支払った場合は4月分として計算します。
なお、標準報酬月額の算出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
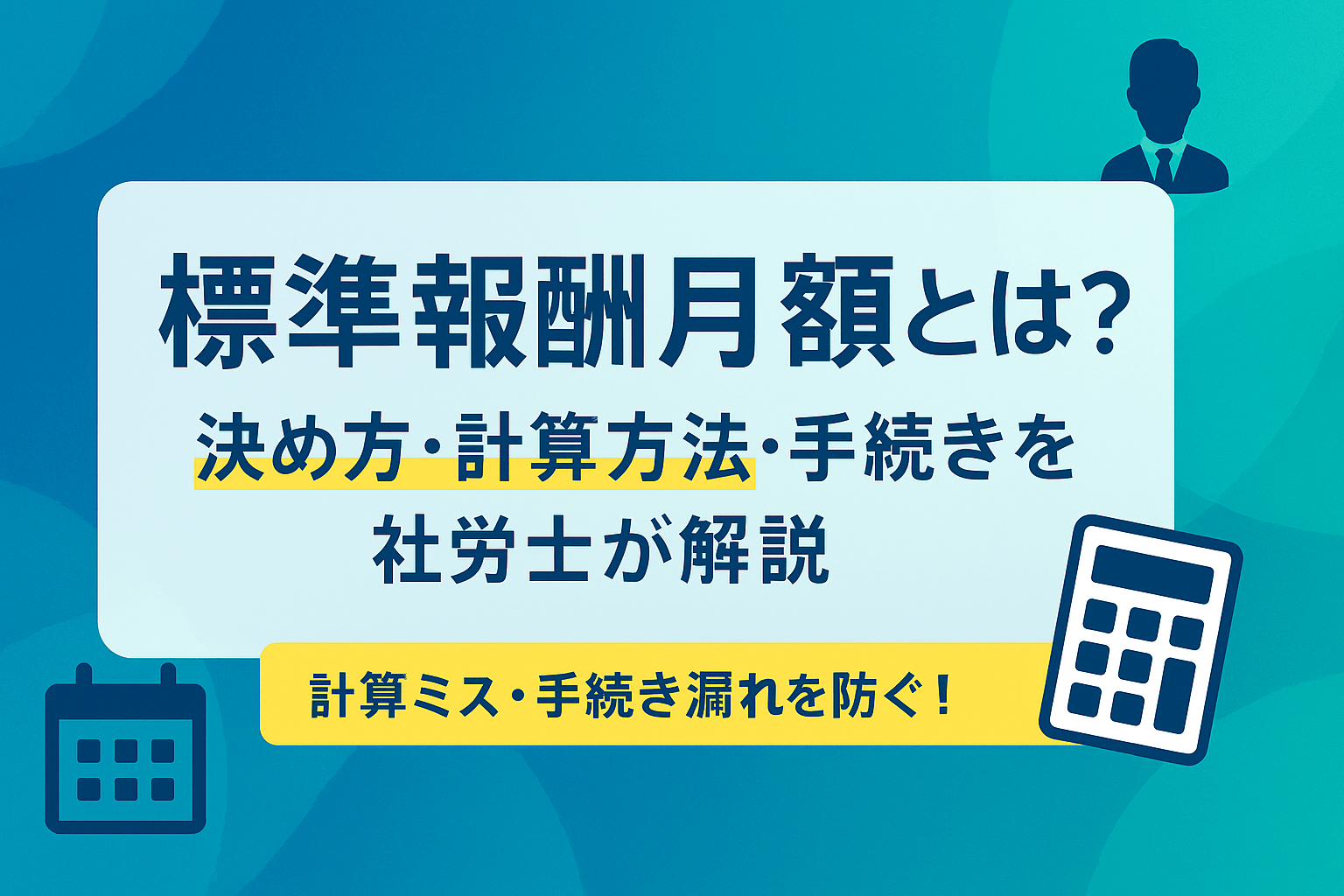 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
算定基礎届は、健康保険と厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額を決定するために、事業主が毎年4月から6月に支払った報酬月額を日本年金機構または健康保険組合に届け出るための書類です。
ここでは、算定基礎届の各項目の書き方について、手順を追って説明します。
算定基礎届の見本(画像)を適宜確認しながらご覧ください。
①(10)の欄に支払基礎日数を記入
画像の赤枠①の部分(届出用紙の⑩の欄)に、4月、5月、6月各月の支払基礎日数を記入します。支払基礎日数とは、報酬支払いの対象となった日数のことです。月給制の場合は暦日数、日給・時給制の場合は出勤日数+有給休暇取得日数が基本となります。
原則、暦日数(その月の総日数)を記入します。ただし、欠勤日数に応じて給与が差し引かれる(欠勤控除)場合は、就業規則等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数を記入します。
実際に出勤した日数に有給休暇の日数を加えて記入します。
支払基礎日数は、給与の支給日ではなく、給与の計算の対象となった日数を記入します。
例えば、月末締め翌月25日払いの会社で、4月分の給与を5月25日に支給する場合でも、4月の欄には4月1日から4月30日までの間の支払基礎日数を記入します。
②(11)~(13)の欄に通貨と現物支給額とその合計を記入
画像②の枠部分(届出用紙の⑪~⑬の欄)「通貨によるものの額」「現物によるものの額」「合計」を記入します。
ここでは、4月から6月の各月に支給した報酬額を、通貨によるもの、現物によるものに分けて記入し、それぞれの合計額を算出します。
◯(11)通貨によるものの額
従業員に支給した基本給のほか、役職手当、通勤手当、残業手当などを含めた、通貨で支払った報酬の総額を記入します。
◯(12)現物によるものの額
食事の支給や社宅の貸与など、通貨以外で支給した報酬がある場合に、厚生労働大臣が定める価額に基づき金額に換算して記入します。現物支給がない場合は、「0」と記入します。
◯(13)合計
「(11)通貨によるものの額」と「(12)現物によるものの額」の合計額を記入します。
通貨による報酬額には、基本給だけでなく、通勤手当や残業手当などの各種手当ても含める必要があります。また、現物支給がある場合は、必ず金額に換算して記入してください。健康保険組合に加入している場合、現物給与の価額の決定方法が異なることがあるため、健康保険組合に確認するとよいでしょう。
③(14)の欄に総計額を記入
画像③の部分(届出用紙の⑭の欄)には、4月、5月、6月の各月の報酬月額(「(13)合計」の欄の金額)のうち、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬月額を合計した金額を記入します。
支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月の報酬を除外して合計額を計算します。
④(15)の欄に平均額を記入
画像④の部分(届出用紙の⑮の欄)には、「(14)総計」の欄に記入した金額を、支払基礎日数が17日以上の月数で割った金額(1円未満切り捨て)を記入します。
4月、5月、6月の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上の場合は、3で割った金額(平均額)を記入します。
⑤(18)の欄に備考がある場合は記入
画像の⑤の部分(届出用紙の⑱の欄)には、従業員に関する特記事項がある場合に記入します。
具体的には、以下のような場合に、該当する番号等を記入します。
◯「1. 昇(給)月」: 4月、5月、6月に昇給や給与体系の変更があった場合に、該当する月に丸を付けます。遡及支払があった場合は、遡及支払月を記入します。
◯「2. 遡及支払額」: 給与等の遡及払いが行われた場合に、遡及支払額を記入します。
◯「3. 月額変更予定」: 7月、8月、または9月に月額変更届の提出予定がある場合に、該当する月に丸を付けます。
◯「4. 途中入社」: 4月、5月、6月の途中で入社した従業員がいる場合に、入社日を記入します。
◯「5. 病休・育休・休職等」: 4月、5月、6月に病気休業、育児休業、休職等があった場合に、該当する月に丸を付けます。
◯「6. 短時間労働者(特定適用事業所等)」: 短時間労働者に該当する場合に丸を付けます。
◯「7. パート」: パートタイマーに該当する場合に丸を付けます。
◯「8. 年間平均」: 年間平均を用いて標準報酬月額を算出する場合に丸を付けます。
◯「9. その他」: 上記以外の事項がある場合に記入します。例えば、休職中の従業員がいる場合、休職開始日と休職期間を記入します。
⑥(5)の欄に従前の標準報酬額を記入
画像の(5)の欄に、現在の標準報酬月額を記入します。健康保険と厚生年金保険の現在の標準報酬月額を記入します。
⑦(7)の欄に⑥の定時決定の月を記入
画像の(7)の欄に、⑥の標準報酬額が適用された年月を記入します。定時決定(算定基礎届)で決定した標準報酬月額の場合は、決定された年の9月と記入します。
ここでは、算定基礎届の具体的な記入例を、事例とともに紹介します。様々なケースを想定していますので、自社の状況に近いものを参考にしてください。
一般的な記入例
まずは、一般的な記入例として、正社員である「算定 太郎」さんのケースを見ていきましょう。
【例】「算定 太郎」さんの情報(正社員)
- 年齢・性別: 32歳 男性
- 勤務地: 東京都の事業所勤務
- 雇用形態: 正社員
- 基本給: 35万円
- 通勤手当: 1万5,000円(全月同額)
- 住宅手当: 3万円(全月同額)
- 家族手当: 1万円(全月同額)
- 残業手当: 4月、5月、6月にそれぞれ異なる時間外労働(残業)あり
- 賞与: 年2回支給
【4月から6月までの勤務実績と報酬】
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 支払基礎日数 | 30日 | 31日 | 30日 |
| 基本給 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 通勤手当 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 住宅手当 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 家族手当 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 残業代 | 30,000円 | 33,000円 | 40,000円 |
| 合計 | 435,000円 | 438,000円 | 445,000円 |
※ 報酬月額の算出にあたっては、1円未満は切り捨てとします。
■算数 太郎さんの算定基礎届の記入例
添付画像の「算定 太郎」さんの記入例を見ながら、各項目の記入方法を確認していきましょう。
【報酬月額算出の手順】
「算定 太郎」さんの4月、5月、6月の3ヶ月すべてが算定の対象となるため、4月、5月、6月の合計額が総計欄(⑭欄)に記載され、それを3で割った金額が平均額(⑮欄)に記載されています。
※支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算します。
- 報酬合計額「⑭欄(総計)」:1,318,000円
- 報酬月額「⑮欄(平均額)」: 439,333円 (1円未満の端数は切り捨て)
支払基礎日数に17日未満の月がある場合の記入例
次に、支払基礎日数に17日未満の月がある場合として、「算定 次郎」さんのケースを見ていきましょう。
【例】「算定 次郎」さんの情報
- 年齢・性別: 30歳 女性
- 勤務地: 東京都の事業所勤務
- 雇用形態: 正社員(欠勤控除あり)
- 基本給: 25万円
- 通勤手当: 1万円(全月同額)
- 住宅手当: 1万円(全月同額)
- 昼食: 1回(1日500円相当/現物)
【4月から6月までの勤務実績と報酬】
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 支払基礎日数 | 20日 | 15日 | 20日 |
| 基本給 | 250,000円 | 207,500円 | 250,000円 |
| 通勤手当 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 住宅手当 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 昼食(現物) | 10,000円 | 7,500円 | 10,000円 |
| 合計 | 280,000円 | 215,000円 | 280,000円 |
■算定 二郎さんの算定基礎届の記入例
添付画像の「算定 二郎」さんの記入例を見ながら、各項目の記入方法を確認していきましょう。
【報酬月額算出の手順】
「算定 二郎」さんの場合、5月の支払基礎日数が15日と、17日未満のため、5月を除外して計算します。
■支払基礎日数
まず、4月と6月の各月の報酬月額(基本給や各種手当の合計)と、現物支給の額を算出します。「⑩通貨によるものの額」、「⑪現物によるものの額」、「⑫合計」の順に計算してください。
つぎに、4月と6月の報酬月額の合計を計算し、その金額を総計欄(⑭欄)に記入します。そして、それを2で割った金額が平均額(⑮欄)となります。
今回は、現物支給(昼食)があるため、「⑪現物によるものの額」に金額を記入します。現物支給の価額は、厚生労働大臣が都道府県ごとに定めた価額を記入します。
- 報酬合計額「⑭欄(総計)」:560,000円
- 報酬月額「⑮欄(平均額)」: 280,000円 (1円未満の端数は切り捨て)
短時間就労者(パートタイマー)の記入例
ここでは、短時間就労者(パートタイマー)である「算定 明美」さんのケースを見ていきましょう。
短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。
具体的には、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者(正社員など)と比べて、4分の3未満である被保険者のことです。
【例】「算定 明美」さんの情報
- 年齢・性別: 30歳 女性
- 勤務地: 東京都の事業所勤務
- 雇用形態: パート
- 基本給: 日給制
【4月から6月までの勤務実績と報酬】
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 支払基礎日数 | 15日 | 16日 | 17日 |
| 基本給 | 105,000円 | 112,000円 | 119,000円 |
| 合計 | 105,000円 | 112,000円 | 119,000円 |
■算定 明美さんの算定基礎届の記入例
添付画像の「算定 明美」さんの記入例を見ながら、各項目の記入方法を確認していきましょう。
【報酬月額算出の手順】
「算定 明美」さんの場合、6月の支払基礎日数が17日以上のため、6月のみを算定の対象とします。
■短時間就労者の支払基礎日数
まず、6月の報酬月額(基本給)を算出します。「⑩通貨によるものの額」、「⑪現物によるものの額」、「⑫合計」の順に計算してください。
つぎに、6月の報酬月額をそのまま総計欄(⑭欄)に記入します。そして、平均額(⑮欄)は、6月の報酬月額を1で割った金額となるため、⑭欄と同じ金額となります。
今回は、6月が17日以上のため、6月の報酬月額で算出します。
また、短時間就労者(パートタイマー)の場合は、備考欄(⑱欄)に「7.パート」と記入し、〇で囲みます。
- 報酬合計額「⑭欄(総計)」:119,000円
- 報酬月額「⑮欄(平均額)」: 119,000円 (1円未満の端数は切り捨て)
短時間労働者の記入例
ここでは、短時間労働者である「算定 三子」さんのケースを見ていきましょう。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働時間に比して短い者、または、1ヶ月の所定労働日数が同一の事業所に雇用される通常の労働者の所定労働日数に比して短い者、もしくはその両方に該当し、かつ、次の要件をすべて満たす方を指します。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれること
- 報酬の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または国もしくは地方公共団体に属する事業所に勤務していること
【例】「算定 三子」さんの情報
- 年齢・性別: 32歳 女性
- 勤務地: 東京都の事業所勤務
- 雇用形態: 短時間正社員
- 基本給: 120,000円(月額)
【4月から6月までの勤務実績と報酬】
| 4月 | 5月 | 6月 | |
| 支払基礎日数 | 13日 | 13日 | 13日 |
| 基本給 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
■算定 三子さんの算定基礎届の記入例
添付画像の「算定 三子」さんの記入例を見ながら、各項目の記入方法を確認していきましょう。
【報酬月額算出の手順】
「算定 三子」さんの場合、4月、5月、6月のすべての月の支払基礎日数が11日以上のため、3ヶ月分すべてを算定の対象とします。
■短時間労働者の支払基礎日数
まず、各月の報酬月額(基本給)を算出します。「⑩通貨によるものの額」、「⑪現物によるものの額」、「⑫合計」の順に計算してください。
つぎに、4月、5月と6月の報酬月額の合計を計算し、その金額を総計欄(⑭欄)に記入します。そして、それを3で割った金額が平均額(⑮欄)となります。
今回は、3ヶ月すべてが対象となるため、3ヶ月分の報酬月額の平均で算出します。
また、短時間労働者の場合は、備考欄(⑱欄)に「6.短時間労働者」と記入し、〇で囲みます。
- 報酬合計額「⑭欄(総計)」:360,000円
- 報酬月額「⑮欄(平均額)」: 120,000円 (1円未満の端数は切り捨て)
算定基礎届は、従業員の入社や退職、昇給や休職など、個別の事情がある場合は、通常とは異なる対応が必要です。
ここでは、算定基礎届の作成時に注意すべきケース別の書き方を解説していきます。
途中入社の場合
4月、5月、6月の途中で入社した従業員がいる場合、入社月以降の報酬と支払基礎日数をもとに標準報酬月額を算出します。ただし、給与計算期間の途中で入社し、最初の給与が1ヶ月分支給されていない月(途中入社月)がある場合は、その月を除外して計算することを覚えておきましょう。
例えば、5月15日に入社し、5月分の給与が1ヶ月分支給されていない場合は、6月分の給与のみで報酬月額を計算します。一方、5月10日入社で、5月分の給与が1ヶ月分支給されている場合は、5月と6月の2ヶ月分の報酬で報酬月額を計算し、標準報酬月額を算出するのです。
また、給与計算期間の途中で入社し、最初の給与が1ヶ月分支給されていない月(途中入社月)がある場合は、算定基礎届の備考欄の「4.途中入社」に〇を付け、対象従業員の資格取得年月日と給与の締め支払日を記載します。この記載により、日本年金機構または健康保険組合側で、途中入社月の扱いを適切に判断できるようになります。
【短時間労働者の場合(注意)】
短時間労働者の場合、特定適用事業所等に該当するかしないかで、支払基礎日数の要件(11日以上、または17日以上)が異なります。特定適用事業所等で働く短時間労働者の場合、5月15日入社で、5月の給与が日割り計算となり支払基礎日数が11日以上であっても、1ヶ月分の給与が支払われていなければ、5月は報酬月額を計算する際の対象外となりますので注意が必要です。
ただし、6月1日以降に入社した従業員は、そもそも算定基礎届の対象外となります。そのため、7月1日時点で被保険者であっても、算定基礎届に含める必要はありません。6月1日以降に入社した従業員については、入社時に提出する「資格取得届」で決定された標準報酬月額が適用されます。
退職者・退職予定者の場合
6月30日以前に退職した従業員は、算定基礎届の提出は不要です。一方、7月1日以降に退職する従業員は、提出が必要になります。
また、7月、8月、9月に退職予定で、退職後に月額変更届の提出が必要ない従業員については、算定基礎届の備考欄に退職予定日を記入することで、算定基礎届の提出を省略可能です。
具体的には、備考欄に「7月31日退職予定」のように記載します。なお、退職者であっても、4月から6月までに支払われた報酬は、算定基礎届の計算に含める必要がありますので、注意してください。
70歳以上の場合
70歳以上の従業員については、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、社会保険の加入状況によって扱いが異なります。健康保険のみに加入している場合は、一般の従業員と同様に、4月から6月の報酬を基に算定基礎届を作成し、提出が必要です。健康保険組合に加入している場合も同様です。
一方、厚生年金保険にのみ加入している、または社会保険のどちらにも加入していない70歳以上の従業員は、算定基礎届の提出対象外です。ただし、70歳以上で、引き続き雇用される従業員については「70歳以上被用者」として、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更相当届」の提出が必要です。この書類は、70歳到達時点および、毎年7月1日時点のデータを基に作成します。
70歳以上の従業員がいる場合には、健康保険と厚生年金保険のどちらの被保険者であるのかを確認し、適切に社会保険の手続きを進めてください。
休職/産休・育休中の場合
休職中や産前産後休業(産休)、育児休業(育休)中の従業員がいる場合の扱いは、休業期間中に給与が支払われているかどうかで異なります。
給与が支払われている場合
通常通り、4月から6月の報酬額を基に算定基礎届を提出します。
給与が支払われていない(無給の)場合
原則として、従前の標準報酬月額で決定します。ただし、休職中で、かつ報酬が全く支払われていない月は、算定の対象外です。例えば、5月1日から休職に入り、5月と6月が無給の場合は、4月の1か月分で算定します。4月から6月の全てで無給の場合は、従来の標準報酬月額で決定します。
産前産後休業や育児休業を取得している従業員については、休業中も社会保険料の納付が免除されますが、算定基礎届の提出は必要です。
この場合、休業前の報酬と支払基礎日数をもとに標準報酬月額を算出します。無給の期間は、支払基礎日数が17日未満の月と同様に扱います。
例えば、5月1日から休職に入り、5月、6月が無給の場合は4月の1か月分で算定基礎届を提出することになります。この場合、備考欄には、「5. 病休・育休・休職等」に〇をつけ、「9. その他」の欄に休業期間を「令和6年5月1日~令和6年10月31日休職」のように記入します。
なお、傷病手当金や出産手当金、育児休業給付金は、報酬に含まれないため注意が必要です。
昇給があった場合
4月、5月、6月に昇給があり、昇給後の3ヶ月の報酬を基に計算した標準報酬月額と、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる場合は、随時改定の対象となります。この場合、月額変更届の提出が必要になるため、算定基礎届の備考欄に「3.月額変更予定」と記載します。
一方、昇給があった場合でも、必ずしも随時改定の対象となるとは限りません。
例えば、4月、5月、6月に支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月を除いて計算した結果、2等級以上の差が生じない場合は、随時改定の対象外です。
また、固定的賃金の変動がない場合も、随時改定の対象にはなりません。昇給があったからといって、必ず月額変更届の提出が必要になるわけではないので注意しましょう。
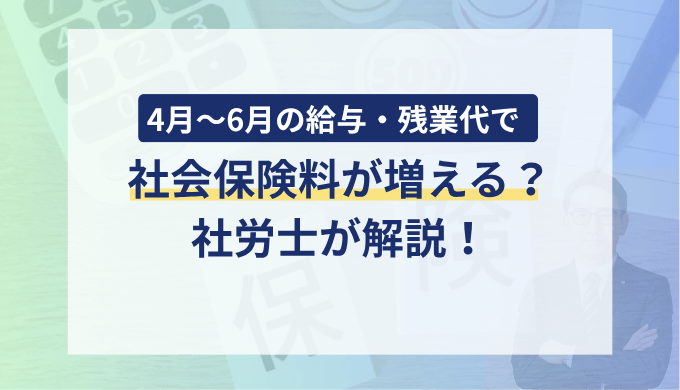 算定基礎届と月額変更届の違いとは?提出タイミング・優先順位をわかりやすく解説
算定基礎届と月額変更届の違いとは?提出タイミング・優先順位をわかりやすく解説
欠勤控除があった場合
従業員が欠勤し、それによって給与が減額された場合(欠勤控除)、欠勤控除後の実際に支払われた報酬額を算定基礎届の計算に含めます。ただし、欠勤控除があった月は、支払基礎日数によって算定基礎額に含めるか含めないかが決まるため、注意が必要です。
月給制の場合、支払基礎日数は、所定労働日数から欠勤日数を差し引いて算出します。
■2つのポイント
◯支払基礎日数17日以上の月
・欠勤控除があっても、その月を含めて計算します。
◯支払基礎日数17日未満の月
・欠勤控除により17日未満となった場合、その月を除外して計算します。
例:所定労働日数20日、欠勤2日の場合、支払基礎日数は18日となり、報酬月額の計算に含めます。
このように、月給制で欠勤控除がある場合、原則として、支払基礎日数が17日以上であればその月を含めて計算し、17日未満であれば除外して計算します。
なお、短時間労働者の場合は扱いが異なります。4月から6月のすべてで支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数が11日以上の月を対象とします。
つまり、算定基礎届を作成する際は、従業員の勤務形態(通常の労働者か短時間労働者か)と、各月の支払基礎日数を確認し、欠勤控除があった月を計算に含めるかどうかを正しく判断することが重要です。
厚生労働省が作成している下記動画「令和7年度算定基礎届事務説明」も参考になります。
算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来受け取る年金額に影響を与える重要な書類です。そのため、記入ミスや漏れがないように細心の注意を払って作成する必要があります。
しかし、どんなに注意していても、間違いに後から気づくこともあるでしょう。
ここでは、提出前と提出後に分けて、算定基礎届の訂正方法について解説します。
提出前の対応
提出前に記入ミスや漏れに気づいた場合は、原則として、間違えた箇所を二重線で抹消し、正しい内容を余白に記入します。
この時、訂正印は使用しません。修正液や修正テープの使用も認められていないため、注意してください。
訂正箇所が多い場合は、新しい用紙に書き直したほうがよいでしょう。
算定基礎届は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。万が一、書き損じた場合に備えて、提出期限や窓口の混雑状況を確認し、提出の準備をしましょう。
提出後の対応
算定基礎届を提出した後に間違いに気づいた場合は、速やかに管轄の年金事務所に連絡し、記入内容に誤りがあること、訂正のため再提出したい旨を伝えてください。状況に応じた適切な訂正方法を案内してもらえます。
原則として「被保険者報酬月額訂正届」を提出し、必要な場合は「保険者算定申立書」を提出します。
そして、提出するさいは新しい算定基礎届の用紙の上部に「訂正」と赤字で目立つように記入します。
特に金額を間違えた場合は、訂正箇所を2段書きにします。上段に誤った金額を赤字で、下段に正しい金額を黒字で記入してください。
「算定基礎届の訂正届」の提出方法は、元の算定基礎届の提出方法(電子申請、郵送、窓口持参)によって異なります。
電子申請で提出した場合は、電子申請で訂正届を提出します。郵送または窓口持参で提出した場合は、郵送または窓口持参で訂正届を提出してください。
提出先は、元の算定基礎届を提出した、事務センターまたは管轄の年金事務所です。健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合にも提出が必要となる場合があります。
算定基礎届の提出方法は、電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参の4種類があります。それぞれの方法について詳しく説明します。
1. 電子申請
電子申請は、インターネットを利用して、自宅やオフィスから24時間いつでも手続きができる便利な方法です。
電子申請を利用するためには、e-Gov電子申請サービスのWebサイトから、各提出する申請先への届出や申請を行う必要があります。
利用するメリットは以下の通りです。
- 時間と場所に縛られない: 年金事務所の開庁時間を気にせず、24時間いつでも手続きが可能。
- 待ち時間がない: 窓口での待ち時間や、郵送にかかる時間を削減できる。
- コスト削減: 郵送にかかる費用を削減できる。
- ペーパーレス: 紙の書類を削減し、環境保護に貢献できる。
申請には電子証明書の取得が必要ですが、慣れると他の提出方法より効率よく提出できます。電子申請は、今後ますます主流になると考えられます。
2. 電子媒体(CDまたはDVD)
電子媒体(CDまたはDVD)による提出は、届出データを記録した電子媒体を、管轄の年金事務所に郵送または持参する方法です。
利用するメリットは以下の通りです。
- 大量のデータを効率的に提出できる: 従業員数が多い場合に特に有効。
- データの正確性が高い: 電子データで提出するため、手書きによる記入ミスを減らすことができる。
電子媒体による提出を希望する場合は、事前に管轄の年金事務所へお問い合わせください。利用にあたっては、日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」を使用し、提出に必要な届出データを作成する必要があります。
3. 郵送
郵送による提出は、最も一般的な方法です。 管轄の年金事務所から送付される算定基礎届の用紙に必要事項を記入し、返信用封筒(通常は送付物に同封されている)に入れて、期限内に提出します。
利用するメリットは以下の通りです。
- 特別な準備が不要: 電子証明書の取得などの準備が不要。
- 手軽に提出できる: 用紙に記入して返送するだけなので、手軽に提出できる。
記入する際には、記入漏れや記入ミスがないよう、十分に注意してください。記入した内容は、必ずコピーを取って保管しておきましょう。 また、郵送事故等による提出遅延のリスクを避けるため、提出期限に余裕をもって準備することが重要です。
4. 窓口持参
窓口持参による提出は、管轄の年金事務所の窓口に直接出向いて提出する方法です。
利用するメリットは以下の通りです。
- 直接確認してもらえる: 職員の方にその場で内容を確認してもらえるため、不備があった場合もすぐに対応できる。
- 安心感がある: 直接手渡しで提出するため、安心感がある。
窓口の受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで(国民年金の届出については、平日17時以降及び土曜日に窓口相談を行っているところもあります)です。提出期限直前は窓口が混雑する可能性があるため、時間に余裕を持って提出しましょう。
どの提出方法を選択するかは、自社の状況や環境に合わせて判断してください。
不明な点がある場合は、管轄の年金事務所や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
社労士クラウドは、全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談、各種給付金・助成金の申請代行を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績!
⇒社労士クラウドのスポット申請代行の料金を確認する
算定基礎届の書き方、作成と提出時によくある質問や疑問について紹介しています。
賞与は算定基礎届に含めますか?
賞与は算定基礎届には原則含めません。算定基礎届は、4月・5月・6月の「定期的な報酬(基本給・手当、通勤手当、残業代など)」のみが対象となります。
賞与については、「賞与支払届」を別途提出する必要があります。
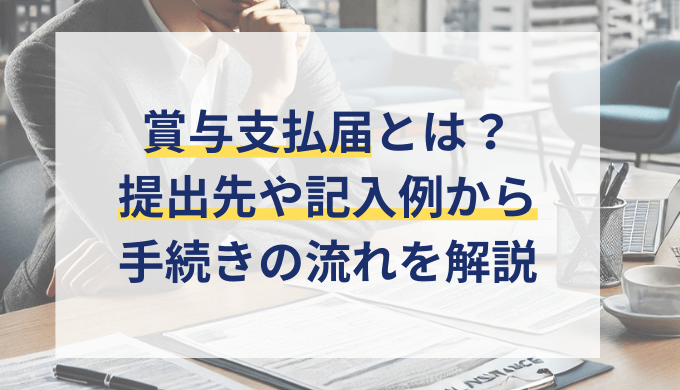 賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
ただし例外として、年4回以上支給される賞与(たとえば毎月のインセンティブなど)は、厚生年金保険・健康保険の取り扱い上、実質的に報酬とみなされるため、算定基礎届に含める必要があります。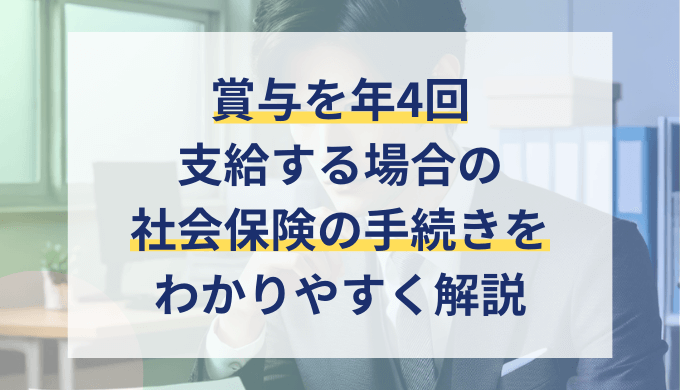 賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
報酬に交通費や残業代は含まれますか?
通勤手当や残業手当、役職手当なども報酬に含まれます。ただし、出張旅費や慶弔見舞金などは含まれません。
6月に途中入社した従業員は対象ですか?費や残業代は含まれますか?
基本的には4月〜6月に在籍し、引き続き使用される見込みのある従業員が対象です。途中入社の扱いはケースによって異なるため、管轄の年金事務所に確認しましょう。
定時決定以外で社会保険料が変更されるタイミングはありますか?
定時決定(算定基礎届による改定)以外にも、賃金が大きく変動した場合や育児休業終了後などに保険料が変更されることがあります。代表的なのは「随時改定(月額変更届)」で、基本給の変更や手当の増減などで3か月間の平均報酬が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上ずれた場合に適用されます。また、育児休業や産前産後休業終了後の改定も対象となります。必要に応じて提出書類や条件を確認しましょう。
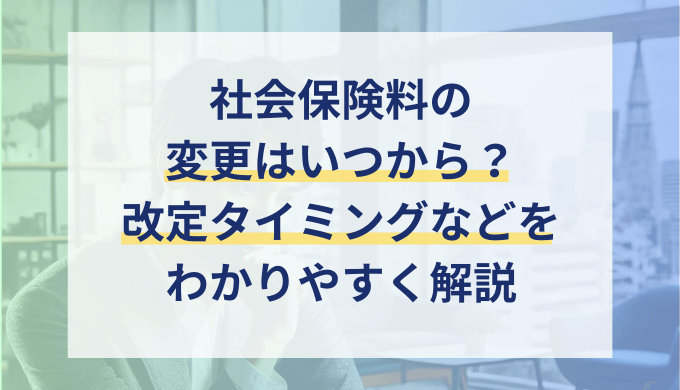 社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
本記事では、算定基礎届について、具体的な書き方や作成手順、注意すべきケースについて事例をまじえた記入例付きでわかりやすく解説していきました。
算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を決定し、社会保険料や将来受け取る年金額、各種給付額を算出するための重要な書類です。誤りがあると、従業員だけでなく会社にも不利益が生じる可能性があるため、正確な内容で期限内に届け出ることが求められます。
算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を決定し、社会保険料や将来受け取る年金額、各種給付額を算出するための重要な書類です。誤りがあると、従業員だけでなく会社にも不利益が生じる可能性があるため、正確な内容で期限内に届け出ることが求められます。
算定基礎届は、社会保険手続きの中でも特に重要であり、提出を怠ったり虚偽の届出を行ったりした場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意が必要です。
本記事を参考に、算定基礎届の書き方を正しく理解し、従業員と会社の双方に不利益が生じないよう、正確に記入し、期限内に提出しましょう。
もし、記入内容や提出方法に不安がある場合、または誤りに気づいた場合は、放置せずに、速やかに社会保険労務士や管轄の年金事務所、健康保険組合に相談し、適切な対応を取りましょう。
社労士クラウドのスポット申請代行サービス
算定基礎届の作成や提出は、専門的な知識を要するため、慣れていないと多くの時間と労力を費やしてしまいます。また、計算ミスや提出漏れなどのリスクも伴います。「社労士へ依頼するのは、費用が心配」「自社で対応できるか不安」といった場合は、社労士クラウドのスポット申請代行サービスの利用を検討してみるのも一つの方法です。
社労士クラウドのスポット申請代行サービスは、必要な時だけ専門家に業務を依頼できるサービスです。例えば、算定基礎届の作成・提出のみを依頼することも可能です。スポットで依頼することで、自社で対応するよりも、確実かつ効率的に手続きを進められる場合があります。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|