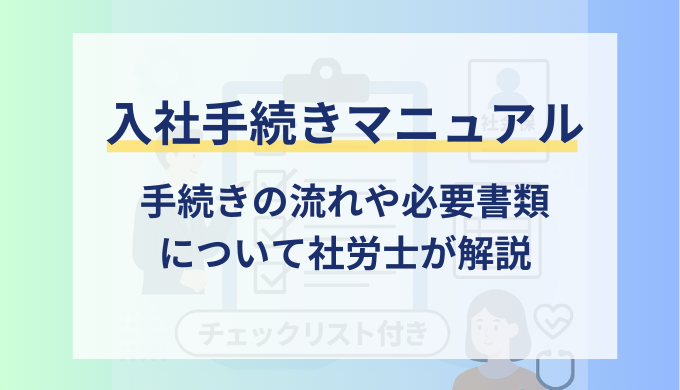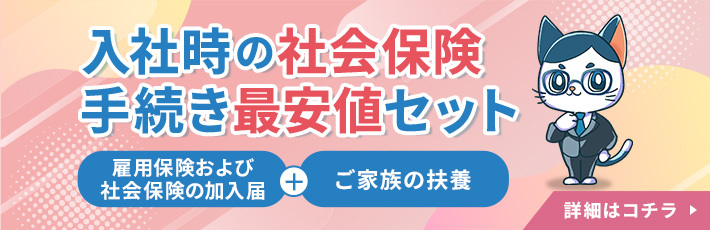従業員を迎えるときに必要となる「入社手続き」は、単なる書類のやり取りではなく、法律で定められた重要な義務です。社会保険や雇用保険の加入、税務処理、雇入れ時の健康診断など、多岐にわたる作業を限られた期限内で正しく進める必要があります。
特に小規模企業では、担当者が他の業務と兼任していることも多く、抜けや漏れが発生しやすいのが現実です。もし手続きに不備があれば、追徴金や罰則のリスクに直結するだけでなく、従業員の不安や不信感を招き、早期離職につながることもあります。
本記事では、会社側が入社前から入社後までに行うべき手続きを、時系列に沿って整理し、必要書類・提出期限・注意点をチェックリスト付きでわかりやすく解説します。
この記事をマニュアルとして活用し、安心して従業員を迎えられる体制を整えましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
YouTubeでも従業員の入社時に会社側が行う社会保険と労働保険の手続きについて詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
従業員を新たに迎え入れる際の入社手続きは、大きく「入社前(内定後〜入社前日)」「入社当日」「入社後」という3つの時期に分けて進めます。
最初に全体の流れを掴んでおけば、どの作業をいつまでに終えるべきかが明確になり、抜け漏れを確実に防げます。
特に、入社後5日以内という大変短い期限が定められている社会保険の手続きなど、優先順位を間違えると大きな問題になりかねません。
以下のチェックリストは、この入社手続き全体の地図となるものです。自社の運用に合わせてご活用ください。
入社前(内定後〜入社前日)
| 主なタスク | 期限 | |
| □ | 労働条件通知書・雇用契約書の準備と送付 | 入社日まで |
| □ | 提出が必要な書類の案内(紛失時の対応も伝える) | 入社日まで |
| □ | 内定者から入社承諾書を回収し、保管する入社 | 入社日まで |
| □ | 雇入れ時健康診断の案内と手配 | 入社日まで |
| □ | PCや備品、社内アカウントの準備 | 入社日まで |
入社当日
| 主なタスク | 期限 | |
| □ | 社員から案内した書類をすべて回収し、不備がないか確認 | 当日中 |
| □ | 雇用契約の締結(双方で保管) | 当日中 |
| □ | 備品を貸与し、オリエンテーションを実施 | 当日中 |
入社後
| 主なタスク | 期限 | |
| □ | 健康保険・厚生年金保険の手続き | 入社日から5日以内 |
| □ | 雇用保険の加入手続き | 入社月の翌月10日まで |
| □ | 住民税の特別徴収手続き(中途採用者の場合) | 入社後速やかに |
| □ | 法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の作成 | 入社後速やかに |
上記チェックリストのタスクはすべて重要ですが、特に太字で示した項目を怠った場合、法律に基づく罰則や追徴金といった直接的なペナルティに繋がる可能性があります。
- 健康保険・厚生年金保険の手続き: 遅延した場合、最大2年分の保険料を追徴される可能性があります。
- 雇用保険の加入手続き: 届出を怠ると、懲役または罰金の対象となる可能性があります。
- 法定三帳簿の作成・保管: 義務を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
このチェックリストにある各項目について、次項から「入社前」「入社当日」「入社後」のフェーズに沿って、一つひとつ具体的に解説していきます。
内定が決まってから新入社員が入社するまでの期間は、当日の混乱をなくし、入社後の手続きを滞りなく進めるための大切な準備期間です。この段階で会社側が行うべきことは、大きく分けて「労働条件の書面合意」「提出書類の事前準備」「健康診断の実施」「受け入れ環境の整備」の4点です。
雇用条件は書面で明確に合意し、新入社員が準備する書類は、提出期限や方法を分かりやすく伝えます。同時に、パソコンの準備や業務用アカウントの発行といった、物理的・IT面の環境整備も進めておきましょう。
準備を抜け漏れなく進めるために、担当者と期限を明確にした段取り表を用意するのがおすすめです。次の項目から、それぞれの具体的な進め方を解説します。
内定通知から契約までに交わす重要書類の作成
入社前の手続きで最も重要なのが、法的な根拠となる書面の整備です。口頭での約束は、後日の「言った、言わない」という食い違いの原因となり、入社早々のトラブルに繋がりかねません。必ず書面で双方の意思と契約内容を明確にしましょう。
手続きは一般的に、①会社からの採用通知、②内定者からの入社承諾、③法的な労働条件の明示、という流れで進みます。
まず、会社が「採用通知書」を送付し、採用の意思を正式に伝えます。それを受け取った内定者は、「入社誓約書」に署名・捺印して返送することで、入社を承諾した意思表示となります。これらは、双方の意思を正式な形で確認するために、実務上、不可欠な書類です。
特に労働条件通知書は、労働基準法で会社から従業員への明示が義務付けられている、法的に最も重要な書類です。
労働条件通知書は、労働基準法で会社から従業員への明示が義務付けられています。特に2024年4月の法改正により、雇入れ直後の就業場所に加え、将来の「就業場所・業務の変更の範囲」も記載することが義務化されました。
例えば、「(変更の範囲)国内の全事業所における経理、人事、総務業務」のように、具体的かつ現実的な範囲で記載する必要があります。「会社の定める場所及び業務」といった曖昧な表現は認められないため、注意が必要です。
提出書類や入社当日の流れに関する案内
採用した社員が期待と安心をもって入社日を迎えられるよう、事前に丁寧な案内状を送付することは、会社ができる最初の「おもてなし」です。しっかりとした案内があれば、従業員は必要な準備をスムーズに進められ、当日の手続きも円滑になります。
案内状には、少なくとも以下の項目を分かりやすく記載しましょう。
◯提出が必要な書類の一覧
全員に提出してもらう書類と、中途採用者や扶養家族がいる方など、該当者のみが必要な書類を明確に区別してリスト化します。
◯書類の準備に関する補足
年金手帳などを紛失した場合の再発行手続きについても、一言添えておくと親切です。
◯入社日当日のスケジュール
集合時間、場所、当日の簡単な流れ(書類提出、オリエンテーションなど)を伝えます。
◯当日の持ち物
筆記用具、印鑑、身分証明書など、必要なものを具体的にリストアップします。
◯問い合わせ先
不明点があった場合に連絡できる担当部署や担当者名、連絡先を明記します。
雇入れ時健康診断の案内と手配
従業員を雇い入れる際の健康診断は、労働安全衛生法で定められた会社の義務です。これは、会社の「安全配慮義務」の一環であり、新入社員の健康状態を把握し、無理のない業務配置を行うことで、従業員と会社の双方を守るために必要な手続きです。
実施時期は入社の直前または直後が基本で、費用は会社が全額負担します。ただし、新入社員が入社前3ヶ月以内に受けた健康診断の結果があり、それが法律で定められた項目をすべて満たしていれば、その結果の提出をもって代えることも可能です。
提出された診断結果は、会社が5年間保管することが義務付けられています。
新入社員の受け入れ準備チェックリスト(PC・備品・アカウント)
採用した社員が初日から円滑に業務を開始できるよう、物理的な受け入れ態勢を整えておくことは、会社ができる大切なおもてなしの一つです。入社初日に自分のデスクやパソコンが用意されていないと、新入社員は「歓迎されていないのでは」と大きな不安を感じてしまいます。
こうした事態を避けることは、業務効率を上げるだけでなく、新入社員が「会社の一員として大切にされている」と感じるきっかけとなり、その後の仕事への意欲や定着率にも良い影響を与えます。
以下のチェックリストを活用し、抜け漏れなく準備を進めましょう。
| 準備チェックリスト [ ] デスク・チェアの確保、座席表の更新 [ ] 社員証・入館証・ロッカーの鍵などの準備 [ ] 名刺の発注 [ ] 制服や作業着の貸与(必要な場合) [ ] 業務用PCのセットアップと周辺機器(モニター、マウスなど)の準備 [ ] 業務用メールアドレスの発行 [ ] 勤怠管理や給与明細システムへのアカウント登録 [ ] 社内チャットツールや各種サービスのアカウント発行と権限設定 |
入社当日は、事前に案内した書類を予定どおりに受け取り、その場で内容に誤りがないかを確認する重要な日です。ここでの確認の精度が、この後に行う社会保険や税金に関する手続き全体の正確さを左右します。
特にマイナンバーのような重要な個人情報は、本人確認書類と厳格に照合し、誰が、いつ、どこで保管するかを明確に決めておきましょう。
回収する書類は「全員必須」「該当者のみ」「会社の規定による」の3つに分けて管理すると、抜け漏れが起きにくくなります。
【必須】全員に提出してもらう書類
ここでは、経歴や家族構成に関わらず、給与の支払いを受ける全ての従業員から提出してもらう、手続きの基本となる書類を解説します。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 基礎年金番号通知書(または年金手帳)
- マイナンバー確認書類
- 給与振込先届出書
【書類を確認するときの主なポイント】
書類を受け取る際は、ただ集めるだけでなく、以下の点を確認すると手戻りを防げます。
| 書類名 | 特に注意すべき点 |
| 扶養控除等申告書 | 署名や日付、扶養親族の人数などに記載漏れや間違いがないかを確認する。 |
| 基礎年金番号 | 番号の桁数や数字に間違いがないか、通知書などと照合する。 |
| マイナンバー | 個人番号カード、または通知カード+本人確認書類(運転免許証など)で、法律に基づき厳格に本人確認を行う。 |
| 給与振込先 | 金融機関名・支店名・口座番号の書き間違いを防ぐため、可能であれば通帳のコピーやスマートフォンの画面などで照合する。 |
【該当者のみ】中途採用者・扶養家族がいる社員から回収する書類
従業員の状況によっては、追加で提出が必要になる書類があります。誰にどの書類が必要なのかを事前に把握しておくことが大切です。
該当するケースと必要書類
| 該当者 | 書類名 | 主な目的と注意点 |
| 中途採用者 | 源泉徴収票 | その年に以前の勤務先から給与を受け取っていた場合、年末調整に必須です。 |
| 中途採用者 | 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入期間を引き継ぐために、記載されている番号が必要です。 |
| 扶養家族がいる | 健康保険被扶養者(異動)届 | 税金の扶養控除より収入基準が厳しく、続柄や収入を証明する書類(住民票の写し等)が別途必要になる場合があります。不備は保険証の発行遅延に直結します。 |
【会社の規定による】免許・資格、卒業証明書など
法律上の義務ではありませんが、会社のルールや、特定の仕事に就くための条件として、提出を求める書類もあります。
- 運転免許証の写し
- 専門資格の合格証・登録証
- 卒業(修了)証明書
- 住民票記載事項証明書
上記書類は、業務上の要件を満たしているか、有効期限は切れていないかなどを確認します。運転免許証や専門資格のように更新が必要なものは、「資格管理台帳」のようなものを作成して有効期限を記録し、期限前に本人へ通知する仕組みを作っておくと、更新漏れを防ぐことができます。
【入社後】会社側が行う行政手続きと社内整理
従業員が入社した後は、法律で期限が定められた手続きを、優先順位をつけて着実に実行していく段階です。最優先は社会保険の資格取得(入社日から5日以内)、次に雇用保険(翌月10日まで)、そして税金関係の手続きへと進みます。
入社後の行政手続きを円滑に進めるコツは、社内で「誰が、何を、いつまでに、どこへ」提出したかを記録する管理表を用意することです。
手続き完了後は、受付番号や控えを必ず保管しておきましょう。こうした記録管理を徹底するだけで、後日の問い合わせなどへの対応が格段に楽になります。
社会保険の手続き(期限:入社日から5日以内!)
健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、入社手続きの中で最優先で対応すべき、最も重要な業務です。
会社は、従業員が入社した日(資格取得日)から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所(または健康保険組合)へ提出します。
この手続きで最も注意すべき点は、提出期限である「5日」が、土日や祝日も含むカレンダー上の日数(暦日)であることです。
例えば、金曜日(9月26日)に入社した場合、期限は5日後の水曜日(10月1日)となります。
もし間の月曜日が祝日であれば、実質的な作業日は火曜と水曜の2日しかありません。このルールを知らないと、意図せず期限を過ぎてしまうリスクが非常に高いため、入社日当日に手続きを開始するくらいの心構えが必要です。
この手続きの遅延は、法律で罰則が定められているだけでなく、最大で過去2年分に遡って保険料を追徴される可能性があり、会社にとって重大な財務負担となり得ます。
【手続きの主な注意点】
入社当日に回収した書類と、届出内容(特に氏名、生年月日、基礎年金番号)に食い違いが起きやすいため、担当者がその場で照合することが手戻りを防ぐ重要なポイントです。電子申請を利用する場合は、事前に必要な設定を済ませ、送信した控えと受付結果を必ず保管しておきましょう。
雇用保険の手続き(期限:入社月の翌月10日まで)
会社は、従業員が入社した月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。
雇用保険は、従業員が万が一失業した場合や、育児・介護で休業する際の生活を支える、法律で定められた大切な制度です。
【手続きの主な注意点】
中途採用者の場合、雇用保険の被保険者番号が重複して発行されないよう、前職の情報を正確に確認することが大切です。この手続きで届け出た内容は、将来の育児休業給付などの起点情報にもなるため、雇用形態や所定労働時間などを正確に記入しましょう。
雇用保険の加入手続きについては下記の記事で詳しく解説しています。
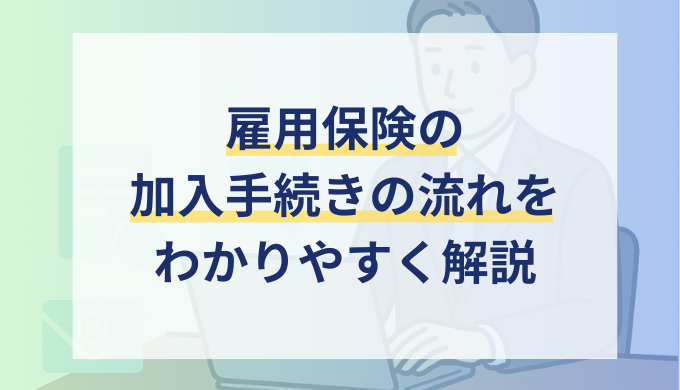 雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
労災保険の手続き(初めて従業員を雇う場合)
労災保険は、法人を設立して初めて、または個人事業主として初めて従業員を雇用する場合にのみ必要となる、会社としての初期設定です。すでに従業員がいる会社が2人目以降を雇い入れる際には、この手続きは不要です。
労災保険は、業務中や通勤中のケガなどに対応する制度で、従業員ごとではなく事業所単位で加入します。
| 必要な手続き | 提出先 | 提出期限 |
| 「保険関係成立届」の提出 | 所轄の労働基準監督署 | 最初の従業員を雇用した日から10日以内 |
初めて従業員を雇う際に必要となる社会保険と労働保険の手続きについては、下記記事でさらに詳しく解説しています。
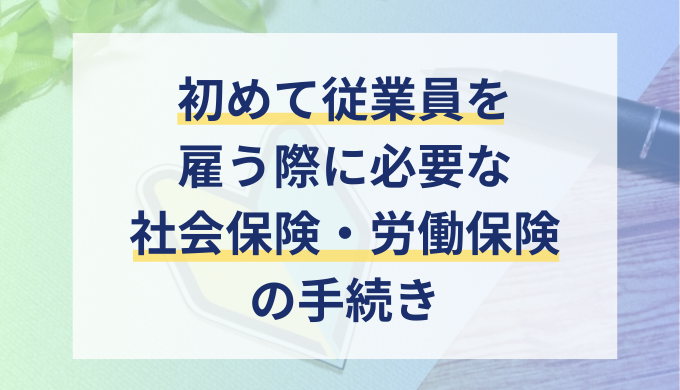 初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
税金の手続き
従業員に給与を支払う上で、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収は、会社の重要な義務です。入社時に回収した「給与所得者の扶養控除等申告書」に基づき、給与計算システムへ正確に情報を反映させましょう。
毎月の給与から、国税庁の税額表に従って所得税を天引きします。扶養控除等申告書の提出がない社員は、より高い税額となる「乙欄」で計算する必要があるため注意が必要です。計算根拠を明確にするため、適用した税額表の区分や扶養人数などを給与データと共に記録しておくのがおすすめです。
原則として、会社が住民税を給与から天引きして各市区町村へ納付します。新卒者は前年の所得がないため、入社2年目の6月から天引きが始まります。中途採用者の場合は、前職での徴収状況を確認し、「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出するなどの手続きで、特別徴収を引き継ぎます。
法律で義務付けられた「法定三帳簿」の作成・保管
労働基準法では、事業者に**「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」**の3つの帳簿(法定三帳簿)を作成し、保管することを義務付けています。これらは適正な労務管理の根幹をなす重要書類であり、作成や保管を怠った場合は罰金(30万円以下)の対象となる可能性があります。
| 帳簿名 | 主な記載事項 |
| 労働者名簿 | 従業員の氏名、生年月日、住所、入社年月日、従事する業務などを記録する名簿。 |
| 賃金台帳 | 給与計算の基礎となる事項や手当ごとの金額、労働時間、控除額などを記録する台帳。 |
| 出勤簿 | 出勤日、労働日数、始業・終業時刻などを記録する帳簿。タイムカードや勤怠管理システムの記録がこれに該当します。 |
法定三帳簿は、原則として5年間(当分の間は3年間)保管する必要があります。
特に注意したいのが、保管期間のカウントが始まる「起算日」が、帳簿ごとに異なる点です。
- 労働者名簿: その従業員が退職または死亡した日からカウント。
- 賃金台帳: 最後の給与を記入した日からカウント。
- 出勤簿: 最後の出勤日からカウント。
また、電子データで保存する場合は、いつでもすぐに検索・印刷できる状態を保ち、誰かが後から内容を書き換えられないような、改ざん防止の措置を講じておく必要があります。
従業員の雇用手続きや必要書類について下記記事でも詳しく解説しています。
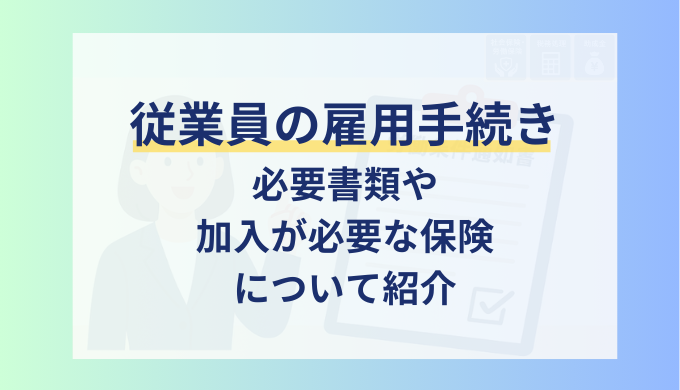 従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
個別の入社手続きとあわせて、会社全体のルールを整えておくことは、健全な組織運営に不可欠です。特に「36協定」や「就業規則」は、新入社員に適正な労働条件を提示し、残業を命じる際の法的根拠となります。
36協定や就業規則の整備が曖昧だと、入社後に命じた残業が違法になったり、給与計算や懲戒処分の根拠が弱くなったりと、深刻な問題に発展しかねません。
ここでは、個別の入社手続きと並行して、会社として必ず整備しておくべきルールについて解説します。
36協定の締結と届出(残業させる場合)
法律で定められた労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて従業員に残業をさせたり、法定休日に働かせたりする可能性がある場合は、従業員が1人でも、「36(サブロク)協定」を届け出る必要があります。
この36協定は労働基準法第36条に基づく労使協定で、この届出がないまま残業を命じることは、たとえ本人が同意していても法律違反となり、行政からの是正指導や罰則の対象になります。
手続きとしては、労働者の代表と残業時間の上限などを定めた協定書を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。多くの場合、有効期間は1年間ですので、毎年更新が必要になる点も覚えておきましょう。
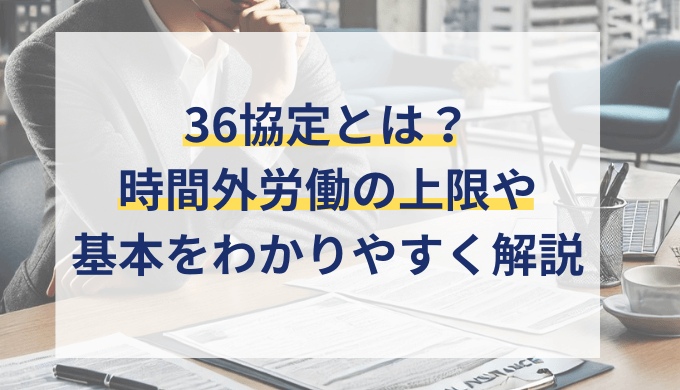 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
就業規則の作成と周知(従業員10人以上の場合)
常時10人以上の労働者(パート・アルバイト等を含む)を使用する事業場は、就業規則を作成し、届け出て、全従業員に周知する義務があります。10人未満でも、労務トラブルを防ぐために作成しておくことを強くおすすめします。
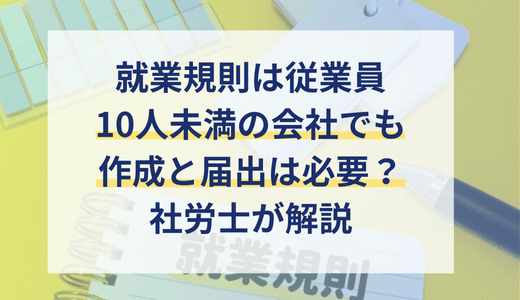 就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説
就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説
就業規則は、労働時間、休日、賃金の決め方、服務規律など、日々の会社運営の土台となるルールブックです。書面でルールが明確になっていることで、公平な判断のよりどころとなります。
①会社のルールをまとめた就業規則の案を作成し、②労働者の代表から意見を聴取し(意見書の添付が必要)、③労働基準監督署へ届け出て、④全員がいつでも見られる形で周知する、という流れです。
固定残業代(みなし残業代)を導入する場合は、その手当に含まれる時間数、金額、そして超過分は別途支払うことを明確に記載します。また、在宅勤務やテレワークを認める場合は、勤怠の記録方法や通信費などの費用負担についても、ルールを定めておきましょう。
社宅、通勤手当、兼業・副業など特殊なケースの注意点
給与や福利厚生に関わる個別のテーマは、就業規則や関連規程で条件をはっきりとさせ、税金や社会保険の扱いも正しく理解しておく必要があります。ここが不明確だと、手取り額の差異や社会保険料の計算間違いなどで、従業員との紛争が起きやすくなります。
◯社宅・家賃補助
会社が貸与する社宅の家賃について、従業員の自己負担額が低すぎると、差額分が給与として扱われ課税対象になる場合があります。税務上のルールを確認し、適切な家賃設定を行いましょう。
◯通勤手当
公共交通機関を利用する場合は月15万円まで非課税ですが、マイカー通勤の場合は距離に応じて非課税の限度額が細かく定められています。給与計算システムの設定を間違えないよう注意が必要です。
◯兼業・副業
従業員が他の会社でも働く場合、労働時間の通算管理や健康への配慮、情報漏えいのリスク管理など、会社側で注意すべき点が多くあります。兼業・副業を認める場合は、申請や許可に関するルールを定めておきましょう。
入社手続きは、どれだけ慎重に準備を進めても、予期せぬ質問や思いがけないトラブルが発生することがあります。特に、担当者が一人で何役もこなすことの多い小規模な会社では、こうした事態にどう対応すればよいか、戸惑うことも少なくありません。
しかし、よくある事例とその対処法を事前に知っておけば、いざという時に慌てず、冷静に、そして的確に対応できます。
ここでは、代表的な質問やトラブルについて、具体的な解決策を解説します。
年金番号や雇用保険番号を紛失したと言われたら?
従業員から「年金手帳が見当たらない」「雇用保険の番号が分からない」と相談された場合、会社側で番号を再発行することはできません。従業員本人に、公的な窓口で手続きを行ってもらうよう、速やかに案内しましょう。
手続きに必要な番号が不明なままだと、社会保険や雇用保険への加入手続きが遅れてしまいます。
以下の案内を参考に、従業員自身で対応してもらうことが重要です。
◯基礎年金番号が分からない場合
最寄りの「年金事務所」の窓口へ、本人が身分証明書を持参して相談するよう伝えます。
◯雇用保険被保険者番号が分からない場合
住所地を管轄する「ハローワーク」の窓口へ、本人が身分証明書を持参して相談するよう伝えます。以前の勤務先の情報が分かると、照会が円滑に進みます。
従業員からの提出を待つ間、提出期限を社内カレンダーに記録し、リマインダーを設定しておくと催促漏れを防げます。
前職の源泉徴収票が提出されない場合は?
中途採用者から、以前の勤務先の「源泉徴収票」が提出されないという相談も、よくある悩みの一つです。
まずは、源泉徴収票の発行は法律で定められた前職の会社の義務であることを伝え、従業員本人から、以前の会社へ発行を強く催促してもらいます。
源泉徴収票がないと会社で正確な年末調整を行うことができず、最終的に従業員本人が自分で確定申告をする手間が発生してしまいます。
それでも発行に応じてもらえない場合は、従業員本人が、自身の住所地を管轄する「税務署」へ相談する方法があります。
税務署には「源泉徴収票不交付の届出書」という書類があり、これを提出することで、税務署から以前の会社へ行政指導が行われます。
入社後すぐにマイナ保険証はすぐに使えますか?
入社直後は、新しい保険情報がシステムに登録されておらず、使えない可能性が高いです。医療機関で確実に受診するため、「健康保険被保険者資格証明書」の利用を案内します。
会社が資格取得の手続きを済ませても、その情報が全国の医療機関のシステムに反映されるまでには数日〜2週間程度かかるためです。
入社後に受診予定がある従業員には、会社が年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」を発行できることを伝えます。この証明書は原則即日発行され、保険証の代わりとして使えます。
もし従業員が証明書なしで受診し、医療費を全額自己負担した場合は、後から払い戻し(療養費請求)が可能です。その際の手順についても、あらかじめ社内で案内方法を決めておくと親切です。
「聞いていた労働条件と違う」と言われたら?
入社後に従業員から「面接で聞いていた話と、実際の労働条件が違う」という申し出があった場合、これは最も慎重な対応が求められるトラブルです。初期のコミュニケーションの食い違いは、早期離職の最大の原因になりかねません。
感情的に反論したり、軽くあしらったりせず、まずは誠実な態度で向き合うことが重要です。以下の手順で、冷静に対応しましょう。
1.傾聴する:
まずは相手の言い分を遮らずに最後まで聞きます。「何が」「どのように」違うと感じているのかを具体的にヒアリングします。
2.事実確認を行う:
入社前に交付した「労働条件通知書」や、署名済みの「雇用契約書」の記載内容を客観的に確認します。
3.面談の場を設ける:
確認した事実に基づき、人事担当者や直属の上司を交えて、改めて話し合いの場を設けます。
4.是正または説明する:
もし会社側に明らかな誤りや説明不足があった場合は、率直に謝罪し、速やかに是正します。もし従業員側の誤解であった場合は、なぜそのような条件になっているのか、背景や理由を丁寧に説明し、納得を求めます。
そもそも、こうしたトラブルを防ぐために、求人票の記載と労働条件通知書の内容に表現の差が生まれないよう、採用段階から言葉を統一しておくことが最も効果的です。
外国人を雇用する場合も、社会保険や雇用保険に加入するのですか?
原則として、国籍を問わず日本人従業員と同じ条件で社会保険・雇用保険への加入義務があります。
ただし、在留資格の種類や、海外の社会保障制度との兼ね合い(社会保障協定)など、いくつかの注意点が存在します。
詳しくは、下記記事「外国人を雇用する際の社会保険や雇用保険に関して」で解説しています。
 【社労士監修】外国人を雇用する際の社会保険や雇用保険に関して
【社労士監修】外国人を雇用する際の社会保険や雇用保険に関して
入社手続きでは、従業員の氏名や住所、給与振込先といった多くの個人情報を扱います。特にマイナンバー(個人番号)は、法律で極めて厳格な管理が義務付けられている「特定個人情報」です。
これらの情報の取り扱いを誤り、万が一漏えいさせてしまうと、会社の社会的信用を大きく損なうだけでなく、法律による罰則の対象となる可能性もあります。
ここでは、会社の信頼を守るために不可欠な、個人情報の取り扱いルールについて解説します。特に注意が必要なマイナンバーの管理と、それ以外の個人情報の管理に分けて見ていきましょう。
マイナンバーの厳格な取り扱いチェックリスト
マイナンバーの取り扱いは「番号法」という法律で、収集から廃棄までの一連の流れ(ライフサイクル)すべてにおいて、事業者に厳格な管理が義務付けられています。以下の4つの段階ごとに、やるべきことを確実に実行しましょう。
従業員からマイナンバーを取得する際は、必ずその利用目的を具体的に伝えなければなりません。利用目的は、社会保険の手続き、税務手続き(源泉徴収など)といった法律で定められた範囲に限られます。
提出されたマイナンバーが本人のものであることを、法律で定められた方法で確認します。具体的には、「番号が正しいかの確認(番号確認)」と「番号の持ち主であるかの確認(身元確認)」の両方が必要です。
・マイナンバーカードがある場合:
カード1枚で「番号確認」と「身元確認」が完了します。・マイナンバーカードがない場合:
「通知カード」や「マイナンバーが記載された住民票」などで番号確認を行い、「運転免許証」や「パスポート」などで身元確認を行います。
マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかるキャビネットや書庫で厳重に保管します。データで管理する場合は、担当者以外がアクセスできないよう、パスワードを設定したり、アクセス権限を限定したりする措置が必要です。
従業員の退職などにより、社会保険や税務の手続きでマイナンバーを利用する必要がなくなった場合、その情報が含まれる書類は速やかに廃棄または削除しなければなりません。シュレッダーにかける、復元できない方法でデータを削除するなど、確実な方法で廃棄しましょう。
マイナンバー以外の個人情報についても、「個人情報保護法」に基づき、適切に取り扱う責任が会社にはあります。従業員のプライバシーを守り、無用なトラブルを避けるために、以下の3つの原則を覚えておきましょう。
◯必要最小限の原則
業務を遂行する上で、本当に必要な個人情報のみを収集します。例えば、業務に直接関係のない家族の職業などを、安易に収集することは避けるべきです。
◯目的外利用の禁止
給与計算のために収集した口座情報を、本人の同意なく他の目的で利用してはいけません。収集時に伝えた利用目的の範囲を超えて、個人情報を扱うことは禁じられています。
◯安全な保管場所の確保
マイナンバーと同様に、他の個人情報が記載された書類も、鍵のかかるキャビネットで保管するなど、第三者が容易に閲覧できないよう、物理的な安全管理を徹底することが大切です。
従業員の入社手続きは非常に多くの作業があり、法的なリスクも伴います。特に、専門の担当者を置くことが難しい小規模な会社では、事業主や他の業務を兼任する担当者にとって、大きな負担となりがちです。
こうした負担を軽くするには、手続きを「デジタル化」すること、そして専門家である「社労士」に任せること、という2つの有効な方法があります。担当者の負担を減らし、ミスを防ぐことは、事業主が本来のコア業務に集中するための、極めて有効な経営戦略です。
ここでは、入社手続きの負担を軽くするための具体的な方法を、この2つの観点から紹介します。
電子申請や電子署名を活用する
行政への届出や契約手続きは、電子申請や電子署名を利用することでオンラインで完結できます。これにより、役所に出向く手間や紙書類の郵送・保管コストが不要となり、業務の効率が大幅に向上します。
具体的には、政府が提供する「e-Gov(イーガブ)」を利用すれば、社会保険や労働保険に関する各種届出を、会社のパソコンからオンラインで提出可能です。また、雇用契約書などをクラウド型の電子契約サービスで結べば、押印や郵送のやり取りが不要となり、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。
進捗管理・リマインダー・チェックリスト機能で手続きの漏れを防止する
入社手続きでは「社会保険の資格取得届は5日以内」といった、絶対に守らなければならない厳しい期限があります。これを担当者の記憶や手作業の管理に頼るのはリスクが高く、抜け漏れや遅延の原因になりかねません。
労務管理システムを導入すれば、誰が何をいつまでに行うべきか、手続きの進捗状況を一覧で確認できます。さらに、提出期限が近づくと自動で通知が届くリマインダー機能を活用すれば、提出忘れの心配がなくなります。こうした仕組みによって、担当者は期限のプレッシャーから解放され、安心して手続きを進められるようになります。
専門家である社労士に、複雑な手続きはアウトソースする
ツールによる効率化は有効ですが、法改正に対応した書類の作成や、複雑なケースでの専門的な判断が必要な場面もあります。これらをすべて自社で対応するのは負担が大きく、意図せず法令違反を犯してしまうリスクも残ります。
このような場合、手続きの専門家である社会保険労務士(社労士)に任せるのが、最も安心で確実な方法です。特に、継続的な顧問契約だけでなく、必要な時に必要な手続きだけを依頼できる「スポット契約」を活用すれば、小規模な会社でも費用を抑えつつ、柔軟に専門家の力を借りることができます。
複雑な行政手続きを専門家に任せることで、事業主は手続きに関する不安から完全に解放され、安心して事業に集中できる体制が整います。
従業員の入社手続きは、単なる事務処理にとどまらず、会社の基盤を整える、攻めの経営活動の一部です。特に、一人ひとりの活躍が業績に直結する小規模な会社にとって、新入社員を万全の体制で迎え入れることには、経営上の大きな意味があります。
正確で期限を守った手続きは、法令違反や追徴金といったリスクから会社を守るだけでなく、入社した従業員が安心して働ける環境の土台となります。この初期段階での安心感が、その後の定着率や活躍に繋がり、ひいては会社全体の成長へと結びついていくからです。
この記事で紹介したチェックリストや手順を活用すれば、ご自身で手続きを進めることは十分に可能です。
しかし、もしあなたが「煩雑な手続きに時間をかけるより、本来の事業にもっと集中したい」「法改正や細かなルールを追いかけるのが大変だ」と感じるなら、専門家である社労士にを頼るのが最も賢明な選択です。
「社労士クラウド」のようなサービスは、顧問契約を結ばなくても、必要な入社手続きだけを専門家である社労士に、必要な時にだけ依頼できます。
会社の貴重な時間を守り、成長を加速させるための一つの方法として、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
ここまで見てきた入社手続きは、社会保険・労働保険・税務と幅広く、期限も厳しいため、担当者にとって大きな負担となります。そこで活用できるのが、スポット申請代行サービス「社労士クラウド」です。
社労士クラウドは、顧問契約を結ぶ必要がなく、その時に必要な手続きだけを依頼できる仕組みになっています。これにより、費用を抑えつつ専門家の知識と経験を活用できる点が大きな特徴です。
また、社会保険や労働保険の手続きはもちろん、書類作成から提出までを迅速に対応するため、担当者の時間を大幅に節約できます。加えて、法改正やケースごとの判断が必要な場面でも、専門家による的確な対応が受けられるため安心です。
入社手続きに不安がある、または限られたリソースで確実に手続きを済ませたい事業主にとって、最も費用対効果の高い選択肢といえるでしょう。まずは気軽に問い合わせて、自社に合った形で活用してみてください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|