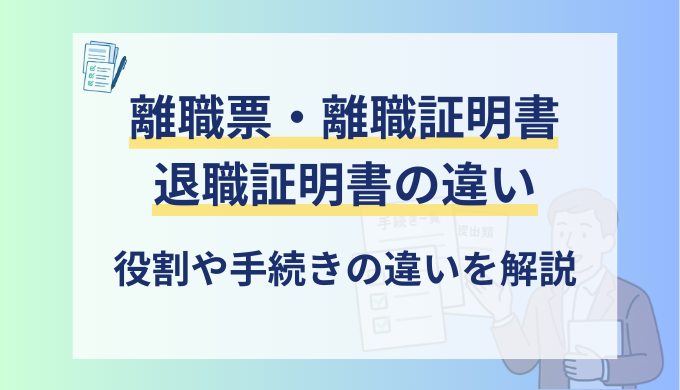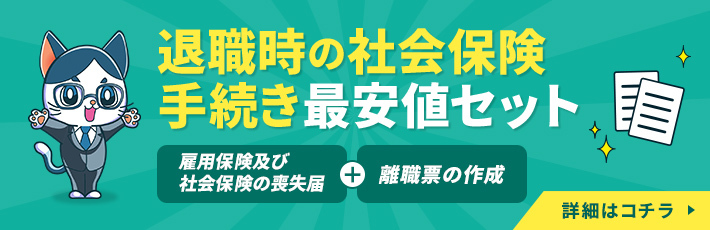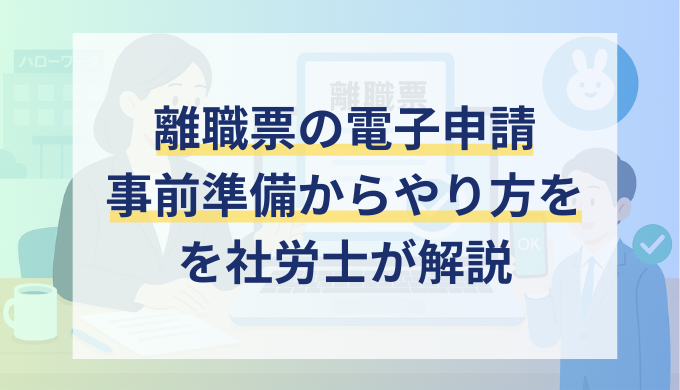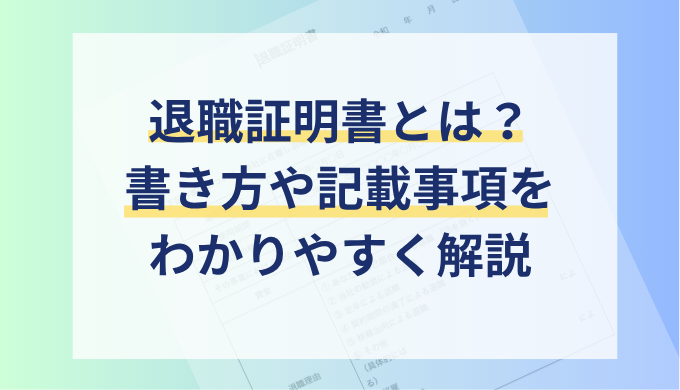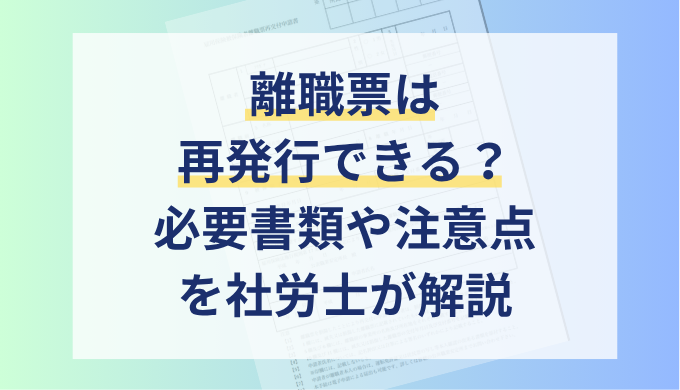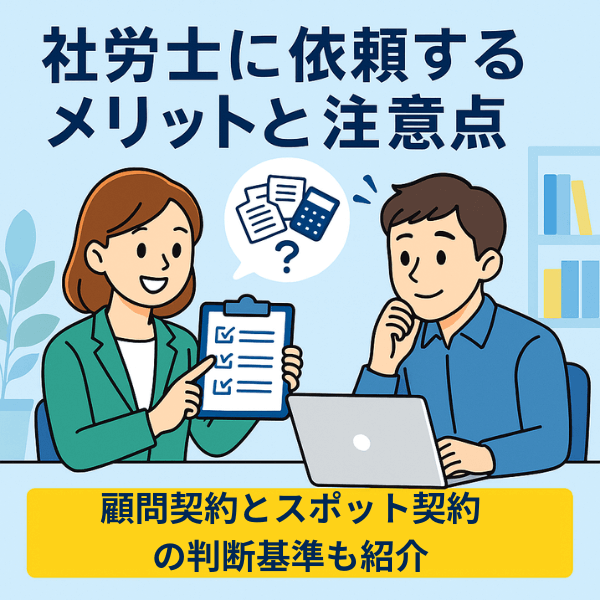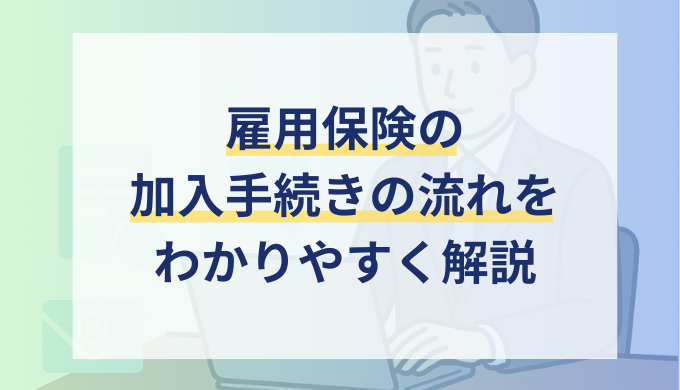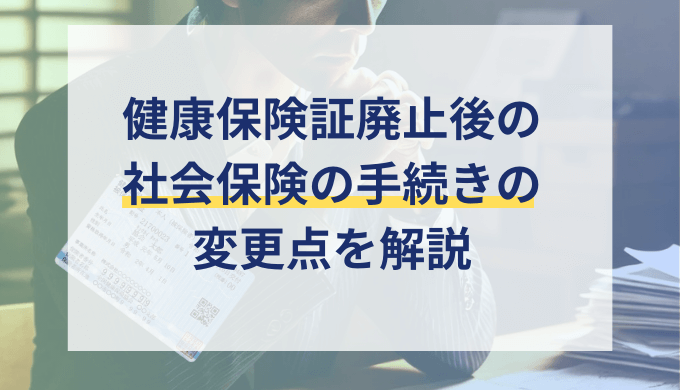就業規則は、会社と従業員のルールを定める「企業のルールブック」であり、労使トラブルの予防にも不可欠です。労働基準業員が退職する際に必要となる書類には「離職票」「離職証明書」「退職証明書」があります。
しかし名称が似ているため、「どの書類を誰に渡せばよいのか」「全部必要なのか」「失業保険の手続きにはどれを使うのか」と迷ってしまう事業主や労務担当者は少なくありません。
結論から言えば、離職票は失業給付の申請に必要なハローワーク発行の公的書類、離職証明書はその前提として会社が作成する書類、そして退職証明書は従業員から請求があった場合に会社が交付する私的証明書であり、目的も法的根拠も異なります。
本記事では、離職票・離職証明書・退職証明書の違いと役割、それぞれの発行手続きの流れから注意点までをわかりやすく解説します。
退職者とのトラブルを避け、期限を守ってスムーズに手続きを進めるためのチェックポイントを押さえていきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業員が退職する際に手続きで必要となる「離職票」「離職証明書」「退職証明書」は、名称が似ているため混同されがちですが、それぞれの書類の役割と目的、法的な位置づけは全く異なります。
特に「離職票」と「退職証明書」は役割が明確に違います。離職票は失業保険(基本手当)の受給に、退職証明書は国民健康保険への加入や転職先への在籍証明に必要となる書類です。
この2つの書類に加えて、離職票の発行手続きに必要となるのが「離職証明書」です。以下の比較表で、それぞれの書類の具体的な違いを正確に理解しましょう。
| 書類名 | 離職票(雇用保険被保険者離職票) | 離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書) | 退職証明書 |
| 目的・役割 | 失業保険(基本手当)受給手続きに必要 | 会社がハローワークへ離職票の発行を申請するため書類 | 退職の事実や期間を証明する(国民健康保険の加入手続き、転職先企業への提出など) |
| 発行元 | ハローワーク(企業が手続き依頼) | 会社 | 会社 |
| 提出先 | 退職者本人 | ハローワーク | 転職先企業や市区町村 |
| 発行義務 | 退職者が希望した場合(59歳以上は必須) | 離職票交付に必須 | 従業員から請求があった場合は発行義務 |
離職票は退職者が失業手当(雇用保険の基本手当)の受給に必要な公的書類です。
その前提として、会社が「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」を作成・提出する必要があり、この手続きを経て初めてハローワークから離職票が交付されます。
一方、退職証明書は労働基準法第22条に基づき、従業員から請求があった場合に会社が発行する私的な証明書で、公的効力はありません。
雇用離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票)とは、従業員が退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)の受給手続きを行う際に、ハローワークへ提出する必要がある公的な書類です。
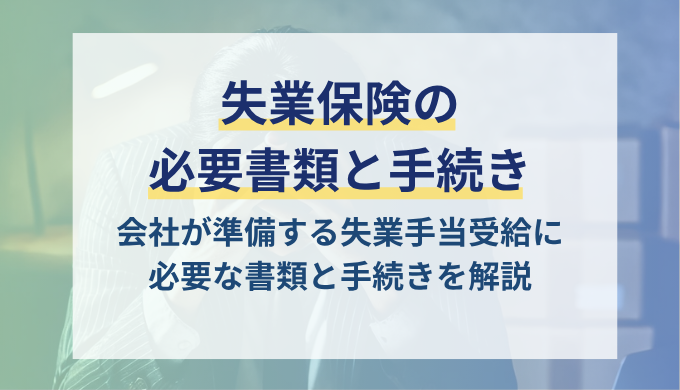 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
この書類には、退職前の賃金支払状況や離職理由などが記載されており、ハローワークが失業手当の受給資格や支給額を決定するための重要な判断材料となります。
会社は、退職する従業員から離職票の交付を希望された場合、または退職時の年齢が59歳以上である場合には、原則として離職票を発行するための手続きを行わなければなりません。
転職先がすでに決まっている退職者など、本人が希望しない場合は発行手続きが不要なケースもあります。
離職票の発行を希望しない場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が交付されます。詳しくは以下の記事で詳しく解説しています。
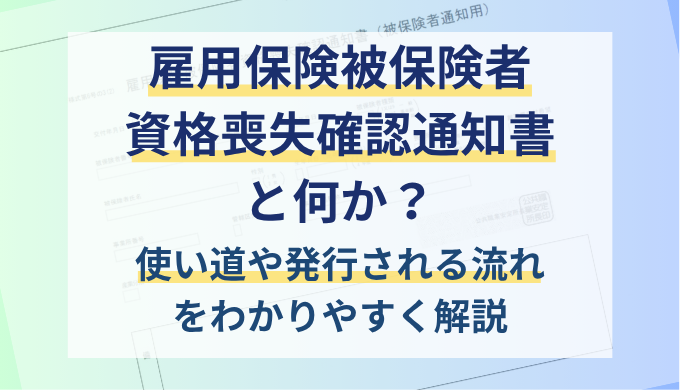 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
離職票と離職証明書の違い
離職証明書は離職票交付の前提としてハローワークへ提出する公的手続き用の会社作成書類、退職証明書は労働基準法第22条に基づき退職者から請求があった場合に会社が交付する在籍・退職事実の私的証明書です。用途・提出先・法的根拠が異なります。
| 書類名 | 離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書) | 退職証明書 |
| 目的・役割 | 離職理由・賃金等の事実を証明し、離職票交付の根拠にする | 在職期間・業務の種類・地位・賃金・退職理由などを証明し、転職先企業提出や国民健康保険手続きで利用 |
| 提出先 | ハローワークへ会社が提出 | 退職者へ会社が交付 |
| 法的根拠 | 離職票交付に必須。(雇用保険法に基づく) | 従業員から請求があった場合に義務となる。(労働基準法第22条に基づく) |
| 期限 | 退職日の翌々日から10日以内に提出 | 請求があった場合は遅滞なく交付 |
ハローワークとの公的な手続きに使うのが「離職証明書」、退職者個人の証明に使うのが「退職証明書」となります。
離職票を発行する手続きの流れ
離職票の発行手続きは、会社が主体となって進めなければなりません。従業員のスムーズな失業手当受給のため、以下の手順離職証明書(正式名称:雇用保険被保険者離職証明書)とは、会社がハローワークへ「離職票」の発行を申請するために会社が作成し提出する公的な書類です。
この離職証明書には、退職者の賃金支払状況や離職理由を具体的に記載します。ハローワークは離職証明書の内容に基づき、失業手当の支給可否や給付日数を決定するため、非常に重要な役割を持ちます。
離職証明書が必要になるタイミングは、退職する従業員が失業手当の受給を希望し、離職票の交付を求めてきた場合です。また、退職時の年齢が59歳以上の従業員については、本人の希望にかかわらず会社は離職証明書を作成し、手続きを行う義務があります。
離職証明書の基本的なことや書き方については下記の記事で詳しく解説しています。
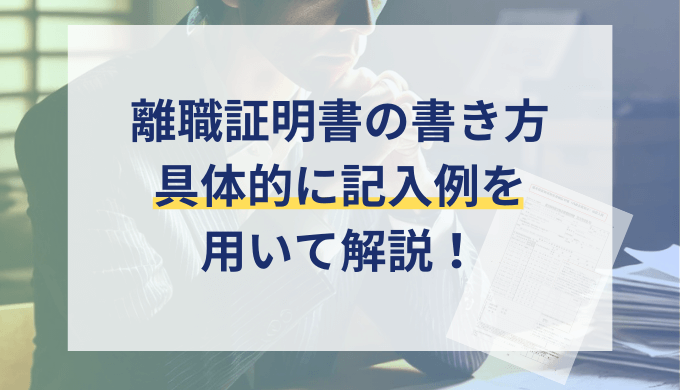 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
労働保険概算保険料申告書の提出・納付
離職証明書の作成から提出までの手続きは、以下の流れで進めます。賃金台帳や出勤簿など、記載内容の根拠となる書類を事前に準備しておくとスムーズです。
【ステップ1】離職証明書の用紙を入手する
離職証明書の用紙は、管轄のハローワークの窓口で受け取るか、一部の電子申請システムからダウンロードして作成します。
【ステップ2】必要事項を記入する
被保険者番号や事業所番号、退職者の住所氏名といった基本情報に加え、退職日以前6ヶ月間の賃金支払状況と、具体的な離職理由を記入します。特に離職理由は、失業手当の給付条件に大きく影響するため、事実に基づき正確に記載してください。
【ステップ3】退職者に内容を確認してもらい、署名・押印をもらう
作成した離職証明書の記載内容、特に離職理由について退職者本人に確認を求め、記名押印または自筆による署名をもらいます。
【ステップ4】ハローワークへ提出する
「雇用保険被保険者資格喪失届」と共に、完成した離職証明書を退職日の翌々日から10日以内に管轄のハローワークへ提出します。この手続きをもって、離職票の交付申請が完了します。
離職票の発行手続きは電子申請(e-Gov)でもできます。電子申請のやり方について下記の記事で詳しく解説しています。
退職証明書とは?必要になるタイミング
退職証明書とは、労働基準法第22条に基づき、退職した従業員から請求があった場合に、会社が退職の事実を証明するために発行する私的な書類です 。
この退職証明書には、在籍期間、業務の種類、役職、賃金、そして退職理由といった項目を記載します 。法律上、会社は従業員が請求しない事項を記載してはならないと定められているため、発行時にはどの項目が必要か本人へ確認することが重要です 。
退職証明書が必要になる主なタイミングは、以下のケースです。
- 転職先企業から提出を求められた場合
- 国民健康保険・国民年金の加入手続き
退職証明書と離職票の違い
退職証明書は会社が退職者へ交付する私的証明、離職票はハローワークが発行し失業給付の申請に用いる公的書類です。目的・発行主体・提出先・法的根拠・義務の有無が異なります。
| 書類名 | 退職証明書 | 離職票 |
| 目的・役割 | 在職期間・業務の種類・地位・賃金・退職理由などを証明するために必要 | 失業給付(基本手当)申請に必要 |
| 提出先 | 退職者、転職先企業、自治体等 | 退職者(ハローワークで申請時に使用) |
| 法的根拠 | 労働基準法第22条(請求があれば交付義務) | 雇用保険法(会社の離職証明書提出が前提) |
| 発行義務 | 退職者が請求した場合に交付義務あり | 退職者が失業給付を受ける場合に会社は手続き義務 |
| 代替可否 | 離職票の代替不可(失業給付では使用不可) | 退職証明書の代替用途は想定外 |
失業手当の申請に退職証明書は使えず、逆に転職先に離職票を提出するケースは一般的ではありません。それぞれの用途を正しく理解することが大切です。
退職証明書を発行する手続きの流れ
退職証明書の発行手続きは、従業員からの請求を受けて開始します。発行義務を怠ると労働基準法違反となる可能性があるため、以下の流れに沿って速やかに対応しなければなりません 。
【ステップ1】退職者からの請求を受ける
退職した従業員から、電話、メール、書面などで退職証明書の発行依頼を受けます。法律上、請求権は退職後2年間有効です 。
【ステップ2】記載事項を確認する
退職者本人に、証明書に記載を希望する項目(在籍期間、役職、退職理由など)を必ず確認します。前述の通り、本人が希望しない項目は記載できません。
【ステップ3】退職証明書を作成・交付する
確認した内容に基づき、会社のフォーマットで退職証明書を作成します。書式は任意ですが、会社の住所・名称を記載し、代表者印を押印するのが一般的です。作成後、請求者である退職者本人へ「遅滞なく」交付します 。
下記の記事で退職証明書の書き方を詳しく解説しています。またテンプレートもダウンロードできます。
ここでは、退職手続きに関する書類について、事業主や担当者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
離職票は再発行できますか?
離職票は再発行することができます。
離職票を紛失した場合など、再発行が必要になった際は、退職者本人が身分証明書などを持参して管轄のハローワーク窓口で直接手続きを行うか、退職した会社を通じて再発行を依頼する方法があります。
離職者本人が管轄ハローワークで再交付申請を行う方法が最も速やかです。
離職票の発行手続きに期限はありますか?
会社は、従業員の退職日の翌々日から10日以内に、管轄のハローワークへ「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。この手続きが遅れると、退職者の失業手当受給が遅延する原因となるため、迅速な対応が求められます。
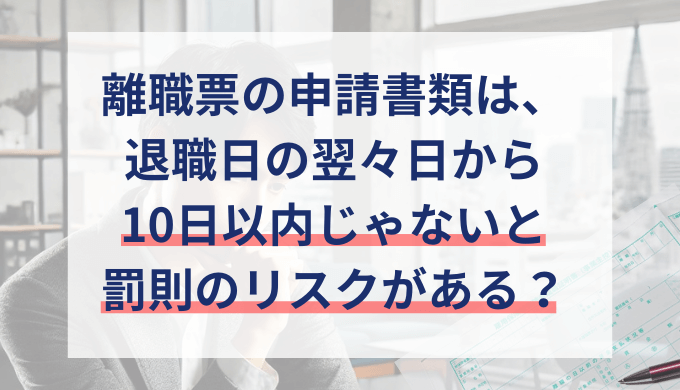 離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
退職証明書は離職票の代わりになる?
原則として退職証明書は離職票の代わりにはなりません。
特に、失業手当の受給手続きにおいては、必ずハローワークが発行した離職票が必要です。退職証明書をハローワークの窓口に提出しても、失業手当の申請はできません。
ただし、国民健康保険への切り替え手続きなど、一部の行政手続きでは「退職日を証明する書類」として、離職票がまだ手元に届かない場合の代替書類として退職証明書が認められるケースがあります。
しかし、これはあくまで例外的な使用方法であり、2つの書類は全く別のものであると認識してください。
従業員が退職する際には、本記事で解説した離職票や退職証明書の発行手続き以外にも、会社側で行わなければならない法的な手続きが複数存在します。
特に「社会保険」「雇用保険」「税金」に関する手続きは、それぞれ提出先や期限が法律で定められており、対応漏れがないよう正確に把握しておくことが重要です。
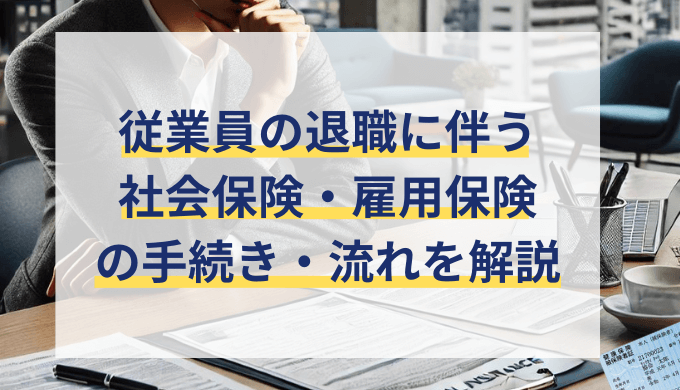 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失手続き
従業員が退職すると、会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入資格を喪失します。会社は、退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所または健康保険組合へ提出しなければなりません。
手続きの際には、退職する従業員本人とその扶養家族分の健康保険被保険者証(保険証)を忘れずに回収してください。
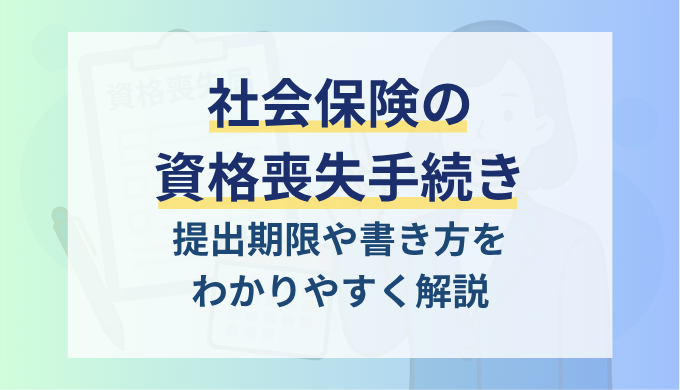 社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
雇用保険の資格喪失手続き
雇用保険についても、社会保険と同様に資格喪失の手続きが必要です。会社は、退職日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークへ提出します。
この手続きは、本記事で解説した「離職証明書」の提出と同時に行うのが一般的です。退職者が離職票の交付を希望しない場合でも、この資格喪失届の提出は必須の手続きとなります。
住民税と所得税関連の手続き
退職時には、税金に関する手続きも発生します。
従業員の住民税を給与から天引き(特別徴収)していた場合、会社は「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出する必要があります。退職月によって、残りの住民税を最後の給与から一括で徴収するか、従業員自身が納付する普通徴収に切り替えるかが異なります。
会社は、その年に支払った給与額や源泉徴収した所得税額を記載した「源泉徴収票」を作成し、退職後1ヶ月以内に退職者本人へ交付する義務があります。この源泉徴収票は、退職者が転職先での年末調整や自身での確定申告に用いる重要な書類です。
従業員の退職で会社側が行う手続き一覧については下記の記事でまとめて解説しています。
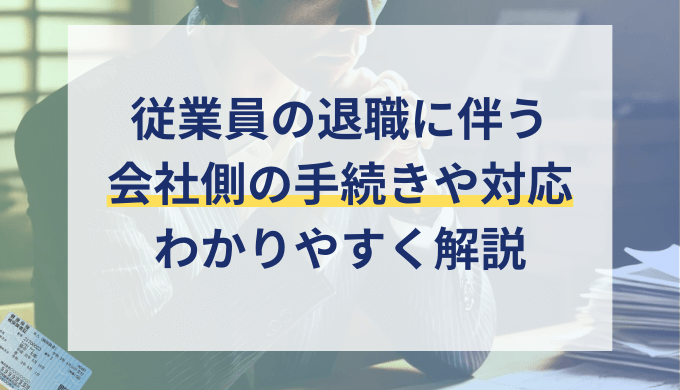 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
離職票・離職証明書・退職証明書は、名称が似ていても目的・発行主体・提出先・義務・法的根拠が明確に異なります。
| 書類の種類 | 概要 |
| 離職票 | 退職者が失業手当の申請に使う、ハローワーク発行の公的書類 |
| 離職証明書 | 離職票の発行を申請するために、会社が作成しハローワークへ提出する書類 |
| 退職証明書 | 退職の事実を証明するために、退職者の請求に基づき会社が発行する私的書類 |
事業主や労務担当者の方は、この3つの書類の違いを正しく理解し、定められた期限内に手続きを完了させることが、トラブルを未然に防ぎ、従業員の円満な退職をサポートする上で不可欠です。
会社側の退職手続きは「期限管理」と「書類の役割整理」が肝心です。チェックリストなどを活用することで漏れを防止できます。
もし手続きに不安がある場合や期限を過ぎてしまった場合には、専門家である社労士に相談、依頼して対応してもらいましょう。
スポット依頼ができる社労士クラウドについて
ここまで解説した通り、退職手続きには複数の書類作成と行政機関への届出が必要となり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
「手続きの内容は理解できたが、いざ自社で対応するとなると不安が残る」 「初めての退職者対応で、絶対にミスをしたくない」 「日々の業務が忙しく、手続きにまで手が回らない」
もしこのようにお困りでしたら、私たち「社労士クラウド」にご相談ください。 社労士クラウドは、月額の顧問契約が不要で、必要な手続きだけを専門家である社会保険労務士に依頼できる「スポット契約」が可能なサービスです。離職票の発行手続き一つから、専門家が迅速かつ正確に代行します。
手続きに少しでも不安を感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|