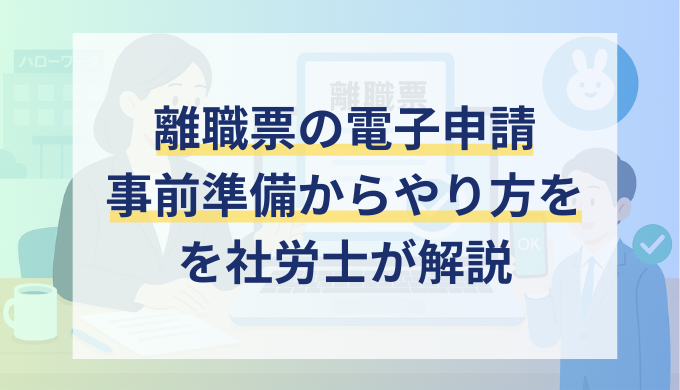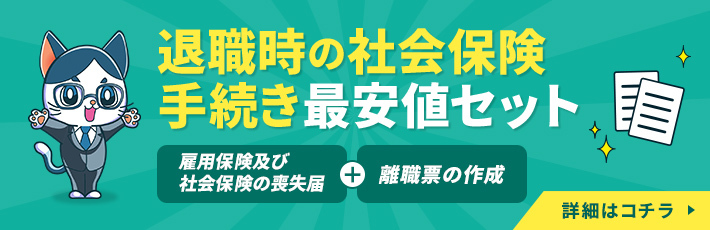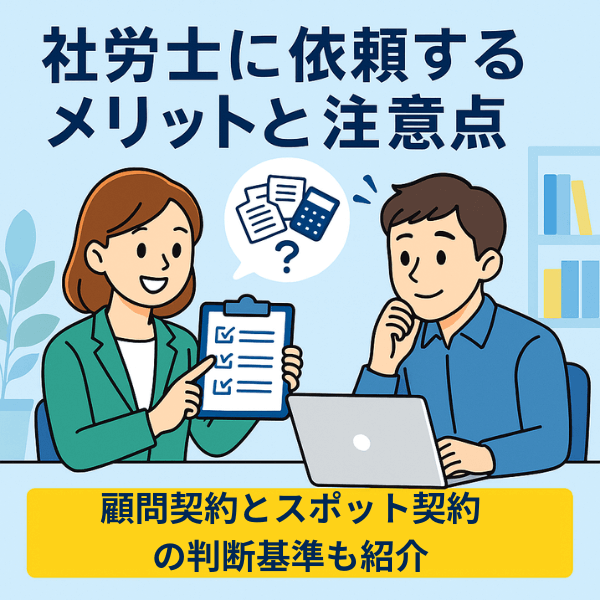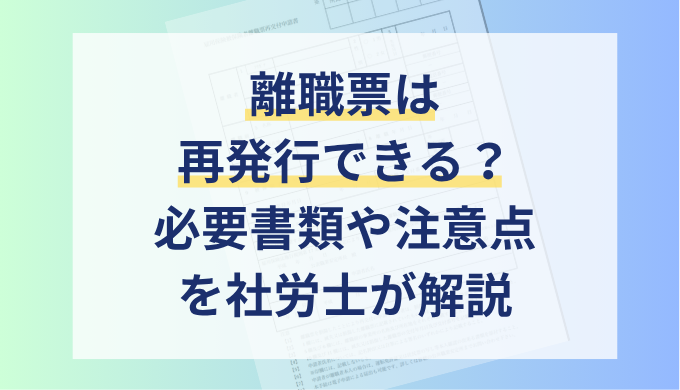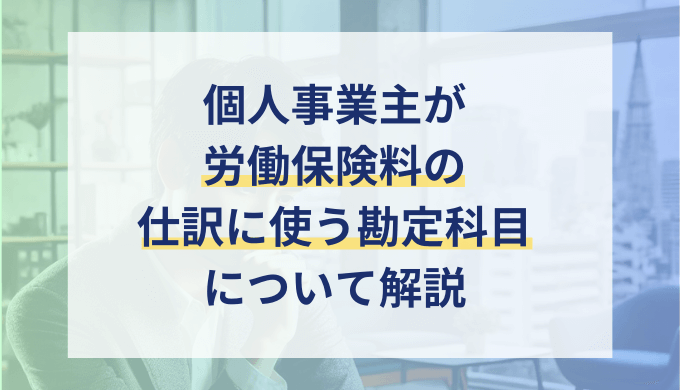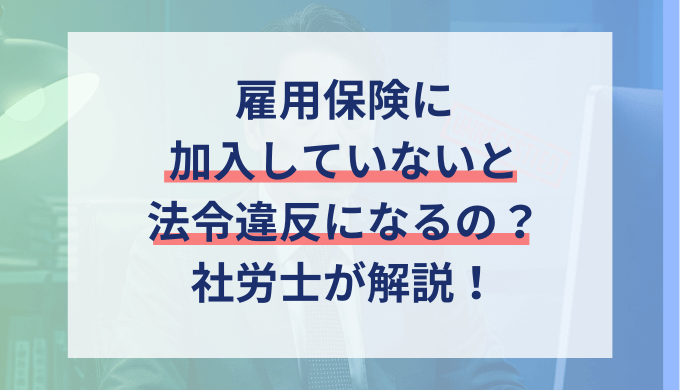従業員の退職に伴い、必ず発生するのが「離職票」の発行手続きです 。近年では、ハローワーク窓口だけでなく電子申請による発行も可能になり、マイナポータルを通じて退職者本人が受け取ることもできます 。
しかし、電子申請には事前準備や手順、注意点があり、従来の窓口申請とは異なるポイントも多くあります 。
本記事では、離職票を電子申請するやり方を事前準備や具体的な申請手順もふまえ、社労士がわかりやすく解説しています 。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
離職票とは、従業員が退職後に失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るために必要な公的書類です。正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職票1と離職票2の2種類があります。
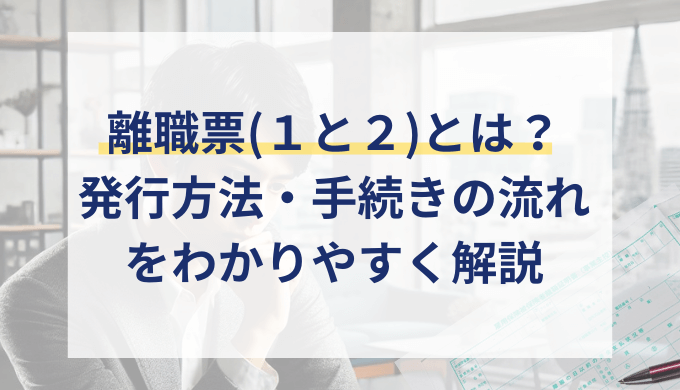 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
事業主は、従業員が退職し、本人から離職票交付の希望があった場合、退職日の翌々日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」を提出し、離職票の発行手続きを行わなければなりません。
離職証明書は離職票を発行してもらうための申請書類であり、事業主が「退職の事実」や「退職理由」「賃金情報」などを記載して提出します(3枚複写の様式)。
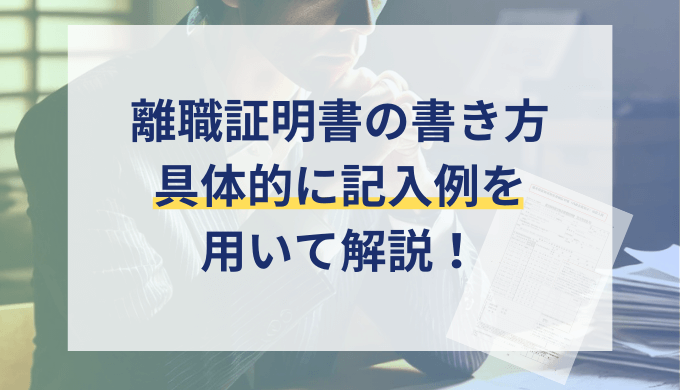 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
手続きが完了すると、ハローワークから事業主へ離職票が交付され、事業主はそれを速やかに退職者本人へ渡す義務があります。
退職者が失業保険を受給するために会社側で準備する必要書類や手続きを下記の記事でまとめています。
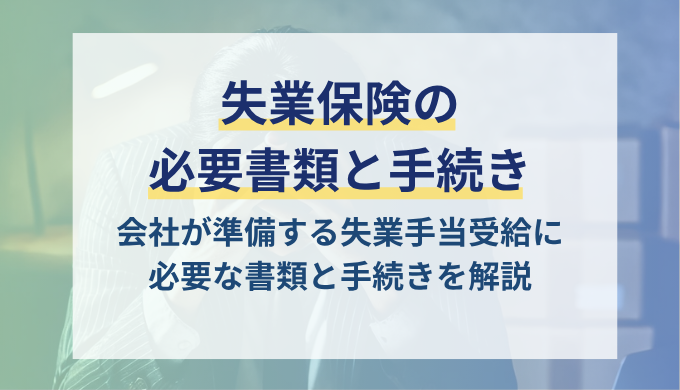 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
離職票の発行手続きには、ハローワークの窓口へ直接書類を持参する「窓口申請」と、政府の電子申請システム「e-Gov」を利用する「電子申請」の2つの方法があります。
近年、政府は行政手続きのデジタル化を推進しており、電子申請が推奨されています。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
| 項目 | 窓口申請(紙申請) | 電子申請 |
| 提出方法 | 事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口へ持参 | e-Gov(電子政府の総合窓口)または連携している労務管理ソフトからオンラインで提出 |
| 受付時間 | ハローワークの開庁時間内のみ | 24時間365日いつでも提出可能 |
| 必要書類 | ・離職証明書(3枚複写) ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・賃金台帳、出勤簿、退職届の写しなど | ・GビズIDまたは電子証明書 ・インターネット環境 ・各種書類の電子データ(PDF等) |
| 導入コスト | なし(書類の印刷代や交通費は別途発生) | 原則無料(GビズIDの場合)。 ※別途、電子証明書や対応ソフトの費用がかかる場合がある。 |
| 離職票の交付 | 原則、後日郵送または再度窓口で受け取り | 電子公文書(PDF)で交付。またはマイナポータル経由で離職者へ直接送付が可能 |
電子申請のメリット・デメリット
- インターネット環境があれば24時間いつでも提出可能
- ハローワークへの移動・待ち時間が不要
- 複数人分をまとめて処理できるため効率的
- 処理が早く、発行までの期間が短縮されやすい
- 利用には電子証明書や対応ソフトの準備が必要
- 初期設定や操作方法の習得に時間がかかる
- 電子申請環境が整っていない事業所では導入ハードルが高い
窓口申請のメリット・デメリット
- 書類不備があってもその場で職員と確認できる
- 初めての申請やイレギュラー対応にも安心
- 導入コストがゼロで、準備不要ですぐ始められる
- 窓口の開庁時間内(平日8:30〜17:15)しか対応できない
- 移動・待ち時間の負担がある
- 繁忙期は混雑し、手続きに時間がかかることもある

離職票の発行手続きが10日を過ぎてしまった場合、企業は雇用保険法に基づく罰則が科される可能性があります。 また、退職者が失業給付を受けられないなどの不利益を生じさせることになります。
ただ、離職票の発行に必要な書類の準備は複雑で難しく、専門的な知識が必要とされます。そのため、社会保険労務士など専門家へ依頼することでミスや手間をなくすことができます。
社労士クラウドなら「離職票の手続き」を顧問料なしのスポット(単発)で簡単かつ迅速にお手続きできます。離職票の見積もりを含め、お困りの場合は、公式LINEまたはChatworkにて社会保険に関するご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
離職票の電子申請をスムーズに完了させるためには、e-Govのシステムにログインする前の事前準備が極めて重要です。
準備不足のまま申請を進めると、入力エラーや差し戻しが発生し、発行までの期間が延びる原因になります。ここでは電子申請をスムーズに行うための主な準備項目を解説します。
GビズID(推奨)または電子証明書を準備・登録
離職票の電子申請を行うには、事業所の身元を証明するための「GビズID(プライム)」または「電子証明書」のいずれかが必要です 。
おすすめは、無料で取得でき、複数の行政手続きに利用できる**「GビズID(プライム)」**です。ただし、取得には郵送での審査があり、申請から1〜2週間程度かかる場合があるため、余裕を持って手続きを進める必要があります。
すでに商業登記電子証明書などをお持ちの場合は、その電子証明書を利用して申請することも可能です。
e-Govポータルでアカウントを作成する
GビズIDまたは電子証明書の準備が完了したら、次にe-Govポータルでアカウントを作成します 。e-Gov(電子政府の総合窓口)は、各省庁への申請や届出をオンラインで行うための政府公式ポータルサイトです 。
アカウント作成後、GビズIDまたは電子証明書と連携させることで、e-Govにログインし、離職票の電子申請手続きを開始できるようになります 。
■「e-Gov電子申請アプリケーション」のインストールを忘れずに
アカウント作成と合わせて、電子申請をスムーズに行うための**「e-Gov電子申請アプリケーション」をパソコンにインストールする必要があります。
このアプリケーションは、ブラウザ上での電子署名などを可能にし、申請手続きを正しく完了させるためのものです。e-Govのサイトから無料でダウンロードできますので、申請を開始する前に必ずインストールを完了させてください。
マイナンバーを被保険者番号に登録する
退職者の離職票をマイナポータル経由で交付するためには、退職者のマイナンバーと雇用保険被保険者番号がハローワークのシステム上で正しく紐づけられている必要があります。
この紐づけが完了していない、または情報が古いままになっている場合、退職者が希望してもマイナポータルで離職票を受け取ることができません。
従業員の入社時にマイナンバーを届け出ていない場合などは、事前に「個人番号登録・変更届」をハローワークへ提出しておく必要があります。
マイナポータルで受取希望の有無を本人に確認する
2025年1月20日から、退職者が希望すれば、離職票をマイナポータルで直接受け取れるようになりました。この方法を利用すると、事業主がPDFをダウンロードして退職者へ送付する手間を省くことができます。
そのため、手続きを開始する前に、退職者本人にマイナポータルでの受け取りを希望するかどうかを確認してください。
退職者が希望する場合は、自身のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらうよう、事前に案内しておく必要があります。
必要な添付書類を確認・準備する
離職票の電子申請では、申請内容を証明するための書類を添付しなければなりません。あらかじめ以下の書類を準備し、PDF形式などでスキャン・データ化しておいてください。
- 賃金台帳:離職日から遡った期間の賃金支払状況がわかるもの
- 出勤簿(またはタイムカードなど):賃金台帳の基礎となる出勤状況がわかるもの
- 退職届:離職理由が確認できる書類(自己都合退職の場合など)
- (本人署名省略の場合)本人の内容確認書または疎明書:離職証明書の内容について、本人が確認したことを示す書類
事前準備が完了すれば、e-Govの画面に沿って情報を入力することで離職票の電子申請が可能です。申請から離職票のダウンロードまでの流れを4つのステップに分けて解説します。
①雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)の手続きを始める
まず、e-Govポータルにログインし、手続きを検索します。 検索窓に「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」と入力して、該当の手続きを選択してください。
この手続き一つで、雇用保険の資格喪失手続きと離職票の交付申請を同時に行えます。
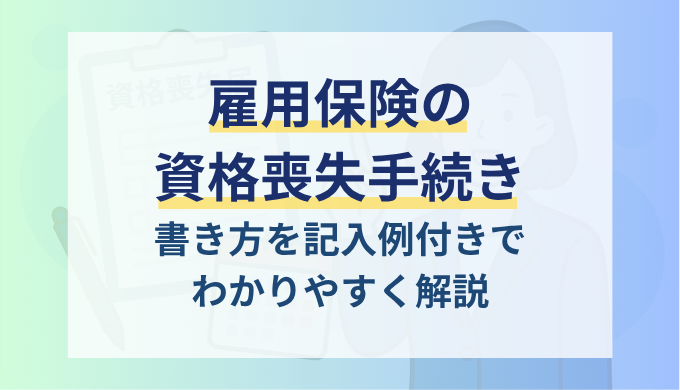 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
②申請書類一式を作成する
手続きを選択すると、申請情報の入力画面が表示されます。画面の指示に従い、必要な情報を入力して申請書類を作成してください 。
離職票の電子申請では、「資格喪失届」→「離職証明書」の順番で帳票を作成します。
◯資格喪失届の作成
事業所情報や退職する従業員の被保険者番号、資格喪失年月日(退職日の翌日)、離職理由などを入力します。
◯離職証明書の作成
退職日以前の賃金支払状況や、具体的な離職理由などを詳細に入力します。 この内容は失業手当の金額を左右する重要な項目であるため、賃金台帳や出勤簿を元に正確に入力しなければなりません。
すべての入力が完了したら、プレビュー画面で誤りがないか必ず確認してください。
③電子署名をして提出する
全ての情報の入力と、事前に準備した添付書類(賃金台帳のPDFなど)のアップロードが完了したら、最後に電子署名を付与して申請データを提出します。
電子署名は、準備したG-Biz IDまたは電子証明書を用いて行います。
電子申請の場合、離職証明書への退職者本人の署名は不要です。 ただし、原則として、記載内容について退職者本人が確認したことを示す「確認書」などを別途添付する必要があります。
提出が完了すると「到達番号」が表示されます。 この到達番号は、申請状況の確認に必要となるため、必ず控えておきましょう。
④審査完了後に離職票をダウンロードする
申請データがハローワークに到達すると、内容の審査が行われます。申請状況はe-Govのマイページからいつでも確認可能です。
審査が完了し、手続きが終了すると、e-Gov経由で通知が届きます。その後、マイページから電子公文書として交付された離職票(PDF形式)をダウンロードできるようになります。
ダウンロードした離職票を印刷し、退職者本人へ交付してください。なお、離職票-2はA3で発行される場合もありますが、A4サイズで印刷しても手続き上の問題はありません。
2025年1月20日より、従業員が希望すれば、事業主が電子申請した離職票を従業員本人のマイナポータルへ直接送付できるようになりました 。
この方法を活用することで、事業主はハローワークから交付された離職票(PDF)をダウンロードし、退職者へメールなどで送付する手間を省くことができます。ただし、この方法を利用するには、申請を行う事業主側だけでなく、受け取る従業員側でも事前の手続きが必要となります。
【申請前】離職者に「雇用保険WEBサービス」との連携を依頼する
マイナポータルで離職票を受け取ることを従業員が希望する場合、事業主は電子申請を行う前に、従業員本人にマイナポータル上での手続きを依頼しなければなりません。
具体的には、従業員本人が以下の手続きを行う必要があります 。
- 自身のスマートフォンなどからマイナポータルにログインする
- メニューの「外部サイトとの連携」から「雇用保険WEBサービス」を選択し、連携設定を完了させる
この連携手続きを行わない限り、事業主が電子申請をしても、離職票がマイナポータルに届くことはありません 。
事業主としては、退職の申し出があった際に、マイナポータルでの受け取りを希望するかどうかを確認し、希望する従業員にはこの連携手続きを早め(退職の2週間程度前まで)に行うよう、忘れずに案内してください 。
【申請完了後】離職者へダウンロードを案内する
事業主が離職票の電子申請を行い、ハローワークでの審査・処理が完了すると、離職票等の書類が自動的に従業員のマイナポータルに直接送付されます 。
事業主は、e-Gov上で手続きの完了を確認した後、退職者へマイナポータルに書類が届いている旨を連絡し、ダウンロードを案内すると親切です。
従業員は、以下の手順で離職票(PDFファイル)を受け取ります 。
- マイナポータルアプリを起動する 。
- ホーム画面の「お知らせ」をタップする 。
- 「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知を確認する 。
- 画面を下にスクロールし、【詳細情報】欄に添付されているPDFデータをダウンロードする 。
この流れを退職者へ事前に伝えておくことで、退職後の手続きをスムーズに進める手助けとなります。
電子申請は便利ですが、いくつか押さえておくべき重要な注意点があります。
特に以下の4点は、手続きの遅延や行政からの差し戻しを防ぎ、スムーズな処理を実現するために必ず確認してください。
離職票の申請は従業員が退職した日の翌日から10日以内に行う
離職証明書の提出は、雇用保険法により「従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内」と定められています 。
この期限を過ぎてしまうと、退職者の失業手当の受給開始が遅れる原因となり、大きな不利益を与えてしまう可能性があります 。正当な理由なく手続きを怠った場合、法律に基づく罰則の対象となる可能性もゼロではありません 。
従業員から退職の申し出を受けたら、速やかに必要書類の準備を開始し、期限を遵守することが事業主の重要な義務です。
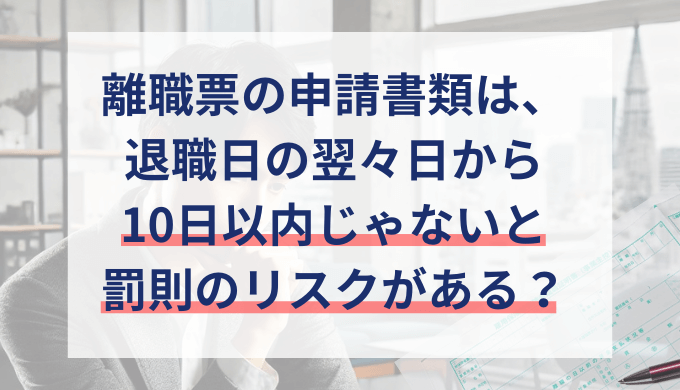 離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
本人署名欄を省略する場合は確認書(または疎明書)の添付が原則
紙の離職証明書には、記載内容を本人が確認したことを示すための署名欄があります。電子申請では、この署名の代わりに、本人が内容を確認したことを証明する書類を添付することが原則となります 。
具体的には、申請する離職証明書の内容を印刷またはPDFで従業員本人に見せ、内容に相違ないことを確認してもらった上で、その旨を記した**「確認書」**に署名をもらい、PDF化して添付します 。
郵送でのやり取りが難しい、すでに関係性が悪化しているなどの理由で本人の署名がもらえない場合は、やり取りの経緯などを記した事業主作成の**「疎明書(そめいしょ)」**を添付する必要があります。
添付書類で省略できるもの、できないものがある
電子申請に際しては、原則として賃金台帳や出勤簿、退職届といった記載内容の根拠となる書類の添付が必要です 。
ハローワークが認めた一部の優良事業所では、これらの添付書類の省略が認められる場合がありますが、これは何度も電子申請を行っている実績などが考慮されるため、初めて申請する場合や設立間もない事業所は対象外です。
| 書類の種類 | 原則 |
| 賃金台帳、出勤簿、退職届など | 省略できない(必ず添付が必要) |
| (本人の内容確認を証明する)確認書など | 省略できない(本人署名欄の代わりとして必要) |
事業主としては、「添付書類は原則すべて必要」と認識し、準備を進めるのが最も確実です。
賃金が確定していない月は欄に「未計算」と入力する
退職日によっては、申請時点で最終月の給与額がまだ確定していない場合があります。その場合、賃金支払状況の欄を空欄にしたり、「0」と入力したりしてはいけません。入力エラーの原因となります。
給与額が未確定の月については、賃金額の欄に「未計算」と入力してください。
ただし、賃金支払状況を記載する最初の行(最も古い月)を「未計算」とすることはできません。必ず給与が確定している月から入力を始める必要があります。このルールを守ることで、軽微な入力ミスによる差し戻しを防ぐことができます。
ここでは、離職票の電子申請に関して、人事・労務担当者の方からよくいただく質問とその回答をまとめました。
電子申請後、発行までにかかる日数は?
申請から発行までの日数は、管轄のハローワークの混雑状況によるため、一概に「何日」とは断定できません。
一般的には、申請がハローワークに到達してから数営業日〜1週間程度で処理されることが多いですが、年度末などの繁忙期は2週間程度かかる場合もあります。申請内容に不備があり、差し戻し(補正指示)があると、さらに期間は延びます。
退職者への迅速な交付を実現するためにも、期限(退職日の翌日から10日以内)の間際ではなく、可能な限り速やかに申請することが重要です。
電子申請は遅いって本当?
「電子申請は遅い」というイメージは、主に初回利用時の事前準備や操作への不慣れから生じることが多いです。
GビズIDの取得には1〜2週間かかるため、その期間を含めると初回の申請は時間がかかります 。しかし、一度環境が整えば、申請データは即時にハローワークへ到達するため、郵送にかかる時間が短縮され、手続きそのものは窓口申請よりもスピーディーです。
申請の遅延は、システムの問題よりも、添付書類の不足や入力内容の誤りによる「差し戻し」が原因であることがほとんどです。準備を万全にし、正確な申請を行えば、電子申請は最も効率的な方法です。
離職票をデータやPDFでもらうことはできる?
事業主が電子申請を行った場合、ハローワークから交付される離職票は電子公文書(PDF形式)となります 。事業主はe-GovのマイページからそのPDFファイルをダウンロードし、退職者へメールなどで送付することが可能です 。
また、退職者本人が希望し、マイナポータルとの連携設定を済ませていれば、事業主を介さず直接本人のマイナポータルに離職票のPDFが送付されます 。
離職票の再交付は電子申請できる?
離職票を紛失した場合などの再交付申請もe-Govから電子申請が可能です。
「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」の手続きがe-Govに用意されており、退職者本人または事業主が申請を行えます。
退職者本人が申請できるため、会社に再発行を依頼する手間を省けるメリットがあります。
従業員が退職する際には、離職票の発行(雇用保険の手続き)と並行して、社会保険や税金に関する手続きも行う必要があります。手続き漏れがないよう、主なものを確認しておきましょう。
社会保険の資格喪失手続き
退職する従業員を、会社の健康保険・厚生年金保険から脱退させる手続きが必要です。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、退職日の翌日から5日以内に、管轄の年金事務所または事務センターへ提出しなければなりません 。提出の際には、退職する従業員とその被扶養者全員分の健康保険証を回収し、添付する必要があります 。
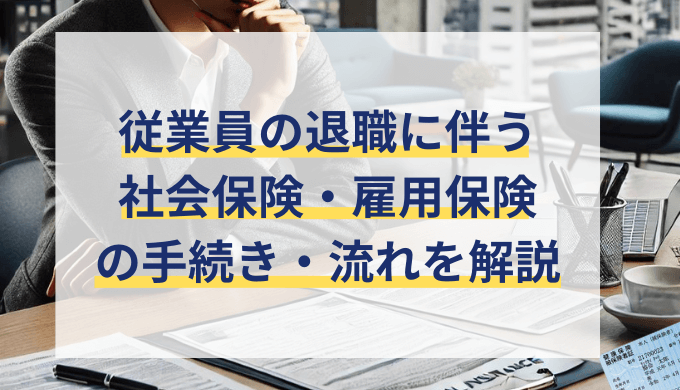 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
住民税(特別徴収)の精算・切替など
給与から住民税を天引き(特別徴収)している従業員が退職した場合、住民税の手続きも必要です。
退職する時期に応じて、最後の給与や退職金から残りの住民税を一括で徴収するか、従業員自身が納付する「普通徴収」に切り替えるかの手続きを行います。
事業主は「給与所得者異動届出書」を作成し、退職日の翌月10日までに、従業員が住む市区町村へ提出しなければなりません。
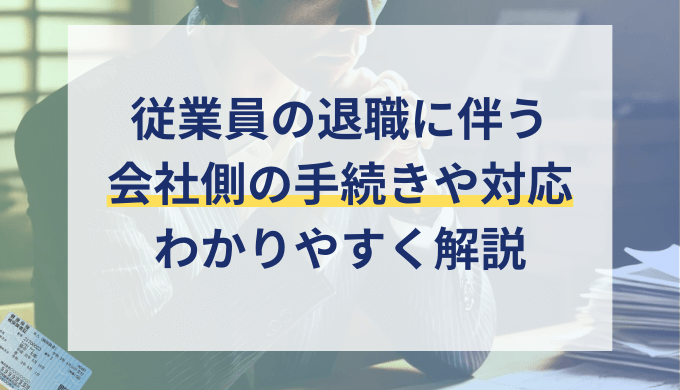 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
離職票は退職後の生活を支える重要な書類であり、事業主には10日以内という厳格な申請期限が課せられています。
電子申請の活用は、ハローワークへ出向く時間やコストを削減し、24時間いつでも手続きを可能にする非常に効率的な方法です 。ただし、事前準備や添付書類の確認を怠ると差し戻しになるリスクもあります。
準備さえ整えれば、e-Govでの手続き自体は画面の指示に従って進めることが可能です 。
しかし、退職日の翌日から10日以内という短い期限や、本人確認のルール、賃金未計算月の入力方法など、初めて手続きを行う担当者にとっては不安な点も多いかもしれません 。
一つひとつの手続きを正確に行うことが、企業のコンプライアンスを守り、退職する従業員との信頼関係を維持することにつながります。
もし手続きに不安がある場合や、コア業務に集中するために労務手続きの負担を軽減したい場合は、専門家である社労士に依頼することも検討しましょう。。
 社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説
社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|