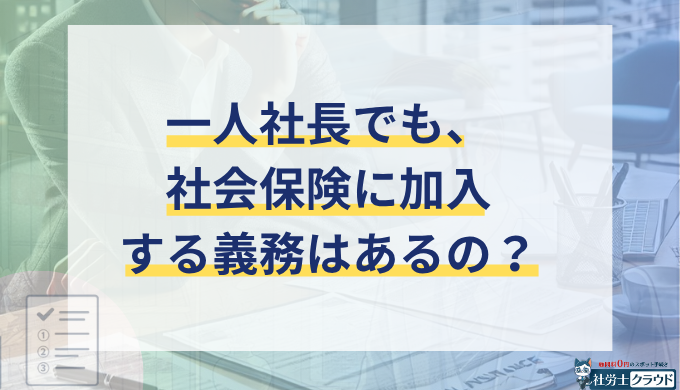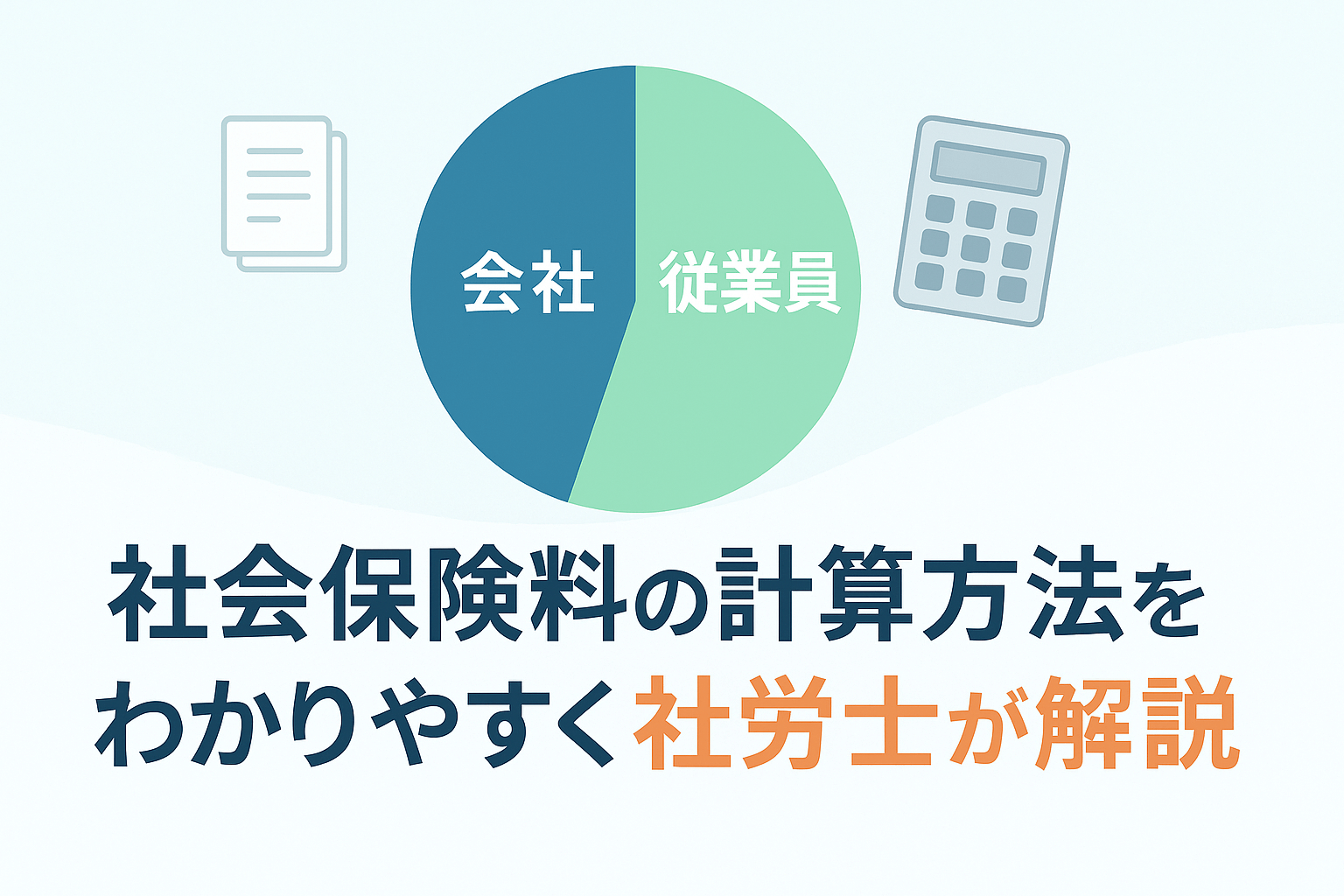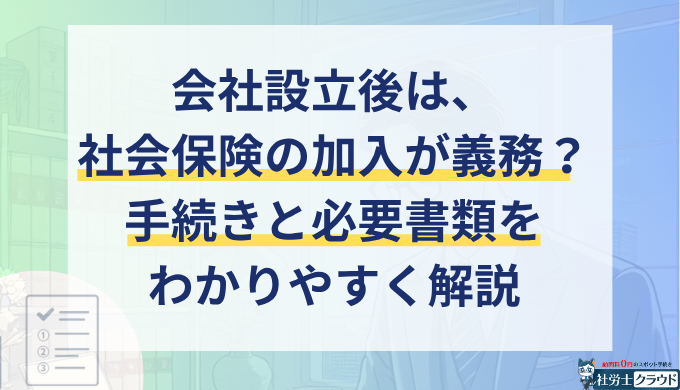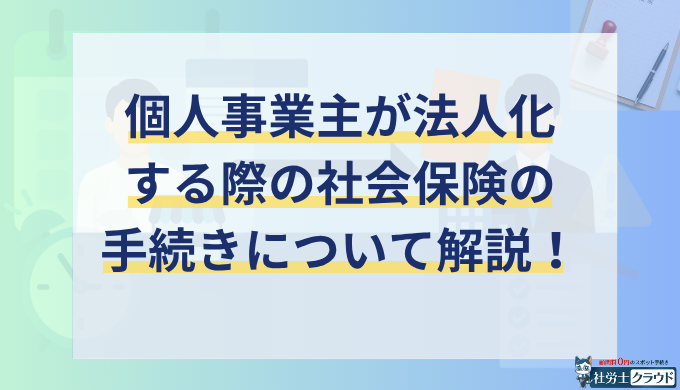会社(法人)を設立し、従業員を雇わない「一人社長」であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は法律で義務付けられています。
日本では、法人を設立して役員報酬を受け取る場合、必ず社会保険に加入しなければなりません。これは、従業員が一人もいない「ひとり社長」の会社でも例外ではありません。
本記事では、法人化して一人社長になった場合に、いつ・どんな手順で・どのような書類を提出する必要があるのかをわかりやすく解説します。
さらに、社会保険に加入しなかった場合に発生する罰則やリスクについても紹介し、会社設立直後にやるべきことを具体的に整理します。
会社設立後の最初の重要手続きとして、この記事を参考にスムーズに社会保険の加入を完了させましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
YouTubeでも会社設立時の社会保険の手続きについて詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
会社(法人)を設立した場合、役員報酬が発生していれば、従業員を雇用しているかどうかに関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は法律上の義務です。
社長一人だけの会社であっても、会社や社長の判断で加入の有無を選ぶことはできません。
「従業員がいないから不要」といった誤解もありますが、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・一般社団法人など、すべての法人は、その規模を問わず「強制適用事業所」に該当します(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条)。
強制適用事業所とは、法律により自動的に社会保険の対象となる事業所のことをいいます。
個人事業主の場合は、業種によっては「従業員が常時5人未満なら任意加入」とされるケースもありますが、法人にはこの例外はありません。したがって、個人事業主から法人化する場合、この点が最も大きな違いになります。
役員報酬を受け取る社長自身は、会社に雇われる立場として「被用者(第2号被保険者)」となり、それまで加入していた国民健康保険や前職の健康保険などから、健康保険・厚生年金への切り替え手続きを行う必要があります。
会社を設立して従業員がいない場合は労働保険への加入は必要なし
社会保険(健康保険・厚生年金)とは異なり、労働保険(雇用保険・労災保険)については、従業員がいない一人社長の会社に加入義務はありません。
これは、労働保険が会社に雇用されて働く「労働者」を保護するための制度であるためです。社長(代表取締役)は、法律上「労働者」ではなく、労働者を雇う側である「使用者」の立場にあたるため、制度の対象外となります。
ただし、将来的にパートやアルバイトを含め、従業員を1人でも雇用した時点では、労働保険の加入義務が発生するため注意が必要です。
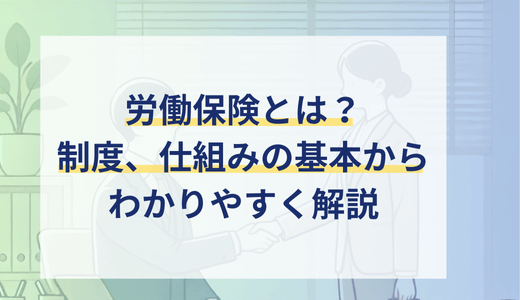 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
社長自身も業務中や通勤中にケガをするリスクはあります。こうしたリスクに備えたい場合は、任意で「労災保険の特別加入制度(中小事業主等)」を利用することができます。
この制度を利用すれば、業務中のケガだけでなく、通勤途中の事故などによる「通勤災害」も補償の対象となります。
特定の業種に限らず、建設業や製造業はもちろん、デスクワーク中心の業種でも加入可能です。加入手続きは、地域の「労働保険事務組合」を通じて行うのが一般的です。
一人社長でも、法人である限り、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則として義務です。
ここで扱う「例外」は、義務を免除する話ではありません。社長個人に被保険者の資格が発生しない(資格が立たない)ため、結果として加入の対象外になる状態を指します。会社が強制適用事業所である事実は変わりません。
資格が立たない代表例は次の二つです。
- 役員報酬が0円のとき
- 勤務の実態が非常勤で、経常的な労務提供がほとんどなく、かつ報酬が著しく低いとき
判断材料は、肩書ではなく実際の報酬と勤務の実態です。形式だけで線引きはできません。登記や議事録、報酬の支払記録、勤務日・業務内容の記録など、客観的に説明できる資料を整えておくと判断がぶれません。
該当しそうかどうかは、設立前後の早い段階で必ず確認してください。後からの修正は手間も負担も大きくなります。
役員報酬がなし(0円)の場合
役員報酬が0円の社長は、社会保険の被保険者にはなりません。
社会保険の加入要件は、法人から労務の対価として報酬を受け取っていることにあります。報酬が0円のままでは、保険料を算定する基礎となる「標準報酬月額」を決められないため、加入資格が成立しない仕組みです。
この状態では、社長個人は引き続き国民健康保険と国民年金に加入することになります。短期的には、会社負担の社会保険料を抑えられるというメリットがあります。
しかし、同時にいくつかのデメリットも生じます。
たとえば、老齢厚生年金が積み上がらないため将来の受給額が減るほか、役員報酬を会社の経費(損金)として処理できないため、法人税の面で不利になります。
さらに、融資などの資金調達の場面でも、報酬ゼロの状態は「経営の継続性に疑問あり」と判断され、マイナス評価につながるおそれがあります。
経営の信頼性や税務上のバランスを考えると、業務実態に見合った適正な報酬を設定し、社会保険に加入しておくことが望ましいといえます。
非常勤の役員で、報酬が著しく低い場合
もう一つの例外は、勤務実態が「非常勤」であり、経常的な労務の提供がほとんどない場合です。
ここで重要なのは、肩書や名刺上の「非常勤」という言葉ではなく、実際の勤務内容と関与度です。
たとえば「月に一度の取締役会に出席するだけで、日常の経営や業務指示に関与していない」といったケースでは、社会保険の被保険者要件を満たさないと判断される可能性があります。
一方で、一人社長として日々の経営・営業・管理に関わっている場合は、形式上「非常勤」とされていても、実態は常勤とみなされるため、社会保険への加入が必要です。
結論として、肩書だけで「非常勤」と称して加入を避けることは現実的ではありません。会社の実態に合った体制を整え、報酬の設定と社会保険の取り扱いを一致させることが、将来の遡及徴収やトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
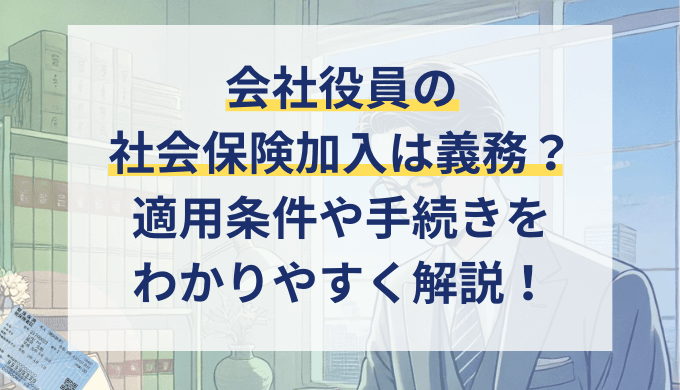 会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
会社役員の社会保険加入は義務?条件は?役員報酬ゼロ場合も解説
社会保険への加入手続きは、会社設立(登記)が完了したらすぐに行います。期限は原則として設立日から5日以内と非常に短いため、迅速な対応が求められます。
手続きは、会社の所在地を管轄する「年金事務所」の窓口に持参するほか、郵送や、政府の電子申請システム「e-Gov」も利用可能です。
社会保険の加入に必要な書類と提出先、提出期限などは、以下のとおりです。
基本となるのは「新規適用届」と「被保険者資格取得届」の2点、扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」もあわせた3点セットになります。
| 書類名 | 目的 | 主な添付書類(例) |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社(事業所)を社会保険に登録する | ・法人の登記事項証明書(原本・90日以内) ・法人番号指定通知書(コピー) |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 社長個人を被保険者として登録する | (特になし) |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 扶養家族を登録する(該当者のみ) | ・住民票(続柄確認用) ・課税(非課税)証明書(収入確認用)など |
詳しくは以下で解説していきます。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、設立した会社(事業所)として、初めて社会保険の適用を受けるために提出する、最も基本となる書類です。
この届出によって、会社が社会保険の対象となる「適用事業所」として正式に登録されます。
届出書には、事業所の名称、所在地、法人番号、設立日(登記日)など、会社の基本情報を記入します。ここで大切なのは、法人の登記事項証明書(登記簿)の表記と、フリガナや住所も含めて完全に一致させることです。
提出時には、「法人の登記事項証明書(原本・発行から90日以内)」と「法人番号指定通知書のコピー」を添付します。
この届出は、次の「被保険者資格取得届」とあわせて、同時に提出するのが一般的です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」は、社長本人を社会保険の「被保険者」として登録するための、非常に重要な書類です。
届出書には、氏名、生年月日、住所などの基本情報のほか、「基礎年金番号」を正確に記入します。
この番号は、過去の国民年金や前職の厚生年金の記録と、新しい会社の記録を正しく紐付けるために使われます。必ず年金手帳や基礎年金番号通知書などで確認しましょう。
また、毎月の社会保険料を算定する基礎となる「役員報酬の額」も、この届出で申告します。
届出のタイミングは、会社の「新規適用届」と同時に行うのが一般的です。同時提出することで手続きがスムーズに進み、健康保険証の発行も早まります。
健康保険被扶養者(異動)届(家族を扶養に入れる場合)
「健康保険被扶養者(異動)届」は、社長に扶養する家族(配偶者・子ども・両親など)がいる場合に提出する書類です。
この届出を提出して認定されると、家族も健康保険の対象となり、扶養家族用の健康保険証が発行されます。
扶養に入れるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は収入要件で、原則として家族の年間収入が130万円未満であることが求められます(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)。
また、同居していること、もしくは別居でも仕送りの実態があることも認定の基準になります。
手続きの際は、続柄を確認するための住民票や、収入を証明する課税(非課税)証明書などの提出が必要です。
添付書類の内容は年金事務所によって異なるため、提出前に管轄の窓口へ確認しておくと安心です。
手続き完了後にやるべきこと(旧保険の脱退・納付)
社会保険の加入手続きが完了し、新しい健康保険証が届いたら、忘れずに行うべきことが2つあります。
それは「これまで加入していた健康保険の脱退」と「社会保険料の納付準備」です。
個人事業主時代に国民健康保険に加入していた場合は、お住まいの市区町村で「国民健康保険の資格喪失手続き」を行います。
新しい健康保険証を持参すると、スムーズに処理できます。
また、会社員から独立し、以前の健康保険を「任意継続」で継続していた場合は、加入していた健康保険組合へ連絡し、「任意継続被保険者資格喪失届」を提出しましょう。
なお、年金については個人での手続きは不要です。提出済みの「被保険者資格取得届」により、国民年金から厚生年金へ自動的に切り替わります。
手続き後しばらくすると、年金事務所から「標準報酬決定通知書」と「納付書」が届きます。
納付期限を確認のうえ、忘れずに支払いましょう。
たとえば、5月1日付で加入した場合は、5月分の保険料の納付書が6月20日頃に届き、納付期限は6月末日です。
郵便トラブルなどで納付書が届かなくても、納付義務は消えません。
期限が近づいても届かない場合は、必ず管轄の年金事務所へ確認してください。未納が続くと、延滞金が発生する可能性があります。
毎月の支払い忘れを防ぐためには、「口座振替」を利用するのが便利です。
「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を作成し、金融機関の窓口に提出することで自動引き落としができます。
利用できる金融機関や口座名義には制限があるため、事前に日本年金機構のウェブサイトで確認しておきましょう。
社会保険への加入は法律上の義務です。「一人社長だから発覚しない」と考えて先延ばしにすると、資金面と信用面の両方で大きな不利益を招きます。
年金事務所は法人登記や税情報と連携して未加入事業所を把握しており、「知らなかった」は理由になりません。未加入は実質的に高金利の負債”を抱えるのと同じ状態です。
リスク1:年金事務所から加入指導・立入検査が来る
未加入が判明すると、まず加入勧奨状が届きます。応じないまま放置すると、電話・訪問での指導、最終段階では立入検査へ進みます。検査では登記事項、給与台帳、役員報酬の支給実績などをもとに、加入義務と遡及期間が確認されます。
リスク2:最大2年分の保険料を遡って「強制徴収」される
加入義務ありと判断されると、時効(2年)の範囲で過去分の保険料(会社負担+個人負担)を納付します。支払いは一括または分割ですが、役員報酬の水準によっては数百万円規模のキャッシュアウトとなり、資金繰りを直撃します。
リスク3:「延滞金」が発生する
遡及分には本来の納付期限に応じた延滞金が上乗せされます。利率は高く、最大で年14.6%(利率は変動)に達する場合があります。対応が遅れるほど負担がふくらむため、通知受領時点で速やかに手続きを進めることが重要です。
リスク4:助成金・補助金が申請できない
多くの制度が「社会保険の適正加入・未納なし」を前提にしています。未加入だとキャリアアップ助成金などの活用機会を失い、さらに金融機関の融資審査でもコンプライアンス面でマイナス評価を受けます。
リスク5:ハローワークに求人を出せない(将来の採用時)
雇用保険の適用には社会保険の整備が前提です。未加入だと求人不受理となり、主要な募集チャネルが使えません。採用の遅れは、事業拡大の速度やサービス品質にも響きます。
未加入は時間が経つほど負担が増えます。早期の適正加入が最小コストの解決策です。具体的な対処や再発防止の流れは、こちらの解説も参考にしてください。
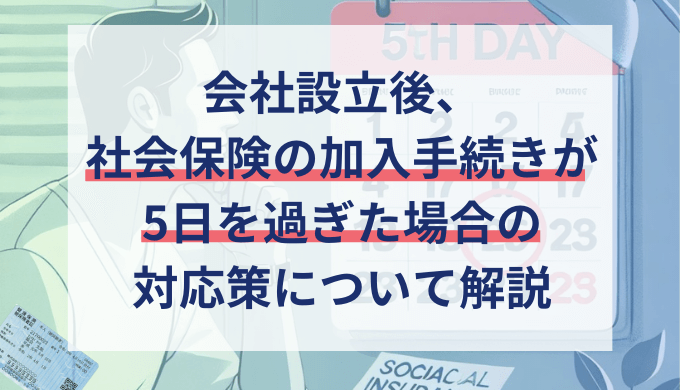 会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
社会保険に加入すると、毎月の保険料負担が発生します。しかし、その負担を上回るほどの「保障の手厚さ」が、加入する最大のメリットといえます。
特に、個人事業主時代に加入していた「国民健康保険(国保)+国民年金」と比較すると、その違いは明らかです。主なメリットは以下の4点です。
◯病気やケガで働けない時も「傷病手当金」がもらえる
健康保険の制度により、連続3日間の休み(待期期間)を経て、4日目から最長1年6ヶ月間、給与(標準報酬月額)のおよそ3分の2が支給されます。国民健康保険には、このような所得補償制度はありません。
◯家族を「扶養」に入れられる(家族分の保険料が不要に)
要件を満たす家族は「被扶養者」として健康保険に加入でき、追加の保険料はかかりません。国民健康保険のように家族の人数に応じて保険料が増える仕組みではないため、世帯単位の負担を抑えやすくなります。
◯将来の年金受給額が(国民年金のみより)増える
国民年金(基礎年金)に加えて、厚生年金に加入することで「老齢厚生年金」が終身で上乗せされます。現役時代に納めた厚生年金保険料(報酬に比例)が将来の受給額に反映される点が大きな違いです。
◯障害・死亡時の保障が手厚くなる
厚生年金に加入することで、「障害厚生年金」(1~3級)や一時金の「障害手当金」、そして「遺族厚生年金」の対象となります。これにより、国民年金のみの場合に比べて保障範囲が広がり、“受給ゼロ”となる空白期間のリスクを減らすことができます。
社会保険料は、社長が受け取る役員報酬を「標準報酬月額」という区分にあてはめ、その金額に健康保険料率と厚生年金保険料率を掛けて計算します。
ここでは、令和7年度(2025年3月分保険料~)、東京都、社長の年齢が40歳未満(介護保険料なし)という前提で試算します。
この場合の保険料率は、健康保険が9.91%、厚生年金が18.3%です。
参考: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和7年度保険料率のお知らせ」
一人社長の場合、保険料は会社と個人で半分ずつ負担しますが、会社負担分も自分の事業から支払うことになります。
そのため、実際の負担感を知るには、「会社負担分+個人負担分=労使合計額」で把握することが大切です。
なお、標準報酬月額には下限があり、役員報酬が8万8千円未満の場合でも、8万8千円として計算します。
【役員報酬8万円の場合】(標準報酬月額:88,000円 ※下限適用)
- 健康保険料(労使合計):88,000円 × 9.91% = 8,720.8円(約8,721円)
- 厚生年金保険料(労使合計):88,000円 × 18.3% = 16,104円
- 合計(月額):約24,825円 (内訳:会社 約12,413円/個人 約12,412円)
【役員報酬20万円の場合】(標準報酬月額:200,000円)
- 健康保険料(労使合計):19,820円
- 厚生年金保険料(労使合計):36,600円
- 合計(月額):56,420円 (内訳:会社 28,210円/個人 28,210円)
【役員報酬30万円の場合】(標準報酬月額:300,000円)
- 健康保険料(労使合計):29,730円
- 厚生年金保険料(労使合計):54,900円
- 合計(月額):84,630円 (内訳:会社 42,315円/個人 42,315円)
役員報酬を高く設定すれば、将来受け取る年金額は増えますが、毎月の会社からの支出(キャッシュアウト)も増加します。逆に報酬を低く抑えれば負担は軽くなりますが、将来の保障は手薄になります。
会社の資金繰りと社長自身のライフプラン、両方のバランスを見ながら、無理のない役員報酬額を設定しましょう。
ここでは、一人社長の社会保険に関して、特に多く寄せられる疑問点について、Q&A形式で回答します。
2社経営している場合、社会保険はどうなりますか?
複数の会社(法人)を経営し、それぞれの会社から役員報酬を受け取っている場合は、原則として両方の会社で社会保険の被保険者となります。 これは、社会保険の資格が「報酬を得ている事業所ごと」に発生する仕組みだからです。
この場合、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、保険料の納付や手続きの窓口となる「主たる事業所」を自分で選択します。
保険料は、両方の会社の報酬額を合算して1つの標準報酬月額が決まり、それに基づいて保険料総額が計算されます。その総額を、各社の報酬額の割合に応じて按分し、それぞれの会社で労使折半して納付する流れです。
実務上のポイント: 複数の会社で給与計算の締め日や支払日が異なると、社会保険料の計算や納付管理が複雑になりがちです。可能であれば、各社の給与計算ルールを揃えておくと、運用がスムーズになります。
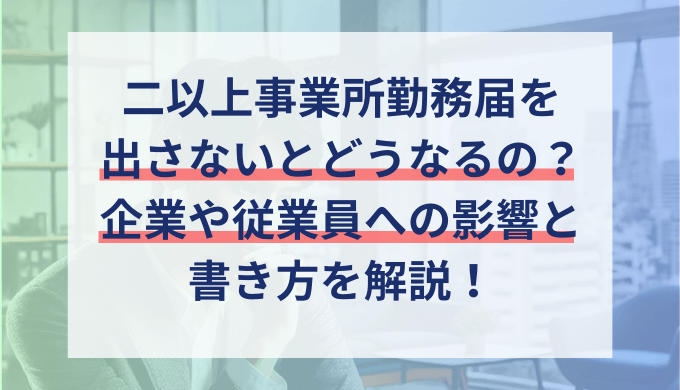 二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説
二以上事業所勤務届を出さないとどうなる?出し忘れた時の対策や書き方を解説
合同会社の場合も社会保険への加入は必須ですか?
合同会社も社会保険への加入は必須です。会社形態(株式会社か合同会社か)に関係なく、「法人」であれば強制適用事業所にあたります。
社会保険の加入義務の基準は「法人かどうか」です。合同会社の代表社員(社長)が会社から報酬を受けているなら、株式会社の代表取締役と同じ扱いで加入手続きが必要になります。
手続きの流れも株式会社と同じです。設立後(登記日)から原則5日以内に、管轄の年金事務所へ「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を提出します。添付書類も同様に「登記事項証明書(原本・90日以内)」と「法人番号指定通知書」のコピーが必要です。
これは、合同会社の代表社員が役員報酬を受け取っている場合の話です。役員報酬を0円にしている場合は資格が発生しないため、報酬設計と加入要否の整合を必ず確認してください。
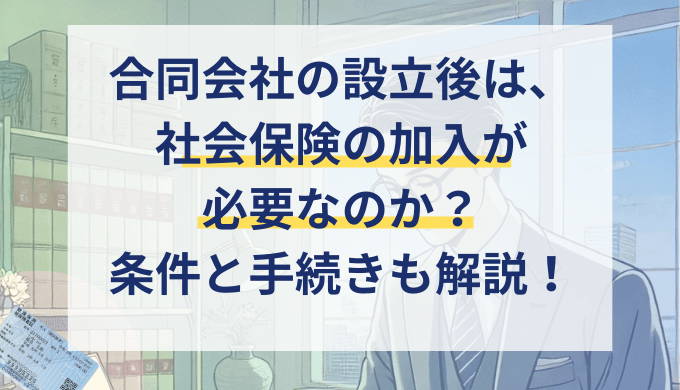 合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
一人社長であっても、法人を設立した時点で、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。「役員報酬ゼロ」のような、そもそも加入資格が発生しない(“資格が立たない”)ごく一部の例外を除き、未加入のまま事業を続けることは違法な状態です。
未加入のまま放置すると、最大2年分の保険料遡及徴収や高額な延滞金といった、事業の存続に関わる重大なリスクがあります。
会社設立後は、事業を軌道に乗せることに集中するためにも、社会保険の手続きは速やかに(原則5日以内)済ませておくことが大切です。
手続き自体も複雑ですが、社会保険料や税金のバランスを考えた「役員報酬」の設定はさらに専門的な知識が求められます。
もし、「手続きが不安」「最適な報酬額がわからない」と感じているなら、社労士のような専門家に相談することをおすすめします。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。
▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由
1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)
2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)
3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)
社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。
まずは、ご相談ください。
「設立時の手続き、具体的に何から始めればいい?」 「期限(5日以内)が迫っているけど間に合う?」
といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。複雑な手続きは専門家に任せて、安心して事業のスタート準備に集中しませんか。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|