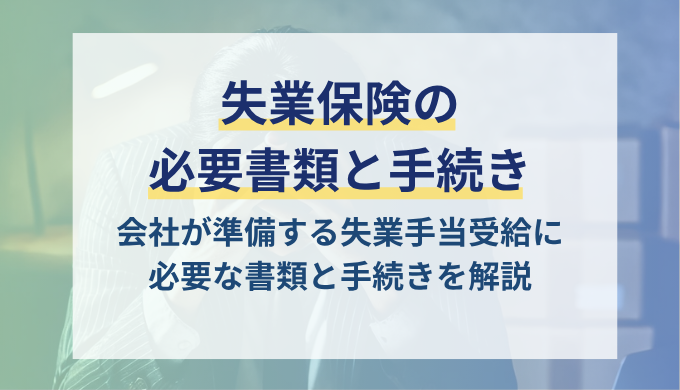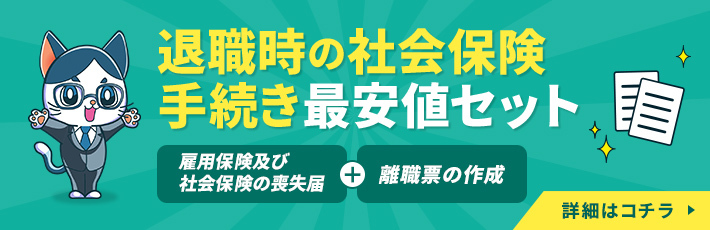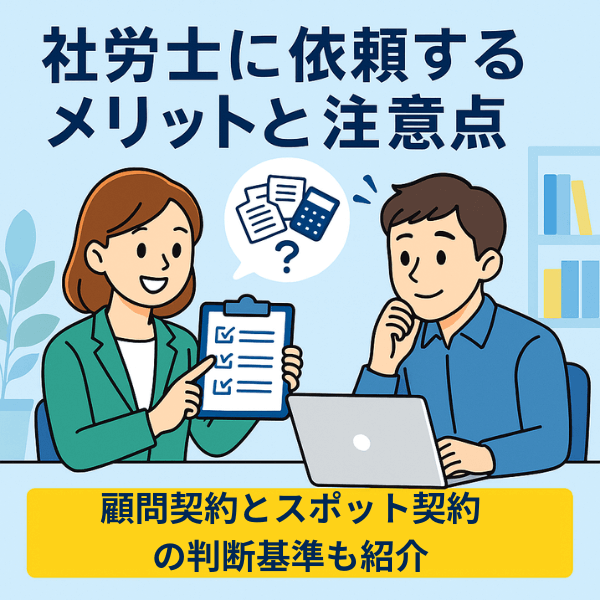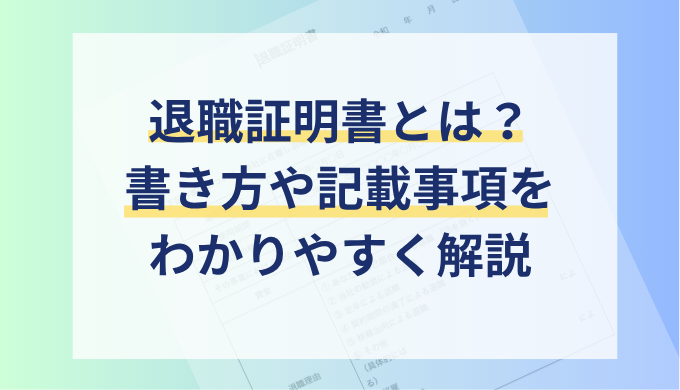失業保険(失業手当)を受給するには、会社側で「雇用保険資格喪失届」や「離職証明書(離職票)」など、複数の書類を期限内に提出する必要があります。この手続きを怠ると、退職者の失業保険の申請が遅れたり、給付開始が後ろ倒しになったりする恐れがあり、最悪の場合、会社への信用問題にもつながりかねません。
さらに、退職に伴って発生するのは失業保険関連の書類だけではありません。
健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き(5日以内)、住民税の徴収方法の変更届、源泉徴収票の発行など、税務・社会保険を含む幅広い手続きが複雑に絡み合います。
これらを混同せず、的確に処理するには、正確な知識と体系的な流れの理解が不可欠です。
本記事では、退職時に会社が準備すべき失業保険の必要書類と手続きのステップを中心に、注意すべき期限・ポイント・実務上のトラブル回避策まで、社労士監修のもとわかりやすく解説します。
この記事を最後まで読むことで、退職時の手続き全体像を明確に把握し、実務での自信と安心感を持って対応できるようになります。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業員が退職し、失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)の受給を希望する場合、会社はハローワークで所定の手続きを行う必要があります 。会社側の対応が遅れると、退職者の失業手当の受給開始が遅れるなど、その後の生活に直接影響を及ぼすため、迅速かつ正確な対応が求められます。
会社が行う失業保険関連の手続きは、主に以下の3つのステップで進められます。ここでは、各ステップの役割と、手続きに必要な書類を早見表形式で確認しましょう 。
【早見表】会社が行う失業保険手続きの3ステップ
| ステップ | 会社が行うこと | 役割と目的 |
| ステップ① | 「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出する | 従業員が雇用保険の加入資格を失ったことを届け出るための手続き 。 |
| ステップ② | 「雇用保険被保険者離職証明書」を作成しハローワークへ提出する | 退職者が失業手当を申請するための「離職票」をハローワークから発行してもらうための手続き 。 |
| ステップ③ | ハローワークから発行された「離職票」を退職者本人へ交付する | 退職者がハローワークで手続きするために必要な重要書類を渡すことが目的 。 |
ステップ①:雇用保険被保険者資格喪失届を提出する(雇用保険の資格喪失手続き)
会社は従業員が雇用保険の被保険者でなくなったことを届け出るために、「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません 。これは、退職者が雇用保険から抜けるための基本的な手続きであり、後続のすべての手続きの起点となります 。
この「雇用保険被保険者資格喪失届」は、従業員が退職した日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出することが法律で定められています 。
この手続きを完了しなければ、退職者が失業手当の申請に必要とする離職票の発行手続きに進むことができないため、期限内に必ず提出してください。
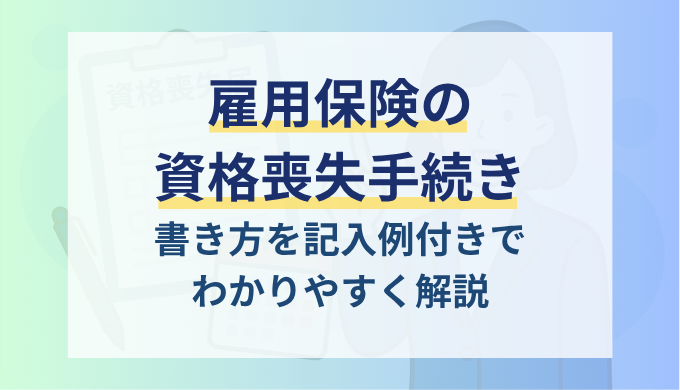 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
ステップ②:離職証明書を作成しハローワークへ提出する(離職票の発行手続き)
退職者が失業手当を申請するために不可欠な「離職票」をハローワークから発行してもらうため、会社は「雇用保険被保険者離職証明書」(通称:離職証明書)を作成し、ハローワークへ提出します 。
この離職証明書が、ハローワークで離職票に変わる「もと」になる書類です。この証明書には、退職前6ヶ月間の賃金支払状況や離職理由などを会社が記入します 。ここに記載された内容は、退職者が受け取る失業手当の給付日数や金額を直接左右するため、きわめて重要です 。
会社は作成した離職証明書の内容を退職者本人に確認してもらい、記名押印または署名をもらった上で、賃金台帳や出勤簿といった添付書類とともに提出しなければなりません 。
実務上は、ステップ①の「雇用保険被保険者資格喪失届」とこの「雇用保険被保険者離職証明書」を、同じく退職日の翌日から10日以内に、同時に提出するのが一般的です。
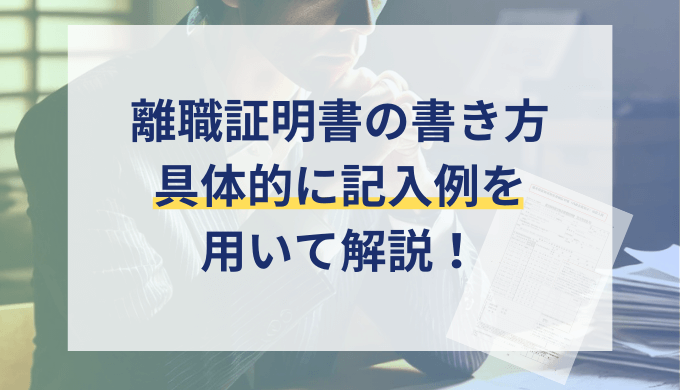 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
ステップ③:発行された離職票を退職者へ交付する
ハローワークに「雇用保険被保険者離職証明書」を提出し、手続きが完了すると、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類の書類が会社宛に交付されます 。会社は、この発行された離職票を速やかに退職者本人へ渡さなければなりません 。
この離職票は、退職者自身がハローワークで失業手当の受給手続きを行う際に必ず必要となる、非常に重要な書類です 。交付が遅れると、退職者の失業手当の受給開始も遅れてしまうため、会社は責任をもって迅速に交付する義務があります。
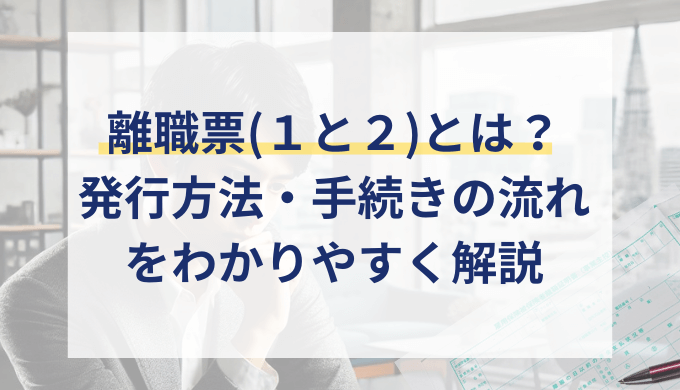 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
【補足】退職者が離職票を希望しない場合は資格喪失確認通知書を交付する
退職者が次の就職先が既に決まっているなどの理由で失業手当の受給を希望せず、「離職票は不要」と意思表示した場合は、手続きが一部異なります 。この場合、会社はステップ②の「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークへ提出する必要はありません 。
離職証明書を提出しない場合、ハローワークでの資格喪失手続きが完了すると、会社には「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」という書類が交付されます 。
会社はこの「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を退職者へ渡すことになります。
ただし、一点注意が必要です。
退職者が59歳以上の場合は、本人が離職票を不要と希望した場合でも、会社は離職票を交付する義務があります 。この点は法律で定められているため、年齢の確認を怠らないようにしてください。
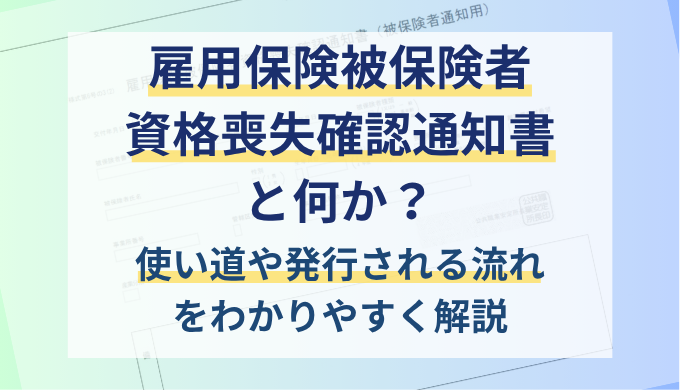 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
従業員の退職時には、失業保険の手続きに加えて、会社には社会保険や税金に関する多くの法定業務が発生します。特に「社会保険の資格喪失手続き」「住民税の徴収方法の変更」「源泉徴収票の発行」は、対応を誤ると行政からの指摘や退職者とのトラブルに繋がりかねない重要な手続きです。
まず、従業員が退職する際に会社側が行うべき手続きの全体像と時間軸を、以下のタイムラインでご確認ください。このスケジュール全体を踏まえた上で、特に重要となる退職日以降の主要な手続き3つを、この後詳しく解説します。
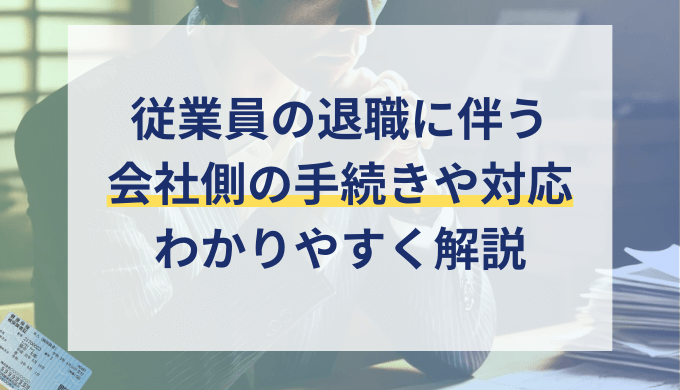 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
それでは、上記タイムラインの中でも特に重要な「社会保険の資格喪失手続き」「住民税の手続き」「源泉徴収票の発行」について、それぞれ見ていきましょう。
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
従業員が退職した場合、雇用保険の手続きとは別に、健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する手続きが必須です。この手続きは、会社と従業員が負担する社会保険料の徴収を正しく停止し、退職者が国民健康保険など次の医療保険制度へスムーズに移行できるようにするために行われます 。
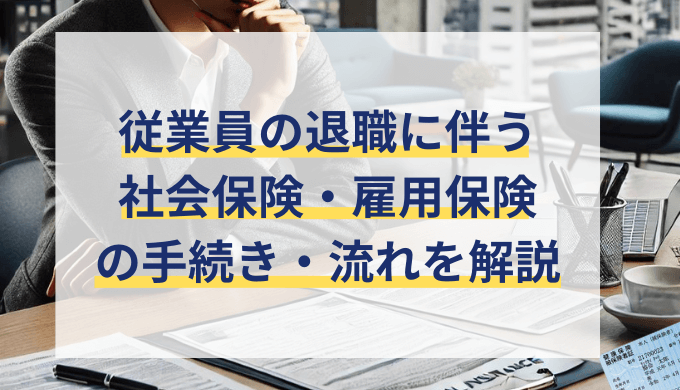 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
会社は、退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センターへ提出しなければなりません 。雇用保険の手続き(提出先:ハローワーク、期限:10日以内)とは提出先も期限も異なるため、混同しないように注意が必要です 。
この手続きで特に重要なのが、退職する従業員本人およびその被扶養者全員分の
健康保険証の回収です 。資格喪失後に誤って保険証が使用されると「無資格受診」となり、後日、保険者から会社へ医療費の返還請求が行われるなど、予期せぬトラブルの原因となるため、必ず退職日までに回収してください 。
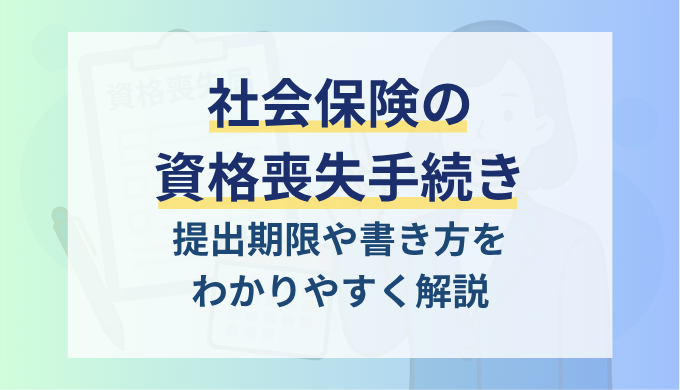 社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
国民健康保険へ切り替える場合には、社会保険(健康保険)資格喪失証明書が必要になることがあります。
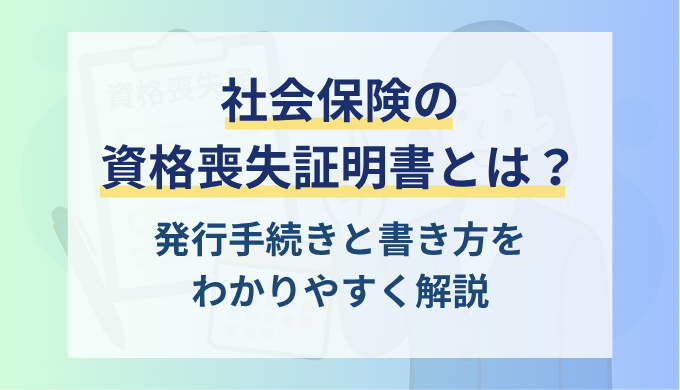 社会保険(健康保険)資格喪失証明書とは?発行手続きと書き方を記入例付きで解説
社会保険(健康保険)資格喪失証明書とは?発行手続きと書き方を記入例付きで解説
住民税の手続き(特別徴収切替/一括徴収)
従業員の住民税を給与から天引き(特別徴収)している場合、退職に伴いその徴収方法を変更する手続きが必要です。会社は、退職月以降の未徴収分を「一括徴収」でまとめて天引きするか、退職者自身が納付する「普通徴収」に切り替えるかの対応をとらなければなりません。
どちらの対応になるかは、原則として退職した時期によって決まります。
| ■1月1日~5月31日に退職する場合 原則として、その年の5月までの住民税の残額を、退職者の最後の給与や退職金から一括で徴収して納付する義務があります。 ■6月1日~12月31日に退職する場合 原則として、退職者が自身で納付する「普通徴収」へ切り替えます。ただし、退職者本人から申し出があれば、残りの税額を最後の給与などから一括徴収することも可能です。 |
いずれの場合でも、会社は従業員が退職した翌月の10日までに、市区町村へ「給与所得者異動届出書」を必ず提出する必要があります。この届出書で、一括徴収したか、あるいは普通徴収に切り替えたかを報告します。
▼ 実務上のポイント
最後の給与の支払額が、一括徴収すべき住民税の残額よりも少ないケースがあります。その場合は一括徴収ができないため、早めに税額を確認し、対応方法を従業員へ説明しておくことがトラブル防止の観点から重要です。
源泉徴収票の発行
会社は、退職した従業員に対し、その年に支払った給与総額や源泉徴収した所得税額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を、退職後1ヶ月以内を目安に発行する義務があります。
この源泉徴収票は、退職者が転職先で年末調整を行う場合や、自身で確定申告をする際に必ず必要となる重要書類です 。
▼ 実務上のポイント
◯対象者
この発行義務は、正社員だけでなく、アルバイト・パートタイマーなど、給与を支払ったすべての従業員に適用されます。
◯退職金がある場合
給与とは別に退職金を支払った場合は、別途「退職所得の源泉徴収票」の発行も必要になるため注意が必要です 。
◯交付方法
書面で作成し、郵送または手渡しで交付するのが一般的です。なお、退職者本人の承諾を得れば、電子データでの交付(電子交付)も認められています。
失業保険の手続きは、多くの企業担当者にとって頻繁に発生する業務ではないため、様々な疑問が生じやすいものです。
特に「離職票の発行が遅れた場合の罰則は?」「退職者が離職票は不要と言った場合は?」「不正受掛の防止策は?」といった実務的な質問が多く寄せられます。
ここでは、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
離職票の発行が遅れたら罰則はある?
正当な理由なく会社が手続きを怠り、離職票の発行が大幅に遅れた場合、法律上の罰則が科される可能性があります。
職業安定法には、離職票の交付を不当に遅らせるなどの行為に対する罰則規定が設けられています 。実務上、少し遅れただけで即座に罰則が適用されることは稀で、まずはハローワークからの催促や指導が入るのが一般的です 。
しかし、最も大きなリスクは罰則そのものよりも、退職者の生活に直接的な影響を与え、深刻な労使トラブルに発展することです。会社の信頼を損なわないためにも、手続きは迅速に進めなければなりません。
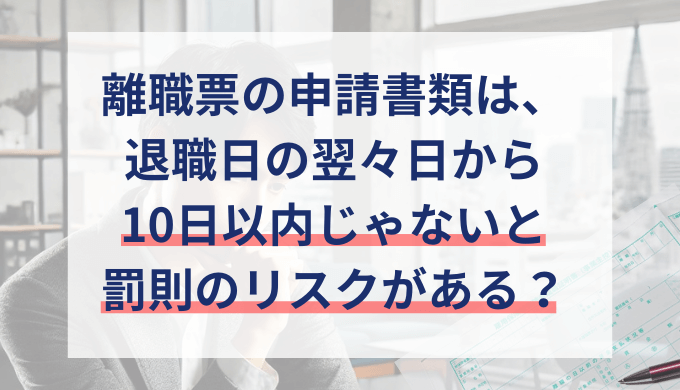 離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
退職者が「離職票は不要」と言った場合どうする?
退職者が次の就職先が決まっているなどの理由で「離職票は不要」と意思表示した場合、会社の対応は退職者の年齢によって異なります。
◯退職者が59歳未満の場合
本人が明確に不要の意思を示した場合、会社が離職証明書をハローワークへ提出する法的な義務はありません 。ただし、後から「やはり必要になった」と言われるケースもあるため、本人の意思を「離職票不要申出書」などの書面で確認しておくことが、後のトラブル防止に繋がります 。
◯退職者が59歳以上の場合
本人の希望にかかわらず、会社は離職票を発行する義務があります 。これは、高年齢求職者給付金の制度に関連するためです。年齢を確認せず安易に手続きを省略すると法令違反となるため、必ず確認してください。
不正受給を防止するため会社ができることは?
会社が不正受給を防止するために最も重要な役割は、ハローワークへ提出する「雇用保険被保険者離職証明書」に、事実に基づいた正確な情報を記載し、提出することです。
ハローワークは、この離職証明書に記載された情報をもとに受給資格の有無や給付額を判断します 。したがって、会社による正確な情報提供が、制度の適正な運用の大前提となります。
意図的に事実と異なる内容を記載すると、会社も不正受給に加担したと見なされ、厳しい指導の対象となる可能性があるため、絶対に行わないでください。
具体的には、以下の点に注意して離職証明書を作成する必要があります。
◯離職理由を正確に記載する
「自己都合退職」であるにもかかわらず、退職者に頼まれて「会社都合」と記載するなどの虚偽の申告は、不正受給に繋がる典型例です。離職理由の判断に迷う場合は、自己判断せずハローワークに確認してください。
◯賃金額を正しく記載する
失業手当の額は、離職前6ヶ月の賃金に基づいて計算されます 。賃金台帳などに基づき、残業代や各種手当も含めて正確な金額を記載しなければなりません。
◯退職日を正確に記載する
在籍期間を偽って記載してはいけません。出勤簿や労働者名簿と相違がないよう、事実を正確に記載してください。
会社の役割は、退職者を監視することではなく、行政に対して事実を正確に報告する義務を果たすことです。実態を正しく届け出ることが、結果的に退職者と会社の双方を法的に保護することに繋がります。
失業手当のもらえる金額は?
会社が退職者の失業手当の正確な金額を算出・保証することはできませんが、人事担当者として計算の基本的な仕組みを説明することは可能です。
失業手当の金額は、主に以下のステップで決定されます。
【失業手当の金額が決まる流れ】
ステップ①:賃金日額の算出
離職前6か月間に支払われた賃金(賞与などを除く)を180で割って、「賃金日額(1日あたりの平均賃金)」を算出します。
例:6か月で150万円の賃金 → 150万円 ÷ 180日 = 8,333円
ステップ②:基本手当日額の決定
賃金日額に対して、年齢・賃金水準に応じた給付率(概ね50~80%)を掛けたものが「基本手当日額」となります。
給付率は賃金が低いほど高く設定されています(逆進的給付率)。
ステップ③:総支給額の計算
この基本手当日額に、「所定給付日数(90日~360日)」を掛けた金額が、受け取れる失業手当の総額です。所定給付日数は、退職理由(自己都合/会社都合)や雇用保険加入期間によって決定されます。
退職者から「自分はいくらもらえるのか?」と質問された場合は、下記のような失業保険のもらえる金額の目安を計算できるシミュレーションツールを案内してあげましょう。
> 失業保険の手当金計算シミュレーション!雇用保険給付金の自動計算ツール
退職者がスムーズに失業手当を受給できるかどうかは、会社による迅速かつ正確な必要書類の準備と手続きが鍵を握ります。特に、退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークへ提出し、発行された「離職票」を速やかに本人へ交付する一連の流れは、最も重要な業務です 。
また、失業保険の手続きと並行して、「健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き(退職日の翌日から5日以内)」や、「住民税の徴収方法の変更」、「源泉徴収票の発行」といった社会保険・税務上の手続きも発生します 。これらはそれぞれ提出先や期限が異なるため、混同せず、漏れなく対応することが不可欠です 。
これらの手続きを正確に行うことは、企業の法的な義務を果たすだけでなく、円満な退職と、退職者のその後の生活をサポートするための会社の重要な責務です。
退職時の手続きは多岐にわたり、専門的な知識も求められます 。もし手続きに不安がある場合や、コア業務に集中するために事務作業の負担を軽減したいとお考えの場合は、社労士などの専門家に相談することも有効な選択肢です 。
スポット申請代行サービスの社労士クラウド
従業員の退職に伴う「雇用保険被保険者資格喪-失届」や「離職証明書」の作成、そして社会保険の資格喪失手続きなどは、提出期限も短く、専門的な知識が求められます。
「離職票の発行手続きが複雑でよくわからない…」 「社会保険や住民税の手続きも漏れなく対応できるか不安…」 「コア業務が忙しく、行政手続きにまで手が回らない…」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスをご検討ください。
当サービスでは、社会保険・労働保険の手続きを、顧問契約不要で、必要な業務だけを1件から社会保険労務士にご依頼いただけます。「従業員1名の退職手続きだけを、すべてお願いしたい」「離職証明書の作成と提出だけを代行してほしい」といった、お客様の状況に合わせたご依頼にも柔軟に対応いたします。
専門家である社労士が、最新の法令に基づいて正確かつ迅速に手続きを代行しますので、お客様は面倒な手続きから解放され、貴重な時間をコア業務に集中させることが可能です。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|