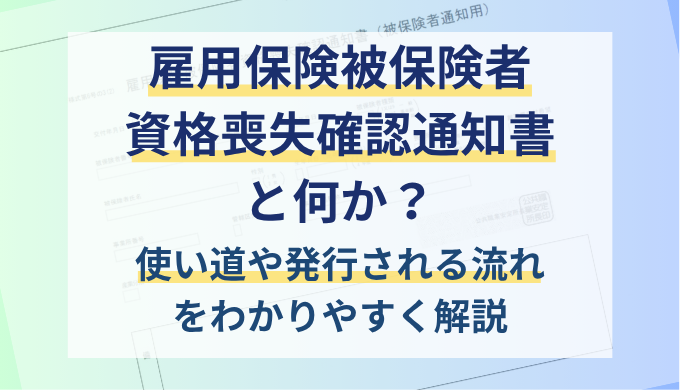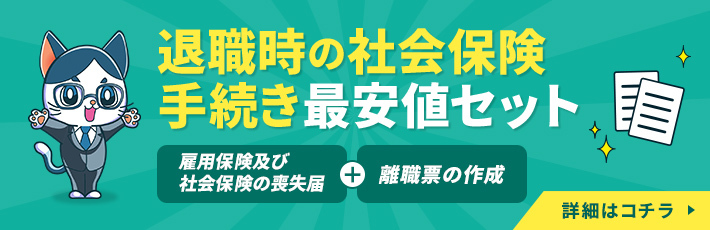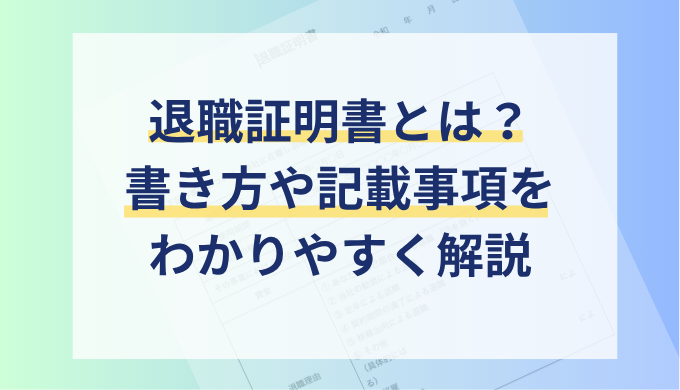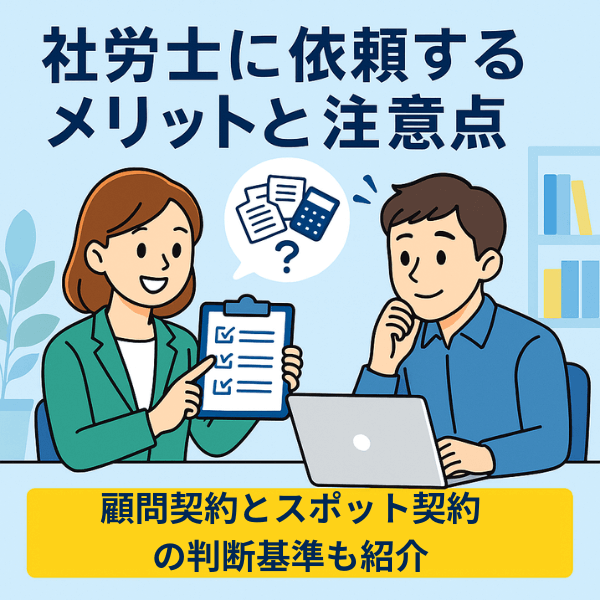雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員が退職した際や、雇用保険の加入要件を満たさない労働契約に変更となった際に、ハローワークが資格喪失を公的に証明し、事業主と従業員本人へ通知するための書類です。
この通知書は、失業手当の申請に必要な「離職票」と混同されやすく、とくに離職票を希望しなかった場合に発行されます。
転職先企業や自治体の国民健康保険窓口などで求められるケースもあるため、会社として正しく管理し、従業員に適切に交付することが重要です。
本記事では、社会保険労務士が「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の役割や使い道、離職票との決定的な違い、発行されるまでの具体的な流れ、そして事業主としての正しい取り扱い方法まで、実務上の注意点を交えて解説します。
退職手続きの抜け漏れを防ぎ、法令遵守と従業員への配慮を両立させるために、ぜひ参考にしてください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、従業員が退職などの理由で雇用保険の加入資格を失った事実を、ハローワークが公的に証明し、事業主と従業員本人へ通知するための書類です。
原則としてこの通知書は、退職者が失業手当(基本手当)の受給を希望せず、「離職票」の発行を求めなかった場合に交付されます 。
逆に、退職者が離職票の発行を希望した場合は、この雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は原則として発行されません。なぜなら、その際に発行される「雇用保険被保険者離職票-1」が、この通知書の役割を兼ねているためです 。
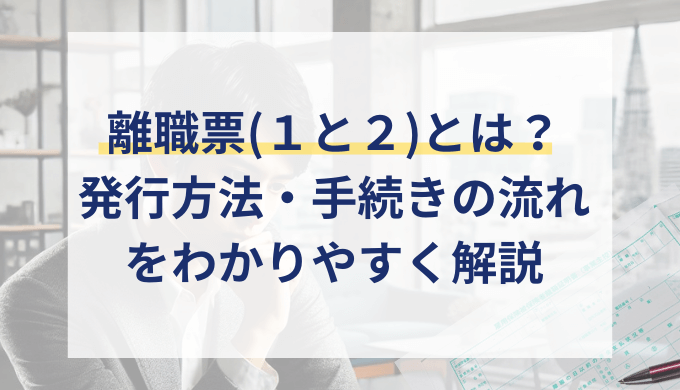 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
この通知書は、会社が提出した「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類がハローワークで正式に受理され、手続きが完了したことの証拠となる役割を持ちます。
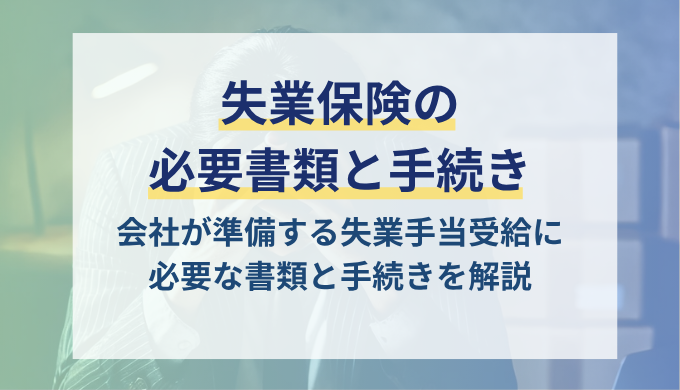 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
事業主にとって、法律に基づいた雇用保険の手続きを適正に履行したことの証明となるため、非常に重要な書類です。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、「被保険者通知用(本人控)」と「事業主控」の2種類で構成されており、どちらも手続き完了後にハローワークから会社へ送付されます。
▼被保険者通知用(本人控)の見本
| 被保険者通知用(本人控) | 会社から退職した従業員本人へ渡すための書類 |
| 事業主控 | 会社が手続きの記録として保管するための書類 |
雇用保険の資格喪失手続きは、会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークへ提出することから始まります。
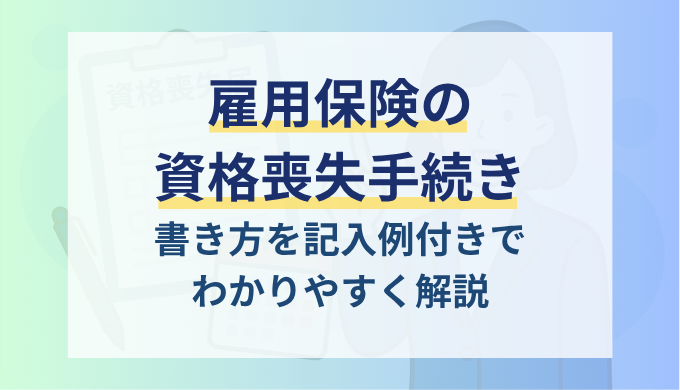 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職者本人が何かの手続きで提出する場面はほとんどありません。
しかし、この通知書は雇用保険の資格喪失を証明する公的な書類のため、以下のような場面で証明資料として役立つ場合があります。
◯転職先で雇用保険被保険者番号を確認するため
転職先での雇用保険加入手続きの際に、「雇用保険被保険者証」を紛失した場合など、本人の被保険者番号を確認する書類として利用できることがあります。
◯市区町村で国民健康保険などに切り替えるため
退職後に国民健康保険へ加入する際など、行政手続きで「退職日を証明する書類」の一つとして認められる場合があります。
また、事業主側にとっても、この通知書は重要な役割を持ちます。従業員の雇用保険手続きを法律に則って正しく実施した証拠として、通知書(事業主控)を社内に保管しておくことが重要です。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員が雇用保険の資格を喪失した場合に、常に発行されるわけではありません。
最も代表的なのは、従業員が離職したものの、失業手当(基本手当)を受給する予定がなく、「離職票」の発行を希望しなかったケースです。
ただし、雇用保険の資格喪失は「離職」だけに限られません。以下のような事情により雇用保険の適用対象から外れた場合、会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出する必要があり、その結果として通知書が交付されることがあります。
【資格喪失届の提出が必要なケース例】
- 従業員が退職した場合(自己都合・会社都合問わず)
- 従業員が死亡した場合
- 従業員が法人の役員に就任し、雇用保険の対象外となった場合
- 労働時間や日数の変更などにより、雇用保険の適用基準を満たさなくなった場合 など
上記の資格喪失ケースのうち、退職者が失業手当の受給を希望するかどうか、つまり「離職票」の発行を希望するかどうかが関係するのは、主に「離職」のケースです。
従業員が離職する際に「すぐに次の転職先が決まっている」「しばらく働くつもりはない」などの理由で離職票の発行を希望しなかった場合、会社はハローワークへその旨を届け出ます。
その結果、ハローワークから離職票の代わりに雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行されるとい
従業員の退職手続きにおいて、事業主や担当者が最も混同しやすいのが、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「離職票」です。この2つの書類は目的も役割も全く異なるため、その違いを正確に理解しておく必要があります。
一言で言えば、退職者がハローワークで失業手当(失業保険)の申請に使えるかどうかが、決定的な違いです。
それぞれの書類の目的や発行されるケースの違いを、以下の表にまとめました。
| 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 | 雇用保険被保険者離職票(離職票) | |
| 目的・役割 | 雇用保険の資格を喪失した事実を通知・証明するため | 退職者がハローワークで失業手当を申請するため |
| 発行される主なケース | 退職者が離職票を希望する場合 | 離職票を希望しない場合 |
| 主な提出先 | 原則なし(本人・会社が保管) | 退職者本人がハローワークへ提出 |
| 書類の構成 | 1枚の通知書(本人用・事業主控) | 離職票-1と離職票-2の2種類 |
このように、退職する従業員が失業手当の受給を考えているかどうかによって、会社がどちらの書類を手配するかが決まります。
失業手当(失業保険)を受け取りたい場合は離職票を発行
退職後に失業手当(正式には雇用保険の基本手当)の受給を希望する従業員がいる場合、会社は必ず「離職票」を発行しなければなりません。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書では、失業手当の申請手続きはできないため、注意が必要です。
離職票には、失業手当の支給額や給付日数を決定するための重要な情報(退職前の賃金支払状況や離職理由など)が記載されています。そのため、離職票はハローワークでの失業手当申請に不可欠な書類となります。
会社は、離職票の元となる「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、ハローワークに提出することで、離職票の交付を受けることになります。
特に従業員が自己都合退職の場合など、離職理由をめぐるトラブルを防ぐためにも、退職時に「離職票が必要かどうか」を明確に確認し、文書で記録しておくと安心です。
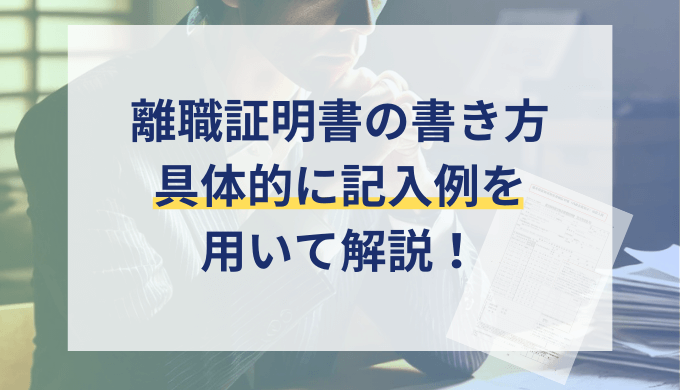 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
失業手当(失業保険)の給付金額がいくらになるか、おおよその目安を計算したい方は、下記の自動計算シミュレーションツールを活用してください。
> 失業保険の手当金計算シミュレーション!雇用保険給付金の自動計算ツール
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員が退職してから自動的に手元に届くわけではありません。会社(事業主)によるハローワークへの届出が完了して、はじめて発行される書類です。
手続きの全体像を把握しておくことで、従業員から「通知書はいつもらえますか?」と質問があった際にも、スムーズに答えられるようになります。
具体的なステップは、以下の通りです。
①雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する
まず、従業員が退職したり雇用保険の適用除外に該当したりした場合、会社は資格喪失日(退職日など)の翌日から起算して10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
この届出をもって、雇用保険の資格喪失が正式に記録されることになります。
喪失届には、喪失理由・喪失年月日・本人情報などを正確に記載しなければなりません。
この届出を正当な理由なく怠った場合、法律に基づき罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があるため、提出期限は必ず守る必要があります。
実務上、従業員の退職時には、このハローワークで行う雇用保険の手続きと並行して、年金事務所へ提出する「健康保険・厚生年金保険(社会保険)」の資格喪失手続きも同時に発生します。
両者は対象となる保険や提出先が異なる全く別の手続きですので、混同しないよう注意が必要です。
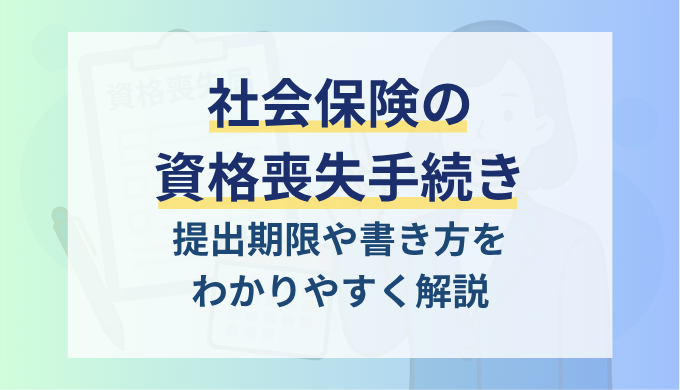 社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
②ハローワークが資格喪失確認通知書を発行し、会社へ送付
会社から提出された「雇用保険被保険者資格喪失届」の内容をハローワークが確認し、手続きが正式に受理されると、ハローワークは「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を発行します 。
この通知書は、退職した従業員本人に直接送付されるのではなく、手続きを行った会社(事業主)宛てに郵送される仕組みです 。
会社には、以下の2種類の通知書が送付されます。
- 被保険者通知用(本人控え)
- 事業主控え
会社がハローワークへ届出を提出してから、これらの通知書が手元に届くまでには、通常1〜2週間程度かかります 。
③本人へ資格喪失確認通知書(本人控え)を渡す
ハローワークから通知書が届いたら、会社は速やかに「被保険者通知用(本人控)」を退職した従業員本人へ郵送または手渡しで交付します 。
もう一方の「事業主控」は、会社が手続きを適正に行った証拠として、他の雇用保険関係書類とともに法律で定められた期間(4年間)保管する義務があります 。
従業員へ通知書を渡す際は、「失業手当の申請には使えませんが、雇用保険の記録として大切に保管してください」といった一言を添えると、より丁寧な対応となります。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について、事業主や人事担当者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。日々の業務で迷った際の参考にしてください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はいつもらえる?
退職した従業員本人が通知書を受け取るのは、会社がハローワークへ届出を行ってから、通常1〜2週間後が目安です。
全体の流れは以下の通りです。
- 会社の手続き
- ハローワークでの発行
- 会社から本人へ交付
もし、退職から2〜3週間以上経っても従業員に届かない場合は、まず会社がハローワークへ届出を提出済みかを確認し、提出済みであれば管轄のハローワークへ処理状況を問い合わせてみましょう。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は再発行できる?
再発行は可能です。万が一、従業員または会社が通知書を紛失してしまった場合は、会社の所在地を管轄するハローワークで再発行の手続きを行えます。
手続きは、退職者本人がハローワークの窓口へ出向いて「雇用保険被保険者関係届出書再交付申請書」という書類を提出するのが基本です。 インターネットでの再発行はできません。
事業主通知用の書類はある?
あります。ハローワークから会社へ送付される際、「被保険者通知用(本人控)」とは別に、会社が保管するための「事業主控」が発行されます。
この「事業主控」は、会社が雇用保険の資格喪失手続きを適正に履行したことの証拠となる重要な書類です。雇用保険法施行規則に基づき、
4年間の保管義務がありますので、他の退職関連書類と一緒に大切に保管してください。
ここまで解説してきた雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員の退職手続きにおける一部です。退職時には、雇用保険だけでなく社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する手続きも同時に発生します。
円満な退職とトラブル防止のために、会社側が行うべき主要な手続きをここで確認しておきましょう。
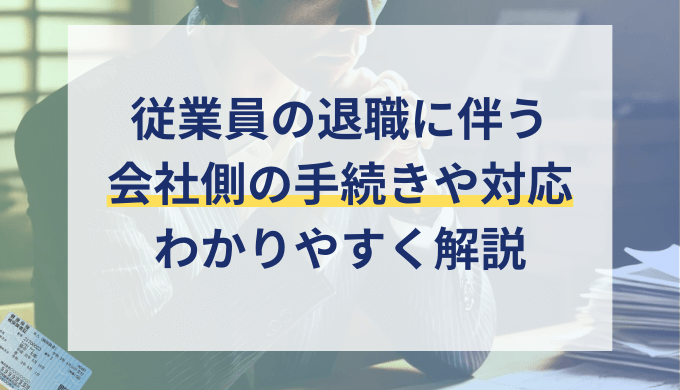 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
①社会保険・雇用保険の手続き
従業員が退職する際は、「社会保険」と「雇用保険」それぞれの資格喪失手続きを、別々に行わなければなりません。提出先や期限が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
■社会保険(健康保険・厚生年金保険)
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
| 提出先 | 管轄の年金事務所または事務センター |
| 提出期限 | 事実発生から5日以内 |
■雇用保険
| 提出書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届 |
| 提出先 | 管轄のハローワーク |
| 提出期限 | 退職日の翌日から10日以内 |
これらの手続きを漏れなく、期限内に完了させることが事業主には求められます。
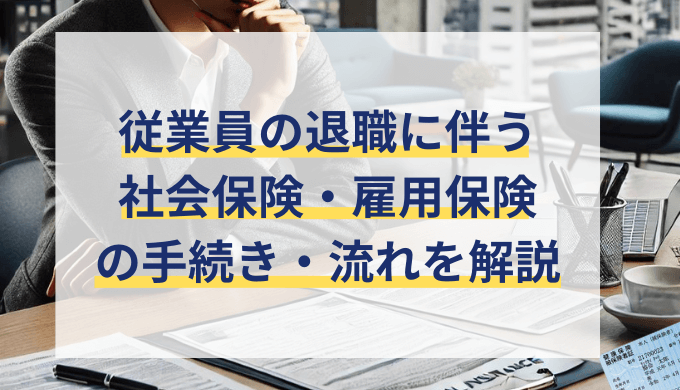 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
②健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の発行手続き
雇用保険の手続きとは別に、退職した従業員から「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書」の発行を求められることが多くあります。
この証明書は、退職者が会社の健康保険から脱退したことを証明するもので、主に以下のような手続きに必要となります。
- お住まいの市区町村で国民健康保険へ加入する手続き
- 家族の健康保険の被扶養者になるための手続き
- 退職後も会社の健康保険を任意で継続する「任意継続被保険者制度」の手続き
この書類は、退職後の従業員の医療保険を確保するために不可欠です。会社として、従業員の求めに応じて速やかに発行できるよう準備しておきましょう。
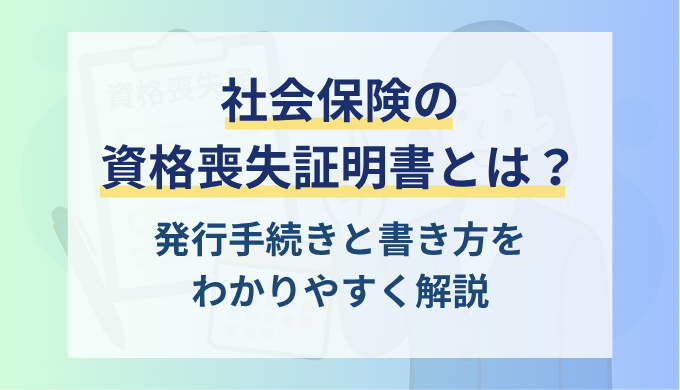 社会保険(健康保険)資格喪失証明書とは?発行手続きと書き方を記入例付きで解説
社会保険(健康保険)資格喪失証明書とは?発行手続きと書き方を記入例付きで解説
③退職証明書の作成(求められた場合)
退職証明書とは、従業員がその企業に在籍していた事実と退職した事実を、会社(使用者)が証明するために発行する「私文書」です 。
主に、従業員の転職活動における在籍期間の証明や、退職後の国民健康保険・国民年金への切り替え手続きなどで必要となる場合があります 。
退職証明書は、転職先から勤務実績の確認を求められたとき、国民年金・国民健康保険への切り替えで離職票が間に合わないときなどに必要になることがあります。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、従業員の退職や雇用保険資格の喪失を適切に証明するための重要な書類です 。
特に、離職票が発行されない場合、この通知書は転職先で雇用保険被保険者番号を確認する際に役立つことがあります 。また、まれに市区町村での国民健康保険への切り替え手続きで、退職日を証明する書類として利用できる場合もあります 。
また、会社側にとっても「手続きを期限内に正しく行った証拠」となるため、社内保管や従業員への交付を確実に行うことが法的リスク回避や信頼維持の面で非常に重要です 。
通知書が発行されるのは、以下の流れで手続きが完了した後です。
- 資格喪失日(退職日など)の翌日から10日以内に、会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出
- ハローワークが内容を審査・処理
- 問題がなければ、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が会社宛に送付
- 会社から従業員本人に「本人控え」が交付される
事務ミスや手続きの遅延が発生すると、従業員が次の手続きに進めなくなるなどのトラブルにもつながります。
このように、従業員の退職に伴う手続きは多岐にわたり、それぞれに期限やルールが定められています。手続きに不安を感じたり、コア業務に集中するために専門家のサポートが必要だと感じた場合は、社労士への依頼も有効な選択肢です。
スポット申請代行サービスの社労士クラウド
従業員の退職に伴う「雇用保険被保険者資格喪失届」の作成や一連の申請手続きは、提出期限も短く、専門的な知識が求められます。
「離職票と通知書のどちらを発行すべきか迷う」「自社で正確に手続きできるか不安…」「コア業務に集中したいので、手続きは専門家に任せたい」といったお悩みはありませんか?
そのような場合には、社労士に相談したり、申請の代行を依頼したりするのも有効な選択肢の一つです。
「社労士クラウド」は、顧問契約が不要で、必要な手続きだけを依頼できる『スポット契約』に特化した社労士サービスです。
「従業員1名の退職手続きだけをお願いしたい」「雇用保険被保険者資格喪失届の作成・提出だけを代行してほしい」といったご要望にも、顧問料0円で柔軟に対応いたします。設立間もない企業様や、普段は自社で手続きしているけれど今回だけ不安がある、といった企業様にも多くご利用いただいています。
経験豊富な社労士が、最新の法改正にも対応しながら、正確かつ迅速な申請手続きをサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|