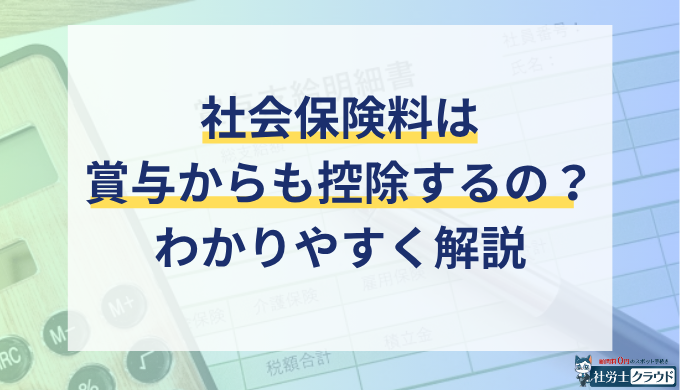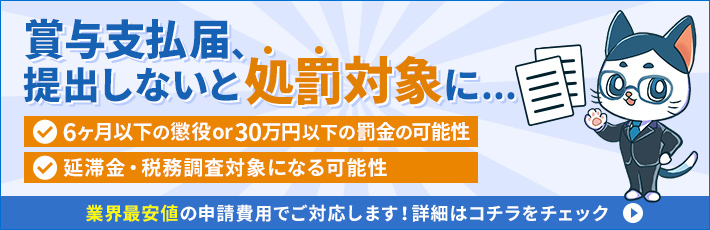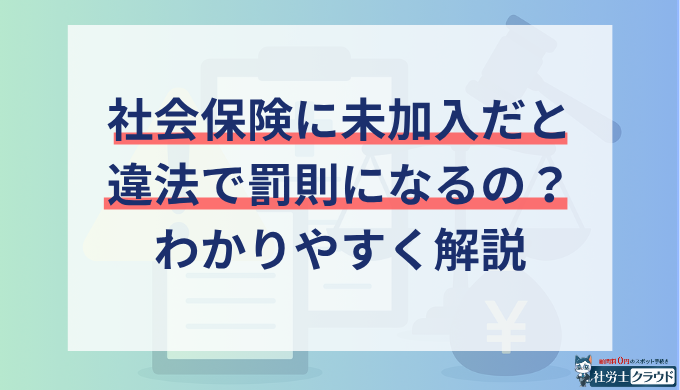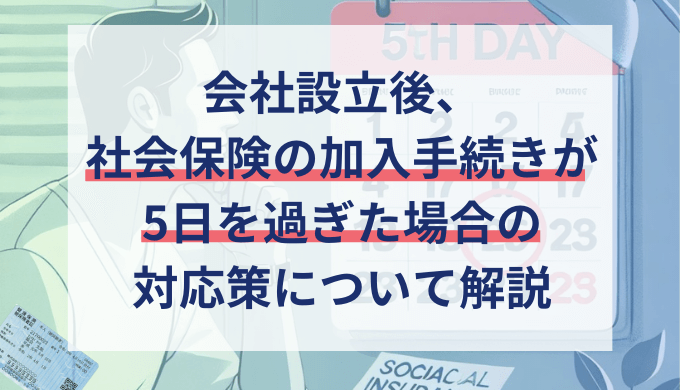賞与(ボーナス)を支給する際には、給与と同様に社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)の控除や届出手続きが必要です。
ただし、賞与の社会保険料計算は年に数回しか発生しないため、実務上の「落とし穴」が多い点に注意が必要です。
特に、支給日から「5日以内」という非常に短い期限で「被保険者賞与支払届」を提出する必要がある点。この手続きを忘れたり、計算を間違えたりすると、将来の追徴金や従業員の年金記録(会社への信頼)に影響が出る重大なリスクがあります。
本記事では、賞与にかかる社会保険料の基本から、具体的な計算方法・届出・納付の流れまでをわかりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業員に賞与(ボーナス)を支給すると、給与と同じように社会保険料が差し引かれます。
ここでは、「どんな支給が“賞与”として扱われるのか」「なぜ賞与からも健康保険・厚生年金が引かれるのか」。
まずは、社会保険料の対象となる「賞与」の定義から確認しましょう。
社会保険上の「賞与」とは?
社会保険でいう「賞与」は、名目ではなく中身で判断します。労働の対価として支払われ、かつ年3回以下の支給が対象です。
名称が「賞与」「ボーナス」「期末手当」「寸志」であっても同じ扱いですし、業績に応じたインセンティブや社員紹介のリファラル手当も、年3回以下なら「賞与」に該当します。
一方、結婚祝金・弔慰金・災害見舞金のような恩恵的な支給は労働の対価ではないため、賞与には含まれません。ここを混同すると、控除額や届出の判断を誤りやすくなります。
【事業主の注意点】
年4回以上の支給は「賞与」ではなく報酬(毎月の給与)として扱います。
たとえばインセンティブを四半期ごと(年4回)に支給する場合は、賞与支払届の対象外となり、月額賃金として標準報酬月額に反映します。
判定を誤ると保険料の過不足や届出漏れにつながるため、まず「労働の対価か」「年3回以下か」で分類してください。
賞与からは、4種類の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)が控除されます。ただし、保険料の種類によって「計算の基礎となる金額」や「料率」が異なるため、実務では注意が必要です。
ここで、それぞれの計算方法を具体的に見ていきましょう。
標準賞与額とは?(1,000円未満切り捨て)
「標準賞与額」は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を計算するための「基礎」となる金額のことです。
具体的には、従業員に支給する税引前の賞与総額から、1,000円未満の端数を切り捨てた額を指します。例えば、賞与総額が 458,700円 の場合、1,000円未満の700円を切り捨てた「458,000円」が標準賞与額となります。
ただし、雇用保険料の計算には、この「標準賞与額」は使いません。
これは、健康保険や厚生年金が「社会保険」であるのに対し、雇用保険は「労働保険」に分類され、制度の仕組みが異なるためです。
労働保険は、年に一度、1年間の「賃金総額(1円単位)」で保険料を精算する仕組み(年度更新)になっており、そのため賞与の計算時点でも1円単位の総額を使う必要があるのです。
① 健康保険料(標準賞与額 × 健康保険料率 × 1/2)
健康保険料は、従業員と会社(事業主)が半分ずつ負担する「労使折半」です。
計算式は、先ほど説明した「標準賞与額」を使って、以下のようになります。
| ▼賞与にかかる健康保険料の計算式(従業員負担分)従業員負担分= 標準賞与額 × 健康保険料率 ÷ 2 |
「健康保険料率」は、会社が加入している健康保険組合によって異なります。 例えば、中小企業が多く加入する「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の場合、料率は都道府県ごとに設定されています。
参考)令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
もし加入先が「組合健保(〇〇健康保険組合など)」の場合は、その組合が独自に設定した料率を使います。賞与計算の前には、自社が加入している組合と、その最新の料率表を必ず確認するようにしてください。
② 介護保険料(40~64歳/標準賞与額 × 介護保険料率 × 1/2)
介護保険料は、健康保険料に上乗せして徴収されますが、対象者が限定されています。 対象となるのは、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)のみです。39歳以下の従業員や、65歳以上の従業員からは徴収しません。
計算方法は健康保険料と同じく労使折半で、以下の通りです。
| ▼賞与にかかる介護保険料の計算式(従業員負担分)従業員負担分 = 標準賞与額 × 介護保険料率 ÷ 2 |
協会けんぽの場合、健康保険料率とは異なり、介護保険料率は全国一律です。
賞与計算時は、必ずこの最新の料率を使用してください。
③ 厚生年金保険料(標準賞与額 × 18.3% × 1/2)
厚生年金保険料も、健康保険料と考え方は同じです。 「標準賞与額」を基礎として、従業員と会社(事業主)が労使折半で負担します。
計算式は以下の通りです。
| ▼賞与にかかる厚生年金保険料の計算式(従業員負担分)従業員負担分 = 標準賞与額 × 18.3% ÷ 2 |
厚生年金保険料率は、健康保険料率や介護保険料率のように毎年度変わることはなく、現在 18.3% で固定されています。 そのため、従業員負担分の料率は、常に「9.150%」となります。
この料率は全国一律で、加入する組合による違いもありません。 計算自体はシンプルですが、1点だけ例外があります。それは、70歳以上の従業員です。
70歳以上の従業員は、厚生年金保険の被保険者ではなくなるため、賞与から厚生年金保険料を徴収する必要はありません。
ただし、健康保険には引き続き加入しているため、「70歳以上の従業員は、健康保険料は引くが、厚生年金保険料は引かない」という、個別の対応が必要になります。
この例外については、後ほど詳しく解説しています。
④ 雇用保険料(注意:賞与の「総額」 × 雇用保険料率)
雇用保険料は、これまでの3つの保険料とは計算ルールが大きく異なるため、特に注意が必要です。
健康保険や厚生年金が「標準賞与額(1,000円未満切り捨て)」を使ったのに対し、雇用保険は1,000円未満の切り捨てを行わず、「賞与総額(額面)」そのものを使用します。
また、労使折半でもありません。従業員負担分の料率と、事業主負担分の料率が個別に定められています。
計算式は以下の通りです。
| ▼賞与にかかる雇用保険料の計算式・従業員負担額 = 賞与総額 × 雇用保険料率(労働者負担分) ・事業主負担額 = 賞与総額 × 雇用保険料率(事業主負担分) |
この雇用保険料率は、年度や事業の種類(一般の事業、農林水産業、建設業など)によって異なります。
具体的な計算方法やシミュレーションについては、以下のツールも参考にしてください。
賞与の社会保険料計算は、基本的な計算以外にも、実務上で間違いやすい「落とし穴」がいくつかあります。
ここでは、事業主が確認すべき6つの注意点を解説します。
注意点1:社会保険料の「上限額」(健保・厚年)
賞与から保険料を計算する際、「標準賞与額」には上限(キャップ)が設けられており、上限を超えた分には保険料がかかりません。
ただし、健康保険と厚生年金で上限のルールが全く異なり、非常に間違いやすいため注意が必要です。
| 健康保険・介護保険:年度(4月1日~翌3月31日)の「累計」で573万円が上限 厚生年金保険:支給「1回」につき150万円が上限(同じ月に2回以上支給した場合は合算) 雇用保険:上限なし |
特に注意が必要なのは、健康保険の「累計管理」です。
これは実務上、担当者が従業員ごとに年間の賞与支給額を管理・累計する必要があることを意味します。
もし累計が573万円を超える見込みとなった場合、年金事務所(または健康保険組合)へ「標準賞与額累計申出書」を提出し、超過分の保険料徴収を停止します。
この「年度累計管理」は手間がかかり、担当者の引き継ぎ時などに漏れが発生しやすいため、ミスの温床となりやすいポイントです。
一方で、厚生年金保険は「1回ごと」の判定で、雇用保険にはそもそも上限がないため、保険ごとにルールが違う点を明確に区別しておくことが重要です。
注意点2:年4回以上支給する場合は「報酬(給与)」扱い
インセンティブなどを四半期ごと(年4回)に支給するなど、年4回以上支払われるものは、社会保険上「賞与」ではなく「報酬(毎月の給与)」として扱われます。
この場合、賞与支給の都度行う「賞与支払届」の対象外となります。代わりに、年間の支給総額(見込額)を12で割った額を、毎月の給与額に加算します。
そして、その合計額を基に「標準報酬月額」を決定(算定基礎届や随時改定)し、毎月の保険料として納付する流れに変わります。
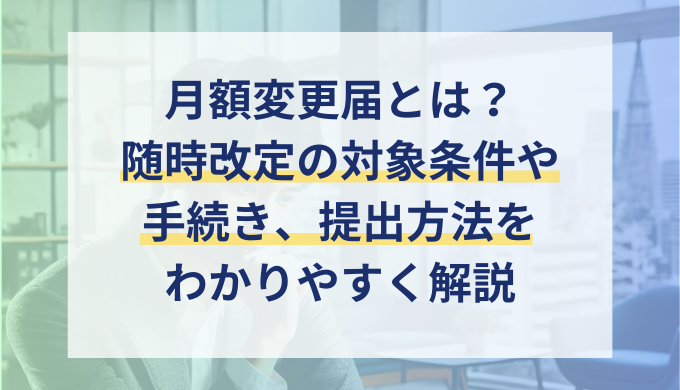 社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きについては、下の記事で詳しく解説しています。
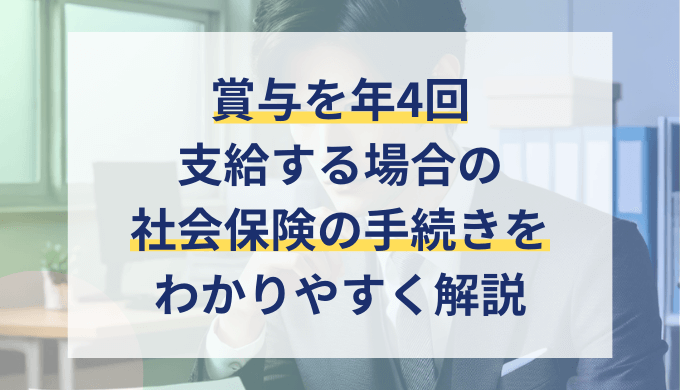 賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
注意点3:同月に2回以上支給する場合は「合算」
同じ月に2回以上賞与を支給した場合(例:7月10日に夏季賞与、7月25日に業績手当)、それらすべてを合算した額で「標準賞与額」を決定します。
例えば、1回目が30万円、2回目が10万円なら、合計40万円(から1,000円未満を切り捨てた額)が標準賞与額です。
手続きとしては、「賞与支払届」を1枚だけ作成し、その月の最後に支給した日(この例では7月25日)を支給日として、合算額(40万円)を記載して提出します。
注意点4:休職者・役員・非常勤従業員への賞与
従業員の状態によっても、取り扱いが変わるため注意が必要です。
◯休職者について
産前産後・育児休業による免除を除き、私傷病などで休職中であっても被保険者資格が継続していれば、その従業員に支給した賞与は保険料の対象となります。
◯役員について
社会保険の被保険者であれば役員賞与も保険料対象です(税務上の損金算入ルールとは別の論点)。
役員だけ別ルールと誤解されやすいため、従業員と同じ計算・届出の流れに組み込まれます。
◯非常勤について
パート・アルバイトであっても、週20時間以上などの社会保険の加入要件を満たしている被保険者であれば、その人に支給する賞与も保険料の対象となります。
注意点5:インセンティブや結婚祝金の取扱い
支給するものが「賞与」にあたるかどうかの判断基準は、それが「労働の対償」であるかどうかです。
例えば、結婚祝金、見舞金、弔慰金などは、恩恵的なものとされるため「労働の対償」ではなく、賞与には該当しません。したがって保険料もかかりません。
一方で、営業インセンティブや社員紹介のリファラル手当などは、業績や貢献に応じた「労働の対償」です。
これらが年3回以下の支給であれば「賞与」として保険料の対象となります。(もし年4回以上になれば「報酬」扱いです)
注意点6:70歳以上の従業員への賞与
70歳以上の従業員は、厚生年金の被保険者資格を喪失しているため、賞与から厚生年金保険料を控除する必要はありません。
一方で、健康保険の被保険者資格は継続するため、健康保険料は通常どおり控除します。(なお、介護保険料は40歳から64歳までが対象のため、65歳に到達している70歳以上の従業員からは控除しません。)
賞与の社会保険料計算には、すべての従業員に一律で適用されるわけではない、実務上特に注意すべき「例外」が存在します。
ここでは、代表的な2つのケースについて解説します。
ケース1:産前産後休業・育児休業中の従業員
従業員が産休・育休を取得している期間は、社会保険料の徴収が免除されます。
事業主が「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(または健康保険組合)に提出することで、休業期間中の社会保険料(健康・介護・厚生年金)が、従業員負担分・会社負担分ともに免除されます。
ただし、特に育児休業中の賞与については、2022年10月の法改正でルールが厳しくなったため注意が必要です。
賞与にかかる保険料の免除を受けるには、「賞与が支給された月の末日を含んだ、連続1ヶ月を超える育児休業」を取得している必要があります。
以前は、賞与月の末日に1日だけ育休を取得しているだけでも免除対象でした。
しかし、現在はそのルールが変わっているため、過去の認識のまま処理すると間違いになります。
【注意】雇用保険は免除されません
この社会保険料の免除は、雇用保険には適用されません。
産休・育休中であっても、賞与を支給した場合は、雇用保険料は通常通り徴収する必要があります。
産前・産後の社会保険料の免除額や期間を算出できるツールもあるのでご活用ください。
ケース2:賞与支給月の「末日より前」に退職した従業員
賞与を支給した月に従業員が退職する場合、社会保険料(健康・介護・厚生年金)の扱いは「退職日」によって変わります。
結論は、賞与支給月の「末日より前」に退職する従業員からは、賞与の社会保険料を徴収する必要はありません。
しかし、賞与支給月の「末日」付けで退職する場合は、徴収対象となります。
この違いは、社会保険の「資格喪失日(退職日の翌日)」と保険料の発生ルールに基づいています。社会保険料は、「資格喪失日が属する月の前月」まで発生する決まりです。
【具体例1:6月25日(末日前)に退職】
- 資格喪失日:6月26日
- 資格喪失日が属する月:6月
- 保険料の発生:5月分まで
結論: 6月分の保険料は発生しません。そのため、6月に支給された賞与からも社会保険料(健康・介護・厚生年金)を徴収しません。
【具体例2:6月30日(末日)に退職】
- 資格喪失日:7月1日
- 資格喪失日が属する月:7月
- 保険料の発生:6月分まで
結論: 6月分の保険料が発生します。そのため、6月に支給された賞与からも社会保険料(健康・介護・厚生年金)を徴収します。
【注意】雇用保険は徴収します
この「末日退職かどうか」のルールも、雇用保険には適用されません。
雇用保険料は、退職日に関わらず、賞与が支給されたのであれば必ず徴収します。
【実務上のポイント】
退職日が1日違うだけで、控除の有無という大きな違いが生まれます。 控除不要のケースで誤って控除してしまった場合は、従業員への返金対応や、年金事務所への訂正届の提出が必要になり、手続きが非常に煩雑になります。
退職日を正確に確認し、後の「賞与支払届」の提出(控除対象とするか否か)にも正しく反映させることが重要です。
賞与を支給する際、事業主が計算すべきは社会保険料だけではありません。
従業員から天引きする「源泉所得税」と、事業主が全額を負担する「子ども・子育て拠出金」の2つについても、同時に処理する必要があります。
源泉所得税(前月の給与額から税率を算出)
賞与からも、毎月の給与と同じように「所得税(復興特別所得税含む)」を源泉徴収します。
ただし、賞与の所得税計算は、毎月の給与計算とは方法が異なります。
国税庁が定めている「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算するのが原則です。
具体的な手順は以下の通りです。
- 賞与支給月の「前月」の給与額(社会保険料控除後)を確認します。
- その金額と従業員の扶養親族の数(甲乙欄の確認)を税率表に当てはめ、賞与にかける税率(%)を特定します。
- 賞与総額から社会保険料(4種類)の合計額を引いた金額に、特定した税率を掛け、源泉徴収する所得税額を計算します。
ただし、この計算方法には例外があります。 前月の給与がなかった場合や、賞与額が前月給与の10倍を超える場合は、この税率表は使えません。その際は、毎月の給与と同じ「月額表」を使った別の計算方法で対応します。
子ども・子育て拠出金 (事業主負担)
賞与計算で、もう一つ忘れてはならないのが「子ども・子育て拠出金」です。子ども・子育て拠出金は、事業主が全額負担する制度で、従業員から天引きはしません。この拠出金は、児童手当や保育所運営など、少子化対策・子育て施策の財源に充てられます。
計算方法は、従業員の「標準賞与額」(および毎月の標準報酬月額)に、拠出金率「0.36%(令和7年11月調べ)」を掛けて算出します。
納付する際は、厚生年金保険料と合わせて、事業主が一緒に納付する流れになっています。
賞与計算時は、従業員から控除する社会保険料だけでなく、この事業主負担分のコストも予算に含めておく必要があります。
なお、政府はこれとは別に、令和8年度(2026年度)から「子ども・子育て支援金」を創設する予定です。この新しい支援金は、現行の拠出金(事業主100%負担)とは異なり、従業員と事業主の「労使折半」となり、健康保険料に上乗せして徴収される見込みです。
賞与を支給した月は、通常の給与計算とは別に「届出」と「納付」の対応が発生します。どちらも期限が短いため、スケジュールの管理が重要になります。
「被保険者賞与支払届」の提出(支給後5日以内)
賞与を支給したら、従業員ごとに「被保険者賞与支払届」を、支給日から5日以内に年金事務所(または健康保険組合)へ提出します。
この届出は、従業員の将来の年金記録の基礎データとなる、非常に重要なものです。 万が一、提出が遅れたり、金額を間違えたりすると、従業員の将来の年金受給額に影響し、会社への信頼問題に直結する可能性があります。
提出方法は、紙での郵送や窓口提出、電子媒体(CD/DVD)も可能です。 しかし、期限が5日間と非常に短いため、迅速かつ記録が残る電子申請(e-Gov、GビズID)の利用が安心です。
もし提出を忘れた場合、判明次第すぐに遡って提出(時効2年)する必要があります。 調査などで発覚した場合は、延滞金を含む追徴のリスクも伴います。 金額を間違えて提出してしまった場合は、速やかに「被保険者賞与支払届訂正届」を提出し、正しい記録に修正します。
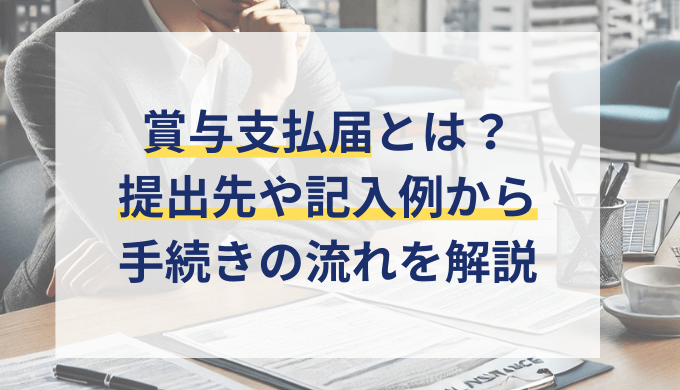 賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
社会保険料と税金の納付
届出が完了したら、次は計算した社会保険料と税金を納付します。
ここで最大の注意点は、社会保険料と源泉所得税で「納付期限が異なる」ことです。この2つの期限を混同しないよう、厳重に管理する必要があります。
【期限①:源泉所得税】:支給月の翌月10日まで
【期限②:社会保険料(+子ども・子育て拠出金)】:支給月の翌月末日まで
源泉所得税のほうが期限が早いことを意識しておきましょう。
社会保険料は、毎月の給与分の保険料と賞与分の保険料が合算された「納入告知書」が届きますので、それに基づき納付します。
納付方法は、口座振替、金融機関の窓口、Pay-easy(ペイジー)などが利用できます。
経営の視点では、「従業員から預かった分」「会社負担分の社会保険料」「子ども・子育て拠出金」のすべてを合計した額が、賞与支給に伴う会社の「総キャッシュアウト」となります。
資金繰りのためにも、この総額を事前に把握しておくことが重要です。
賞与(ボーナス)には、原則として健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険がかかります。
控除額の計算や届出に誤りがあると、追徴金のリスクだけでなく、従業員の将来の年金記録にも影響し、会社への信頼を損なうことにもなりかねません。正確な計算と処理は、事業主の重要な責任です。
特に、
- 「標準賞与額(1,000円未満切り捨て)」と「賞与総額」の使い分け
- 支給日から「5日以内」の「被保険者賞与支払届」の提出
- 「源泉所得税(翌月10日)」と「社会保険料(翌月末日)」の異なる納付期限
といった点は、実務上、特に間違いやすいポイントです。
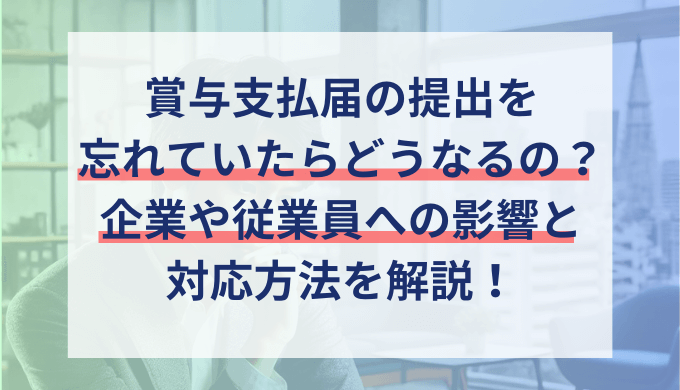 賞与支払届の提出を忘れていた場合の対応策!5日以内を過ぎた場合の罰則とリスクも解説
賞与支払届の提出を忘れていた場合の対応策!5日以内を過ぎた場合の罰則とリスクも解説
さらに、産休・育休中や70歳以上の従業員など、例外的な処理も求められます。
賞与計算は年に数回しかなく、法改正(令和7年度の介護保険料率変更など)も見落としやすいため、本記事で解説したポイントを活用し、ミスのないよう確実に処理しましょう。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。
賞与(ボーナス)の計算や、期限が短い「被保険者賞与支払届」の提出など、年に数回しか発生しない面倒な手続きも、オンラインでスムーズに進められます。
▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由
1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)
2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)
3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)
社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。
まずは、お気軽にご相談ください。 「賞与支払届の期限(5日以内)が迫っているけど間に合う?」 「うちの従業員(育休中・70歳以上)の計算、合ってる?」 「法改正(令和7年度介護保険料)が計算に反映できているか不安」 といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|