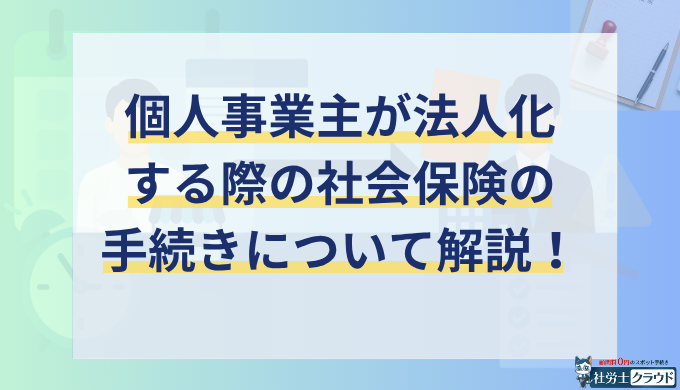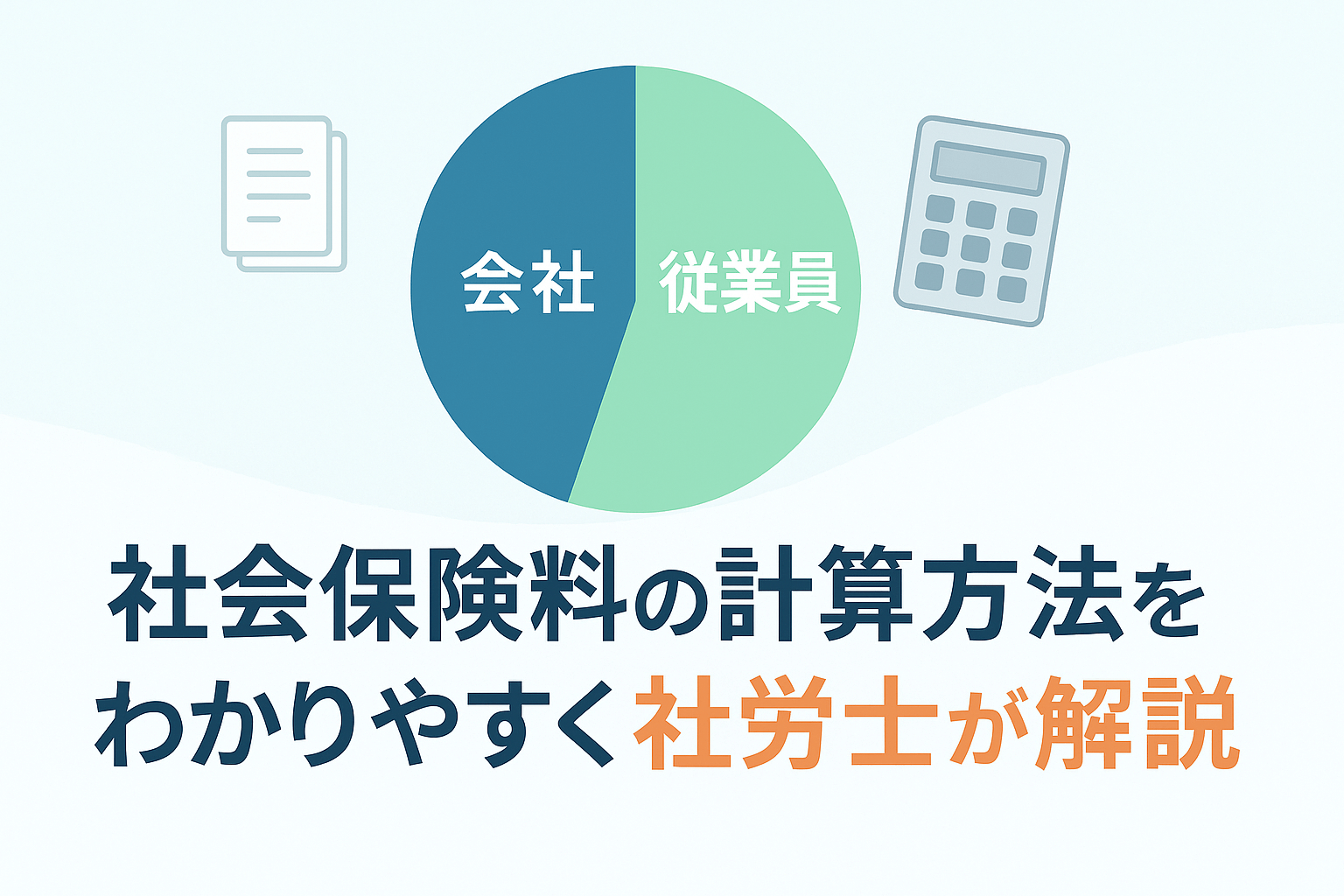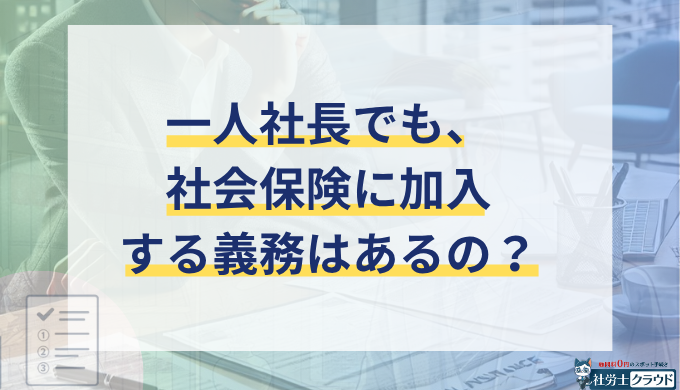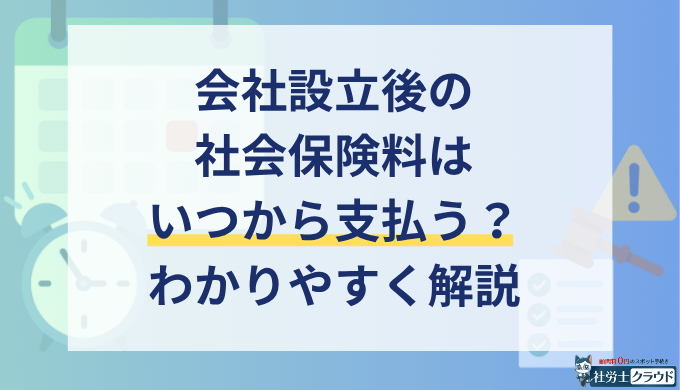個人事業主から法人化(法人成り)する際に、多くの方がつまずくのが社会保険の手続きです。
「社長一人でも加入は義務?」「手続きの期限はいつまで?」「保険料はいくらになるの?」など、次々と疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
特に社会保険は、法人設立から5日以内に手続きが必要な場合があるなど、期限が非常にタイトです。知らずに進めてしまうと、後から大きなトラブルになりかねません。
本記事では、個人事業主から法人化する際の社会保険について、手続きの流れから必要書類、保険料の目安まで、わかりやすく解説します。
個人事業主時代との違いや、加入のメリット・デメリット、未加入の場合の罰則までまとめて紹介しています。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
個人事業主から法人化(法人成り)すると、社会保険の扱いが大きく変わります。
これまで国民健康保険や国民年金に加入していた方も、法人化した時点で健康保険・厚生年金への加入が法律上の義務となることです。 これは、株式会社や合同会社といった「法人」が、法律上「強制適用事業所」に該当するためです。
「強制適用事業所」とは、法人を設立した時点で自動的に社会保険の対象となる事業所のことを指します。個人事業主のように従業員数によって加入を選べる「任意適用事業所」とは根本的に異なります。
たとえ社長一人だけの会社であっても、法人から役員報酬を受け取る限り、健康保険・厚生年金への加入は法律上の義務です。
ただし、例外的に社会保険に加入できない、加入が不要となるケースもあります(この点はのちほど詳しく解説します)。
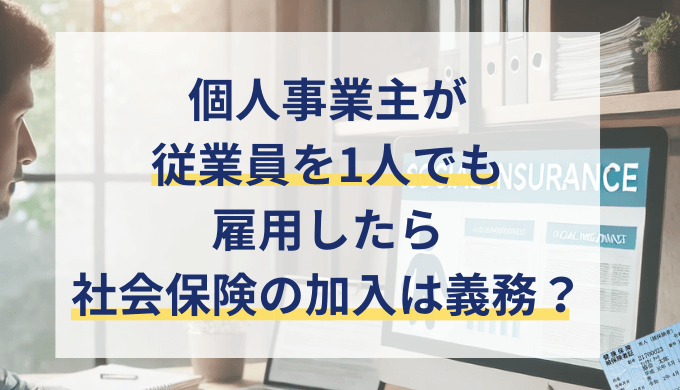 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
従業員を雇用する場合は「労働保険」の手続きも必須
また、従業員(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用する場合は、社会保険とは別に「労働保険(労災保険・雇用保険)」の手続きも必須となります。
個人事業主時代に労働保険に入っていた場合も、法人として新規に手続きが必要になるので注意しましょう。
法人化すると、社会保険は具体的に何が変わるのか。個人事業主時代と比べた4つの大きな違いを、まずは比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | 法人(法人化後) | 個人事業主(現在) |
| ① 保険の種類 | 健康保険・厚生年金 | 国民健康保険・国民年金 |
| ② 保障内容 | 手厚い(傷病手当金など) | 限定的 |
| ③ 保険料の計算 | 役員報酬(標準報酬月額) | 所得(前年の利益) |
| ④ 保険料の負担 | 会社と個人で折半 | 全額自己負担 |
このように、加入する制度が変わり、保障は手厚くなります。
一方で、保険料は「前年の所得」ではなく「自分で設定する役員報酬」を基準に計算され、会社と個人で半分ずつ負担する形に変わります。この仕組みの違いが、保険料を計画的に管理する上で重要なポイントになります。
(※各項目の詳しいメリット・デメリットは、後の章で解説します)
法人化(会社設立)を行ったら、最初に着手すべき重要な手続きが健康保険・厚生年金への加入です。法人は強制適用の対象にあたるため、加入を後回しにできません。
とくに期限が要点です。法人設立(登記)の日から5日以内という短い期限が定められています。登記準備と並行して書類を整えないと、期限を守るのは難しくなります。
期限を過ぎると、設立日にさかのぼって加入とみなされ、遅れた期間分の保険料を後からまとめて支払う「遡及加入」のリスクが生じます。
手続きの窓口は、本店所在地を管轄する年金事務所(または事務センター)です。
初回から納付を安定させるため、各種届出とあわせて保険料口座振替依頼書も提出しておくと運用がスムーズになります。
提出する主な書類は次のとおりです。
| 書類名 | 目的 | 主な添付書類(例) |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 会社(事業所)を社会保険に登録する | ・法人の登記事項証明書(原本・90日以内) ・法人番号指定通知書(コピー) |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 社長個人を被保険者として登録する | (特になし) |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 扶養家族を登録する(該当者のみ) | ・住民票(続柄確認用) ・課税(非課税)証明書(収入確認用)など |
詳しくは以下で解説していきます。
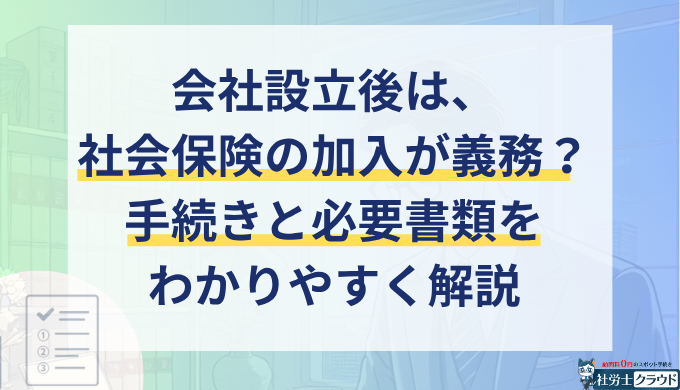 会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介
会社設立時の社会保険の手続きや必要書類を全解説!加入義務の有無についても紹介
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
「新規適用届」は、設立した会社(事業所)が初めて社会保険の適用を受けるために提出する、最も基本となる書類です。会社として社会保険に正式に登録するための手続き、と考えると分かりやすいでしょう。
この届出には、会社名・本店所在地・法人番号・設立年月日・主な事業内容といった、法人の基本情報を正確に記入します。これらは、社会保険を管理する上で基礎となる情報のため、登記内容と一致しているか確認することが重要です。
提出の際には、以下の添付書類が必要です。
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書):原本(発行から90日以内のもの)
- 法人番号指定通知書のコピー:法人番号を確認できる書類
これらの書類によって、法人が法的に存在していることを証明し、社会保険の適用事業所として登録されます
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
「新規適用届」が会社(事業所)を社会保険に登録する書類であるのに対し、「被保険者資格取得届」は、実際に保険へ加入する個人(社長・役員・従業員)を登録するための書類です。
社長(役員)はもちろん、社会保険の加入対象となる従業員がいる場合は、その全員分を提出します。
記入項目は、加入する人の氏名・生年月日・マイナンバー(または基礎年金番号)・役員報酬(報酬月額)などです。
とくに重要なのが、記入する「報酬月額」です。ここで届け出た金額をもとに、毎月の社会保険料を計算する標準報酬月額が決定されます。
そのため、株主総会などで正式に決めた役員報酬の金額と一致している必要があります。報酬額に誤りがあると、後日訂正や場合によっては調査が必要になるため、慎重に確認しましょう。
健康保険 被扶養者(異動)届(※扶養家族がいる場合)
社長(役員)や従業員に、生計をともにする家族(配偶者・子など)がいる場合は、「被扶養者(異動)届」を提出します。
これは、家族を被保険者の健康保険に被扶養者として登録するための手続きです。 被扶養者に認定されると、本人が保険料を負担することなく医療費の補助などの保険給付を受けられます。
国民健康保険のように家族の人数分保険料が増えることはなく、扶養の範囲内であれば追加負担がないのが特徴です。
この届出は、扶養家族がいる場合のみ提出します。提出時には、以下のような添付書類が求められる場合があります。
- 住民票(被保険者との続柄を確認)
- 所得証明書・非課税証明書(被扶養者の収入が基準額を下回ることを確認)
なお、社会保険上の扶養認定基準は、税法上の扶養控除とは異なります。年収130万円未満という基準だけでなく、勤務実態や収入の安定性なども総合的に見られるため、自己判断せずに確認することが大切です。
法人化して社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きを進める際、従業員(パート・アルバイトを含む)がいるなら、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必ず行います。
労働保険は社会保険とは別の制度で、労働者を使う事業であれば加入が義務です。
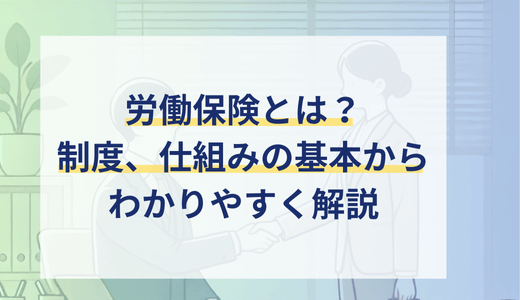 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
個人事業主の時に労働保険へ加入していた場合でも、そのまま継続にはできません。事業主が「個人」から「法人」に変わるため、原則として法人として新規に保険関係を成立させる必要があります。
事業の実態によっては名称・所在地変更で足りることもありますが、基本は新規適用と考えて準備すると安全です。
おおまかな流れは、まず労働基準監督署で「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出します。
続いて、ハローワークで「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」を提出します。
届出先が社会保険(年金事務所)と異なる点に注意し、採用日や提出期限を見落とさないよう、あらかじめ台帳類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)と必要書類をそろえて進めてください。
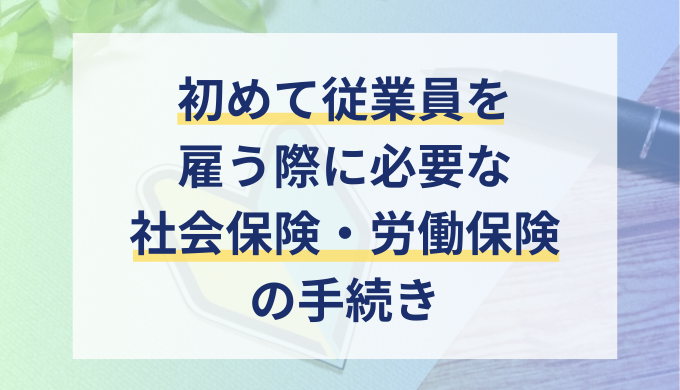 初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
労災保険の手続きと必要書類
労働保険の一つである「労災保険」は、従業員が仕事中や通勤の途中でケガをしたり、病気になったりした場合に、治療費や休業中の給付を行うための保険です。
この労災保険は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、雇用する全ての従業員が対象となります。保険料は全額会社負担です。
手続きは、法人の所在地を管轄する「労働基準監督署」で行います。提出する主な書類と期限は以下の通りです。
| 書類名 | 提出時期 | 提出方法 |
| 保険関係成立届 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係が成立した翌日から50日以内 | 窓口・郵送・電子申請 |
「保険関係成立届」は、労働保険(労災保険・雇用保険)の関係が始まったことを届け出るための、最初に行う重要な手続きです。
従業員を雇い入れた日の翌日から10日以内に、法人の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
書類には、会社名・所在地・事業の種類・雇入年月日・従業員数など、基本情報を記載します。
受理された控えは、後の「概算保険料申告書」や年度更新手続き、金融機関・助成金申請時などにも使用するため、必ず保管しておきましょう。
「概算保険料申告書」は、年度末(通常3月31日)までに従業員へ支払う予定の賃金総額の見込み額を基に、概算の労働保険料を申告・納付するための書類です。
提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。
実務上は、先に提出する「保険関係成立届」とセットで労働基準監督署へ提出します。
保険料を計算する際に用いる労災保険料率は、事業の種類ごとに定められており、建設業や製造業などでは他業種より高く設定されています。
業種区分を誤ると保険料の過不足や指摘につながるため、事業内容に合った区分で申告することが重要です。
原則として、社長や役員、代表者といった「事業主」は労働者ではないため、労災保険の対象外です。そのため、業務中にケガをしても労災から給付を受けることはできません。
ただし、中小企業の役員などで、実際に従業員と同じように現場作業を行う場合は、「特別加入制度」を利用して任意で労災保険に加入することができます。
この制度を利用すれば、事業主本人が業務上のケガを負った場合でも、治療費や休業補償の給付を受けられます。
特別加入の申請は、労働基準監督署に直接ではなく、厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」を通じて行うのが一般的です。加入する際は、作業内容や従事状況に応じて給付基礎日額(補償の基準額)を選択します。
雇用保険の手続きと必要書類
労働保険のもう一つである「雇用保険」は、従業員が失業した場合の失業手当(基本手当)や、育児休業・介護休業を取得した場合の給付金などを支給するための保険です。
ただし、雇用保険は全ての従業員が対象となるわけではありません。加入対象となるのは、「1週間の所定労働時間が20時間以上」であり、かつ「31日以上の雇用見込みがある」という両方の条件を満たす従業員です。
手続きは、法人の所在地を管轄する「ハローワーク(公共職業安定所)」で行います。
以下で、それぞれの書類の内容・添付書類・提出期限をまとめます。
| 届出書 | 書類の内容 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用を受けるための事務所の設置を届け出る書類 | 雇用した日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の被保険者資格を取得したことを届け出る書類 | 雇用した月の翌月10日まで |
「適用事業所設置届」は、会社(事業所)として初めて雇用保険の対象となる従業員を雇い入れた際に提出する書類です。
提出期限は、対象従業員を雇い入れた日(事業所を設置した日)の翌日から10日以内です。
添付書類として、法人の登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)など、従業員の雇用実態を確認できる書類の提出が求められます。
これらの書類により、雇用関係が実際に存在することを証明します。提出先は法人所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
「被保険者資格取得届」は、雇用保険の加入条件を満たす従業員を被保険者として登録するための書類です。
提出期限は、従業員が加入条件を満たした日(通常は雇い入れ日)が属する月の翌月10日までです。
登録対象となるのは、原則として週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員です。
一方、社長や役員は「労働者」に該当しないため、原則として雇用保険の対象外です。
ただし、取締役営業部長など、役員でありながら従業員としての職務を兼ねており、労働者としての実態がある場合は「使用人兼務役員」として加入できることもあります。
加入の可否は実態をもとに個別判断されるため、判断が難しい場合はハローワークや社労士へ確認するのが確実です。
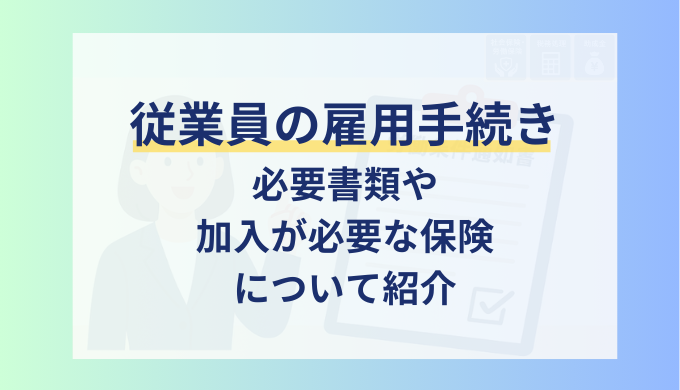 従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
法人化して会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したら、忘れてはならないのが、これまで加入していた**「国民健康保険」と「国民年金」**から抜ける(脱退する)手続きです。
特に国民健康保険は自動で脱退しないため要注意です。
手続きを忘れると、給与から会社の健康保険料が引かれているにもかかわらず、市区町村からも国民健康保険料の請求が届き続け、保険料を二重に支払うことになってしまいます。
一方、国民年金は、会社が行う厚生年金の資格取得手続きの情報が日本年金機構のシステムで自動連携されるため、原則として個人で脱退手続きを行う必要はありません。
もし国民健康保険の脱退が遅れて二重払いになった場合でも、後から手続きをすれば、会社の健康保険に加入した日にさかのぼって資格喪失が認められ、払いすぎた保険料が還付(精算)されることがあります。
詳しくは、お住まいの市区町村役場で確認してください。
国民健康保険の脱退手続きは、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した後に、住民票のある市区町村役場の「国民健康保険」担当窓口で行います。
法人化を検討するときに最初に気になるのが「毎月いくら保険料がかかるのか」です。個人事業主時代の国民健康保険とは計算の考え方が異なるため、仕組みを早めに押さえておくことが重要です。
法人化後の社会保険料は、①役員報酬を等級表に当てはめて決まる「標準報酬月額」と、②協会けんぽ等が定める「保険料率」の2要素で決まります。役員報酬をどう設定するかで負担額が変わる仕組みです。
算出された保険料は、会社と個人で折半(労使折半)します。
経営者は、役員報酬とは別におおよそ15%前後(会社負担分)が毎月のキャッシュアウトになる前提で、資金計画を立ててください。
会社負担分は経費(法定福利費)にできますが、資金繰りには直結します。所在地によって保険料率が異なるため、最新の料率表で試算しておくと安心です。
保険料は「標準報酬月額」と「役員報酬」で決まる
法人の健康保険料と厚生年金保険料は、毎月の「役員報酬」の金額を基準にして計算されます。個人事業主時代のように、前年の所得が自動的に反映される仕組みではありません。
具体的な計算の流れは、まず役員報酬の月額を「標準報酬月額等級表」という一覧表に当てはめ、保険料計算の土台となる「標準報酬月額」を決定します。
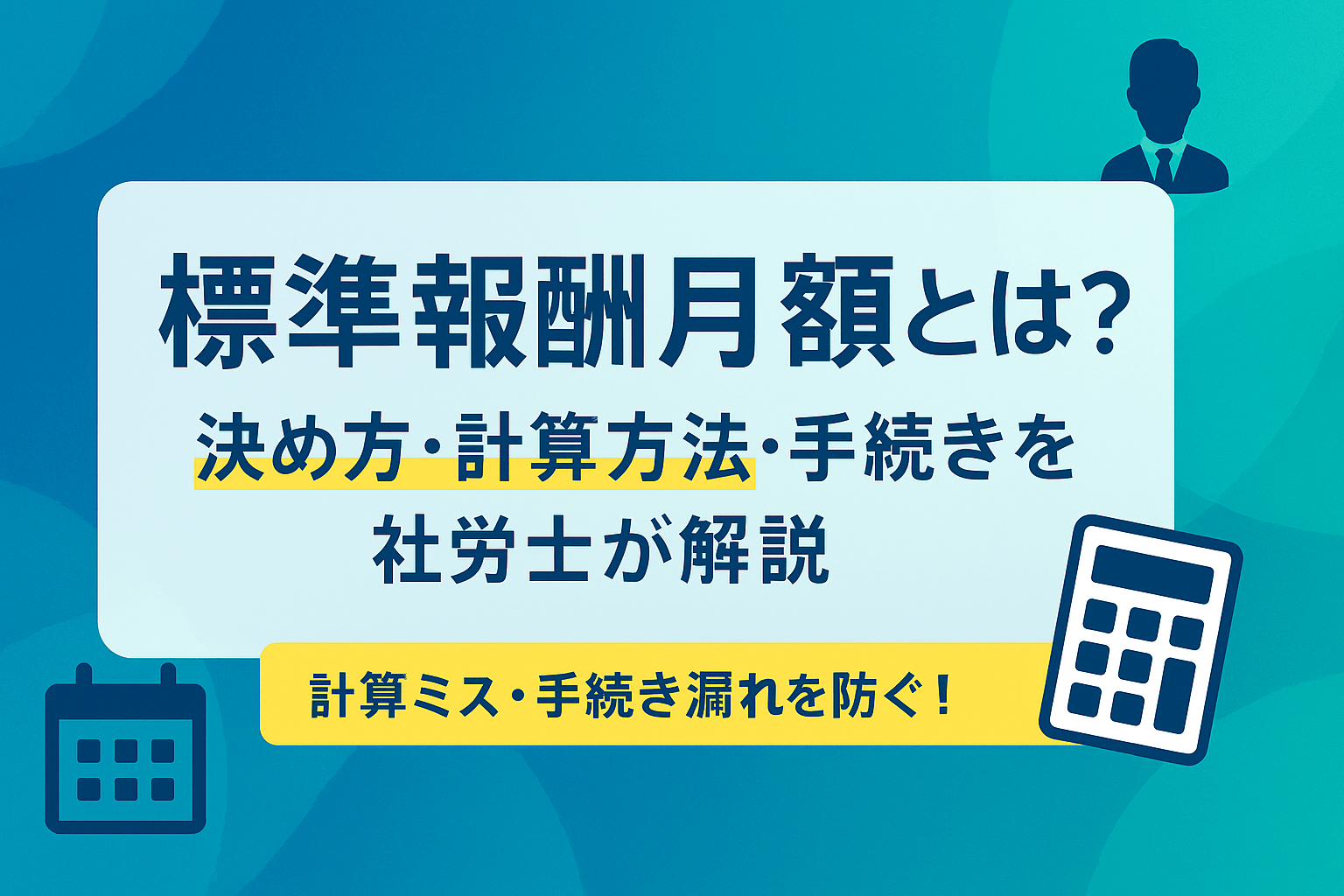 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する場合、健康保険の料率は都道府県ごとに異なります。 そのため、自社の本店所在地がある都道府県の保険料率を確認する必要があります。
社会保険料の計算例
実際に役員報酬の額によって社会保険料がいくらになるのか、具体的な例を見ていきましょう。
ここでは、東京都の会社で働く40歳未満の方(介護保険料の負担なし)を前提に、最新の令和7年度の保険料率を使って計算します。令和7年度の東京都の健康保険料率は9.91%、厚生年金保険料率は18.3%です。
参考: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和7年度保険料率のお知らせ」
【例1】役員報酬が月額20万円の場合
このケースの標準報酬月額は20万円です。
- 健康保険料:月額19,820円(個人負担 9,910円 / 会社負担 9,910円)
- 厚生年金保険料:月額36,600円(個人負担 18,300円 / 会社負担 18,300円)
→ 個人と会社の負担額は、それぞれ月額28,210円となります。
【例2】役員報酬が月額40万円の場合
このケースでは、報酬月額395,000円~425,000円の等級が適用されるため、標準報酬月額は41万円です。
- 健康保険料:月額40,631円(個人負担 20,316円 / 会社負担 20,315円)
- 厚生年金保険料:月額75,030円(個人負担 37,515円 / 会社負担 37,515円)
→ 個人の負担額は月額57,831円、会社の負担額は月額57,830円となります。
このように、役員報酬を高く設定すれば社会保険料の負担も増えますが、その分、将来受け取る厚生年金の額も手厚くなります。現在の会社のキャッシュフローと、将来の自分への保障を両立できる役員報酬額を決めることが重要です。
法人化に伴い、社会保険への加入は法律で義務づけられていますが、同時に経営上のメリットとデメリットの両方があります。
個人事業主時代とは保障内容や保険料の仕組みが大きく変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
ここでは、社会保険に加入することで得られるメリットと、新たに発生するデメリットについて、それぞれ具体的に解説します。
加入するメリット
社会保険への加入は、単なるコスト負担ではなく、事業を安定させるための基盤づくりにもつながります。特に以下の4点は、個人事業主のままでは得られない大きな利点です。
- 傷病手当金・出産手当金などの保障が手厚くなる
- 厚生年金によって将来の年金額が増える
- 「社会保険完備」で信用・採用力が上がる
- 家族の保険料負担がなくなる(被扶養者制度)
それぞれを順に見ていきましょう。
メリット1:病気やケガの保障が手厚くなる
法人の健康保険には、国民健康保険にはない「傷病手当金」という制度があります。これは、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、連続して3日間休んだ後の4日目から、給与のおよそ3分の2が最長1年6ヶ月にわたって支給されるものです。万が一の際の収入を保障してくれる、非常に心強い制度です。
メリット2:将来受け取る年金額が増える
個人事業主が加入する国民年金は、日本の年金制度の1階部分にあたる「基礎年金」のみです。一方、法人の厚生年金に加入すると、この基礎年金に上乗せする形で、2階建て部分の年金が支給されます。支払った保険料に応じて将来の年金額が増えるため、老後の生活設計に大きな安心感が生まれます。
メリット3:社会的信用が向上し、人材採用に有利になる
求職者の多くは、就職先を選ぶ際に「社会保険完備」を必須条件としています。社会保険に加入していることは、福利厚生が整っている証明となり、会社の社会的信用を高めます。これにより、優秀な人材を確保しやすくなり、組織力の強化につながります。
メリット4:家族(被扶養者)の保険料負担がなくなる
国民健康保険では、家族の人数が増えるとその分保険料も上がります。しかし、会社の健康保険では、一定の条件を満たす家族を「被扶養者」として認定でき、被扶養者分の追加保険料はかかりません。扶養する家族が多い方ほど、このメリットは大きくなります。
加入するデメリット
一方で、法人化により社会保険へ加入すると、金銭面・事務面での負担が新たに発生します。設立直後の小規模法人にとっては、経営を圧迫する要因にもなりかねません。
- 社会保険料の負担が増える
- 手続きや毎月の事務作業が増える
それぞれを順に見ていきましょう。
デメリット1:社会保険料の負担が(会社負担分を含め)増える
最も大きなデメリットは、社会保険料の負担です。保険料は会社と個人が半分ずつ負担(労使折半)するため、役員報酬から天引きされる個人負担分とは別に、同額程度の会社負担分が発生します。この会社負担分は「法定福利費」として経費にできますが、会社のキャッシュフローを直接圧迫する固定費となる点を理解しておく必要があります。
デメリット2:加入手続きや毎月の事務負担が発生する
社会保険に関する事務作業が、恒常的に発生することも大きな負担です。法人設立から5日以内という非常にタイトな加入手続きに始まり、従業員の入退社のたびに行う資格の取得・喪失手続き、毎月の保険料計算と納付、年に一度の「算定基礎届」の提出など、専門的な手続きが継続的に求められます。
法人化後の社会保険料は、経営における大きな固定費となります。しかし、法律で定められたルールの範囲内で、負担額を「適正化」するための考え方や方法が存在します。
違法な保険逃れではなく、あくまで合法的な知識として知っておくことが重要です。ここでは、保険料を適正に管理するための3つのポイントを紹介します。
役員報酬を適正に設定し、保険料をコントロールする
社会保険料を適正化する最も基本的な方法は、保険料の基礎となる「役員報酬」を計画的に設定することです。保険料は「標準報酬月額」という等級表で決まるため、この仕組みを理解しておく必要があります。
ポイントは次のとおりです。
◯標準報酬月額の等級の境目を意識する
わずか数千円の報酬差で等級が1段階変わり、保険料が大きく変動する場合があります。等級表を確認し、無駄のない報酬設定を行うことが有効です。
◯報酬を下げれば保険料は下がるが、年金額も減る
社会保険料を抑えるために報酬を低く設定すると、将来の厚生年金受給額も少なくなります。また、法人税・所得税とのバランスを考慮しないと、結果的に手取りが減るケースもあるため注意が必要です。
◯報酬の変更は「算定基礎届」や「随時改定」に反映される
社会保険料は、毎年4〜6月の報酬額で決定する「算定基礎届」や、報酬変動時の「随時改定」に基づいて見直されます。このルールを理解しておくことで、より計画的に報酬を調整できます。
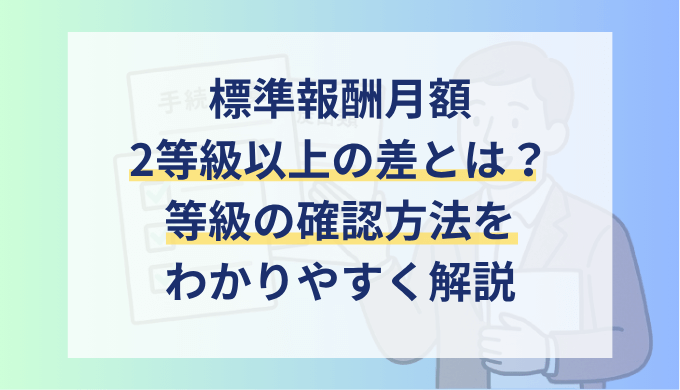 標準報酬月額2等級以上の差とは?等級の確認方法と随時改定(月額変更届)のタイミングを解説
標準報酬月額2等級以上の差とは?等級の確認方法と随時改定(月額変更届)のタイミングを解説
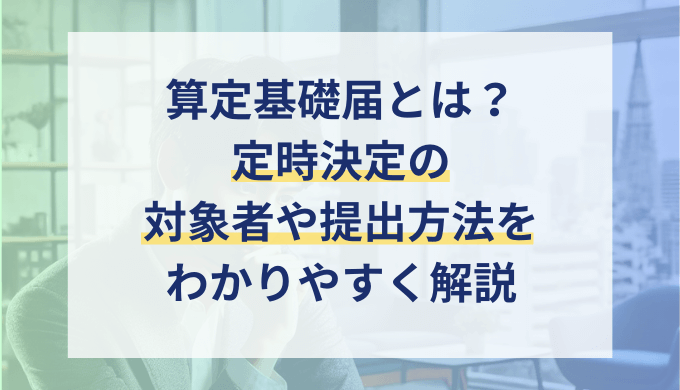 算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
家族・配偶者を非常勤役員にして扶養者に入れる(注意点あり)
家族を非常勤役員にし、報酬を低く設定して「被扶養者」にすることで、家族分の保険料を節約できる場合があります。ただし、この方法には厳格な条件とリスクがあり、安易に行うことはできません。
特に注意すべきポイントは次のとおりです。
◯社会保険の扶養基準は税法上の扶養と異なる
「年収130万円未満」といった収入条件に加え、勤務実態(常勤性の有無)が厳しく審査されます。
◯勤務実態のない「名ばかり役員」は扶養不可
実際に業務を行っていないのに役員として登録している場合、年金事務所の調査で「社会保険逃れ」と判断されるおそれがあります。
◯否認リスクと追徴請求の可能性
扶養認定を取り消された場合、過去に遡って保険料を請求されることもあります。判断は非常に難しいため、必ず社労士へ相談しましょう。
法人化に伴う社会保険の手続きを進めるうえで、思わぬ落とし穴にはまらないために、絶対に知っておくべき注意点がいくつかあります。
特に重要なのが、加入義務を果たさなかった場合の罰則と、反対に加入したくてもできない例外的なケースの存在です。この2つのポイントを正しく理解しておくことが、設立後の安定した経営につながります。
未加入のままだと罰則やペナルティがある
法人には社会保険への加入義務があるため、手続きをせずに未加入のまま事業を続けることは、経営における最大のリスクです。
「設立したばかりの小さな会社だから見つからないだろう」と考えるのは非常に危険です。現在、年金事務所は国税庁と法人登記情報を連携させており、未加入の事業所を的確に把握する体制を強化しています。
もし未加入であることが発覚した場合、以下のような厳しいペナルティが科せられます。
- 最大2年分の保険料を延滞金付きで一括請求される
- 雇用調整助成金など、国の助成金が申請できなくなる
- 悪質な場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の対象になる
このように、未加入は「後で入ればいい」では済まず、法的・金銭的リスクが極めて大きい点を理解しておく必要があります。
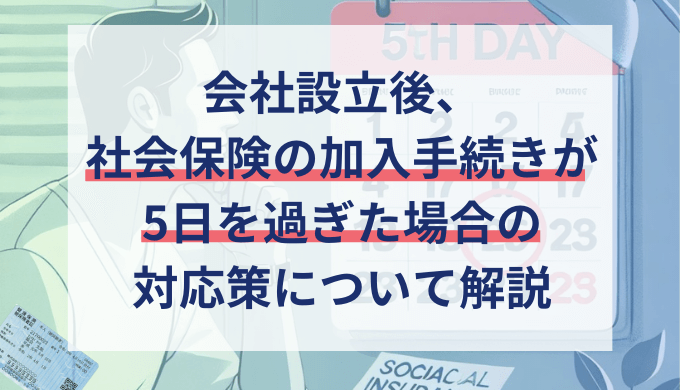 会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
会社設立後に社会保険の加入手続きが5日過ぎたら?間に合わない場合の対処法と必要書類を解説
例外的に加入できないケースもある
社会保険の加入義務がある法人でも、実態によっては加入できない(対象外となる)ケースも存在します。
加入対象外となる主なケースは次のとおりです。
◯役員報酬がゼロ円の場合
社会保険料は役員報酬の額をもとに計算されるため、報酬が全く支払われていない場合は、算定の基礎がなく加入できません。
◯非常勤役員である場合
代表取締役であっても、毎日出社せず業務への関与も限定的で、主な収入を別の会社から得ているなど、勤務の実態がほとんどない「非常勤役員」と判断される場合は、加入対象外となることがあります。
◯年齢による上限
厚生年金は70歳、健康保険は75歳になると加入資格を失います(75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行)。
これらのケースに当てはまりそうだと感じたとしても、「自分は対象外だろう」と安易に判断するのは絶対に避けてください。
勤務実態などの判断は専門家でなければ難しいため、必ず年金事務所や社労士に事前に確認することが重要です。
個人事業主から法人化するさいは、どのタイミングで法人化するのがいいのか?役員報酬はどうすればいいのか?悩みの種は多いですよね。中でも大きな悩みの種となるのが社会保険の手続きです。
今回の記事の重要なポイントを改めて振り返っておきましょう。
- 法人化すれば、社長一人でも社会保険への加入は必須
- 従業員を雇うなら労働保険の手続きも必要
- これまで加入していた国民健康保険の脱退手続きも忘れずに
法人を設立した直後は、本業の立ち上げに加え、税務や法務、そして今回解説した社会保険の手続きなど、慣れない作業が山積みになります。特に社会保険の手続きは期限が厳しく、書類も複雑です。手続きの漏れやミスは、将来の大きなトラブルにつながりかねません。
このようなリスクを避け、経営者が安心して本業に集中するためにも、複雑な手続きは専門家である社労士に任せるのが最も確実な方法です。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
「社労士クラウド」は、顧問契約なしで必要な手続きだけ依頼できるスポット申請代行サービスです。
▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由
1.必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる(顧問契約は不要)
2.オンラインで完結、圧倒的なスピード対応(すべてオンラインで迅速に対応)
3.社労士による確実な手続き(経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応)
社労士クラウドは、24時間365日いつでも依頼できるため、設立準備で忙しい事業主の方でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進められます。
まずは、ご相談ください。
「設立時の手続き、具体的に何から始めればいい?」 「期限(5日以内)が迫っているけど間に合う?」
といった具体的な疑問や不安に、専門家が直接お答えします。複雑な手続きは専門家に任せて、安心して事業のスタート準備に集中しませんか。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|