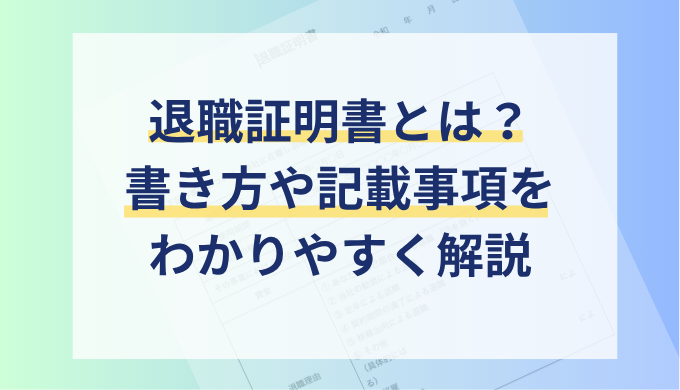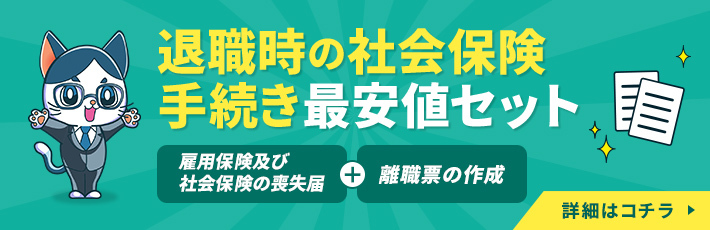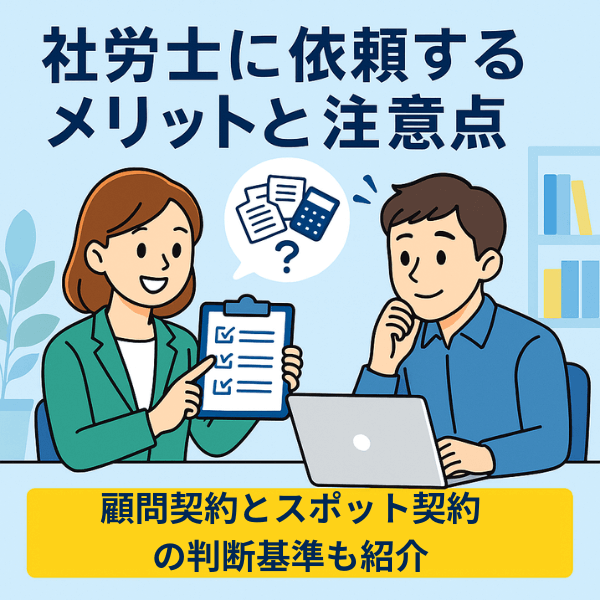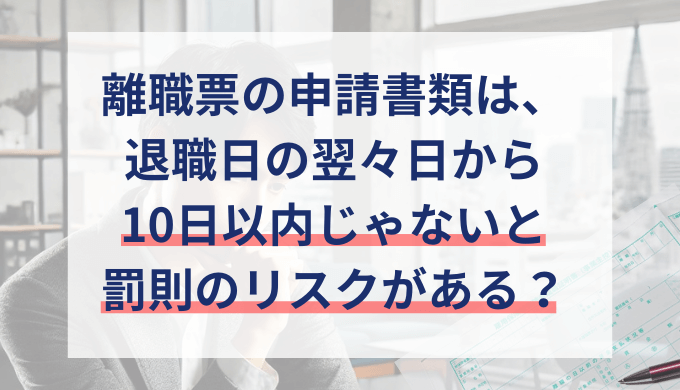退職証明書は、労働者から請求があった場合に企業が発行しなければならない、法律で発行が義務付けられた文書です。発行のルールは労働基準法で明確に定められており、対応を怠ると企業に罰則が科される可能性もあるため、正確な知識と実務対応が求められます。
また、退職証明書は従業員の希望に応じて、記載事項を調整する必要があります。 離職票や在籍証明書と混同しやすい書類でもあるため、それぞれの違いを理解したうえでの対応が不可欠です。
本記事では、社会保険労務士が退職証明書の書き方や記載事項、注意点を実務視点でわかりやすく解説。すぐに使えるテンプレートや離職票との違いについても紹介しています。
退職者とのトラブルを避け、適切かつ迅速な対応ができるよう、ぜひこの記事を活用してください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
退職証明書とは、従業員がその企業に在籍していた事実と退職した事実を、会社(使用者)が証明するために発行する「私文書」です 。
主に、従業員の転職活動における在籍期間の証明や、退職後の国民健康保険・国民年金への切り替え手続きなどで必要となる場合があります 。
従業員から「退職証明書を発行してほしい」と求められた際に、企業側には発行する法的な義務があります。この義務は法律で明確に定められており、会社の任意で発行を拒否することはできません。
退職証明書の発行義務について
企業は退職した従業員から退職証明書の発行を請求された場合、その請求に必ず応じなければなりません 。 このルールは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての「労働者」に適用されます 。
この発行義務の根拠となっているのが、労働基準法第22条です。
| (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 (条文抜粋) |
このように、法律によって、企業は従業員から証明書の請求があった際には「遅滞なく」交付することが義務付けられています。
もし、正当な理由なく発行を拒否したり、意図的に発行を遅らせたりした場合は、労働基準法第120条に基づき、労働基準法違反とみなされ、30万円以下の罰金が科されます 。 なお、従業員が退職証明書を請求できる権利は、退職時から2年間有効です 。
実務上、「そもそも退職証明書が何かわからなかった」「離職票で代用できると思った」などの理由で発行を怠るケースも見受けられますが、これらは法的に通用する正当事由にはあたりません。
退職証明書は、転職先での在籍確認や公的手続き(例:失業給付の仮手続き、国民健康保険の加入など)に使用されることがあるため、迅速な発行対応が求められます。
退職証明書は、従業員が退職後の生活で次のステップに進むために重要な役割を担う書類です。発行を求められる場面は限定的ですが、企業担当者としては、どのようなケースで必要となるかを正確に把握しておく必要があります。
以下に、実際に退職証明書の発行が求められる代表的なケースを紹介します。
転職先から勤務実績の確認を求められたとき
退職証明書が最も多く利用されるのは、従業員が転職する際に、新しい勤務先から提出を求められるケースです。 転職先の企業は、採用した人物の経歴に間違いがないかを確認するため、その裏付け資料として退職証明書の提出を要求することがあります。
具体的には、履歴書や職務経歴書に記載された以下の内容と相違がないかを確認する目的で利用されます。
- 在籍期間
- 従事していた業務内容
- 役職や地位
- 退職理由
企業がコンプライアンスや経歴詐称のリスク管理の観点から、客観的な証明書類を求めることは一般的です。
国民年金・国民健康保険への切り替えで離職票が間に合わないとき
従業員が退職して会社の社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失し、すぐに転職しない場合は、お住まいの市区町村役場で「国民健康保険」および「国民年金」への加入手続きを本人が行わなければなりません。
この手続きには、通常「雇用保険被保険者離職票(離職票)」などの退職を証明する書類が必要となります。 しかし、離職票は会社がハローワークで手続きを行った後に交付されるため、発行までに数日から1週間以上かかることもあり、手続きの期限に間に合わない場合があります。
そのような場合に、自治体の窓口では離職票が届くまでの「一時的な代替資料」として、会社が発行した退職証明書が利用できることがあります。 企業担当者としては、退職者から「離職票が届くまでのつなぎとして、国民健康保険の手続きに使いたい」と依頼される可能性があることを念頭に置き、迅速に対応できるように準備しておくとよいでしょう。
失業給付の仮手続きで離職票の代替として使うとき
退職後に失業給付(雇用保険の基本手当)を受給するためには、原則としてハローワークが発行する「雇用保険被保険者離職票(1・2)」が必須です。
しかし、会社の離職票発行手続きが遅れているなどの理由で、退職者がすぐに離職票を準備できない場合でも、失業給付の「仮手続き(求職申込みや受給資格確認)」を進めることは可能です。 この際、退職の事実を証明する書類として会社が発行した退職証明書を提出すれば、ハローワークが手続きを進めてくれる場合があります。
ただし、これはあくまで補助的な扱いであり、後日、正式な離職票をハローワークへ提出しなければなりません。 企業担当者としては、退職証明書の発行と並行して、離職票の発行手続きも遅滞なく進める必要があることを認識しておきましょう。
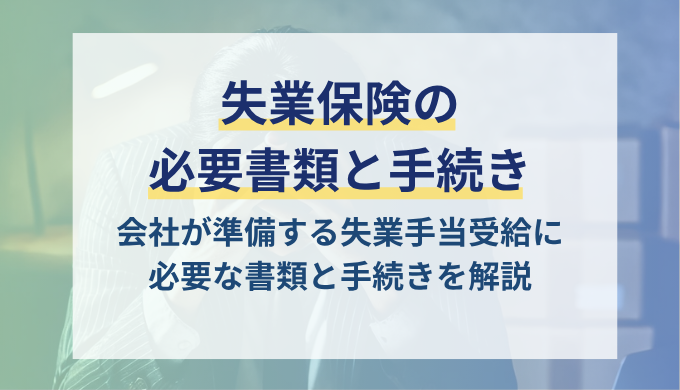 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職証明書と混同されがちな書類として、「離職票」「解雇理由証明書」「在籍証明書」があります。それぞれの役割や目的は異なるため、違いをしっかり理解しておくことが重要です。
これらの書類は、それぞれ発行元、目的、法的な位置づけが全く異なるため、その違いを正確に理解しておくことが、手続きのミスを防ぎ、従業員への適切な案内につながります。
離職票との違い
退職証明書と離職票は、退職時に発行される点で共通していますが、その役割と発行プロセスは根本的に異なります。
退職証明書が「会社が発行する私文書」であるのに対し、離職票は「ハローワークが発行する公文書」です。
その最も大きな違いは、失業給付(雇用保険の基本手当)の申請に使えるかどうかという点です。 失業給付の申請に必須となるのはハローワークが発行する離職票であり、会社が発行する退職証明書では原則として申請できません。
【退職証明書と離職票の主な違い】
| 比較項目 | 退職証明書 | 雇用保険被保険者離職票(離職票) |
| 発行元 | 会社(使用者) | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 法的性質 | 私文書 | 公文書 |
| 主な目的 | ・転職先への在籍証明 ・国民健康保険/年金の手続き | 失業給付(雇用保険)の受給手続き |
| 発行の要件 | 従業員から請求があった場合に発行義務発生 | 原則、退職者(被保険者)が希望する場合に会社が手続きを行い交付 |
| 主な記載内容 | 労働者が請求した事項のみ(使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職事由) | 雇用保険の加入履歴、退職理由、退職前6ヶ月間の賃金情報など |
また、発行プロセスにも明確な違いがあります。退職証明書は会社が単独で作成・発行できますが、離職票の発行には、会社がまず「雇用保険被保険者離職証明書」という別の書類を作成してハローワークへ提出し、それに基づいてハローワークから交付される、という連携した事務処理が必要となります。
企業担当者としては、「離職票はハローワークでの失業給付手続きに使う公的な書類」、「退職証明書は退職者から個別に依頼された場合に会社が発行する私的な証明書」と覚えておくことが重要です。
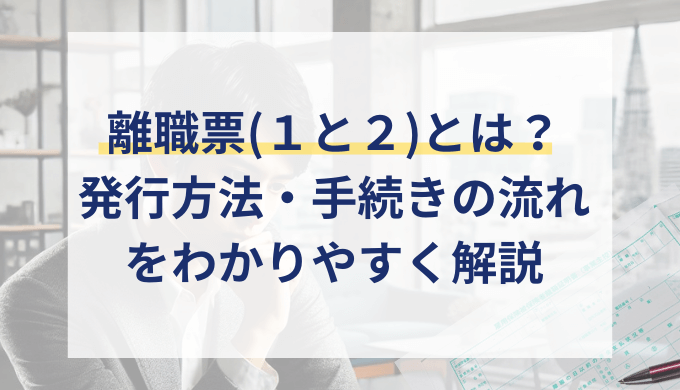 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
解雇理由証明書・在籍証明書との違い
退職証明書の他に、手続き上混同しやすい書類として「解雇理由証明書」と「在籍証明書」があります。退職証明書は退職に関する情報を広く証明できる柔軟な書類ですが、これら二つはより専門的な目的のために発行されます。
この証明書は、労働者が解雇された場合に、その具体的な理由を証明するための書類です。労働基準法第22条第2項では、解雇された労働者がその理由について証明書を請求した場合、会社(使用者)は遅滞なく交付しなければならないと定められています。
退職証明書にも退職理由の一つとして「解雇」の事実を記載することはできますが、解雇理由証明書は「なぜ解雇に至ったのか」という理由に特化して、就業規則の該当条文などを含め詳細に記載する点で異なります。 主に、解雇の妥当性を争う場面などで使用されます。
この証明書は、「従業員が現在その会社に在籍していること」を証明する書類です。 住宅ローンの審査、賃貸契約、あるいは子どもの保育園入園手続きなど、安定した収入や就労状況の証明が求められる場面で利用されます。
退職の事実を証明する退職証明書とは異なり、在籍中の従業員に対して発行されるのが原則です。記載内容も、一般的に氏名、在籍期間、所属部署といった在籍の事実を証明する項目に限られ、退職事由や賃金情報などは含まれません。
職証明書の作成にあたって、何をどのように記載すればよいのかは、担当者が最も迷うポイントです。
まず大原則として、退職証明書には「退職した従業員が請求した事項のみを記載する」というルールを必ず守らなければなりません。
労働基準法では、労働者が希望しない事項を会社が任意で記載することを禁止しています。 会社が良かれと思って請求されていない項目まで記載すると、かえってトラブルの原因となる可能性もあるため、注意が必要です。
ここでは、厚生労働省が示す様式も参考にしつつ、具体的な記載事項とそれぞれの書き方のポイントを詳しく解説します。
以下は、厚生労働省の様式を参考に作成したテンプレート(雛形)です。企業側でこの様式を参考に、独自のフォーマットを作成・使用して問題ありません。
▼退職証明書のテンプレート(雛形)
厚生労働省や東京労働局のHPで配布されている「退職証明書」のテンプレートには、「解雇理由証明書」も添付されています。
法律で定められた5つの証明事項と記載例
労働基準法第22条では、従業員から請求があった場合に会社が証明しなければならない事項として、以下の5つが定められています。 これらが退職証明書の基本的な記載項目となります。
しかし、実際に証明書に記載するのは、その5項目の中から従業員本人が「記載してほしい」と希望(請求)した項目だけです。
例えば、従業員が「使用期間と業務の種類だけ記載してください」と希望した場合、会社は賃金や退職理由などを記載してはならず、希望された2つの項目のみを記載した退職証明書を発行しなければなりません。
従業員が希望していない情報を会社が勝手に記載することは、法律で禁止されています。
従業員がその会社で勤務した期間を具体的に記載します。
◯書き方
「YYYY年MM月DD日 ~ YYYY年MM月DD日」のように、入社日から退職日までを正確に記入してください。 有給休暇の消化期間も在籍期間に含まれるため、最終的な退職日を記載する必要があります。
従業員が在籍中に主に従事していた業務内容を記載します。
◯書き方
「営業職」「経理事務」「システムエンジニア」など、具体的な職種を記載します。 複数の業務を経験している場合は、本人の希望に応じて主要なものを記載するか、複数列記します。
退職時点での最終的な役職や社内での立場を記載します。
◯書き方
「営業部 課長」「企画部 主任」のように、最終的な所属部署と役職名を正確に記載してください。 特に役職がなかった場合は「一般社員」などとします。
退職時の賃金額を記載します。
◯書き方
月給制であれば退職直近の月給総額、年俸制であれば年収など、どの期間の賃金を記載するかは本人の希望を確認します。 税金や社会保険料が控除される前の「総支給額」を記載するのが一般的です。
退職に至った理由を記載します。 この項目は特に慎重な対応が求められ、必ず事実に基づき、客観的に記載しなければなりません。
◯自己都合退職の場合:「一身上の都合により退職」が基本
従業員自らの意思で退職した場合は、退職届の記載に合わせて「自己都合による退職」または「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。
◯会社都合退職(退職勧奨など)の場合の注意点
経営上の理由による人員整理や、退職勧奨に応じて従業員が退職に合意した場合は、「当社勧奨による退職」や「事業部門縮小のため」など、事実を客観的に記載します。 退職者と合意した内容を正確に反映させることが重要です。
◯解雇の場合:具体的かつ客観的な理由の記載が紛争を防ぐ
従業員を解雇し、本人から理由の記載を求められた場合は、その具体的な理由まで記載する義務があります。 その際は、就業規則のどの条項に違反したのか、そしてその条項に該当する具体的な事実を客観的に記載する必要があります。
(例:「就業規則第〇条〇号(●●の事実)に該当するため、YYYY年MM月DD日付をもって懲戒解雇」) 感情的な表現や憶測を避け、事実のみを淡々と記載することが、将来の労使トラブルを防ぐ上で極めて重要です。
従業員の希望に応じて記載する項目
繰り返しになりますが、退職証明書に記載すべきなのは、あくまで退職した従業員本人が請求した項目のみです。
例えば、従業員が「使用期間と業務の種類だけ証明してほしい」と希望した場合、企業は賃金や退職理由を記載する必要はなく、むしろ記載してはいけません。
証明書を作成する前には、必ず本人にどの項目の記載を希望するのかをヒアリングし、その要望に沿って作成することを徹底してください。
退職証明書の発行手続きは、定められたステップに沿って進めることで、ミスなく迅速に対応できます。
従業員との不要なトラブルを避け、円滑な退職手続きを完了させるために、社内での基本的な業務フローを確立しておきましょう。
従業員からの請求を受けたらまず確認すること
退職する従業員から証明書の発行依頼を受けたら、まず「どの項目の証明を希望するのか」を正確に確認することが最も重要です。
前述の通り、会社は従業員が希望していない項目を記載してはなりません。 口頭での確認は「言った・言わない」のトラブルになりかねないため、メールや簡単なチェックシートを用いて、どの項目(使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由)が必要なのかを、書面やデータで明確に回答してもらうようにし、証拠を残すことが望ましいです。
あわせて、以下の点も確認しておきましょう。
- 証明書の用途(転職先へ提出、国民健康保険の手続きなど)
- 受取方法の希望(最終出社日に手渡し、郵送など)
- 郵送先住所(郵送を希望する場合)
記載内容の確認と書類作成
従業員が希望する記載事項が確定したら、その内容に基づき書類を作成します。その際、記載する情報が社内の公式な記録と一致しているか、必ず確認しなければなりません。
記載内容の正しさを担保するため、以下の社内書類などを参照してください。
- 労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書
- 就業規則(特に役職や賃金に関する規定)
- 過去の給与明細や賞与明細
これらの書類を基に、使用期間、業務の種類、最終役職、賃金額などに誤りがないかを確認します。
特に退職理由を記載する場合は、ハローワークへ提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の記載内容と矛盾が生じないように、整合性を取ることが極めて重要です。 内容が異なると、後日、従業員の失業給付受給などで問題が発生する可能性があります。
これらの確認が完了したら、会社のテンプレートや厚生労働省の様式を参考に、正確な日付、表記ゆれのない役職名や金額、客観的な事実に基づいた退職理由を記載して、証明書を完成させます。
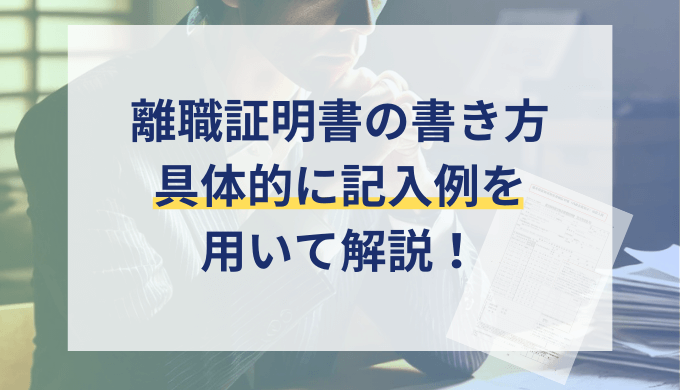 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
退職証明書の交付とその後の対応
作成した退職証明書は、従業員の希望する交付方法(最終出社日に手渡し、または郵送など)で、「遅滞なく」速やかに交付します。 スムーズな交付は、従業員との信頼関係を維持する上で重要です。
また、交付後の対応として、以下の2点を社内ルールとして徹底することを強く推奨します。
1. 交付記録の保管
トラブルを防ぐために、発行日、交付日、交付方法(手渡しか郵送かなど)を記録として残しておきましょう。退職に関する書類をいつ、どのように本人へ渡したかを明確にしておくことは、企業の責任ある対応を示す上で有効です。
2. 発行した証明書コピーの保管
発行した退職証明書のコピー(控え)を保管しておくことも重要です。 法律でコピーの保管が義務付けられているわけではありませんが、保管には以下のメリットがあります。
- 再発行依頼へのスムーズな対応
- トラブル発生時の記録
保管期間については、労働基準法で労働者名簿などの書類の保管期間が5年間と定められていることを踏まえ、それに合わせて最低でも5年間保管するのが望ましいでしょう。
| 退職証明書の発行準備・交付対応リスト[ ] 従業員本人に記載希望項目を確認したか [ ] 労働者名簿や賃金台帳と記載内容に相違はないか [ ] 離職票の記載内容と矛盾はないか [ ] 交付日と交付方法を記録したか [ ] 発行した証明書のコピーを保管したか |
このように、退職証明書の発行は単なる事務作業ではなく、法令遵守と円滑な労務対応に欠かせない業務です。
退職証明書の作成は、単に様式を埋めるだけの作業ではありません。法令で定められたルールを遵守することはもちろん、将来の労務トラブルを未然に防ぐための実務上のポイントがいくつか存在します。
ここで解説する注意点を正確に理解しておくことが、企業のリスク管理と従業員との円満な関係維持につながります。
退職者が希望しない項目は記載禁止
退職証明書を作成する上で最も重要なルールは、「退職者が請求していない事項は、一切記載してはならない」という点です。
これは労働基準法第22条で定められた、労働者を守るための重要な決まりです。 たとえ会社が良かれと思ったとしても、本人が希望していない退職理由や賃金額などを記載すると、その情報が本人の再就職活動で不利に働く可能性があり、法律違反となる場合があります。
必ず証明書を作成する前に、どの項目の証明が必要なのかを本人に確認し、その請求内容通りの証明書を発行することを徹底してください。
離職票・賃金台帳と矛盾がないようにする
退職証明書に記載する内容は、すべて客観的な事実であり、賃金台帳や労働者名簿といった会社の公式な記録と完全に一致している必要があります。
特に注意すべきなのが、退職理由や賃金額など、ハローワークへ提出する「雇用保険被保険者離職証明書」(離職票の元となる書類)と重複する項目です。 これらの情報に矛盾があると、従業員が失業給付を申請する際にハローワークから確認が入るなど、手続きが滞る原因となります。
必ず社内の複数資料を確認し、他書類との整合性が取れた、正確な内容を記載してください。
ハンコ・印鑑を求められる場合があるため、念のため社印を押しておく
退職証明書への押印は、法律で義務付けられているわけではありません。しかし、証明書の信頼性を担保し、提出先での無用な混乱を避けるためにも、会社の社印(角印)を押印しておくことを強く推奨します。
転職先企業や市区町村の窓口担当者によっては、押印がないことを理由に、書類の信憑性を疑問視したり、受理をためらったりするケースも考えられます。
退職者がスムーズに手続きを進められるよう、発行者である会社の名称・所在地・代表者名を記載した上で、社印を押印するのが最も丁寧な対応です。
ここでは、退職証明書に関して、人事・労務担当者や従業員からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
退職証明書はハローワークで発行してもらえる?
ハローワーク(公共職業安定所)では退職証明書を発行することはできません。
退職証明書は、あくまで「その会社に在籍していた事実」を証明する私文書であり、発行できるのは元々勤務していた会社(使用者)のみです。
ハローワークが発行するのは、失業給付の受給手続きに必要な「雇用保険被保険者離職票(離職票)」という公文書であり、退職証明書とは役割が全く異なります。
自分で退職証明書を作成できますか?(退職者からよくある質問)
退職した従業員本人が自分で退職証明書を作成することはできません。
退職証明書は、第三者である会社(使用者)が、その従業員の在籍期間や業務内容などを客観的に証明するからこそ効力を持つ書類です。本人が作成したものでは証明にならず、転職先企業や行政機関へ提出する正式な書類として認められません。
退職証明書が必要な場合は、必ず退職した会社に発行を請求してください。
退職証明書の発行期限は?
退職証明書の発行期限は、「会社側(発行する側)」と「従業員側(請求する側)」でそれぞれ押さえるべきポイントが異なります。
◯会社側の発行期限
労働基準法第22条により、従業員から請求があった場合、会社は**「遅滞なく」**発行しなければならないと定められています。 正当な理由なく発行を遅らせることは、法律違反となる可能性があります。
◯従業員側の請求期限
従業員が会社に対して退職証明書の発行を請求できる権利は、退職日から2年間です。 これは労働基準法第115条の時効の規定に基づくものです。
パート・アルバイトにも発行義務はある?
労働基準法は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての「労働者」に適用されます。
したがって、パートタイマーやアルバイトの従業員から退職証明書の発行を請求された場合でも、会社は正社員と同様に、遅滞なく証明書を発行する義務を負います。
従業員の退職時には、退職証明書の発行以外にも、社会保険・雇用保険の手続きから税務処理まで、会社として対応すべき法的な手続きが数多く存在します。これらの手続きを正確かつ期限内に完了させることが、法令遵守と円滑な退職処理の実現に不可欠です。
まず、従業員が退職する際に会社側が行うべき手続きの全体像と時間軸を、以下のタイムラインでご確認ください。このスケジュール全体を踏まえた上で、特に重要となる退職日以降の主要な手続き3つを、この後詳しく解説します。
それでは、上記タイムラインの中でも特に重要な「社会保険の資格喪失手続き」「住民税の手続き」「源泉徴収票の発行」について、それぞれ見ていきましょう。
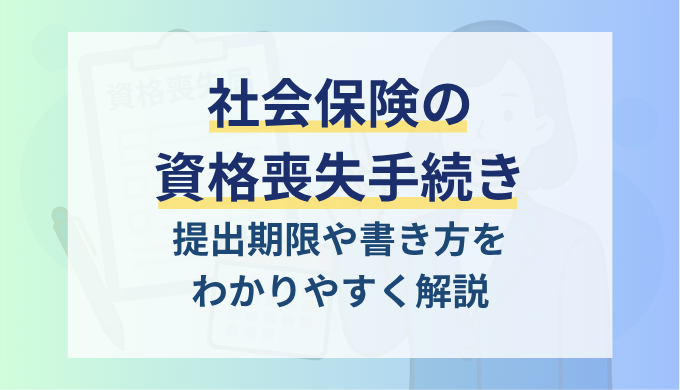 社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
離職証明書の作成とハローワークへの提出
退職した従業員が失業給付(基本手当)の受給を希望する場合、会社は「雇用保険被保険者離職証明書」を作成し、管轄のハローワークへ提出する義務があります。 この手続きを経て、ハローワークから本人宛に「離職票」が交付されます。
| 提出期限 | 従業員の退職日の翌日から10日以内 |
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
従業員が退職すると、会社の健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、その手続きが必要です。
会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成し、日本年金機構(または加入している健康保険組合)へ提出します。 この際、退職する従業員本人およびその被扶養者全員分の健康保険証を回収し、届出書に添付しなければなりません。
| 提出期限 | 退職日の翌日から5日以内 |
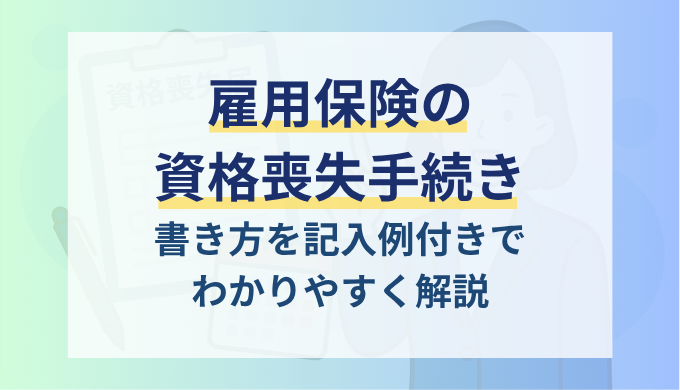 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
離職証明書の作成とハローワークへの提出
離職証明書の提出とは別に、雇用保険の被保険者資格を喪失したこと自体を届け出る手続きも必要です。
会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成し、管轄のハローワークへ提出します。 この手続きは、多くの場合、前述の「離職証明書」と同時に提出します。
| 提出期限 | 退職日の翌日から10日以内 |
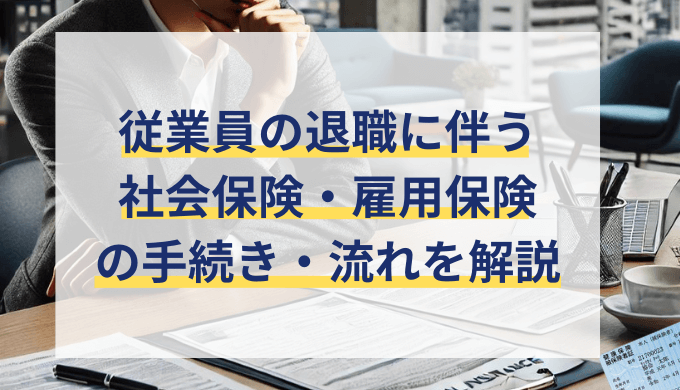 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
その他、住民税、源泉徴収票の作成・交付に関する手続き
社会保険・労働保険の手続きに加え、税金に関する以下の対応も必要です。
退職する従業員のその年の住民税のうち、未納分をどのように納付するかを確認し、手続きを行います。退職時期に応じて、最終給与から一括で天引きする「一括徴収」か、従業員本人が後日自分で納付する「普通徴収」に切り替えるかの対応を取り、市区町村へ届け出ます。
会社は、その年に支払った給与や天引きした所得税額を記載した「源泉徴収票」を作成し、退職した従業員へ交付する義務があります。 この源泉徴収票は、従業員が転職先での年末調整や、自身での確定申告の際に必要となる重要な書類です。
| 交付期限 | 退職日から1ヶ月以内 |
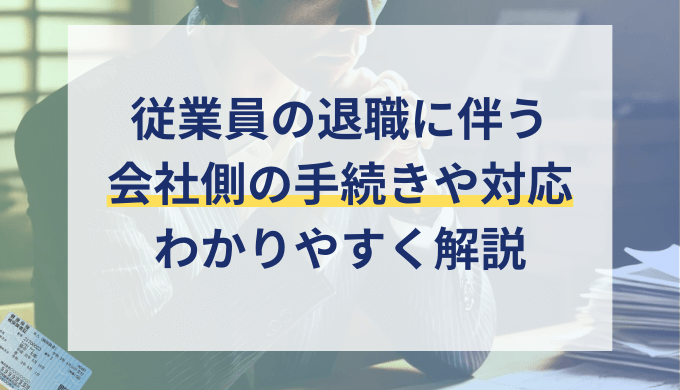 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
退職証明書は、従業員の退職時に会社が交付すべき重要な文書であり、単なる事務処理ではなく、労働基準法で明確に義務付けられた実務対応です。とくに、退職者本人から請求があった場合には、企業側は遅滞なく発行する必要があります。
企業として押さえておくべき基本ポイントは以下のとおりです。
- 発行は退職者からの請求があった場合に限り義務が発生する
労働基準法第22条により明記されています。 - 記載内容は退職者が希望する項目のみ
不要な情報の記載はトラブルやプライバシー侵害の原因になります。 - 記載内容は社内の公式記録と整合性をとる
賃金台帳や離職票など他の書類と内容が矛盾しないようにしましょう。 - 発行した証明書はコピーを社内で保管しておく
法定義務ではありませんが、トラブル対応の観点から最低2年、できれば5年間の保管が推奨されます。
退職証明書の正確かつ迅速な発行は、企業の法令遵守体制を示すだけでなく、退職する従業員との良好な関係を維持するための最後の重要なコミュニケーションです。
従業員の退職時には、社会保険・雇用保険の資格喪失手続きや税務処理など、専門知識を要する多くの業務が発生します。もし、これらの手続きに少しでも不安がある場合や、コア業務に集中するために手続き業務を効率化したいとお考えの場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
スポット申請代行サービスの社労士クラウド
従業員の退職時には、この記事で解説した退職証明書の発行のほか、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職証明書」の作成、社会保険の資格喪失手続きなど、提出期限も短く、専門的な知識が求められる業務が集中します。
- 「退職証明書の書き方や記載事項の判断に自信がない…」
- 「離職票との違いや、社会保険の手続きも漏れなく対応できるか不安…」
- 「コア業務が忙しく、退職者一人ひとりの手続きにまで手が回らない…」
このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスをご検討ください。
当サービスでは、退職証明書の作成サポートはもちろん、一連の退職手続きを、顧問契約不要で、必要な業務だけ1件から社会保険労務士にご依頼いただけます。「従業員1名の退職手続き一式をお願いしたい」「退職証明書と離職証明書の作成だけを代行してほしい」といった、お客様の状況に合わせたご依頼にも柔軟に対応いたします。
専門家である社労士が、最新の法令に基づいて正確かつ迅速に手続きを代行しますので、お客様は面倒な手続きから解放され、貴重な時間をコア業務に集中させることが可能です。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|