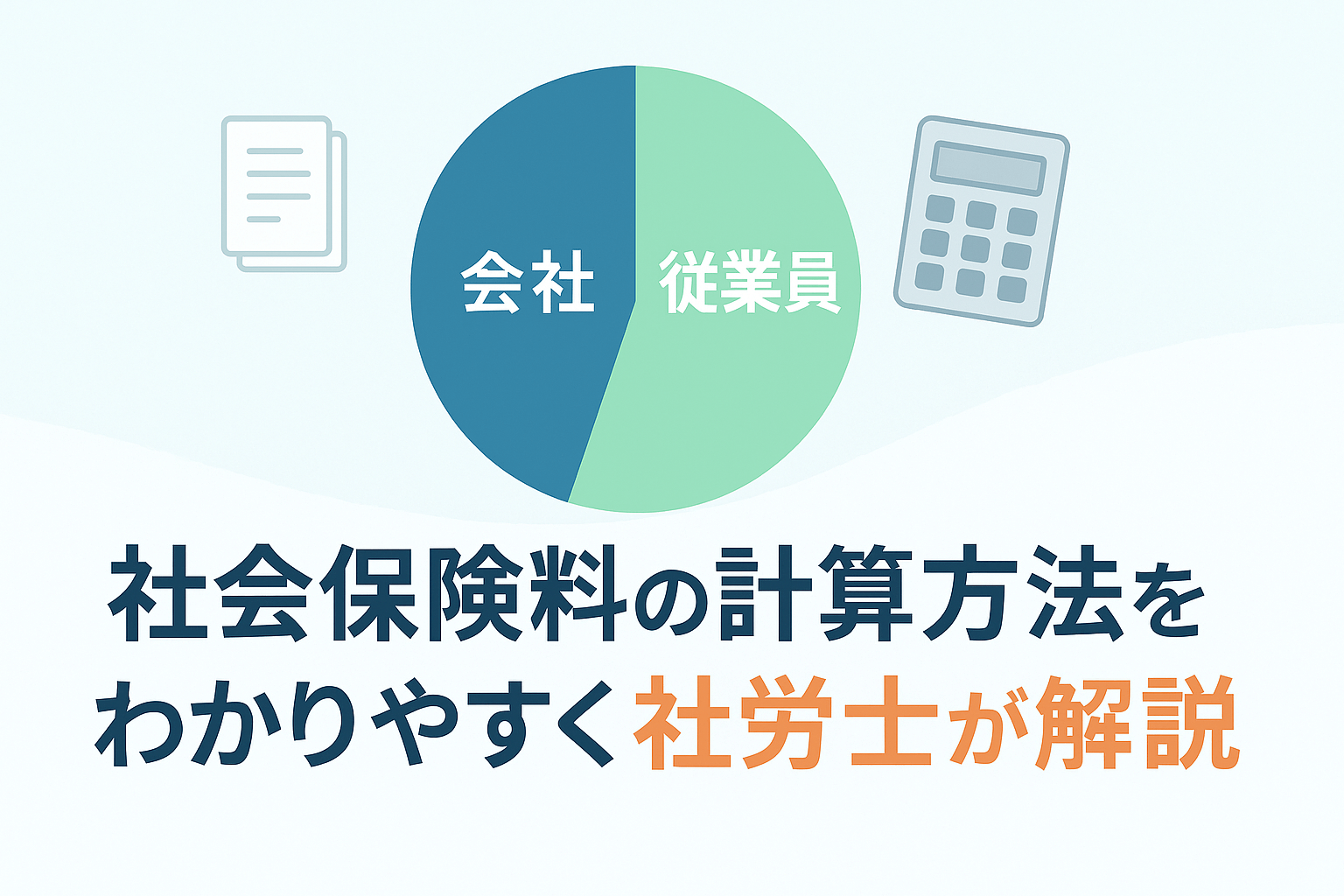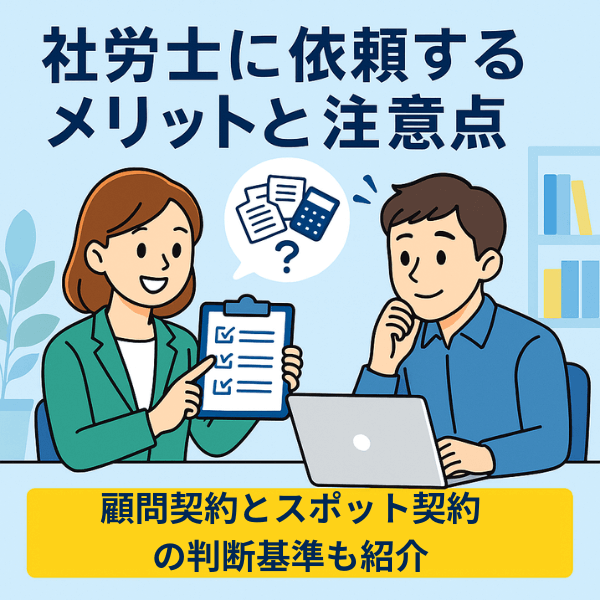雇用保険は、従業員の生活と雇用の安定を支える公的な保険制度です。従業員を一人でも雇用すれば、事業主には法律に基づく加入手続きと保険料の納付が義務付けられますが、その手続きは複雑で、届出の遅れはトラブルの原因にもなりかねません。
この記事では、雇用保険の概要と役割、加入条件、各種手続き、保険料の計算、そして2025年の法改正のポイントを合わせて分かりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定を守り、再就職を促進するための公的な保険制度です 。万が一、従業員が失業して収入が途絶えた場合や、育児・介護で一時的に休業する場合に、生活を支えるための給付金を支給する重要な役割を担っています。
この雇用保険制度は、大きく分けて2つの機能を持っています。
1.失業等給付(セーフティネット機能)
失業した場合の「基本手当(いわゆる失業手当)」 や、育児休業・介護休業を取得した際の「雇用継続給付」 など、労働者が安心して生活を送り、再就職活動や休業に専念できるよう経済的に支援する役割です。
2.雇用保険二事業(雇用の安定と能力開発)
労働者のスキルアップを支援する「能力開発事業」 と、事業主による雇用の維持や新たな雇用創出をサポートする「雇用安定事業」(各種助成金など) から成り立っています。
このように、雇用保険は単に失業したときのためだけではなく、労働者が働き続けられる環境を整え、企業の雇用を支えるための多面的な制度です。事業主には、要件を満たす従業員を雇用保険に加入させる法的な義務があります。
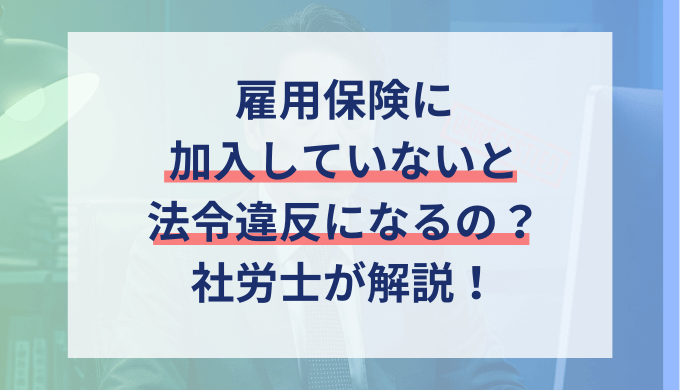 雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
社会保険との違い
社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険は、どちらも労働者の生活を守るための制度ですが、対象とするリスクや手続きの窓口、保険料の計算方法が異なります 。
| 社会保険(狭義) | 主に業務外での病気・ケガ、老齢、死亡に備える制度 |
| 労働保険(雇用保険・労災保険) | 主に失業や休業、労働災害に備える制度 |
給与計算を行う際は、これらの制度の違いを理解し、「社会保険料」と「労働保険料(雇用保険料)」を正しく区別して控除する必要があります。
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金保険など) | 労働保険(雇用保険・労災保険) |
| 主な目的 | 業務外の病気やケガ、老齢・障害への備え | 失業予防、雇用安定、労働災害への備え |
| 管轄 | 日本年金機構、健康保険組合 | ハローワーク、労働基準監督署 |
| 保険料計算の基礎 | 標準報酬月額 | 賃金総額 |
特に、保険料の計算基礎が「標準報酬月額」か「賃金総額」かという点は、給与計算実務における重要な違いとなるため、正確に理解しておく必要があります。
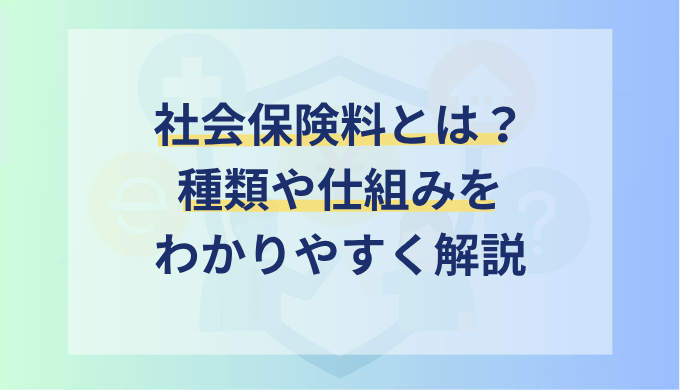 社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
社会保険料とは?種類や内訳、会社の負担割合や仕組みをわかりやすく簡単に解説
【2025年4月~順次施行】雇用保険法の改正について
2025年度(令和7年度)から雇用保険法が改正され、育児中の従業員への支援拡充や教育訓練給付の強化など、いくつかの重要な変更が順次施行されます 。事業主として、これらの変更点を事前に把握しておくことが重要です。
特に注目すべき主な改正点は以下の通りです。
◯雇用保険料率の変更(2025年4月1日~)
令和7年4月1日から雇用保険料率が変更されます 。失業等給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに見直されるため、給与計算に直接影響します 。
◯新たな育児関連給付の創設(2025年4月1日~)
育児休業給付とは別に、新たに「出生後休業支援給付」および「育児時短就業給付」が創設されます 。これらは、子ども・子育て支援金を財源としています 。
◯教育訓練給付の拡充(2025年10月1日~)
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、新たに「教育訓練休暇給付金」が創設されます 。
これらの法改正は、従業員の福利厚生や企業の労務管理に直接影響します。最新の情報を常に確認し、給与計算システムの更新や社内規定の見直しなど、適切な対応を準備する必要があります。
| 事業主が2025年の法改正で対応すべき実務のチェックリスト [ ] 就業規則や雇用契約書の更新:新たな休業・給付制度に対応した規定の見直し [ ] 給与計算システムの更新:新しい雇用保険料率への設定変更 [ ] 従業員への周知:保険料の変更や利用できる新制度に関する案内 [ ] 電子申請体制の整備:今後の手続き電子化の流れに対応できる準備 |
改正内容は年度ごとに追加・変更が予定されているため、厚生労働省の最新情報を確認し、「いつから」「誰に影響があるのか」「事業主のToDoは何か」を明確にして対応する必要があります。
雇用保険は、法律で定められた要件を満たす労働者を一人でも雇用した場合、事業主(会社・個人事業主)に加入手続きを行う義務が発生する強制保険制度です。事業の規模や業種を問わず、原則としてすべての事業が対象となります。
企業の経営者や労務担当者は、どの事業所が対象となり、どのような条件の従業員を加入させなければならないのかを正確に把握しておく必要があります。
加入義務が生じる適用事業所
労働者を一人でも雇用する事業所は、原則として「適用事業所」となり、雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。
これは、会社の設立直後や、個人事業主が初めて従業員を雇用するタイミングで必ず発生する法的な義務です。法人であるか個人事業主であるかを問わず、この原則は適用されます。
ただし、個人事業主で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の一部は、当面の間、任意適用事業とされています。
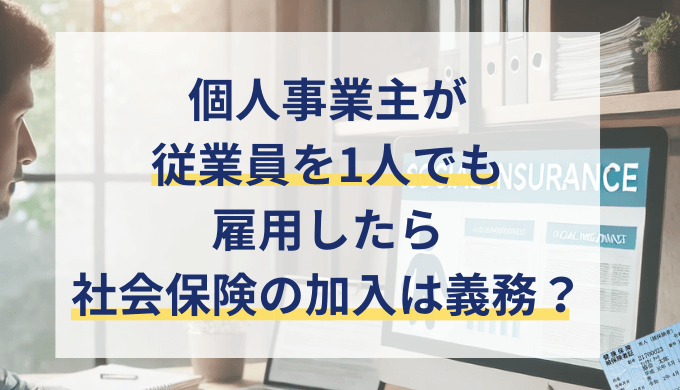 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
加入対象となる従業員の条件
適用事業所に雇用される従業員は、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)にかかわらず、以下の2つの要件を両方満たす場合に雇用保険の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則で定められた労働時間を指します。「31日以上の雇用見込み」とは、契約期間の定めがない場合や、契約期間が31日以上である場合、または31日未満であっても契約更新の可能性がある場合などが該当します。
なお、上記の条件を満たしていても、昼間学生(夜間や通信制、定時制の学生は除く)や、法人の代表取締役などは原則として加入対象外です。
被保険者区分の早見
雇用保険の被保険者は、働き方や年齢に応じていくつかの種類に区分されます。事業主は、従業員がどの区分に該当するかを正しく把握し、適切な手続きを行う必要があります。
| 区分 | 対象となる労働者 | 主なポイント |
| 一般被保険者 | 65歳未満の常用労働者など、下記の区分に該当しない労働者。 | 最も一般的な区分です。 |
| 高年齢被保険者 | 65歳以上の労働者で、短期雇用特例・日雇労働被保険者ではない者。 | 65歳に達すると自動的に一般被保険者から切り替わります。雇用保険料の労働者負担分・事業主負担分が免除されます。 |
| 短期雇用特例被保険者 | 季節的な業務に雇用される労働者(例:スキー場のスタッフ、農家の収穫作業員など)。 | 雇用期間が4ヶ月以上1年未満で、週の所定労働時間が30時間以上などの要件があります。失業した際は、基本手当ではなく「特例一時金」が支給されます。 |
| 日雇労働被保険者 | 日々雇用される、または30日以内の期間を定めて雇用される労働者。 | 一般の被保険者とは異なり、日雇労働被保険者手帳の交付を受け、賃金の支払いを受ける都度、印紙で保険料を納付します。 |
| マルチジョブホルダー | 複数の事業所で働く65歳以上の労働者で、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上になるなどの要件を満たす者。 | 1つの事業所では加入要件を満たさなくても、2つの事業所の労働時間を合算して加入できる制度です。本人がハローワークに申し出て手続きを行います。 |
雇用保険は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」という2つの要件を満たす労働者を雇用する場合、原則として加入が義務付けられています。
しかし、これらの要件を満たさない働き方の場合や、法律上「労働者」とみなされない立場の場合は、加入対象となりません。実務で判断に迷いやすい代表的なケースを整理します。
加入対象外となる主なケース(原則)
- 週の所定労働時間が20時間未満の労働者
雇用契約書で週の所定労働時間が20時間に満たないパートタイマーやアルバイトは、加入対象外です。シフト制で労働時間が変動する場合でも、契約上の平均労働時間で判断します。 - 31日以上の雇用見込みがない労働者
採用時点で30日以内に雇用契約が終了することが明確な、日雇いや短期のアルバイトは原則として加入対象外となります。 ※ただし、後述する「日雇労働被保険者」の制度に該当する場合があります。 - 昼間学生
大学や高等学校などの昼間部に在学中の学生は、学業が本分とされるため、原則として加入できません。ただし、休学中の学生や、夜間・通信・定時制の学生は加入対象となります。 - 法人の代表者・役員
代表取締役や取締役など、会社の役員は「労働者」ではないため、原則として加入できません。ただし、部長などを兼務し、労働者としての側面が強い「使用人兼務役員」は加入できる場合があります。 - 業務委託契約者や個人事業主
指揮命令関係のない業務委託契約や請負契約で働くフリーランスなどは、雇用契約ではないため対象外です。
以下のケースは「雇用保険に加入できない」わけではありませんが、一般的な労働者とは異なる別の被保険者区分として扱われます。手続きを誤ると手戻りが発生するため注意が必要です。
- 短期雇用特例被保険者
季節的な業務(例:農家の収穫作業)のために、4ヶ月以上1年未満の期間を定めて雇用される労働者が該当します。 - 日雇労働被保険者
日々雇用される、または30日以内の期間を定めて雇用される労働者が該当します。
| 加入対象外かどうかの最終確認チェックリスト [ ] 雇用契約書:所定労働時間が週20時間未満、または雇用期間が31日未満になっていないか? [ ] 学生の確認:昼間学生に該当しないか?(夜間・休学など例外に当たらないか証明書で確認) [ ] 役員の確認:労働者性のない代表取締役や役員ではないか? [ ] 契約形態の確認:業務委託契約ではなく、雇用契約であるか? [ ] 被保険者区分の確認:短期雇用特例や日雇労働被保険者に該当しないか?(該当する場合は一般被保険者で届出しない) [ ] 副業の確認:他社との労働時間を合算して「マルチジョブホルダー制度」の対象にならないか? |
事業主は、従業員の採用から退職までの各場面で、雇用保険に関する法的な手続きを適切に行う義務があります。手続きにはそれぞれ提出期限が定められており、特に入社時の届出と退職時の届出では期限の考え方が異なるため注意が必要です。
電子申請(e-Gov)を利用すれば、受付から公文書の受領までをオンラインで完結でき、業務の効率化に繋がります。
従業員が入社するときの加入手続き
従業員を雇用した場合、その事実があった日(入社日)の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークへ提出しなければなりません。
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | 電子申請(e-Gov)、郵送、または窓口持参 |
手続きが完了すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」と「資格取得確認通知書」が交付されるので、これらを従業員本人へ渡してください。
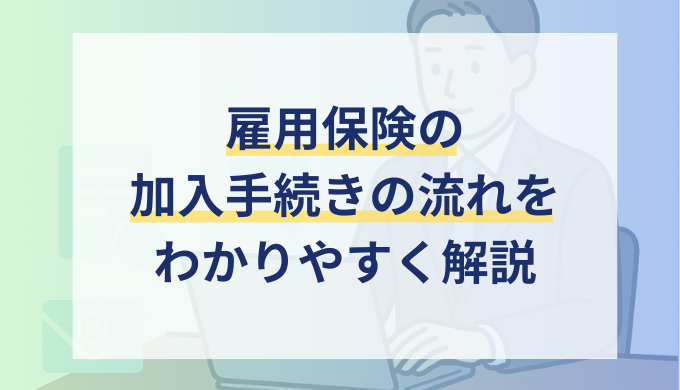 雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
 【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
従業員が退職するときの資格喪失手続き
従業員が退職した場合、その事実があった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。退職者が離職票の交付を希望する場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」もあわせて提出します。
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 添付書類 | 離職証明書を提出する場合、賃金台帳や出勤簿、退職理由がわかる書類(退職届など)が必要。 |
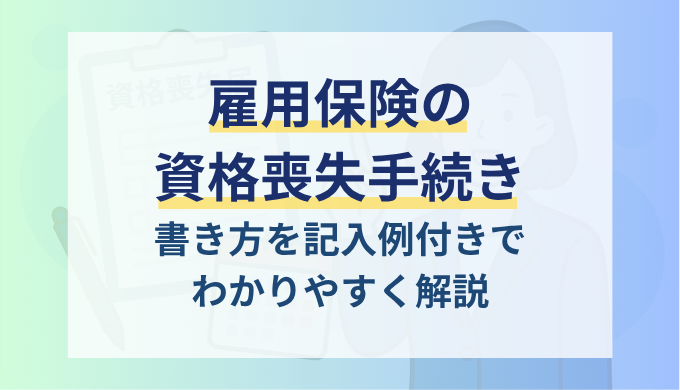 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介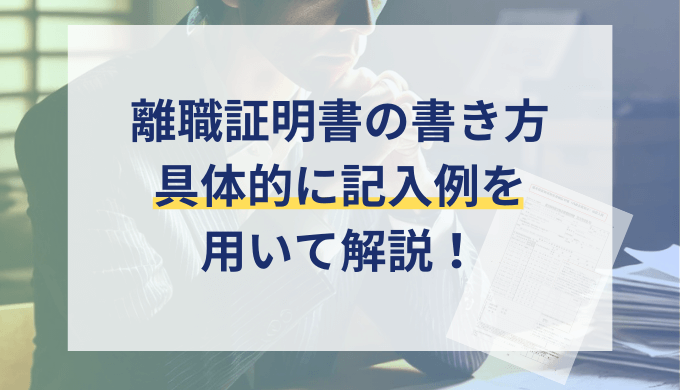 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説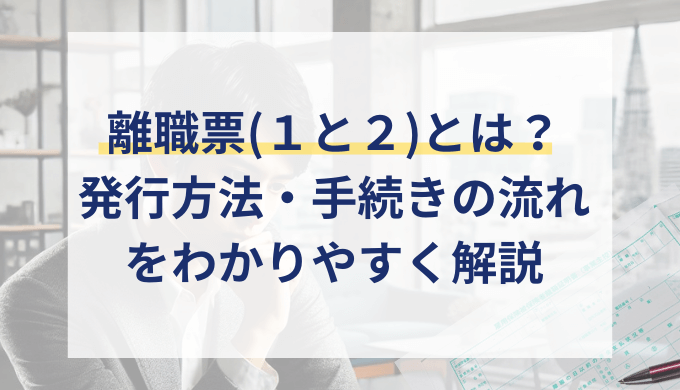 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
雇用保険の保険料率と計算方法
雇用保険料は、従業員に支払う毎月の給与や賞与の総額に、定められた「雇用保険料率」を掛けて算出します 。この保険料は、従業員(労働者)と事業主(会社)の双方が、それぞれ決められた負担割合に応じて納付します。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が「標準報酬月額」という基準額をもとに計算されるのに対し、雇用保険料は実際に支払われた賃金の総額(基本給、残業手当、通勤手当などを含む額面金額)が計算の基礎となる点が大きな違いです 。
| ■計算式雇用保険料 = 賃金総額(毎月の給与や賞与の額面) × 雇用保険料率 |
令和7年度の雇用保険料率と負担割合
雇用保険料率は、事業の種類によって異なり、毎年度見直されます 。令和7年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の雇用保険料率は以下の通りです 。
健康保険・厚生年金保険など、計算の基礎が異なる他の社会保険料の計算方法とあわせて、より詳しく確認したい場合は下記の記事が役立ちます。
また、社会保険料を簡易的に計算できるシミュレーションツールもご活用ください。
雇用保険の給付は、単に失業した場合だけでなく、労働者の生活安定やキャリア形成を支えるため、大きく分けて「求職者給付」「雇用継続給付」「教育訓練給付」「就職促進給付」の4つの系統に整理されています。
事業主としては、これらの制度を理解しておくことで、従業員への適切な情報提供や、自社で活用できる助成金の検討に繋がります。特に2025年度からは育児関連給付の新設や既存給付の見直しなど、重要な制度変更があるため、正確な知識のアップデートが不可欠です。
求職者給付(失業したとき)
求職者給付とは、従業員が離職し、次の就職先を探す間の生活を支えるための給付で、「基本手当(いわゆる失業手当)」がその中心です。
この給付を受けるためには、離職理由や雇用保険の加入期間など、一定の要件を満たした上で、本人がハローワークで求職の申込みを行う必要があります。
事業主は、退職する従業員へ「雇用保険被保険者離職票」を遅滞なく交付する義務があります。この離職票に記載する離職理由や賃金額が、給付内容に直接影響するため、正確な届出が極めて重要です。
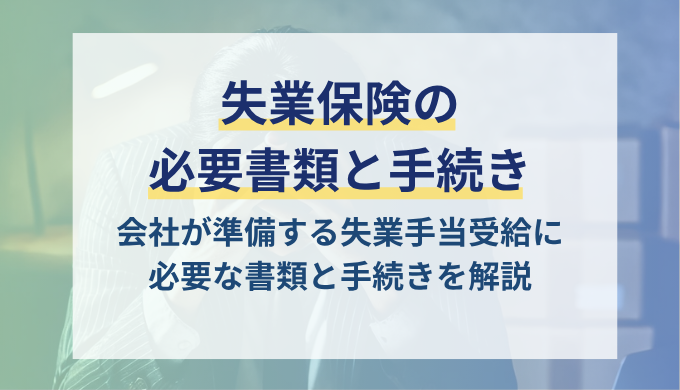 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
雇用継続給付(働き続けるため)
雇用継続給付とは、育児や介護、あるいは高齢といった理由で雇用の継続が難しくなる局面において、労働者が働き続けられるよう支援するための給付です。
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
- 高年齢雇用継続給付
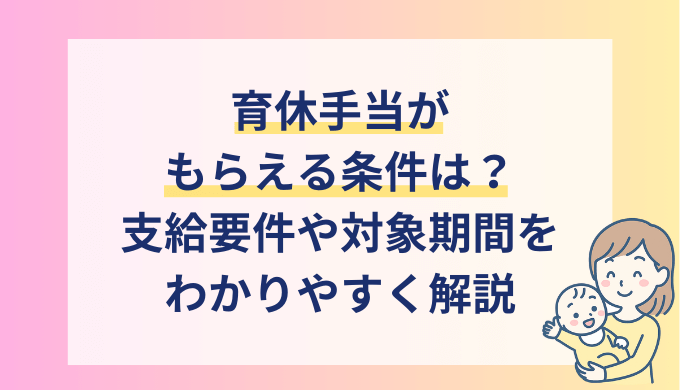 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
教育訓練給付(スキルアップのため)
教育訓練給付とは、労働者が主体的に能力開発やスキルアップに取り組むことを支援するための給付制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給されます。
従業員の自律的なキャリア形成を後押しするだけでなく、企業の人材育成施策と連携させることも可能です。
就職促進給付(再就職を後押しするため)
就職促進給付とは、失業中の労働者が一日でも早く安定した職業に再就職できるよう後押しするための給付です。代表的なものに、基本手当の受給資格がある人が早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」があります。
この給付についても、事業主が発行する離職票の内容が申請の基礎となるため、退職時の手続きを正確に行うことが、元従業員の円滑な再就職支援に繋がります。
雇用保険制度は複雑なため、実務では様々な疑問が生じます。ここでは、事業主や担当者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
雇用保険の納付方法は?
雇用保険料は、労災保険料とあわせて「労働保険料」として、年に一度まとめて申告・納付するのが原則です(これを「年度更新」といいます)。
事業主は、毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成して提出します。保険料の納付は、金融機関の窓口や口座振替、電子納付(e-Gov)などの方法で行うことができます。
なお、従業員から預かる雇用保険料(労働者負担分)は、毎月の給与や賞与を支払う都度、天引き(控除)しておく必要があります。
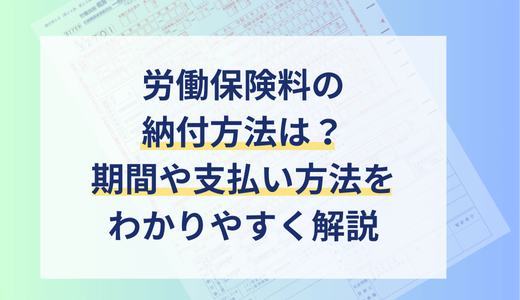 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
雇用保険とは失業保険のこと?
一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれているものは、正式には「雇用保険」制度の給付の一部である「基本手当」を指します。
歴史的には「失業保険法」という名称でしたが、失業時の給付だけでなく、育児・介護休業支援や能力開発支援など、より総合的な役割を担う現在の「雇用保険法」へと変わりました。そのため、現在では「雇用保険」が正式名称となります。
副業先でも雇用保険に入る?二重加入になる?
雇用保険は、複数の会社で同時に加入(二重加入)することはできません。従業員は、最も多くの賃金を受け取っている主要な勤務先(主たる事業所)でのみ、被保険者となります。
例えば、A社とB社で副業(ダブルワーク)をしていて、両方の会社で加入要件を満たしている場合でも、より賃金が高い方の会社でしか雇用保険に加入できません。
【例外:マルチジョブホルダー制度】
ただし、65歳以上の方に限り、例外的な制度があります。2つ以上の会社で働いていて、それぞれの会社では週20時間未満でも、2つの会社の労働時間を合計して週20時間以上になるなどの要件を満たせば、本人がハローワークに申し出ることで特別に雇用保険に加入できる「マルチジョブホルダー制度」が利用できます。
雇用保険は、失業・育児・介護などの事由で収入が減少した従業員を支える公的保険であり、助成金や教育訓練の仕組みを通じて雇用の安定と人材育成を後押しする制度です。労働者を一人でも雇用する事業主には、法律に基づく加入手続きと保険料の納付義務が課されます。
本記事では、制度の目的と役割、加入条件、入社・退職・変更時の手続き、保険料の計算方法、主要な給付(求職者給付・雇用継続給付・教育訓練給付・就職促進給付)まで、実務の順で解説しました。
入社・退職・資格変更の届出には期限があるため、事実発生日から速やかな提出が不可欠です。
雇用保険の料率や給付上限は年度ごとに更新され、2025年の見直しをはじめ、社会情勢に応じた制度改正が継続しています。最新の告示・通達・様式を定期的に確認し、給与計算・社内規程・案内文を適時アップデートしてください。
これらの複雑な手続きや法改正への対応に少しでも不安がある場合や、より本業に集中したい場合は、専門家である社会保険労務士(社労士)に相談することも検討しましょう。
スポット依頼ができる社労士クラウドについて
「雇用保険の手続きが複雑で、自社だけで対応するのは不安…」 「年に数回の手続きのために、顧問契約で毎月費用を払うのは負担が大きい…」 「必要な業務だけを、専門家にピンポイントで依頼したい」
このようなお悩みをお持ちの事業主様や人事担当者様には、「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスがおすすめです。
当サービスでは、雇用保険の各種手続きはもちろん、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など、専門知識が必要な手続きを顧問契約不要で、必要な業務だけを1件から社会保険労務士にご依頼いただけます。
専門家である社労士が、最新の法令に基づいて正確かつ迅速に手続きを代行しますので、お客様は面倒な手続き業務から解放され、貴重な時間をコア業務に集中させることが可能です。オンラインで全国どこからでも簡単にご依頼いただけますので、手続きに不安がある場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|