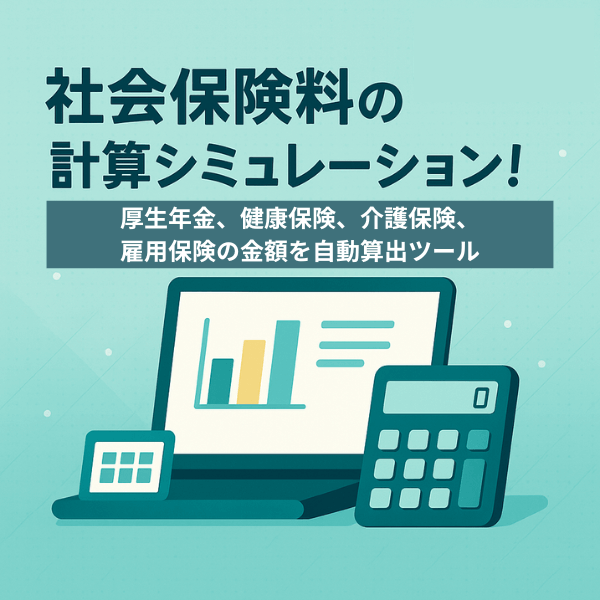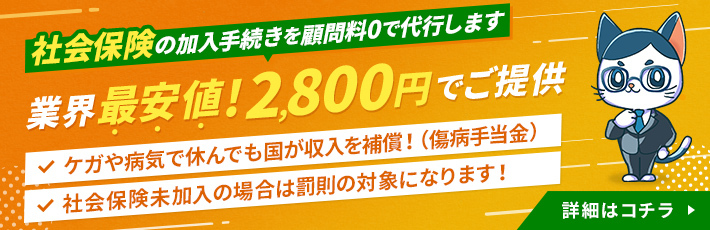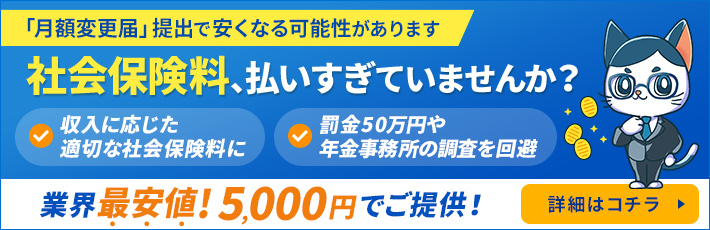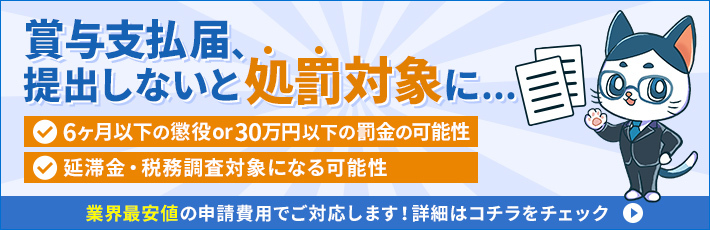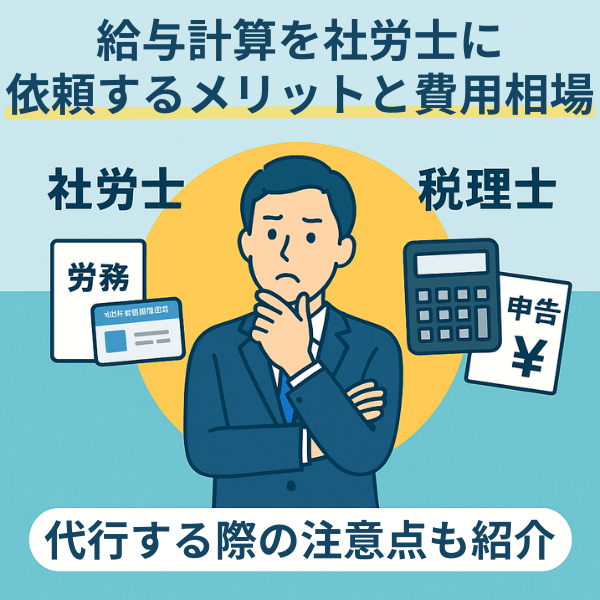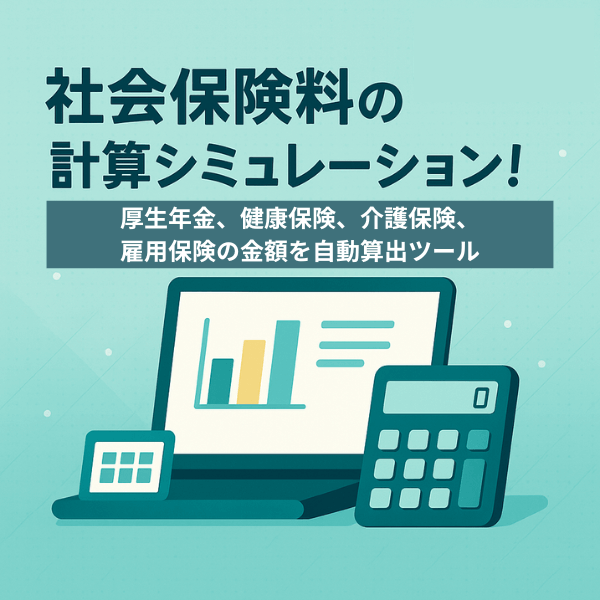
自動計算ツールで算出できる社会保険料には、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、そして標準報酬月額の金額と等級が含まれます。また早見表もご確認いただけます。
厚生年金保険料と健康保険料が計算シミュレーションできる社会保険料の自動計算ツールです。月給と賞与でタブを分けており、それぞれのケースで簡単に試算いただけます。
この自動計算ツールで算出できる社会保険料および関連情報には、主に以下のものが含まれます。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)
- 雇用保険料
- 適用される標準報酬月額の金額と等級
日々の業務や、従業員への説明資料作成など、様々なシーンでご活用ください。
社会保険料計算シミュレーション
計算結果
厚生年金保険
等級:
標準報酬月額: 円
保険料(労働者負担分): 円
健康保険
等級:
標準報酬月額: 円
保険料率: %
保険料(労働者負担分): 円
介護保険
保険料率: %
保険料(労働者負担分): 円
雇用保険
保険料率: %
保険料(労働者負担分): 円
社会保険料合計(月額)
円
事業主負担分
厚生年金保険: 円
健康保険: 円
介護保険: 円
雇用保険: 円
事業主負担 合計
円
ここでは、東京都の協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している従業員の方を例に、月収(報酬月額)別の社会保険料(従業員負担合計額)の概算をまとめた早見表をご紹介します。
従業員の方の年齢(40歳未満か、40歳以上65歳未満か)によって介護保険料の負担有無が変わるため、2つのケースに分けて掲載します。
| 報酬月額(目安) | 社会保険料 (40歳未満) | 社会保険料 (40歳以上65歳未満) |
|---|---|---|
| 200,000円 | 約 29,310円 | 約 31,110円 |
| 250,000円 | 約 38,043円 | 約 40,383円 |
| 300,000円 | 約 43,965円 | 約 46,665円 |
| 350,000円 | 約 52,698円 | 約 55,938円 |
| 400,000円 | 約 60,026円 | 約 63,746円 |
| 450,000円 | 約 64,542円 | 約 68,502円 |
| 500,000円 | 約 73,275円 | 約 77,775円 |
| 550,000円 | 約 82,008円 | 約 87,048円 |
| 600,000円 | 約 86,464円 | 約 91,774円 |
※ 報酬月額(目安):基本給のほか、役職手当、通勤手当、残業手当などを含んだ1ヶ月の総支給額です。この報酬月額を基に、協会けんぽの保険料額表に定められた「標準報酬月額」が決定されます。
年収ベースで社会保険料(従業員負担合計額)の概算を知りたいという方向けに、上記の月収別早見表を基にした年間の社会保険料の目安をご紹介します。
| 年収(目安) | 年間社会保険料 (40歳未満) | 年間社会保険料 (40歳以上65歳未満) |
|---|---|---|
| 2,400,000円 | 約 351,720円 | 約 373,320円 |
| 3,000,000円 | 約 456,516円 | 約 484,596円 |
| 3,600,000円 | 約 527,580円 | 約 559,980円 |
| 4,200,000円 | 約 632,376円 | 約 671,256円 |
| 4,800,000円 | 約 720,312円 | 約 764,952円 |
| 5,400,000円 | 約 774,504円 | 約 822,024円 |
| 6,000,000円 | 約 879,300円 | 約 933,300円 |
| 6,600,000円 | 約 984,096円 | 約 1,044,576円 |
| 7,200,000円 | 約 1,037,568円 | 約 1,101,288円 |
これらの早見表は、あくまで概算を把握するための参考としてご活用ください。 社会保険料の計算は、従業員の方の報酬額や年齢、加入している健康保険組合、そして毎年のように見直される保険料率など、多くの要素によって変動します。
下記、給与の手取り・控除額がシミュレーションできる給与計算ツールもあわせて活用ください。
> 給与(月収・年収・賞与)手取り計算シミュレーションツール【2025年版】
社会保険料や雇用保険料の計算に不安がある、専門家に確認してもらいたい事業主の方は、社労士に代行依頼することも検討しましょう。
社会保険料とは、会社員(役員を含む)が加入する国の社会保障制度である「健康保険」「介護保険(40歳以上65歳未満の場合)」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5つの保険にかかる保険料の総称です。
これらは、従業員やその家族の病気やケガ、老齢、失業、労働災害など、様々なリスクに備え、生活を保障するための重要な仕組みとなっています。
一般的に、このうち「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」をまとめて(狭義の)社会保険料と呼び、「雇用保険料」と「労災保険料」をまとめて労働保険料と呼ぶこともあります。
社会保険の計算に必要な標準報酬月額とは
健康保険料、厚生年金保険料、そして40歳以上65歳未満の方が負担する介護保険料。これらの社会保険料を計算する上で、最も基本となるのが「標準報酬月額」というものです。
「標準報酬月額」という言葉は少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言うと、従業員の方が受け取る毎月のお給料(基本給や各種手当などを含みます)を、キリの良い金額で区分した等級ごとの金額のことです。
この等級に応じて、毎月の社会保険料が決まります。
【関連記事】
> 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
> 賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
標準報酬月額の計算の基礎となる「報酬」には、基本給(月給・週給・日給など)のほか、役職手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当など、従業員が労働の対償として会社から経常的に受け取るものが、名称を問わず原則としてすべて含まれます。
ただし、お祝い金や見舞金のような臨時に受け取るものや、年3回以下の回数で支給される賞与(ボーナス)は、月々の報酬とは区別され、標準報酬月額の算定基礎には含まれません(賞与には別途「標準賞与額」に基づいて社会保険料がかかります)。
標準報酬月額は、一度決まったらずっと同じというわけではなく、いくつかのタイミングで見直されます。
主なタイミングは以下の通りです。
- 資格取得時決定(入社時など)
- 定時決定(算定基礎届)
- 随時改定(月額変更届)
- 育児休業等終了時改定
これらの決定・改定によって、従業員一人ひとりの標準報酬月額が設定され、それに基づいて毎月の社会保険料が計算されることになります。
【関連記事】
> 社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
> 算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
> 社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険の保険料は、事業主と従業員で折半します。労災保険の保険料は事業主が全額負担です。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険は、従業員の老後の生活や、万が一の障害・死亡に備えるための公的年金制度です。
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 (賞与の場合:標準賞与額 × 厚生年金保険料率)
※厚生年金保険料率は、現在(令和7年5月時点)、厚生年金保険料率は 18.3% で固定されています。この保険料率を従業員(被保険者)と会社(事業主)で半分ずつ負担しますので、それぞれ 9.15% ずつの負担となります。
健康保険料の計算方法
健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをした際の医療費負担を軽減したり、出産や死亡時に一時金を支給したりするための制度です。
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 (賞与の場合:標準賞与額 × 健康保険料率)
※健康保険料率は、加入している健康保険組合(例:協会けんぽ、組合健保など)によって異なります。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合
都道府県ごとに保険料率が設定されており、原則として毎年見直されます。 - 組合健保の場合
各健康保険組合が独自に保険料率を定めています。
健康保険料も、会社(事業主)と従業員(被保険者)で半分ずつ負担します(労使折半)。
※実際の保険料率は、必ず最新の協会けんぽの保険料額表や加入している健康保険組合の情報をご確認ください。
介護保険料の計算方法
介護保険は、高齢化社会を支えるため、40歳以上の国民が加入し、介護が必要になった際にサービスを受けるための財源となる保険制度です。
対象者:40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(第2号被保険者と呼ばれます)
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 (賞与の場合:標準賞与額 × 介護保険料率)
※介護保険料率は、介護保険料率も、加入している健康保険組合によって異なります。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合
全国一律の料率が定められており、健康保険料率とあわせて告知されます。原則として毎年見直されます。 - 組合健保の場合
各健康保険組合が独自に保険料率を定めています。
介護保険料も、健康保険料と同様に会社(事業主)と従業員(被保険者)で半分ずつ負担します(労使折半)。 40歳になると自動的に徴収が始まり、65歳になると徴収方法が変わります(通常は年金からの天引き)。
※実際の保険料率は、必ず最新の協会けんぽの保険料額表や加入している健康保険組合の情報をご確認ください。
雇用保険料の計算方法
雇用保険は、従業員の失業時の生活保障や再就職支援、育児・介護休業中の給付などを行うための制度です。
雇用保険料 = 毎月の賃金総額(※) × 雇用保険料率 (賞与の場合も同様に、賞与額 × 雇用保険料率)
- 毎月の賃金総額(※)
雇用保険料の計算基礎となるのは、健康保険料や厚生年金保険料で用いる「標準報酬月額」とは異なり、実際に支払われる税金や社会保険料控除前の賃金総額(基本給、諸手当、通勤手当、残業代などを含む) です。 - 雇用保険料率
雇用保険料率は、厚生労働省が毎年(または必要に応じて)決定し、事業の種類(一般の事業、農林水産業・清酒製造業、建設業など)によって異なります。また、従業員(労働者)負担分と会社(事業主)負担分の料率がそれぞれ定められています。
※雇用保険料率は年度や経済状況によって変動する可能性があるため、必ずその年度の最新の料率を厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
【関連記事】
> 社会保険料の計算方法を会社負担を含めてわかりやすく解説!