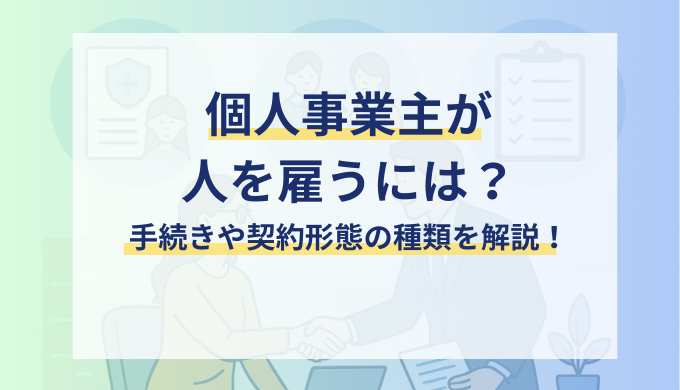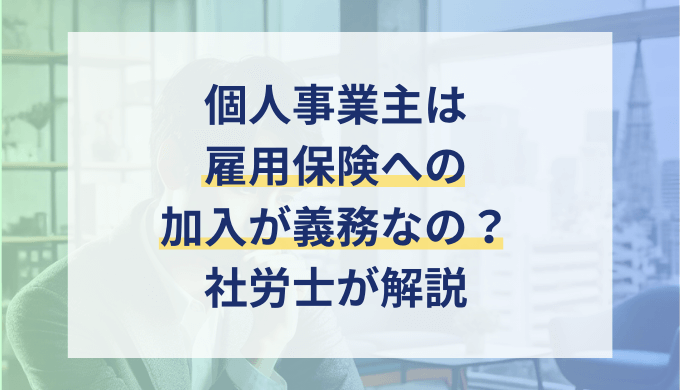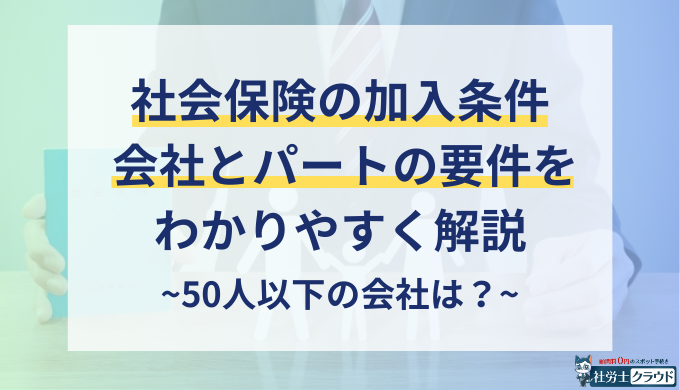事業が軌道に乗り「そろそろ人を雇って事業を拡大したい」と考えている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
しかし、人を一人雇うだけでも、社会保険や労働保険、税金など、これまで経験したことのない複雑な手続きや法的な責任が発生し、何から手をつければ良いか分からず不安に感じてしまいます。
本記事では、個人事業主が人を雇う際に必要な手続きや注意点、従業員を雇用するメリットとデメリットについて解説します。
また契約形態についても、期間の定めのない「正社員」や、働く時間が短い「パート・アルバイト」、そして仕事を外注する「業務委託契約」などがあります。それぞれの特徴を理解し、事業に合った手続きを進めることが大切です。
これから従業員を雇用しようとお考えの個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
個人事業主が従業員を雇う場合、契約・雇用形態は大きく3種類に分けられます。
具体的には、雇用契約を結ぶ「正社員」「パート・アルバイトなどの非正規雇用」、そして雇用契約ではなく仕事を外注する「業務委託(外注)」です。
どの形態を選ぶかによって、事業主が負う責任や必要な手続き、コストの仕組みが大きく変わります。まずはそれぞれの特徴を理解することが、適切な雇用形態を選ぶための第一歩です。
以下では、各形態のメリット・デメリットや必要な手続きを比較表で整理しましたので、ご自身の事業に最も合う形を検討してみましょう。
| 契約・雇用形態 | メリット | デメリット | 必要な手続き |
|---|---|---|---|
| 正社員 | ・安定した労働力を確保できる ・事業の核となる業務を任せられる | ・人件費や社会保険料の負担が大きい ・解雇には厳しい制約がある | ・労働条件通知書・雇用契約書の作成 ・労働保険(労災・雇用保険)の加入 ・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入 ・税務署への届出 ・源泉徴収 |
| パート・アルバイト | ・繁忙期など必要な時間だけ雇える ・人件費を調整しやすい | ・勤務時間が短く任せられる業務が限られる ・長期定着が難しいこともある | ・正社員とほぼ同じ ※労働時間により雇用保険 ・社会保険が不要な場合あり |
| 業務委託(外注) | ・社会保険料の負担がない ・専門スキルを必要な時だけ活用できる | ・業務の進め方を細かく指示できない ・社内にノウハウが蓄積されにくい | ・業務委託契約書の締結 ・源泉徴収 ・デザイン料など対象業務のみ) |
正社員(正規雇用)としての雇用
事業の根幹を担う人材を長期的に確保し、組織として成長させたい場合に最適なのが正社員としての雇用です。例えば、将来の店長候補や、事業の核となる技術を任せる人材を育てたい場合などに適しています。
契約期間の定めがなくフルタイムでの勤務が基本となるため、従業員は事業への帰属意識を持ちやすく、責任感を持って業務に取り組んでくれることが期待できます。
一方で、従業員を手厚く保護する必要があり、毎月の給与に加えて社会保険料の負担など、コストが最も大きくなる形態です。また、労働法によって従業員の立場は強く守られているため、一度雇用すると、事業主の都合で簡単に解雇することはできません。
非正規雇用(パート・アルバイト等)としての雇用
例えば、ネットショップの受注・梱包作業や、月末月初の事務作業など、特定の業務や期間に合わせて人手を確保したい場合に適しているのが、パート・アルバイトとしての雇用です。
業務の繁閑に合わせて柔軟に人手を確保できるため、事業の状況に合わせて人件費を調整しやすい利点があります。
ただし、正社員と同じく労働法の保護対象である「労働者」であることに変わりはありません。
労働時間や日数によっては、社会保険や雇用保険への加入義務も発生します。例えば雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合は加入対象となります 。
短時間勤務だからといって、法律上の責任が軽くなるわけではない点を理解しておくことが大切です。
業務委託(外注)としての契約
デザインやWeb制作など、成果物の完成を目的とする専門的な業務を、プロジェクト単位で外部の専門家にお願いしたい場合に有効なのが業務委託契約です。
これは「雇用」ではなく、対等な事業者への「仕事の発注」という位置づけになります。ちなみに業務委託契約は通称で、法律上は「請負契約」や「委任契約」などに分かれます。
労働法の適用を受けないため、事業主は労働保険や社会保険の保険料を負担する必要がなく、コストを抑えやすいのが大きなメリットです。必要な時に、高い専門性を持つプロの力を借りることができます。
最も注意すべき点は、相手は従業員ではないため、事業主は業務の進め方について具体的な指示(指揮命令)ができないことです。もし勤務時間を管理したり、仕事の手順を細かく指示したりすると、実態は雇用であるとみなされ「偽装請負」という違法状態になる可能性があります。あくまで仕事の完成を目的とする契約だと覚えておきましょう。
個人事業主が従業員を雇うときには、複数の法律に基づいた手続きを進める必要があります。労働条件を明示する書類の交付から、労働保険や社会保険、税務署への届け出まで幅広く対応しなければなりません。
ここでは、必ず押さえておくべき主要な手続きを整理します。
労働条件通知書の作成・交付
従業員を雇う際は、労働時間や賃金、休日などの労働条件を記載した「労働条件通知書」を交付することが法律で義務付けられています 。これは事業主から従業員へ通知する文書で、口頭の説明だけでは不十分です。
書面で明示が必要な項目には、契約期間、仕事の場所や内容、労働時間、賃金の決まり方、退職に関する事項などがあります 。
さらに、2024年4月からはルールが強化され、「業務の変更の範囲」や「就業場所の変更の範囲」など、将来的に労働条件が変わる可能性のある項目についても明示が必要になりました。違反した場合、行政指導や罰則の対象となるため注意が必要です。
雇用契約書の締結・保管
雇用契約書の作成は法的な義務ではありませんが、実務上は強く推奨されます。
労働条件通知書が事業主からの通知であるのに対し、雇用契約書は労使双方が署名・捺印することで合意の証拠となります。
契約書を作成しておくことで、残業代や賞与などを巡る後々のトラブルを防ぎやすくなります。労働契約法でも、労働者と使用者はできる限り書面で契約内容を確認する必要があると定められています 。
労働条件通知書と合わせて作成・保管するのが安心です。
 雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?
雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?
労働保険(労災・雇用保険)の加入手続き
従業員を1人でも雇った場合、個人事業主には労働保険(労災保険と雇用保険)への加入義務が発生します 。
労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気に備えるもので、パートやアルバイトを含む全ての従業員が対象です 。
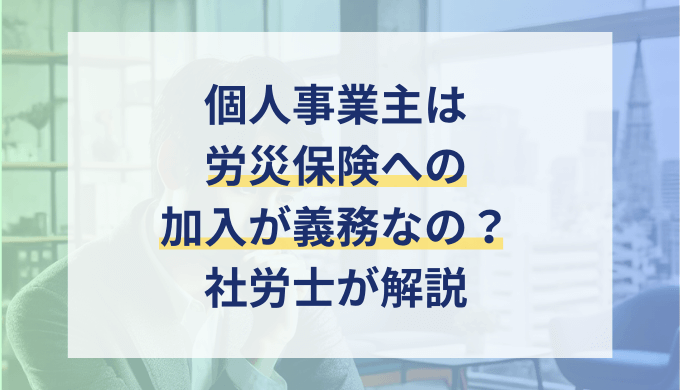 個人事業主は従業員を雇用したら労災保険の加入が義務!手続きや負担金額を社労士が解説
個人事業主は従業員を雇用したら労災保険の加入が義務!手続きや負担金額を社労士が解説
雇用保険は、従業員が失業した際の生活を支えるもので、週20時間以上働くなど一定の条件を満たす場合に加入義務が生じます 。
手続きは、まず労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出します。その後、条件を満たす従業員について、ハローワークで雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き
個人事業主の場合でも、常時5人以上の従業員を雇用する事業所(一部の業種を除く)は、健康保険と厚生年金保険への加入が義務となります 。
また、製造業や建設業などの「法定業種」に該当する場合は、従業員数に関係なく強制的に社会保険へ加入しなければなりません 。加入義務がある場合、事実が発生してから5日以内に年金事務所へ届け出を行います。
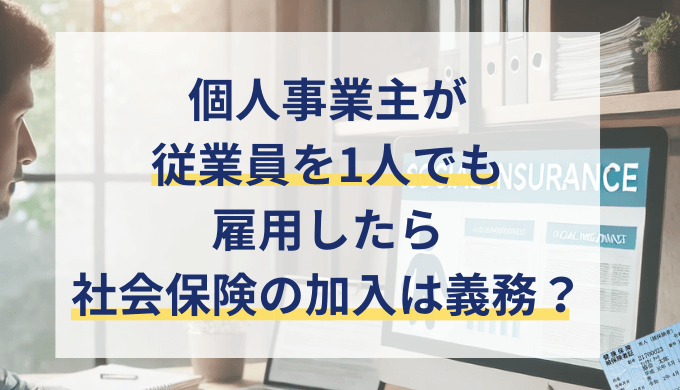 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
一方、これらの強制加入の条件に当てはまらない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て、年金事務所に申請し認可を受けることで、任意で社会保険に加入することができます。
 【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について
【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について
YouTubeでも「個人事業主が従業員を社会保険に加入させるための任意適用」について詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
税務署への届け出
従業員に給与を支払う場合、給与支払開始から1か月以内に税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
この手続きにより、事業主は「源泉徴収義務者」として登録され、毎月の給与から所得税を差し引いて国に納める責任を負います。
源泉徴収の準備
給与を支払う際は、従業員から所得税を天引き(源泉徴収)し、国に納付する必要があります。そのために、まず従業員から「扶養控除等申告書」を回収し、正しい税額を計算することが欠かせません。
納付は原則毎月行いますが、従業員が常時10人未満の事業所では「納期の特例」を利用することで、年2回にまとめて納めることもできます。小規模事業主にとっては事務負担を減らせる制度です。
従業員を雇用する際の手続きについては下記の記事でも詳しく解説しています。
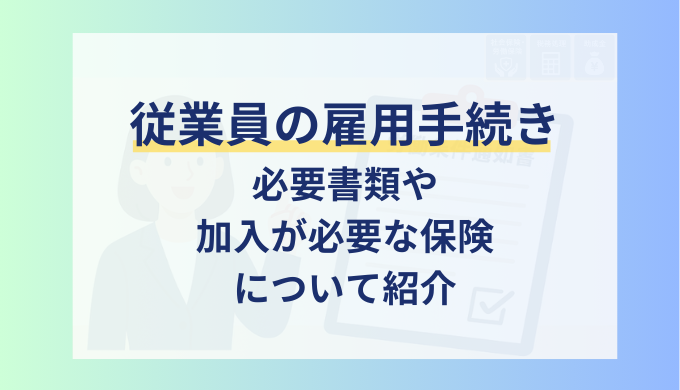 従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
従業員の雇用手続きと必要書類を解説!加入が必要になる保険は?
従業員を雇うと、給与計算や保険手続き以外にも守らなければならない労務管理上のルールがあります。とくに記録の整備や残業管理、従業員数が増えたときの義務については見落としやすいため、あらかじめ理解しておきましょう。
法定三帳簿の作成が義務
従業員を雇った場合、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つは必ず作成・保管しなければなりません。これらは「法定三帳簿」と呼ばれ、労働基準法で義務付けられています。
特に出勤簿などの労働時間の記録は、未払い残業代を巡るトラブルの際に重要な証拠となります。紙の帳簿だけでなく、勤怠管理システムやタイムカードによる管理でも問題ありません。保存期間はそれぞれ法律で定められているため、破棄のタイミングにも注意が必要です。
法定時間を超えた残業が発生する場合は、36協定の届出が必要
1日8時間、週40時間を超えて従業員に働いてもらう場合は、必ず「36(サブロク)協定」を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この手続きを経ずに時間外労働をさせることは法律違反です。
また、働き方改革によって時間外労働の上限も定められており、原則として「月45時間・年360時間」を超える残業は認められていません。違反した場合は行政指導や罰則の対象となるため、労務管理を徹底することが求められます。
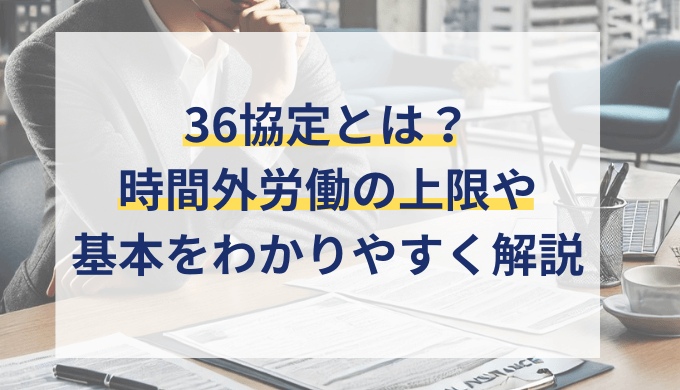 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
従業員数が10人を超える場合は就業規則の作成も必要
従業員が常時10人以上となった事業所では、職場のルールをまとめた「就業規則」を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります 。
就業規則には、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項などを必ず記載しなければなりません 。作成にあたっては、従業員側の代表から意見を聴くことも義務付けられています 。
10人を超えると、労務管理が口頭での取り決めだけでは対応できなくなり、制度として整備する必要が生じます。作成した就業規則は、見やすい場所への掲示や書面の交付などで、従業員へ周知することも必要です。
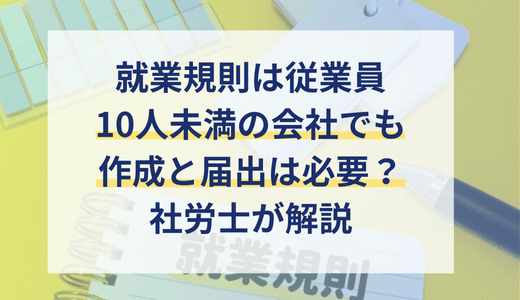 就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説
就業規則は10人未満の会社でも作成すべき?就業規則作成の義務とメリットを社労士が解説
従業員を雇うことには、事業拡大に役立つ大きなメリットがある一方で、費用や手続き面のデメリットも伴います。ここでは、メリットとデメリットを整理して解説します。
人を雇うことの主なメリット
個人事業主が従業員を雇うメリットは、以下の通りです。
事務作業や日常業務を従業員に任せることで、事業主は営業や企画、商品開発といった売上に直結する活動に集中できます。
一人で事業を回していると、雑務に追われて本来の強みを発揮できないケースも少なくありません。従業員を配置することで業務効率が上がり、結果的に事業の拡大や収益力の向上に繋がります。
青色申告をしている個人事業主は、家族を従業員として雇い給与を支払うことで、その給与を「青色事業専従者給-与」として全額経費に計上できます。
これにより課税所得を抑えられ、所得税や住民税の節税効果が期待できます。
ただし、対象となるのは事業に専ら従事している15歳以上の家族であり、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
注意すべき主なデメリット
一方で、個人事業主が従業員を雇うデメリットは、以下の通りです。
従業員を雇うと、給与の支払いに加えて社会保険料の事業主負担分が発生します。健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主と労働者が折半で負担します 。これらを合わせると、給与額面の約15%程度を追加で負担する必要があります。
少人数の事業主にとっては、この負担が大きな経営リスクとなる可能性があります。
労働保険や社会保険の加入、税務署への届出、源泉徴-収、年末調整など、従業員を雇うと事務作業が一気に増えます。これらは一度やれば終わりではなく、毎月の給与計算や定期的な届出といった継続的な管理が必要です。
本業と並行してこれらの手続きを正確に行うのは負担が大きく、専門的な知識も求められます。
従業員を雇うと、労働基準法などの労働法令を遵守する義務が生じます。労働時間の管理や休暇の付与、安全配-慮義務などを怠ると、労務トラブルに発展する可能性があります。
また、一度雇用した従業員は、簡単には解雇できません。採用内定の取り消しですら、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上認められない場合は無効となります 。経営状況の悪化を理由とする整理解雇であっても厳格な条件を満たす必要があり、注意が必要です。
従業員の雇用は、事業成長の起爆剤となりうる一方で、コストや法的な責任という重い負担も伴います。紹介したメリットとデメリットを判断材料として、「責任を負ってでも事業の核となる人材を育てたい」なら雇用契約を、「まずはリスクを抑えたい」なら業務委託契約を検討するなど、ご自身の事業の段階に合った選択をすることが重要です。
従業員の雇用を検討する中で、多くの事業主が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。
個人事業主が従業員を雇用するなら会社設立(法人化)すべき?
一概には言えませんが、年間の事業所得が800万~1000万円を恒常的に超えるようになった場合や、優秀な人材を確保したいと考え始めた場合は、法人化が有利になる可能性が高いです。
理由の一つは税金です。個人事業主の所得税は所得が増えるほど税率も上がる「累進課税」ですが、法人税は税率がほぼ一定です。そのため、所得が一定額を超えると、法人の方が税負担を抑えられる傾向にあります。
もう一つの理由は、社会保険です。法人の場合、社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます 。福利厚生が手厚くなるため、採用活動において個人事業主よりも有利に働くことがあります。
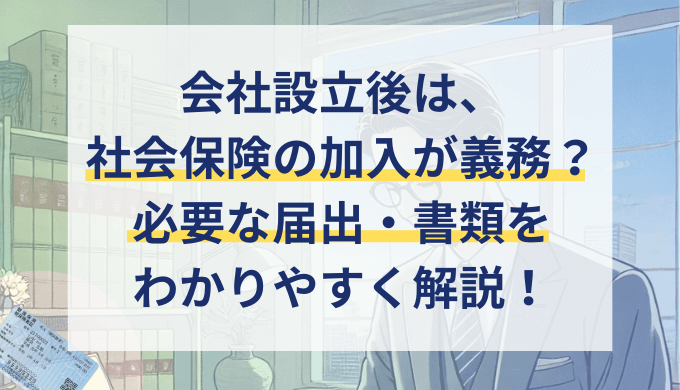 会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説
会社設立後は社会保険の加入が義務!手続きの流れや必要書類を全解説
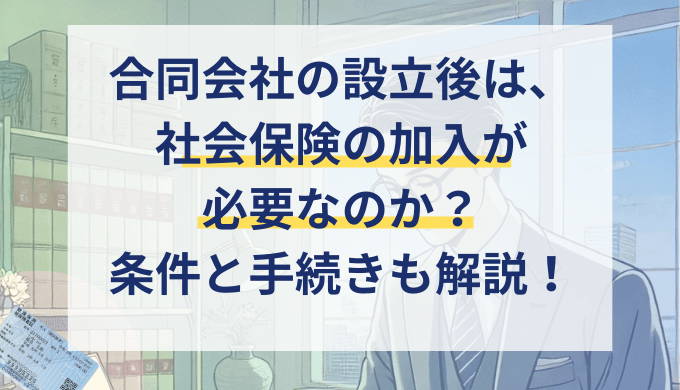 合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
合同会社設立後の社会保険加入は義務?条件や手続き方法を解説!
家族を従業員にする場合、何か特別な手続きは必要?
生計を同一にする家族に支払う給与は、原則として経費にできません。しかし、青色申告を行っている個人事業主であれば、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、家族に支払う給与を全額経費として計上できるようになります。
この特例を適用するには、「その事業にもっぱら従事していること」など、いくつかの要件を満たす必要があります。
また、注意点として、事業主と生計を同一にする家族は、原則として雇用保険に加入することができません。
個人事業主でも従業員を雇う際に活用できる助成金や補助金はある?
国の制度として様々な助成金が用意されています。これらは、事業主が従業員の雇用を安定させるための取り組みを支援するものです。
代表的なものに「キャリアアップ助成金」があります。これは、パートタイマーや有期契約労働者といった非正規雇用の従業員を、正社員へ転換するなどの取り組みを行った場合に支給されるものです。
ただし、こうした助成金は、取り組みを実施した後に申請しても受給できません。必ず、正社員への転換などを行う前に、管轄のハローワークへ計画書を提出し、認定を受ける必要があります。事前の計画が不可欠だと覚えておきましょう。
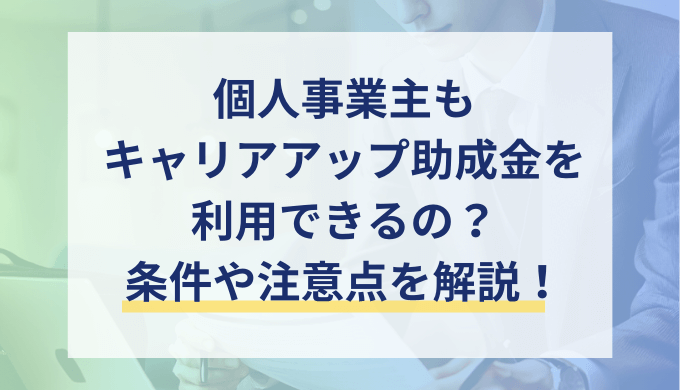 キャリアアップ助成金は個人事業主も利用できる助成金制度?申請条件と対象者を解説
キャリアアップ助成金は個人事業主も利用できる助成金制度?申請条件と対象者を解説
個人事業主が人を雇う場合、選択肢は大きく「雇用」と「業務委託」に分かれます。
「雇用」を選ぶなら、労働条件の明示 、労働保険 や社会保険の加入 、税務署への届出や源泉徴収の準備など、多くの手続きを正しく進める必要があります。事業の成長に繋がる一方で、人件費や社会保険料の負担、労働法上の責任といったデメリットも伴います。
一方の「業務委託」は、社会保険や労働法の義務はなく、対等な立場で特定の業務を依頼できる点が特徴です。ただし、指揮命令はできず、契約内容の不備がトラブルにつながるリスクもあります。
事業の規模や任せたい業務の内容を踏まえて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。必要な手続きや契約を適切に管理することが、安心して事業を拡大していくための第一歩になります。
従業員を雇うには、労働条件の明示や就業規則の整備、労働保険や社会保険の加入など、多くの専門的な手続きが伴います。これらを事業主が本業と並行してすべて自力で対応するのは、大きな負担となりやすいでしょう。
もし手続きに漏れや誤りがあれば、法律違反にあたるだけでなく、将来的に従業員とのトラブルへ発展する可能性もあります。
そのため、社労士といった専門家の力を借りることは「外注費」ではなく、事業主が安心して本業に集中し、法的リスクを最小限に抑えるための大切な投資といえます。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
従業員を初めて雇うときに必要な社会保険や労働保険の手続きは、提出先が複数に分かれていて非常に複雑です。少しの記入ミスや提出の遅れでも、従業員の保険証の発行や給付に影響してしまうため、正確さとスピードが欠かせません。
こうした不安を解消する方法として、社会保険労務士に依頼するのは効果的です。手続き漏れや記入ミスを防ぎ、事業主は本業や経営に集中できます。特に、初めての雇用手続きに戸惑う小規模事業主にとっては、専門家に任せることが最も安心で合理的な選択といえるでしょう。
「社労士クラウド」では、顧問契約は不要。必要なときにだけ依頼できるスポット申請代行サービスを提供しています。初めての雇用手続きを確実に進めたい方や、自分で対応するのが不安な方に最適です。
まずは無料相談で、自社の状況に合わせた最適な対応を確認してみてください。安心して従業員を迎えられる体制を、専門家と一緒に整えましょう。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|