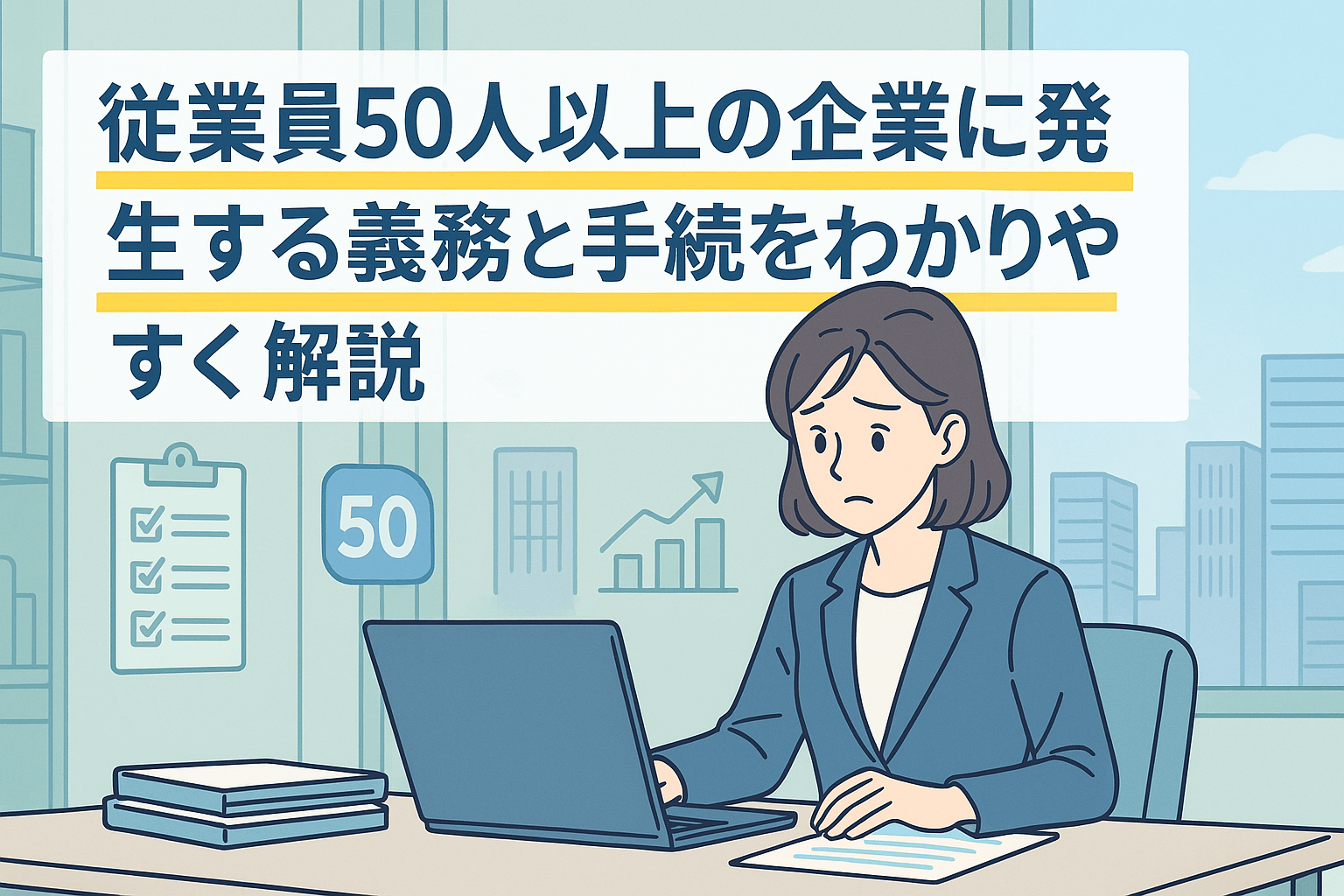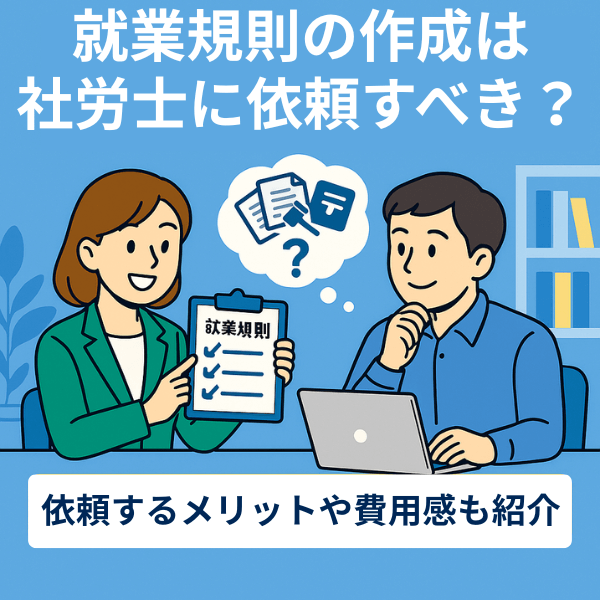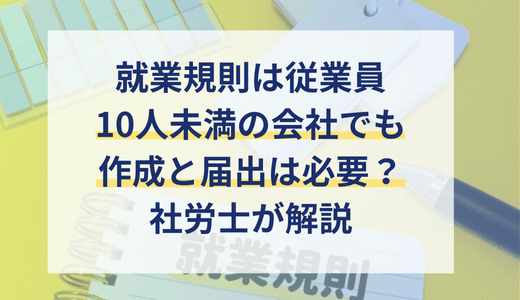従業員数が50人を超えると、「労働安全衛生法」に基づき、「産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会(+安全委員会)設置、ストレスチェック年1回実施、定期健康診断結果報告書の提出」という5つの主要な義務が企業に課されます。
この義務は、事業場ごとの従業員数に応じて発生するもので、パートタイマーや派遣社員などの非正規雇用者も含めたカウント方法を正しく理解する必要があります。
この記事では、5つの義務の詳細とその対応(手続き)方法、適用範囲(人数の数え方)について詳しく紹介します。また、これらの義務に対応しないことで発生する罰則リスクやその影響についても解説します。
人事・労務担当者の方が社内で適切に対応できるよう、実務上のポイントや準備すべきことを具体的にご案内します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧 ・当日申請・フリー価格・丸投げOK| 1,800社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
目次 非表示
- 従業員50人以上で必須!「労働安全衛生法」に基づく主な義務
- 常時50人以上とは?人数カウントと「事業場」の定義を正確に理解しよう
- 従業員50人以上で必要な義務①:産業医の選任と届出
- 従業員50人以上で必要な義務②:衛生管理者(+安全管理者)の選任
- 従業員50人以上で必要な義務③:衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置
- 従業員50人以上で必要な義務④:ストレスチェックの年1回実施
- 従業員50人以上で必要な義務⑤:定期健康診断結果報告書の提出
- 【補足義務】休養室の設置ほか追加安全衛生措置
- 【要注意】義務違反による罰則と事業への影響・リスクまとめ
- 関連する制度についての補足
- 従業員50人以上の義務に関するよくある質問(Q&A)
- まとめ:従業員50人以上の義務と手続きを理解し、専門家も活用しながら早期対応を
労働安全衛生法に基づき、「常時使用する労働者が50人以上の事業場」に対して、5つの主要な義務が課されます。
この「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、契約社員、パート社員、アルバイト社員などの直接雇用社員のほか、出向社員も含まれます。また、派遣社員についても、派遣元だけでなく派遣先の事業場でもカウント対象となります(詳しい定義と数え方は後ほど解説します)。
従業員50人以上の事業場で行わなければならない5つの主な義務は、以下の通りです。
① 産業医の選任
② 衛生管理者の選任(業種によっては安全管理者も)
③ 衛生委員会の設置(業種によっては安全委員会も)
④ ストレスチェックの年1回実施
⑤ 定期健康診断結果報告書の提出
さらに常時50人以上または常時女性30人以上の事業場では、休養室の設置が必要になります。また業種によっては安全管理者の選任も必要になってきます。これらの義務への対応が遅れると、罰則を受けるリスクがあります。
【主な義務一覧表】
以下の表では、従業員50人以上の事業場で対応が必要な主な義務について、内容・手続き・期限をまとめています。これらの義務はすべて労働安全衛生法に基づくものであり、不履行の場合は罰則対象となる可能性があります。
| 義務の名称 | 主な内容 | 主な対応・手続き | 期限の目安 |
| ① 産業医の選任と届出 | 従業員の健康管理等を行う医師を選任し、労基署へ届け出る(労働安全衛生法 第13条) | 選任、契約、届出(様式第3号) | 発生後14日以内 |
| ② 衛生管理者の選任 | 職場の衛生管理を担う有資格者を社内から選任し、届け出る(労働安全衛生法 第12条) | 選任、届出(様式第3号) | 発生後14日以内 |
| ③ 衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置 | 職場の安全衛生について労使で審議する委員会を設置・運営(労働安全衛生法 第18条) | 設置、構成員選任、月1回以上の開催、議事録作成・保管 | 発生後遅滞なく |
| ④ ストレスチェックの年1回実施と実施状況の報告 | 従業員の心理的負担を把握する検査を実施し、状況を労基署へ報告(労働安全衛生法 第66条の10) | 計画、実施、結果通知、面接指導、集団分析、報告(様式第6号の2) | 年1回実施・報告 |
| ⑤ 定期健康診断結果報告書の提出 | 従業員の定期健診結果概要を労基署へ報告(労働安全衛生法 第66条) | 結果集計、報告書作成(様式第6号)、提出 | 実施後遅滞なく |
| 【補足】休養室の設置 | 体調不良者が休めるスペースを設置(労働安全衛生規則 第618条) | 男女別設置(※) | – |
| 【特定業種のみ】安全管理者の選任 | 職場の安全に関する技術事項を管理する者を選任(労働安全衛生法 第11条) | 選任、届出(様式第3号) | 発生後14日以内 |
(※休養室は常時50人以上または常時女性30人以上の事業場)
義務① 産業医の選任と届出
専門家である医師(産業医)を選任し、従業員の健康管理や職場環境の維持改善に関する指導・助言を受けるための義務です。選任後は労働基準監督署へ届け出なければなりません。
詳しくは「従業員50人以上で必要な義務①:産業医の選任と届出」で解説しています。
なお、従業員数が多い大企業や、メンタルヘルス対策を重視する職場では産業看護師を雇う場合もあります。
参考)産業看護師になるためには?未経験から目指すコツやQ&Aまで必要な情報をまるっと解説
義務② 衛生管理者の選任
職場の衛生にかかわる技術的な事項を管理する、国家資格を持つ者(衛生管理者)を事業場ごとに選任する義務です。
詳しくは「従業員50人以上で必要な義務②:衛生管理者(+安全管理者)の選任」で解説しています。
義務③ 衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置
労働者の健康障害を防止したり、健康の保持増進を図るための対策など、職場の安全衛生に関する事項を調査審議するため、労使双方のメンバーで構成される委員会を設置し、毎月1回以上開催する義務です。(※業種により安全委員会または安全衛生委員会となります)
詳しくは「従業員50人以上で必要な義務③:衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置」で解説しています。
義務④ ストレスチェックの年1回実施と実施状況の報告
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を年1回実施し、その実施状況を労働基準監督署へ報告する義務です。
詳しくは「従業員50人以上で必要な義務④:ストレスチェックの年1回実施」で解説しています。
義務⑤ 定期健康診断結果報告書の提出
従業員に実施した定期健康診断の結果(有所見者の数など)を記載した報告書(定期健康診断結果報告書)を、遅滞なく労働基準監督署へ提出する義務です。(※健康診断の実施自体は従業員1人から義務です)
詳しくは「従業員50人以上で必要な義務⑤:定期健康診断結果報告書の提出」で解説しています。
【補足義務】休養室の設置
従業員が業務中に体調不良となった場合などに、横になって休める休養室または休養所を設ける義務です。(※常時50人以上または常時女性従業員30人以上の事業場が対象)
詳しくは「【補足義務】休養室の設置ほか追加安全衛生措置」で解説しています。
このように、従業員50人以上の事業場では、安全衛生に関する様々な対応が求められます。次の章で、これらの義務が発生する前提条件である「常時50人以上」と「事業場」の定義について、詳しく見ていきましょう。
従業員の人数に応じて、会社には就業規則の作成などの手続きが求められます。なかには、事業主や担当者だけでは対応が難しい手続きもあるため、そうした場合は社労士への相談や依頼も検討するとよいでしょう。
 社労士(社会保険労務士)に相談・依頼できること(事業主向け)知らずに違反しているケースや依頼タイミングも解説
社労士(社会保険労務士)に相談・依頼できること(事業主向け)知らずに違反しているケースや依頼タイミングも解説
労働安全衛生法に基づく義務は、「事業場」ごとに「常時使用する労働者」が50人以上いる場合に発生します。
それぞれの定義(意味)と具体的なカウント方法(数え方)をわかりやすく解説します。
「事業場」とは? – 義務が発生する”場所”の単位
労働安全衛生法などの義務は、多くの場合、会社全体ではなく「事業場」を単位として適用されます。「事業場」とは、一定の場所で継続的に事業活動が行われているひとつの経営単位を指します。イメージとしては、ひとつの支店や営業所、工場などがそれぞれ独立した事業場となるケースが多いです。
【基本的な考え方】
◯場所的な独立性
本社、支店、工場、店舗など、地理的に場所が分かれている場合は、原則としてそれぞれ別の事業場として扱います。
◯組織的な独立性
ある程度の組織的な関連性があり、独立して業務が行われている単位であることも考慮されます。
例えば、同じ建物内であっても、人事労務管理や指揮命令系統が明確に分かれている部門があれば、別の事業場とみなされる可能性もあります。
【具体例】
| OK例 | 東京本社(60人)+大阪支店(30人) → 東京本社のみ義務発生 |
| NG例 | 会社全体で70人だから義務発生 → 誤り。各事業場の人数で判断 |
ただし、支店や出張所であっても、従業員数が極端に少なく、人事労務管理などの機能が独立しておらず、実質的に本社などの上位組織の指揮命令下で一体として運営されている場合は、上位組織とまとめて一つの事業場として扱われることもあります。
判断に迷う場合は、必ず所轄の労働基準監督署や社労士に確認するようにしてください。
「常時50人以上」の正しい人数カウント方法 – パート・派遣社員の扱いは?
「常時使用する労働者」が50人以上いるかどうかのカウント方法です。ここでのポイントは「常時」と「使用する労働者」の解釈です。
「常時使用する労働者」には、いわゆる正社員だけでなく、以下の従業員も原則として含まれます。
- パートタイマー
- アルバイト
- 契約社員
- 嘱託社員 など
重要なのは「常時」という点です。これは、一時的な繁忙期だけ50人を超えるのではなく、常態として50人以上の従業員を使用している状態を指します。
日々雇い入れられる労働者や試用期間中の労働者も、雇用期間や更新の実態からみて常態として使用されていると判断されれば、人数に含める必要があります。
派遣社員のカウントについては特に注意が必要です。労働安全衛生法の観点からは、派遣社員は、派遣元(雇用契約のある企業)と派遣先(実際に勤務している事業場)の両方でカウントされます。
これは「二重カウント」と呼ばれ、以下の理由によります(昭和61年 基発第333号通達に基づく考え方です)。
| 派遣元 | 雇用関係があるため、自社の労働者としてカウント |
| 派遣先 | 実際にその事業場で働いており、職場の安全衛生管理の対象となるためカウント |
例えば、派遣社員が10人いる事業場では、直接雇用の従業員が40人いれば合計50人となり、労働安全衛生法上の義務が発生することになります。
「事業場」の範囲と「常時使用する労働者」の人数を正確に把握することが、従業員50人以上の義務への対応の第一歩となります。自社の各事業場の状況を、雇用契約書や労働者名簿などでしっかり確認しましょう。
判断に迷う場合や複雑なケースでは、自己判断せずに必ず所轄の労働基準監督署や、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
従業員数が常時50人以上の事業場になった場合、まず対応すべき必須の義務の一つが「産業医」の選任です。産業医とは、従業員の健康管理について専門的な立場から指導・助言を行う医師のことであり、労働安全衛生法第13条によってその選任が義務付けられています。
選任した産業医は、従業員の健康診断結果の確認や、長時間労働者・高ストレス者への面接指導、職場巡視、衛生委員会への出席などを通じて、企業の安全衛生水準の向上をサポートします。
産業医選任の基本的なルール(概要と選任基準)、具体的な手続きの流れ、見落としがちな注意点、そして忙しい担当者のための効率化のヒントまで、わかりやすく解説します。
産業医の選任基準
まず、産業医選任に関する基本的なルールを押さえましょう。
常時使用する労働者が50人以上になった日から14日以内に産業医を選任しなければなりません。期限が短いため、50人に達する前から準備を進めることが重要です。
- 産業医の主な役割は以下の通りです。
- 健康診断結果に基づく就業上の措置に関する助言・指導
- 長時間労働者や高ストレス者への面接指導
- 作業環境の維持管理や改善に関する助言・指導
- 職場巡視(原則として月1回以上 ※条件により2ヶ月に1回も可)
- 衛生委員会(または安全衛生委員会)への出席・助言
- 健康教育、健康相談 など
事業場の規模によって、必要な産業医の形態が異なります。
| 従業員数 50人~999人の事業場 | 嘱託産業医(非常勤)を1人以上選任する必要があります。多くの中小企業が該当。 |
| 従業員数 1000人以上(または有害業務に常時500人以上従事)の事業場 | 専属産業医(その事業場に専属で勤務)を1人以上選任する義務がある。 |
| 従業員数 3001人以上の事業場 | 専属産業医を2人以上選任する義務ががある。 |
産業医になるためには、医師免許を持っていることに加え、労働安全衛生法施行規則第14条第2項で定められた以下のいずれかの要件を満たす必要があります。単に医師であれば誰でも良いわけではありませんので注意が必要です。
- 厚生労働大臣が指定する研修(日本医師会認定産業医制度研修など)を修了した者
- 産業医科大学で所定の課程を修了し卒業した者
- 労働衛生コンサルタント試験(試験区分:保健衛生)に合格した者
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師の経験者 など
産業医を選任する手続き(探し方から届出まで)
産業医の選任から労働基準監督署への届出までの具体的な手続きは、以下のステップで進めます。
- ステップ1:候補となる医師(産業医)を探す
- ステップ2:産業医と契約を締結する
- ステップ3:労働基準監督署へ選任報告書を提出する(14日以内)
- ステップ4:提出方法を確認する
まず、上記の要件を満たす産業医の候補者を探す必要があります。主な探し方としては、以下のような方法があります。
- 地域産業保健センター(産保センター)に相談する
- 地域の医師会に相談する
- 産業医紹介サービスを利用する
- 健康診断を依頼している医療機関に相談する
- 顧問社労士や他の企業の担当者に相談する
選任する産業医が決まったら、口約束ではなく、必ず書面で契約を締結しましょう。契約書には、以下の内容を明記することが重要です。
- 産業医の氏名、所属医療機関等
- 職務内容(健康相談、職場巡視、衛生委員会への出席など、具体的に)
- 活動頻度・時間(例:月1回、2時間訪問など)
- 報酬(月額、時間単価など)
- 守秘義務に関する事項
- 契約期間、更新・解除に関する事項
契約内容を明確にしておくことで、後のトラブルを防止できます。
産業医を選任したら、その日から14日以内に、事業場を管轄する労働基準監督署長宛てに「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を提出しなければなりません。
- 使用する様式(様式第3号)
- 添付書類(選任した産業医が要件を満たすことを証明する書類(研修修了証のコピー、医師免許証のコピーなど))
作成した選任報告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- 所轄労働基準監督署の窓口へ持参
- 郵送
- 電子申請(e-Gov)
産業医の選任・届出でよくあるミスと注意点
産業医の選任・届出に関して、企業が陥りやすいミスや注意点をまとめました。罰則に繋がる可能性もあるため、しっかり確認しましょう。
- 届出忘れ・期限超過
- 契約内容の不備・未締結
- 名義貸しの禁止
- 要件を満たさない医師の選任
- 罰則規定
産業医の選任・届出で最も注意すべきは選任後14日以内という届出期限を守れないケースです。また、職務内容などを明確にした書面での契約を締結しないと、後々トラブルの原因となる可能性があります。
形式的に名前だけを借りる「名義貸し」や、医師免許だけでは不十分な法定要件を満たさない医師の選任は認められません。
上記の義務違反や届出不備は、労働安全衛生法第120条に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があるため、十分な確認と期限内の手続きが不可欠です。
従業員数が常時50人以上の事業場では、産業医の選任と並んで、「衛生管理者」の選任も労働安全衛生法第12条によって義務付けられています。衛生管理者は、職場の衛生レベルを維持・向上させ、労働者の健康障害を防止するための専門的な役割を担います。
また、建設業や製造業など一定の業種では、衛生管理者に加えて「安全管理者」の選任も必要となる場合があります。
まず衛生管理者(および安全管理者)に求められる資格要件と必要な人数を確認し、その後、具体的な選任・届出の手続きフロー、そして社内に資格者がいない場合の資格取得に向けたロードマップを解説します。
資格要件と必要な人数
衛生管理者として選任するためには、誰でも良いわけではなく、特定の資格が必要です。また、事業場の規模に応じて選任すべき人数も定められています。
衛生管理者の資格は 原則として、以下のいずれかの国家資格を持つ者でなければなりません。
- 第一種衛生管理者免許(すべての業種の事業場で選任可能)
- 第二種衛生管理者免許(有害業務との関連が少ない業種(金融、保険、卸売、小売業など)でのみ選任可能)
※その他、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなども資格者とみなされます。
事業場の常時使用する労働者数に応じて、以下の人数を選任する必要があります。
- 50人~200人:1人以上
- 201人~500人:2人以上
- 501人~1000人:3人以上
(以降、規模に応じて増加)
衛生管理者は、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければなりません。つまり、他の事業場の衛生管理者を兼務することはできません。
労働安全衛生法施行令で定められた業種(建設業、製造業、運送業、電気・ガス業など)で、かつ常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、安全管理者の選任も義務付けられています。
◯資格要件
大学等の理科系の課程を修了し一定の実務経験がある者、労働安全コンサルタント、または厚生労働大臣が定める研修を修了した者など、専門的な知識・経験が求められます。
選任・届出フロー
衛生管理者(および該当する場合は安全管理者)の選任から労働基準監督署への届出までの手続きは、以下の流れで進めます。産業医と同様、選任から届出までの期限は14日以内と定められています。
まず、社内に上記の資格要件を満たす従業員がいるか確認します。該当者がいれば、その者の中から衛生管理者(または安全管理者)として選任します。
社内に適格者がいない場合は、資格取得を支援するか(後述)、資格を持つ人材を新たに採用する必要があります。
「社内に衛生管理者がいない!」となる前に、従業員40人頃から候補者を選び、eラーニング等の学習費用を会社が支援して資格取得を支援するなど準備を開始しておきましょう。
衛生管理者(または安全管理者)を選任したら、その日から14日以内に、事業場を管轄する労働基準監督署長宛てに「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を提出します。
- 使用する様式(様式第3号)
- 添付書類(選任した者の資格を証明する書類(免許証のコピーなど))
提出方法は窓口持参、郵送、または電子申請(e-Gov)が可能です。
【兼任に関する注意点】
- 衛生管理者と安全管理者は、原則として兼任できません。
- 他の職務との兼務は可能ですが、衛生管理者としての職務が適切に遂行できる範囲に限られます。
従業員数が常時50人以上の事業場では、「衛生委員会」を設置し、毎月1回以上開催することが労働安全衛生法第18条で義務付けられています。これは、労働者の健康障害防止や健康の保持増進に関する重要事項について、労使が一体となって調査審議し、事業者へ意見を述べるための重要な会議体です。
また、一定の業種(建設業、製造業など)では「安全委員会」の設置も別途義務付けられていますが、その場合は衛生委員会と安全委員会の機能を統合した「安全衛生委員会」として設置・運営することが可能です。
形骸化させず、実効性のある委員会を運営していくためには、基本的なルールと効果的な進め方のコツを押さえておくことが大切です。このセクションでは、委員会のメンバー構成やルール、年間スケジュール例と議事録の扱い、そして近年関心が高まっているオンライン開催の可否や運営のヒントについて解説します。
メンバー構成と開催ルール
まず、衛生委員会(または安全衛生委員会)を構成するメンバーと、基本的な開催ルールを確認しましょう。
委員会は以下のメンバーで構成する必要があります。委員の指名は事業者(会社)が行いますが、重要なルールとして、議長を除く委員の半数については、労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。
- 議長: (原則として、事業場の安全衛生に関する業務を統括管理する者/例:事業場のトップ、工場長、支店長など)
- 産業医: (選任している産業医)
- 衛生管理者: (選任している衛生管理者)
- 労働者側委員: (事業場の労働者で、衛生(安全衛生)に関し経験を有する者)
- ※安全衛生委員会を設置する場合(または安全委員会を設置する場合)は安全管理者も必要です。
開催頻度は毎月1回以上、定期的に開催することが義務付けられています。
委員会では、以下のような従業員の健康や安全に関する幅広いテーマについて調査審議し、事業者へ意見を述べます。
- 衛生に関する規程の作成・変更
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善
- 労働者の健康診断の結果と、その後の措置
- 長時間労働による健康障害の防止対策
- メンタルヘルス対策
- 職場環境測定の結果と対策
- 労働災害の原因調査と再発防止策(安全衛生委員会の場合、安全に関する事項も含む) など
委員会を計画的かつ効果的に運営するためには、年間の議題スケジュールを立て、議事録をきちんと作成・保管することが重要です。
従業員数が常時50人以上の事業場では、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的として、「ストレスチェック」を年1回以上実施することが労働安全衛生法第66条の10で義務付けられています(2015年12月施行)。
ストレスチェックは、従業員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善に繋げ、労働者がより健康に働ける環境を作るための重要な取り組みです。
こちらでは、ストレスチェックの対象となる従業員や実施内容、具体的な実施から労働基準監督署への報告までの流れ、そして「高ストレス者」と判定された従業員への対応(面接指導)について、注意点を交えながら解説します。
対象者と実施内容(調査票)について
まず、誰にストレスチェックを実施し、どのような内容で行うのか、基本的なルールを確認しましょう。
対象となる従業員は、原則として、以下の要件を満たす「常時使用する労働者」が対象となります。
- 期間の定めのない労働契約により使用される者(または契約期間が1年以上、もしくは1年以上使用されることが予定・更新されている者)。
- 週の所定労働時間が、同じ事業場で同様の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上である者。
パートタイマーやアルバイトであっても、上記の要件を満たせば対象となります。
派遣社員は、派遣元企業が実施義務を負うため、派遣先のストレスチェックの対象には通常含めません。
社長や役員は、労働者性がなければ対象外です。
実施内容(調査票)
ストレスチェックは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士などの「実施者」が、質問票を用いて行います。
質問票には、労働安全衛生規則で定められた以下の3つの領域に関する項目を含める必要があります。
- 職場における心理的な負担の原因(仕事の量・質、対人関係など)
- 心理的な負担による心身の自覚症状(疲労感、不安感、抑うつ感など)
- 職場における他の労働者による支援(上司・同僚のサポートなど)
厚生労働省は、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」や、それを簡略化した「簡易版(23項目)」を推奨しています。これらの項目が含まれていれば、衛生委員会等での調査審議を経て、会社独自の項目を追加することも可能です。
実施~報告までのステップ解説
ストレスチェックの実施から労働基準監督署への報告までは、概ね以下のステップで進めます。プライバシー保護に十分配慮し、計画的に進めることが重要です。
実施者(医師、保健師など)と、実施の補助を行う実施事務従事者(人事担当者など。ただし人事権を持つ者はなれない場合あり)を指名します。実施者と実施事務従事者には守秘義務が課せられます。
実施時期、対象者、質問票の種類、結果の通知方法、面接指導の申し出方法、集団分析の方法などを定めた実施計画を作成し、事前に衛生委員会等で調査審議し、決定します。
ストレスチェックの目的、実施方法、個人の結果は本人の同意なく事業者に提供されないこと、不利益な取り扱いを受けないことなどを、従業員に十分に周知します。(※受検は任意ですが、事業者は従業員が受検するよう努める必要があります)
Webまたは紙の質問票でストレスチェックを実施します。
実施者が回答を分析・評価し、「高ストレス者」に該当するかどうかを選定します。
ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者から、遅滞なく直接本人に通知されます。本人の同意なく、事業者が結果を知ることはできません。 このプライバシー保護は非常に重要です。
個人の結果とは別に、部署や課などの一定規模の集団ごとのストレス傾向を集計・分析することが努力義務とされています。(※個人が特定されないよう、10人未満の集団は対象外とするなどの配慮が必要)
分析結果を衛生委員会等で報告・審議し、職場環境の改善点(例:業務負荷の見直し、コミュニケーション対策など)を特定し、具体的な改善活動に繋げることが期待されます。
年に1回、ストレスチェックを実施した後、遅滞なく、検査を受けた労働者数、面接指導を受けた労働者数などを記載した「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を作成し、所轄の労働基準監督署長に提出します。(電子申請も可能です)
なお、ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員には、医師による面接指導を受けるよう勧奨することが必要です。
もし従業員から申し出があった場合は、会社は面接指導(費用は会社負担)を実施し、医師の意見を聴いて必要な配慮を行わなければなりません。
【高ストレス者への対応について】
重要な注意点として、ストレスチェックの結果や面接指導の申し出を理由とした不利益な扱いは法律で固く禁止されています。 個人の結果や面接内容はプライバシー情報として厳重に管理してください。
従業員への定期健康診断の実施は、企業規模にかかわらず、労働安全衛生法で定められた事業者の義務です。しかし、常時使用する労働者が50人以上の事業場においては、それに加えて、実施した定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告する義務(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第52条)が課せられます。
これは単なる事務手続きではなく、事業場全体の健康状態を把握し、必要な措置や職場環境の改善に繋げるための重要なプロセスです。
【報告の概要】
・報告対象:主に年1回の定期健康診断の結果
・使用様式:「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」
・提出先:事業場を管轄する労働基準監督署
・提出期限:健診実施後、「遅滞なく」提出(一般的には1〜2か月以内が目安)
・罰則:報告義務違反には50万円以下の罰金
提出する内容は、受診者数、有所見者数、要再検査者数などの統計的なデータであり、労働者個人の健診結果を提出するわけではありません。
深夜業などの特定有害業務に従事する労働者がいる場合は、6か月ごとに実施する「特定業務従事者健康診断」(様式第6号の2)の結果報告も必要となります。
定期健康診断結果報告書の提出は、従業員50人以上の事業場における重要な義務の一つです。期限を守り、正確な内容で報告を行うようにしましょう。報告義務違反には罰則もありますので、遅滞なく対応することが重要です。
これまで解説してきた主要な義務に加えて、従業員50人以上の事業場では、労働者の健康と安全を守るために注意すべき、その他の安全衛生上の措置があります。
特に「休養室の設置」は多くの事業場に関係する義務です。また、自社の業務内容によっては、特別な管理が必要となるケースもあります。
休憩室の設置について
従業員が業務中に体調が悪くなった際に、気兼ねなく横になって休めるスペースは重要です。これは、体調不良者を一時的に休ませたり、必要に応じて救急隊を待つ間に待機させたりするためのスペースです。
労働安全衛生規則第618条では、常時50人以上または常時女性従業員が30人以上の事業場において、労働者が横になれる「休養室または休養所」を、男女別に設けることを義務付けています。
休養室の未設置も労働安全衛生規則違反となり、指導の対象となる可能性があります。従業員が安心して働ける環境づくりの一環として、スペースの確保を検討しましょう。
有害業務がある場合の作業環境測定・特殊健診
自社の業務内容によっては、従業員規模にかかわらず、労働安全衛生法に基づき、より専門的な安全衛生管理が求められる場合があります。特に注意が必要なのは、有機溶剤、特定化学物質、粉じん、騒音など、労働者の健康に有害な影響を及ぼす可能性のある物質や環境下で作業を行う場合です。
このような場合、通常の健康診断とは別に、定期的な「作業環境測定」の実施と評価、有害業務従事者への「特殊健康診断」の実施、場合によっては「作業主任者」の選任といった追加の義務が発生することがあります。
自社の事業場でこれらの有害業務に該当するかどうかの判断や、具体的な対応方法(測定の要否、健診項目、作業主任者の要件など)は専門的な知識が必要です。 少しでも該当する可能性がある場合や、判断に迷う場合は、自己判断せず、必ず所轄の労働基準監督署や、作業環境測定士、労働衛生コンサルタント、社労士などの専門家に相談してください。
従業員50人以上の事業場に課せられる労働安全衛生法上の義務は、単なる努力目標ではありません。これらの義務への対応を怠った場合、法律に基づく罰則が科されるだけでなく、企業の経営全体に様々な悪影響を及ぼすリスクがあります。
「知らなかった」「忙しくて手が回らなかった」では済まされない可能性があるため、そのリスクを正確に理解しておくことが極めて重要です。
以下では主な義務違反に対する具体的な罰則の内容と、それ以外に想定される事業への影響についてまとめて解説します。
主な義務違反に対する罰則(労働安全衛生法)
労働安全衛生法には、義務違反に対する罰則が明確に定められています。主なものを確認しましょう。
【主な義務違反と罰則(概要)】
| 義務違反の内容例 | 罰則の内容(労働安全衛生法) |
| 産業医・衛生管理者・安全管理者の未選任 | 50万円以下の罰金(第120条) |
| 選任報告書の未提出・虚偽報告 | 50万円以下の罰金(第120条) |
| 衛生委員会・安全衛生委員会等の未設置 | 50万円以下の罰金(第120条) |
| 定期健康診断結果報告書の未提出・虚偽報告 | 50万円以下の罰金(第120条) |
| ストレスチェック関連の守秘義務違反 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第119条) |
| ストレスチェック関連の不利益取扱い | (直接的な罰則はないが、民事訴訟リスク等) |
| 休養室の未設置など(安衛則違反にあたる措置義務) | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(第119条) |
| 労働基準監督署への虚偽の報告・不出頭 | 50万円以下の罰金(第120条) |
※上記は主な例であり、個別の状況によって適用される条文や罰則が異なる場合があります。
※ストレスチェックの実施自体には直接的な罰則はありませんが、関連する報告義務違反や守秘義務違反には罰則があります。
このように、多くの義務違反に対して罰金刑が定められています。「これくらい大丈夫だろう」という安易な判断は禁物です。
罰則だけではない!義務違反がもたらす経営リスク
法的な罰則はもちろんですが、義務違反はそれ以外にも以下のような様々な経営リスクを引き起こす可能性があります。
- 行政指導・処分
- 企業名公表
- 労働災害発生時の責任
- 従業員の信頼失墜・エンゲージメント低下
- 採用活動への悪影響
- 社会的信用の低下
従業員50人以上の事業場における労働安全衛生法上の義務は、単なる手続きではなく、従業員の命と健康を守り、ひいては企業の持続的な成長を支えるための経営基盤そのものです。
罰則やリスクを回避するためだけでなく、従業員が安心して働ける職場環境を構築するという前向きな視点で、早期かつ確実に対応を進め、継続的に安全衛生管理体制を整備していくことが重要です。必要に応じて、社労士などの専門家の支援を活用することも検討しましょう。
従業員数が50人前後の企業では、労働安全衛生法上の義務以外にも、特に以下の制度への対応が同時に必要となるケースが多くあります。
社会保険の適用拡大
パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)加入義務の対象となる企業規模要件が段階的に引き下げられています。
51人以上の企業では、週20時間以上働くなどの要件を満たす短時間労働者も社会保険に加入させる必要があります。カウント方法などが労働安全衛生法とは異なるため、注意が必要です。
【あわせて読みたい】
2024年10月〜パート・アルバイトの社会保険の適用範囲が拡大!企業が取るべき対応と影響を解説
障害者雇用の義務
民間企業には、常時雇用する労働者数に応じて、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。
40.0人以上の企業が対象となるため、50人規模の企業はこちらの対応も必要です。雇用状況の報告なども求められます。
企業の成長段階に応じて、求められる労務管理・安全衛生管理のレベルも変わってきます。自社の従業員数の推移を把握し、それぞれの節目でどのような対応が必要になるのか、早めに情報を収集し、計画的に準備を進めることが、スムーズな企業運営とコンプライアンス遵守の鍵となります。
従業員50人以上の義務に関するよくある質問(Q&A)
取締役などの役員は人数に含めますか?
役員であっても、代表権や業務執行権を持たず、工場長や部長などの職務に就き、労働者として賃金を受けている実態があれば「労働者」としてカウントの対象となります。代表取締役など、純粋な経営者は通常含めません。
業務委託契約のフリーランスなどは含めますか?
業務委託契約や請負契約に基づき働く方は、労働者には該当しないため、原則としてカウントに含めません。ただし、契約形式に関わらず、実態として会社の指揮命令下で働いていると判断される場合(偽装請負など)は、労働者として扱われる可能性があります。
従業員数が50人前後で変動する場合や、50人未満になった場合の義務はどうなる?
義務の発生・継続・解除は、一時的な従業員数の増減ではなく、「常態として」50人以上の労働者を使用しているかどうかで判断します。
◯義務の発生
繁忙期など一時的に50人を超えても、常態として50人未満であれば、通常は義務は発生しません。年間を通じての実績や今後の雇用計画で判断します。
◯義務の継続
一度義務が発生した後、一時的に従業員数が50人を下回っても、すぐに義務が解除されるわけではありません。常態として50人以上使用している状況が続く限り、義務は継続します。
◯義務の解除
人員整理などで「常態として」50人未満となることが明確になった場合に、義務は形式上解除されます。ただし、解除後も安全衛生体制を維持することが望ましい場合が多く、解除に関する手続き(選任解除の届出等)が必要か労働基準監督署に確認することをおすすめします。
いずれのケースも、判断に迷う場合は、過去の従業員数の推移や今後の雇用計画などを踏まえ、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。
日雇いや数日のみの短期アルバイトは含めますか?
雇用期間の長短にかかわらず、「常態として使用されている」と判断されれば、短期のアルバイトの方も「常時使用する労働者」の人数カウントに含める必要があります。
ポイントは「常態として使用されているか」どうかです。
例えば、日雇い契約や数日間のみといった、雇用期間が極めて短く臨時的な場合は「常時」使用とは言えず、通常はカウントに含まれません。
しかし、短期の契約であっても、それが繰り返し更新され、事実上継続して雇用されているような実態があれば、「常態として使用されている」とみなされ、カウント対象となる可能性が高いです。個々の契約や勤務の実態に基づいて判断することが重要です。
在宅勤務中心の場合の数え方は?
在宅勤務(テレワーク)を行っている従業員も、会社と雇用契約がある労働者ですので、「常時使用する労働者」の人数カウントの対象となります。
論点となるのは「事業場」の考え方です。一般的には、在宅勤務者が所属し、業務上の指揮命令を受けているオフィス(本社、支店、営業所など)が事業場とみなされ、その事業場の従業員数としてカウントされます。
仮に、在宅勤務者がある程度まとまって所属し、独立した労務管理機能を持つサテライトオフィスのような場所があれば、そこが独立した事業場となる可能性もあります。どこで労務管理され、指揮命令を受けているかが判断のポイントです。迷った場合は、これも労働基準監督署に確認するのが確実です。
この記事では、従業員数が常時50人以上に達した事業場に課される労働安全衛生法上の主な義務と、その対応手続き、適用範囲となる「常時50人以上」や「事業場」の定義、そして義務違反のリスクについて、わかりやすく解説してきました。
産業医や衛生管理者の選任、衛生委員会の設置・運営、ストレスチェックの実施と報告、定期健康診断結果報告書の提出、そして休養室の設置などは、単なる事務手続きではありません。これらはすべて、従業員の皆さんが心身ともに健康で安全に働き続けることができる職場環境を維持・向上させるための、企業にとって非常に重要な取り組みです。
法令を遵守することはもちろんですが、これらの義務に早期かつ適切に対応することが、労働災害やメンタルヘルス不調を未然に防止し、従業員からの信頼を高め、ひいては企業の持続的な成長を支える基盤となります。
「そろそろ50人を超えそうだ」「超えたばかりで何から手をつければいいか分からない」という人事・労務担当者の方は、まずこの記事でご紹介した義務のポイントやQ&Aを参考に、自社の状況を正確に把握することから始めましょう。そして、14日以内や遅滞なくといった期限のある手続きも多いため、計画的に準備を進めることが何よりも大切です。
とはいえ、特に設立間もない企業や、担当者が他の業務も兼任している場合、複雑な手続きや専門的な対応をすべて自社だけで完璧に行うのは、時間的にも知識的にも負担が大きいかもしれません。
そのような場合、対応に不安がある、あるいはより効率的・確実に進めたいとお考えであれば、社労士など、外部の専門家のサポートを活用することも有効な選択肢です。
特に、「顧問契約を結ぶほどではないけれど、必要な手続きだけをスポットで依頼したい」「オンラインで気軽に専門家に相談できる方法を探している」といったニーズをお持ちの企業には、顧問料0円から、必要な手続きの申請代行や労務相談をスポットで依頼できる「社労士クラウド」のようなサービスも、有力な選択肢の一つとなるでしょう。
自社の状況やニーズに合ったサポート形態を検討してみてはいかがでしょうか。
【あわせて読みたい】
社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|