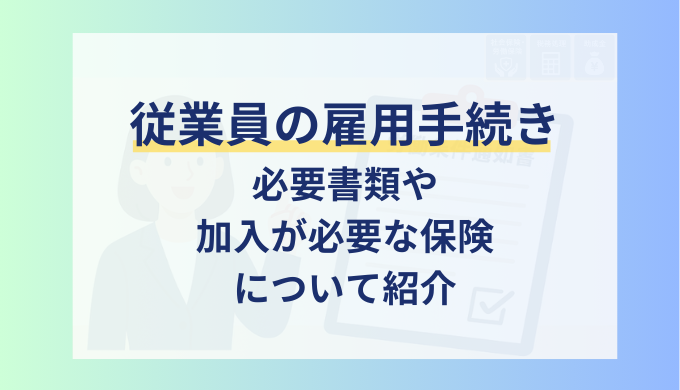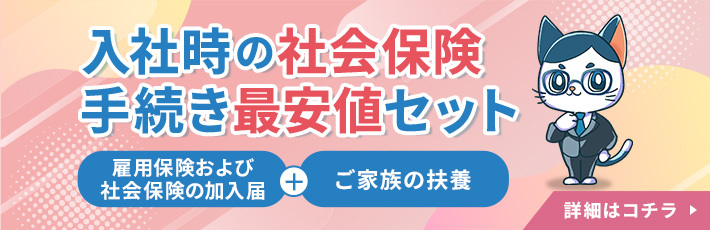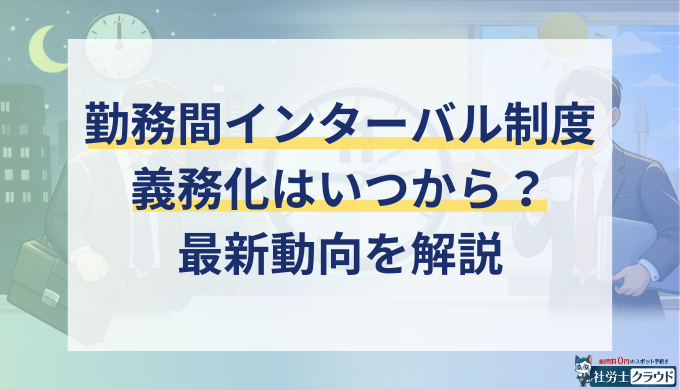従業員を初めて雇用する、あるいは新たに正社員・パート・アルバイトを採用して入社させるとき、会社側には多くの手続きが求められます。
労働条件通知書や雇用契約書の作成・交付に加え、社会保険・雇用保険・労災保険の加入手続き、所得税や住民税に関する税務処理、さらに法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の整備まで、やるべきことは多岐にわたります。
社会保険・労働保険や税金に関する各種手続きには法律で提出期限が定められており、期限を守らなければ従業員とのトラブルや行政からの指導につながるおそれがあります。
一方で、手続きの全体像を正しく把握し、必要書類や提出先を整理して進めれば、事業主自身でも対応は可能です。
本記事では、従業員の雇用手続きについて流れや必要書類、加入が必要になる保険、税金の手続きについてわかりやすく解説しています。
さらに、会社設立直後の事業主様や初めて人を雇う個人事業主様でも安心して進められるよう、ケース別の注意点や活用できる助成金制度も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
YouTubeでも従業員の入社時に会社側が行う社会保険と労働保険の手続きについて詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
従業員を雇用する際の手続きは、多岐にわたりますが、一般的に次の3つのステップで進めます。
労働条件通知書や雇用契約書を用意し、就業場所・勤務時間・賃金などを明確に定めます。従業員との認識のズレを防ぎ、後のトラブルを回避するための重要な手続きです。
管轄の年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ必要書類を提出し、従業員を公的な保険制度に加入させます。法律で定められた事業主の義務となります。
毎月の給与から天引きするために必要な「給与所得者の扶養控除等申告書」を従業員から回収したり、住民税の納付方法を切り替えるための届出を行ったりします。
従業員を雇用する際の手続きには、それぞれ法律で定められた期限があります。手続きの漏れは、従業員とのトラブルや行政からの指導につながる可能性があるため、全体の流れを正確に把握しておくことが重要です。
| 【手続きの抜け漏れ防止チェックリスト】 □ 労働条件通知書・雇用契約書の交付および署名完了 □ 社会保険の被保険者資格取得届を入社日から5日以内に提出 □ 雇用保険の被保険者資格取得届を入社月の翌月10日までに提出 □ 労災の保険関係成立届を雇入れ翌日から10日以内、概算保険料申告を50日以内に提出・納付 □ 扶養控除等申告書・前職の源泉徴収票・住民税特別徴収の異動届を回収・処理 □ 給与計算システムへ家族情報・通勤手当・保険料天引き設定を登録 |
従業員を雇用する際には、会社が準備して従業員に交付する書類と、従業員から提出してもらう書類の2種類があります。
特に、会社が準備する書類の中でも「労働条件通知書」の交付は、労働基準法で定められた事業主の重要な義務です。
ここではまず、会社が主体となって準備し、従業員との間で取り交わす「労働条件通知書」と、トラブル防止のために作成が推奨される「雇用契約書」について解説します。
労働条件通知書
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、会社が従業員に対して交付を法律で義務付けられている書類です。この書類は、賃金や労働時間、休日といった労働条件を従業員に書面で明示するためのもので、「言った、言わない」といった後の労務トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。
雇用契約書を作成した場合でも、この労働条件通知書の交付義務はなくならないため、必ず準備が必要です。
労働条件通知書に記載すべき内容は法律で厳密に定められています。特に、以下の「絶対的明示事項」(必ず書面で明示しなければならない事項)に漏れがあると、法律違反となる可能性があるため注意が必要です。
【絶対的明示事項(書面での明示が必須)】
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務の内容(※2025年4月以降は「変更の範囲」も明示必須)
- 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇
- 賃金の決定・計算方法、支払時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
そのため、労働条件通知書の作成は、社会保険労務士などの専門家に依頼することが最も安全で確実な方法です。
もしご自身で作成される場合には、少なくとも厚生労働省が提供する最新の様式(テンプレート)を必ず参考にし、記載事項に漏れがないよう細心の注意を払って作成してください。厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からは、様々な雇用形態に対応した労働条件通知書のテンプレートをダウンロードできます。
雇用契約書
雇用契約書は、労働条件通知書で示された内容について、会社と従業員の双方が合意したことを証明するための契約書類です。 労働条件通知書が会社からの一方的な「通知」であるのに対し、雇用契約書は双方の署名・捺印を取り交わす「合意の証」となる点が大きな違いです。
法律上の作成義務はありませんが、双方の認識違いによるトラブルを防止するという観点から、実務上は作成が必須と言えます。
特に、万が一のトラブルが発生した際に会社の正当性を主張するための重要な証拠となるため、必ず作成・保管しておきましょう。
実務では、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一つの書類にまとめ、従業員に内容を説明の上で署名・捺印をもらい、会社と従業員の双方で1部ずつ保管する方法が一般的で効率的です。
 雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?
雇用契約書(労働条件通知書)の法的な必要性と事業主の義務とは?
会社が準備する書類とは別に、社会保険や税金の手続きを正確に行うために、入社する従業員から提出してもらうべき重要な書類が多数あります。
これらの提出書類は、社会保険・雇用保険の加入手続きや、毎月の給与計算(所得税の源泉徴収・住民税の特別徴収)、給与振込先の登録などに不可欠です。提出が遅れると、従業員の保険証の発行が遅れたり、給与計算に支障が出たりする可能性があるため、入社時に確実に回収する仕組みを整えることが重要です。
以下に、一般的に従業員から提出を求める書類の一覧を紹介します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- マイナンバー(個人番号)
- 年金手帳 または 基礎年金番号通知書(基礎年金番号)
- 雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証番号)
- 源泉徴収票(前職がある場合)
- 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
- 住民票記載事項証明書
- 給与振込先の口座情報
- 通勤手当の申請に関する書類
| チェックリスト □ 入社初日に全ての提出書類を回収できるよう、事前に従業員へ案内したか □ マイナンバーを収集する際、「番号確認(マイナンバーカード等)」と「本人確認(運転免許証等)」の両方を行ったか □ 前職の源泉徴収票が提出されない場合、従業員自身で確定申告が必要になることを説明したか |
従業員を雇用した場合、事業主には、その従業員を社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる法律上の義務があります。これは従業員の病気や怪我、将来の年金生活を支えるための国の制度であり、会社の信頼性にも直結する非常に重要な手続きです。
特に、法人事業所(株式会社など)であれば、従業員を1人でも雇用した場合は強制的に適用事業所となり、社会保険への加入が必須となります。
手続きは、主に従業員の入社日(資格取得日)から5日以内に、管轄の年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出して行います。この手続きは提出期限が非常に短いため、入社前から準備を進めておくことが重要です。
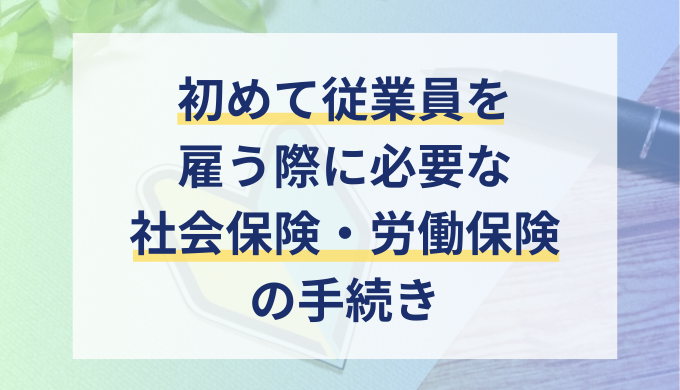 初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険・労働保険の手続きを解説!
加入条件
社会保険の加入義務は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった短時間労働者にも、以下の要件を満たす場合には適用されます。自社で雇用する従業員がどの条件に該当するのかを正確に把握しておきましょう。
【原則的な加入対象者】
- 法人の事業所で常時使用される従業員(代表者や役員も含む)
- 個人事業所でも、常時5人以上の従業員を雇用する場合(※農林水産業、サービス業の一部などを除く)
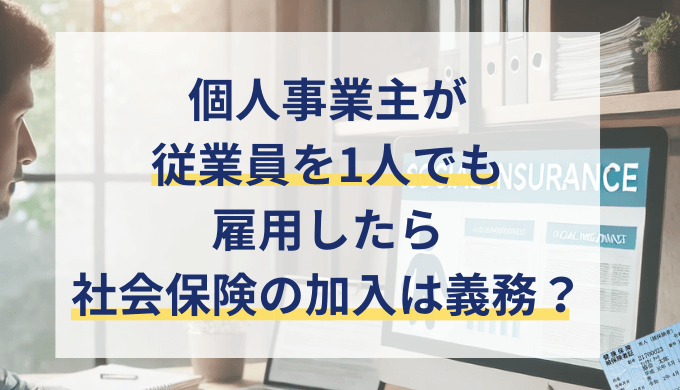 個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
個人事業主が従業員1人、5人以下を雇う場合の社会保険加入の条件は?手続きや注意点も解説
【パート・アルバイト等の短時間労働者の主な加入要件】
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
- 学生でないこと
これらの加入条件を満たす従業員がいる場合は、手続きの準備が必要です。
 【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
社会保険と並行して、事業主は従業員を労働保険(雇用保険・労災保険の総称)に加入させる法律上の義務があります。労働保険は、従業員が失業した場合や、業務中・通勤中に怪我をした場合などに生活を保障するための、国による重要なセーフティネットです。
従業員を一人でも雇用した事業主は、原則として労働保険の適用事業所となり、手続きを行わなければなりません。
従業員を一人でも雇用した事業主は、原則として労働保険の手続きを行わなければなりません。手続きが多岐にわたるため、まず最初に、主な届出の種類と提出先、期限を一覧で確認しましょう。
【労働保険の主な手続き一覧】
| 届出の種類 | 提出先と提出期限 | 備考 |
| 保険関係成立届 | 労働基準監督署 (雇用日の翌日から10日以内) | 初めて従業員を雇用した際 |
| 概算保険料申告書 | 労働基準監督署・銀行等 (保険関係成立の日から50日以内) | 初めて従業員を雇用した際 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク (設置の事実があった日の翌日から10日以内) | 初めて雇用保険対象者を雇用した際 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク (雇用した月の翌月10日まで) | 従業員ごと |
これらの手続きを怠ると、遡って保険料を徴収されるだけでなく、万が一の際に従業員が給付を受けられないという重大なリスクにつながるため、確実な対応が求められます。
雇用保険の手続き
雇用保険は、従業員が失業した際の生活の安定や再就職の支援を目的とするほか、育児休業や介護休業を取得した際の給付金の原資ともなる制度です。
手続きには、①会社として初めて従業員を雇用した際に行う手続きと、②従業員ごとに行う手続きの2段階があります。
① 雇用保険適用事業所設置届の提出(初回のみ)
初めて雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合、まず会社自体が雇用保険の適用事業所になるための「雇用保険適用事業所設置届」を、設置の事実があった日(=最初の従業員を雇用した日)の翌日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出する必要があります。
② 雇用保険被保険者資格取得届の提出(従業員ごと)
上記の設置届とあわせて、個々の従業員を雇用保険に加入させるための「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。この届出は、2人目以降の従業員を雇用する際にも、その都度必要となります。提出期限は、従業員が入社した月の翌月10日までです。
加入条件
雇用保険の加入対象となるのは、以下の要件をすべて満たす従業員です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
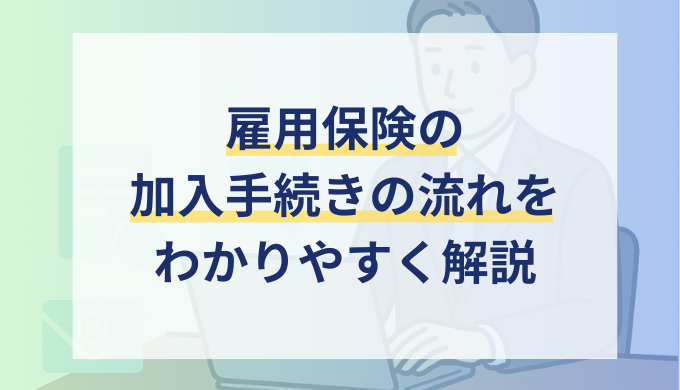 雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
雇用保険の加入手続きの方法を解説!必要書類・手続きの流れを含めて紹介
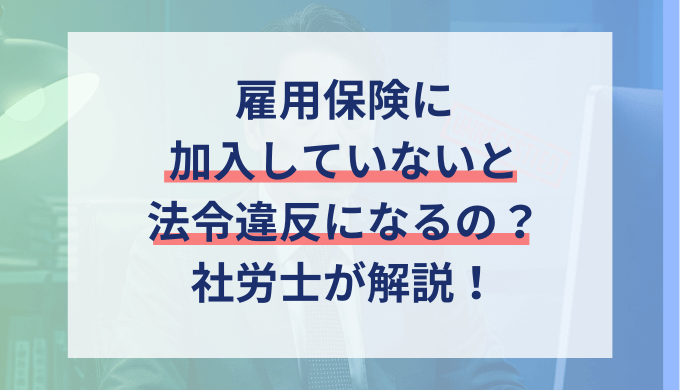 雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
労災保険の手続き
労災保険(労働者災害補償保険)は、従業員が業務上の事由または通勤中に、負傷、疾病、障害、死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険の最大の特徴は、正社員・パートタイマー・アルバイトといった雇用形態を問わず、全ての従業員が加入対象となる点です。たとえ1日だけの雇用であっても、事業主には加入手続きの義務が発生します。
手続きは、初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、管轄の労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出することから始まります。その後、50日以内に「労働保険 概算保険料申告書」を提出し、その年度分の労働保険料を納付する必要があります。
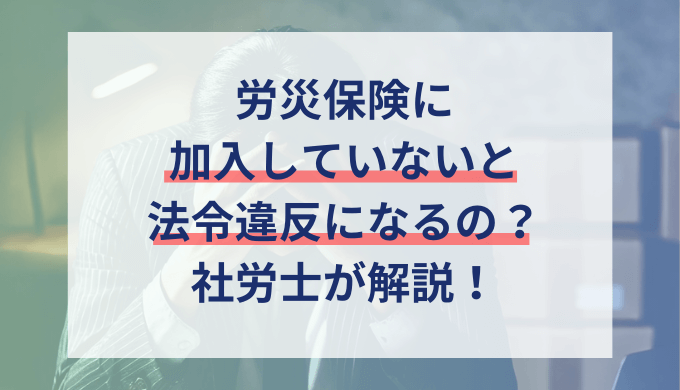 労災保険に加入していないと違法?未加入時の会社のリスクと対応方法を解説
労災保険に加入していないと違法?未加入時の会社のリスクと対応方法を解説
従業員に給与を支払う事業主には、社会保険料のほかに、所得税と住民税を従業員に代わって国や市区町村に納付する法律上の義務があります。
所得税は毎月の給与から天引き(源泉徴収)し、住民税は市区町村からの通知に基づき天引き(特別徴収)するのが原則です。どちらも正確な給与計算に直結するため、入社時に必要な書類を確実に回収し、正しい税額を控除できる体制を整えることが重要です。
所得税の手続き
所得税の手続きとは、会社が従業員の毎月の給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、従業員本人に代わって税務署に納税する手続きのことです。
【主な手続き】
1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の回収
源泉徴収する所得税の金額は、この申告書に記載された扶養家族の人数などに基づいて決定されます。この書類が提出されない場合、本来より高い税率(乙欄)で税額を計算することになり、従業員の手取り額が大きく減ってしまうため、入社時に必ず回収してください。
2.「給与支払事務所等の開設届出書」の提出(初回のみ)
初めて従業員を雇用し給与の支払いを開始する事業主は、給与支払事務所を開設した日から1か月以内に、所轄の税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。
源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに国に納付します。
住民税の手続き
住民税の手続きとは、主に中途入社した従業員の住民税の納付方法を、個人で納付する「普通徴収」から、会社が給与から天引きして納付する「特別徴収」へ切り替える手続きのことです。
新卒入社の従業員など、前年に所得がなかった場合は、入社初年度の住民税は発生しません。そのため、この手続きは主に前職で給与所得があった中途入社の従業員が対象となります。
【主な手続き】
「特別徴収への切替申請書」の提出
従業員から、前職の会社または市区町村から交付された住民税の納税通知書などを提出してもらい、その情報をもとに会社が「特別徴収への切替申請書(または依頼書)」を作成し、従業員が住んでいる市区町村へ提出します。
手続きが完了すると市区町村から会社宛てに通知が届き、給与からの天引きを開始できるようになります。
| チェックリスト □ 扶養控除等申告書を入社時に必ず回収したか □ 前職の源泉徴収票を受領し、年末調整の準備はできているか □ 所得税の源泉徴収額を、給与支払月の翌月10日までに納付する体制は整っているか □ 中途入社社員の住民税について、市区町村へ特別徴収への切替申請を行ったか |
従業員を一人でも雇用した場合、事業主には、労働基準法に基づき「法定三帳簿(ほうていさんちょうぼ)」を作成し、事業所に備え付けて保管する法律上の義務が発生します。
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの書類の総称です。この3つの帳簿は、従業員の労働状況を正確に把握し、適切な労務管理を行うための基礎となるだけでなく、労働基準監督署の調査(臨検監督)が入った際に、まず提出を求められる非常に重要な書類となります。
作成や保管を怠った場合、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があるため、従業員を雇用すると同時に必ず整備しなければなりません。
労働者名簿
労働者名簿は、雇用する従業員の氏名、生年月日、住所といった基本的な情報を管理するための帳簿です。従業員の情報を正確に把握し、各種手続きを円滑に進めるために作成が義務付けられています。
- 根拠条文: 労働基準法第107条
- 保存期間: 従業員の退職や死亡の日から5年間(※当面の間は3年間)
- 実務上のポイント: 記載内容に変更があった場合は、その都度すみやかに更新する必要があります。
賃金台帳
賃金台帳は、従業員一人ひとりに対して、支払った給与の金額や計算基礎などを記録するための帳簿です。給与が正しく支払われていることを証明する重要な書類となります。
- 根拠条文: 労働基準法第108条
- 保存期間: 最後の賃金を記入した日から5年間(※当面の間は3年間)
- 実務上のポイント: 給与明細と内容が一致しているか、社会保険料や税金の控除額が正確に記録されているかを確認します。クラウド型の給与計算ソフトを利用すると、多くの場合、自動で作成できます。
出勤簿
出勤簿は、従業員の日々の出勤・退勤時刻を記録し、労働時間を客観的に管理するための帳簿です。タイムカードやICカードの記録、パソコンの使用時間の記録などが該当します。
- 根拠条文: 労働基準法第109条(記録の保存義務)
- 保存期間: 従業員の最後の出勤日から5年間(※当面の間は3年間)
- 実務上のポイント: 賃金台帳に記載する労働時間数の根拠となるため、日々の労働時間(始業・終業時刻、休憩時間)を1分単位で正確に記録・管理する必要があります。
| チェックリスト □ 労働者名簿を従業員ごとに作成し、法律で定められた期間、保管する体制は整っているか □ 賃金台帳に基本給・手当・控除項目を正しく記録し、給与明細と一致しているか □ 出勤簿をタイムカードや勤怠管理システム等で整備し、客観的な労働時間を記録しているか □ 「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿の内容が、相互に矛盾なく整合しているか |
労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間・週40時間」までと上限が定められています(法定労働時間)。
この法定労働時間を超えて従業員に残業をさせたり、法律で定められた休日に労働させたりする場合には、あらかじめ従業員の代表と会社との間で協定を結び、「36(サブロク)協定」として労働基準監督署に届け出る必要があります。
この届出をせずに残業や休日出動をさせることは法律違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
少しでも残業や休日労働の可能性があるならば、最初の従業員を雇用したタイミングで、「保険関係成立届」などと一緒に提出しておくべき手続きです。
36協定に関しては以下の記事をご参照ください。
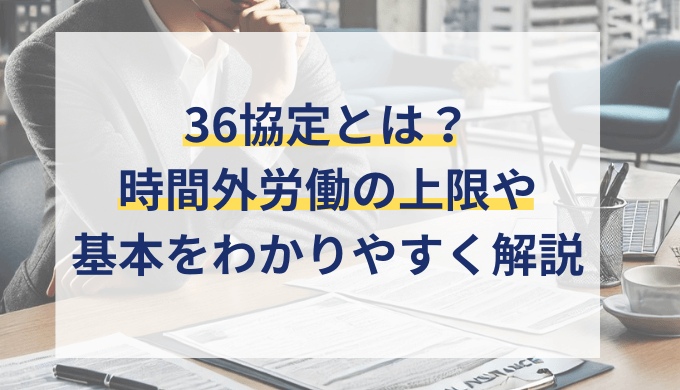 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
基本的な手続きの流れは同じですが、事業所の状況や雇用する従業員の属性によって、特に注意すべき点がいくつか存在します。ここでは、特に質問が多い「個人事業主」「パート・アルバイト」「外国籍従業員」の3つのケースについて、それぞれの手続きのポイントを解説します。
個人事業主が初めて従業員を雇う場合
個人事業主であっても、従業員を一人でも雇用した場合は、法人と同様に労働保険(労災保険・雇用保険)への加入義務が発生します。まずは管轄の労働基準監督署で「保険関係成立届」を提出し、ハローワークで「雇用保険適用事業所設置届」の手続きを行わなければなりません。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、常時雇用する従業員が5人以上になった場合に加入義務が発生します(※農林水産業、サービス業の一部などを除く)。従業員が4人以下の場合は加入義務はありませんが、従業員の福利厚生を手厚くするために、任意で加入することも可能です。
また、法人と比べて就業規則や法定三帳簿の整備が後回しになりがちですが、これらは個人事業主であっても法律で義務付けられているため、最初の雇用時点で必ず準備を進めておくことが重要です。
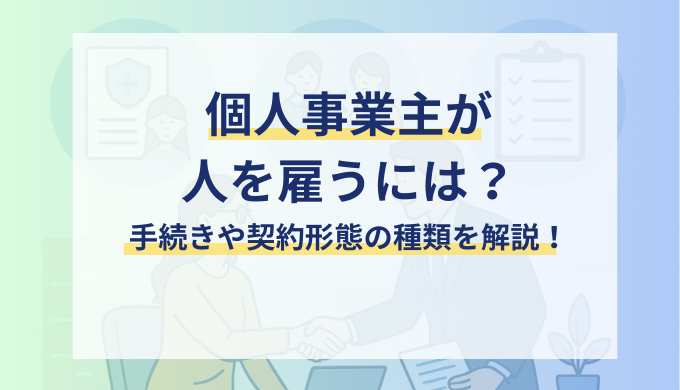 個人事業主が人を雇う際に必要な手続きやメリットを解説!社員・業務委託など、契約形態別の違いや注意点は?
個人事業主が人を雇う際に必要な手続きやメリットを解説!社員・業務委託など、契約形態別の違いや注意点は?
パート・アルバイト雇用時の注意点
パートタイマーやアルバイトを雇用する場合、最も重要な注意点は**「正社員と同様に労働基準法が適用される」**という点です。特に、社会保険と雇用保険の加入条件を正確に確認しなければなりません。
【社会保険の主な加入要件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
- 学生でないこと
また、労働条件を明示する「労働条件通知書」の交付も必須です。その際、通常の記載事項に加え、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、以下の項目についても明示することが法律で定められています。
- 昇給の有無
- 賞与(ボーナス)の有無
- 退職金の有無
外国籍の従業員を雇用する場合の注意点
外国籍の従業員を雇用する場合、他の手続きに先立って、必ず「在留カード」を確認し、就労が許可されているかを確認しなければなりません。不法就労をさせた場合、事業主も罰則(不法就労助長罪)の対象となるため、極めて重要な確認事項です。
【在留カードで確認すべきポイント】
- 在留資格: 「技術・人文知識・国際業務」など、就労が認められている資格か確認します。
- 就労制限の有無: 「就労不可」と記載されていないか、許可されている業務内容と実際の業務が一致しているかを確認します。
- 在留期間: 在留期間が満了していないかを確認します。
また、外国籍の従業員を雇用した場合(および離職した場合)は、その事実をハローワークへ届け出る**「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。この届出は、雇用保険の加入手続きとは別に、雇用した月の翌月10日まで**に行う必要があります。
| チェックリスト □ 【個人事業主】初めての雇用時に、労働保険関係成立届と雇用保険適用事業所設置届を提出したか □ 【パート・アルバイト】所定労働時間と賃金を確認し、社会保険の適用対象となるかを正確に判定したか □ 【外国籍従業員】**在留カードで就労資格を必ず確認し、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行ったか |
従業員を雇用する際に活用できる助成金制度
従業員の雇用や人材育成に取り組む事業主を支援するため、国は返済不要の助成金制度を多数用意しています。国の助成金制度を活用することは、採用コストなどの経済的負担を軽減するだけでなく、従業員のスキルアップや定着率の向上にもつながる、有効な経営戦略の一つです。
特に、非正規雇用の従業員のキャリアアップを支援する「キャリアアップ助成金」は、多くの企業で活用されています。
【キャリアアップ助成金の主な活用例】
- 有期雇用の従業員(パートタイマーなど)を正社員に転換した場合
- 従業員のために、賞与や退職金制度を新たに導入した場合
- 従業員に専門的な訓練(OJT・Off-JT)を実施した場合
ただし、助成金は自動的に受け取れるものではなく、適切な手順で申請を行う必要があります。多くの場合、取り組みを始める前に「計画書」を管轄の労働局へ提出し、認定を受ける必要があったり、申請には厳密な期限が設けられていたりと、手続きは非常に複雑です。
雇用手続きと助成金の申請は密接に関連しています。自社で活用できる助成金があるか知りたい、申請手続きをスムーズに進めたいといった場合には、社会保険労務士などの専門家へ早めに相談することを検討しましょう。
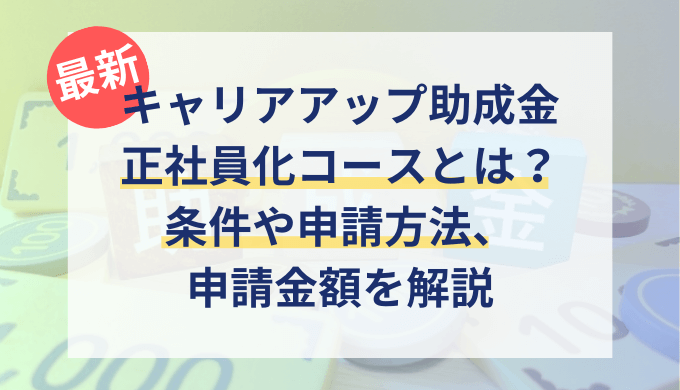 【令和7年版】キャリアアップ助成金の正社員化コースとは?条件や申請方法、支給金額を社労士がわかりやすく解説
【令和7年版】キャリアアップ助成金の正社員化コースとは?条件や申請方法、支給金額を社労士がわかりやすく解説
従業員の雇用手続きに関するよくあるQ&A
従業員の雇用手続きを進める上では、実務上の細かい疑問やイレギュラーな事態が発生することも少なくありません。ここでは、人事・労務担当者から特に多く寄せられる3つの質問について、具体的な対応方法を解説します。
従業員が年金手帳や雇用保険被保険者証を紛失した場合は?
結論として、紛失した場合でも再発行が可能です。 従業員から紛失の申し出があった場合は、慌てずに再発行の手続きを案内してください。
◯年金手帳(基礎年金番号)を紛失した場合
手続きに必要なのは「基礎年金番号」です。従業員本人が、最寄りの年金事務所の窓口で本人確認書類を提示すれば、「基礎年金番号通知書」を即日再発行してもらえます。会社として、この手続きを従業員に案内してください。
◯雇用保険被保険者証を紛失した場合
手続きに必要なのは「雇用保険被保険者番号」です。従業員本人が、最寄りのハローワークの窓口で「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出すれば、原則として即日再発行が可能です。 実務上は、会社が「資格取得届」を提出する際に、備考欄に前職の会社名を記載すれば、ハローワーク側で番号を特定してくれるケースも多いです。
提出期限に間に合わなかった場合は?
気づいた時点ですぐに、管轄の行政機関(年金事務所やハローワークなど)へ連絡し、速やかに書類を提出してください。
手続きの遅延を放置すると、以下のようなリスクが発生します。
◯従業員への不利益
社会保険の資格取得届が遅れると、従業員の健康保険証の発行が遅れます。その間に医療機関を受診した場合、従業員は一時的に医療費を全額(10割)自己負担しなければならなくなります。
◯会社へのペナルティ
行政機関からの指導が入るほか、悪質なケースと判断された場合は、延滞金や追徴金が課されたり、遡って保険料を徴収されたりする可能性があります。法律上は罰則(懲役や罰金)も定められています。
手続きの遅延は、従業員との信頼関係を損ない、会社の信用問題にもつながります。期限内の手続きを徹底してください。
従業員への説明で気をつけるべきことは?
従業員に安心して入社してもらい、スムーズに書類を提出してもらうためには、丁寧なコミュニケーションが不可欠です。特に以下の3つの点を意識してください。
1.必要書類のリストを事前に渡す
入社日までに準備すべき書類を一覧にしたチェックリストを、内定通知などとあわせて事前に渡しておきましょう。「いつまでに」「何を」準備すればよいかが明確になり、提出漏れを防ぎます。
2.書類の利用目的を明確に伝える
特にマイナンバーなどの個人情報を提出してもらう際は、「法律に基づき、社会保険と税金の手続きにのみ利用します」といったように、具体的な利用目的を明確に伝えることが重要です。従業員の不安を払拭し、信頼関係を築くことにつながります。
3.質問できる窓口を案内する
「手続きに関して不明な点があれば、担当の〇〇まで気軽に質問してください」と一言添え、相談しやすい雰囲気を作ることが大切です。
本記事では、従業員を雇用する際に会社側が行うべき手続きについて、網羅的に解説しました。
従業員を一人雇用すると、労働条件の明示、社会保険・労働保険の手続き、税金の手続き、法定三帳簿の整備など、事業主が対応すべき業務は多岐にわたります。従業員を雇用する際の手続きには、それぞれに法律で定められた期限があり、一つでも漏れがあると、罰則の対象となるだけでなく、何よりも従業員との信頼関係を損なう原因となりかねません。
正確な手続きを期限内に完了させることは、法令を遵守するだけでなく、従業員が安心して働ける職場環境の基礎を築くための第一歩です。
とはいえ、本記事で解説した通り、従業員の雇用手続きは複雑で、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。手続きに少しでも不安がある場合や、事業主様が本業に専念できる体制を整えたいとお考えの場合は、専門家である社会保険労務士への相談・依頼を検討することをおすすめします。
スポット申請代行サービスの社労士クラウド
従業員の雇用手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。
「初めての雇用で、何から手をつければいいか分からない」 「本業が忙しく、手続きに時間をかけられない」 「法改正に対応できているか不安なので、専門家のサポートが欲しい」
このようなお悩みをお持ちの事業主様は、ぜひ**「社労士クラウド」**にご相談ください。
社労士クラウドは、顧問料0円から、入社時の社会保険手続きなどを1名様分から代行するスポットサービスを提供しており、必要な手続きだけを低コストで専門家に依頼することが可能です。
従業員が安心して入社し、事業主様が本業に専念できる体制づくりのために、ぜひ社労士クラウドの活用をご検討ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|