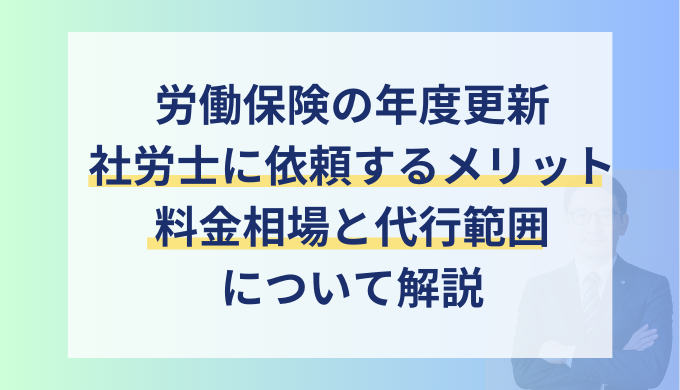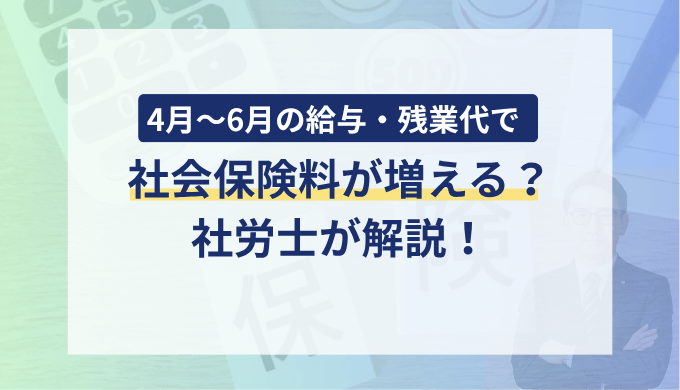労働保険の年度更新は、従業員を雇用する事業主にとって、毎年必ず対応すべき重要な手続きです。
この手続きには、賃金総額の集計や保険料の計算など、専門知識が求められる複雑な作業が多く含まれます。そのため、社労士に依頼することで、より正確かつスムーズな対応が可能になります。
また、申告・納付が期限に遅れたり、記載ミスがあったりすると、追徴金が課されたり修正申告の手間が生じたりするリスクも無視できません。
この記事では、労働保険の年度更新を社労士に依頼するメリット、代行可能な業務範囲、そして気になる報酬相場について、詳しく解説していきます。
本記事を、自社で対応するか、専門家である社労士への依頼を検討するか、最適な選択をするための判断材料としてご活用ください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
労働保険の年度更新や算定基礎届など、労働保険・社会保険の手続きは、1年のうちで決まったタイミングで発生するものと、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きが必要なもの、また生年月日に応じて必要な必須の手続きがあります。
⇒社会保険・労働保険手続きの年間スケジュール(PDF)を無料ダウンロード
事業を運営し、従業員を雇用されている事業主にとって、毎年必ず対応しなければならない重要な手続きの一つが「労働保険の年度更新」です。
労働保険の年度更新とは、事業主が毎年1回、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の申告と納付を行う手続きのことです。
具体的には、前年度(前年の4月1日から当年3月31日)に支払いが確定した賃金総額に基づいて確定保険料を算出して報告し、新年度(当年の4月1日から翌年3月31日)に見込まれる賃金総額から概算保険料を計算して申告・納付する、という一連の手続きです。
つまり、前年度分の保険料を精算し、当年度分の保険料を概算で前納する、年に一度の大切な申告手続きです。
労働保険の年度更新の期間は、原則として毎年6月1日から7月10日までと定められており、令和7年度(2025年度)は6月2日(月)~7月10日(木)が申告期間となっています。
この期限内に、必要な書類を作成し、管轄の労働局や労働基準監督署へ提出、そして保険料の納付までを完了させなければなりません。
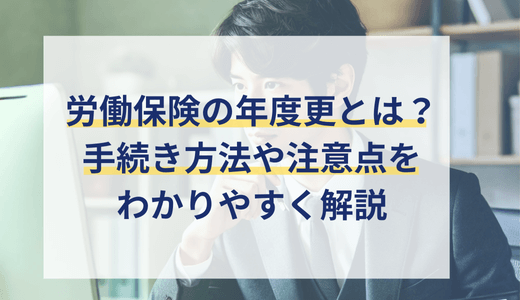 【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
労働保険(労災保険・雇用保険)のおさらい
労働保険とは、一つの保険制度を指す名称ではなく、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」という二つの社会保険制度を総称したものです。
農業の一部などを除き、労働者を一人でも雇用している事業であれば、企業規模や業種に関わらず、原則として加入することが法律で義務付けられています。
【労災保険と雇用保険の概要】
| 保険の種類 | 制度の内容 | 適用対象 |
| 労災保険 | 労働者が業務上や通勤途中に負傷したり、病気になったりした場合に、治療費や休業中の給付を行う制度 | 原則として労働者を一人でも雇用しているすべての事業所 |
| 雇用保険 | 労働者が失業した場合に生活の安定を図るための給付を行ったり、再就職を支援したりする制度 | 原則として労働者を一人でも雇用しているすべての事業所(一部例外あり) |
年度更新では、この二つの保険の保険料をまとめて申告・納付することになります。特に、年度更新の際に正確な賃金総額の集計が求められるため、年度途中で人員の増減や賃金の変更が多かった場合は、計算が複雑になることがあります。
また、近年は電子申請の利用が推奨されており、電子申請を使えば、労働局や労働基準監督署に直接出向く手間が省け、書類のミスも減らせます。電子申請に不安がある場合は、社労士に申請手続きを代行してもらう方法もおすすめです。
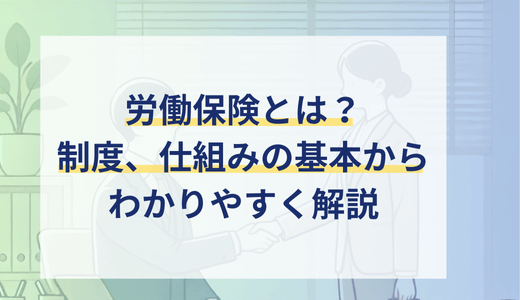 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく社労士が解説
労働保険の年度更新は、保険料の計算や申告書類の作成など、手順が複雑で時間もかかるため、事業主や担当者にとっては大きな負担になりがちです。
特に、年に一度の作業であるうえ、法改正が絡むと処理がさらに煩雑になり、対応に多くの手間と時間を取られることもあります。
労働保険の年度更新の手続きを社労士に任せることで、正確な申告ができるのはもちろんのこと、労働保険料の過払いを未然に防げるというメリットもあります。また、作業時間が大幅に削減されるため、本業に集中できる環境を整えることにもつながります。
ここからは、社労士に年度更新を依頼することで得られる具体的なメリットを、より詳しくご紹介していきます。
労働保険の年度更新業務を社労士に依頼することには、主に以下の3つの大きなメリットが考えられます。
- 正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避
- 複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減(コア業務への集中)
- 法改正への確実な対応
正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避
労働保険料の計算は、単に賃金総額に保険料率を掛けるだけではありません。
雇用保険と労災保険それぞれの保険料率の確認、対象となる労働者や賃金の範囲の正確な把握、算定期間中の入退社や雇用形態の変更の反映、端数処理など、細かなルールが多く存在します。
特に建設業のように有期 事業の要素がある場合などは、さらに注意が必要です。
もし計算方法を誤ったり、集計にミスがあったりすると、保険料を過剰に納付してしまうだけでなく、逆に少なく納付してしまい、後日、労働局などから指摘を受けて追徴金や延滞金が発生するリスクも伴います。
社労士は労働保険料の計算に関する専門的な知識を持っているため、正確な計算が可能です。
例えば、通勤手当や残業代などの各種手当の扱いや、短期で雇用したアルバイトの賃金の算入方法など、事業主が迷いやすいポイントも適切に処理できます。
また、申告書の記載ミスによる労働局からの問合せや、修正申告の手間も省くことができます。これにより、事業主は安心して本来の事業活動に集中することができるでしょう。
複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減(コア業務への集中)
2つ目のメリットとしては、煩雑な手続きからの解放による時間創出です。
年度更新の手続きには、賃金台帳などの書類を準備し、従業員一人ひとりの賃金データを集計、申告書への記入、そして労働基準監督署や労働局への提出、納付といった一連の作業が伴います。
特に、従業員人数が多い企業や、毎月の給与計算が複雑な事業所では、この期間、担当者は相当な時間と労力を費やすことになります。
事業主自身や、他の業務も兼任されている担当者がこれを行う場合、本来注力すべき経営判断や営業活動、顧客対応、現場管理といったコア業務にしわ寄せがいく可能性も否定できません。
社労士に年度更新業務を依頼(代行)すれば、これらの煩雑な事務作業から解放されます。創出された時間を、企業の成長に直結するより重要な業務に充てられるようになることは、経営上の大きなメリットと言えるのではないでしょうか。
さらに、申告書の作成だけでなく、電子申請や窓口への提出代行も社労士に依頼できるため、手続きの全プロセスを任せることが可能です。申告期限に間に合わせるための焦りや不安も軽減されます。
法改正への確実な対応
3つ目のメリットは、法改正への確実な対応です。
労働保険に関する法令や保険料率、申告書の様式などは、毎年のように改定されます。また、雇用保険に関する各種助成金の制度変更などが、年度更新の計算に関連してくるケースも考えられます。
こうした最新の制度改正を常に把握し、正確に手続きへ反映させることは、専門家でなければ容易ではありません。
例えば、保険料率の変更や、新たな助成金制度の創設など、事業主にとって有利な情報も含めて、適切なアドバイスを得ることができるでしょう。
社労士は、日頃から厚生労働省などの発表する最新情報に精通しており、法改正にも適切に対応した書類作成・申請を行います。
これにより、意図せず法令違反となってしまうリスクを防ぎ、コンプライアンスを遵守した企業運営にも繋がります。
このように、社労士に依頼することで、複雑な計算や手続きのミスを防ぎ適正な保険料納付を実現するとともに、事業主や担当者の負担を大幅に軽減し、法改正にも確実に対応できるという大きなメリットが期待できます。
特に、労務管理に専門的な知識を持つスタッフがいない中小企業にとっては、大きな安心感を得られる選択肢となるでしょう。
労働保険の年度更新において、社労士に依頼できる業務は多岐にわたります。具体的に依頼できる業務内容や範囲は、契約形態(スポット契約か顧問契約か)や個別の契約内容によって異なります。
ここでは、労働保険の年度更新においてどのような業務を社労士に依頼できるのか、一般的に代行してもらえる業務の範囲について解説していきます。
- 書類作成(賃金集計表、申告書など)
- 労働保険料の計算代行
- 電子申請または窓口への提出代行
- 労働局などからの問い合わせ対応
書類作成(賃金集計表、申告書など)
社労士に依頼できる業務の中心となるのが、年度更新に必要な書類の作成です。年度更新の申告書の作成は煩雑で手間がかかる作業です。
具体的には、労働保険概算・確定保険料 申告書はもちろんのこと、その計算の基礎となる「算定基礎賃金等の報告」(賃金集計表)の作成などが挙げられます。
特にこの賃金集計表は、前年度に従業員へ支払った賃金を正確に集計する必要があり、対象となる賃金の範囲や労働者の区分など、専門的な知識が求められる部分です。
例えば、以下のような細かな確認作業が多く含まれます。
- 賃金台帳や給与明細から、従業員ごとの賃金データを集計
- 労災保険と雇用保険それぞれの対象となる賃金の区分け
- 通勤手当、残業代、賞与などの各種手当の適切な扱い
- 短期間で雇用したアルバイトやパートの賃金の適切な算入
- 役員報酬の扱いの判断(労災保険のみ対象か、両方対象かなど)
また、書類作成は単純なケースばかりではありません。
例えば、年度途中で事業を開始したり廃止したりした場合、あるいは事業内容や従業員数に大きな変動があった場合など、通常とは異なる計算や書類の添付が必要となる特殊なケースでも、社労士であれば適切な対応が可能です。
さらに、申告書本体だけでなく、後日の労働局からの問い合わせの際に根拠資料としても重要となる賃金集計表や内訳書といった添付書類についても、正確に作成します。
特に建設業など一括有期事業に該当する場合には、「一括有期事業報告書」といった専門的な書類の作成も必要となりますが、これらも依頼することができます。
労働保険料の計算代行
書類作成と並んで年度更新の核心となるのが、労働保険料の計算です。社労士は、この複雑な保険料計算も代行します。
具体的には、以下のような計算を代行します。
- 業種ごとの労災保険料率の適用(事業の実態に合った料率の選定)
- 雇用保険料率の適用(一般の事業・農林水産・清酒製造の区分)
- 前年度の確定保険料の計算(実際の賃金総額に基づく)
- 当年度の概算保険料の計算(見込み賃金総額に基づく)
- 確定保険料と前納した概算保険料との差額の精算
- 一般拠出金(石綿健康被害救済法に基づく)の計算
特に、保険料の計算には様々な注意点があります。
例えば、千円未満の端数処理や、労災保険と雇用保険で異なる計算方法の適用など、細かいルールがあります。社労士はこれらのルールに精通しているため、ミスのない正確な計算が可能です。
また、事業主の状況に応じた最適な計算方法を提案することもできます。
例えば、概算保険料の算出において、前年度と比べて賃金総額が大きく変動する見込みがある場合には、それを考慮した金額を設定することで、後日の精算額を小さくすることができます。
電子申請または窓口への提出代行
作成・計算が完了した申告書を、事業主に代わって行政機関へ提出する手続きも社労士に代行を依頼できます。
近年、厚生労働省は電子申請(e-Govを利用した申請)を推奨しており、多くの社労士事務所がこの電子申請による代行に対応しています。
電子申請を利用すれば、労働局や労働基準監督署の窓口へ直接出向いたり、書類を郵送したりする手間が省け、時間やコストの削減につながります。
また、システムによる入力チェック機能があるため、記入ミスの防止も期待できます。電子申請に不慣れな方や、過去に設定で挫折した経験がある事業主にとっては、提出まで任せられるのは大きなメリットとなります。
もちろん、ご希望に応じて、従来通りの窓口提出や郵送による提出代行も可能です。
また、納付書の作成や納付方法の相談もできます。労働保険料は一括納付だけでなく、延納(3回分割)も選択できますので、事業主の資金繰りに合わせた提案も行ってくれます。
労働局などからの問い合わせ対応
年度更新の申告書を提出した後、まれに労働局などの行政機関から、記載内容の確認や不明点について問合せの連絡が入ることがあります。
例えば、前年と賃金総額が大きく異なる場合や、記載内容に疑問点がある場合などは、確認の連絡が入ることも考えられます。
社労士に年度更新業務を依頼している場合、こうした行政からの問合せへの対応についても、窓口となって代わりに行ってくれるケースが多くあります。
専門家が間に入ることで、スムーズかつ適切な対応が期待でき、事業主様が直接対応する負担を軽減できます。
ただし、この問合せ対応まで業務範囲に含まれるかどうかは、契約内容によって異なります。契約内容にもよりますが、具体的には次のような対応が考えられます。
- 労働局からの問い合わせ電話への対応
- 追加資料の作成と提出
- 説明が必要な場合の労働局への訪問
- 修正申告が必要な場合の手続き代行
- 追徴金・延滞金が発生した場合の対応
特に、年度更新業務のみを単発で依頼する「スポット契約」の場合には、提出までが業務範囲で、その後の問合せ対応は別途費用が発生したり、そもそも対応範囲外であったりする可能性があります。
一方、継続的な「顧問契約」を結んでいる場合は、顧問料の範囲内で対応してくれることが一般的です。
いずれにしても、依頼する際には、どこまでの問合せ対応が含まれるのか、追加費用が発生する可能性があるのか等、業務範囲と費用について事前にしっかりと確認しておくことが非常に重要です。
労働保険の年度更新を社労士に依頼する際、気になるのが費用面です。ここでは、社労士への依頼における一般的な料金の報酬相場について紹介します。
主な契約形態には、年度更新業務だけを単発で依頼する「スポット契約」と、月額の顧問料を支払うことで継続的に労務サポートを受ける「顧問契約」の二種類があります。
顧問契約の料金相場
社労士と顧問契約を結ぶ場合、月額の顧問料が発生します。
一般的な顧問料の相場は、企業の従業員規模によって大きく変動します。例えば従業員数10名未満の小規模な企業であれば、月額32,000円程度から依頼できるケースもあります。
顧問契約の場合、年度更新だけでなく、日常的な労務管理のサポートや各種届出の代行、就業規則の作成・見直しなど、幅広いサービスを受けることができます。
労働保険の年度更新手続きは、多くの場合、この月額顧問料の範囲内で対応してもらえます
【重要】顧問料に関する注意点
顧問料に関する注意点 月額顧問料も、従業員数はもちろんのこと、依頼する業務の範囲によって大きく異なります。
例えば、毎月の給与計算代行や勤怠管理まで依頼する場合、就業規則の新規作成や大幅な改定を依頼する場合(これらは通常、別途費用となることが多いです)、助成金申請を依頼する場合(成功報酬が設定されることが多い)など、契約に含める業務内容によって金額は変動します。
顧問契約は月々の費用が発生しますが、年度更新だけでなく日頃から労務に関する相談ができたり、他の手続きも任せられたりするため、人事・労務に関する業務負担を継続的に軽減したい企業にとっては、トータルで見ると費用対効果が高い選択肢となることもあります。
また、労務管理に関する相談も随時行えるため、トラブルの未然防止につながります。
顧問契約を検討する際は、複数の社労士事務所のサービス内容や料金体系を比較し、自社のニーズや状況に最も合ったプランを選ぶことをおすすめします。
スポット契約の料金相場
労働保険の年度更新手続きだけを単発で依頼したい場合に利用するのが「スポット契約」です。顧問契約を結んでいない場合や、特定の業務だけを専門家に任せたい場合に適しています。費用の目安として「32,000円」という料金設定を提示している社労士事務所もありますが、これはあくまで一例です。この金額は、従業員数や業務の複雑さによって変動することがあります。
例えば、従業員数が多い場合や、複数の事業所がある場合などは、基本料金に加算される場合もあります。
スポット契約のメリットは、必要な時期に必要な業務のみを依頼できることです。年度更新の時期だけ専門家のサポートを受けたい場合や、普段は自社で労務管理を行っているが年度更新だけは正確に行いたい場合などに適しています。
スポット契約の場合でも、依頼する業務範囲によって料金が変わることがあります。
例えば、賃金集計や申告書作成のみを依頼する場合と、電子申請や提出代行まで含める場合では、費用が異なる可能性があります。依頼前に、具体的な業務内容と料金について確認することをお勧めします。
【重要】スポット契約の料金に関する注意点
実際のスポット契約の料金は、企業の従業員数、業種(例:建設業など労災保険料率が高い、または計算が複雑な事業)、事業所の状況(支店の有無など)、そして具体的に依頼する業務範囲(例えば、労働局からの問合せ対応まで含むか否かなど)によって大きく変動します。
特に、従業員数は料金を決定する上で最も大きな要因となることが一般的です。10人未満の企業と100人規模の企業では、集計や計算にかかる手間が全く異なるため、報酬額も変わってきます。
したがって、「相場は〇〇円」と一概に言うことは非常に難しいため、依頼を検討される際には、必ず複数の社労士事務所から具体的な業務内容に基づいた見積もりを取り、料金体系とサービス内容を比較検討することをおすすめします。
見積もりを取る際には、料金にどこまでの業務が含まれているのか(例:賃金集計は自社で行うのか、問合せ対応は含まれるのか等)を明確に確認することが、後々のトラブルを防ぐためにも不可欠です。
労働保険の年度更新は、毎年決められた期間内に行わなければならない重要な手続きです。
ここでは、年度更新の基本的な流れを解説し、各ステップでの注意点や、社労士に依頼する際のポイントについても触れていきます。
この一連の流れを把握することで、手続き全体のボリューム感や、どの部分に特に手間がかかるのか、社労士に依頼するメリットをより具体的にイメージしやすくなるでしょう。
STEP1:申告書類の確認(緑の封筒の中身)
年度更新の手続きは、まず、都道府県労働局から送られてくる関係書類を受け取ることから始まります。毎年、通常は5月末から6月初旬頃に、緑色(うぐいす色)の封筒で「労働保険 年度更新申告書」をはじめとする一式が事業所宛てに郵送されてきます。
この封筒が届いたら、まず中身を確認しましょう。
緑の封筒に含まれる主な書類は以下の通りです。
- 労働保険料申告書
- 一般拠出金申告書
- 申告書の記入例
- 申告書の記入手引き
- 労働保険料の計算支援ツールの案内
これらの書類が揃っていない場合や、封筒自体が届いていない場合は、所轄の労働局や労働基準監督署に連絡して取り寄せる必要があります。
社労士に依頼する場合は、この緑の封筒をそのまま社労士に渡すことになります。封筒には前年度の情報が印字されており、これをもとに今年度の申告書が作成されるためです。
STEP2:前年度の従業員の確定賃金総額の集計と確定保険料を計算する
労働保険の年度更新において、多くの方が最も時間と労力を要すると感じるのが、この「前年度の確定賃金総額の集計」と、それに基づく「確定保険料の計算」のステップです。
これは、前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)に支払った賃金の総額を正確に把握し、最終的な労働保険料を算出するための、非常に重要な基礎作業となります。
まず取り掛かるのは、前年度に支払った全ての労働者(アルバイトやパートタイム労働者も含む)の賃金データを集計することです。そのために、賃金台帳や毎月の給与明細といった資料を準備し、労災保険と雇用保険、それぞれの保険料算定の対象となる賃金を正確に区分けしていく必要があります。
基本給はもちろんのこと、残業代、通勤手当、賞与など、どの項目が対象となるのかを、一つひとつ確認しながら集計しなくてはなりません。
この集計作業を正確に行い、その結果を整理しまとめるために、「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」(いわゆる賃金集計表)を作成すると計算ミスを防ぐだけでなく、手続きをスムーズに進めることができます
特に、従業員の入退社が頻繁だったり、手当の種類が多かったりする企業では、この賃金集計のプロセスは非常に複雑になりがちです。
賃金表の詳しい使い方やダウンロード先は以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
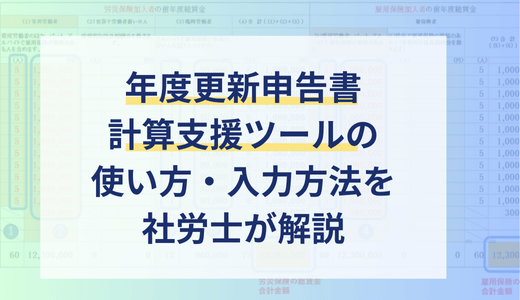 【社労士監修】労働保険 年度更新申告書計算支援ツール・入力ガイドの使い方を解説
【社労士監修】労働保険 年度更新申告書計算支援ツール・入力ガイドの使い方を解説
正確な確定賃金総額が集計できたら、次に確定保険料の計算へと進みます。
集計した確定賃金総額に、定められた労災保険料率と雇用保険料率をそれぞれ適用し(乗じて)、前年度に納めるべきであった確定保険料額を算出します。
STEP3:今年度の概算保険料を計算する
確定保険料の計算が終わったら、次に新年度(当年4月1日から翌年3月31日まで)分の概算保険料を計算します。これは、新年度に支払うであろう賃金の総額を見積もり、それに基づいて保険料を前払いするための計算です。
概算賃金総額は、原則として、前年度の確定賃金総額と同額として計算します。ただし、新年度に従業員数が大幅に増減する予定があるなど、賃金総額が大きく変動することが見込まれる場合は、その見込み額に基づいて申告することも可能です。
計算方法は確定保険料と同様で、算出した(または見込んだ)概算賃金総額に、新年度の労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、概算保険料額を算出します。
STEP4:申告書の作成
確定保険料と概算保険料の計算が終わったら、それらの情報を申告書に記入します。
労働局から送られてきた「労働保険 概算・確定保険料 申告書」に、計算結果や事業所の情報などを記入していきます。
申告書には、算出した確定保険料額や概算保険料額のほか、それぞれの計算の基礎となった賃金の内訳、労働保険番号、事業の名称・所在地、従業員数など、多くの項目を正確に記入する必要があります。
記入にあたっては、同封されている「書き方の手引き」をよく読み、間違いのないように慎重に作成を進めましょう。
特に数字の転記ミスや、記入漏れがないか、計算結果は合っているかなどを十分に確認することが大切です。また、申告書には通常、「算定基礎賃金等の報告」(賃金集計表)などの添付書類も必要となるため、それらも忘れずに準備します。
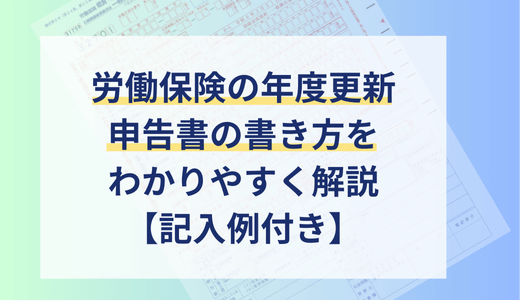 労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説
労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説
STEP5:申告・納付手続きの方法(電子申請・窓口・郵送)
申告書が完成したら、最終ステップとして申告と納付を行います。
作成した申告書は、期限である7月10日(令和7年度は7月10日(木))までに、管轄の労働局、労働基準監督署、または金融機関(銀行や郵便局など。ただし、納付のみ可能な場合が多い)に提出しなければなりません。
提出方法には、主に以下の3つがあります。
- 窓口提出: 管轄の労働局や労働基準監督署などの窓口に直接持参する方法
- 郵送: 管轄の労働局(または都道府県によっては労働基準監督署)へ郵送する方法
- 電子申請: 政府のオンラインサービス「e-Gov(イーガブ)」を利用してインターネット経由で申請する方法
近年、厚生労働省はこの電子申請を推奨しており、24時間いつでも申請可能(※令和7年度は6月1日(日)から入力可能ですが、受付開始は6月2日(月))、窓口に出向く時間や郵送コストが不要、提出履歴が残るなどのメリットがあります。
社労士に依頼する場合、この電子申請による代行が可能なケースが多くあります。
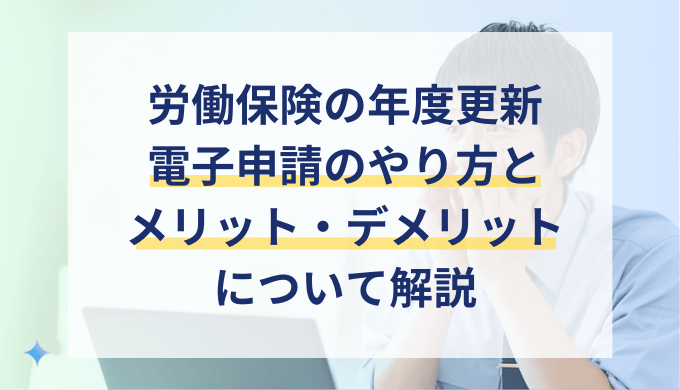 労働保険の年度更新の電子申請のやり方を社労士が解説!メリットや納付方法、注意点まで
労働保険の年度更新の電子申請のやり方を社労士が解説!メリットや納付方法、注意点まで
保険料の納付は、申告書の提出と同時に行うか(金融機関窓口など)、申告書に同封されている納付書を使って金融機関の窓口やATM、インターネットバンキング(ペイジーを利用した電子納付)などで別途行います。
また、事前に手続きを行えば、口座振替による納付も可能です。 なお、概算保険料額が一定額以上(40万円以上、労災保険または雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)の場合や、労働保険事務組合に事務委託している場合は、保険料を3回に分割して納付する「延納」の制度を利用することもできます。
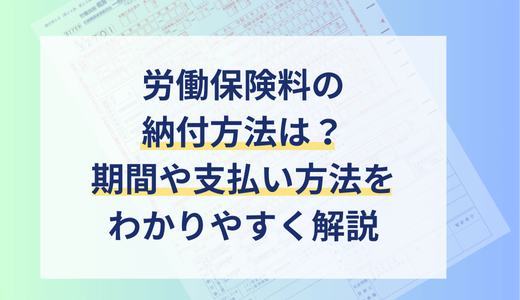 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険の年度更新は、労働者を雇用する全ての事業主にとって毎年必ず行わなければならない義務であり、期限内に正確な保険料を申告・納付することが求められる重要な手続きです。
年度更新の申告書作成などには、賃金総額の集計や保険料の計算など、専門知識が必要な複雑な作業が含まれています。そのため日々の経営やコア業務で多忙な中小企業の事業主や担当者にとっては、大きな負担となります。
社労士に年度更新を依頼することで、専門家による正確な計算と申告が可能となり、計算ミスによる追徴金などのリスクを回避できます。
また、煩雑な書類作成や提出といった手続きから解放され、貴重な時間を本来注力すべき業務に集中させることが可能になります。
さらに、毎年のように行われる可能性のある法改正にも適切に対応してもらえるため、コンプライアンス面での安心感も得られるでしょう。
特に労務管理に専門スタッフがいない中小企業や、本業に集中したい経営者の方には、社労士への依頼を検討する価値があるでしょう。
 社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説
社労士との顧問契約の必要性・顧問料の相場・サポート内容・メリットデメリットを徹底解説
社労士クラウドの年度更新スポット代行サービスについて
社労士クラウドの「年度更新スポット代行サービス」は、労働保険の年度更新に必要な手続きだけを、社会保険労務士に単発でご依頼いただけます。
例えば、「労働保険料の計算だけお願いしたい」「申告書の作成と提出(電子申請含む)だけ代行してほしい」「自社で作成した申告書の内容をチェックしてほしい」といった、お客様の状況に合わせた部分的なご依頼にも柔軟に対応いたします。
当サービスでは、労働保険の専門家である社労士が、最新の法令に基づいて正確に手続きを代行します。
お客様には賃金台帳などの必要な情報をご提供いただくだけで、面倒な計算や書類作成、提出といった手続きから解放されます。これにより、お客様は貴重な時間をコア業務に集中させることが可能となり、経営の効率化にも繋がります。
必要な業務のみをスポットでご依頼いただけるため、顧問契約に比べて費用を抑えることができるのも大きなメリットです。また、オンラインでのやり取りを基本としており、全国どの地域からでも簡単にご依頼いただけます。専門家による正確な手続きで、ミスや遅延のリスクを回避できるため、安心して本来の事業活動に集中していただけます。
自社で対応するには時間や人手が足りない、計算や手続きに不安があるという企業様にとって、当社のスポット代行サービスは年度更新を確実に乗り切るための有効な選択肢です。労働保険の年度更新手続きでお困りの際は、ぜひ一度、「社労士クラウド」のスポット代行サービスをご検討ください。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|