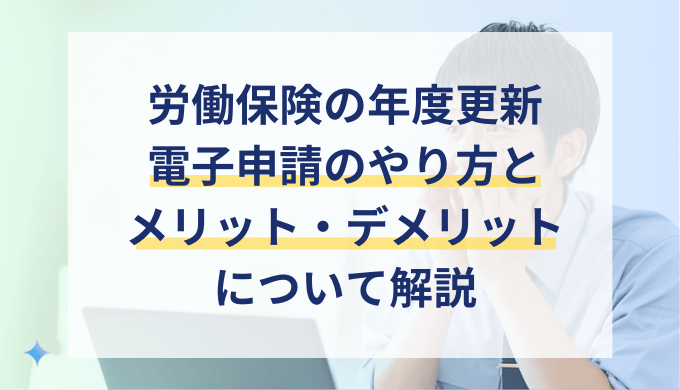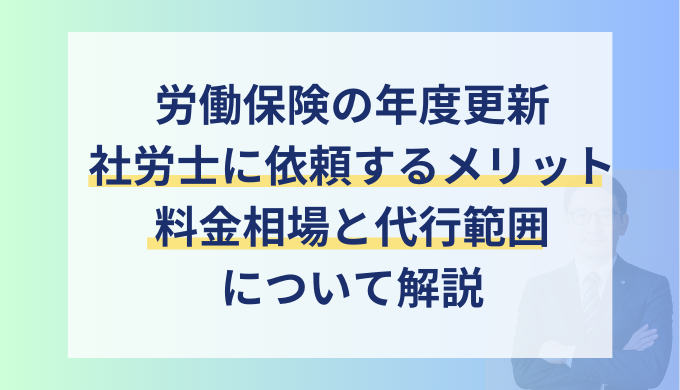労働保険の年度更新とは、事業主が年に一度、労働保険料の精算を行う手続きのことです。毎年6月1日〜7月10日の期間内に行う必要があります。
近年では行政手続きの電子化が進み、多くの企業が紙の申請から電子申請に切り替えています。2020年4月以降、一部法人には電子申請が義務化され、今後さらに電子化の流れが加速することが予想されます。
しかし、電子申請には窓口での待ち時間や訪問の手間を省けるなどメリットが多い一方で、事前準備や操作方法に戸惑う事業主や担当者も少なくありません。
本記事では、労働保険の年度更新を電子申請する具体的なやり方や事前準備、注意点をわかりやすく解説します。
初めて電子申請を行う方でも安心して進められるよう、よくあるトラブルへの対処法も紹介しています。正確かつ効率的に年度更新を行うために、ぜひ本記事を参考にしてください。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
労働保険の年度更新や算定基礎届など、労働保険・社会保険の手続きは、1年のうちで決まったタイミングで発生するものと、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きが必要なもの、また生年月日に応じて必要な必須の手続きがあります。
⇒社会保険・労働保険手続きの年間スケジュール(PDF)を無料ダウンロード
労働保険の年度更新の電子申請とは、従業員を雇用するすべての事業主が年に一度必ず行う必要がある年度更新手続きを、紙ではなくオンラインで行うシステムです。e-Govなどの電子申請サービスを利用して、従来の郵送や窓口持参に代わり、インターネットで簡単に手続きを完結できます。
これまでは、中小企業を中心に紙の申請が一般的でしたが、行政のデジタル化推進によって電子申請は徐々に一般的になりつつあります。大企業など一定の条件を満たす事業所に対して電子申請が義務化されました。今後も電子申請の対象範囲は拡大する見込みであり、早めに電子申請に慣れておくことは、業務効率化の観点からも非常に重要です。
「電子申請は難しそう」「パソコン操作に自信がない」と感じている方もいるかもしれませんが、一度使い方を覚えてしまえば作業効率の向上やミス防止につながります。また、一度電子申請を行うと、次年度から過去データを活用でき、より簡単に年度更新を進められるというメリットもあります。
労働保険の年度更新とは?
労働保険の年度更新とは、事業主が年に一度、労働保険料の精算を行う手続きのことです。毎年6月1日〜7月10日の期間内に行う必要があります。
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」をまとめた総称で、労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として加入が義務付けられています。
【関連記事】
> 労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
> 労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく解説
年度更新では、前年度(4月1日〜3月31日)に実際に支払った賃金総額をもとに「確定保険料」を計算します。また、新年度(4月1日〜翌年3月31日)に支払う予定の賃金総額から「概算保険料」を算出し、それらをまとめて申告・納付する仕組みです。
万が一、年度更新を期限内に行わない場合、政府(労働局)によって保険料額が一方的に決定されるほか、追加で「追徴金(確定保険料の10%)」が課される可能性があります。また、労災事故が発生した際や従業員が雇用保険を受給する際に支障が出る恐れもあるため注意が必要です。
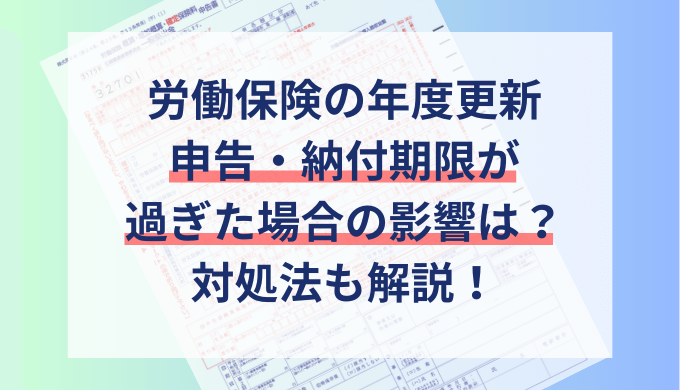 労働保険の年度更新の期限を過ぎたら? 遅れた場合の罰則・リスクと対処法を解説
労働保険の年度更新の期限を過ぎたら? 遅れた場合の罰則・リスクと対処法を解説
電子申請の義務化について
労働保険の年度更新は、従来、紙の申告書で行うのが一般的でしたが、2020年4月からは、特定の法人について電子申請が義務化されました。これは、行政手続きのデジタル化を推進し、事業主の負担軽減と行政運営の効率化を目的としたものです。
電子申請が義務化されたのは、以下のいずれかに該当する法人です。
- 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
- 相互会社(保険業法に基づく)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律に基づく)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律に基づく)
これらの法人は、e-Gov(電子政府の総合窓口)というウェブサイトを通じて、電子申請を行う必要があります。もし、これらの法人が電子申請を行わずに、紙の申告書を提出しても、原則として受理されません。
電子申請の義務化は、2020年4月以降に開始する事業年度から適用されています。
自社が電子申請義務化の対象となるかどうか不明な場合は、厚生労働省のホームページやe-Govのウェブサイトで確認するか、最寄りの労働局または労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
なお、上記の義務化対象に該当しない中小企業などの事業所であっても、電子申請を利用することは可能です。むしろ、電子申請には多くのメリットがあるため、積極的に活用することをおすすめします。
労働保険の年度更新を電子申請をスムーズに行うためには、事前に必要な準備を整えておくことが重要です。ここでは、電子証明書の取得方法やe-Govアカウントの登録手順、パソコンの環境設定など、電子申請を始める前に必要な準備について詳しく解説します。
特に初めて電子申請を利用する方は、申請期間(6月1日〜7月10日)に間に合うよう、申請期限の1ヶ月以上前から準備を始めることをおすすめします。これらの準備は最初は少し手間がかかりますが、一度完了すれば次年度以降も使い回すことができます。それでは、具体的な準備の内容と手順を見ていきましょう。
電子証明書の取得
電子申請を行うためには、本人確認を行うための電子証明書が必要です。電子証明書とは、インターネット上での本人確認や文書の改ざん防止のために使用される電子的な身分証明書のようなものです。紙の申請書における印鑑証明書に相当するものと考えるとわかりやすいでしょう。
電子証明書の取得方法には主に以下の2つの方法があります。
- マイナバーカードの利用
- GビズIDプライムの取得(電子証明書不要)
マイナンバーカードには、電子証明書が標準で搭載されています。この電子証明書を利用することで、個人事業主や企業の代表者が電子申請を行うことができます。マイナンバーカードを利用する場合のメリットは、追加費用なしで電子証明書を利用できる点です。
2021年3月からは、GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーを利用することで、電子証明書なしでも労働保険の年度更新手続きを電子申請できるようになりました。GビズIDとは、1つのアカウントで複数の行政サービスにログインできる認証システムです。(GビズIDの公式ページ)
以前は、商業登記に基づく電子証明書(有料)も利用できましたが、GビズIDの普及により、利用するケースは少なくなっています。
また、電子証明書の取得には時間がかかる場合があるため、年度更新の時期(6月1日~7月10日)が近づいてから慌てて準備するのではなく、余裕を持って準備を始めるようにしましょう。
特に、GビズIDプライムを取得する場合は、2週間程度かかりますので、早めに手続きを済ませてください。
e-Govアカウントの登録
e-Govは、政府が提供する行政手続きのオンラインサービスです。労働保険の電子申請をするためには、e-Govのアカウントを取得する必要があります。ただし、GビズIDやMicrosoftアカウントを持っている場合は、それらを利用してログインすることも可能です。ここでは、e-Govアカウントの登録手順と注意点について説明します。
e-Govアカウント登録手順
- e-Govの公式サイトにアクセス
- 「新規ユーザー登録」ページで基本情報を入力
- メールアドレス認証を行い、ログイン情報を設定
- 必要に応じて、電子証明書を登録
- 登録には、会社名・代表者名・メールアドレスなどの情報が必要です。
- 電子証明書を使用する場合、事前に取得・設定しておくことが重要です。
- e-Govアカウントは個人に紐づくものなので、同じアカウントを複数人で共有しないようにしましょう。
- GビズIDプライムまたはメンバーを持っている場合は、e-Govアカウントを新たに作らなくても、GビズIDでログイン可能です。
e-Govアカウントの登録は比較的簡単に完了しますが、実際の電子申請にはさらに環境設定などが必要です。
パソコンの環境設定
労働保険の電子申請を行うためには、パソコンの環境設定も重要です。特に初めて電子申請を行う場合は、申請前に以下の環境設定を確認・実施しておきましょう。
まずはお使いのOSとブラウザが対応しているか確認します。Windows 10/11のMicrosoft Edge、Google ChromeやMozilla Firefoxが推奨されています。
ブラウザの設定では、ポップアップブロックの解除が必要です。ブラウザ右上のメニューから設定画面を開き、「e-gov.go.jp」をポップアップ許可サイトに追加します。併せて「信頼済みサイト」への登録も行っておくとスムーズです。
次に、e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。e-Govポータルサイトの「電子申請」→「ご利用準備」からダウンロードできます。管理者権限でインストールを実行し、完了したらパソコンを再起動させましょう。
以前はJavaの設定も必要でしたが、現在の電子申請システムではJava環境は不要になりました。専用アプリケーションを使用するため、この設定は省略できます。
より詳しい設定方法については、厚生労働省が提供する「電子申請事前準備ガイドブック」を参考にするとよいでしょう。設定完了後、e-Govにログインして正常に操作できるか確認しておくことをおすすめします。
労働保険の電子申請説明動画パート1(初期設定編)
事前準備チェックリスト
労働保険の年度更新を電子申請するための準備を漏れなく行うために、以下のチェックリストをご活用ください。申請期限(7月10日)に余裕をもって準備を進めるためのスケジュールも合わせて記載しています。
| 項目 | 内容 | 期限 |
| 電子証明書の取得 | マイナンバーカード(個人事業主)またはGビズIDプライム(法人)を取得する。 | 5月末まで |
| e-Govアカウントの登録 | e-Govのウェブサイトでアカウントを登録する。 | 5月末まで |
| パソコンの環境設定 | 推奨ブラウザ(Edge, Chrome, Firefox, Safari)の最新版をインストールする。Java(JRE)をインストールし、設定を行う。ポップアップブロックを解除する。 | 5月末まで |
| 賃金集計表の作成 | 前年度(4月1日~3月31日)の賃金総額を集計する。 | 5月末~6月初旬 |
| 労働保険番号・アクセスコードの確認 | 労働局から送付される年度更新申告書で確認する。 | 6月上旬 |
この事前準備チェックリストを活用して、計画的に電子申請の準備を進めることで、スムーズな労働保険の年度更新手続きが可能になります。特に初めて電子申請を行う場合は、予想以上に時間がかかることもありますので、十分な余裕をもって準備を進めてください。
労働保険の年度更新を電子申請で行う具体的な手順を紹介します。事前準備が整っていることを前提に、ここからは実際の申請作業の流れを順番に解説していきます。
初めて電子申請を行う方でも分かりやすいよう、各ステップを詳しく説明していますので、画面を見ながら一つずつ進めていきましょう。
労働保険の年度更新を含め、電子申請に不安がある場合は、社労士に申請代行依頼など、相談することもおすすめですよ。
1. 賃金集計表の作成
労働保険の年度更新申告を行う前に、まず賃金集計表を作成する必要があります。賃金集計表とは、前年度(4月1日から3月31日まで)に労働者に支払った賃金の総額を集計した表です。この集計した賃金額を基に労働保険料が計算されます。
賃金集計表の作成方法には、「労働保険 年度更新申告書計算支援ツール」などを利用して作成すると便利です。このツールは、Excel形式で提供されており、必要事項を入力するだけで、自動的に労働保険料を計算してくれます。
賃金集計表を作成する際の主なポイントは以下の通りです。
- 労災保険の対象となる賃金総額と雇用保険の対象となる賃金総額を区分して集計する
- 役員報酬は労働保険料の算定対象外(労働者として扱われない)
- 通勤手当(非課税限度内)や出張旅費など、賃金に含まれない項目を除外する
- 賞与も含めた年間の総支給額を集計する
- 65歳以上の労働者の賃金も含める(2020年4月以降、雇用保険料の徴収対象)
集計作業が完了したら、算出された賃金総額を元に確定保険料と概算保険料を計算します。この数値は後の電子申請の入力時に必要となります。集計表自体は電子申請時に添付する必要はありませんが、申告内容の裏付け資料として社内で保管しておくことをお勧めします。
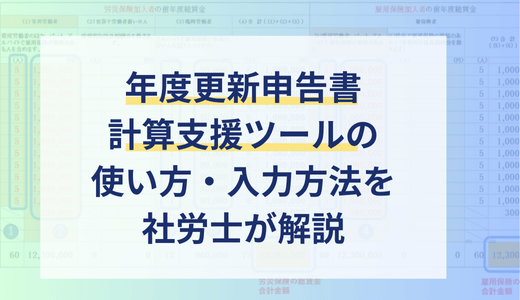 【社労士監修】労働保険 年度更新申告書計算支援ツール・入力ガイドの使い方を解説
【社労士監修】労働保険 年度更新申告書計算支援ツール・入力ガイドの使い方を解説
2. e-Govにログインして、申請書選択(労働保険年度更新申告)
賃金集計表が完成したら、次にe-Govにログインして電子申請を開始します。以下の手順で進めてください。
- e-Govポータルサイトへのアクセス
- 電子申請のページに移動( トップページの「電子申請」ボタンをクリック)
- 「ログイン」ボタンをクリックし、e-Gov電子申請アプリケーションを起動
- ログイン後の画面で、「手続検索」クリックし、検索窓に「労働保険年度更新申告」と入力して検索する
- 検索結果から適切な年度更新申告書の選択する(通常は「継続事業 年度更新申告書」)
自社が一元適用事業(多くの一般企業が該当)であれば「労働保険年度更新申告書」を選択します。二元適用事業(建設業や林業など)の場合は、労災保険分と雇用保険分を別々に申告する必要があるため注意してください。 - 適切な年度更新申告書を選択したら、「申請書入力へ」進む
手続き選択時の注意点として、年度更新申告書は毎年更新されるため、必ず当年度の申告書を選択するようにしてください。
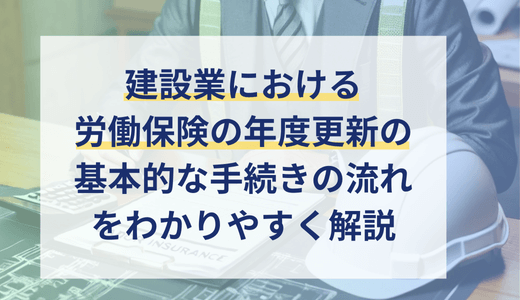 建設業の労働保険の年度更新(一括有期事業)の申告・納付手続きをわかりやすく解説
建設業の労働保険の年度更新(一括有期事業)の申告・納付手続きをわかりやすく解説
3. 労働保険番号・アクセスコード等の入力
申請書選択後、最初に入力する重要な情報が「労働保険番号」と「アクセスコード」です。これらは事業所を識別するための基本情報となります。
■労働保険番号:
労働保険関係成立届を提出した際に、労働基準監督署から交付される14桁の番号です。毎年送付されてくる年度更新申告書(紙)の左上に記載されています。
■アクセスコード:
年度更新申告書(紙)の右上に記載されている8桁の番号です。
労働保険番号とアクセスコードが正しく入力されると、申告書の入力画面に進みます。これらの番号がわからない場合や、入力してもエラーが出る場合は、管轄の労働局または労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
また、電子申請を続けるには、次に基本情報として「申請者情報」と「連絡先情報」の入力が必要になります。画面の指示に従って、会社名や住所、担当者名、電話番号などを入力してください。一度入力した情報は保存しておくことができ、次回以降の申請時に再利用することができます。
4. 賃金等の入力(雇用保険分、労災保険分)
労働保険番号とアクセスコードの入力が完了すると、労働保険料の計算に必要な賃金情報などを入力する画面に進みます。この画面では、先ほど作成した賃金集計表のデータを基に、確定保険料と概算保険料の計算に必要な情報を入力します。
■事業所情報:
事業所の名称、所在地などの情報が自動的に表示されます。(一部、手入力が必要な項目もあります。)
■保険料算定基礎賃金:
雇用保険分と労災保険分、それぞれに分けて賃金総額を入力します。二元適用事業(建設業など)の場合は、労災保険分と雇用保険分で申告書が異なるため、注意が必要です。
■保険料額:
賃金総額を入力すると、保険料率に基づいて自動的に計算されます。
■一般拠出金:
労働保険料と併せて徴収される一般拠出金についても、自動的に計算されます。
各項目の入力欄の横にある「?」マークをクリックすると、その項目の詳しい説明が表示されますので、参考にしながら入力してください。
また、e-Govには、入力内容に誤りがないか自動的にチェックする機能があります。もし、入力ミスや漏れがあると、エラーメッセージが表示されますので、メッセージに従って修正してください。
5. 提出先を選択して電子証明書の添付(またはGビズID認証)
賃金情報などの入力が終わったら、申請書の提出先を選択し、電子署名を行います。この手順は、紙の申請書における提出先の選択と、押印に相当する重要なステップです。
ステップとしては、
- 提出先を選択する
- 電子署名をする
提出先は、事業所の所在地を管轄する労働局を選択するのが基本です。複数の事業所がある場合でも、本社または主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出します。ただし、二元適用事業の場合は、労災保険と雇用保険で提出先が異なる場合があるので注意が必要です。
提出先を選択した後、「内容を確認」ボタンをクリックし、申請内容に問題がなければ「署名対象の指定」画面に進みます。ここで電子署名を行います。
GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーでログインしている場合は、電子証明書を使用した電子署名は不要です。GビズID自体が本人確認の役割を果たしているため、署名のステップはスキップされます。この場合、提出先選択後に直接、申請内容の最終確認画面に進みます。
6. 内容を確認して申請データの送信
電子署名を完了後(またはGビズIDでログインしている場合は提出先選択後)、申請内容の最終確認画面が表示されます。この段階で申請内容を確認し、問題がなければ申請データを送信します。
送信が完了すると、受付番号と受付日時が表示されます。この番号は、後で申請状況を確認する際に必要になりますので、必ず控えておきましょう。
7. 保険料を納付する
申請データの送信が完了したら、次は労働保険料の納付手続きを行います。電子申請を行っても、保険料の納付は自動的に行われるわけではないため、必ず、期限内に別途納付手続きを行う必要があります。
労働保険料はインターネットバンキングまたはATMで納付しましょう。
労働保険料の納付期限は、原則として毎年7月10日です。ただし、7月10日が土日祝日の場合は、その翌開庁日が期限となります。期限を過ぎると、延滞金が発生する場合がありますので、注意が必要です。
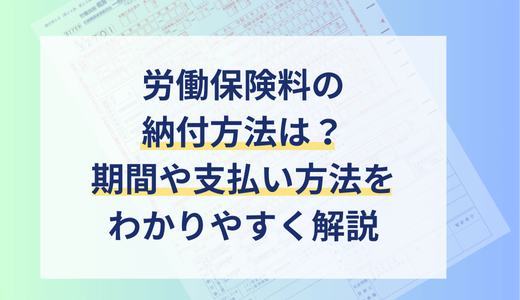 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
電子公文書(申請書控え)の取得・保管方法
労働保険の年度更新を電子申請で行うと、紙の申告書控えの代わりに、「電子公文書」と呼ばれるPDF形式の控えが発行されます。この電子公文書は、申請内容を証明する重要な書類ですので、必ず取得し、適切に保管してください。
電子公文書は、e-Govのマイページからダウンロードできます。
- e-Govのマイページにログインします。
- 「公文書」メニューをクリックします。
- 取得したい年度更新申告書の「到達番号」をクリックします。
- 「公文書ダウンロード」ボタンをクリックし、PDFファイルを保存します。
電子公文書は、発行から90日間のみダウンロードが可能です。この期間を過ぎてしまうと、e-Govから取得できなくなってしまいますので、必ず期限内にダウンロードするようにしてください。
ダウンロードしたPDFファイルは、パソコン内の安全な場所、例えばパスワード付きのフォルダなどに保存することをおすすめします。また、万が一の事態に備えて、必要に応じて印刷し、紙の控えとして保管しておくことも可能です。
顧問の社会保険労務士がいる場合は、電子公文書を共有しておくことで、その後の手続きや相談がスムーズに進むことがあります。
労働保険の年度更新を電子申請することで、手続きを効率化できます。しかし、電子申請にはメリットだけでなくデメリットもあるため、それらをしっかり把握しておくことが重要です。
ここでは、電子申請の具体的なメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
電子申請のメリット
電子申請の主なメリットを以下にまとめました。
電子申請には郵送費や印刷費が不要なため、コストを抑えられます。また、役所に出向く交通費や業務時間も節約できます。中小企業でも追加コストなしで導入できるため、費用面でのメリットが大きいです。
電子申請では入力漏れや計算間違いを自動でチェックする機能があります。これにより人的なミスが減り、修正手続きに伴う余計な手間やトラブルを未然に防ぐことができます。
電子申請は24時間365日申請可能です。申告期限ギリギリでも、窓口の営業時間を気にせずに申請が行えます。業務の空いた時間に作業が可能なため、計画的な手続きを進めやすくなります。
一度電子申請を行うと、翌年度以降は過去のデータをそのまま利用できます。同じ内容を再入力する必要がなくなり、年度更新作業の効率化が実現します。特に複数の事業所がある企業では、大きな作業時間の削減につながります。
その他にも、申請後の処理状況をウェブ上で随時確認できたり、公文書(申請書控え)を電子データで管理できたりする利便性もあります。
さらに、政府が行政手続きの電子化を推進している背景から、将来的には電子申請がより一般的になることが予想されます。早めに対応しておけば、今後の手続きもより円滑に進められるでしょう。
電子申請のデメリット
電子申請はメリットが多い一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。初めて電子申請を行う際には特に注意が必要なため、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。
電子申請を利用するには、e-Govアカウント登録や電子証明書(GビズIDプライムなど)の取得、ブラウザ設定やソフトのインストールなどの準備が必要です。特にGビズIDプライムを取得するには、申請書類の郵送などで2〜3週間程度かかるため、年度更新の期限(7月10日)に余裕を持って準備しましょう。
子申請には、基本的なパソコン操作スキルが求められます。電子申請システムの操作や、電子証明書の取得・設定など、ある程度のITリテラシーが必要です。パソコン操作が苦手な場合、最初は操作に戸惑うかもしれません。ただし、厚生労働省などが公開している操作マニュアルや説明動画を活用すれば、初心者でもスムーズに進められるようになっています。
電子申請では、システム障害やメンテナンスによる一時的なサービス停止などのリスクがあります。特に申告期限直前はアクセスが集中してシステムが重くなったり、自社のネットワーク環境のトラブルで申請が中断したりする可能性も考えられます。こうしたリスクを避けるため、期限には余裕をもって早めに申請を完了しておくことが重要です。トラブルが起きた場合はe-Gov利用者サポートデスクに問い合わせできますが、繁忙期は対応が遅れる場合もあります。
これらのデメリットは、初回利用時に特に感じられることが多いですが、一度操作に慣れてしまえば次回以降はスムーズに電子申請を行えるでしょう。長期的にはメリットが大きいため、ぜひ導入を検討してください。
紙申請との比較表
労働保険の年度更新における電子申請と紙申請の違いを、以下の表でまとめています。
| 項目 | 電子申請 | 紙申請 |
| 申請方法 | オンライン | 郵送または窓口提出 |
| 手続き時間 | 短縮(即時送信可能) | 書類作成・郵送・処理待ちが必要 |
| コスト | 低い(郵送費・印刷費不要) | 高い(郵送費・印刷費が発生) |
| 入力ミスのリスク | 低い(システムがエラーチェック) | 高い(記入ミスによる修正が発生) |
| 申請可能時間 | 24時間対応 | 窓口受付時間内のみ |
| 控えの管理 | 電子データで保存・管理が容易 | 紙の保管が必要 |
| システム障害の影響 | あり(障害時は申請不可) | なし(手書きで提出可能) |
この比較表からわかるように、電子申請は特に時間的・空間的な制約が少なく、ミス防止や業務効率化の面で優れています。一方、紙申請はITスキルを必要とせず、特別な準備なしに始められるという利点があります。
年度更新の申請方法を選ぶ際には、自社の業務環境や担当者のスキル、申請頻度などを考慮して判断することが大切です。ただし、先述のように一部の法人には電子申請が義務化されていることや、今後電子化がさらに進む可能性があることを考えると、将来を見据えて電子申請に移行する準備を進めることをお勧めします。
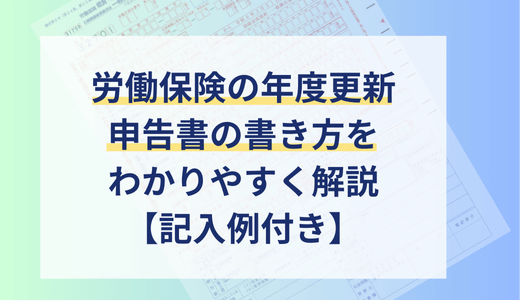 労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説
労働保険年度更新申告書の書き方を記入例付きでわかりやすく解説
労働保険の年度更新を電子申請で行うには、いくつかの重要な注意点があります。電子申請はメリットが多い反面、初めて利用する場合や準備が不十分な場合に思わぬトラブルが発生することがあります。
ここでは、電子申請を円滑に進めるための注意点と、よくあるトラブルの対処法をまとめました。事前に確認しておくことで、申請時の不安を軽減し、スムーズな手続きにつなげることができます。
特に電子証明書の有効期限や事業の種類による申告方法の違い、修正申告の方法などは重要なポイントですので、しっかりと理解しておきましょう。
電子証明書の有効期限を確認しておく
電子証明書は一定の有効期限があり、期限切れの証明書では電子申請ができません。申請直前になって証明書の期限切れに気づき、慌てて更新手続きをするというトラブルを避けるため、事前に有効期限を確認しておくことが重要です。
特に、ICカード形式の電子証明書(マイナンバーカードなど)を利用する場合は、有効期限に注意が必要です。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、原則として発行日から5回目の誕生日までです。ただし、マイナンバーカード自体の有効期限(10回目の誕生日、未成年者は5回目の誕生日)とは異なる場合があるため、注意が必要です。
有効期限が近づいてきたら、早めに更新手続きを行いましょう。マイナンバーカードの電子証明書の更新は、市区町村の窓口で行うことができます。
なお、GビズIDプライムを利用する場合は、電子証明書は不要です。
一元・二元適用事業の事業区分を間違えない
労働保険の適用事業には「一元適用事業」と「二元適用事業」の2種類があり、事業の種類によって申告方法が異なります。
| 一元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険関係が一つにまとめられている事業所です。一般的な事業所は、こちらに該当します。 |
| 二元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険関係が別々に成立している事業所です。建設業や農林水産業の一部などが該当します。 |
一元適用事業の場合は、年度更新申告書を1枚提出すれば良いのですが、二元適用事業の場合は、労災保険分と雇用保険分、それぞれ別の申告書を提出する必要があります。
自社がどちらの適用事業に該当するかは、労働保険番号の最初の2桁で確認できます。労働保険番号が「01」「02」「04」「05」「06」で始まる場合は一元適用事業、「31」「32」「33」「34」「35」で始まる場合は二元適用事業です。
二元適用事業の場合は、申告漏れがないように、特に注意が必要です。
納付後の修正申告は紙申請
電子申請で年度更新申告書を提出し、保険料を納付した後に、申告内容に誤りがあることに気づいた場合、原則として、e-Gov上で修正することはできません。これは、保険料の計算が確定し、納付が完了しているため、システム上での修正ができないためです。
この場合は、紙の「労働保険訂正再申告書」を作成し(厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます)、管轄の労働局または労働基準監督署に提出する必要があります。
ただし、保険料を納付する前であれば、労働局に連絡することで、電子申請データを取り消し、再申請できる場合があります。
いずれにしても、申告内容に誤りがないか、提出前に十分に確認することが重要です。
以下に該当する場合は、修正申告が必要になります。
- 賃金総額の申告に誤りがあった場合
- 労働者数や被保険者数の申告に誤りがあった場合
- 保険料の算定に誤りがあった場合
- 対象となる労働者の範囲を誤って申告した場合
修正申告の必要性をできるだけ減らすためにも、当初の申告時には賃金集計や入力内容を十分に確認することが大切です。計算や入力に不安がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
年度更新の申告期限を過ぎたら罰則やペナルティのリスクがある
労働保険の年度更新の申告・納付期限は、毎年7月10日です(土日祝日の場合は翌開庁日)。この期限を過ぎてしまうと、延滞金が課される場合があります。さらに、政府が保険料額を決定し、追徴金(確定保険料の10%)が課される可能性もあります。
また、年度更新の手続きが遅れると、労働保険給付(労災保険や雇用保険の給付)の受給にも影響が出る可能性があります。
必ず期限内に手続きを完了させるようにしましょう。特に、電子申請は、締め切り直前になると、システムが混み合ってつながりにくくなることがあります。余裕を持って、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
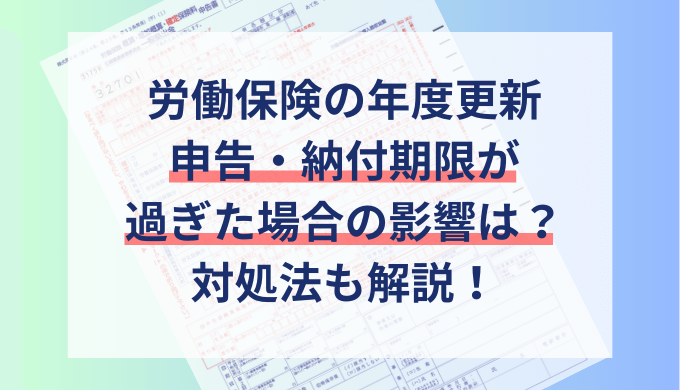 労働保険の年度更新の期限を過ぎたら? 遅れた場合の罰則・リスクと対処法を解説
労働保険の年度更新の期限を過ぎたら? 遅れた場合の罰則・リスクと対処法を解説
よくある電子申請トラブルと解決策
電子申請は便利ですが、システム操作時にトラブルが発生することもあります。ここではよくあるトラブルとその対処法をまとめました。
| トラブル内容 | 原因と対処法 |
| ログインができない場合 | ・e-Govがメンテナンス中の場合があります。公式サイトのメンテナンス情報を確認しましょう。 ・入力したIDやパスワードが間違っていないか、再度確認しましょう。 ・GビズIDを利用している場合は、「プライム」か「メンバー」かIDの種類も再確認しましょう。 |
| アクセスコードが見つからない場合 | アクセスコードを紛失した場合は、管轄の労働局に連絡し、再発行を依頼しましょう。 |
| 電子証明書が有効期限切れの場合 | ・マイナンバーカードの電子証明書を使っている場合、市区町村の窓口で更新手続きを行います。 ・商業登記に基づく電子証明書の場合は、法務局で更新が必要です。 |
| 納付したのに督促状が届いた場合 | ・e-Govの申請履歴画面から申請状況を確認しましょう。 ・電子納付をした場合は、金融機関の取引履歴を確認してください。 ・解決できない場合は、速やかに管轄の労働局へ問い合わせましょう。 |
上記以外にも予期しないトラブルが起こることがあります。自分で解決が難しい場合は無理せず、専門家(社労士)や管轄の労働局に相談することをおすすめします。
労働保険の年度更新を電子申請で行う際に、疑問や不安を感じることもあるかと思います。ここでは、電子申請に関するよくある質問とその回答をまとめました。
電子申請したのに後日督促状が届いたのですが?
電子申請を行ったにもかかわらず、後日督促状が届いた場合は、以下の手順で状況を確認・対応しましょう。
①申請状況をe-Govで確認
②納付状況の確認(電子納付の場合)
③口座振替の場合の確認
④管轄の労働局に問い合わせる
各手順を具体的に解説します。
①申請状況をe-Govで確認
e-Govのマイページにログインし、「申請案件一覧」から年度更新申告の状況を確認します。「審査終了」と表示されていれば、申請は正常に受理されています。もし「未送信」や「取下げ」となっている場合は、申請が正常に完了していないため、再申請が必要です。
②納付状況の確認(電子納付の場合)
電子納付をした場合、銀行の取引履歴やクレジットカードの利用明細を確認し、実際に納付が完了していることを確認してください。また、e-Govのマイページからも納付状況が確認できます。
③口座振替の場合の確認
口座振替を利用している場合は、指定口座の残高や取引履歴を確認し、引き落としが完了しているか確認してください。
④管轄の労働局に問い合わせる
上記を確認しても解決しない場合、労働局側の事務処理ミスやシステムトラブルの可能性があります。e-Govで取得できる申請の受付番号を控えて、管轄の労働局に問い合わせて状況を伝えましょう。
多くの場合、労働局に連絡することで問題は解決します。焦らず、落ち着いて対応しましょう。
労働保険の年度更新の電子申請に行政手数料はかかりますか?
労働保険の年度更新を電子申請で行う際、e-Gov自体の利用には行政手数料はかかりません。ただし、以下の場合には別途費用が発生する可能性があります。
- 電子証明書の取得費用
- 電子納付時の手数料
電子納付(ペイジー、ネットバンキング、クレジットカードなど)を利用する際、金融機関や決済サービスによって手数料が発生する場合があります。
労働保険の年度更新の電子申請の振込者氏名は誰の氏名ですか?
労働保険の年度更新の電子申請で保険料を納付する際、振込者氏名(名義人)は、原則として事業主の氏名を入力します。
- 法人の場合: 法人名(株式会社○○など)と代表者名を続けて入力します。
- 個人事業主の場合: 事業主の氏名を入力します。
社会保険労務士が代理で電子申請を行う場合でも、振込者氏名は、必ず事業主の氏名を入力してください。社労士の氏名を入力してしまうと、労働局側で入金確認が正しく行われず、未納扱いになってしまう可能性があります。
なお、e-Govの申請書入力画面では、「振込者氏名」の入力欄がありますが、これは、電子納付を行う場合にのみ使用する項目です。口座振替や納付書による納付を行う場合は、この欄に入力しても、実際の振込者氏名には反映されませんので、注意してください。
労働保険の年度更新は、事業主が毎年必ず行わなければならない手続きです。この記事では、紙申請に代わる電子申請の方法や手順、メリット・デメリット、注意点などを詳しく解説してきました。
労働保険の年度更新は、電子申請を活用することで業務の効率化やミス防止、コスト削減など多くのメリットを得られます。ただし、電子申請を初めて利用する場合は事前準備やトラブル対策が重要です。
事前に電子証明書の取得やe-Govアカウントの登録、パソコンの設定を済ませ、トラブル時の対応方法も把握しておくことで、安心して電子申請を進められます。
今後さらに電子申請の利用が拡大すると予想されます。早めの導入と準備で、年度更新手続きを効率的かつスムーズに行いましょう。
スポット申請代行サービスの社労士クラウドとは?
労働保険の年度更新は専門的で複雑な作業が多く、「自社で対応できるか不安」「計算ミスや申告漏れが心配」と感じる事業主様も多いでしょう。
「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスは、労働保険の年度更新に必要な手続きだけを、専門家である社労士に依頼できるサービスです。
例えば、「労働保険料の計算だけお願いしたい」「申告書の作成と提出だけ代行してほしい」「申告書を確認してほしい」といった、部分的な依頼も可能です。
「社労士クラウド」は、労働保険の専門家である社会保険労務士が、最新の法令に基づき正確に手続きを代行します。面倒な手続きを私たちにお任せいただくことで、お客様は貴重な時間を有効活用できます。必要な業務のみをスポットでご依頼いただけるため、費用も抑えられます。全国どこからでもご依頼可能です。
スポットで依頼することで、自社で対応するよりも、確実かつ効率的に年度更新の手続きを進められる場合があります。 労働保険料の納付手続きでお困りの際は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|