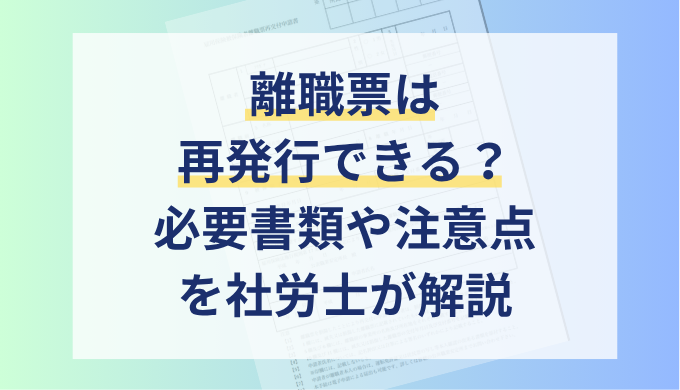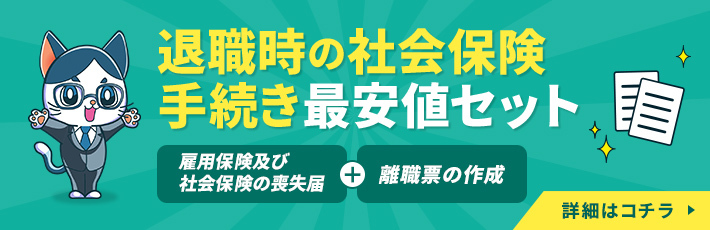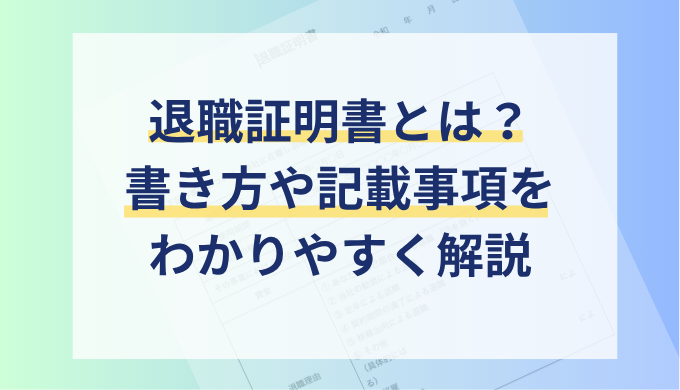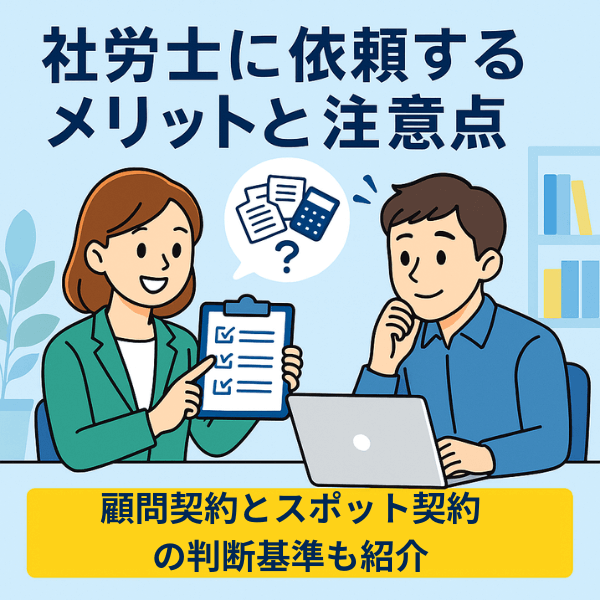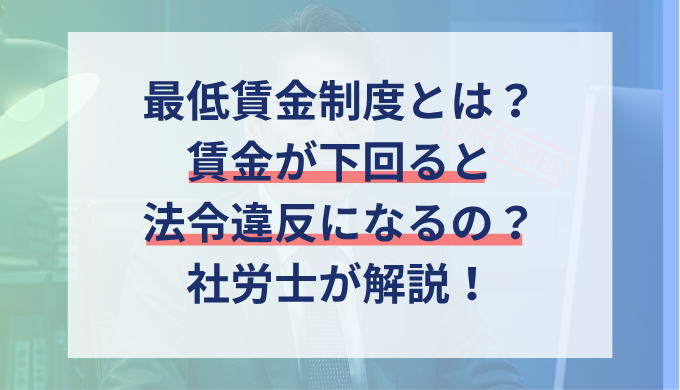離職票は、失業保険の受給に必要不可欠な公的書類です。再発行を退職者から依頼された場合、企業が適切に対応しなければ、退職者の生活設計に大きな支障をきたす可能性があります。
「再発行はそもそも可能なのか?」「会社に対応義務はあるのか?」「手続きの流れは?」「対応しなかった場合、罰則はあるのか?」
離職票の再発行対応は、判断に迷うことが多い業務のひとつです。
結論として、離職票の再発行はハローワークで申請が可能です。しかも申請方法は、会社経由・退職者本人による申請・電子申請など複数あり、それぞれの特徴を理解しておくことでスムーズに対応できます。
本記事では、離職票を再発行する際の手続きの流れ、必要書類、注意点までを網羅的に解説します。会社経由で申請する方法と、退職者本人がハローワークで手続きする場合の違い、それぞれのメリット・デメリットも丁寧にご紹介します。
この記事を最後まで読むことで、離職票の再発行に関するあらゆる疑問を解消し、迅速かつ正確に対応できるようになります。
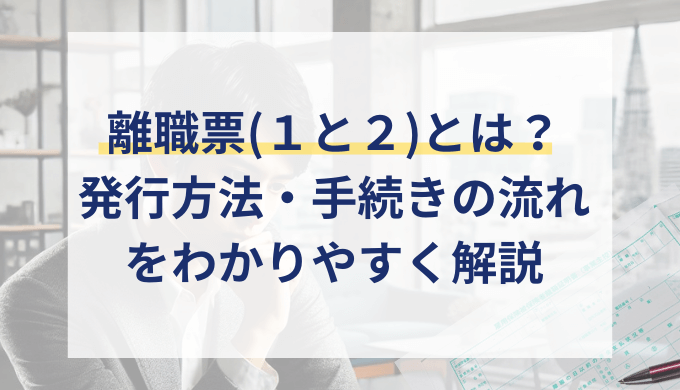 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
離職票は退職時に一度しか発行されない書類と思われがちですが、紛失や破損があった場合は、法律上何度でも再発行を申請することが可能です。
雇用保険法施行規則第17条第4項では、離職票を滅失・損傷した場合に再交付を請求できると明確に定められており、その回数に制限はありません 。したがって、退職者が望めば何度でも再発行申請ができます。
ただし、離職票そのものに有効期限はありませんが、失業手当(基本手当)の受給期間は原則として退職日の翌日から1年間と定められています 。
失業手当の受給を目的として離職票を必要としている退職者も多いため、企業担当者としては迅速な対応が求められます。
会社経由の再発行は「退職翌日から4年以内」が現実的
会社が退職者の依頼を受けて再発行手続きを代行する場合、その対応が可能なのは、法律上の書類保管義務がある「退職日の翌日から4年間」が現実的な期限となります 。
これは、雇用保険法施行規則第143条により、事業主には離職票発行の根拠となる「離職証明書」や関連する賃金台帳・出勤簿といった書類を、4年間保存する義務が課せられているためです 。この保管期間内であれば、会社は記録に基づいて再発行手続きに協力できます。
しかし、4年を超えると会社の保管義務がなくなり、記録の確認が困難になるため、再発行への協力が事実上難しくなります 。
本人がハローワークで申請する場合は期限なし
退職者本人が直接ハローワークで再発行を申請する場合、原則として申請期限はありません 。ハローワークには過去の雇用保険の加入記録が保管されているため、退職から何年経過していても、必要な書類を揃えれば再発行が可能です。
会社が倒産していたり、書類の保管期間である4年を過ぎていたりする場合でも、本人が直接手続きを行えることを覚えておきましょう。
離職票の再発行手続きは、主に「会社が代理で申請する方法」と「退職者本人が直接申請する方法」の2つに大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。企業担当者としては、両方のパターンを理解し、退職者へ適切に案内できるようにしておきましょう。
方法① 会社が所轄ハローワークで再交付申請
退職者から依頼を受けた会社が、代理で事業所の所在地を管轄するハローワークに再発行を申請する方法です。退職者にとっては、会社に任せられるため手間が少ないというメリットがあります。
企業担当者は、退職者から依頼を受けたら速やかに対応する義務があります 。手続きは以下の流れで進めます。
ハローワークのウェブサイトから申請書をダウンロードするか、最寄りのハローワークで入手します 。申請書には、会社の名称・所在地、退職者の氏名や被保険者番号、再発行の理由などを正確に記入し、社印を押印します。
申請書に加えて、退職者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピーを添付します。
作成した申請書と添付書類を、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。提出方法は、窓口への持参、郵送、またはe-Gov(電子政府の総合窓口)を通じた電子申請が可能です 。
ハローワークで手続きが完了すると、新しい離職票が会社へ交付されます。受け取った離職票は、速やかに退職者本人へ郵送してください。会社経由の場合、郵送のやり取りが発生するため、退職者の手元に届くまでには数日から1週間程度の時間がかかるのが一般的です 。
| 【会社経由手続きのチェックリスト】 [ ] 退職者の依頼内容(氏名・退職日・連絡先)を確認し、記録したか [ ] 「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に必要事項を正確に記入・押印したか [ ] 退職者の身分証明書や雇用保険被保険者証のコピーなど、添付書類は揃っているか [ ] 管轄ハローワークへ、適切な方法(窓口・郵送・電子申請)で提出したか [ ] 再発行された離職票を退職者へ送付し、元の離職票が無効になる旨を伝えたか |
方法② 退職者本人が直接ハローワーク窓口で即日申請
退職者本人が、自身の身分証明書などを持参してハローワークの窓口で直接申請する方法です。急いで離職票を必要とする場合には、この方法が最も迅速な手段となります。
特に、退職した会社の所在地を管轄するハローワークで手続きを行えば、記録の確認がその場でできるため、原則として即日発行が可能です。企業担当者は、退職者から「急いでいる」と相談された際に、この方法を案内できると非常に親切です。
企業担当者は、退職者へ以下の手順を案内すると良いでしょう。
①必要書類を準備する
- 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの身分証明書が必要)
- 印鑑
- 雇用保険被保険者証(手元にあれば持参。紛失していても申請は可能です)
②管轄のハローワーク窓口で申請する
即日発行を希望する場合は、退職した会社の所在地を管轄するハローワークへ本人が直接出向く必要があります。現住所の最寄りのハローワークでも申請は可能ですが、その場合は書類が郵送になるなど発行までに数日かかります。
◯会社が倒産・連絡不能な場合
会社がすでになく連絡が取れない状況でも、ハローワークは過去の記録に基づき再発行手続きを進めることができます。
◯代理人による申請
本人が病気などで窓口に行けない場合は、委任状と代理人の身分証明書があれば、家族などが代理で手続きを行うことも可能です。
会社側の対応としては、退職者から申請に必要な情報(会社の事業所番号や所在地、電話番号など)を尋ねられた際に、速やかに正確な情報を提供することが求められます。
方法③ 郵送・e-Govで電子申請
ハローワークの窓口へ直接出向くのが難しい場合は、郵送や電子申請(e-Gov)を利用する方法もあります。
退職者本人が、必要書類のコピーと返信用封筒を同封して、管轄のハローワークへ郵送で申請します 。会社が郵送で手続きを代行することも可能です。ただし、窓口申請に比べて日数がかかる点には注意が必要です。
政府が運営する「e-Gov(電子政府の総合窓口)」を利用すれば、24時間いつでもオンラインで再発行の申請ができます 。窓口に行く手間が省け、手続きの進捗状況もオンラインで確認できるため非常に便利です。
企業が電子申請を利用するには、事前に「GビズID」のアカウントを取得するなどの準備が必要ですが、一度設定すれば他の社会保険手続きにも活用できるため、業務効率化の観点から導入を検討する価値は高いでしょう 。
なお、2025年1月からはマイナポータル経由での離職票交付も可能になるなど、手続きのデジタル化は今後さらに進んでいく見込みです 。
離職票の再発行をスムーズに進めるためには、事前の書類準備が不可欠です。会社が手続きを代行する場合でも、退職者本人が申請する場合でも、基本的に必要となる書類は共通しています。
提出先や申請者(退職者本人または会社)によって必要書類が異なる場合もあるため、以下のチェックリストをもとに抜け漏れのない準備を進めましょう。
雇用保険被保険者離職票再交付申請書
再発行手続きの中心となるのが「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」です。この書類がなければ、手続きを開始できません。この申請書は、ハローワークに対して正式に再交付を依頼するための書類であり、以下のような情報を記入する必要があります。
- 被保険者番号
- 氏名・生年月日
- 退職年月日
- 最後に勤務していた事業所名と所在地
- 再交付を希望する理由(例:紛失・汚損など)
申請書はハローワークの窓口や公式サイト(e-Gov含む)から入手可能です。手書きで提出する場合は黒ボールペンで丁寧に記入し、記載漏れがないようにしましょう。
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
申請者の身元を確認するため、公的な本人確認書類の提示またはコピーの提出が必須となります。申請者本人が手続きを行う場合、必ず本人確認書類の提示が求められます。認められる書類としては、以下のようなものがあります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 健康保険証+補完書類(公共料金の領収書など)
本人が窓口で申請する場合は原本の提示、会社が代理で申請する場合や郵送申請の場合は、これらの書類のコピーを添付します。
雇用保険被保険者証・離職票番号ほか
再交付をスムーズに進めるためには、過去に発行された離職票の情報が分かる資料があると便利です。必須ではありませんが、次のような情報・書類があると申請時に役立ちます。
- 雇用保険被保険者証(※退職時に本人へ交付されている場合)
- 以前の離職票のコピー
- 離職票の交付番号や交付日(会社の控え、メール履歴などで確認)
- 最後に勤務していた事業所の所在地・名称・電話番号
上記の情報がない場合でも再発行は可能ですが、ハローワークでの本人確認や照合に時間がかかることがあります。できるだけ正確な情報を準備しておきましょう。
| 実務対応チェックリスト(会社担当者向け) [ ] 雇用保険被保険者離職票再交付申請書を入手・記入した [ ] 本人確認書類(コピー)を用意した [ ] 離職票番号・退職日・事業所情報を確認した [ ] 提出先のハローワーク管轄を調べた [ ] 書類一式を整えて提出(窓口・郵送・電子申請) |
離職票は再発行が可能な書類ですが、再発行の際にはいくつか重要な注意点があります。実務上のトラブルや手続きの遅延を防ぐため、以下のポイントを必ず確認してください。
離職票が未発行だった場合の手順
離職票の「再発行」以前に、そもそも会社が離職票を発行していなかったケースも少なくありません。この場合、最初に行うべきは離職票の新規発行手続きです。
退職者が「失業給付を受けたい」と希望しているにもかかわらず離職票が未発行であった場合、会社は速やかに以下の手続きを行う必要があります。
①雇用保険被保険者離職証明書の作成
退職者の在籍時の賃金台帳や出勤簿を基に「雇用保険被保険者離職証明書」を3枚複写で作成します。この書類が離職票の元となります。
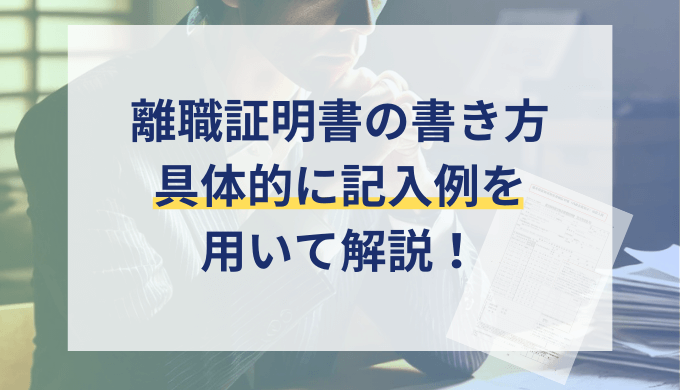 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
②離職証明書への本人署名
作成した離職証明書の記載内容(特に離職理由)について退職者本人に確認を求め、記名押印または署名をもらいます。
③管轄ハローワークへの提出
作成した書類を、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。この手続きには厳密な期限が定められているため、注意が必要です。
◯提出書類
- 雇用保険被保険者離職証明書(本人の署名または記名押印済みのもの)
- 雇用保険被保険者資格喪失届(未提出の場合)
◯提出期限
従業員が離職した日の翌々日から10日以内に提出する必要があります。提出が遅れると、退職者の失業手当受給開始も遅れてしまうため、期限内に必ず手続きを完了させてください。
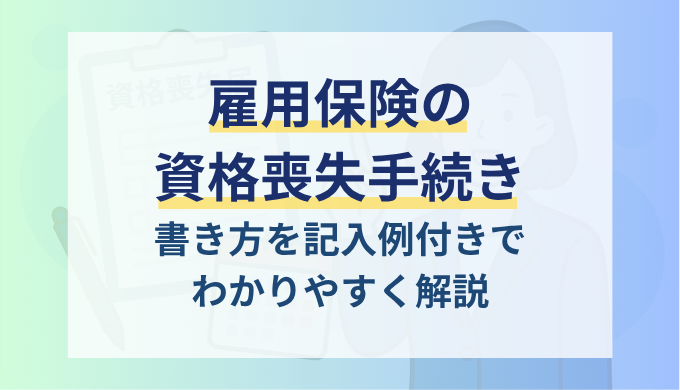 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
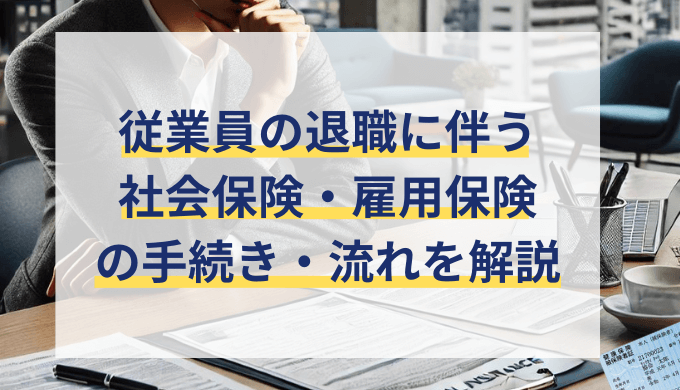 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
このように、離職票が未発行だった場合は「再発行」とは手続きの根本が異なります。まずは社内の記録を確認し、過去の発行履歴をチェックすることが重要です。
会社経由での再発行は日数がかかる
会社が退職者の依頼を受けて再発行手続きを代行する場合、退職者本人が直接ハローワークの窓口で申請するよりも時間がかかる点を理解しておく必要があります。
会社が申請書を作成し、郵送でハローワークとやり取りを行い、さらに発行された離職票を退職者へ郵送するというステップを踏むため、一般的には数日から1週間程度の期間を要します。
失業手当の申請期限が迫っているなど、退職者が離職票を急いで必要としている場合は、会社経由での手続きにかかる日数を正直に伝えた上で、本人が直接ハローワークへ行けば即日発行も可能であることを案内するのが親切な対応です。
紛失した離職票の交付年月日と交付番号の記入が必要
離職票の再交付を申請する際には、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に、以前発行された離職票の「交付年月日」と「交付番号」を記入する欄があります。
この情報は、ハローワークが過去の交付記録を正確に特定するために必要となります。退職者本人がこれらの情報を覚えていないケースがほとんどであるため、会社側で保管している離職証明書の控えや、ハローワークから交付された「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」などで確認し、正確に記入してください。
もし会社の控えでも確認できない場合は、申請書を提出する前に管轄のハローワークへ電話などで問い合わせ、確認方法について指示を仰ぐとスムーズです。
再発行後は元の離職票が無効になる
離職票の再発行手続きが完了し、新しい離職票が交付されると、紛失したと思っていた元の離職票は法的に無効となります 。
これは、二重の申請による不正受給などを防ぐための重要なルールです。後から元の離職票が見つかったとしても、それを使って失業手当の申請手続きを行うことはできません。
企業担当者としては、この点を必ず退職者本人に伝え、「もし古い離職票が見つかっても使わずに、必ず今回新しく発行されたものを使用してください」と明確に案内する義務があります。この説明を怠ると、退職者が誤って無効な書類を使用してしまい、トラブルに発展する可能性があります。
離職票を再発行しない場合の罰則
退職者から離職票の交付を求められたにもかかわらず、会社が正当な理由なく手続きに協力しなかったり、発行を拒否したりした場合、法律に基づく罰則の対象となる可能性があります。
雇用保険法第83条には、事業主が法令に違反した場合の罰則が定められており、悪質なケースでは「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることがあります 。
離職票の交付は、退職者のその後の生活保障に関わる重要な手続きであり、会社に課せられた法的な義務です。手続きを依頼された際は、迅速かつ誠実に対応することが、企業のコンプライアンス(法令遵守)と信頼を守る上で不可欠です。
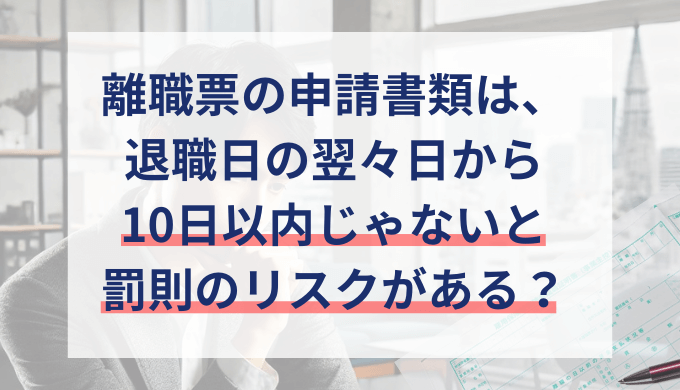 離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の再発行に関する手続きは、会社側・退職者側どちらにも初めての対応であることが多く、不安や疑問が生じやすい分野です。ここでは、特に問い合わせの多い質問について、わかりやすく解説します。
離職票の再発行が間に合わない場合は、退職証明書で一時的に代用できる?
結論として、失業手当の受給手続きにおいて、退職証明書を離職票の代わりとして使用することはできません。
離職票は、失業手当の受給資格や支給額を決定するための公的な証明書です。一方、退職証明書は、あくまで会社が在籍の事実や退職理由を証明する私的な文書であり、公的な効力はありません。
ただし、退職者が国民健康保険への切り替え手続きなどを行う際に、離職票が手元にない場合に、退職証明書が状況を証明する書類として一時的に認められるケースはあります。しかし、失業手当の手続きには、必ずハローワークが発行する正式な離職票が必要となるため、混同しないように注意が必要です。
退職証明書は再発行できるの?
退職証明書も離職票と同様に再発行が可能です。
労働基準法第22条では、退職した従業員から請求があった場合、事業主は遅滞なく証明書を交付しなければならないと定められています。この義務は、退職後の2年間は有効です。
したがって、退職から2年以内の元従業員から退職証明書の再発行を依頼された場合、会社は原則として応じる法的義務があります。2年を経過した後も、可能な限り対応することが望ましいでしょう。
失業手当の期限が迫っていると急かされたら?(仮受付制度)
退職者から「失業手当の申請期限が迫っているので急いでほしい」と催促された場合、ハローワークの「仮受付制度」について案内するのが有効です。
これは、離職票の発行が遅れるなどの理由で、失業手当の受給資格決定手続きの期限に間に合わない場合に、離職票がなくても先に仮の手続きを進めておくことができる制度です。
仮手続きを済ませておくことで、後日離職票を提出すれば、受給開始が不利になることを防げます。企業担当者としては、再発行手続きを急ぐと同時に、「万が一間に合わない場合は、ハローワークで仮手続きができます」と退職者に伝えることで、相手を安心させることができます。
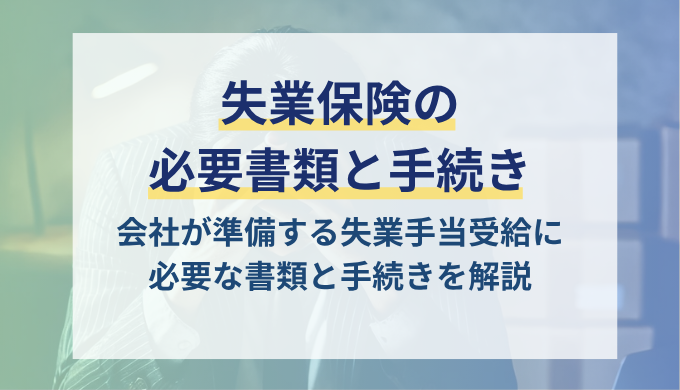 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
離職票の再発行にかかる時間・期間は?
再発行にかかる日数は、申請方法や処理するハローワークの混雑状況によって異なります。
| 申請方法 | 所要期間の目安 | 備考 |
| ハローワーク窓口(本人申請) | 即日〜3営業日 | 管轄内であれば即日対応が多い |
| 郵送申請(本人 or 会社) | 約5〜10日 | 書類不備があると遅れる可能性あり |
| e-Gov(電子申請) | 約3〜7日 | 処理状況により前後。事前設定が必要 |
| 会社経由の再申請 | 約1〜2週間 | 会社→ハローワーク→会社→退職者の流れ |
退職者から「すぐに必要」と連絡があった場合は、本人が直接ハローワークへ出向く方法が最短です。会社としてもその旨を案内することで、対応スピードを高めることができます。
離職票は、退職者が失業手当(失業給付)の受給手続きを進めるうえで欠かせない公的書類です。その再発行対応は、企業に課せられた重要な責務であると認識しておく必要があります。
結論として、離職票は法的に何度でも再発行が可能です。ただし、会社経由で対応する場合や本人申請の場合で、手続き方法や所要日数、必要書類が異なるため、企業側には正確な対応が求められます。
特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 離職票の再発行は、原則として何度でも可能です
- 会社経由での申請は「退職翌日から4年以内」が現実的な対応期限です
- 退職者本人がハローワークで直接申請することも可能で、多くの場合、即日発行されます
- 対応を怠ると、雇用保険法違反や給付遅延につながる可能性があります
離職票の再発行手続きは、単なる事務作業ではなく、退職者の生活基盤を支える重要なプロセスの一部です。企業としては、迅速かつ誠実な対応を徹底することで、コンプライアンスの強化と円満な労使関係の維持につなげることができます。
万が一、手続きに不安がある場合や、日々の業務で対応が難しいと感じる場合には、社会保険労務士にスポットで相談することも有効な選択肢です。適切なサポートを受けることで、ミスや遅延のリスクを避け、スムーズな再発行対応が可能になります。
スポット申請代行サービスの社労士クラウド
離職票の再発行対応では、「会社経由での手続きは何をすればいいのか分からない」「ハローワークへの申請書類が揃っていない」「交付番号や交付年月日が分からず手続きが進められない」といったお悩みがよく寄せられます。
- 「退職者から離職票の再発行を依頼されたが、対応方法がわからない…」
- 「記入ミスや漏れが不安で、社内対応では手続きが滞っている…」
- 「コア業務が多忙で、ハローワークとのやりとりまで手が回らない…」
このような場合には、社労士クラウドのスポット申請代行サービスをご活用ください。
当サービスでは、離職票の再発行手続きをはじめ、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職証明書」の作成、社会保険の資格喪失手続きまで、退職に伴う一連の業務を1件から社会保険労務士が代行いたします。顧問契約は不要で、「今回だけ」「退職者1名分だけ」といったご依頼にも柔軟に対応しています。
最新の法令に準拠した正確な処理と、迅速な対応で、退職者への影響を最小限に抑え、企業としての信頼性を守ります。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|