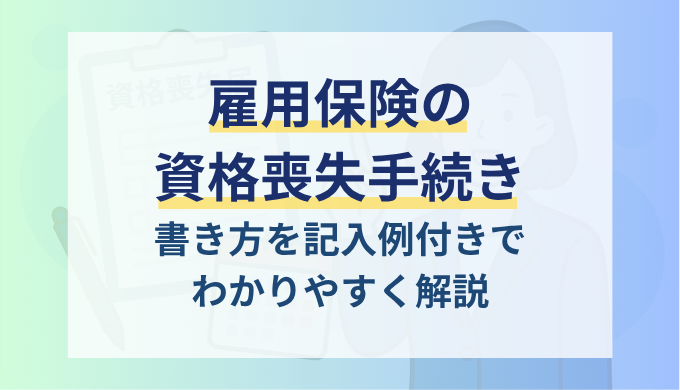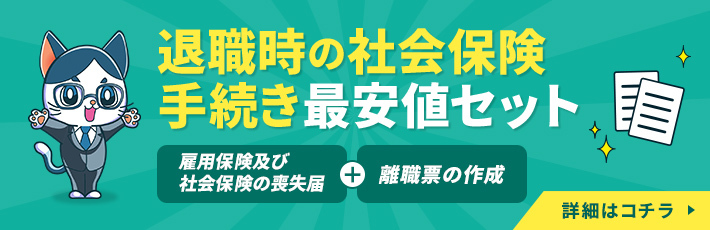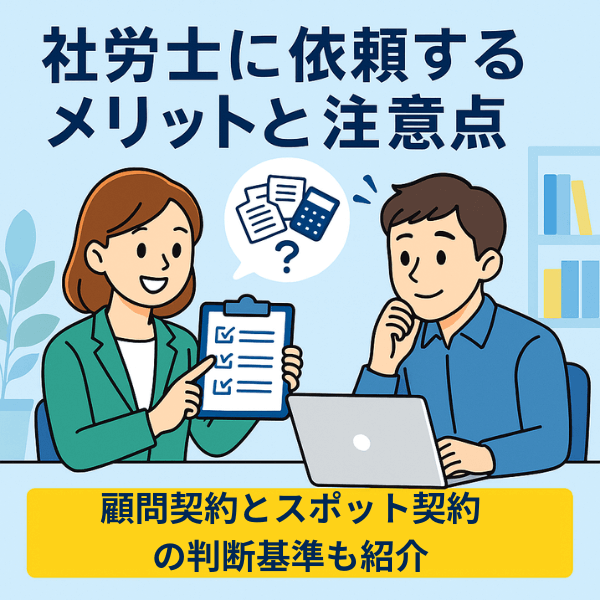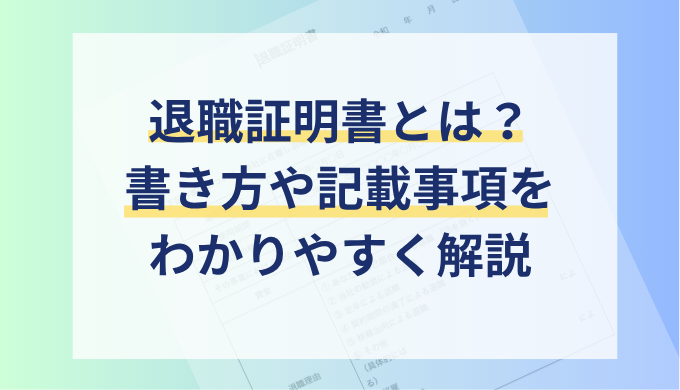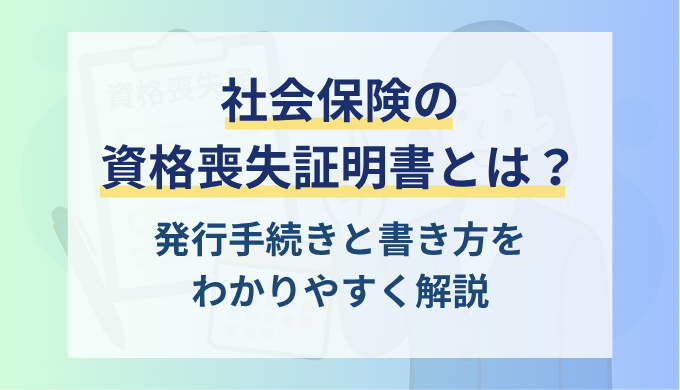従業員の退職や労働条件の変更など、雇用保険の資格を失う場面で事業主として必ず対応しなければならないのが「雇用保険被保険者資格喪失届」の手続きです。
しかし、提出期限は事実発生の翌日から10日以内と短く、離職票や離職証明書といった似た名前の書類も関わるため、「どの書類を、いつまでに、どう書けばいいのか」「記入ミスで会社や元従業員に迷惑をかけたくない」と悩む人事・労務担当者の方や事業主様は少なくありません。
本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届について、手続きが必要になる様々なケースから、具体的な書き方・記入例、添付書類、提出方法、そして注意点までを社労士が徹底解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、雇用保険の資格喪失手続きに関する不安を解消し、自信を持って正確に業務を遂行できるようになります。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
雇用保険被保険者資格喪失届とは、従業員が退職・死亡・労働時間の変更などによって、雇用保険の加入資格を失った際に、事業主がハローワークへ提出することが法律で義務付けられている届出書類です。
 雇用保険とは?加入条件や手続き、計算方法までわかりやすく解説
雇用保険とは?加入条件や手続き、計算方法までわかりやすく解説
この手続きの主な目的は、以下の2点です。
- 従業員が失業後の生活を支える「基本手当(いわゆる失業保険)」を適正に受給できるようにすること
- 事業主が納付する雇用保険料を、在籍する被保険者の状況に合わせて正確に計算・管理すること
この届出は、原則として資格喪失日(退職日の翌日など)から10日以内に提出しなければなりません。
もし正当な理由なくこの手続きを怠った場合、事業主には雇用保険法に基づき「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます 。また、提出が遅れると離職票の交付も遅れ、退職した従業員の生活に影響が及ぶおそれがあるため、迅速な対応が不可欠です。
一連の雇用保険手続きは専門的な知識を要するため、特に以下のようなケースでは慎重な判断が求められます。
- 自己都合退職か会社都合退職かの判断に迷う場合
- 提出期限の10日を過ぎてしまった場合の対応
- 外国人労働者やパートタイマーなど、特殊な雇用形態の従業員の手続き
このような判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、専門家である社会保険労務士へ相談することも有効な手段です。
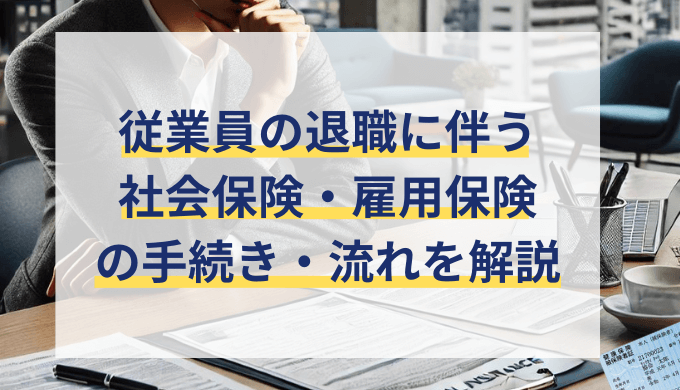 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が「雇用保険の加入条件を満たさなくなったタイミング」で、速やかに提出が求められます。多くの場合は退職に伴う提出となりますが、それ以外にも「死亡」「役員就任」「労働時間の短縮」など、就業状況の変化によって資格を喪失するケースがあります。
提出漏れを防ぐためにも、どのようなケースで手続きが発生するのかを正確に把握しておくことが重要です。
以下で、主な提出タイミングをケース別に解説します。
従業員が退職した場合(自己都合・会社都合など)
最も一般的な提出タイミングは、従業員が退職したときです。
退職日(最終出勤日)の翌日が「資格喪失日」となり、その日から10日以内に資格喪失届を提出しなければなりません。
退職理由によって、書類の記載内容や添付書類が異なるため、以下の点に注意が必要です。
- 自己都合退職:本人の意思で退職したケース(例:転職、結婚、体調不良など)
- 会社都合退職:解雇、会社都合による契約終了、倒産、雇止めなど
- 定年退職:60歳や65歳など、就業規則に基づく自然退職
退職理由によって「失業給付の給付制限の有無」や「離職票の交付の必要性」が変わります。記載ミスはトラブルの原因になるため、事前に従業員本人と退職理由の確認をしておくことが大切です。
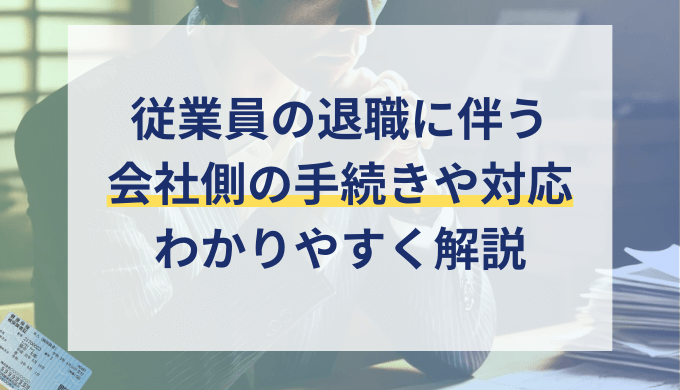 従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
従業員の退職で会社側が行う退職手続き一覧・流れや必要書類を社労士が解説
死亡、役員就任、転籍など特別なケース
従業員の退職以外にも、以下のような特別なケースに該当した場合、資格喪失の手続きが必要となります 。
- 従業員が死亡したとき
- 従業員が法人の役員に就任したとき
- 他社へ転籍したとき
役員就任後も実質的に雇用契約が継続している場合は、被保険者としての資格が継続することもあります。判断に迷う場合は年金事務所や社労士へ確認を。
所定労働時間が20時間未満になった場合
雇用保険の加入要件の一つに、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」が定められています。
そのため、正社員からパートタイマーになるなど雇用契約の内容が見直され、週の所定労働時間が継続的に20時間未満になった場合も、雇用保険の資格喪失の対象となります 。
▼よくあるケース
- 正社員から時短パートへの変更
- 子育て・介護などによる時短勤務制度の利用
- 出勤日数の削減による週20時間未満化
ただし、繁忙期が終わったなどの理由で、一時的に労働時間が短くなっただけでは対象となりません。あくまで雇用契約そのものが変更され、恒常的に労働時間が基準を下回る場合に手続きが必要だと理解しておきましょう。
その他の提出が必要となる例(労働者が雇用保険の適用除外になるケースなど)
上記以外にも、従業員が法律で定められた雇用保険の「適用除外」の条件に該当した場合や、特殊な状況下で雇用契約が終了した場合に、資格喪失の手続きが必要となります。
代表的な例は以下の通りです。
- 昼間学生になった場合
- 65歳以上で雇用される労働者の場合
- 外国人労働者の在留資格が変更・終了した場合
これらのケースでは、雇用契約の実態や個別の状況を総合的に判断する必要があるため、手続きに迷った際は管轄のハローワークや社会保険労務士に事前に確認することをおすすめします。
雇用保険被保険者資格喪失届は、「ハローワークの窓口」または「インターネットからのダウンロード」で入手できます。急いで書類を準備する場合や、手元に用紙がない場合には、インターネットからのダウンロードが便利です。
ハローワーク窓口での入手
最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)の窓口で、「雇用保険被保険者資格喪失届」の様式を直接受け取ることができます。
初めて手続きを行う事業所や、複数の届出様式を一度に入手したい場合は窓口での取得が便利です。
■チェックポイント
窓口では、離職票や離職証明書の様式も併せて受け取ることができます。提出予定の書類が複数ある場合は、窓口職員に目的を伝えると必要な様式を一式で案内してもらえます。
ハローワークインターネットサービスからのダウンロード
雇用保険被保険者資格喪失届は、厚生労働省の「ハローワークインターネットサービス」から無料でダウンロード可能です。
ダウンロードできるPDFには、主に2つの種類があります。
- 様式のみ印刷するPDF
- 内容を入力して印刷するPDF
ダウンロード先)ハローワークインターネットサービス | 厚生労働省
ダウンロードした様式を印刷する際には、特に注意が必要です。この届出書はOCR(光学文字認識)という機械で読み取られるため、印刷設定を誤るとハローワークで受理されない可能性があります 。
以下のチェックリストを参考に、正しく印刷されているか必ず確認してください。
| 項目 | 注意点 |
| 用紙サイズ | A4サイズの白い普通紙に印刷してください 。感熱紙や色のついた紙は使用できません。 |
| 印刷倍率 | 必ず「倍率100%(実際のサイズ)」で印刷してください 。縮小・拡大は絶対に行わないでください 。 |
| 両面印刷 | 様式の第1面と第2面を、1枚の用紙に両面印刷するか、または片面ずつ2枚に分けて印刷してください 。 |
| OCRマークの確認【最重要】 | 用紙の四隅にある3つの黒い四角(■)マークが、欠けたりかすれたりしていないかを必ず確認してください 。このマークは、機械が書類の位置を正しく認識するために不可欠です 。 |
| 印刷品質 | 文字や枠線がかすれていたり、二重に印刷されたりしていないか確認してください 。インクジェットプリンターの場合は、インクのにじみにも注意が必要です。 |
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員の個人情報や退職に関する情報を正確に記入する必要があります。特に、番号や日付、離職理由は失業給付の算定に直接影響するため、細心の注意を払って作成しなければなりません。
ここでは、届出用紙の各項目について、公式の記入例を基に具体的な書き方と、実務で間違いやすいポイントを解説します。
項目別の記入例
(1)個人番号(マイナンバー)
退職する従業員の12桁の個人番号(マイナンバー)を正確に記入します。
※提出書類にはマイナンバー記載欄がありますが、「個人番号を記載しない場合は代わりに被保険者番号を記入」してください。
(2)被保険者番号
「雇用保険被保険者証」に記載されている11桁の被保険者番号(4桁-6桁-1桁)を記入します。
(3)事業所番号
会社の「雇用保険適用事業所番号」を記入します。
この番号は、雇用保険の適用事業所になった際にハローワークから交付される「適用事業所設置届の控」や、従業員の資格取得時に受け取る「資格取得確認通知書」などで確認できます。
(4)資格取得年月日
当該従業員が雇用保険に加入した年月日(入社日など)を和暦で記入します。
| 記入例 | 令和2年4月1日入社 → 「5-020401」のように元号コード(令和=5)と年月日を6桁で記入します。 |
元号コードを間違えないように注意してください(平成=4、昭和=3)。
(5)離職等年月日
被保険者資格を失った原因となる日(離職日など)を和暦で記入します。
| 記入例 | 令和7年3月31日に退職 → 「7-070331」のように記入します。 |
ここでいう「離職年月日」とは、在籍最終日そのものを指します。有給休暇の消化などで最終出社日と異なる場合でも、雇用契約上の最終日を記入してください。
(6)喪失原因
資格を失った理由を、以下の区分から選択して番号で記入します。
| <喪失原因の区分> 1. 離職以外の理由 死亡、在籍出向、役員就任など、退職以外の理由で資格を失った場合に選択します。 2. 3以外の離職 事業主の都合による離職(解雇など)以外の理由で離職した場合に選択します。自己都合退職や契約期間満了、定年退職などが該当します。 3. 事業主の都合による離職 解雇(重責解雇を除く)や退職勧奨など、会社の都合によって離職した場合に選択します。 |
この区分は失業給付の受給資格に大きく影響するため、従業員と離職理由を十分に確認し、事実に基づいて正確に選択する必要があります。
(7)離職票交付希望
退職者が失業給付の申請に必要な「離職票」の交付を希望するかどうかを選択します。
1. 有:交付を希望する場合に選択します。
2. 無:交付を希望しない場合に選択します。
従業員が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票の交付が義務付けられているため、必ず「1(有)」を選択してください。
(8)1週間の所定労働時間
退職時点での、雇用契約書などで定められた1週間の所定労働時間を記入します。
| 記入例 | 週40時間勤務 → 「4000」と記入します。 |
残業時間は含めず、契約上の所定労働時間を記入してください。
(9)補充採用予定の有無
この退職者の後任として、新たな従業員を採用する予定がある場合に「1(有)」を選択します。予定がない場合は空欄で問題ありません。
ケース別の記入例と注意点
それぞれのケースによって、資格喪失届に記載する「喪失原因」の選択や、離職票の交付要否などが異なります。 ここでは代表的な5つのケースについて、具体的な記載内容と実務上の注意点を解説します。
| (6)喪失原因 | 「2」(3以外の離職) を選択。転職や結婚、学業専念などを理由とする、従業員自身の都合による退職がこれに該当。 |
| 添付書類 | 原則不要(ただし、退職届を社内で保管しておくと安心) |
| 離職証明書の記載 | 離職票を交付する場合、離職証明書の「離職理由」欄には、より具体的な理由を記載します。(例:「自己都合による退職(転職希望のため)」) |
▼ポイント
後の失業給付の受給条件に影響するため、従業員から提出された「退職届」の内容と、届出の記載内容が一致しているか必ず確認してください。
| (6)喪失原因 | 「3」(事業主の都合による離職) を選択。 倒産や事業所の廃止、人員整理による解雇、退職勧奨などが該当。 |
| 添付書類 | ハローワークから、離職理由を客観的に証明する書類(例:解雇予告通知書の写し、希望退職募集の案内資料など)の提出を求められることがあります。 |
| 離職証明書の記載 | 会社都合退職の具体的な理由(例:契約期間満了、経営悪化による整理解雇など)を明記 |
▼ポイント
会社都合退職は、従業員の失業給付の受給において大きな意味を持ちます。後のトラブルを避けるためにも、離職に至った経緯を客観的な資料とともに記録・保管しておくことが重要です。
| (6)喪失原因 | 「1」(離職以外の理由) を選択。死亡は「離職」にはあたらないため、この区分を選択。 |
| 添付書類 | 通常は不要ですが、ハローワークから指示があった場合は死亡診断書などの写しを求められることがある。 |
| 離職票の交付 | 不要 |
| 備考 | ご遺族が未支給の失業給付などを請求する際には、ハローワークで別途手続きが必要となります。 |
▼ポイント
従業員の死亡という大変な状況ではありますが、資格喪失届の提出は事業主の法的な義務です。忘れずに手続きを行ってください。
| (6)喪失原因 | 「1」(離職以外の理由) を選択。 |
| 添付書類 | 必要に応じて、役員就任通知書や登記事項証明書などの確認資料を求められる場合がある。 |
| 備考 | 従業員としての身分を完全に失い、役員報酬のみを受ける立場になった場合に限り、資格喪失の対象となります。 |
▼ポイント
部長兼務役員のように、役員でありながら労働者としての性格が強く、雇用関係が継続していると判断される場合は、被保険者資格を継続することがあります。判断に迷う場合は、必ず事前にハローワークへ確認してください。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際には、資格を喪失した従業員(被保険者)の状況に応じていくつかの書類を添付する必要があります。
特に、会社を離職する従業員が失業給付の受給に必要となる「離職票」を希望するかどうかで、添付書類が大きく異なります。
離職証明書(離職票)を発行する場合の添付書類
退職する従業員が離職票の交付を希望する場合、事業主は「雇用保険被保険者資格喪失届」とあわせて**「雇用保険被保険者離職証明書」**を提出しなければなりません 。
さらに、ハローワークは離職証明書に記載された内容(賃金額や離職理由など)が事実であることを確認するため、以下の確認書類の添付を求めます。
以下の書類は、離職証明書に記載する賃金支払状況や出勤状況の裏付けとなるため、原則として提出が必要です。
■原則として必要になる添付書類
- 労働者名簿
- 出勤簿、タイムカードなど(賃金の支払い基礎となった期間分)
- 賃金台帳(賃金の支払い基礎となった期間分)
離職理由は失業給付の受給条件に大きく影響するため、その理由を客観的に証明する書類の提出を求められることがあります。
| 離職理由 | 主な確認書類の例 |
| 自己都合退職 | 従業員本人から提出された「退職届」や「退職願」 |
| 会社都合による解雇 | 会社が交付した「解雇予告通知書」 |
| 契約期間満了 | 「雇用契約書」など、契約期間が明記された書類 |
| 定年退職 | 「就業規則」など、定年に関する規定が記載されている部分の写し |
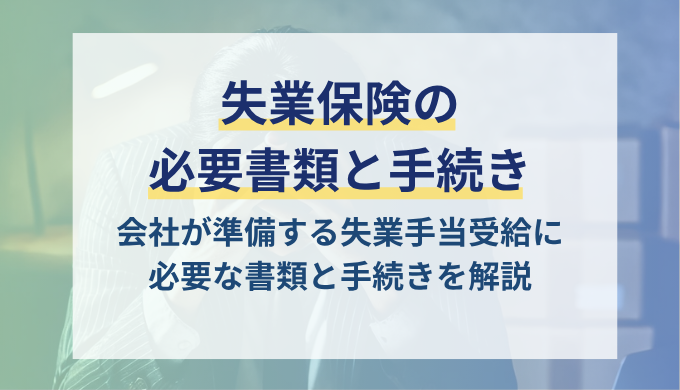 退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
退職時に会社が準備する失業保険受給に必要な書類と手続きを解説
【実務のポイント】
ハローワークは、提出された離職証明書の内容が正確かどうかを、これらの添付書類と照合して厳密に審査します。特に会社都合退職のケースでは、その理由を証明する客観的な資料が重要となります。手続きをスムーズに進めるためにも、求められる書類を事前に準備しておくことが大切です。
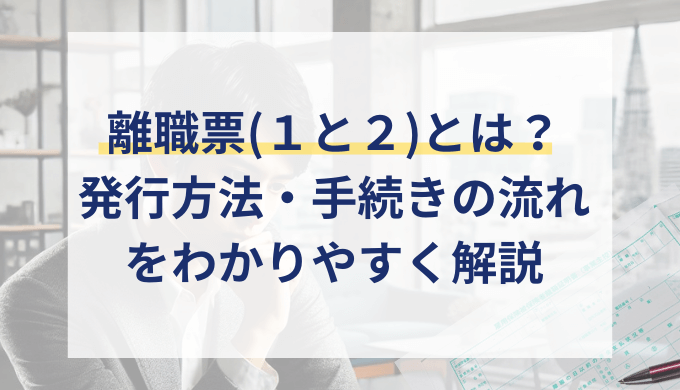 離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
離職票とは?発行手続きの流れや必要書類、使い道を社労士が解説
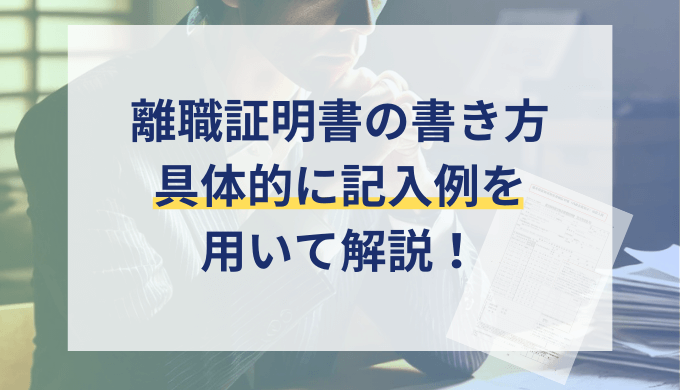 雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
雇用保険被保険者離職証明書とは?書き方と必要書類を記入例付きで社労士が解説
離職証明書を発行しない場合の添付書類
従業員が59歳未満で、かつ離職票の交付を希望しない場合には、離職証明書の提出は不要です 。
ただし、その場合でも事業主は退職の事実を証明するために、資格喪失届とあわせて以下の書類を提出する必要があります。
- 労働者名簿
- 退職日が確認できる書類(例:退職届の写し、賃金台帳、出勤簿など)
【重要】59歳以上の従業員への対応
従業員が離職日に59歳以上である場合は、本人が離職票の交付を希望しないと申し出たとしても、事業主は離職証明書を作成し、ハローワークへ提出する義務があります。
離職票を希望しない場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行されます。
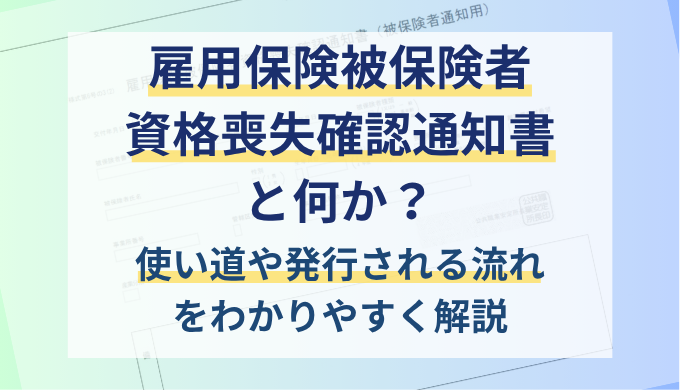 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?使い道や離職票との違いを社労士が解説
賃金台帳・出勤簿・労働者名簿の準備方法
雇用保険の手続きでは、賃金支払いや勤務の実態を証明するために、労働関係の重要書類(法定三帳簿)の提出が求められます。日頃から正しく整備しておくことが、スムーズな手続きの鍵となります。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿・タイムカード
【実務のポイント】
これらの書類は、提出用にコピー(写し)を用意するのが一般的です。内容に不備があると手続きが滞る原因となるため、必要な情報がすべて正確に記載されているか、提出前に必ず確認しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失届は、法律で定められた期限内に、正しい方法で提出することが事業主に義務付けられています。
ここでは、提出期限や提出先、各提出方法の違い、そして遅れた場合のリスクについて詳しく解説します。
提出期限は退職の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、従業員が資格を喪失した日(通常は退職日の翌日)の翌日から起算して10日以内です。
これは土日祝日を含む期間であり、非常に短いため、迅速な対応が求められます。
| 退職日 | 資格喪失日 | 提出期限 |
| 3月31日 | 4月1日 | 4月10日まで |
| 6月15日 | 6月16日 | 6月25日まで |
【ポイント】
提出期限の最終日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。この期限に遅れると、従業員の失業給付の手続きに遅れが生じ、トラブルの原因となるため、必ず期限を遵守しましょう。
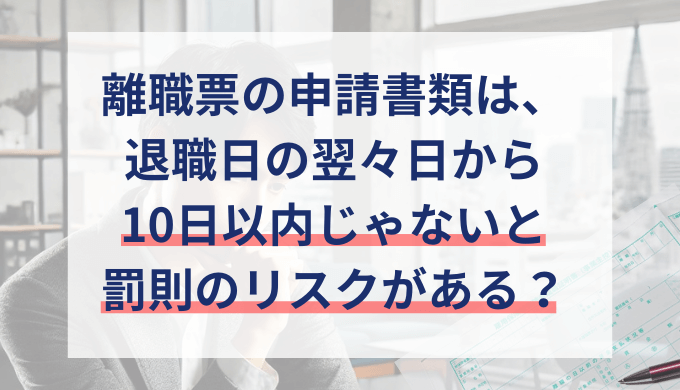 離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
離職票の申請期限10日以内を過ぎると罰則?期限内に提出できなかった場合の対処法も解説
提出先(ハローワーク)と窓口・郵送・電子申請の違い
届出は、会社の事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。 提出方法は、会社の状況に応じて以下の3つから選択できます。
| 提出方法 | メリット | デメリット・注意点 |
| 窓口持参 | ・その場で書類の不備をチェックしてもらえる ・不明点を直接質問できる | ・ハローワークの開庁時間内に行く必要がある・混雑時には待ち時間が発生することがある |
| 郵送 | ・ハローワークへ行く手間が省ける | ・手元に届くまで時間がかかる ・離職票の返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒の同封が必要 ・配達記録が残る特定記録郵便や簡易書留を推奨 |
| 電子申請 (e-Gov) | ・24時間いつでもオンラインで提出可能 ・業務効率が大幅に向上する | ・利用にはGビズIDや電子証明書の事前準備が必要 ・資本金1億円超の特定法人は電子申請が義務化されている |
提出が遅れた場合の罰則や従業員への影響
資格喪失届を正当な理由なく提出しなかったり、大幅に遅れたりした場合は、事業主と元従業員の双方に不利益が生じます。
雇用保険法第83条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。 また、ハローワークからの是正勧告や調査の対象となることもあります。
元従業員にとって最も大きな影響は、失業給付(基本手当)の受給手続きが大幅に遅れることです。 離職後の生活設計に直接的な影響を与えるため、会社への不信感やトラブルにつながるリスクが非常に高くなります。
提出時の注意点(マイナンバー・印刷形式など)
手続きを一度で不備なく完了させるために、提出時には以下の点に注意してください。
◯マイナンバーの取り扱い
届出書には従業員の個人番号(マイナンバー)を正確に記載します。 個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。
◯印刷様式の確認
ダウンロードして印刷する場合は、A4サイズの白い普通紙に、倍率100%で印刷します。 機械が読み取るためのOCRマーク(■)がかすれたり欠けたりしていないか
、必ず確認してください。
◯押印を忘れない
届出書には事業主の記名押印または署名が必要です。提出前に必ず確認してください。
◯添付書類の準備
離職票を交付するかどうかで、離職証明書や賃金台帳などの添付書類が変わります。事前に従業員の意向を確認し、必要な書類を揃えましょう。
◯控えの保管
提出する前に、必ず届出書のコピーをとり、会社の控えとして保管しておくことをお勧めします。
ここでは、雇用保険被保険者資格喪失届の手続きに関して、実務担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
雇用保険資格喪失届と離職票・離職証明書の違いは?
雇用保険資格喪失届は、雇用保険の資格が消滅したことを事業主がハローワークに届け出るための書類です。
一方で、離職票(1・2)および離職証明書は、従業員が失業給付を申請する際に必要な証明書類です。
| 書類名 | 目的・役割 | 提出先・交付先 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 従業員が雇用保険の資格を失った事実をハローワークに届け出るための書類。 | 事業主がハローワークへ提出。 |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 退職者が失業給付を申請する際に、その金額を算定するための賃金支払状況や離職理由を証明する書類。(3枚複写の用紙) | 事業主がハローワークへ提出。 |
| 離職票(-1、-2) | 退職者本人がハローワークで失業給付を申請するために使用する公的な書類。 | ハローワークが離職証明書に基づき発行し、事業主経由で退職者本人へ交付される。 |
資格喪失届は必須書類であり、離職票は従業員が希望した場合のみ提出・発行されます。
離職票と間違いやすい書類に退職証明書もあります。
自己都合か会社都合か判断がつかないときは?
離職理由の区分(自己都合か会社都合か)は、退職者の失業給付の受給日数や給付開始時期に大きく影響するため、非常に重要です。
判断に迷った場合は、事業主が勝手に判断せず、客観的な事実に基づいて慎重に対応する必要があります。
1.客観的な資料を確認する
まずは、従業員から提出された「退職届」や、会社側で作成した「解雇通知書」、面談の記録など、離職理由の根拠となる資料を確認します。
2.従業員本人と事実確認を行う
認識の齟齬を防ぐため、退職に至った経緯について本人と改めて確認し、合意しておくことが後のトラブル防止につながります。
3.専門機関に相談する
それでも判断に迷う場合は、管轄のハローワークに問い合わせるか、社会保険労務士に相談することをお勧めします。専門家の助言を仰ぐことで、適切な判断が可能になります。
▼判断の目安
| 区分 | 主な内容 |
| 自己都合退職 | 本人の意思による退職(転職・結婚・家庭の事情など) |
| 会社都合退職 | 解雇・倒産・雇止め・退職勧奨・経営悪化による退職など |
資格喪失届を提出し忘れた場合、どうすればいい?
提出を忘れていたことに気づいた場合は、決して放置せず、直ちに手続きを行ってください。
まず、速やかに「雇用保険被保険者資格喪失届」と必要な添付書類を準備します。その上で、管轄のハローワークに連絡し、提出が遅れた事情を正直に説明して、その後の指示に従いましょう。
意図的に提出を怠った場合は罰則の対象となりますが、気づいた時点ですぐに誠意ある対応をすれば、問題を最小限に抑えることができます。
▼対応の流れ
- 管轄ハローワークに連絡し、提出遅延の理由を説明
- 必要な書類(資格喪失届・離職証明書等)を速やかに提出
- ハローワークからの指導が入ることもありますが、自主的な対応で重い処分は通常回避できます
外国人労働者や短時間労働者にも提出が必要?
雇用保険に加入していた従業員であれば、国籍や雇用形態に関わらず、資格を失った際にはこの届出を提出する義務があります。
◯短時間労働者(パート・アルバイト)の場合
週20時間以上の契約で雇用保険に加入していた方が、契約変更によって週の所定労働時間が20時間未満になった場合、資格を失うため届出が必要です。
◯外国人労働者の場合
手続きは基本的に日本人従業員と同じですが、届出用紙の第2面(裏面)にある「在留カード番号」などの外国人特有の項目も忘れずに記入する必要があります。
雇用保険被保険者番号がわからないときの対応は?
雇用保険被保険者番号(11桁)は、従業員一人ひとりに割り当てられた重要な番号です。手続きをスムーズに進めるため、まずは以下の書類で番号を確認してください。
【被保険者番号が記載されている主な書類】
・会社が保管している書類: 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主控)」
・従業員本人が保管している書類: 「雇用保険被保険者証」、「離職票」(前職分など)
もし、上記の書類がどうしても見当たらない場合は、以下の手順で対応します。
- 届出用紙の番号欄は空欄のまま提出する
- 個人番号(マイナンバー)は必ず記載する
- 備考欄に補足情報を記入する
個人番号の記載は、被保険者番号の代替にはなりません。 あくまで本人を特定するための補助情報という位置づけです。被保険者番号は雇用保険制度における最も重要な管理番号のため、可能な限り探して記載するよう努めてください。
社会保険の被保険者資格喪失届との違いは?
従業員の退職や死亡など、雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の両方の資格を同時に喪失する際には、それぞれで資格喪失の手続きが必要になります。
これら2つの手続きは、名称が似ていますが全く別の制度であり、提出先や期限、様式が異なるため、混同しないように注意してください。
| 項目 | 雇用保険 資格喪失届 | 社会保険 資格喪失届 |
| 対象保険 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 |
| 提出先 | ハローワーク | 年金事務所 (または健康保険組合) |
| 提出期限 | 資格喪失の翌日から10日以内 | 資格喪失から5日以内 |
| 主な添付書類 | 離職証明書、賃金台帳など | 健康保険証 |
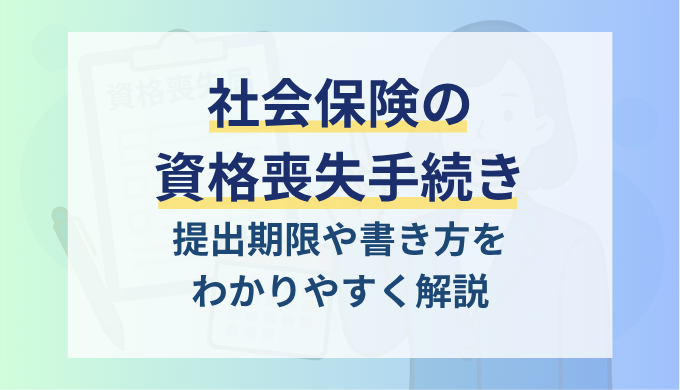 社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
社会保険の被保険者資格喪失届とは?記入例や提出先、遅れた場合の影響について解説
ここまで解説してきたように、雇用保険被保険者資格喪失届の手続きは、従業員が退職や労働条件の変更などによって雇用保険の加入資格を失った際に、事業主が必ず行わなければならない法的な義務です。
この手続きを怠ると、退職した従業員が失業後の生活を支えるための「基本手当」を速やかに受け取れなくなるなど、直接的な不利益を与えてしまうだけでなく、事業主自身も法律に基づく罰則の対象となる可能性があります。
提出期限は、資格喪失日の翌日から10日以内と非常に短く設定されています。手続きには、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿といった書類の準備も必要となるため、日頃から労務管理を適切に行い、退職者が発生した際には迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。
一連の手続きは専門的な知識を要するため、特に設立間もない企業や人事労務の専任者がいない事業所にとっては、大きな負担となり得ます。
もし手続きに少しでも不安がある場合や、コア業務に集中するために手続き業務を効率化したいとお考えの場合は、専門家である社労士に相談することをお勧めします。
社労士クラウドのスポット申請代行サービス
初めての手続きや、判断に迷うケース(役員就任、死亡退職、外国人労働者など)では、社労士など専門家のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑えることができます。
社労士クラウドのスポット申請代行サービスは、必要な時だけ専門家に業務を依頼できるサービスです。例えば、算定基礎届の作成・提出のみを依頼することも可能です。
スポットで依頼することで、自社で対応するよりも、確実かつ効率的に手続きを進められる場合があります。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|