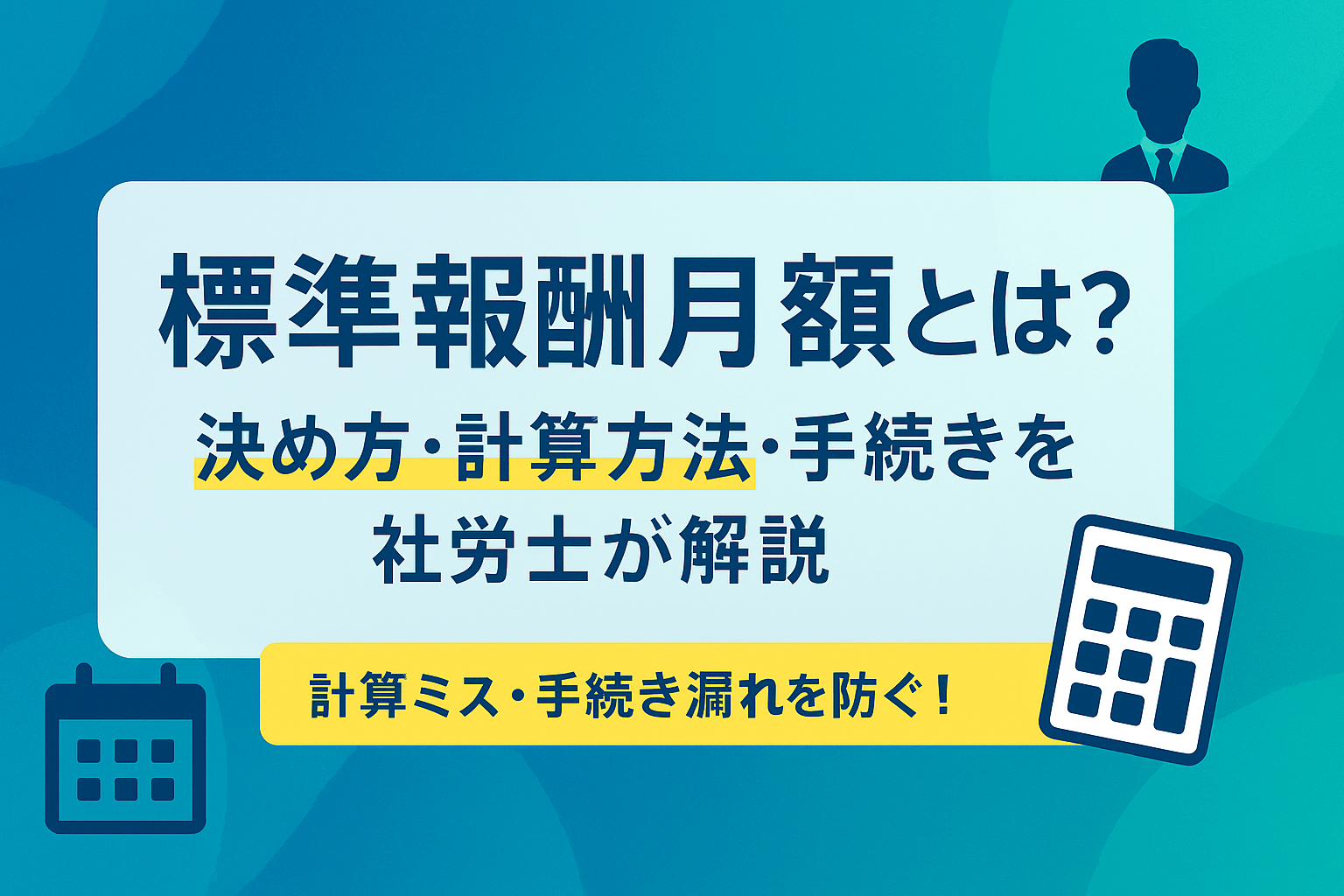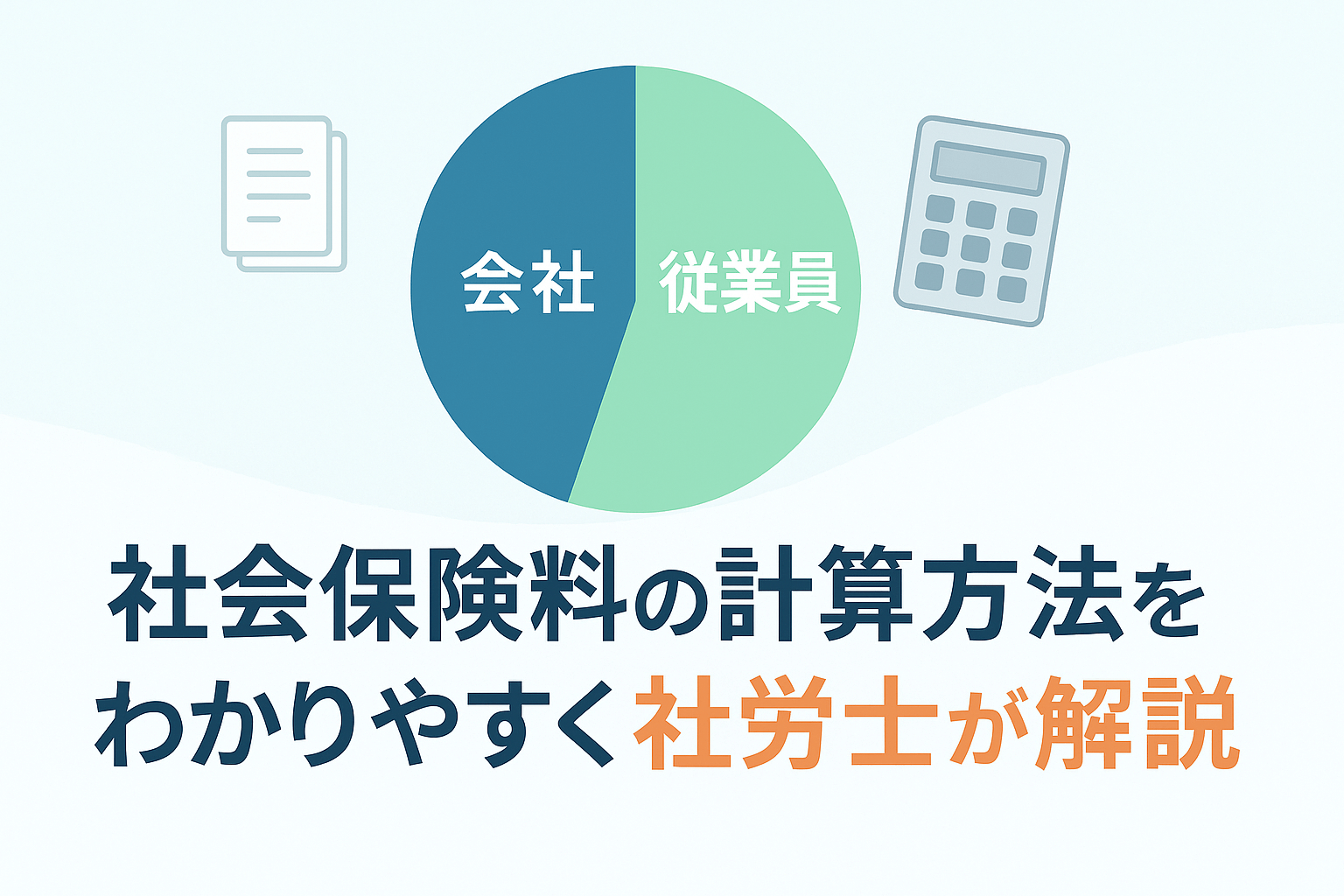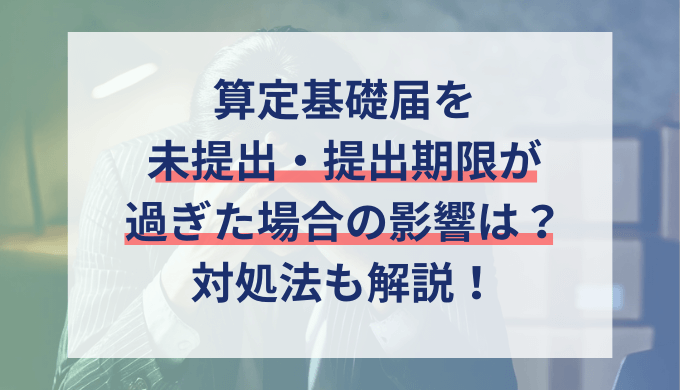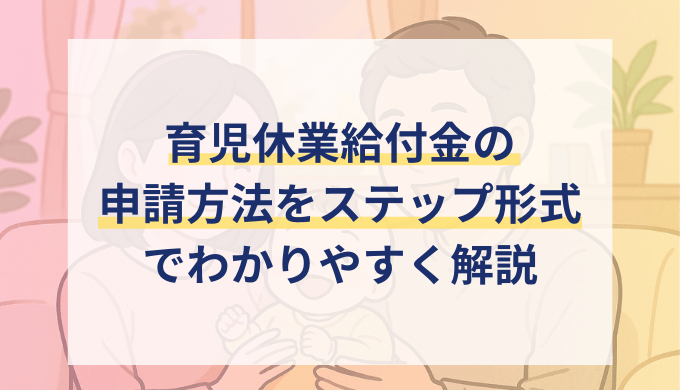標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料の計算基礎となる重要な金額です。
しかし、「どうやって決まるの?」「計算方法は?」「どの手当が含まれる?」といった疑問や、算定基礎届・月額変更届などの手続きの複雑さから、多くの事業主様や人事労務担当者様が頭を悩ませるポイントでもあります。
計算ミスや手続き漏れは、保険料の追徴だけでなく、将来の年金額にも影響を及ぼす可能性があるため、正確な理解が不可欠です。
本記事では、標準報酬月額とは何か、その決め方や計算方法、対象となる報酬の範囲、調べ方、そして定時決定や随時改定といった手続きのタイミングまで、実務担当者が押さえておくべき点をわかりやすく解説します。
この記事で解説したポイントを押さえ、標準報酬月額に関する手続きのミスや疑問点を解消し、日々の正確な業務遂行を実現しましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧 ・当日申請・フリー価格・丸投げOK| 2,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料を計算するための「基準となる月々の報酬額」 のことです。従業員に支払われる給与(報酬)は、残業手当などで毎月変動することがありますが、その都度保険料を計算し直すのは実務上、非常に煩雑になります。
そこで、従業員の実際の報酬額を、一定の幅で区切られた「等級」 に当てはめて標準報酬月額を決定し、これをもとに社会保険料を計算します。この仕組みにより、毎月の保険料計算が簡略化され、事業主や人事労務担当者の事務負担が軽減されます。
標準報酬月額の等級は、保険の種類によって異なります。
| 健康保険(協会けんぽの場合) | 第1級(5万8千円)から第50級(139万円)までの全50等級 |
| 厚生年金保険 | 第1級(8万8千円)から第32級(65万円)までの全32等級 |
※最高等級に達した場合、給与が上がったとしてもそれ以上の保険料が発生することはありません。
この標準報酬月額は、主に以下の社会保険料の計算に適用されます。
- 健康保険料(協会けんぽ、または各健康保険組合)
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳から64歳までの被保険者が対象)
標準報酬月額の調べ方・確認方法は、全国健康保険協会が毎年発表する「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から確認できます。(標準報酬月額の調べ方は後ほど詳しく解説します。)
参考までに以下は、東京都の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」です。
参照元:令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・構成年金保険の保険料額表(東京支部)
標準報酬月額と給与(額面)との違いとは?
標準報酬月額と、毎月支払われる「給与(額面給与)」は、社会保険料計算の基となる点で関連しますが、金額そのものは異なります。この違いを正しく理解することが、社会保険料の計算や手続きを正確に行うための重要な第一歩です。
給与(給料)と標準報酬月額の違いを下記の表にまとめています。
| 項目 | 給与(給料) | 標準報酬月額 |
| 目的・性質 | 労働の対価として従業員に実際に支払われる金額(基本給、諸手当など) | 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)を計算するための基準額 |
| 変動性 | 残業時間や手当により毎月変動する可能性がある | 原則として1年間は固定(年1回の定時決定や昇給・降給時の随時改定で見直しされる) |
| 指すもの | 税金や社会保険料が引かれる前の「額面」の金額 | 実際の報酬を基に等級区分に当てはめた「みなし報酬月額」 |
| 計算例 | 基本給20万円 + 残業代3万円 + 通勤手当1万円 = 24万円 | 報酬月額23万円以上25万円未満なら24万円(健康保険20等級などに該当)※ |
※等級は保険の種類や都道府県により異なります。
このように、標準報酬月額は、社会保険料を計算しやすくするために、実際の給与(報酬)を基に一定のルールで決定される「みなしの月額報酬」 と言えます。毎月の給与額が残業代などで変動しても、原則として標準報酬月額は1年間変わらないため、毎月の社会保険料額も安定します。(ただし、年に1回の定時決定や、給与が大幅に変動した場合の随時改定で見直されます。)
重要な点として、給与(額面給与)も標準報酬月額も、実際に従業員が受け取る「手取り額」とは異なります。 手取り額は、額面給与から社会保険料や税金が控除された後の金額です。
なお、標準報酬月額の計算の基礎となる「報酬」には、基本給だけでなく通勤手当や住宅手当なども含まれる場合があります。どの手当が報酬に含まれ、どの手当が含まれないかについては、後ほど詳しく解説します。
標準報酬月額の算出方法と等級表の見方
標準報酬月額は、原則として特定の期間に従業員へ支払われた報酬の平均額(これを「報酬月額」といいます)を算出し、その金額を「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の等級区分に当てはめて決定します。
算出の基礎となる報酬を集計する期間は、標準報酬月額を決定・改定するタイミング(例えば、年に1回の定時決定、入社時の資格取得時決定、給与が大幅に変動した際の随時改定など)によって異なります。
ここでは、最も基本的な算出方法である「定時決定」のケースを例に、具体的な計算方法と保険料額表(等級表)の見方を解説します。
標準報酬月額の算出例(定時決定の場合)と等級の調べ方
定時決定では、毎年4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額(報酬月額)を基に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
【ステップ1:報酬月額の計算】
まず、対象となる従業員の4月、5月、6月に支払われた報酬(基本給や各種手当など、標準報酬月額の対象となるもの全て)の合計額を3で割って、報酬月額を算出します。
| ◯計算式 (4月に支払われた報酬額 + 5月に支払われた報酬額 + 6月に支払われた報酬額) ÷ 3 = 報酬月額 |
【計算例】
| 4月に支払われた報酬 | 250,000円 |
| 5月に支払われた報酬 | 260,000円 |
| 6月に支払われた報酬 | 255,000円 |
この場合の報酬月額は、 (250,000円 + 260,000円 + 255,000円) ÷ 3 = 255,000円 となります。
【ステップ2:保険料額表(等級表)での確認】
次に、算出した報酬月額を、事業所の所在地がある都道府県の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に当てはめて、該当する等級と標準報酬月額を確認します。
【確認例(東京都・令和7年度の場合)】
| 等級 | 月額 | 報酬月額 |
| 18(15) | 220,000 | 210,000〜230,000 |
| 19(16) | 240,000 | 230,000〜250,000 |
| 20(17) | 260,000 | 250,000〜270,000 |
| 21(18) | 280,000 | 270,000〜290,000 |
報酬月額が255,000円の場合、東京都の保険料額表を見ると、「報酬月額の範囲」が250,000円~270,000円の区分に該当します。したがって、この従業員の標準報酬月額は以下のようになります。
- 健康保険: 20等級 / 標準報酬月額 260,000円
- 厚生年金保険: 17等級 / 標準報酬月額 260,000円
【注意点:支払基礎日数】
報酬月額の計算に含める月は、原則として報酬の支払基礎日数(給与計算の対象となった日数)が17日以上ある月のみです。
例えば、4月、5月、6月のうち、5月の支払基礎日数が16日だった場合、5月分の報酬は計算から除外し、4月と6月の報酬の平均額で報酬月額を算出します((4月報酬 + 6月報酬) ÷ 2)。
3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、原則として従前の標準報酬月額がそのまま適用されます(ただし、後述する短時間就労者の特例があります)。
支払基礎日数の数え方は、月給制(暦日数)か日給・時給制(出勤日数)か、また欠勤控除の有無によって異なりますので、自社の給与規定を確認する必要があります。
短時間労働者(パート・アルバイト)の算出方法
パートタイマーやアルバイトなど、短時間で勤務する労働者の標準報酬月額の算出(特に定時決定時)においては、支払基礎日数の扱いに特別なルールが適用される場合があります。通常の労働者とは条件が異なるため、注意が必要です。
まず、短時間労働者は大きく2つの区分(短時間就労者と短時間労働者)に分けられ、それぞれ定時決定の算出方法が異なります。
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である被保険者を指します。フルタイムに近い働き方をするパートタイマーなどが該当。
■定時決定の計算方法
| 1か月でも17日以上の月がある | 17日以上の月の報酬平均額をもとに決定 |
| 15日以上17日未満の月がある | 15日以上17日未満の月の報酬平均額をもとに決定 |
| 3ヶ月とも15日未満 | 以前決定した標準報酬月額を継続 |
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満であり、かつ以下の要件を全て満たす被保険者。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヶ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が88,000円以上
- 学生ではない
- 特定適用事業所(※)または国・地方公共団体に勤務している (※特定適用事業所:厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所。
■定時決定の計算方法
| 1か月でも11日以上の月がある | 11日以上の月の報酬平均額をもとに決定 |
| 3ヶ月とも11日未満 | 以前決定した標準報酬月額を継続 |
【実務上のチェックポイント】
- [ ] 対象となる従業員が「短時間就労者」か「短時間労働者」のどちらに該当するかを正確に判断する。
- [ ] 該当する区分の支払基礎日数のルールに基づいて、報酬月額の計算対象月を正しく選択する。
- [ ] 特に「短時間労働者」の要件(週20時間、月額8.8万円など)は法改正等で変更される可能性があるため、常に最新情報を確認する。
このように、短時間で働く方の場合は、その働き方によって適用されるルールが異なります。算定基礎届を作成する際には、従業員一人ひとりの区分と支払基礎日数を確認し、適切な方法で標準報酬月額を算出・届け出ることが重要です。
標準報酬月額が決定されると、それに基づいて従業員が負担する毎月の健康保険料、厚生年金保険料、そして介護保険料(40歳~64歳の場合)の具体的な金額が計算されます。社会保険料は、原則として会社と従業員で半分ずつ負担(労使折半)します。
ここでは、それぞれの保険料の計算方法について解説します。
健康保険料の計算方法
健康保険料は、以下の計算式で算出します。
| 計算式: 標準報酬月額 × 健康保険料率 = 健康保険料(月額) |
算出された健康保険料を会社と従業員で半分ずつ負担します。
健康保険料率は、加入している健康保険組合によって異なります。全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、都道府県ごとに保険料率が設定されており、毎年見直しが行われます。
また、40歳から64歳までの従業員(介護保険第2号被保険者)については、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が上乗せされます。
自社の従業員に適用される最新の保険料率は、必ず協会けんぽや加入している健康保険組合の公式サイトで確認してください。
参照:都道府県毎の保険料率|全国健康保険協会 (協会けんぽ 令和7年度)
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は、以下の計算式で算出します。
| 計算式: 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 = 厚生年金保険料(月額) |
算出された厚生年金保険料も、会社と従業員で半分ずつ負担します。厚生年金保険料率は、現在 18.3% で全国一律となっています(令和6年度時点)。
参照:厚生年金保険料額表|日本年金機構 (日本年金機構 令和2年9月分~)
※厚生年金基金に加入している場合は、基金ごとに保険料率の一部が免除される場合があります。
標準報酬月額の計算ツール(簡易版)
従業員の月額給与(報酬月額)、年齢、都道府県を入力すると、該当する標準報酬月額の等級、健康保険料(従業員負担分)、厚生年金保険料(従業員負担分)の概算をシミュレーションできます。
標準報酬月額簡易計算ツール
計算結果
厚生年金保険
等級:
標準報酬月額: 円
保険料(労働者負担分): 円
健康保険
等級:
標準報酬月額: 円
保険料率: %
保険料(労働者負担分): 円
介護保険
保険料率: %
保険料(労働者負担分): 円
社会保険料合計(月額)
円
労働保険料との違い
ここで注意したいのが、労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の計算方法です。
社会保険料(健康保険・厚生年金)が「標準報酬月額」を基準にするのに対し、労働保険料は、従業員に支払われた「賃金総額」(実際に支払った給与や手当の合計額)にそれぞれの保険料率を掛けて計算します。
- 雇用保険料 = 賃金総額 × 雇用保険料率
- 労災保険料 = 賃金総額 × 労災保険料率 (全額事業主負担)
計算の基礎となるものが異なるため、混同しないように注意が必要です。
労働保険については下の記事で詳しく解説しています。
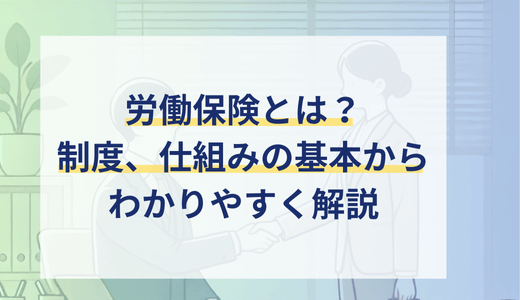 【社労士監修】労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく解説
【社労士監修】労働保険とは?制度、労災・雇用保険の違いを簡単にわかりやすく解説
社会保険料の計算に不安がある、概算の金額を知りたいという方は、社会保険料の計算が簡易的にできるシミュレーションツールをご活用ください。
自動計算ツールで算出できる社会保険料には、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、そして標準報酬月額の金額と等級が含まれます。また早見表もご確認いただけます。
標準報酬月額を正しく計算するためには、どの給与や手当が計算の基礎となる「報酬」に含まれ、どれが含まれないのかを正確に理解しておく必要があります。判断の基本的な考え方は、「労働の対償として、事業所から定期的または継続的に受けるものかどうか」です。
ここでは、標準報酬月額の対象となる報酬とならない報酬の具体的な例を解説します。
対象となるもの
標準報酬月額の計算の基礎となる報酬には、基本給だけでなく、毎月固定的に支払われる各種手当や、労働の対価として支払われる変動的な手当などが広く含まれます。金銭(通貨)だけでなく、現物で支給されるものも報酬とみなされます。
【対象となる報酬の具体例】
| 報酬の種類 | 具体例 | 備考 |
| 基本賃金 | 月給、週給、日給、時給など | 雇用形態に関わらず、基本的な賃金は対象です。 |
| 諸手当(固定的) | 役付手当、職階手当、勤務地手当(地域手当)、家族手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当(※1) | 毎月決まって支払われる性質の手当は対象となります。 |
| 諸手当(変動的) | 残業手当(時間外勤務手当)、深夜手当、休日手当、宿直手当、日直手当、精勤手当、皆勤手当、能率手当、奨励給など | 勤務実績などに応じて変動する手当も、労働の対償であれば対象です。 |
| 賞与(年4回以上) | 就業規則等で年4回以上の支給が定められている賞与(ボーナス) | 年間の合計額を12で割った額を各月の報酬に加えて算定します。(※2) |
| 現物給与 | 通勤定期券、回数券、社宅・寮の提供(※3)、食事・食事券の支給(※4)、被服(制服・作業着以外)、自社製品の支給など | 金銭以外で支給されるものも、定められた評価額に基づいて報酬とみなされます。 |
| その他 | 休職手当、継続的に支給される見舞金など |
(※1)通勤手当
税法上非課税とされる金額であっても、社会保険においては全額が報酬に含まれます。定期券などで支給される場合も同様です。
(※2)年4回以上の賞与
算定基礎届や月額変更届の際に、前年7月~当年6月(または変動月前の1年間)に受けた賞与の合計額÷12を、各月の報酬額に上乗せして計算します。
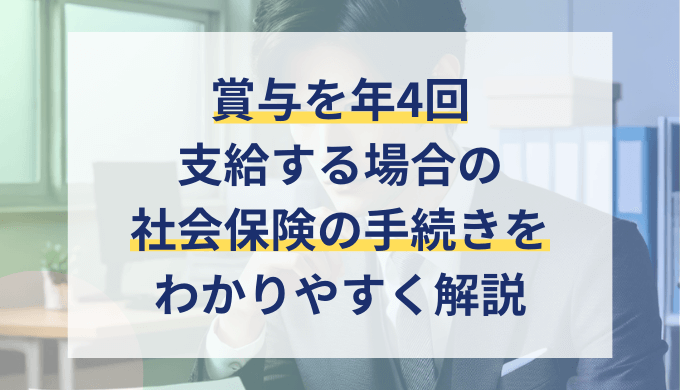 賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
賞与を年4回以上支給する時の社会保険の手続きを年3回以下の場合との違いを含めて解説!
(※3)社宅・寮
無償または低い家賃で提供される場合、都道府県ごとに定められた「現物給与の価額」に基づいて評価された額が報酬となります。
(※4)食事
従業員の負担額が、厚生労働大臣が定める価額(都道府県により異なる)の3分の2未満の場合、その差額が報酬となります。
対象とならないもの
一方で、臨時に支払われるものや、実費弁償的な性質のもの、恩恵的に支給されるものなどは、原則として標準報酬月額の対象となる報酬には含まれません。
【対象とならない報酬の具体例】
| 報酬の種類 | 具体例 | 備考 |
| 賞与(年3回以下) | 賞与、期末手当、決算手当など(年3回以下の支給) | 「標準賞与額」の対象となり、別途賞与支払届の提出と保険料納付が必要です。(※5) |
| 臨時的な収入 | 大入袋、見舞金(傷病見舞金、災害見舞金など)、結婚祝金、慶弔費 | 恩恵的・一時的な支給であり、労働の対償とはみなされません。 |
| 退職金・解雇予告手当 | 退職時に支払われる手当 | 退職後の生活保障等の性質を持つため、報酬には含まれません。 |
| 実費弁償的なもの | 出張旅費、赴任旅費、交際費、作業用品代(会社が負担すべきもの) | 業務遂行に必要な経費の立て替え・精算であり、報酬とは性質が異なります。 |
| 公的保険給付など | 傷病手当金、出産手当金、労災保険の休業(補償)給付 | 健康保険や労災保険から支給されるものであり、事業所からの報酬ではありません。 |
| 公的保険給付など | 制服、作業着(業務に必要なもの)、食事(本人負担が価額の3分の2以上の場合) | 業務遂行に直接必要不可欠なものや、本人 |
(※5)年3回以下の賞与
標準報酬月額の計算には含めませんが、「標準賞与額」として別途保険料計算の対象となります。
ボーナスを支給した場合は、賞与支払届の提出が必要になります。賞与支払届について下の記事で詳しく解説しています。
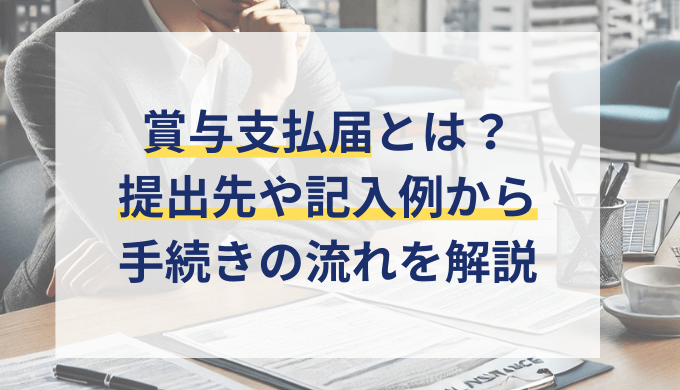 賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
賞与支払届とは?書き方のポイントや記入例、提出先から手続きの流れを解説
【実務上のチェックポイント】
[ ] 各種手当が「固定的」か「変動的」かだけでなく、「労働の対償」として「定期的または継続的に」支払われるものかを判断する。 [ ] 「現物給与」に該当するものがないか確認し、ある場合は適切な評価額を算定するルールを把握する。(都道府県ごとの価額を確認) [ ] 賞与の支給回数(年3回以下か、4回以上か)を正確に把握し、標準報酬月額に含めるか、標準賞与額として扱うかを正しく判断する。 [ ] 在宅勤務手当など、新しい手当については、その性質(通信費・光熱費の実費弁償部分か、給与としての性質を持つ部分か)を判断し、適切に処理する。(不明な場合は専門家への確認を推奨)報酬の範囲を正しく判断することは、社会保険料の計算ミスを防ぐ上で非常に重要です。不明な点があれば、日本年金機構のガイドラインを参照したり、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
標準報酬月額は、一度決定されると原則として1年間(通常は9月から翌年8月まで)適用されますが、常に固定されているわけではありません。
従業員の入社や退職、給与の変動、ライフイベントなどに応じて、標準報酬月額が決定されたり、見直されたり(改定)するタイミングが主に5つあります。
それぞれのタイミングで必要となる手続きが異なるため、事業主や人事・労務担当者は、どのケースに該当するのかを正確に把握し、適切な手続きを行う必要があります。
ここでは、標準報酬月額が決定・改定される5つの主なタイミングと、それぞれの手続きについて解説します。
1. 定時決定(毎年7月算定基礎届)
定時決定とは、年に一度、全従業員の標準報酬月額を見直すための手続きです。毎年7月1日時点での全被保険者を対象に、その年の4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額(報酬月額)を算出し、その年の9月から翌年8月までの1年間に適用される新しい標準報酬月額を決定します。
これは、実際の報酬額と標準報酬月額との間に大きな乖離が生じるのを防ぐために行われます。
| 対象者 | 毎年7月1日現在の全ての被保険者。 ■以下の該当者は対象外 ・6月1日以降に被保険者資格を取得した人 ・7月に随時改定(月額変更届を提出)が行われる人 ・8月または9月に随時改定が行われる予定の人(申出が必要) |
| 算定基礎 | 4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額(報酬月額) |
| 手続き | 事業主が「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を作成し、原則として毎年7月1日から7月10日までに管轄の年金事務所または事務センターへ提出。 |
| 適用期間 | 決定された新しい標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用。 |
| 【定時決定 実務チェックリスト】 [ ] 7月1日時点の全被保険者をリストアップしたか? [ ] 対象外となる従業員(6月以降入社、7~9月随時改定予定者など)を除外したか? [ ] 4月、5月、6月それぞれの報酬額(対象となる手当を含む)は正確か? [ ] 各月の支払基礎日数が17日以上あるか確認したか?(17日未満の月は除外) [ ] 短時間労働者・短時間就労者の支払基礎日数ルールを適用したか? [ ] 算定基礎届の記入漏れや計算ミスはないか? [ ] 提出期限(原則7月10日)までに提出できるか? |
算定基礎届については下記の記事も合わせて確認してください。
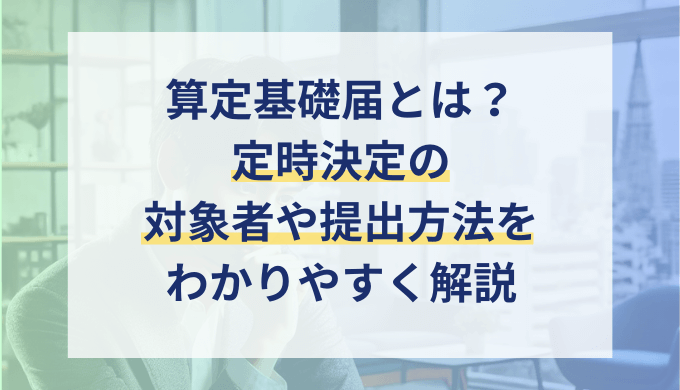 算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
算定基礎届とは?対象者や提出期限、作成時の注意点をわかりやすく解説
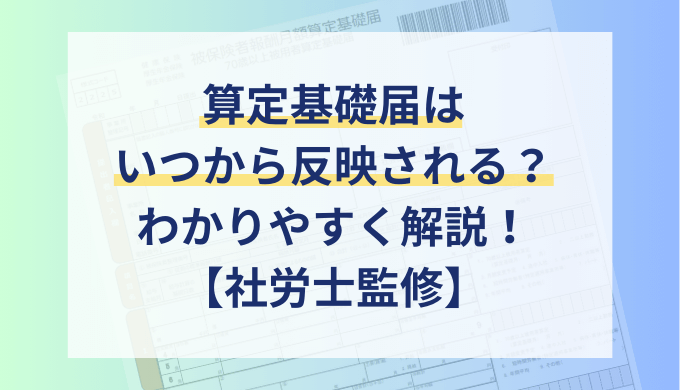 算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説
算定基礎届(定時決定)はいつから反映?社会保険料の変更時期と給与計算の注意点を社労士が解説
2. 随時改定(昇給・降給で2等級以上差)
随時改定とは、昇給や降給などにより月々の給与額(固定的賃金)に大幅な変動があった場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。「月額変更」とも呼ばれます。
これにより、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じた状態が長期間続くことを防ぎます。
随時改定は、以下の3つの条件すべてに該当した場合に行われます。
①固定的賃金の変動
昇給・降給、給与体系の変更(日給から月給へ等)、固定的な手当(住宅手当、役付手当、通勤手当など)の新設・廃止・変更などにより、固定的賃金に変動があったこと。
残業手当や能率給といった非固定的賃金のみの変動では、随時改定の対象とはなりません。
②2等級以上の差
固定的賃金の変動があった月以後継続した3ヶ月間に支払われた報酬の平均額(報酬月額。残業代などの非固定的賃金も含む)から算出した標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたこと。
③支払基礎日数17日以上
固定的賃金の変動があった月以後継続した3ヶ月間すべてにおいて、報酬の支払基礎日数が17日以上であること。(短時間労働者の場合は11日以上)
| 手続き | 上記3つの条件をすべて満たした場合、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」(月額変更届)を速やかに管轄の年金事務所または事務センターへ提出 |
| 適用期間 | 改定された新しい標準報酬月額は、固定的賃金の変動が反映された給与が支払われた月から起算して4ヶ月目から、次の定時決定(通常は8月)まで適用 |
月額変更届については下の記事も合わせて確認してください。
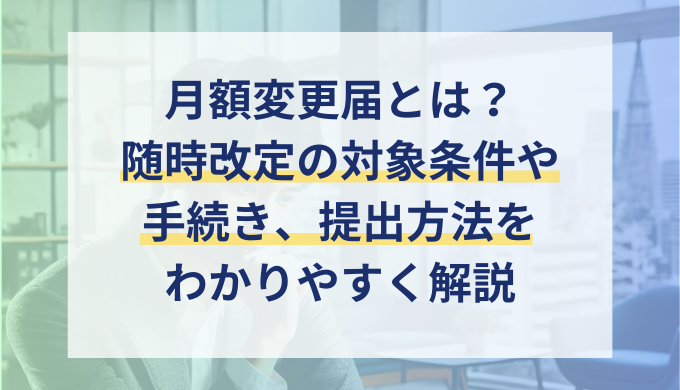 社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
| 【随時改定 実務チェックリスト】 [ ] 昇給・降給など「固定的賃金」の変動があったか?(残業代のみの増減ではないか?) [ ] 変動後3ヶ月間の報酬月額を計算し、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があるか? [ ] 変動後3ヶ月間すべての支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上あるか? [ ] 上記3つの条件をすべて満たしているか? [ ] 条件を満たした場合、月額変更届を速やかに提出する準備はできているか? |
3. 資格取得時決定(新入社員の入社時)
資格取得時決定とは、新入社員の採用など、新たに従業員が健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得した際に、最初の標準報酬月額を決定する手続きです。
- 決定方法: 被保険者資格を取得した時点(入社日など)の報酬見込み額に基づいて決定します。具体的には、雇用契約書などで定められた基本給や諸手当(通勤手当などを含む)を基に、1ヶ月あたりの報酬額を算出し、保険料額表に当てはめて標準報酬月額を決定します。
- 日給や時間給の場合は、同様の業務に従事し同様の報酬を受ける他の従業員の報酬額などを参考に決定します。
- 手続き: 事業主は、従業員が被保険者資格を取得した日から原則として5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所または事務センターへ提出しなければなりません。
- 適用期間: 決定された標準報酬月額は、資格取得日からその年の8月まで(6月1日から12月31日までに資格取得した場合は翌年の8月まで)適用されます。その後は、定時決定によって見直されます。
| 【資格取得時決定 実務チェックリスト】 [ ] 入社した従業員の雇用契約書等を確認したか? [ ] 基本給、固定手当、通勤手当など、報酬見込み額の計算に必要な情報を把握したか? [ ] 日給・時間給の場合は、適切な報酬見込み額を算定したか? [ ] 算出した報酬見込み額を保険料額表に当てはめ、正しい標準報酬月額を決定したか? [ ] 被保険者資格取得届を、資格取得日(入社日など)から5日以内に提出できるか? |
4. 産前産後休業終了時改定
産前産後休業終了時改定とは、産前産後休業を終了して職場復帰した従業員が、休業前と比べて報酬が低下した場合に、本人の申出によって標準報酬月額を見直すことができる制度です。
育児のために時短勤務を選択するなどして報酬が下がった場合に、社会保険料の負担を軽減することを目的としています。
| 対象者 | 産前産後休業を終了し、引き続き同じ事業所で働く被保険者で、休業終了日(※)の翌日が含まれる月以後3ヶ月間に支払われた報酬の平均額(報酬月額)に基づく標準報酬月額が、休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上低下した場合。 (※)出産日が出産予定日後の場合は、出産日から起算して産後休業期間(通常56日)を計算した最終日の翌日。 |
| 手続き | 従業員本人からの申出があった場合に、事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届」を管轄の年金事務所または事務センターへ提出。 申出は、休業終了日の翌日から2ヶ月以内に行う必要がある。 |
| 適用期間 | 改定された新しい標準報酬月額は、休業終了日の翌日から起算して4ヶ月目から、次の定時決定(または随時改定)まで適用。 |
5. 育児休業終了時改定
育児休業終了時改定は、産前産後休業終了時改定と同様に、育児休業を終了して職場復帰した従業員が、休業前と比べて報酬が低下した場合に、本人の申出によって標準報酬月額を見直すことができる制度です。
特に、育児のために時短勤務などを選択した場合の保険料負担を軽減する目的があります。
| 対象者 | 3歳未満の子を養育するために育児休業等を終了し、引き続き同じ事業所で働く被保険者で、休業終了日の翌日が含まれる月以後3ヶ月間に支払われた報酬の平均額(報酬月額)に基づく標準報酬月額が、休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上低下した場合。 支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外。 |
| 手続き | 従業員本人からの申出があった場合に、事業主が「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を管轄の年金事務所または事務センターへ提出。 申出は、休業終了日の翌日から2ヶ月以内に行う必要がある。 |
| 適用期間 | 改定された新しい標準報酬月額は、休業終了日の翌日から起算して4ヶ月目から、次の定時決定(または随時改定)まで適用。 |
| 【産休・育休後改定 実務チェックリスト】 [ ] 復職する従業員に、産休後・育休後改定の制度について説明したか? [ ] 従業員から改定の申出があったか? [ ] 復職後3ヶ月間の報酬額を正確に計算したか?(支払基礎日数17日未満の月は除外) [ ] 休業前の標準報酬月額と比較して1等級以上の差があるか確認したか? [ ] 該当する場合、適切な届出書(産休後・育休後)を作成し、提出期限内に提出できるか? |
標準報酬月額が変更される5つのタイミングを正しく理解し、それぞれに必要な手続きを適切な時期に行うことが、社会保険事務を円滑に進める上で非常に重要です。
【関連記事】
社会保険料の変更はいつから?改定のタイミングや注意点を社労士がわかりやすく解説
従業員の標準報酬月額は、いくつかの方法で調べたり確認したりすることができます。事業主・人事担当者として正確な情報を把握することはもちろん、従業員から質問があった際に説明できるよう、主な確認方法を知っておきましょう。
毎年の「標準報酬決定通知書」を読むポイント
事業主にとって、従業員の標準報酬月額を公式に確認する最も確実な方法は、日本年金機構から送付される「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」を確認することです。
この通知書は、主に以下のタイミングで事業所に届きます。
| 定時決定後(通常毎年9月頃) | 4月~6月の報酬に基づいて決定された、9月からの新しい標準報酬月額が記載 |
| 資格取得時決定後 | 新入社員などの資格取得手続き後に送付 |
| 随時改定後 | 月額変更届の提出・処理後に送付 |
| 産休・育休終了時改定後 | 各改定手続き後に送付 |
【通知書を読む際のチェックポイント】
- 対象となる被保険者氏名・整理番号: どの従業員の情報かを確認。
- 決定(改定)後の標準報酬月額: 健康保険と厚生年金保険それぞれの標準報酬月額を確認。
- 等級: 決定された標準報酬月額がどの等級に該当するかを確認。
- 適用年月(その標準報酬月額がいつから適用されるのか)の確認。
この通知書は、社会保険料の計算や給与計算の基礎となる重要な書類です。内容を正確に確認し、適切に保管しておく必要があります。
給与明細と保険料額表から確認する手順
従業員自身が自分の標準報酬月額や等級のおおよその目安を知りたい場合や、事業主・担当者が検算したい場合には、毎月の給与明細と公開されている保険料額表を使って推定することができます。
【確認手順】
給与明細に記載されている「健康保険料」と「厚生年金保険料」の控除額(従業員負担分)を確認します。介護保険料(40歳~64歳の場合)が含まれているかも確認しましょう。
事業所が所在する都道府県の最新の「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を用意します。協会けんぽのウェブサイトなどで確認できます。
参照:都道府県毎の保険料率|全国健康保険協会 (協会けんぽ 令和7年度)
険料額表の中から、給与明細の健康保険料(従業員負担分)と厚生年金保険料(従業員負担分)の金額が記載されている行を探します。(表には通常、折半額が記載されています)
年齢によって介護保険料の有無が異なるため、該当する欄(介護保険第2号被保険者に該当するか否か)を確認します。
保険料額が一致する行に記載されている「標準報酬月額」と「等級」を確認します。これが、その従業員に適用されている標準報酬月額と等級の目安となります。
【注意点】
- この方法はあくまで推定です。正式な金額は「標準報酬決定通知書」で確認する。
- 健康保険組合に加入している場合は、協会けんぽとは保険料率が異なるため、組合独自の保険料額表を確認する必要がある。
- 給与計算ソフトなどでの端数処理の違いにより、完全に一致しない場合もある。
こちらで紹介した方法で標準報酬月額を確認し、日々の給与計算や社会保険手続きに役立ててください。
標準報酬月額は社会保険料計算の基礎となる重要な数値ですが、その取り扱いにはいくつかの注意点があります。計算ミスや手続き漏れは、追徴金や延滞金、従業員からの信頼損失につながる可能性もあるため、実務担当者は以下の点に特に注意して業務にあたる必要があります。
保険料額表は料率が更新されるから都度チェック
健康保険料率は、都道府県ごと、そして毎年度(通常3月分(4月納付分)から)改定されるのが通例です。協会けんぽの料率は毎年2月頃に発表されます。また、介護保険料率も変更されることがあります。厚生年金保険料率は現在18.3%で固定されていますが、将来的に変更がないとは限りません。
給与計算を行う際は、必ず最新の保険料額表を参照するように習慣づけましょう。古い料率で計算してしまうと、保険料の徴収額に過不足が生じ、後で精算が必要になるなど、煩雑な事務処理が発生します。
| 【チェックポイント】毎年2月~3月頃に協会けんぽや加入健保組合のウェブサイトを確認し、最新の保険料額表を入手・適用する。 |
労働保険料は標準報酬月額を基準としない
社会保険料(健康保険・厚生年金)と労働保険料(雇用保険・労災保険)では、保険料計算の基礎が異なります。
| 社会保険料 | 標準報酬月額(および標準賞与額)が基準 |
| 労働保険料 | 実際に支払った賃金総額が基準 |
この違いを混同すると、保険料計算を誤る原因となります。特に雇用保険料は従業員負担分もあるため、計算ミスは給与の手取り額にも影響します。それぞれの計算方法を正しく理解しておきましょう。
傷病手当金・出産手当金も標準報酬月額が基になる
標準報酬月額は、毎月の保険料計算だけでなく、従業員が病気やケガで休業した際に支給される「傷病手当金」や、産休中に支給される「出産手当金」の支給額を計算する際の基礎にもなります。
標準報酬月額が実態より低く設定されていると、これらの手当金の支給額も少なくなってしまいます。適正な手続きで、実態に合った標準報酬月額を決定しておくことは、従業員のセーフティネットを守る上でも重要です。
報酬範囲の誤認(特に手当・現物給与)
標準報酬月額の計算ミスで特に多いのが、計算基礎となる「報酬」の範囲の誤認です。どの手当を含め、どれを含めないかの判断は正確に行う必要があります。
| ◯よくある誤り税法上非課税の通勤手当を、社会保険でも対象外としてしまう。年3回以下の賞与を、標準報酬月額の計算に含めてしまう(正しくは標準賞与額の対象)。食事や社宅などの現物給与の評価・算入を忘れる、または評価額を誤る。在宅勤務手当など、新しい手当の扱いを誤る。 |
前述した「対象となるもの/ならないもの」の表や具体例を参考に、迷った場合は必ず日本年金機構のガイドラインを確認するか、専門家である社労士に相談しましょう。
随時改定の条件見落とし・誤適用
随時改定(月額変更)は、適用条件がやや複雑なため、誤りが生じやすい手続きです。
| ◯よくある誤り残業代の増減など、固定的賃金の変動がないのに月額変更届を提出してしまう。固定的賃金は変動したが、変動後3ヶ月間の平均報酬月額が2等級以上の差に満たないのに届出をしてしまう。変動後3ヶ月間の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)未満の月があるのに届出をしてしまう。固定的賃金の定義を誤解している(例:一時的な手当を固定的賃金とみなす)。 |
随時改定の3つの条件(①固定的賃金の変動、②2等級以上の差、③支払基礎日数17日以上)をすべて満たしているか、チェックリストなどを活用して慎重に確認しましょう。
手続きの遅延・漏れ
算定基礎届や月額変更届などの各種手続きには、提出期限が定められています。
| 算定基礎届 | 原則 毎年7月10日まで |
| 月額変更届 | 随時改定の要件に該当後、速やかに |
| 資格取得届 | 資格取得日(入社日など)から5日以内 |
これらの届出が遅れたり、提出を忘れたりすると、保険料の遡及訂正や延滞金が発生する可能性があります。また、年金事務所から指導を受けることもあります。
各手続きの期限を管理し、余裕を持ったスケジュールで準備・提出を行いましょう。特に随時改定は発生ベースでの対応となるため、給与計算時に常にチェックする体制を整えることが重要です。
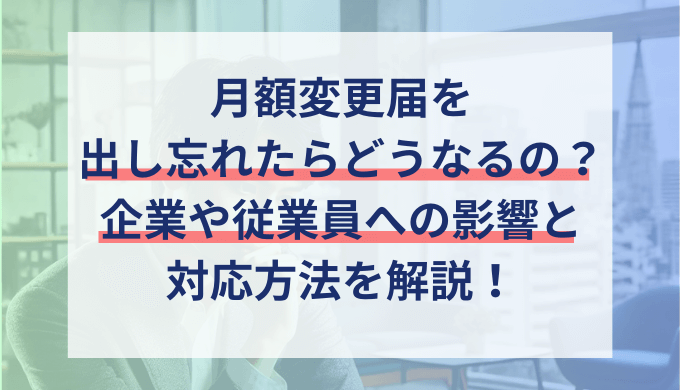 月額変更届(随時改定)を申請しなかったらどうなる?出し忘れた場合の罰則と対応方法を解説
月額変更届(随時改定)を申請しなかったらどうなる?出し忘れた場合の罰則と対応方法を解説
標準報酬月額に関して、実務担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
標準報酬月額はどこで確認できますか?
主な確認方法は2つあります。
◯事業主・担当者の場合
日本年金機構から送付される「被保険者標準報酬決定通知書」で確認するのが最も確実です。定時決定後(9月頃)や資格取得時、随時改定後などに届きます。
◯従業員の場合(目安として)
毎月の給与明細に記載されている健康保険料・厚生年金保険料の控除額と、協会けんぽ等が公開している保険料額表を照らし合わせることで、ご自身の標準報酬月額や等級を推定できます。
詳しくは、前述の「標準報酬月額の調べ方・確認方法」の項目をご参照ください。
4月~6月の残業が多いと、社会保険料は高くなりますか?
4月、5月、6月の残業が多いと社会保険料が高くなる可能性があります。
毎年7月に行われる定時決定では、4月、5月、6月に支払われた報酬(残業手当を含む)の平均額を基に、その年の9月からの標準報酬月額が決定されます。
そのため、この期間に残業が多く、支払われた報酬額が増えると、標準報酬月額の等級が上がり、結果として9月以降の社会保険料が高くなることがあります。
賞与は標準報酬月額に含まれますか?
原則として賞与は含まれません。ただし、例外があります。
◯年3回以下の賞与(ボーナスなど)
標準報酬月額の計算基礎となる「報酬」には含まれません。その代わり、「標準賞与額」として、別途、賞与から保険料が徴収されます(賞与支払届の提出が必要です)。
◯年4回以上の賞与
就業規則などで年4回以上の支給が定められている場合は、賞与ではなく「報酬」とみなされ、標準報酬月額の計算に含まれます。この場合、年間の賞与合計額を12で割った額を、各月の報酬に上乗せして標準報酬月額を計算します。
賞与の支給回数によって扱いが異なる点に注意が必要です。
標準報酬月額が高いとどんなメリット・デメリットがありますか?
標準報酬月額が高いことには、メリットとデメリットの両方があります。
①将来受け取る厚生年金額が多くなる。
厚生年金の受給額は、加入期間中の標準報酬月額に基づいて計算されるため、標準報酬月額が高いほど年金額も増えます。
②傷病手当金や出産手当金の支給額が多くなる。
これらの手当金の1日あたりの支給額も、標準報酬月額を基に計算されるため、支給額が増える可能性があります。
毎月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)の負担が大きくなる。
標準報酬月額が高いほど、等級が上がり、毎月の保険料負担(従業員負担分・会社負担分ともに)が増加します。
つまり、現在の保険料負担は増えますが、将来の年金受給額や万が一の際の給付額は手厚くなる、という関係にあります。
本記事では、社会保険料や将来の給付額の基礎となる「標準報酬月額」について、基本的な考え方から実務上の注意点まで解説しました。
標準報酬月額は、実際の給与を等級に当てはめた「みなし報酬月額」であり、給与額面や手取りとは異なります。この基準額は定時決定だけでなく、随時改定や入社時、産休・育休後も見直され、報酬範囲の正確な判断が不可欠です。
算定基礎届や月額変更届などの手続きは期限内に正確に行う必要があり、計算ミスや届出漏れは追徴金等のリスクを伴います。また、保険料率は毎年度改定されるため、最新情報の確認も欠かせません。
標準報酬月額の仕組み、計算方法、調べ方、そして各種手続きのルールを正しく理解しておくことが、これらの複雑な業務を適切に進める上での大前提となります。
特に、年に一度の定時決定や、随時改定の要件判断は、担当者にとって負担が大きく、専門知識も求められます。
正確かつ効率的な手続きのためには専門家である社労士に相談、申請代行することも検討しましょう。
社労士クラウドのスポット申請代行サービス
「算定基礎届の作成が毎年大変…」「随時改定の条件判断に自信がない」「専門家に頼みたいが、顧問契約は費用が…」このようなお悩みをお持ちではありませんか? 標準報酬月額に関する手続きは専門知識が必要で、ミスは追徴金のリスクにも繋がります。
そんな課題を解決するのが、「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスです。
当サービスでは、今回解説した標準報酬月額に関わる算定基礎届や月額変更届の作成・提出代行をはじめ、社会保険手続きを必要な業務だけスポット(単発)でご依頼いただけます。
顧問契約は不要ですので、費用を抑えつつ、専門家である社会保険労務士のサポートを受けることが可能です。
社労士が最新の法令に基づき、正確かつ迅速に手続きを代行することで、お客様は面倒な手続きから解放され、コア業務に集中いただけます。オンラインで全国どこからでもご依頼可能です。
ぜひ一度「社労士クラウド」のスポット代行サービスをご検討ください。
の健全な運営と従業員の安心につながります。5日を過ぎてしまった場合も、社労士の専門知識とサポートを受けることで、大きな問題に発展することなく、会社の安定した運営が可能になります。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 1,800社以上の社会保険手続き実績|

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 2,000社以上の社会保険手続き実績|