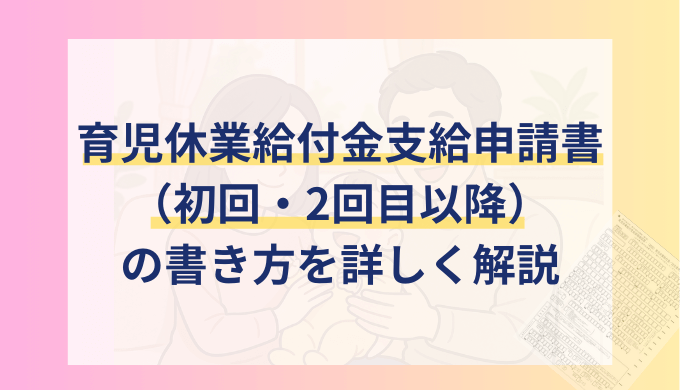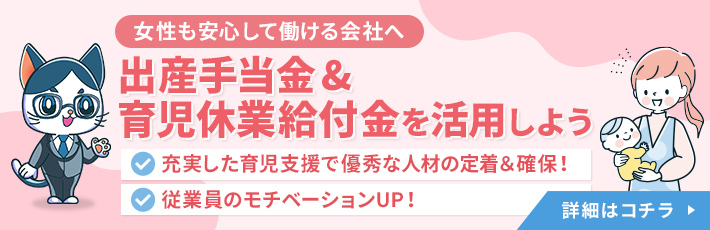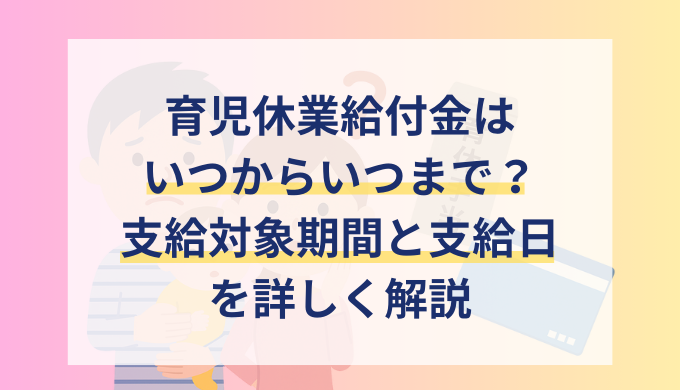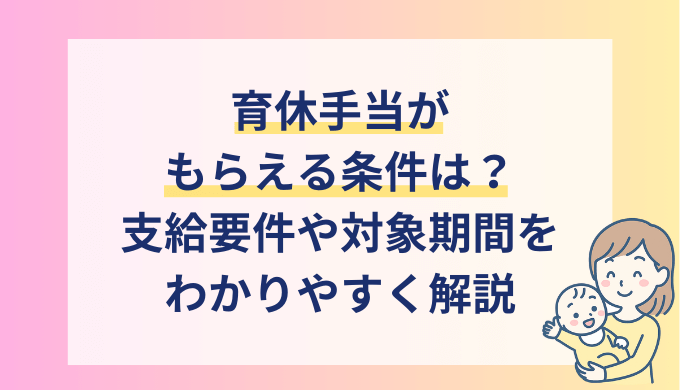育児休業給付金支給申請書は、育児休業を取得する従業員の生活を支える重要な手続きですが、初回用と2回目以降用で様式が異なり、記入項目も多岐にわたるため、正しい書き方に迷う方が多くいます。特に初めて手続きを担当される方や、設立間もない企業の担当者の方にとっては、戸惑う場面も多いのではないでしょうか。
この記事では、「育児休業給付金支給申請書」の正しい書き方を、具体的な記入例(画像付き)でわかりやすく解説します。初回申請時に使用する「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」や「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」から、2回目以降の申請書、さらに延長する場合の記入方法まで詳しく紹介。
また、申請に必要な添付書類や提出期限、よくある記入ミスとその防止策についても具体的に説明しています。
特に2025年4月から施行された「出生後休業支援給付金」との関連にも触れ、制度を総合的に理解できる内容となっています。会社側と従業員がともに知っておくべき知識を身につけ、ミスなくスムーズに給付金を受け取るための正しい手続きをマスターしましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業の産休・育休で会社が行う必要がある手続きを下記の記事でまとめています。
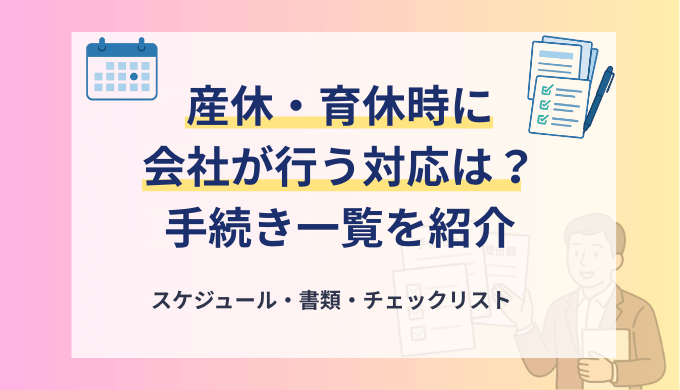 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
育児休業給付金支給申請書は、育児休業を取得する従業員が雇用保険から給付金を受け取るために提出する公的な申請書類です。育休中の従業員の生活を支える育児休業給付金を受給するには、この申請書が不可欠となります。
育児休業給付金の概要や支給要件については「育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説」の記事で詳しく解説しています。
この申請書には主に以下の2種類があり、提出するタイミングで使い分けます。
| 育児休業給付受給資格確認票 ・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 初めて申請する際に使用し、受給資格の確認と初回の給付金申請を同時に行う申請書 |
| 育児休業給付金支給申請書 (2回目以降) | 初回申請後、継続して給付金を受け取るために、原則2ヶ月ごとに提出する申請書 |
この育児休業給付金支給申請書には、被保険者番号や育休期間、就業状況、賃金などの情報を記入し、必要書類と共にハローワークへ提出します。
提出された内容に基づき審査が行われ、給付金の支給が決定されるため、正確な作成と期限内の提出が極めて重要です。特に初めて手続きを担当される方は、この書類の役割と種類をまず理解しておきましょう。
原則会社が支給申請書を作成・提出する
育児休業給付金の支給申請書は、原則として事業主(会社側)が作成とハローワークへの提出をする必要があります。 これは、雇用保険制度に基づく給付であることから、被保険者(育児休業を取得する従業員)に代わって、雇用主である会社が申請手続きを担うと定められているためです。
会社は、従業員から育児休業の申し出があった場合、必要な書類を準備し、従業員に必要な情報を確認した上で申請書を作成し、管轄のハローワークへ提出する役割を担います。
具体的には、休業期間や休業中の就業状況、支払われた賃金などを正確に記載し、証明する必要があり、例えば「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」などの作成も求められます。
ただし、従業員本人が希望し、会社が必要な書類の提供や記載内容の証明に協力する場合は、従業員本人が申請手続きを行うことも可能です。
しかし、その場合でも会社側の証明等は不可欠であり、手続きが煩雑になるケースも見られます。
特に設立間もない企業で担当者の方が不慣れな場合、この申請業務は負担に感じられるかもしれません。まずは、「手続きは原則会社が行う」という点を押さえておくことが大切です
育児休業給付金の申請手続きは、初回の提出で完了するものではなく、育児休業期間中は原則として2か月ごとに申告書を作成・提出する必要があります。
申請の流れは、大まかに「従業員からの申し出 → 支給要件確認 → 必要書類準備・申請書作成 → 初回申請 → 2回目以降の継続申請」となります。
それぞれの段階で会社と従業員が連携し、期限を守って進めることが重要です。
より詳細な申請方法(制度の概要や支給条件などを含む全体像)については、以下の記事も合わせてご参照ください。
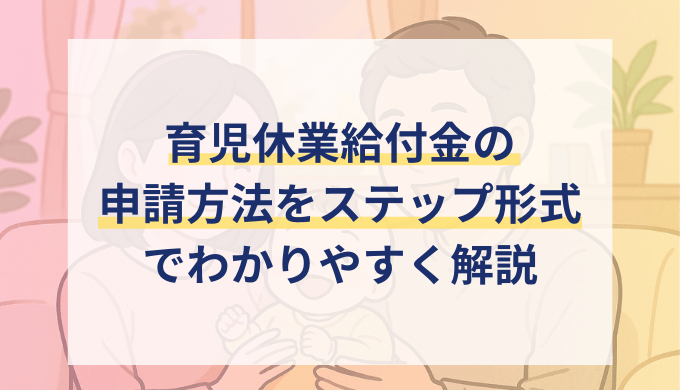 育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
育児休業給付金支給申請書をスムーズに作成・提出するためには、事前の情報収集と必要書類の準備が不可欠です。特に初回申請時には準備すべき書類が多く、不備があると申請が遅れてしまう可能性もあります。
こちらでは、申請書を書く前に準備すべきか、具体的には「従業員から入手すべき情報・書類」「初回申請に必要な書類リスト」「2回目以降の申請に必要な書類」について詳しく解説します。早めに準備に取り掛かり、漏れがないように進めましょう。
従業員から必要な情報・書類を入手する
育児休業給付金の申請手続きを進める上で、従業員本人から提供してもらうべき情報や書類がいくつかあります。会社側だけでは完結しないため、早めに従業員に依頼し、協力を得ることが円滑な手続きのポイントです。
具体的に従業員から入手・確認が必要な主な情報・書類は以下の表の通りです。
| 依頼する項目 | 具体的な内容 / 目的 | 入手方法 / 注意点 |
| 従業員の基本情報 | 氏名、住所、生年月日、個人番号(マイナンバー) | 申請書記入に必要。※マイナンバーの取得・利用は厳格なルール遵守。 |
| 育児対象となる子の情報 | 氏名、続柄、出産(予定)年月日 | 申請書記入、育児事実確認に必要。※母子健康手帳などで確認。 |
| 育児休業期間 | 従業員が取得を希望する具体的な開始日・終了(予定)日 | 申請書記入、休業期間の確認に必要。 |
| 振込先口座情報 | 給付金受取口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号) | 申請書記入、給付金の振込先指定に必要。必ず従業員本人名義であること。※通帳やキャッシュカードのコピーで確認。 |
| 母子健康手帳のコピー | 出産・育児の事実証明(表紙、出生届出済証明ページなど) | 初回申請時の添付書類として必要。 |
| その他(必要に応じて) | 配偶者の育休取得状況、延長希望の有無など | パパ・ママ育休プラス利用時や延長申請の可能性確認のため。 |
▼実務上のポイント
従業員へ情報提供や書類提出を依頼する際は、その目的、必要な情報・書類リスト、提出期限を明確に記載した依頼文書(メールテンプレートなど)を用意すると、認識の齟齬を防ぎ、スムーズな情報収集に繋がります。
初回申請に必要な書類
育児休業給付金の初回申請時には、複数の書類を揃えてハローワークへ提出する必要があります。準備すべき書類は会社側で用意するものと、従業員に準備してもらうものがあります。
以下の表に必要な書類をまとめました。抜け漏れがないか確認するための【チェックリスト】としてもご活用ください。
| 書類名 | 主な準備者 | 概要・注意点 |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 会社 | 初回申請のメインとなる申請書。様式はハローワークまたは厚生労働省サイトからダウンロードで入手可能。 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 会社 | 育休開始前の賃金を証明する重要書類。ハローワークで様式を入手(ダウンロード不可の場合あり)。 |
| 賃金台帳のコピー | 会社 | 申請書や賃金月額証明書の記載内容(賃金額、支払状況など)を証明する添付書類。通常、育休開始前1年分程度。 |
| 出勤簿(またはタイムカード)のコピー | 会社 | 勤務実績(就業日数、時間など)を証明する添付書類。通常、育休開始前1年分程度。 |
| 母子健康手帳など、育児・出産の事実が確認できる書類のコピー | 従業員 | 子の氏名、生年月日、申請者との続柄などを証明。表紙と出生届出済証明ページなど。 |
| 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー | 従業員 | 給付金の振込先口座を確認するための書類。 |
| その他(必要に応じて) | 会社/従業員 | 育休期間延長の証明書類、住民票(続柄確認等)など、ハローワークから指示された場合。 |
上記の書類を正確に準備し、内容を確認した上で初回申請に臨むことが重要です。特に賃金月額証明書は給付額の算定基礎となるため、正確な記載が求められます。
2回目以降の申請に必要な書類
初回の申請・支給決定後は、育児休業が終了するまで原則として2ヶ月ごとに申請を継続します。2回目以降の申請で必要となる書類は、初回と比較して少なくなります。
主に以下の書類を準備・提出します。
| 育児休業給付金支給申請書(2回目以降) | 通常、初回申請後にハローワークから会社宛てに送付される様式を使用。 |
| 賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)のコピー | 該当する支給単位期間中の就業日数や支払われた賃金額などを証明するために添付。 |
初回申請時に提出した母子健康手帳のコピーや通帳のコピーなどは、2回目以降の申請では原則として提出不要です。ただし、記載内容に変更があった場合(振込先口座の変更など)は、別途手続きが必要になる場合があります。
【あわせて読みたい】
> 出産手当金・育児休業給付金の金額・期間の計算ツール
育児休業給付金だけでなく、関連する出産手当金の概算額や支給期間を簡単に試算できます。さらに、社会保険料の免除額や、育児休業に関連する各種手続きの推奨申請時期などもシミュレーション可能ですので、手続き全体のスケジュールや影響額を把握するために、ぜひご活用ください。
育児休業給付金支給申請書の具体的な書き方について、記入例を交えながら詳しく解説していきます。
育児休業給付金をスムーズに支給してもらうためには、申請書への正確な記入が欠かせません。
手続きの流れとしては、まず初回申請時に提出する書類(①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)の書き方、そして育児休業期間中に継続して提出する③「2回目以降の育児休業給付金支給申請書」の書き方を順番に見ていきましょう。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の書き方
育児休業給付金の初回申請において、中心となるのがこの「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」です。
この一枚の書類で、従業員の受給資格の確認と、初回分の給付金支給申請を同時に行います。
項目数が多く少し複雑に見えるかもしれませんが、一つ一つの意味を理解し、ポイントを押さえて記入すれば決して難しくはありません。
通常、この申請書はA3用紙1枚(両面印刷)の形式です。記入にあたっては、黒のボールペンを使用し、事前に従業員の雇用保険被保険者証、母子手帳、振込先口座情報などを手元に準備しておくとスムーズです。
申請書のダウンロード及び、パソコンでの入力は下記ハローワークのページからおこなえます。
ハローワーク(育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書)
■記入例(育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書)
以下、主要な項目と特に注意が必要な項目【※注意】について、書き方を解説します。
雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号(通常は4桁-6桁-1桁)を正確に転記してください。ハイフンは記入不要です。
従業員が入社時に受け取った被保険者証が見当たらない場合は、会社保管の書類や過去のデータで確認するか、ハローワークに照会しましょう。
雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号(通常は4桁-6桁-1桁)を正確に転記してください。ハイフンは記入不要です。
従業員が入社時に受け取った被保険者証が見当たらない場合は、会社保管の書類や過去のデータで確認するか、ハローワークに照会しましょう。
会社の雇用保険適用事業所番号(通常10桁または11桁)を記入します。不明な場合は、「雇用保険適用事業所設置届」の控えや「適用事業所台帳」などで確認してください。
従業員が実際に育児休業を開始した年月日を正確に記入してください。
女性従業員の場合、多くは産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が終了した日の翌日が育児休業開始日となります。
男性従業員の場合、配偶者の出産日以降で、本人が育児休業を開始すると定めた日など、個別の取り決めに従った開始日となります。
ここで記入する日付は「出産日」ではない点に十分注意が必要です。日付を間違えると、支給期間や給付金額の計算に影響が出る可能性があります。従業員と会社双方で休業開始日を正確に確認しましょう。
育児休業の対象となる子の情報を、母子手帳などで確認し正確に記入します。
◯出産後に申請する場合:
- 項目6「出産年月日」に実際の出産日を記入します。
- 項目7「出産予定日」は、実際の出産日が予定日と異なる場合にのみ、当初の出産予定日を記入するのが一般的です。(予定日通りか、予定日より後に出産した場合は、項目6のみ記入し、項目7は空欄または斜線で消すことが多いです。)
◯出産前に申請する場合:(※初回申請は通常出産後に行います)
- 項目7に出産予定日を記入します。
従業員本人の12桁の個人番号を記入。提出時には本人確認書類の提示または写しの添付が必要になる場合があります。マイナンバーの取得・保管・利用に関する社内ルールを遵守してください。
育児休業給付金は、育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」として、その期間ごとに支給額が計算され、申請が行われます。暦月(1日~末日)単位ではない点に注意が必要です。
この欄には、それぞれの支給単位期間の初日と末日を和暦または西暦で記入します。
例: 育児休業開始日が令和7年4月16日の場合
- 最初の支給単位期間(13欄): 令和7年4月16日~令和7年5月15日
- 次の支給単位期間(17欄): 令和7年5月16日~令和7年6月15日
初回申請では、通常2期間分(13欄と17欄)をまとめて記入し申請します。
育児休業が終了する日を含む最後の期間については、21欄にその期間の初日と育児休業終了日を記入します。
各支給単位期間に対応して支払われた賃金の総額(社会保険料や税金などが控除される前の額。いわゆる「額面」)を記入します。
基本給だけでなく、残業代、通勤手当、家族手当、住宅手当なども原則として含まれます。
ただし、賞与(ボーナス)など臨時に支払われる賃金(明確な基準あり、通常3か月を超える期間ごとに支払われるもの)は含みません。
この欄に記入された賃金額によって、育児休業給付金が減額されたり、支給されなくなったりする場合があります(目安として、休業開始前賃金の80%以上の賃金が支払われると不支給)。賃金台帳などで確認できる正確な金額を記入してください。
この項目は、配偶者の育児休業取得状況など、夫婦での育休取得に関連する情報を記入する欄です。
育児休業の分割取得や、2025年4月1日から施行された「出生後休業支援給付金」(父母ともに14日以上の育休取得が主な要件)などの制度利用に関わるため、会社として把握している範囲で正確に記入しましょう。
育児休業給付金の「パパ・ママ育休プラス」や「出生後休業支援給付金」といった夫婦での育休取得を支援する制度を活用したい場合は、原則として育児休業給付金の初回申請時に併せて申告を行う必要があります。
該当する場合は、項目27の「パパ・ママ プラス制度活用」欄(または関連するチェックボックス)を確認・チェックし、項目28「配偶者の被保険者番号」、項目29「配偶者の育児休業開始年月日」といった必要事項を正確に記入してください。
【あわせて読みたい】
出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
育児休業給付金の振込先となる金融機関の口座情報を正確に記入する欄です。添付する通帳コピーなどと相違ないように注意深く記入しましょう。
必ず従業員「本人名義」の口座を指定してください。結婚等で姓が変わっている場合、旧姓のままの口座は使用できません。
金融機関コード(4桁)、支店コード(3桁)、預金の種別(普通・当座など)、口座番号(右詰めで記入)を、通帳やキャッシュカードで正確に確認して記入しましょう。記入ミスがあると振込が遅れる原因になります。
事業主証明欄: 申請書全体の記載内容が事実に相違ないことを会社(事業主)が証明する欄です。事業所名・所在地・電話番号、事業主名を正確に記入してください。**令和3年からの法改正により、押印は任意(省略可能)**となっています。
申請者署名欄: 原則として、従業員本人が記載内容を確認した上で氏名を署名します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の書き方(初回のみ)
初回申請時には、先ほどの申請書とセットで必ず提出しなければならないもう一つの重要な書類があります。それが「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」です。この書類は、育児休業給付金の支給額を算定する際の基礎となる「休業開始時賃金日額」を計算するために用いられるため、極めて正確な記入が求められます。
この「休業開始時賃金月額証明書」は、従業員ではなく会社(事業主)が責任をもって作成する必要があります。様式は原則としてハローワークで受け取るか、郵送で取り寄せます(複写式のためダウンロードできない場合が多い点に注意してください)。
2回目以降の育児休業給付金支給申請書の書き方
初回申請を無事に終え、育児休業給付金の支給が開始された後も、育児休業が終了するまでは原則として2ヶ月ごとに継続して申請を行う必要があります。その際に使用するのが「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」です。
初回申請と比較すると様式は簡略化されており、記載済みの情報も多いですが、支給単位期間ごとの就業日数や支払われた賃金額などを正確に記入し、期限内に提出することは引き続き重要です。
通常、この申請書はハローワークから会社宛に送られてきます。
■記入例(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)
以下、主要な項目について、書き方のポイントと注意点を解説します。この書類は給付金額の算定基礎となるため、賃金台帳や出勤簿と照合しながら正確に作成しましょう。
まず、申請書と同様に、従業員の雇用保険被保険者番号(1)、会社の事業所番号(2)、従業員の氏名(3)を正確に記入します。
項目4「休業等を開始した年月日」には、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の項目5に記入した育児休業開始年月日と同じ日付を記入してください。
項目5「事業主証明欄」には、事業所の名称・所在地・電話番号、事業主名を記入します。
項目6「休業等を開始した者の住所又は居所」には、従業員の住所を記入します。
育児休業給付金の支給額算定の基礎となるため、特に正確な記入が求められます。賃金台帳や出勤簿などの書類と照合しながら、慎重に作成しましょう。
◯項目7「休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」
少し複雑な項目名ですが、これは育児休業開始日の前日から遡って、被保険者であった期間を記入する欄です。
原則として、賃金支払基礎日数(※)が11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月とし、最大2年間まで遡って月ごとに記入します。
ただし、このような月が12か月以上確認できれば、それ以上遡って記入する必要はありません。
(※賃金支払基礎日数:月給者の場合は暦日数、日給・時給者の場合は出勤日数など、賃金計算の基礎となる日数)
◯項目8「⑦の期間における賃金支払基礎日数」
上記⑦で記入した各月について、それぞれの賃金支払基礎日数を記入します。
◯項目9「賃金支払対象期間」
育児休業開始日の直前の賃金締切日の翌日から遡って、賃金締切日ごとに区切った期間(1か月)を、原則として過去2年間記入します。
ただし、このうち賃金支払基礎日数(項目10で後述)が11日以上ある月(これを「完全な月」と呼びます)が直近で6か月以上あれば、それより前の期間の記入は省略できます。
例: 賃金締切日が月末、育休開始が11月5日の場合、10/1~10/31、9/1~9/30…と遡って記入。
◯項目10「⑨の基礎日数」
上記⑨で記入した各賃金支払対象期間(1か月)における賃金支払基礎日数を記入します。月給者は原則「暦日数」、日給・時給者は「出勤日数」となります。
◯項目11「賃金額」【※注意】
上記⑨で記入した各賃金支払対象期間に対応して支払われた賃金の総額(社会保険料や税金などが控除される前の「額面」)を記入します。
A欄には月給・週給など(主に固定給部分)、B欄には日給・時間給など(主に変動給部分)を分けて記入します(該当する場合)。両方ある場合はA欄+B欄の合計を計欄に記入します。
通勤手当、家族手当、住宅手当なども原則として含みますが、賞与(ボーナス)など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金や、臨時に支払われる賃金は含みません。
この欄に記入された賃金額を基に休業開始時賃金日額が計算され、給付金額が決まります。算定対象となる賃金・ならない賃金を正確に区分し、賃金台帳と一致する金額を記入してください。
項目12「備考」欄には、⑦~⑪欄を記入する上での参考事項(例:月給者で欠勤控除があった月の計算根拠、休業手当を支払った場合の内訳など)があれば記入します。
項目13「賃金に関する特記事項」欄には、3か月以内の期間ごとに支払われる賃金(例えば、3か月ごとに支給される報奨金など、賞与とは異なるもの)があれば、その名称と金額、支給年月日などを記入します。該当がなければ斜線を引きます。
申請書と同様に、会社(事業主)が記載内容を証明する欄です。事業所名・所在地・電話番号、事業主名を正確に記入してください。こちらも押印は任意(省略可能)です。作成年月日も忘れずに記入しましょう。
2回目以降の育児休業給付金支給申請書の書き方
初回申請が受理されると、次回以降の申請に使う「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」がハローワークから会社宛に送付されてきます(電子申請の場合はシステム上で確認・作成)。
この申請書は、初回の様式よりも簡略化されており、記入が必要な箇所は少なくなります。
以下、主な項目について書き方と注意点を解説します。
■記入例(育児休業給付金支給申請書(2回目以降)
参照元:ハローワーク「育児休業給付金支給申請書2回目以降記入例」など
申請書の上部には、被保険者番号、氏名、事業所番号など、初回申請時に登録された情報が既に印字されている場合が多いです。
まずはこれらの印字内容に誤りがないかを確認しましょう。もし誤りがあれば、二重線で訂正し、正しい情報を記入します(訂正印は不要な場合が多いですが、管轄ハローワークにご確認ください)。
今回申請する対象となる支給単位期間(通常2か月分)の初日と末日が印字されているか確認します。空欄の場合は、前回の支給決定通知書などを参考に正確に記入してください。
期間の考え方は初回申請時と同じです(育児休業開始日から1か月ごと)。
各支給単位期間ごとに、従業員が実際に就業した(働いた)日数を記入します。
カウント方法は初回と同様、1日のうち短時間でも働けば「1日」です。全く就業しなかった場合は「0」と記入するか空欄にします。
ここで記入する日数が10日を超える(11日以上)と、その期間の給付金は原則支給されませんので、出勤簿などで正確に確認してください。
上記の就業日数が11日以上となった場合にのみ、その期間の合計就業時間数(分は切り捨て)を記入します。
就業日数が10日以下の場合は記入不要です。就業時間が80時間を超える場合も給付が受けられないため、こちらも正確に記入してください。
各支給単位期間に対応して支払われた賃金の総額(税引前)を記入します。初回と同様に、基本給や各種手当は含みますが、賞与など臨時に支払われる賃金は除きます。
この賃金額によっても給付金が減額・不支給となる場合があります。賃金台帳と照合し、正確な金額を記入してください。
もし申請対象期間中に従業員が育児休業を終了し、職場復帰した場合には、その年月日を記入します。復帰せずに育児休業を継続している場合は記入不要です。
記載内容に誤りがないことを確認の上、事業主証明欄に会社(事業主)が必要事項を記入します(押印は任意)。
労働者記入欄(またはそれに準ずる欄)については、様式の指示に従い、従業員による確認や署名(または記名押印)が必要か確認してください(初回申請時の同意書があれば省略可能なケースもあります)。
2回目以降の申請は原則2ヶ月ごとに提出が必要です。申請を忘れると給付が遅れます。ハローワークからの申請書到着を待つだけでなく、社内で提出期限を管理する仕組み(リマインダー設定など)を整え、申請漏れを防ぎましょう。
【出産手当金と育児休業給付金の申請代行を全国スポット対応!】
社労士クラウドなら顧問料0円、業界最安値の料金で専任の社労士がスポットで申請代行!
- 複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減してコア業務にしたい
- 正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避したい
- 法改正への確実な対応がしたい
\ 顧問料0円で全国対応!/
> 社労士クラウドのスポット料金・報酬を確認する
ここでは、育児休業給付金支給申請書の書き方でよく寄せられる質問を、Q&A形式でわかりやすく紹介します。
申請書はどこで入手できますか?ダウンロードは?
育児休業給付金支給申請書の様式を入手するには、主に以下の3つの方法があります。
① ハローワークの窓口で受け取る:
管轄のハローワークで直接入手できます。
② ウェブサイトからダウンロードする:
厚生労働省やハローワークのウェブサイトから、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」や「育児休業給付金支給申請書(2回目以降)」の様式(PDFファイルなど)をダウンロードし、印刷して手書きまたは入力して使用できます。必ず最新の様式をご利用ください。
③ 電子申請システム上で作成する:
電子申請(e-Gov)を利用する場合、システム上で申請書を作成し、そのままオンラインで提出することも可能です。
ただし、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」(初回申請時に必要)については、複写式の様式が用いられることが多く、原則としてダウンロードはできません。こちらはハローワーク窓口で入手するか、郵送で取り寄せる必要がありますのでご注意ください。
申請書は誰が書くのが正しいですか?会社が代筆しても良い?
申請書の作成・提出は、原則として会社(事業主)が行うこととされています。しかし、従業員本人が記入することも可能です。その場合でも、事業主が内容を確認し、証明する欄への記入は必須です。
会社の担当者が従業員の代わりに申請者欄を記入(代筆)する場合は、必ず事前に従業員本人から**「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を書面で取得し、会社で保管してください。同意書があれば、申請者欄に従業員の氏名を記載し、「(申請について同意済み)」などと追記することで代筆が認められます。
書き間違えた場合の修正方法は?
申請書の記入を間違えた場合は、修正液や修正テープは使用せず、以下の方法で訂正するのが一般的です。
間違えた箇所を二重線で消す。その上(または近くの余白)に正しい内容を記入します。訂正箇所に訂 訂印(申請書に使用した印鑑と同じもの、または担当者の認印など)を押印します。
(※近年、押印省略の流れがありますが、訂正の場合は押印を求められるケースもまだあります。不明な場合は提出先のハローワークにご確認ください。)
捨印(あらかじめ欄外に押しておく訂正用の印)があれば、それを利用できる場合もあります。正確な修正方法については、提出先のハローワークにご確認いただくのが最も確実です。
申請書の提出が遅れた場合の影響は?
育児休業給付金の申請には提出期限があります。
初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降の申請: 各支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
この期限を過ぎてしまうと、給付金の支給が遅れてしまいます。
また、申請する権利は2年間の時効があるため、提出が大幅に遅れると、該当期間の給付金を受け取れなくなる可能性があります。 万が一遅れてしまった場合は、速やかにハローワークに相談し、指示に従ってください。遅延理由書の提出などを求められる場合があります。
添付書類の通帳コピーは必須ですか?電子申請の場合は?
初回申請時には、給付金の振込先口座を確認するため、原則として従業員本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピーの添付が必要です。金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる部分のコピーを提出します。
電子申請(e-Gov)を利用する場合は、申請画面で口座情報を直接入力します。そのため、通帳コピーの画像データ等の添付は原則不要となることが多いですが、システム上の指示やハローワークの運用によって異なる場合もありますので、申請時に確認が必要です。
育休期間を延長する場合は手続きは必要ですか?
育児休業期間を延長し、それに伴って育児休業給付金の支給期間も延長したい場合は、別途手続きが必要です。
保育所に入れないなどの延長理由に応じて定められた証明書類(例:市区町村発行の入所不承諾通知書など)を準備し、「育児休業給付金支給申請書」の延長に関する欄(例:初回申請書の項目26など)に必要な情報を記入して申請する必要があります。
延長申請を行うタイミング(原則として子が1歳や1歳6か月に達する日の翌日以降の支給単位期間の初日の前日までなど)も決まっていますので、延長が見込まれる場合は早めに準備を進めましょう。
男性の育休(産後パパ育休含む)申請書の書き方は?
育児休業給付金支給申請書の様式自体は、男女で違いはありません。基本的な書き方は同じです。
ただし、男性が育児休業を取得する場合、
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を利用するかどうか
- 育児休業を分割して取得するかどうか
- 出生後休業支援給付金(2025年4月~)の支給対象となるか(父母ともに14日以上の育休取得)
などによって、申請書のチェック項目(例:項目27など)や、場合によっては添付書類が異なる可能性があります。
特に配偶者の育児休業取得状況などを正確に記入することが重要になります。基本的な書き方は同じですが、利用する制度に合わせて様式の指示をよく確認し、不明な点はハローワークに相談することをお勧めします。
育児休業給付金支給申請書の作成と提出は、育児休業を取得する従業員の生活を支える上で、企業が責任を持って行うべき重要な手続きです。この申請書を正確に作成し、期限内に提出することが、給付金のスムーズな支給に繋がります。
この記事では、初回・2回目以降それぞれの申請書や休業開始時賃金月額証明書の具体的な書き方、必要書類の準備、申請の流れ、そして注意すべきポイントを解説してきました。
育児休業給付金の申請にともなう書類には多くの記入項目があり、賃金額や就業日数の正確な把握、支給単位期間の考え方など、間違いやすい点も少なくありません。
特に、申請には厳格な提出期限が設けられており、初回申請時には複数の添付書類も必要となるため、事前の準備と計画的な進行が求められます。また、申請に必要な情報提供など、従業員との円滑なコミュニケーションを取り、協力を得ることも不可欠です。
日頃から手続きのポイントを理解し、準備を整えておくことが、いざという時のスムーズな対応の鍵となります。
申請書の記入ミスや提出遅延は、従業員への給付金支給が遅れたり、最悪の場合支給されなくなったりするリスクも伴います。これを回避するためには、この記事で解説した正しい書き方を実践し、賃金台帳等と照合しながら正確な内容で申請を行うことが非常に重要です。
育児休業給付金の制度は複雑な面もありますが、正しい知識を身につけ、速やかに申請を行うことで、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整え、企業としての信頼を高めることができます。
とはいえ、特に設立間もない企業の担当者の方にとっては、慣れない手続きに不安を感じたり、他の業務との兼ね合いで手が回らなかったりすることもあるかもしれません。
育児休業給付金支給申請書に関する相談や申請を社労士がスポット代行
育児休業給付金支給申請書の作成や一連の申請手続きは、専門的な知識が求められ、記入項目も多く複雑です。「書き方は理解できたけれど、自社で正確にできるか不安…」「他のコア業務に集中したいので、手続きは専門家に任せたい」といったお悩みはありませんか?
そのような場合には、社労士に相談したり、申請の代行を依頼したりするのも有効な選択肢の一つです。
「社労士クラウド」は、顧問契約が不要で、必要な手続きだけを依頼できる『スポット契約』に特化した社労士サービスです。
「育児休業給付金の申請だけをお願いしたい」「申請書の内容チェックだけしてほしい」といったご要望にも、顧問料0円で柔軟に対応いたします。設立間もない企業様や、普段は自社で手続きしているけれど今回だけ不安がある、といった企業様にも多くご利用いただいています。
経験豊富な社労士が、最新の法改正にも対応しながら、正確かつ迅速な申請手続きをサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|