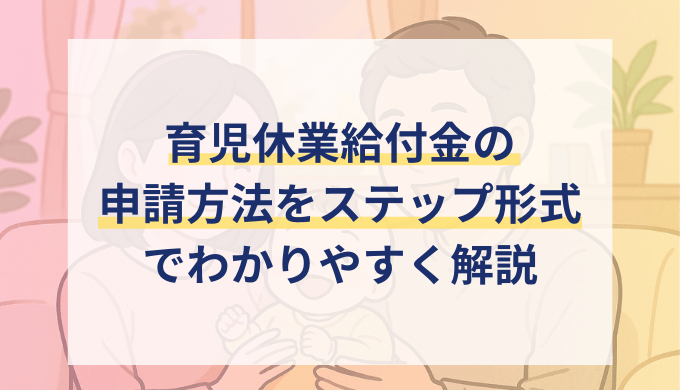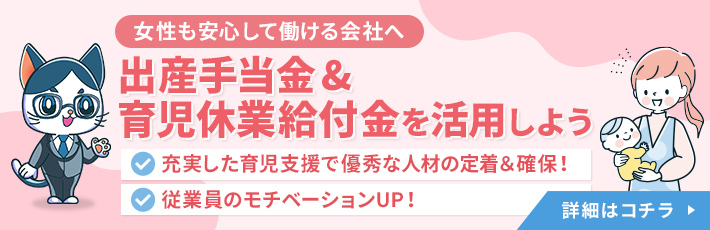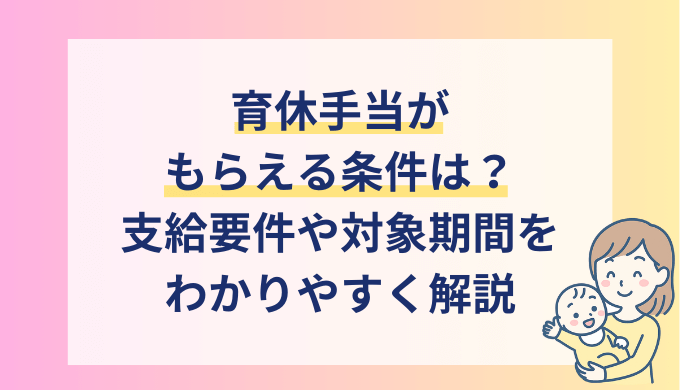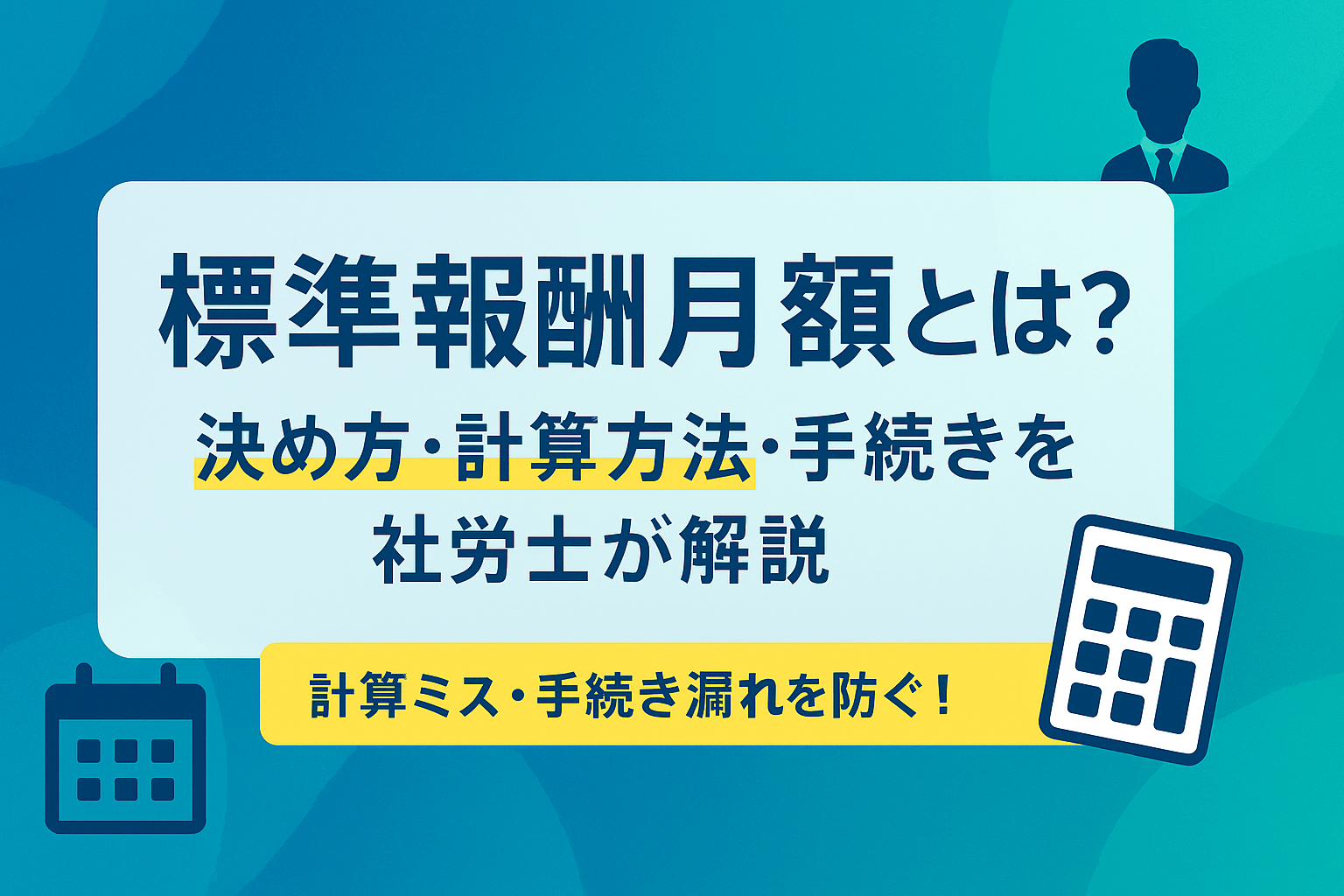育児休業給付金は、育児と仕事の両立を支援するために設けられた制度で、雇用保険に加入している従業員が育児休業を取得した場合に、一定期間の生活を補償する給付金が支給されます。
申請は原則として事業主(会社)側が行う必要があるため、人事・労務担当者にとっては必ず押さえておくべき重要な手続きです。
とはいえ実際には、「初回申請の流れがわからない」「継続申請はいつ何を出せばいい?」「書類は誰が用意するのか?」など、申請のタイミングや流れに不安を抱えている担当者も少なくありません。
加えて近年は、「産後パパ育休」や「出生後休業支援給付金」など新たな制度も導入され、対応の複雑さが増しています。
この記事では、育児休業給付金の申請方法を、制度の基礎知識から初回・2回目以降の申請フロー、必要書類、延長手続き、よくあるミスや注意点まで、ステップごとにわかりやすく解説しています。
従業員に確実に給付金を受け取ってもらうために、会社としてどのように対応すべきかを整理し、申請ミスやトラブルを未然に防ぐためのポイントを押さえておきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業の産休・育休で会社が行う必要がある手続きを下記の記事でまとめています。
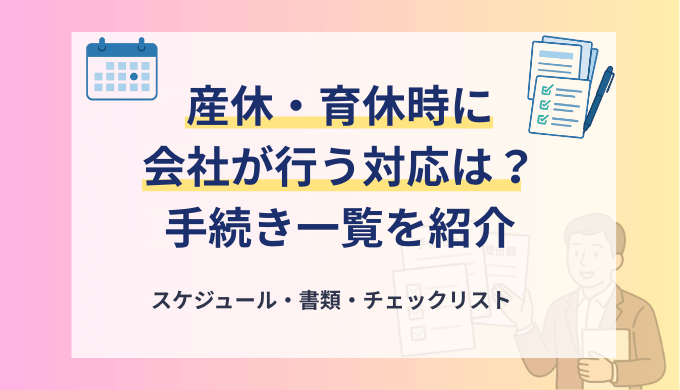 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
育児休業給付金とは、子どもが1歳になるまでの育児休業期間中に、一定の条件を満たした労働者に対して雇用保険から支給される給付金です。会社を休んで子育てに専念する期間中、収入がゼロになるのを防ぎ、生活の安定を支援することが目的とされています。
対象となるのは、原則「1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者」で、要件を満たせば父親や有期契約の従業員でも受給が可能です。
また、育児休業の延長や育休中の就業状況によって、支給期間や支給額が変動する場合もあります。申請を行う際は、こうした制度の仕組みを簡単に把握しておくと手続きもスムーズになります。
支給対象となる従業員の主な要件(受給資格)
育児休業給付金を受け取るためには、育児休業を取得する従業員が雇用保険の被保険者であり、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。
事業主としては、申請手続きを進める前に、該当する従業員がこれらの条件をクリアしているか、事前にしっかり確認することが重要です。
育児休業給付金を受給するためには、主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
| ・1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者であること ・育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12か月以上あること ・育児休業期間中の就業日数が、1支給単位期間あたり10日(または就業時間80時間)以下であること |
なお、契約社員やパートタイマーなど、期間を定めて雇用される、いわゆる有期雇用労働者の方が育児休業を取得する場合は、上記の要件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
| ・養育する子どもが1歳6か月に達する日までに、その労働契約期間が満了することが明らかでないこと |
つまり、「育休終了後に職場復帰できる見込みがあるか」が問われます。契約が更新される予定である場合や、「更新されない」と明確に決まっていない場合は、原則としてこの要件を満たすと判断されます。契約の更新有無が不明確な場合は、管轄のハローワークに確認することをおすすめします。
【あわせて読みたい】
> 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
対象となる期間(いつからいつまで?)と延長
育児休業給付金が支給される期間は、原則として子どもが1歳になるまでの育児休業期間中です。ただし、保育園の利用を希望しても見つからない場合など、一定の要件を満たすときは、最大で子どもが2歳になるまで育児休業を延長し、育児休業給付金を受け取ることが可能です。
開始日については、母親の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)が終了した翌日から、父親の場合は子どもの出生日または出産予定日のうち早い方から育児休業を取得できますので、その開始日からが対象となります。
なお、2022年の育児・介護休業法 改正で創設された産後パパ育休(出生時育児休業)も、別に設けられた出生時育児休業給付金の支給対象期間となりますが、通常の育児休業とは異なる制度ですので、混同しないよう注意が必要です。
「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用して、夫婦ともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、子どもが1歳2か月に達する日まで支給対象期間が延長されます。これは、父親の育児休業取得を促進するための制度です。
【あわせて読みたい】
> 育児休業給付金(育休手当)はいつからいつまで?支給日と支給期間を詳しく解説
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の支給金額は、原則として育児休業 開始前の賃金(給与)を基にした計算式で算出され、雇用保険から支給されます。
支給額の基本的な計算方法は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」です。給付率は育児休業 開始からの期間によって異なり、具体的には以下の計算式で求められます。
| ・支給開始後180日目まで:支給額=賃金日額×休業日数×67% ・支給開始後181日目以降:支給額=賃金日額×休業日数×50% |
ここでいう「休業開始時賃金日額」とは、原則として育児休業 開始前6か月間の賃金総額(賞与など臨時に支払われる賃金は除く)を180で割った金額。また、「支給日数」は、原則として1か月あたり30日(育児休業が終了する月は終了日までの日数)で計算します。
ただし、この「休業開始時賃金日額」には上限額と下限額が定められています(2025年4月13日現在、令和7年7月31日までは上限額15,690円、下限額2,869円)。
下記のシミュレーションツールで、育児休業給付金だけでなく、出産手当金の支給金額や産休・育休期間の目安も簡単に算出できます。
【あわせて読みたい】
出産手当金・育児休業給付金の金額・期間の計算ツール
育児休業給付金の申請は、初回の手続きだけで完了するわけではなく、育児休業期間中は原則として2か月ごとに継続して申請する必要があります。そのため、初回と2回目以降では、それぞれ提出する書類や申請期限、申請の流れが異なります。
会社側としては、従業員から育休の申し出があった段階で、速やかに申請準備に着手することが重要です。申請の遅れや書類不備は、従業員への給付金支給の遅延につながり、信頼関係や職場環境にも影響を及ぼしかねません。
ここでは、育児休業給付金の申請手続きについて、以下の5つのステップに分けて、会社が実務上対応すべき流れと注意点をわかりやすく解説します。
- STEP1:従業員からの育休申し出と申請準備の開始
- STEP2:必要書類の準備と確認
- STEP3:受給資格確認と初回申請の手続き
- STEP4:2回目以降の支給申請(2ヶ月ごと)
- STEP5:育休終了・職場復帰時の手続き
はじめて育児休業給付金の申請業務を行う担当者でも安心して取り組めるよう、制度の基本と流れを丁寧に確認していきましょう。
STEP1:従業員からの育休申し出と申請準備の開始
育児休業給付金の申請は、従業員から育児休業の申し出を受けるところからスタートします。
法律上、育休の申し出は原則として、育児休業開始の1か月前までに会社へ提出することと定められています。
このタイミングでまず確認しておきたいのが、従業員が育児休業給付金の受給資格を満たしているかどうかです。
あわせて、申請者が父親である場合は、「出生後休業支援給付金」の対象となるかどうかも確認しておくと安心です。
どちらの制度についても、早い段階で必要情報を把握しておくことで、申請漏れやトラブルを防げます。
以下は、この時点で従業員からヒアリングしておきたい主な情報です。
■従業員から確認しておきたいチェックリスト
- 出産予定日または出生予定日
- 育児休業の開始予定日と終了予定日
- 育児休業の取得形態(1回 or 分割予定)
- 取得予定者が父親である場合、出生後8週間以内に4日以上取得する予定があるか
- パパママ育休プラスなど他制度との併用予定があるか
STEP2:必要書類の準備と確認
育児休業給付金の申請には、会社側(事業主)が用意する書類と、育児休業を取得する従業員本人から提供を受ける必要がある書類があります。
どちらかが欠けても申請ができず、給付金の支給が遅れる原因となりますので、担当者は必要書類の種類と内容を正確に把握し、抜け漏れなく準備を進めましょう。
育児休業給付金の申請にあたり、会社側が準備・作成すべき代表的な必要書類は、主に以下の3点です。それぞれの書類の内容(役割)と入手先をしっかり確認しましょう。
| 必要書類 | 書類の内容 | 入手先 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 給付金の支給額を計算するための基礎となる、休業開始前の賃金額を証明するための書類 | 原則として事業所の管轄ハローワークから取り寄せる |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 従業員が給付金の受給資格を満たしているかを確認し、同時に初回の給付金を申請するための書類 | 厚生労働省のホームページなどからダウンロードが可能 |
| 育児休業等取得者申出書(新規・延長) | 育児休業中の健康保険・厚生年金保険料の免除を申請するための書類。提出により、本人・会社ともに社会保険料が免除される。 | 年金事務所、または日本年金機構のサイトから入手可能 |
主要な申請書類に加えて、申請書に記載した内容の確認資料として、「賃金台帳」「出勤簿」「労働者名簿」などの写しの添付も求められます。
これらの添付書類は、主に従業員の受給資格 要件である『育児休業 開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること』の確認や、「休業開始時賃金月額証明書」に記載した賃金額の根拠を確認・証明するために必要となるものです(場合によっては最大2年間分)。
したがって、添付する書類も含め、従業員の就業実績や給与情報が正確に反映されていることが大前提となります。
とりわけ注意が必要なのは「休業開始時賃金月額証明書」で、その記載内容と添付する賃金台帳などの情報に齟齬がないか、細心の注意を払って確認してください。
育児休業給付金の申請にあたっては、会社側が用意する書類のほかに、従業員本人からの提出が必要となる書類もあります。これらの書類がそろっていない場合、申請が受理されなかったり、給付金の支給が遅れたりする恐れがあるため、提出時には内容の確認を徹底することが重要です。
従業員に提出をお願いする必要がある主な書類は、以下の表の通りです。
| 提出書類の種類 | 詳細(確認内容・注意点) | 代替可能な書類 |
| 母子健康手帳のコピー | 「出生届出済証明」のページで、育児休業を取得する従業員本人の名前が記載されたものが必要。 | ・住民票(世帯全員の記載があり、“続柄”の省略がないもの)・ 出産手当金 申請書コピー(名前・出産日・医師または医療機関の証明が記載されているもの) |
| 振込先口座の確認書類 | 従業員本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー。必ず本人名義であり、旧姓のままの口座は使用できませんので注意が必要。 | マイナポータルの公金受取口座を指定することも可能(事前にハローワークへのマイナンバー届出等の確認が必要) |
加えて、上記の添付書類の準備と並行して、会社が作成する「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」についても、従業員本人に記入・署名してもらう必要があります。
具体的には、振込先口座情報、マイナンバー、そして本人署名欄などです。事前に同意書を取得している場合は署名を省略できますが 、いずれにしても従業員への依頼と回収が必要ですので、他の書類と合わせて早めに依頼・回収を進めましょう。
これらの書類に不備や記載漏れがあると、ハローワークから差し戻しとなり、全体の申請手続きが遅延する原因となります。
特に多いのは、以下のような実務上のミスです:
- 旧姓のままの口座が使われている
- 住民票に“続柄”の記載がない
- 母子手帳の該当ページが未記入
こうしたリスクを避けるためにも、提出を受け取った担当者が内容をダブルチェックする体制を整えておくことをおすすめします。
【あわせて読みたい】
> 育児休業給付金支給申請書の書き方を記入例付きで解説!初回・2回目以降まで
STEP3:育児休業給付金の受給資格確認と初回支給申請の手続き
必要書類の準備が整ったら、次はハローワークで「受給資格確認」と「初回支給申請」の手続きを行います。
初回の手続きでは、従業員が育児休業給付金の受給資格を満たしているかどうかを確認するとともに、最初の支給申請もあわせて行います。提出期限を過ぎると給付金が受けられなくなるため、提出期間・期限と必要書類を事前にしっかり確認しておきましょう。
また、初回申請と同時に「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を年金事務所へ提出することも検討してください。この届出を行うことで、育休期間中の健康保険料・厚生年金保険料が会社・従業員ともに免除されます。
初回申請で最も注意すべき点は、提出期限の管理です。
たとえば、従業員が「7月10日」に育児休業を開始した場合、申請期限は「11月30日(4か月後が属する月の末日)」になります。
この期限を過ぎてしまうと、育児休業給付金の支給対象から外れてしまう恐れがあるため、スケジュール管理は慎重に行いましょう。
以下に、初回の申請に関する主な情報をまとめます。
【初回手続き(受給資格確認と初回申請)の概要】
| 項目 | 内容 |
| 提出期限 | 育児休業を開始した日から起算して4か月が経過する月の末日まで |
| 提出書類 | ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・賃金台帳、出勤簿などの添付資料・母子健康手帳の写し等、育児の事実を確認できる書類 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | ・窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)対応 |
なお、夫婦で育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合は『出生後休業支援給付金』も初回申請時に同時に申請できます。この制度は2025年4月から開始されたもので、該当する場合は申請書への記載などが必要となります。
【あわせて読みたい】
【2025年4月~】出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
初回申請に不備がなければ、後日ハローワークから会社宛てに「支給決定通知書」と「次回支給申請書」が送られてきます。
届いたら内容を確認し、結果を速やかに従業員へ共有しましょう。
「次回支給申請書」は2回目以降の申請に必要なため、紛失しないよう保管し、次の申請期限もあわせて確認しておきましょう。
給付金の振込は、決定後おおむね1週間程度が目安ですが、処理状況によっては前後することもあります。
STEP4:2回目以降の支給申請(2ヶ月ごと)
育児休業給付金は、初回申請後も育休期間中は2か月ごとに継続申請が必要です。原則として事業主が2か月ごとに申請しますが、従業員が希望すれば、本人が申請を行うことや1か月単位で申請することも可能です。
【申請概要】
| 項目 | 内容 |
| 申請時期 | ハローワークから指定される期間内(「次回支給申請日指定通知書」で要確認)。原則2か月ごと。 |
| 提出書類 | ・育児休業給付金支給申請書(次回分)・賃金台帳、出勤簿、タイムカード等の写し |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | ・窓口持参、郵送、電子申請(e-Gov)対応 |
2回目以降の申請時期は、初回申請後に交付される「次回支給申請日指定通知書」で指定されます。この通知には、申請期間と対象となる支給期間が記載されていますので、必ず内容を確認してください。
提出が遅れると給付金の支給も遅れてしまうため、担当者は通知に基づいて確実にスケジュール管理を行いましょう。
継続申請には、ハローワークから交付された**「育児休業給付金支給申請書(次回分)」**を使用します。この書類には、申請期間中の以下の情報を記載する必要があります:
- 就業の有無や就業日数・時間
- 会社からの賃金支払いの有無・金額
これらの内容は支給可否や金額の決定に直結するため、誤りのない記載が求められます。また、申請書の裏付けとして、賃金台帳や出勤簿、タイムカードの写しを添付します。
定型的な手続きとはいえ、毎回の記入・添付・期限管理を確実に行うことが大切です。
STEP5:育休終了・職場復帰時の手続き
育児休業が終了したら、その月を含む最後の支給申請を行います。この申請書には職場復帰日(育休終了日)を記載する欄があり、これをもって給付金の支給が正式に終了します。
地域によっては、「育児休業給付金支給終了確認票」などの追加提出を求められる場合もありますので、初回申請時に交付された書類一式を再確認しておくと安心です。
また、職場復帰後に時短勤務等の働き方の変更がある場合は、就業条件変更の手続きや、社会保険料の免除継続(子が3歳になるまでの制度)にも対応する必要があります。
【育休終了後に会社が行う主な手続き一覧】
| 書類名 | 内容・提出先 |
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 復帰後の3か月間の賃金をもとに社会保険料を見直すための届出【提出先】年金事務所 |
| 養育期間標準報酬月額特例申出書 | 育休明けに賃金が下がっても、将来の年金額が下がらないようにするための申請【提出先】年金事務所 |
| (一部地域)支給終了確認票など | 育児休業給付金の最終支給に関連する報告書類(必要な場合のみ)【提出先】ハローワーク |
【合わせて読みたい】
社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳に達する日までですが、特定の状況においては、その期間を延長することが可能です。
担当者としては、「保育所に入所できない」といった従業員からの相談を受けるケースも少なくないでしょう。ここでは、延長が認められるケースや、実際の申請手続きに必要な書類について解説します。
延長が認められるケースと条件
育児休業給付金の支給期間は、基本的に子どもが1歳の誕生日の前日までですが、以下のような事情がある場合は最長2歳まで延長申請が可能です。
■ 主な延長理由
- 保育所に申し込んだが入所できなかった場合(待機児童)
- 育休を取得している配偶者が、子どもを引き続き養育できない事情がある場合(病気・けがなど)
- やむを得ない理由により職場復帰が困難であるとハローワークが認めた場合
延長理由の中で最も多いのが「保育所に入れない」という場合です。
この場合は、入所不承諾通知書(保育所の不承諾通知)を提出することで延長が認められます。
なお、1歳6か月までの延長と、1歳6か月以降2歳までの再延長は別申請となるため、それぞれのタイミングで再度申請手続きを行う必要があります。
延長申請に必要な書類と手続き方法
延長を希望する場合は、対象期間が終了する前に、次のような書類を揃えてハローワークに提出します。
| 項目 | 内容 |
| 延長申請に必要な書類 | ・育児休業給付金支給申請書(延長分)・延長理由を証明する書類(例:保育所の不承諾通知書など)・賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどの写し |
| 手続きのタイミング | ・延長開始日が属する支給単位期間の末日までに申請。(例:1歳の誕生日が8月15日 → 8月末までに申請) |
延長を希望する際は、本人からの「育児休業期間変更申請書」も必要です。
これは、育児休業の就業契約上の延長を会社として承認するための書類で、会社側が確認・準備のうえ従業員に案内しましょう。
また、「育児休業給付金支給申請書」には延長理由の記入欄があります。理由の概要を記載し、証明書類と一緒に提出してください。
■ 延長理由別の必要書類(主な例)
| 延長理由 | 添付すべき書類 |
| 保育所に入れない | 市区町村が発行した「保育所入所保留通知書」など |
| 配偶者が死亡した | 世帯全員が記載された住民票、母子健康手帳の写し |
| 配偶者と離婚・別居した | 同上 |
| 配偶者が病気などで育児が困難 | 医師の診断書 |
| 本人が再度出産予定/産後である | 母子健康手帳の該当ページの写し |
※上記に該当しない場合は、原則として延長は認められません。
育児休業給付金は、原則として非課税所得に分類され、支給を受けても所得税や住民税は課されません。また、育児休業中に会社から賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払い義務もありません。
さらに、健康保険や厚生年金保険についても、以下の届出を行うことで、会社・本人ともに社会保険料が免除される制度があります。
【社会保険料免除のための申出】
| 項目 | 内容 |
| 提出期限 | 育児休業開始日以降、育児休業終了日の翌日から起算して1か月以内 |
| 提出書類 | ・育児休業等取得者申出書(新規・延長) |
| 提出先 | 年金事務所 |
| 提出方法 | ・窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)対応 |
この申出により、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の、毎月の報酬にかかる保険料が免除されます。
育児休業給付金の申請に関しては、会社側・従業員側ともに不安や疑問を抱きやすいポイントがいくつかあります。
ここでは、実務の中でよく聞かれる質問について、わかりやすく解説します。
育児休業給付金の支給申請時期が過ぎた・忘れていた場合はどうなりますか?
育児休業給付金の申請には期限があり、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に手続きを行う必要があります。
期限を過ぎると、原則としてその期間分の給付金は受け取れません。
ただし、天災や病気などやむを得ない理由がある場合に限り、育児休業開始日から2年以内であれば、遡って申請(遡及申請)できる可能性もあります。
ただし、単なる失念などでは認められないケースがほとんどです。
会社側の申請漏れが原因で期限を過ぎた場合、従業員が給付金を受け取れず、信頼関係の悪化や労務リスクにつながる恐れがあります。
申請漏れに気づいたら、すぐに管轄のハローワークに相談しましょう。
トラブルを防ぐには、社内でのスケジュール管理と申請チェック体制の整備が重要です。
男性の育児休業給付金の申請方法はどうなりますか?
男性が育児休業を取得する場合も、女性(母親)と同様の受給資格要件(雇用保険への加入、休業前の就業実績など)を満たせば、育児休業給付金の支給対象となります。
申請の手続きや必要書類(休業開始時賃金月額証明書、申請書、賃金台帳、出勤簿、母子手帳の写し等)も、基本的には女性の場合と変わりません。
ただし、男性は出産予定日から育児休業を取得できる点や、2022年に創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」という別の休業制度があり、そちらを利用する場合は「出生時育児休業給付金」の対象となる点など、男性特有の制度もあります。
さらに、夫婦で育児休業を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」制度による支給期間の延長や、「出生後休業支援 給付金」の対象となる可能性もありますので、関連制度も含めて確認するとよいでしょう。
給付金は申請してからどのくらいで振り込まれますか?
ハローワークでの支給決定後、申請書で指定された従業員の口座に給付金が振り込まれるまでの期間は、通常1〜2週間程度が目安とされています。ただし、ハローワークの処理状況や混雑具合によっては、若干前後することもあります。
特に初回の申請の場合は、受給資格の確認や賃金額の決定などの審査に時間がかかるため、申請書類を提出してから最初の給付金が振り込まれるまでには、育児休業 開始から2~3か月程度かかることも珍しくありません。
2回目以降の継続申請については、初回ほどの時間はかからず、申請から比較的速やかに振り込まれることが多いですが、ハローワークの処理状況によって変動する可能性はあります。従業員には、特に初回は振込まで時間がかかる旨を伝えておくとよいでしょう。
賞与(ボーナス)は育児休業給付金の金額に影響しますか?
原則としてボーナス(賞与)が育児休業給付金の支給金額に影響することはありません。育児休業給付金の支給額は、育休開始前の6か月間の賃金をもとに算出されます。
賞与のように臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、この計算の基礎に含まれません。したがって、育児休業 開始前に賞与が支払われていても給付額は増えませんし、育休期間中に賞与が支給されたとしても、それが理由で給付金が減額されることもありません。
育休中に在宅で少し仕事をしたら給付金は止まりますか?
育児休業中でも、一時的・短時間の就業であれば給付金の対象外にはなりません。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 支給単位期間あたりの就業日数が10日以下
(または、就業時間が80時間以下)
この上限を超えて就業した場合は、その期間の給付金は支給されません。
さらに、上限内に収まっていたとしても、就業により会社から賃金の支払いがあった場合は、給付金の額が減額調整されることがあります。
従業員が育休中に在宅ワークや一部出勤を希望する場合、会社としては制度上の影響をきちんと説明し、事前に確認・同意を得る体制を整えておくことが大切です。就業実績については、出勤簿やタイムカードなどでの日数・時間の記録と賃金額の管理が求められます。
自営業やフリーランスには何か支援はありますか?
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者を対象とした制度です。そのため、雇用保険に加入していない自営業者やフリーランスの方は、残念ながら育児休業給付金の支給対象とはなりません。
育児休業中の所得補償を目的とした、これに代わる国の支援制度は、現在のところ設けられていません。
ただし、出産に際しては、国民健康保険などから「出産育児一時金」(出産費用の補助)が支給されたり、国民年金加入者であれば保険料の免除制度が利用できたりします。
また、お住まいの自治体が独自に子育て支援を行っている場合もありますので、市区町村の窓口などで利用できる制度がないか確認してみるとよいでしょう。
育児休業給付金は、従業員の育児と仕事の両立を支援するための重要な制度です。この恩恵を従業員が確実に受け、安心して休業し職場復帰するためには、会社(事業主・担当者)が申請方法と手続きを正確に把握し、責任を持って実行することが不可欠となります。
初回申請における必要書類の準備や提出期限の厳守はもちろんのこと、特に重要なのが育休期間中、原則として2か月ごとに行う継続申請です。申請ミスや期限遅れは給付金の支給遅延を招き、従業員の生活に影響を与えるだけでなく、会社への信頼を損なうことにも繋がりかねません。
育児休業は、従業員にとって人生の一大イベントであると同時に、会社にとっても職場環境や信頼関係の質が問われるタイミングなのです。
また、延長申請の要件や産後パパ育休・出生後休業支援 給付金といった最新制度への対応も求められます。育児・介護休業法は改正も頻繁なため、常に厚生労働省の資料などで最新情報を確認する姿勢が大切です。
もし、自社での対応に不安がある場合や複雑なケースに直面した際は、社労士など専門家への相談も有効な選択肢でしょう。
確実な給付とスムーズな手続きのために、今一度、社内の申請 業務フローやスケジュール管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。
適切な対応は、従業員の円滑な職場復帰を支え、ひいては企業の発展にも貢献します。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|