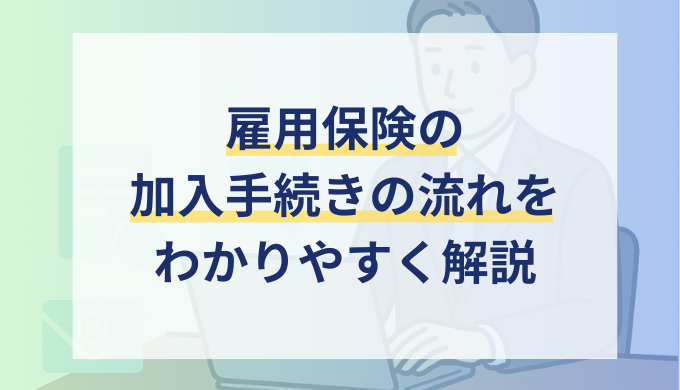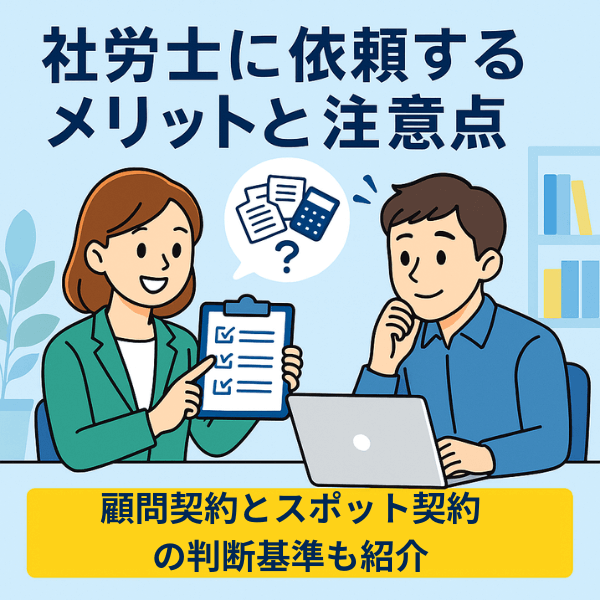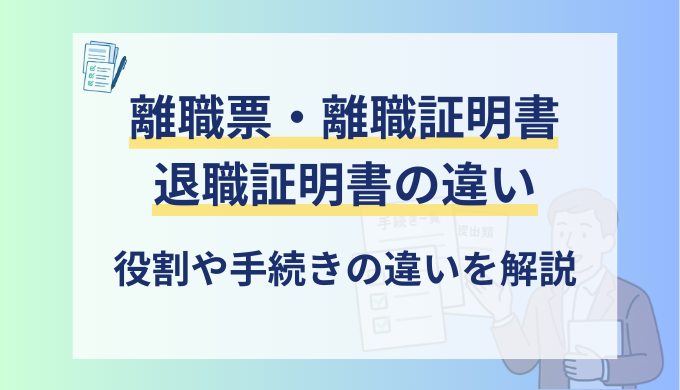従業員を一人でも雇用した場合、事業主には雇用保険の加入手続きを行う義務があります。雇用保険は、失業や育児休業などの際に給付を通じて生活を支える公的制度であり、従業員の安心と企業の信頼を守るうえで欠かせません。
ただし、雇用保険の手続きは労働基準監督署とハローワークへの複数の届出が必要で、提出期限や必要書類も異なります。書類の記載ミスや提出の遅れは、罰則や遡及加入といったリスクにつながるため、正しい流れを理解して進めることが重要です。
本記事では、雇用保険の加入手続きの流れをわかりやすく社労士が解説します。労働基準監督署で行うべきこと、ハローワークで行うべきことを順番に追いながら、必要書類や期限、注意点まで網羅的に紹介しています。
この記事を最後まで読めば、事業主は初めての雇用保険手続きでも迷わず進められるようになり、従業員に安心を提供できる、信頼される職場環境の第一歩を踏み出せます。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
雇用保険とは、従業員が失業した場合や育児・介護で休業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定を図ることを目的とした、政府が管掌する強制的な公的保険制度です。
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種や規模にかかわらず原則として「適用事業所」となり、雇用保険への加入が法律で義務付けられています。雇用保険の手続きを怠ると罰則の対象となる可能性があるため、事業主は制度の概要を正しく理解しなければなりません。
手続きは、主に管轄の労働基準監督署(労働保険関係の成立手続き)とハローワーク(雇用保険の事業所設置や従業員の資格取得手続き)で行います。
なお、一般的に「労働保険」という言葉が使われることがありますが、労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。このうち雇用保険は、従業員の雇用の安定と失業の予防に関わる保険制度と覚えておきましょう。
雇用保険の加入対象となる従業員
雇用保険の加入対象となる従業員は、国が定める基本的な要件をすべて満たす労働者です。事業主は、従業員を雇用するたびに、従業員が雇用保険の加入要件に該当するかどうかを正確に判断する必要があります。
雇用保険の被保険者となる主な基本要件は、以下の3つです 。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上継続して雇用される見込みがあること
- 昼間学生ではないこと
正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、有期契約労働者であっても、上記の要件を満たす場合は被保険者として必ず加入手続きを行わなければなりません。
ただし、学生の扱いには例外があります。夜間学部や定時制、通信課程、または休学中の学生は適用除外とはならないため、他の労働時間や雇用見込みの条件を満たせば、雇用保険の被保険者となります。
一方で、代表取締役や役員、個人事業主本人は、原則として雇用保険の対象外です 。
【雇用保険の加入対象になる?ならない?】
STEP 1:役員・事業主の確認
質問:従業員は、会社の役員や個人事業主本人ですか?
はい(YES)の場合 → 加入対象外です。
いいえ(NO)の場合 → 次のSTEP 2へ進んでください。
STEP 2:労働時間の確認
質問:1週間の所定労働時間は20時間以上ですか?
いいえ(NO)の場合 → 加入対象外です。
はい(YES)の場合 → 次のSTEP 3へ進んでください。
STEP 3:雇用期間の確認
質問:31日以上、継続して雇用される見込みがありますか?
いいえ(NO)の場合 → 加入対象外です。
はい(YES)の場合 → 最後のSTEP 4へ進んでください。
STEP 4:学生かどうかの確認
質問:従業員は、昼間学生ですか?
はい(YES)の場合 → 加入対象外です。(※夜間・通信・休学中は除く)
いいえ(NO)の場合 → 【加入対象】となります。
※上記の全てのステップをクリアした従業員が、雇用保険の加入対象となります。
特にパートタイマーやアルバイトを雇用する際は、労働時間や雇用期間の条件を雇用契約書で明確にし、加入漏れがないよう注意が必要です。また、65歳以上の高年齢労働者も「高年齢被保険者」として加入対象となるため、手続きを忘れないようにしましょう 。
雇用保険の加入条件や制度の詳しい内容については、下記の記事でわかりやすく解説しています。
 雇用保険とは?加入条件や手続き、計算方法までわかりやすく解説
雇用保険とは?加入条件や手続き、計算方法までわかりやすく解説
雇用保険の加入手続きは、まず労働基準監督署で労働保険全体の加入手続き(労働保険関係成立届の提出)を行い、その後ハローワークで雇用保険の加入手続き(雇用保険適用事業所設置届の提出)を行うのが基本的な流れとなります。
手続きをスムーズに進めるために、全体の流れと必要書類を事前に確認しておきましょう。雇用保険の加入手続きは、以下の順番で進めます。
従業員を雇用した日(保険関係が成立した日)から始まります。まずは事業所を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出します。
成立届を提出した後、その年度末までの労働保険料を概算で計算し、「労働保険概算保険料申告書」を提出・納付します。
労働保険の手続きと並行して、事業所を管轄するハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。これにより、事業所が雇用保険の適用事業所となります。
従業員ごとに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークへ提出します。これにより、従業員が雇用保険の被保険者となります。
雇用保険の提出書類・提出先・提出期限の一覧表
各手続きで必要となる主な書類、提出先、提出期限は以下の通りです。
| 提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 労働保険関係成立届 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した日(従業員を雇用した日)の翌日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または日本銀行(代理店である金融機関も可) | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 所轄のハローワーク | 事業所を設置した日(雇用保険の対象となる従業員を初めて雇用した日)の翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄のハローワーク | 資格取得の事実があった日(従業員を雇用した日)が属する月の翌月10日まで |
従業員を初めて雇用する事業主は、労働保険(労災保険と雇用保険)への加入が法律で義務付けられています。
この手続きは「①労働基準監督署 → ②ハローワーク」の順番で、それぞれ定められた期限内に完了させる必要があり、手続きの遅延や漏れは罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
主な手続きの流れは以下の通りです。
- 【労働基準監督署】労働保険関係成立届 の提出
- 【労働基準監督署・金融機関】労働保険概算保険料申告書 の提出・納付
- 【ハローワーク】雇用保険適用事業所設置届 の提出
- 【ハローワーク】雇用保険被保険者資格取得届 の提出
以下では、各ステップの具体的な内容と期限について解説しますので、順番に確認し、確実な手続きを進めましょう。
労働保険関係成立届の提出
初めて従業員を雇う場合、まず最初に行うのが「労働保険関係成立届」の提出です。これは、事業所として労働保険(労災保険・雇用保険)の適用対象となるための手続きで、法人・個人事業主を問わず義務付けられています。
この届出を提出し受理されると、事業所に労働保険番号が付与されます。この番号は、今後の保険料の納付やハローワークでの手続きに必ず必要となる重要なものです。
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(従業員を雇った日)の翌日から10日以内 |
| 主な必要書類 | ・労働保険関係成立届・履歴事項全部証明書(登記事項証明書)の写し(法人の場合)・事業主の住民票の写し(個人事業主の場合)・事業の概要資料(業種判定の参考資料) |
【実務ポイント】
届出の控えは、受理印を押してもらって必ず受け取り、大切に保管してください。この後のハローワークでの手続き(雇用保険適用事業所設置届)の際に、添付書類として提出を求められます。
労働保険概算保険料申告書の提出・納付
労働保険関係成立届を提出したら、次はその年度末(3月31日)までの見込み賃金総額をもとに、概算の労働保険料を申告・納付します。
この労働保険概算保険料申告書はあくまで概算での前払いであり、支払った保険料は翌年度の「年度更新」という手続きで、実際に支払った賃金総額をもとに計算した確定保険料と精算されます。
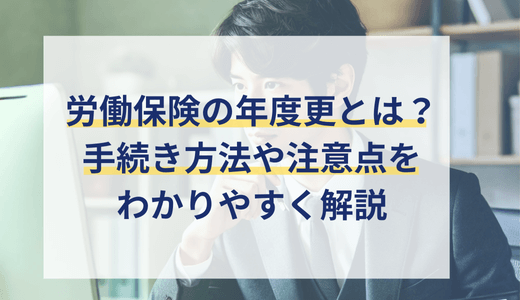 【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
【令和7年度】労働保険の年度更新の計算方法や手続き、申告書作成時の注意点をわかりやすく解説
| 提出先 | 所轄の労働基準監督署、都道府県労働局 ※労働保険事務組合に委託している場合は組合経由で提出 |
| 納付先 | 日本銀行、銀行、信用金庫、郵便局などの金融機関 |
| 提出・納付期限 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
| 主な必要書類 | ・労働保険概算保険料申告書・その年度末までの賃金総額の見込額・業種ごとに定められた労働保険料率 |
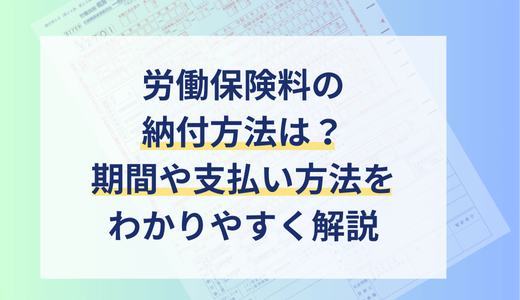 労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
労働保険料の納付方法・流れを支払い時期や分割納付をまじえ社労士が解説
【実務ポイント】
納付した際の控えは、翌年度の「年度更新」で保険料を精算するまで大切に保管してください。特に新設法人の場合、賃金総額をどのように見積もったか(従業員数、給与、賞与の見込みなど)のメモを残しておくと、翌年度の年度更新や調査の際にスムーズに対応できます。
雇用保険適用事業所設置届の提出
労働基準監督署での手続きが完了したら、次に事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
これにより、事業所が正式に雇用保険の適用事業所として登録されます。この手続きには、先だって労働基準監督署で受理された「労働保険関係成立届」の控えが添付書類として必須となりますので、必ず準備してください。
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) |
| 提出期限 | 事業所を設置した日(初めて従業員を雇った日)の翌日から10日以内 |
| 主な必要書類 | ・雇用保険適用事業所設置届・労働保険関係成立届の事業主控(労働保険番号の確認のため)・履歴事項全部証明書(法人の場合)・事業所の所在地や実在を確認できる書類(賃貸借契約書のコピーなど) |
雇用保険被保険者資格取得届の提出
これまでの手続きで事業所が雇用保険の適用事業所となった後、最後に行うのが従業員一人ひとりを被保険者として登録する「雇用保険被保険者資格取得届」の提出です。
この手続きは、従業員を雇用するたびに必要です。正社員や契約社員だけでなく、パートタイマー・アルバイトであっても、以下の加入要件をすべて満たす場合は対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 昼間学生ではないこと
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 従業員を雇用した月の翌月10日まで |
| 主な必要書類 | ・雇用保険被保険者資格取得届(マイナンバーの記載が必須)・労働条件が確認できる書類(雇用契約書、労働者名簿、出勤簿など)・前職の「雇用保険被保険者証」(従業員が持っている場合) |
手続きが完了すると、ハローワークから「雇用保険被保険者証」と「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されますので、速やかに本人に渡してください。
既に労働保険・雇用保険の適用事業所となっている事業主が、2人目以降の新しい従業員を雇い入れる場合の手続きについて解説します。
初めて従業員を雇用する際と比べて手続きは大幅に簡素化され、原則としてハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するだけで完了します。
初めて従業員を雇用するときに必要な会社側の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてチェックしてください。
 【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
【必須】初めて従業員を雇用した際に会社が行う社会保険手続き9選とは?
一度、事業所としての登録(労働保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届)が完了していれば、その後の手続きは従業員個人を保険に加入させる届出のみとなります。
| 提出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 従業員を雇用従業員を雇用した月の翌月10日までした月の翌月10日まで |
| 準備する書類 | ・雇用保険被保険者証(前職がある従業員。番号の統一管理に必須)・マイナンバー(個人番号)と本人確認書類・雇用契約書・勤務シフト・就業規則(所定労働時間と31日以上の見込みの根拠資料)・会社の押印の要否・添付物の要否は所轄ハローワークの運用に従う |
【実務ポイント】
届出書への押印の要否や、上記以外の添付書類(賃金台帳や出勤簿のコピーなど)が必要かどうかは、提出先のハローワークの運用によって異なる場合があります。不明な点は事前に管轄のハローワークへ確認することをお勧めします。
「雇用保険被保険者資格取得届」をはじめとする各種手続きは、ハローワークの窓口への持参や郵送だけでなく、政府の電子申請システムを利用したオンライン申請も可能です。
ハローワークの開庁時間を気にすることなく24時間いつでも申請できるため、手続きにかかる手間やコストを大幅に削減できます。さらに、郵送中の紛失といった情報漏洩のリスクを低減できる点も、電子申請の大きなメリットです。
雇用保険の手続きは、従業員を一人でも雇用するすべての事業主に課せられた法的義務です。手続きを正しく行わないと、加入漏れや期限超過はもちろん、加入要件の誤認やマイナンバーの管理不備といった、様々な実務上のリスクにつながります。
以下では、事業主が特に注意すべき点を解説します。
未加入のままだと法律違反となり罰則がある
雇用保険の加入要件を満たす従業員を雇用しているにもかかわらず、事業主が手続きを怠った場合、雇用保険法に基づく法律違反となります。
未加入が発覚した場合、ハローワークからの指導が入るだけでなく、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
◯過去の保険料の遡及徴収(追徴金含む)
原則として過去2年間にさかのぼり、本来支払うべきだった労働保険料と、さらに追徴金が徴収されます。
◯各種助成金の利用制限
雇用調整助成金など、国が提供する様々な助成金が利用できなくなる不利益が生じます。
◯刑事罰(悪質な場合)
指導に再三応じないなど、特に悪質なケースでは「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることがあります。
もし未加入の状態に気づいた場合は、決して放置せず、速やかに管轄のハローワークに相談の上、必要な期間を遡って「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。
雇用保険に未加入の場合のリスクや罰則について、詳しくは以下の記事で解説しています。
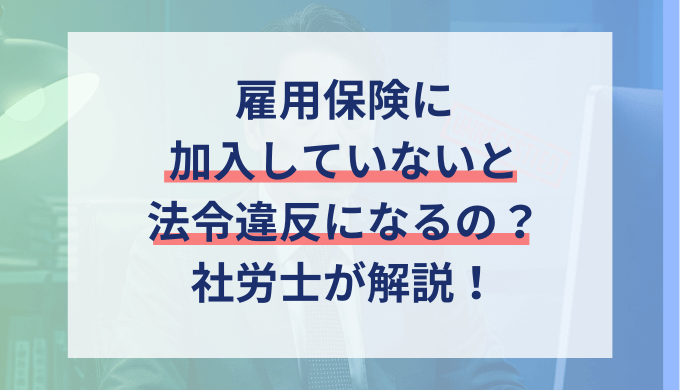 雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
雇用保険に未加入だと違法?入ってない場合の罰則と発覚時の対処法を解説
加入条件を満たさなくなった場合は資格喪失手続きをする
従業員が以下の理由などで雇用保険の加入要件を満たさなくなった場合、事業主は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する義務があります。
- 退職または死亡
- 週の所定労働時間が20時間未満になった
- 役員に就任した(労働者性がなくなった場合)
- 昼間学生になった
この手続きを怠ると、本来支払う必要のない保険料を払い続けてしまうことになります。提出期限は、原則として資格喪失の事実があった日(退職日など)の翌日から10日以内です。
特に従業員が退職する場合、本人が失業手当(基本手当)の受給を希望するときは、「資格喪失届」とあわせて「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません。
この離職証明書をもとに、従業員が失業手当を受け取るために不可欠な「離職票」が交付されます。
資格喪失の手続きや、従業員の退職時に必要となる社会保険手続き全般については、以下の記事で詳しく解説しています。
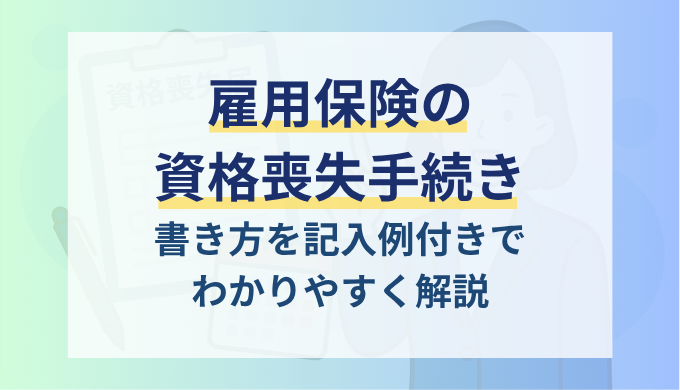 雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を記入例付きで解説!添付書類や提出時の注意点も紹介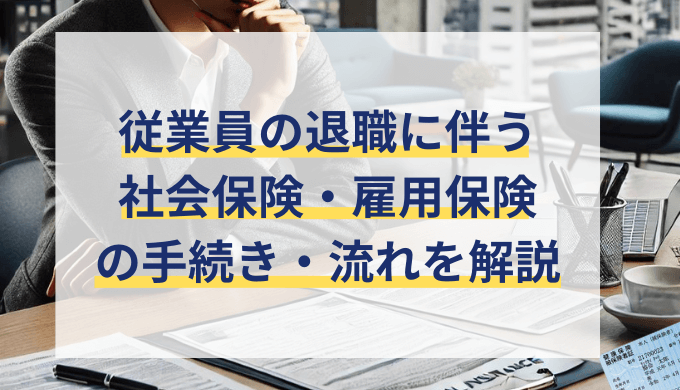 従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
従業員の退職で会社側が行う社会保険・雇用保険の手続き!必要書類や流れを解説
手続きにはマイナンバーが必要
雇用保険に関するすべての届出(資格取得届、資格喪失届など)には、原則として対象となる従業員のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
手続きを円滑に進めるため、従業員を雇用する際には、事前にマイナンバーを提出してもらうよう案内しておきましょう。また、収集したマイナンバーは法律に基づき、厳重に管理しなければなりません。
65歳以上、パート・アルバイト、短期労働者も条件を満たせば手続きをする
雇用保険の対象は、正社員に限りません。
65歳以上の高年齢労働者や、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員といった有期雇用の労働者であっても、以下の要件を両方満たす場合は加入義務があります。(昼間学生は原則除外)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 昼間部の学生ではないこと
「うちはパートだけだから関係ない」と思い込まず、一人ひとりの労働条件をきちんと確認し、対象となる従業員がいないか必ずチェックしてください。
【ケース別】雇用保険の加入対象となるかの早見表
| 対象者 | 加入義務 | 備考(補足) |
|---|---|---|
| パートタイマー・アルバイト | あり | 上記の要件を満たす場合は、名称にかかわらず加入対象です。 |
| 65歳以上の労働者 | あり | 「高年齢被保険者」として加入します。適用される要件は同じです。 |
| 短期・日雇い労働者 | 条件による | 当初の契約が31日未満でも、契約更新が見込まれる場合などは加入対象となります。 |
| 昼間部の学生 | 原則なし | 要件を満たしていても、原則として加入対象外です。(※休学中などは例外あり) |
| 夜間・通信課程の学生 | あり | 学生であっても、要件を満たす場合は加入対象となります。 |
雇用保険の加入手続きは、事業主に課せられた法的義務であり、従業員の万一の場合の生活を守るための大切なセーフティネットです。正社員だけでなく、パート・アルバイトや65歳以上の高年齢者も、法律で定められた要件を満たせば必ず加入させなければなりません。
手続きの基本的な流れは、まず①労働基準監督署で「労働保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出し、次に②ハローワークで「適用事業所設置届」と従業員ごとの「資格取得届」を提出するという順序になります。
それぞれの手続きには厳格な提出期限が定められており、遅延すると保険料の遡及徴収や罰則のリスクが生じます。また、手続きにおけるマイナンバーの適正な管理や、転職者などの被保険者番号の確認も、事業主が責任をもって行うべき重要なポイントです。
従業員の入退社や雇用形態、就業条件の変更があった際は、その都度、雇用保険の加入条件について改めて確認し、加入漏れや喪失手続き忘れが無いよう注意しましょう。
これらのポイントを押さえ、適正な手続きを心掛けましょう。もし判断に迷うことがあれば、管轄のハローワークや社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
スポット申請代行ができる社労士クラウドについて
「雇用保険の手続きが複雑で、自社だけで対応するのは不安…」 「年に数回の手続きのために、顧問契約で毎月費用を払うのは負担が大きい…」 「必要な業務だけを、専門家にピンポイントで依頼したい」
このようなお悩みをお持ちの事業主様や人事担当者様には、「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスがおすすめです。
当サービスでは、雇用保険の各種手続きはもちろん、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届など、専門知識が必要な手続きを顧問契約不要で、必要な業務だけを1件から社会保険労務士にご依頼いただけます。
専門家である社労士が、最新の法令に基づいて正確かつ迅速に手続きを代行しますので、お客様は面倒な手続き業務から解放され、貴重な時間をコア業務に集中させることが可能です。オンラインで全国どこからでも簡単にご依頼いただけますので、手続きに不安がある場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
理由に賃金や休暇などの待遇で不合理な差を設けることはできません。こうした複雑な法的要件をクリアするためにも、専門家である社労士への相談が有効です。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|