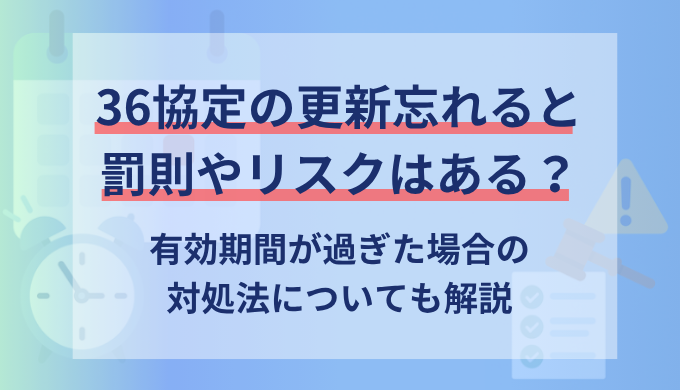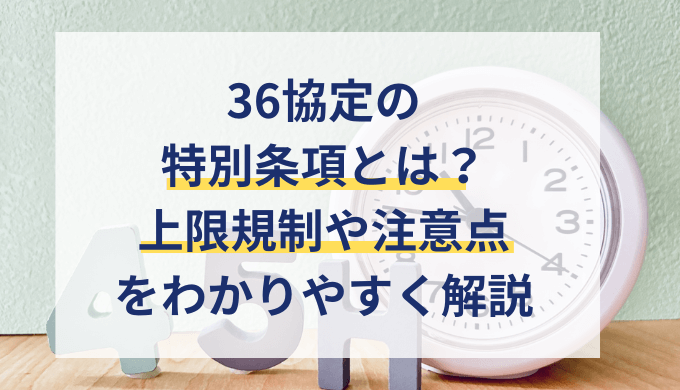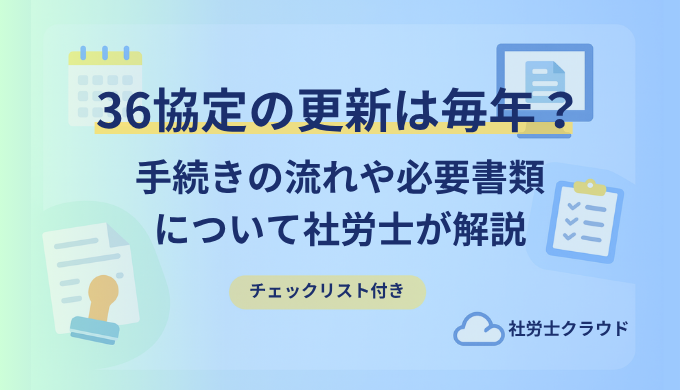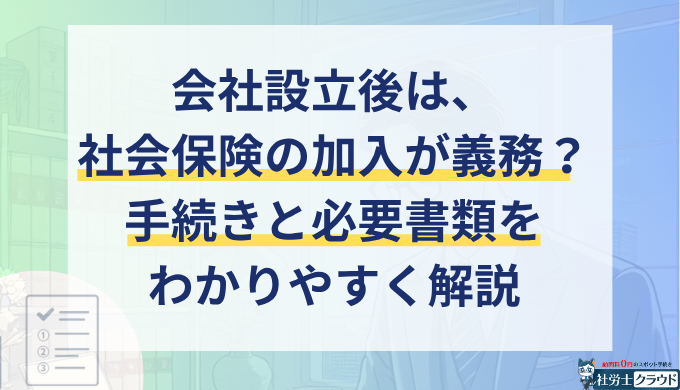36協定(サブロク協定)の更新忘れは、単なる事務手続きミスではなく、発覚した瞬間から会社が労働基準法に違法している状態に入る重大な問題です。
残業命令の根拠が消え、刑事罰の可能性、従業員からの残業命令拒否、企業名の公表による信用低下、そして「後から提出しても過去に遡れない」という不利益が一気に現実になります。
小規模企業や個人事業主ほど担当が限られ、うっかりが致命傷になりやすい点にも注意が必要です。
本記事では、36協定の更新忘れで生じるリスクや罰則、発覚後の緊急対応方法、そして更新忘れを予防する方法についてわかりやすく社労士が解説します。
「いつまでに」「何を」「誰が」やるかが明確になれば、更新忘れは防げます。
まずは、この記事で紹介する手順に沿って、一つずつ着実に対応を進めていきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
36協定の更新忘れは、「うっかり忘れていた」という単純な事務ミスでは決して済みません。
一つのミスが、法的な罰則、従業員との信頼関係の悪化、そして社会的な信用の失墜といった、深刻な経営リスクに次々と連鎖していく可能性があります。
特に、運送業、建設業、IT業、介護・医療業など、恒常的に時間外労働が発生しがちな職場では、日々の残業がそのまま経営リスクに直結します。
「担当者のうっかりミス」で済ませず、経営課題としてその重大性を理解することが不可欠です。
ここでは、36協定の更新忘れで特に問題になりやすい4つの経営リスクを解説します。
【刑事罰】経営者も対象!「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
36協定を届け出ずに法定労働時間を超えて従業員を働かせる行為は、労働基準法第32条違反に該当し、同法第119条に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。
これは交通違反の反則金のような行政罰(過料)とは違い、前科となりうる重い「刑事罰」です。
さらに、罰則の対象は法人としての会社だけでなく、違法な残業を指示・容認した経営者や現場管理職といった個人も含まれます。労働基準監督署の調査で「忙しくて忘れていた」という言い訳は通用しません。
【命令拒否】従業員は残業命令を拒否できる
そもそも、会社が従業員に残業を命じるためには、①就業規則などによる規定と、②有効な36協定の届出という2つの法的根拠が揃っている必要があります。
36協定が失効(有効期間が切れている)している状態では、この根拠の一方が崩れているため、従業員は残業命令を合法的に拒否する権利を持ちます。
もし、残業を拒否した従業員に対して評価を下げたり、叱責したりといった不利益な取り扱いをすれば、その措置は無効です。そればかりか、パワーハラスメントとして逆に企業が訴えられるリスクさえ生じます。
現場の混乱を避けるためにも、36協定の更新忘れが発覚した時点で「所定時間内で業務を終える運用」へ即時に切り替えるという、経営トップの明確な指示が不可欠です。
【信用失墜】企業名が公表される可能性
金銭的なペナルティ以上に深刻なのが、社会的な信用の失墜です。
労働基準法違反が悪質であると判断され、労働基準監督署から検察へ書類送検されたような場合、厚生労働省がウェブサイト上で「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、企業名、事業場名、違反内容が公表されることがあります。
これは、いわゆる「ブラック企業リスト」としてインターネット上に残り続け、結果的に社会に広く認知され、企業の社会的信用に長期的なダメージを与えます。
一度公表されれば、優秀な人材の採用が困難になる、従業員の離職が相次ぐ、取引先から契約を見直される、金融機関からの融資が厳しくなるといった、事業の根幹を揺るがす事態に発展し、あらゆる側面に深刻な影響が及びます。
【遡及不可】後から提出しても過去の違反は消えない
36協定の効力は、労働基準監督署が届出を受理した日から将来に向かってのみ発生します。過去の違反期間に遡って適用されることはありません(不遡及の原則)。
「急いで提出すれば、過去の残業も合法になる」という考えは、根本的な誤りです。
例えば、9月30日に有効期間が切れ、慌てて10月15日に再届出したとします。
この場合、協定が有効になるのは10月15日からです。10月1日から14日までの間に行わせた時間外労働が違法であったという事実は、決して消えません。
ただし、だからといって再届出が無意味なわけではありません。速やかに違法状態を是正したという事実は、労働基準監督署に対して改善の意思を示すことになり、その後の行政指導の内容に影響を与える可能性は考えられます。
では、これまでの重大なリスクを踏まえ、発覚後は具体的に何を、どのような順番で行うべきなのでしょうか。
36協定を締結・届出せずに従業員に残業させた場合の罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。
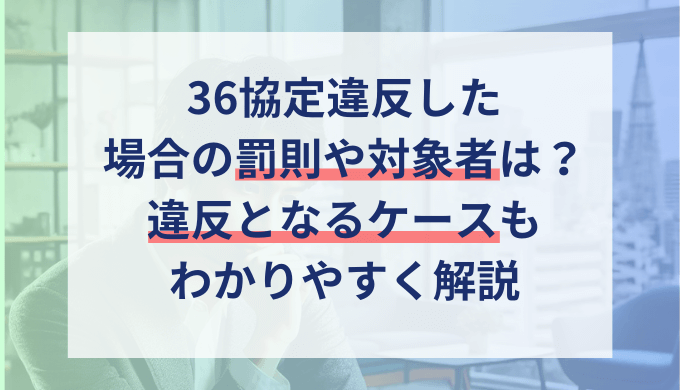 36協定に違反するとどうなる?罰則や発覚するケースを社労士が解説
36協定に違反するとどうなる?罰則や発覚するケースを社労士が解説
次項で、ダメージを最小化するための緊急対応策をステップごとに解説します。
これまで解説したような深刻な経営リスクを回避し、ダメージを最小化するためには、発覚後いかに迅速に行動できるかが鍵となります。
36協定の有効期間が切れた時点で、会社は時間外労働・休日労働を命じる根拠を失い、労働基準法に違反している状態にあります。そのため、一刻も早い対応が求められます。
36協定の有効期間が過ぎてしまった緊急事態では、①時間外労働の即時停止、②36協定の迅速な再届出、③未払い賃金の精算という3つのステップを、この順番通りに進めることが極めて重要です。
この手順を踏むことで、継続的な法令違反を食い止めると同時に、万が一、労働基準監督署の調査が入った際に「発覚後、直ちに是正措置を講じた」という客観的な事実を示すことができます。
担当者任せにせず、経営トップの主導で全社的な対応に切り替えてください。
ステップ①:全従業員の時間外労働・休日労働を即時全面停止する
36協定の更新忘れが発覚して、最初に行うべき最も重要な行動は、全従業員に対する時間外労働および休日労働を、即時かつ全面的に停止させることです。
有効な36協定がない状態では、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員を働かせる法的な根拠が一切ありません。つまり、協定が無効な状態での残業や休日出勤は、たとえ1分であってもすべてが違法行為となります。
この措置は、単に担当部署からの通知で済ませてはいけません。 具体的には、以下の2点を直ちに実行してください。
- 経営トップの名前で「新たな36協定が受理されるまで、一切の時間外・休日労働を禁止する」と全社に文書で通達します。
- 全部門の管理職に対し、本日の業務内容と人員体制を見直し、必ず所定労働時間内に業務を終えるよう厳命します。
口頭での指示は証拠が残らず、「言った・言わない」のトラブルになりかねません。必ずメールや社内ポータルなど記録に残る形で、日時、対象者、責任者を明確にして通達します。「この業務だけは…」といった例外は一切認めない姿勢が、リスク拡大を防ぐ上で不可欠です。
ステップ②:1日でも早く36協定を再締結し、電子申請で労働基準監督署へ届け出る
時間外労働を完全に停止したら、次は1日でも早く36協定を再締結し、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。
ここで絶対に押さえておくべき重要な原則は、36協定の法的な効力が、社内で労使が協定を結んだ日からではなく、労働基準監督署が協定届を「受理した日」から発生する、という点です。
手続きが1日遅れるごとに、法令違反の状態が1日ずつ長引いてしまいます。
このような時間的猶予のない状況では、郵送や窓口での提出ではなく、24時間365日いつでも手続きが可能なe-Gov(電子政府の総合窓口)を利用した電子申請が最も有効な手段です。
電子申請であれば、原則として即時に届出が完了するため、違法状態を最短で解消できます。
ただ、e-Govの利用には事前のID登録などが必要なため、初めて電子申請をする場合はかえって時間がかかってしまうことも少なくありません。
1日でも早く違法状態を解消したいこの緊急時には、手続きの専門家である社労士に依頼・相談することが最も確実で、結果的に早い解決に繋がります。
ステップ③:過去3年分の未払い割増賃金がないか確認し、速やかに精算する
協定の再締結手続きと並行して、過去の割増賃金(残業代)に未払いがないかを確認し、もしあれば速やかに精算することが不可欠です。
たとえ協定が無効だった期間の労働であっても、従業員が実際に行った時間外労働や休日労働に対しては、労働基準法第37条に基づき、定められた割増率での賃金を支払う義務があります。
この支払義務は、協定の不備によって免除されることは一切ありません。
特に、2020年の法改正によって、従業員が未払い賃金を請求できる期間は3年に延長されています。
今回の更新忘れという問題は、従業員の労働に関する権利意識を高めるきっかけとなり、過去の未払い残業代請求の引き金となる可能性も否定できません。
将来的なトラブルを防ぐためにも、これを機に過去3年分の労働時間管理が適切であったかを自主的に監査し、問題があれば誠実に対応することが賢明です。
36協定の更新忘れは、制度の目的や手順への理解不足から起こります。担当者の注意だけに頼るのではなく、担当者が代わっても揺らぐことのない管理体制を構築することが不可欠です。
ここでは、法律を守るための基礎となる36協定の基本と、毎年必ず行うべき更新手続きの流れを解説します。
そもそも36協定とは?
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定の通称です。
法律で定められた法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて、従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合に、必ず事前に会社と従業員の代表との間で締結し、労働基準監督署へ届け出る必要がある協定です。
この協定は、正社員や契約社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトを含め、雇用形態にかかわらず事業場で働くすべての労働者が対象となります。
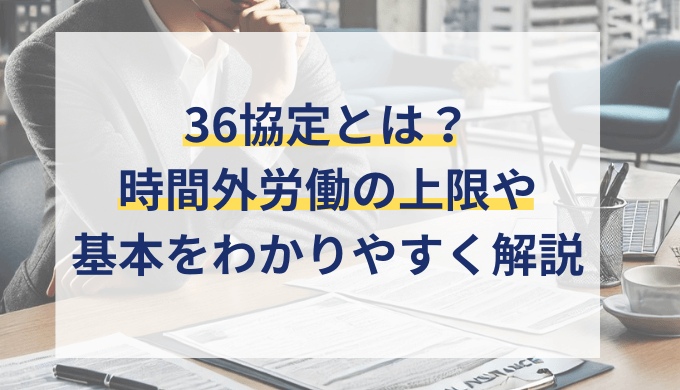 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
また、36協定を結べば無制限に残業させられるわけではなく、時間外労働には上限(原則として月45時間・年360時間など)が法律で定められています。
なお、臨時的な特別な事情があって上限を超える可能性がある場合は、「特別条項付き協定」を結ぶことになりますが、その場合はより厳格な手続きが求められます。
36協定の有効期間と起算日
36協定には、必ず「有効期間」を定めなければなりません。労働者の健康を守る観点から、有効期間は最長でも1年とすることが強く推奨されています。
法律が毎年の更新を求めているのは、会社の事業内容や人員の変化に合わせ、協定の内容を常に実態に即したものに保つためです。
協定の効力が始まる「起算日」は、会社が自由に設定できますが、一度決めたら毎年同じ日付に固定し、更新準備をスケジュール化することが、管理上の最も重要なポイントです。
多くの企業では、会計年度に合わせて「4月1日」を起算日としていますが、自社の繁忙期などを考慮して管理しやすい日付を設定すると良いでしょう。
例えば、「有効期間満了の2ヶ月前には準備を開始する」といった社内ルールを定め、共有カレンダーなどで担当者と管理職がダブルチェックできる体制が理想です。
失敗しない!36協定の更新・届出 5ステップ(従業員代表の選出〜周知義務まで)
36協定を正しく更新するための手続きは、大きく5つのステップに分かれます。特に最初の「従業員代表の選出」は、協定全体の有効性を左右する最も重要なポイントです。
会社の指名や一方的な選任は無効の原因になります。必ず投票や挙手といった民主的な方法で選び、選出プロセスの記録を残してください。
選ばれた代表者と、延長できる時間数や休日労働の条件などを具体的に話し合い、労使双方で合意した内容を協定書として書面にします。
作成した協定書に、会社(使用者)と従業員代表がそれぞれ署名または記名押印することで、正式な合意として成立します。
締結した協定書は、管轄の労働基準監督署へ届け出て初めて法的な効力を持ちます。 24時間提出できるe-Govでの電子申請が最も確実です。
届出を済ませた協定は、社内の見やすい場所に掲示するなどして全従業員に知らせる法律上の義務があります。これを怠ると罰則の対象となるため、必ず実行してください。
参考)36協定の更新は毎年必要?更新手続き流れや必要書類、提出期限を解説
年に一度の36協定の更新は、多忙な業務の中では、つい後回しにされたり忘れられたりしがちです。
だからこそ、個人の記憶や注意深さに頼るのではなく、「仕組み」で更新忘れを防止することが不可欠になります。
ここでは、そのための具体的な再発防止策を3つ紹介します。
【アナログ管理】管理台帳やカレンダーで有効期間を管理する
最も手軽に始められるのが、Excelなどで「労使協定管理台帳」を作成し、Googleカレンダーのようなスケジュールツールと組み合わせる方法です。
管理台帳には、協定の有効期間だけでなく、次回準備を開始すべき日(例:満了日の90日前)などを一覧化します。
その上で、カレンダーには満了日の90日前、60日前、30日前といった段階的なリマインダーを設定し、通知先は担当者に加え、上長や代替担当者など必ず複数名を登録します。
◯メリット
特別なコストをかけずに、すぐにでも始められる点です。また、協定管理の状況が一覧で可視化されるため、チーム内での情報共有や、定期的なチェック会議の議題にしやすくなります。
◯デメリット
やはり、入力や更新作業が人に依存するため、記入漏れや更新忘れといったヒューマンエラーのリスクを完全には防げない点です。この方法を採る場合は、必ず「月1回の台帳レビュー」や「チェックリストによる二重確認」といった、定期的なチェック作業とセットで運用することが不可欠です。
【システム活用】勤怠管理システムのリマインド機能を活用する
より確実性を高めるのが、クラウド型の勤怠管理システムなどが持つ、届出管理やリマインド機能を活用する方法です。各種協定の有効期間を登録しておくことで、システムが自動で更新時期を通知してくれます。
◯メリット
システムが自動で通知を行うため、人的なミスや引き継ぎ漏れのリスクを劇的に減らせます。担当者が誰であっても更新忘れが起こらない「仕組み」を構築でき、属人化からの脱却が可能になります。
◯デメリット
システムの導入・運用にコストが発生します。しかし、一度の更新忘れが招く経営リスクを考えれば、これは「コスト」ではなく、企業のコンプライアンス体制を強化するための有効な「投資」と捉えることができます。
【専門家へ委託】手続きが不安なら社会保険労務士に相談する
最も安全かつ確実な方法が、労働法の専門家である社会保険労務士(社労士)に手続きを委託することです。
社労士に依頼すれば、法改正の反映、従業員代表の選出手順の適法性確認、協定書の作成・レビュー、電子申請の代行、受理後の周知徹底まで、更新サイクル全体をワンストップで任せることができます。
◯メリット
法的な正確性が担保され、担当者の煩雑な手続きや「忘れてはいけない」という心理的負担から解放されるのはもちろん、担当者が交代しても更新業務が滞らない体制を構築できます。これにより、企業は本来注力すべきコア業務に集中できます。
◯デメリット
委託費用が発生します。しかし、更新忘れによって発生しうる刑事罰や多額の未払い残業代の支払いリスクを考えれば、これはコンプライアンス体制を維持するための「保険料」と捉えるのが合理的です。社内の担当者と専門家である社労士の「ダブルチェック体制」を構築することも、突発的な人員の変動に強い組織を作る上で非常に有効です。
例えば「顧問契約はハードルが高い」と感じる場合には、『社労士クラウド』のように、顧問契約なしで36協定の作成・届出や更新案内といった必要なサービスだけを利用できる選択肢もあります。
36協定の更新忘れに関して、実務担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
提出が遅れた場合、遅延理由書は必要ですか?
法律で定められた提出義務はありません。
ただし、労働基準監督署によっては、行政指導の一環として、なぜ提出が遅れたのかという経緯と、今後の再発防止策について文書で報告を求めてくることがあります。
そのように求められた場合は、単なる事務処理と捉えず、会社の反省と改善の意思を示す機会と捉え、誠実に対応することが望ましいでしょう。
割増賃金を支払っていれば罰則を免れますか?
罰則は免れることはできません。
「残業代さえきちんと支払っていれば、36協定の届出は忘れても大丈夫」という考えは、根本的な誤りです。
労働基準法が定める**①割増賃金の支払い義務(第37条)**と、**②36協定の届出義務(第36条)**は、それぞれ独立した法律上の義務です。①と②の両方を満たして初めて、時間外労働は適法となります。
協定を自動更新にすることはできますか?
36協定は自動更新することはできません。
たとえ協定書に「労使双方から特に申し出がない限り、1年間自動的に更新する」といった自動更新条項を設けたとしても、その条項自体が法的に無効と判断されます。
法律が毎年の更新を求めているのは、形骸化した手続きを繰り返すためではありません。その時々の事業場の実態に合わせ、労使間で真摯な話し合いと合意形成を毎年行うことを確保するためです。
本記事で解説してきた通り、36協定の更新忘れは、単なる事務ミスでは済みません。刑事罰、多額の未払い残業代、そして企業の社会的信用の失墜に直結する、極めて重大な経営リスクです。
一度でも更新を忘れてしまうと、その期間が違法であったという事実は消せません。
だからこそ、担当者の記憶や注意深さに頼る属人的な管理体制から脱却し、更新忘れが起こり得ない「仕組み」を構築することが、すべての事業主にとって不可欠。
勤怠管理システムの導入も有効な一手ですが、法改正への対応や、協定の有効性を左右する「従業員代表の適正な選出」といった専門的な判断が求められる場面は少なくありません。
複雑な問題をクリアし、最も安全かつ効率的に管理するためには、労働法の専門家である社労士への相談が最善の選択肢と言えるでしょう。
専門家の活用は、目先のトラブルを回避するだけでなく、企業の持続的な成長を支える「守りの経営」の要です。健全な企業運営を実現するための確実な一手として、「社労士クラウド」のような専門サービスへの相談をぜひご検討ください。
スポット申請代行サービス「社労士クラウド」について
社労士クラウドは、顧問契約が不要で、必要なときにだけ依頼できるスポット申請代行サービスを提供しています。
▼『社労士クラウド』が選ばれる3つの理由
1. 必要な時だけ、無駄のないコストで依頼できる
顧問契約は一切不要です。「今回の36協定の更新だけ」といった、単発の手続きからご依頼いただけます。料金体系もシンプルで分かりやすく、安心してご利用いただけます。
2. オンラインで完結、圧倒的なスピード対応
ご相談から申請完了まで、すべてオンラインでスピーディーに対応します。24時間365日いつでもご依頼いただけるため、日中お忙しい事業主の方でもご自身のタイミングで手続きを進められます。
3. 社労士による確実な手続き
すべての手続きは、経験豊富な社会保険労務士が責任を持って対応します。法改正にも準拠した、法的に有効で確実な手続きをお約束します。
まずは、ご相談ください。
「うちの会社の場合は、まず何から手をつければいい?」 「過去の未払い賃金も心配…」
といった具体的なご相談に、専門家が直接お答えします。更新忘れという緊急事態を乗り越え、安心して従業員を雇用できる体制を、私たちと一緒に整えましょう。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|