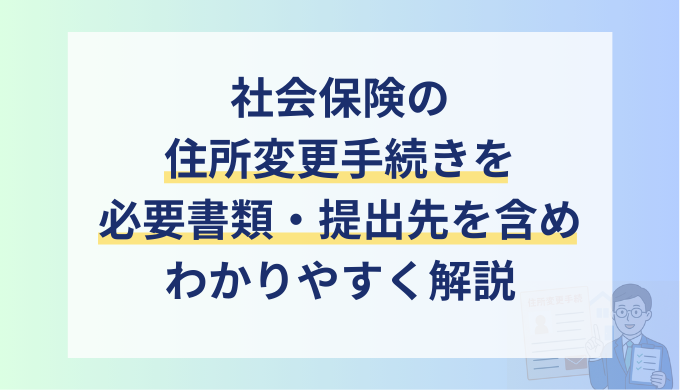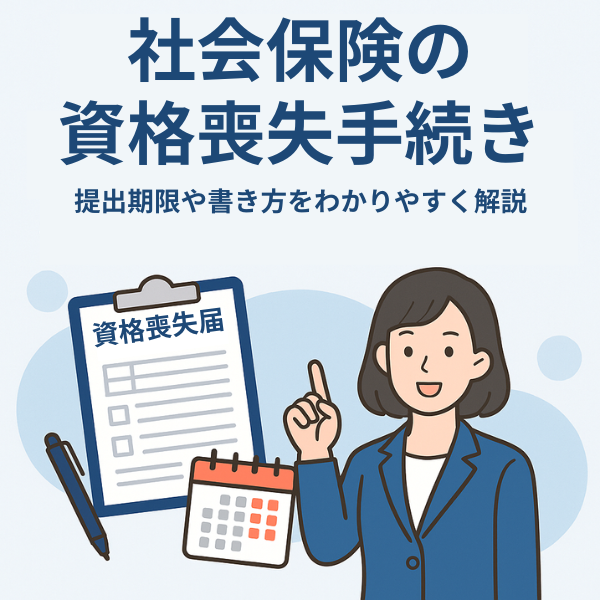社会保険に加入している従業員が引っ越した場合、社会保険の住所変更手続きが必要になります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、原則として「被保険者住所変更届」を事業主が提出する必要があります。一方で、雇用保険に関しては原則として住所変更の届出は不要ですが、労務管理上の対応が求められる場面も少なくありません。
また、マイナンバーと基礎年金番号の連携が済んでいる場合、住所情報が自動で連携されるケースもありますが、すべての従業員に当てはまるわけではなく、提出が必要な例外も存在します。
本記事では、社会保険の住所変更手続きが必要なケースと不要なケースを整理しながら、書類の記入方法・提出先・よくあるミス・扶養家族や役員の場合の注意点まで実務で役立つ情報をわかりやすく解説します。
「うっかり対応を忘れていた…」とならないよう、チェックリスト付きで解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
会社(法人)が引っ越しで住所変更した場合に必要な「本店移転登記」などの手続きは、以下の関連記事で詳しく解説しています。
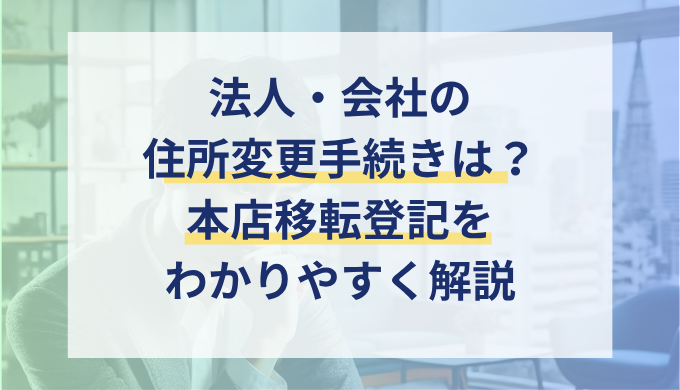 法人(会社)の住所変更手続き一覧!本店移転登記の必要書類や提出先も解説
法人(会社)の住所変更手続き一覧!本店移転登記の必要書類や提出先も解説

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧 ・当日申請・フリー価格・丸投げOK| 2,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
社会保険に加入している従業員が引っ越しをして住所変更があった場合、会社(事業主)は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険でそれぞれ異なる対応が求められます。
健康保険・厚生年金保険については、原則として会社経由での住所変更手続きが必要です。一方で、雇用保険に関する住所変更の届出は、会社側では原則不要となります。
以下で、それぞれの保険制度ごとに必要な対応を詳しく解説します。
健康保険・厚生年金保険の住所変更は原則「必要」
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している従業員が住所変更をした場合、会社は原則として「被保険者住所変更届」を日本年金機構へ提出する必要があります 。この届出は、日本年金機構から従業員へ送付される「ねんきん定期便」や、保険証の再発行時などにおける重要書類を、新しい住所へ正確に届けるために不可欠です。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、住民票の住所を変更した際にその情報が日本年金機構に連携されるため、原則として「被保険者住所変更届」の提出は原則として不要とされています。
【注意点:届出が別途必要になるケース】
以下のようなケースでは、マイナンバー連携済みでも届出が必要になります。
- マイナンバーと基礎年金番号の結びつきが完了していない従業員
- 海外居住者や短期在留外国人である従業員
- 住民票の住所以外の場所(居所)を登録する場合
- 健康保険組合によっては、独自の届出を求めている場合
実務上、個々の従業員の状況を正確に把握するのが難しい場合もあります。そのため、手続きが必要かどうかの判断に迷った際は、後々のトラブルを避けるためにも「被保険者住所変更届」を提出しておくのが最も確実な対応です。
雇用保険の住所変更は「原則不要」だが注意点あり
雇用保険については、従業員の住所が変更されても、会社からハローワークへ届出を行う必要は、原則としてありません。
雇用保険の資格取得や喪失などの主要な届出は、氏名・生年月日・マイナンバーなどの本人特定情報に基づいて管理されているため、住所以外の情報で管理が可能となっています。
ただし、失業給付や育児休業給付金などを申請する場合は注意が必要です。
ハローワークから本人宛に郵送物が届くケースでは、住所情報が最新でないと通知が届かない可能性があります。必要に応じて、従業員本人からハローワークへ直接住所変更を申告することが推奨されます。
他にも会社として対応すべきことが2点あります。
1.労働者名簿の住所を更新する
労働基準法第107条に基づき、会社は従業員の住所を記載した「労働者名簿」を作成し、変更があった場合は遅滞なく更新する義務があります。 雇用保険の届出が不要であっても、社内の労務管理として、必ず最新の住所情報を反映させてください。
2.通勤手当を再計算する
住所変更に伴い通勤経路や距離が変わり、通勤手当の支給額に影響が出る場合があります。 新しい住所を基に通勤手当を再計算し、給与計算に正しく反映させる必要があります。
なお、雇用保険の登録住所は、従業員本人が離職後に失業手当(基本手当)を受給する際などに、本人がハローワークで直接変更手続きを行います。会社側での事前の届出は不要ですが、この点を従業員に案内しておくことで、信頼性の高い人事対応といえます。
【制度別】住所変更時に会社が行う手続きと注意点まとめ
| 保険の種類 | 会社が行う住所変更手続き | 会社が留意すべきこと |
| 健康保険・厚生年金保険 | 原則必要(被保険者住所変更届を年金事務所へ提出) | ・マイナンバー連携済みなら不要な場合あり ・手続き漏れは重要書類の未達リスク |
| 雇用保険 | 原則不要 | ・労働者名簿の更新が必要 ・通勤手当の再計算が必要 |
従業員の引っ越しにより住所が変わった場合、単に社会保険や雇用保険の手続きだけでなく、会社側が正確な住所情報を把握しておくこと自体が重要な管理業務の一環となります。
以下の3つの観点から、住所情報の最新化が不可欠である理由を解説します。
① 労働基準法で労働者名簿を更新する義務があるため
会社は、従業員ごとに「労働者名簿」を作成・管理する義務があり、氏名・生年月日・性別・住所などの情報は、変更があった場合に遅滞なく修正することが法令で定められています(労働基準法第107条)。
住所情報が古いままになっていると、監督署の調査時などに是正を求められる可能性があるため、法令順守の観点からも注意が必要です。
② 総務・労務の業務(社会保険料の算出や通勤手当の再計算等)に必要なため
従業員の住所が変更されると、通勤経路や交通費の支給額に影響が出る可能性があります。通勤手当を正確に支給するためには、現住所に基づいた通勤経路・距離の再確認と再計算が必要です。また、社会保険料の算出や年末調整、住民税の通知書送付先の登録など、各種労務・経理処理にも正確な住所情報は不可欠です。情報が更新されていない場合、給与計算ミスや通知物の誤送が発生するリスクがあります。
③ 従業員の無断欠勤や災害時などに安全配慮義務を行使するため
従業員が連絡なく欠勤を続けた場合や、自然災害・事故など緊急時の安否確認が必要な場面において、会社は「安全配慮義務(民法第415条)」の一環として適切に対応する責任があります。正確な住所を把握していないと、本人や家族に連絡が取れず、対応が遅れることによるリスクや責任問題にも発展しかねません。特に中小企業では、少人数ゆえにこうした緊急対応が属人的になりがちですが、住所情報の更新を徹底することで会社としての信頼性や管理体制を強化することができます。
従業員の住所変更に関する手続きは、届出書の作成から社内業務まで、大きく3つのステップで進めます。全体の流れを把握し、抜け漏れなく対応しましょう。
日本年金機構のウェブサイトから「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」をダウンロードし、これまでの解説を参考に必要事項を正確に記入します。
記入した届出書を、会社の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所へ、郵送・窓口持参・電子申請のいずれかの方法で速やかに提出します。
届出の提出後、以下の社内業務も忘れずに行い、一連の手続きを完了させます。
- 労働者名簿の住所を更新する
- 通勤手当を再計算し、給与に反映させる
- 緊急連絡先の名簿などを更新する
詳しい記入方法やケース別の提出書類については、次項で解説します。
従業員の引っ越しにより住所が変わった場合、会社は原則として「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」を提出する必要があります 。この届出は、年金事務所や健康保険組合に登録されている住所情報を正しく更新し、通知書類などが確実に届くようにするための重要な手続きです。
健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届とは?
「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」は、従業員の住所を最新情報に更新し、日本年金機構や健康保険組合の登録内容を正確に保つための届出書類です 。
この届出書は、多くの場合、以下の2枚が複写式になっています 。
- 1枚目:被保険者(従業員本人)用
- 2枚目:国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)用
どちらの書類を提出するかは、会社の保険加入状況と住所が変わった人に応じて異なります。
会社の加入制度と、誰の住所が変更になるかによって、提出する書類が異なります。自社の状況に合わせて、提出すべき書類を確認してください。
ケース①:協会けんぽの健康保険と厚生年金保険に加入(または厚生年金保険のみ加入)の場合
| 住所変更がある方 | 提出書類 |
| 被保険者と被扶養配偶者の両方 | 1枚目と2枚目を提出 |
| 被保険者のみ | 1枚目のみ提出(2枚目は不要) |
| 被扶養配偶者のみ | 2枚目のみ提出(1枚目は不要) |
ケース②:協会けんぽの健康保険のみに加入の場合
| 住所変更がある方 | 提出書類 |
| 被保険者(被扶養配偶者の有無を問わず) | 1枚目のみ提出(2枚目は不要) |
| 被扶養配偶者のみ | 届出は不要 |
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を指します 。
マイナンバー制度の導入により、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者は、原則として住所変更届の提出が不要になりました 。しかし、以下に該当する場合は、引き続き届出が必要です。
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない従業員の住所が変わったとき
- 海外居住者や、短期在留の外国人である従業員の住所が変わったとき
- 住民票の住所以外の場所(居所)を登録・変更したいとき
- 加入している健康保険組合から提出を求められているとき
「被保険者住所変更届」を提出する際、原則として住民票などの添付書類は不要です 。
ただし、被扶養者が従業員と別居になる場合など、扶養の事実を確認するために追加の書類を求められることがあります。特殊なケースでは、事前に管轄の年金事務所や健康保険組合に必要書類を確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。
従業員の住所変更にともない提出する「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」には、被保険者本人に関する基本情報を正確に記入する必要があります。書類の差し戻しや手続きの遅延を防ぐためにも、記入のポイントと注意点を押さえておきましょう。
ここでは、主な記載項目と、実務でよくある記入ミスについて解説します。
記載が必要な主な項目と記入例
健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」には、主に以下の情報を記入します。
届出用紙は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできますので、実際の様式と照らし合わせながらご確認ください。
【主な記入項目一覧】
- 被保険者の氏名・フリガナ
- 生年月日
- 基礎年金番号またはマイナンバー(12桁または10桁)
- 旧住所と新住所(郵便番号を含む)
- 住所変更年月日
- 事業所整理記号・被保険者整理番号
- 事業所名・所在地・代表者名
- 被扶養配偶者がいる場合:配偶者の氏名・生年月日・住所
個人番号欄の記入は右詰め。マイナンバー12桁、基礎年金番号10桁。どちらか一方のみ記入でOKです。
書類冒頭の「健康保険」「厚生年金保険」の欄は、会社の加入状況に応じて〇で囲む必要があります。
| 加入状況 | 丸囲みのルール |
| 厚生年金保険のみ加入(健保組合など) | 「厚生年金保険」を〇で囲む |
| 健康保険組合のみ加入 | 「健康保険」を〇で囲む |
| 協会けんぽ+厚生年金保険加入 | 〇で囲む必要なし |
よくある記入ミスと注意点
届出書は基本的に添付書類なしで手続きが完了しますが 、以下のような記入ミスが散見されるため注意が必要です。
| ミス内容 | 解説・補足 |
| 番地や建物名を略記(例:1-2-3→1-2) | 住民票と異なる表記では受付不可になる場合あり |
| 旧住所・新住所が混在している | 手続きの遅れや訂正依頼の原因になるため要確認 |
| マイナンバー・基礎年金番号の誤記 | 他人情報との照合エラーを引き起こすリスクあり |
| 被保険者と配偶者が同居なのに欄外チェックを忘れる | 「同居チェック」があれば配偶者欄の省略可(※PDF注記あり) |
「被保険者と配偶者は同居している」に✔を入れると、配偶者欄の記入を省略できます。
従業員の住所変更にともなって会社が作成する「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」は、所定の提出先へ適切な方法で提出する必要があります。
ここでは、提出先・提出方法・提出時期、そして提出が遅れた場合のリスクについて解説します。
提出先は所在地を管轄する年金事務所
届出の提出先は、原則として会社の所在地を管轄する「事務センター」または「年金事務所」です 。
- 郵送の場合:管轄の事務センターへ送付します 。
- 窓口へ持参する場合:管轄の年金事務所の窓口へ提出します 。
自社の管轄がどこになるかは、日本年金機構の公式サイトで郵便番号から検索できます。なお、加入している健康保険組合によっては、別途組合への届出が必要な場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
提出方法は郵送・持参・電子申請が可能
被保険者住所変更届は、以下のいずれかの方法で提出します 。
| 提出方法 | 概要 |
| 郵送 | 控えに返送が必要な場合は、返信用封筒を同封するのが望ましい |
| 持参 | 年金事務所の窓口に直接持ち込む。その場で確認してもらえる利点あり |
| 電子申請 (e-Gov) | 社労士クラウドなど電子申請対応システムからの提出も可能。控えの電子交付あり |
【補足】
e-Govを利用した電子申請には、事前にGビズIDのアカウント作成などが必要になる場合があります。初めて利用する場合は準備に時間がかかることもあるため、提出を急ぐ場合は郵送または窓口持参が確実です。
提出時期と遅延した場合のリスク
「被保険者住所変更届」には、「資格取得届(5日以内)」のような法律で定められた明確な提出期限(〇日以内)はありません。しかし、日本年金機構は「速やかに」提出することを求めています 。
住所変更の事実が発生したら、会社はできるだけ早く手続きを進めることが実務上推奨されます。
ただし、届出の提出が遅れた場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
◯重要書類の不達
「ねんきん定期便」や社会保険料に関する通知など、日本年金機構からの重要なお知らせが旧住所に送付され、従業員が自身の情報を確認できなくなります。
◯退職・扶養手続きの不備
退職時の資格喪失手続きや、家族を扶養に入れる際の手続きで、登録されている住所情報が古いと、他の書類との整合性が取れずに手続きが滞る原因となります。
◯健康保険証に関する通知の遅延
保険証の再発行や給付に関する通知などが、本人に正しく届かなくなる可能性があります。
◯安否確認の遅れ
災害時や緊急時の安否確認において、会社が最新の住所を把握していないと、迅速な対応が困難になります。
これらのリスクを避けるためにも、住所変更の手続きは後回しにせず、速やかに行うようにしましょう。
従業員本人の住所変更だけでなく、家族構成の変化や経営者自身の引っ越しなど、実務上の判断が分かれるケースも存在します。
ここでは特に注意が必要な2つのケースについて、対応のポイントを解説します。
注意が必要なケース① 扶養家族の住所が変わった場合
従業員の扶養に入っている家族(被扶養者)の住所のみが変更された場合、原則として「被保険者住所変更届」の提出は不要です。
しかし、扶養認定条件に影響が出るケースがあるため、状況を正確に確認したうえで必要に応じて追加手続きを行いましょう。
健康保険の扶養認定には、「同居が必要な親族」(例:義父母など)があります。こうした被扶養者が別居した場合、扶養認定の条件を満たさなくなる可能性があります。
→ 必要に応じて「被扶養者(異動)届」を提出し、扶養から外す手続きを行いましょう。
子どもや親の転居により、「従業員が生活費を支援している」という実態が失われた場合も、扶養認定が外れることがあります(例:親が別の兄弟と同居し、その家で生計を立てるようになった場合 など)。
従業員から扶養家族の住所変更の申し出があった際は、単なる住所の変化ではなく、同居・仕送り状況など実態の変化がないかを必ず確認してください。
注意が必要なケース② 社長本人が引っ越した場合(1人社長含む)
会社の代表者や役員であっても、社会保険に加入している場合は「被保険者」として扱われます。そのため、社長自身が引っ越した場合も、被保険者住所変更届の提出が必要です。
最も注意すべき点は、法務局へ提出する「役員変更登記(代表取締役の住所変更など)」の手続きと、年金事務所へ提出する「社会保険の住所変更手続き」は、全く別の手続きであるという点です。
役員変更登記を済ませただけでは、社会保険上の登録住所は自動で更新されません。必ず両方の手続きを、それぞれ所定の窓口で行う必要があります。
役員変更登記と社会保険の住所変更の違い(比較表)
| 項目 | 役員変更登記 | 社会保険の住所変更 |
| 手続きの目的 | 会社の登記事項(住所など)を更新 | 社会保険上の被保険者情報を更新 |
| 提出先 | 法務局 | 年金事務所(または事務センター) |
| 根拠法令 | 会社法 | 健康保険法・厚生年金保険法 |
| 自動連携の有無 | なし | なし(双方を個別に申請する必要がある) |
社会保険の住所変更手続きに関して、実務担当者から特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
社会保険とマイナンバーを紐づけていると住所変更手続きは不要になるの?
「マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、住所変更の届出は一切不要になる」と考えるのは誤解であり、注意が必要です。
確かに、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、事業主からの「被保険者住所変更届」は不要です 。住民票の住所を変更すると、その情報が日本年金機構に連携されるためです。
しかし、以下のようなケースでは、マイナンバーが連携されていても届出が必要になります。
- マイナンバーと基礎年金番号の結びつきが完了していない従業員
- 海外居住者や、短期在留の外国人である従業員
- 住民票の住所以外の場所(居所)を登録・変更したいとき
- 70歳以上で厚生年金には加入せず、健康保険のみに加入している従業員
- 加入している健康保険組合が、別途届出を求めている場合
結論として、「マイナンバーがある=手続き不要」と一概に判断するのは危険です。自社の従業員がどのケースに該当するか不明な場合は、届出を提出しておくのが最も確実な対応といえます。
社会保険以外にも会社側に必要な手続きはある?
社会保険の住所変更手続き以外にも、会社として必ず対応すべき重要な業務が存在します。
これらの手続きを怠ると、法令違反や給与計算のミスに繋がる可能性があるため、注意してください。
- 労働者名簿の住所を更新する
- 通勤手当を再計算し、給与に反映させる
- 緊急連絡先の名簿などを更新する
詳しくは本記事の「社会保険の住所変更手続きの流れ(Step3)」をご覧ください。
社会保険の住所変更手続きを怠る・しないとどうなるの?
社会保険の住所変更手続きを怠った場合、現時点で直接的な罰則規定はありません。しかし、罰則がないからといって手続きを軽視すると、従業員の不利益や、後々の労務トラブルに繋がる様々なリスクが発生します。
- 重要書類が届かない
- 各種手続きに支障が出る
- 会社の信頼を損なう
- 緊急時に安否確認ができない
こうしたトラブルを防ぐためにも、住所変更は会社が責任を持って迅速に対応することが重要です。
従業員が引っ越しをした際、社会保険(健康保険・厚生年金)の住所変更手続きは原則として会社の対応が必要です。一方で、雇用保険については住所変更の届出は原則不要ですが、労働者名簿の更新や通勤手当の再計算といった社内業務が求められます。
また、扶養家族の転居や社長本人の引っ越しなど、見落としやすいケースでも適切な対応が必要です。マイナンバー制度により一部の手続きが不要となる場合もありますが、例外が多いため注意が必要です。
手続きを怠ることで、通知の不達や退職時の手続きトラブル、従業員との信頼関係の悪化につながる恐れがあります。会社としての義務を果たすためにも、従業員からの住所変更の連絡を受けたら、速やかに社会保険の届出と社内の関連業務を完了させることが大切です。
もし実務に不安がある場合は、社会保険手続きに特化した社労士にスポットで依頼することも検討してみてください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 2,000社以上の社会保険手続き実績|