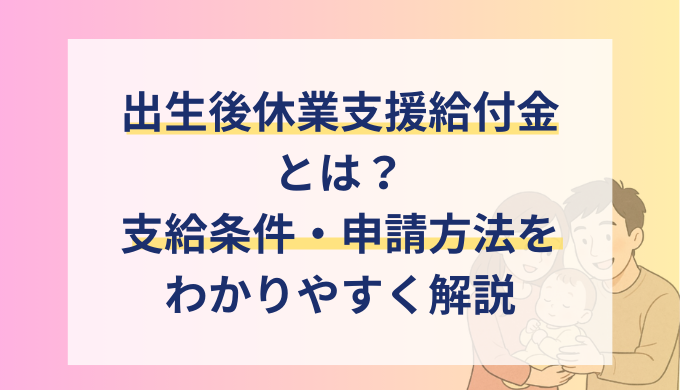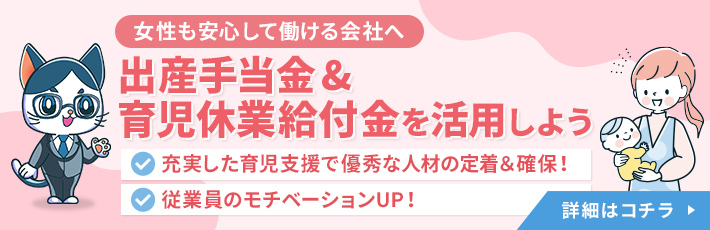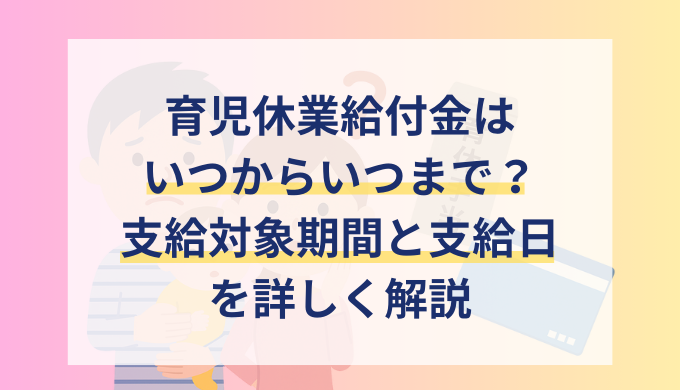2025年4月1日から施行された「出生後休業支援給付金」は、子育て支援を目的とした画期的な新制度です。夫婦がともに育児休業を取得する際の経済的負担を軽減し、特に男性の育児参加を促進することを目的としています。
この給付金の最大の特徴は「実質手取り10割相当」の保障です。従来の育児休業給付金に上乗せされるため、休業前とほぼ同等の手取り収入を確保することができます。
ただし、支給要件や対象期間、申請手続きが複雑で、「受給条件は?」「いくら支給されるの?」などの疑問も多く寄せられています。制度を十分に活用するためには、人事・労務担当者が正しく理解し、従業員に適切な説明を行うことが不可欠です。
本記事では、出生後休業支援給付金の概要や支給条件、対象者、支給額、申請方法をわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、従業員の仕事と育児の両立支援、さらには働きやすい職場環境の構築につなげましょう。
出生後休業支援給付金の申請方法・手続きは、原則として会社経由で、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の初回申請手続きと併せて行うこととされています。
(詳しくは「出生後休業支援給付金の申請方法と手続きの流れ」で解説↓)

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
労働保険の年度更新や算定基礎届など、労働保険・社会保険の手続きは、1年のうちで決まったタイミングで発生するものと、入社や退社など、イベントが発生するごとに必要な手続きが必要なもの、また生年月日に応じて必要な必須の手続きがあります。
⇒社会保険・労働保険手続きの年間スケジュール(PDF)を無料ダウンロード
従業の産休・育休で会社が行う必要がある手続きを下記の記事でまとめています。
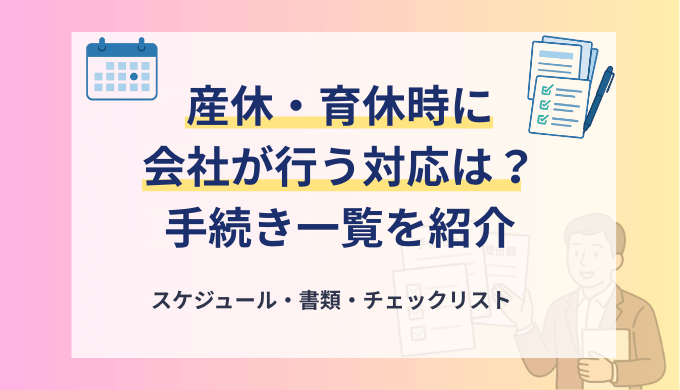 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
出生後休業支援給付金とは、子の出生直後の一定期間内に、夫婦(両親)それぞれが原則として14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」に“上乗せ”して支給される新しい給付金制度です。
そのため、出生後休業支援給付金のみを単体で受け取ることはできません。
一定期間とは、男性従業員は子どもの出生後8週間以内、女性従業員は産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
2025年4月から施行されたこの制度は、共働き・共育てを推進し、特に男性の育児休業取得を経済面から力強く促進することを主な目的として創設されました。
この給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額の13%相当額が基本となり、最大28日間支給されます。これにより、従来の育児休業給付金等の給付率67%に13%が加算され、合計で休業前の賃金の80%相当の支給を受けることができます。
さらに重要な点として、育児休業期間中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担が免除され、雇用保険料の負担もなく、これらの給付金は非課税扱いとなります。そのため、この給付率80%という数字は、実質的な手取り額で考えると、休業前の給料のほぼ10割に相当する水準となり、従業員の経済的な不安を大幅に軽減する効果があります。
ただし、この出生後休業支援給付金は単独で受給できるものではなく、あくまで既存の育児休業給付金等の支給を受ける方が対象となる追加的な支援である、という点を正確に押さえておく必要があります。
企業としては、この制度を十分に理解し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境整備を進めることが、今後の人材確保や定着、そして企業価値の向上にもつながる重要な取り組みとなるでしょう。
【あわせて読みたい】
> 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
新設された出生後休業支援給付金ですが、育児休業を取得すれば誰もが支給対象となるわけではありません。この給付金を受け取るためには、雇用保険の育児休業給付制度における基本的な受給資格を満たした上で、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。
出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、主に以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
- 育児休業を開始した日より前の2年間に、「みなし被保険者期間」が通算して12か月以上あること。
- 給付金を申請する被保険者本人が、対象期間内に取得した育児休業(産後パパ育休を含む)の日数が、通算して14日以上であること。
- 原則として、被保険者の配偶者も、対象期間内に14日以上の育児休業を取得していること(ただし、これには重要な例外ケースがあります)。
支給要件1
まず最初の要件である「みなし被保険者期間」についてです。
これは、育児休業給付金や出生時育児休業給付金と同様の考え方で、育児休業を開始した日(※分割取得の場合は初回の開始日)より前の2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12か月以上必要である、というものです。
この「1か月」は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払基礎日数が11日未満であっても、その月の労働時間が80時間以上ある月を指します。この条件を満たさない場合は、他の要件を満たしていても給付金は支給されませんので、最も基本的な受給資格として確認が必要です。
支給要件2
次に、被保険者本人の育児休業取得日数に関する要件です。
子の出生直後の定められた対象期間内(具体的な期間は後ほど解説します)に、産後パパ育休(出生時育児休業)または通常の育児休業を、合計して14日以上取得することが求められます。
この「14日以上」の日数は、必ずしも連続している必要はなく、対象期間内であれば複数回に分割して取得した日数を通算することが可能です。また、土日祝日など会社の休日であっても、休業期間に含まれていれば日数としてカウントされます。
この点は、従業員が柔軟に育休を計画する上で重要となります。
支給要件3
最後に、原則として配偶者も同様に14日以上の育児休業を取得するという要件があります。
これは夫婦での育児を促進するという制度の目的を反映したものですが、様々な家庭の状況に配慮し、この要件が適用されない例外ケースが設けられています。
どのような場合に例外となるかについては、次のセクションで詳しく解説します。
支給要件が例外となるケース
出生後休業支援給付金は、原則として夫婦そろって14日以上の育児休業を取得することが支給要件となっています。しかし、様々な家庭の状況に配慮し、配偶者の育児休業取得を要件としない例外ケースが以下の通り定められています。このいずれかに該当する場合、被保険者本人(従業員)のみの育休取得でも給付金を受給できる可能性があります。
- (例外1)配偶者がいない場合
- (例外2)配偶者が子と法律上の親子関係がない場合
- (例外3)配偶者がDV被害により別居中の場合
- (例外4)配偶者が無業(専業主婦/夫など)の場合
- (例外5)配偶者が雇用保険に加入していない場合(自営業など)
- (例外6)配偶者が産後休業中の場合
- (例外7)その他やむを得ない理由がある場合(※)
(※その他やむを得ない理由の具体例:配偶者が日雇い労働者、労使協定で育休申出不可の有期雇用者、海外居住、傷病等による養育困難、配偶者自身の妊娠・出産前後など)
上記例外に該当する場合でも、申請する被保険者本人は14日以上の育児休業を対象期間内に取得する必要があります。また、申請時には例外に該当することを証明する書類の提出が求められる場合があります。個別のケースが例外に該当するかどうかの最終的な判断や必要書類については、必ず管轄のハローワークにご確認ください。
出生後休業支援給付金の支給要件として「14日以上の育児休業取得」が求められますが、この育休はいつでも取得すれば良いというわけではありません。
給付金の対象となるためには、子の出生に関連した特定の期間内に取得する必要があります。この「対象期間」の考え方は、育児休業を取得するのが父親か母親か(より正確には、産後休業を取得したかどうか)によって異なります。
企業の人事・労務担当者としては、従業員からの育休計画の相談に対応したり、申請時の期間を確認したりする上で、このルールを正しく理解しておくことが不可欠です。
ここでは、いつからいつまでの育児休業が出生後休業支援給付金の対象となるのか、具体的な対象期間のルールについて、ケース別に詳しく紹介します。
産後休業を取得しなかったとき(主に男性のケース)
出産をしていない方の被保険者、つまり主に父親や、養子を迎えた場合の母親などが育児休業を取得するケースです。
この場合、労働基準法上の産後休業を取得しないため、対象期間は以下のように定められています。
対象期間は、『「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から開始し、「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」まで』となります。
少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントは、開始日は出生日か予定日の早い方を基準とし、終了日は出生日か予定日の遅い方を基準に8週間後(の翌日)まで、という点です。
この定められた期間内に、産後パパ育休(出生時育児休業)または通常の育児休業を、通算して14日以上取得することが、出生後休業支援給付金の支給を受けるための要件となります。
父親の場合、子の出生後すぐに休業を開始することが可能ですので、この8週間という期間を意識して取得計画を立てることが重要です。
産後休業を取得したとき(出産した女性のケース)
出産した女性(母親)が育児休業を取得するケースです。母親の場合、通常、出産の翌日から8週間は労働基準法に基づく産後休業を取得します。この産後休業期間は育児休業とは異なるため、出生後休業支援給付金の対象期間の考え方も父親の場合とは異なります。
母親(産後休業を取得した場合)の対象期間は、『「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から開始し、「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」まで』となります。
開始日の考え方は父親の場合と同じですが、終了日が「8週間」ではなく「16週間」を経過する日の翌日までと、より長くなっています。
これは、8週間の産後休業期間を考慮したものです。母親は、この16週間の対象期間内に、産後休業が終了した後で、育児休業を通算して14日以上取得することが要件となります。
多くの場合、産後休業終了(出産翌日から8週間後)に引き続いて育児休業にスムーズに入る形になるかと思いますが、その育児休業の開始が対象期間(出生等から16週間後まで)に収まっているかを確認する必要があります。
予定日と出生日がずれた場合の対象期間
対象期間の定義において、「出生日または出産予定日のうち早い日/遅い日」という基準が用いられている点が少し複雑に感じられるかもしれません。
これは、出産予定日に合わせて従業員が育児休業の計画を立てていたとしても、実際の出生日が前後した場合に、給付金の対象となる期間が不当に短くなったり、取得できなくなったりしないように配慮されたルールです。
具体例で考えてみましょう。例えば、出産予定日が2025年6月10日だったとします。
- 開始日:6月10日
- 終了日:6月10日から起算して、男性等は8週間後(8月5日)の翌日=8月6日まで。女性は16週間後(9月30日)の翌日=10月1日まで
- 開始日:「早い日」である6月1日
- 終了日:「遅い日」である予定日6月10日から起算して、男性等は8週間後(8月5日)の翌日=8月6日まで。女性は16週間後(9月30日)の翌日=10月1日まで。
- 開始日:「早い日」である予定日6月10日
- 終了日:「遅い日」である出生日6月20日から起算して、男性等は8週間後(8月15日)の翌日=8月16日まで。女性は16週間後(10月10日)の翌日=10月11日まで。
このように、開始日は「早く始まった方」に合わせ、終了日は「遅く終わる方」に合わせることで、従業員が休業を取得できるチャンスが広がるように設計されています。
企業の担当者は、従業員から出産予定日と実際の出生日の報告を受けた際に、このルールに基づいて正確な対象期間を確認し、案内できるように準備しておきましょう。
対象外になるケース(制度開始前の育休など)
出生後休業支援給付金は比較的新しい制度であり、対象期間も限定されているため、対象外となるケースについても理解しておく必要があります。
まず最も注意が必要なのは、制度の施行日(2025年4月1日)との関係です。
2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている被保険者については、対象期間の開始日が2025年4月1日より前であったとしても、「2025年4月1日」を対象期間の開始日とみなして支給要件(14日以上の取得など)を確認する、という経過措置が設けられています。
しかし、この読み替えを行ったとしても、対象期間の終了日が2025年4月1日より前に到来してしまっている場合や、読み替えた対象期間内に14日以上の育児休業を取得できない場合は、給付金の対象外となります。
例えば、2025年1月に出生し、父親が2月から3月にかけて8週間の育児休業を既に取得し終えているような場合は、制度開始時点で対象期間が終了しているため、対象外となる可能性が高いでしょう。
また、当然ながら、前述の基本的な支給要件(雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること、対象期間内に14日以上の育児休業を取得することなど)を満たさない場合は、対象外となります。
さらに、対象期間を経過した後に育児休業を取得した場合も、その休業は出生後休業支援給付金の対象とはなりません(通常の育児休業給付金の対象にはなり得ます)。
企業の担当者としては、従業員の子の出生日(及び出産予定日)、育児休業の取得(予定)期間、雇用保険の加入状況などを正確に把握し、出生後休業支援給付金の対象期間内に要件を満たす取得となるかを確認し、誤解のないよう案内することが重要です。
不明な点があれば、ハローワークや社労士に確認してください。
出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始前の賃金日額を基に算出されます。
具体的には以下の計算式で算出されます。
■計算式
| 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 対象期間内に休業をした日数(上限28日) × 13% |
ここでいう「休業開始時賃金日額」とは、原則として、育児休業を開始した日(産後パパ育休の場合は出生時育児休業を開始した日)より前の6か月間に支払われた賃金の合計額を180で割った金額です。これは、既存の育児休業給付金や出生時育児休業給付金の計算で用いられるものと同じ考え方に基づいています。
そして、「対象期間内に休業をした日数(支給日数)」は、対象期間内に取得した育児休業(産後パパ育休を含む)の日数を指しますが、この出生後休業支援給付金による上乗せの対象となるのは、被保険者一人につき最大28日間分が上限と定められています。
たとえ対象期間内に28日を超えて育児休業を取得したとしても、この13%の上乗せが適用されるのは最初の28日分までとなります。
支給額は実質手取り10割の仕組み
出生後休業支援給付金の最大の特徴は「実質手取り10割相当」である点です。この給付金(給付率13%)は、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(休業開始から180日目までは給付率67%)に上乗せして支給されます。
対象期間(最大28日間)では、合計給付率は「67%+13%=80%」となります。
これが実質手取り10割相当と言われる理由は、育児休業中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除され、給付金自体も非課税だからです。
通常、給与からは約20%の社会保険料等が差し引かれるため、結果的に休業前とほぼ同等の手取り額が確保できます。
この仕組みが育児休業中の経済的不安を軽減し、夫婦揃って育児休業を取得しやすくなります。
【注意】賃金月額の上限と高所得者の場合
ただし、この「実質手取り10割相当」が全ての従業員に当てはまるわけではない点には、十分な注意が必要です。
育児休業給付金等の計算の基礎となる「休業開始時賃金月額」には、上限額と下限額が定められています(2025年4月1日時点の上限額は473,100円※)。
賃金がこの上限額を超えている高所得の従業員の場合、支給額は「上限額 × 80%」で計算されるため、休業前の手取り額を下回る可能性があります。
【ケース別】支給額シミュレーション
育児休業中の実際の収入がどのくらいになるか、出生後休業支援給付金を含めたシミュレーションを見てみましょう。
※実際の支給額は個人の賃金や休業日数によって変わります。
■前提条件
- 夫:月給35万円、産後パパ育休14日間取得
- 妻:月給30万円、産後休業後に育児休業1か月(30日)取得
- 夫婦とも出生後休業支援給付金の要件を満たす
■支給額計算
夫の場合(14日間)
- 日額:約11,667円(月額35万円÷30日)
- 支給額:11,667円 × 14日 × 80% = 約13万円
妻の場合(30日間)
- 日額:約10,000円(月額30万円÷30日)
- 支給額:10,000円 × 30日 × 80% = 約24万円
※上乗せ対象は最大28日までですが、概算として全期間80%で計算
■結果
- 夫:約半月で13万円(通常の手取り約27〜28万円/月と比較)
- 妻:1か月で24万円(通常の手取り約23〜24万円/月と比較)
→ 育児休業中でも、休業前とほぼ同等の手取り収入が確保できます。
■前提条件
- 夫:月給60万円、育児休業1か月(30日)取得
- 妻:専業主婦(無業者のため例外ケースに該当)
- 夫のみで出生後休業支援給付金の要件を満たす
■支給額計算
- 夫の月給60万円は上限額(473,100円)を超えるため、上限で計算
- 休業開始時賃金日額:15,770円(上限)
- 支給額:15,770円 × 30日 × 80% = 約37.8万円
■結果
休業前の手取り月額(約45万円と仮定)と比べると、給付額は約37.8万円となり「手取り10割」には届きません。ただし、従来の育児休業給付金(67%)より約6万円増額されており、経済的支援は強化されています。
■前提条件
- ケース1と同じ夫婦(夫:月給35万円、妻:月給30万円)
- 夫が育児休業1か月(30日)、妻が育児休業6か月(180日)取得
- 夫婦とも出生後休業支援給付金の要件を満たす
■支給額計算
夫(1か月間)
- 支給額:約28万円(35万円×80%)
※上乗せ対象は最大28日までですが、概算として計算
妻(6か月間)
- 最初の1か月:約24万円(30万円×80%)※上乗せ対象は28日まで
- 2〜6か月目:月あたり約20.1万円(30万円×67%)
- この期間は出生後休業支援給付金の上乗せ終了
- 育児休業給付金の通常給付率67%が適用
- (7か月目以降は給付率50%に下がり、月約15万円)
■結果
出生後休業支援給付金による上乗せ(80%給付)は最大28日間のみ適用されます。それ以降は給付率が67%(181日目以降は50%)に戻ります。特に休業直後の物入りな時期に手厚い支援があることが大きな安心材料になるでしょう。長期取得の場合の支給額変動についても説明するとよいでしょう。
ご自身の状況に合わせた正確な金額を知りたい方は、下記の計算ツールをご利用ください。休業できる期間や給付金額、支給タイミングが一目でわかります。
【計算ツール】
> 出産手当金・育児休業給付金の支給金額・期間自動計算ツール
(出生後休業支援給付金の計算もできます)
このツールでは、休業可能期間の早見表も含めて、出生後休業支援給付金、出産手当金、育児休業給付金について自動で計算できます。
出生後休業支援給付金の申請手続きは、原則として会社経由で、育児休業給付金等(育児休業給付金または出生時育児休業給付金)の初回申請手続きと併せて行うこととされています。
ここでは、出生後休業支援給付金の申請は誰がどこに行うのか、いつ申請するのか、そして申請から支給までの大まかな流れについて、企業の実務担当者向けに詳しく解説していきます。
出生後休業支援給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金の申請書・添付書類、手続き先、申請するタイミングについて下の表にまとめています。
原則として従業員(雇用保険被保険者)から手続きに関する同意を得た上で、事業主(企業)が被保険者に代わって行うことになります。
| 申請手続き | 申請書・添付書類 | 申請タイミング | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | ・育休給付金/出生時育休給付金 支給申請書(追記項目あり) ・賃金台帳、出勤簿 等・母子健康手帳(出生証明)の写し 等 ・【重要】配偶者の状況等確認書類 | 「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の初回の支給申請と併せて行う | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 育児休業給付金 | ・育児休業給付金 支給申請書 ・賃金台帳、出勤簿 等 ・母子健康手帳(出生証明)の写し 等 | ◯初回申請: 原則、休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。 ◯2回目以降: 支給対象期間ごと(通常2か月ごと)に申請。 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 出生時育児休業給付金 | ・出生時育児休業給付金 支給申請書 ・賃金台帳、出勤簿 等 ・母子健康手帳(出生証明)の写し 等 | 原則、出生時育児休業期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
申請のタイミングについては、出生後休業支援給付金は、単独で申請するものではなく、原則として「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」または「育児休業給付金」の“初回”の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととされています。
従業員から育児休業取得の申し出があった際には、この初回申請のタイミングで出生後休業支援給付金の申請も同時に行えるよう、準備を進めることが重要です。
夫婦ともに育児休業を取得する場合、父親と母親のどちらの初回申請に合わせて出生後休業支援給付金を申請するかは、それぞれの休業開始のタイミング等によって異なってきます。
一般的には、先に休業を開始する方(例えば、産後パパ育休を取得する父親など)の初回申請に含めて手続きを進めるケースが多くなるでしょう。
ただし、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給要件を満たしたことが判明した場合などには、後から別途申請することもできます。
その場合は、既存の給付金が支給された後に申請を行うことになります。
【出産手当金と育児休業給付金の申請代行を全国スポット対応!】
社労士クラウドなら顧問料0円、業界最安値の料金で専任の社労士がスポットで申請代行!
- 複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減してコア業務にしたい
- 正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避したい
- 法改正への確実な対応がしたい
\ 顧問料0円で全国対応!/
> 社労士クラウドのスポット料金・報酬を確認する
申請から給付金の支給までの大まかな流れ
出生後休業支援給付金の申請から給付金の支給までの大まかな流れは以下の5ステップになります。
従業員からの育児休業取得の申し出と情報確認 従業員から育児休業の申し出があったら、企業は取得期間や給付金の支給要件(雇用保険被保険者期間、配偶者の状況など)を確認します。
申請書や添付書類の準備・作成 企業は従業員から必要な情報(配偶者の被保険者番号など)や書類(母子手帳の写しなど)を回収し、申請書を作成します。賃金台帳や出勤簿など、企業側で用意する書類も準備します。
管轄ハローワークへの提出 作成した書類一式を、申請期限内に事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します(窓口持参、郵送、または電子申請)。
審査と支給決定 ハローワークにて提出書類に基づき審査が行われ、支給が決定されると、事業主及び被保険者本人に支給決定通知書(または不支給決定通知書)が送付されます。
給付金の振り込み 支給決定後、申請書に記載された被保険者本人名義の金融機関口座へ給付金が振り込まれます。
ハローワークでの審査や支給決定には一定の期間を要するため、申請から実際の振り込みまでには数週間から1、2か月程度かかる場合がある点も、従業員へ説明しておくと良いでしょう。
詳しくは 「育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで」の記事で詳しく解説しています。
出生後休業支援給付金の申請は、原則として育児休業給付金等の初回申請と併せて行うため、その申請期限を守ることが非常に重要です。期限を過ぎると給付金が受給できなくなる可能性があるため、正確に把握しておきましょう。
申請期限は、主にどちらの給付金(育児休業給付金または、出生時育児休業給付金)の初回申請に併せるかによって考え方が異なります。
通常の育児休業給付金の初回申請期限は、原則として「育児休業を開始した日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」とされています。出生後休業支援給付金をこの申請に併せて行う場合、この期限が適用されます。
起算日は休業開始日の5月10日です。そこから4か月を経過する日は、9月9日となります。
9月9日の属する月は9月ですので、その末日である 2025年9月30日 が申請期限となります。
出生時育児休業給付金の申請期限は、原則として「出生時育児休業(産後パパ育休)期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで」とされています。出生後休業支援給付金をこの申請に併せて行う場合、この期限が適用されます。
休業期間の末日は6月28日です。起算日は末日の翌日である6月29日となります。そこから2か月を経過する日は、8月28日となります。
8月28日の属する月は8月ですので、その末日である 2025年8月31日 が申請期限となります。
申請期限は、申請書類の準備や内容確認にかかる時間も考慮し、余裕をもって手続きを進めることが肝心です。
2025年4月に出生後休業支援給付金が加わり、育児休業等に関連する雇用保険の給付金は主に3種類となりました。それぞれの制度には異なる目的や支給要件、対象期間があります。
企業の人事・労務担当者が従業員へ正確な説明を行うためには、これらの違いを把握しておくことが大切です。以下の比較表で、各給付金の主なポイントを確認しましょう。
【育児関連給付金 制度内容比較表】
| 比較項目 | 出生後休業支援給付金 | 育児休業給付金(通常) | 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) |
| 主な目的・位置づけ | ・出生直後の夫婦での育休取得支援 ・既存給付への「上乗せ」 | 育児休業期間全体の生活保障 | 産後パパ育休期間の生活保障 |
| 対象となる休業期間 | 出生後8週/16週以内の休業期間の一部 | 原則、子が1歳(最長2歳)までの休業期間 | 出生後8週以内の休業期間(最大4週間) |
| 主な支給要件 | +原則、夫婦で14日以上取得(例外あり) | 被保険者期間、休業、就業日数・賃金等 | 被保険者期間、休業、就業日数・賃金等 |
| 給付率 | 13% (既存給付と合わせ合計80%) | ・休業開始後180日まで67% ・181日目以降50% | 67% |
| 支給上限日数 | 最大28日間 | 支給対象期間全体 | 最大28日間 |
各給付金制度にはそれぞれの役割と特徴があります。
特に新しい出生後休業支援給付金は、支給要件や対象期間が限定的ですが、取得できれば非常に手厚い支援となります。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)と出生後休業支援給付金は同時に利用が可能
産後パパ育休(出生時育児休業)と出生後休業支援給付金は、支給要件を満たせば『同時に利用が可能』です。
| 出生時育児休業給付金 (産後パパ育休) | 父親などが産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に、休業開始時賃金日額の67%が支給される制度 |
| 出生後休業支援給付金 | 子の出生直後の対象期間内に夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得した場合(または例外に該当する場合)に、既存の給付金に13%が上乗せされる制度 |
父親は産後パパ育休の期間(最大28日間)について、出生時育児休業給付金(給付率67%)に加えて、出生後休業支援給付金(給付率13%)も上乗せして受給することができます。
つまり、父親が産後パパ育休を取得した場合でも、夫婦での育休取得などの条件を満たせば、その休業期間中は休業開始時賃金の合計80%相当(手取り10割相当)という手厚い経済的支援を受けられることになります。
これは、父親が産後の特に大変な時期に、経済的な心配をせずに育児に参加することを強力に後押しするものです。
ただし、重要な注意点として、父親が産後パパ育休を取得すれば、自動的に出生後休業支援給付金が上乗せされるわけではない、ということを理解しておく必要があります。
あくまで、出生後休業支援給付金の支給要件(配偶者の14日以上の育休取得または例外該当など)を満たすことが前提となります。
企業の担当者は、従業員、特に父親から産後パパ育休の相談を受けた際には、この出生後休業支援給付金による上乗せの可能性と、そのための条件についても併せて説明できると、より丁寧な対応となるでしょう。
社労士クラウドは、全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談、各種給付金・助成金の申請代行を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績!
⇒社労士クラウドのスポット申請代行の料金を確認する
出生後休業支援給付金の制度内容や申請の流れを理解した上で、次に重要となるのが、企業としてどのようにこの制度に対応していくか、という実務上の注意点です。
従業員がスムーズに給付金を受給できるようサポートすることはもちろん、制度導入を機に、男性も女性もより育児休業を取得しやすく、働きやすい職場環境を整備していく視点が求められます。
ここでは、企業の人事・労務担当者や事業主の皆様が押さえておくべき、実務上の具体的な注意点について解説します。
育児休業給付金または出生時育児休業給付金と併せて申請する
生後休業支援給付金の申請手続きにおいて、まず基本として押さえておくべき最も重要な注意点は、この給付金が単独で申請されるものではない、ということです。
手続きの際には、必ず既存の給付金と「併せて」行う必要があります。
出生後休業支援給付金は、原則として「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」の初回の支給申請と同時に、同一の支給申請書を用いて申請することが基本ルールとなっています。
企業の担当者は、従業員から育児休業の申し出があり、かつ出生後休業支援給付金の支給要件を満たす可能性がある場合には、初回の育休関連給付金の申請時に、申請書の所定欄(配偶者の被保険者番号、育児休業開始年月日、または配偶者の状態など)への記載を漏れなく行う必要があります。
この記載がなければ、上乗せ給付である出生後休業支援給付金は支給されませんので、細心の注意を払いましょう。
もし、何らかの理由で初回申請時に併せての申請ができなかった場合でも、後から別途申請することは可能とされていますが、その場合は既存の給付金の支給決定後に手続きを行うなど、プロセスが煩雑になる可能性があります。
男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりへの取り組み
出生後休業支援給付金のような経済的支援は、従業員、特にこれまで取得率が低かった男性が育児休業を取得する上で大きな後押しとなるものです。
しかし、制度という「ハード面」が整っても、職場で育休を取得しにくい雰囲気や、取得後のキャリアへの不安といった「ソフト面」の課題が残っていては、制度の効果は十分に発揮されません。
出生後休業支援給付金の創設の目的である男性の育児休業取得を真に促進するためには、企業として、男性も気兼ねなく育児休業を取得できるような職場風土づくりに積極的に取り組むことが極めて重要になります。
具体的な取り組みを、『社内ルールの整備』と『効果的な周知方法』に分けて見ていきましょう。
- 就業規則や育児・介護休業規程を最新の法改正に対応させる
- 申請手続きフローを明確化(誰に・いつまでに・どんな書類で)
- 休業中の連絡方法や業務引継ぎルールの設定
- 管理職向け研修の実施(ハラスメント防止など)
- 社内ポータル、社内報、説明会などで全従業員に周知
- 経営トップからの明確なメッセージ発信
- 相談窓口の設置
- 育休取得者(特に男性)の体験談共有
手厚い経済支援が魅力の出生後休業支援給付金ですが、申請すれば必ず支給されるわけではありません。
支給要件を満たさない場合や、手続き上の不備など、いくつかの理由で不支給となるケースがあります。
企業の人事・労務担当者としては、どのような場合に給付金が受け取れないのかを事前に把握しておくことで、従業員への誤った案内を防ぎ、トラブルを未然に防止することにも繋がります。
以下の表で、不支給となる主なケースを整理して確認しましょう。
【出生後休業支援給付金が不支給となる主なケース(まとめ表)】
| 不支給となる主な理由 | 具体的な内容・ポイント |
| 1. 前提となる給付金の不支給 | 育児休業給付金等が不支給の場合(例:休業開始前の被保険者期間不足、休業中の就業日数・時間超過、賃金支給による調整で給付額ゼロなど) |
| 2. 本人(申請者)の休業日数不足 | 被保険者本人が、定められた対象期間内に通算して14日以上の育児休業を取得していない場合。 |
| 3. 配偶者の休業日数不足(かつ例外非該当) | 配偶者が対象期間内に通算して14日以上の育児休業を取得しておらず、かつ例外ケース(無業者、産後休業中など)にも該当しない場合。 |
| 4. 対象期間外での休業取得 | 14日以上の育児休業を取得していても、それが定められた対象期間(出生後8週/16週以内など)の外であった場合。 |
| 5. 申請期限の超過 | 原則、育児休業給付金等の初回申請と併せて行う申請が、所定の期限までに行われなかった場合。 |
| 6. 申請書類の不備・誤り | 申請書への記載漏れや誤り、必要な添付書類(配偶者の状況証明など)が不足している場合。 |
この表は、出生後休業支援給付金が不支給となる主な理由をまとめたものです。
前提となる育児休業給付金等の要件から、この給付金独自の要件、そして申請手続き上の注意点まで、多岐にわたることがわかります。
企業の担当者としては、従業員からの育休申し出時にこれらの点を確認し、申請が適切に行われるようサポートすることが重要です。個別のケースで判断に迷う場合や、詳細な条件については、管轄のハローワークや社労士へ確認するようにしましょう。
ここでは、企業の人事・労務担当者の方から寄せられることの多い質問や、特に注意しておきたい点について、Q&A形式でわかりやすく紹介します。
施行日直前の出産(2月生まれ、3月生まれ)の場合は対象外?
対象期間の考え方によりますが、対象となる可能性があります。
出生後休業支援給付金の制度は2025年4月1日から施行されました。この給付金を受給するには、原則として夫婦それぞれが対象期間内に14日以上の育児休業を取得する必要があります。
2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている方については、対象期間の開始日が2025年4月1日より前であっても、「2025年4月1日」を対象期間の開始日とみなして支給要件を確認するという経過措置があります。
対象期間の終了日は「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して、父親等は8週間、母親は16週間を経過する日の翌日」までです。
例えば2025年2月や3月に出産があった場合でも、この対象期間の終了日が2025年4月1日以降であり、かつ、2025年4月1日以降の対象期間内に14日以上の育児休業を取得する(した)場合には、給付金の対象となる可能性があります。
個別のケースについて、対象期間を正確に計算し、期間内に要件を満たす休業があるかを確認することが必要です。
双子の場合、給付金は2倍もらえる?
給付額が2倍になることはありません。
出生後休業支援給付金は、「1回の出産または養子縁組」に関連して取得される育児休業に対する支援という考え方に基づいています。そのため、双子や三つ子など多胎児の出産であったとしても、支給される給付金の額(上乗せされる13%分、最大28日間)が子の人数に応じて増えることはありません。
公務員は対象になるの?
原則として対象外です。
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者を対象とした給付金制度です。国家公務員や地方公務員の多くは、雇用保険の適用が除外されており、代わりに各共済組合の制度に加入しています。
したがって、雇用保険の被保険者ではない公務員の方は、この出生後休業支援給付金の支給対象とはなりません。
ただし、公務員についても、共済組合等において独自の育児休業に関する手当金制度が設けられており、今回の雇用保険制度の改正と同様の趣旨で、支援内容の拡充(給付率の引き上げなど)が検討・実施されている場合があります。
詳細については、所属する組織の人事担当部署や、加入している共済組合等にご確認いただく必要があります。
育休を分割取得した場合(例:1ヶ月育休→復職→再度1ヶ月育休)、14日要件はどうカウントされますか?
対象期間内であれば、分割して取得した休業日数を通算してカウントします。
出生後休業支援給付金の支給要件である「14日以上の育児休業取得」は、連続した14日間である必要はありません。定められた対象期間(父親等は出生後8週間以内、母親は16週間以内)の中であれば、複数回に分けて育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合でも、その日数を合計(通算)して14日以上となれば要件を満たします。
例えば、対象期間内に1週間の育休を2回取得した場合、合計14日となりますので、他の要件を満たせば支給対象となります。
給付金は課税されますか?扶養や年末調整への影響は?
非課税です。社会保険上の扶養や税法上の控除等の判定においても、通常、収入や所得として扱われません。
出生後休業支援給付金は、前提となる育児休業給付金や出生時育児休業給付金と同様に、所得税法上非課税所得とされています。
したがって、所得税や住民税は課税されません。年末調整や確定申告で収入として申告する必要もありません。 また、健康保険等の被扶養者の認定における収入要件(通常、年間収入130万円未満など)の判定においても、この非課税の給付金は収入に算入されないのが一般的です。
ただし、加入している健康保険組合によっては独自の基準を設けている可能性もゼロではありませんので、念のため確認するとより確実でしょう。
さらに、税法上の配偶者控除や配偶者特別控除の適用判定における合計所得金額にも、この給付金は含まれません。 このように、税金や社会保険の扶養判定においては有利な扱いとなっています。
出生後休業支援給付金と一緒に「育児時短就業給付金」も始まると聞きましたが?
出生後休業支援給付金と同じく2025年4月1日から、「育児時短就業給付金」という新しい制度も創設されました。
育児時短就業給付金は、出生後休業支援給付金とは別の制度です。こちらは、2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮する時短勤務(育児時短就業)を行う雇用保険被保険者を対象としています。
時短勤務によって賃金が低下した場合に、その低下した賃金の一部(原則として時短勤務中の賃金額の10%)を支給することで、育児と仕事の両立を支援し、柔軟な働き方を促進することを目的としています。
育児休業からの復職後に時短勤務を選択する従業員などにとっては重要な支援制度となりますが、出生後休業支援給付金とは対象となる働き方や支給要件、給付内容が異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
2025年4月1日施行の「出生後休業支援給付金」は、子の出生直後に夫婦が共に育児休業を取得する際の経済的負担を軽減する制度です。
最大の特徴は、休業前の手取り収入のほぼ全額が保障される点で、経済的理由で育休をためらっていた男性従業員にも大きな後押しとなります。この制度の活用は、法令遵守だけでなく従業員満足度向上にもつながります。安心して育児とキャリアを両立できる環境整備は、人材確保・定着戦略の要です。
実務上は、雇用保険の被保険者期間や育休取得日数などの支給要件を正確に把握し、申請手順や必要書類を事前に確認しておきましょう。また、従業員からの問い合わせに迅速に対応し、支給額の上限や不支給のケースなど正確な情報提供も重要です。
本制度は従業員と企業双方にメリットがあります。最大限に活用し、従業員の豊かなライフプランとキャリア形成を支援しましょう。不明点があればハローワーク等専門機関への相談も有効です。
仕事と育児の両立を支える企業文化の構築は、企業の持続的成長に直結します。新制度を追い風に、誰もが活躍できる職場環境を整えましょう。
社労士クラウドの年度更新スポット代行サービスについて
出生後休業支援給付金をはじめとする育児休業関連の給付金申請は、支給要件の確認や書類作成、提出など、正確性が求められる上に時間もかかり、企業の担当者にとって負担となることがあります。
「専門家に任せたいが、顧問契約の費用は…」「今回の申請だけ、ピンポイントでサポートが欲しい」といったお悩みはありませんか?
そのようなニーズにお応えするのが、「社労士クラウド」のスポット申請代行サービスです。出生後休業支援給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出産手当金などの各種申請手続きを、労働保険の専門家である社労士に単発でご依頼いただけます。
当サービスでは、最新の法令に基づき社労士が正確に手続きを代行します。お客様には必要な情報をご提供いただくだけで、面倒な日数計算や書類作成、提出といった手続きから解放され、貴重な時間をコア業務に集中させることが可能となり、経営の効率化にも繋がります。
必要な業務のみをスポットでご依頼いただけるため、顧問契約に比べて費用を抑えられるのも大きなメリットです。オンラインでのやり取りを基本としており、全国どの地域からでも簡単にご依頼いただけます。専門家による正確な手続きで、ミスや遅延による不支給リスクを回避し、安心して事業活動に集中していただけます。
自社での対応に時間や人手が足りない、計算や手続きに不安があるという企業様にとって、当社のスポット代行サービスは給付金申請を確実に、そして効率的に進めるための有効な選択肢です。出生後休業支援給付金などの手続きでお困りの際は、ぜひ一度、「社労士クラウド」のスポット代行サービスをご検討ください。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|