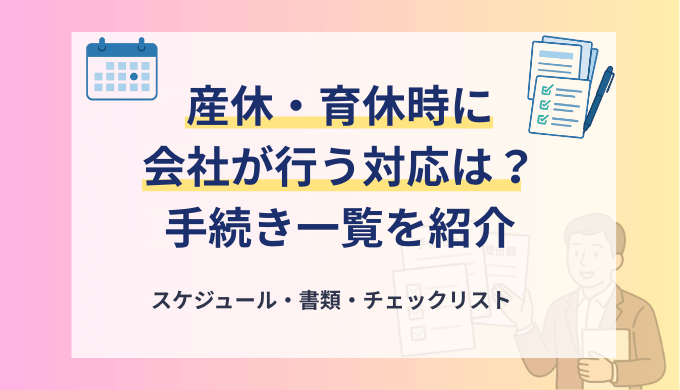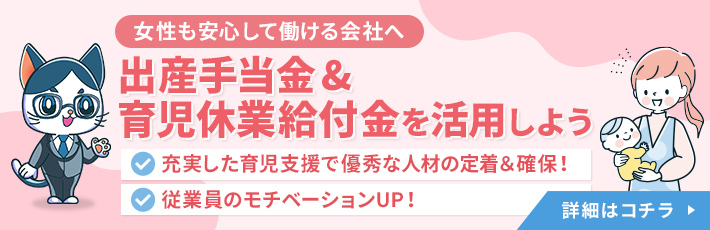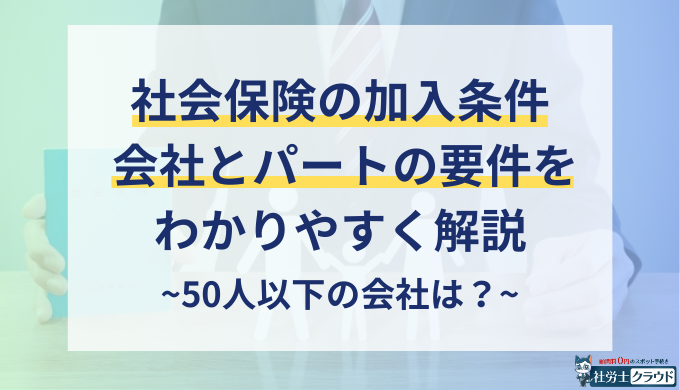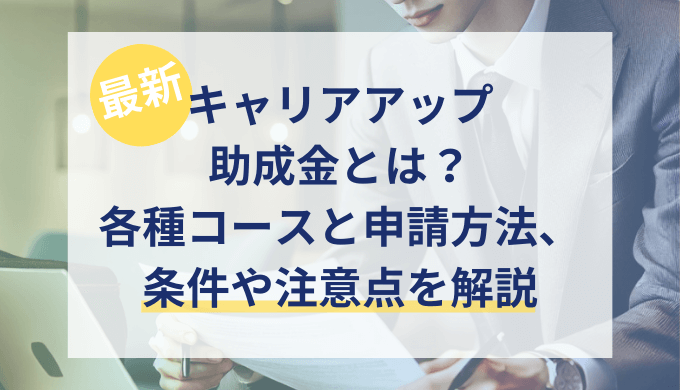産休・育休に関する会社側の手続きは多岐にわたり、それぞれに期限や注意点があるため、初めて対応される事業主、担当者にとっては不安も多いかと存じます。
この記事では、事業主や企業の人事・労務担当者の皆様に向けて、従業員が産休・育休を取得する際に会社が行うべき一連の手続き、必要な書類、申請先、大まかなスケジュール、そして関連する社会保険料の免除や給付金の申請について、ステップごとに分かりやすく解説します。
また、実務でよくある疑問点をQ&A形式で解消し、産休・育休制度の基本的な考え方についても触れていきます。
この記事を読むことで、産休・育休に関する会社の手続きの全体像を掴み、法令を遵守しながらスムーズな対応ができるようになることを目指します。
従業員が安心して休業に入り、気持ちよく職場復帰できるよう、しっかり準備を進めていきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業員から妊娠の報告を受け、産休(産前産後休業)や育休(育児休業)の申し出があった場合、会社側が行うべき手続きは多岐にわたります。
こちらでは、まず産休・育休期間全体を通して、会社が対応する必要のある申請や書類の提出、社会保険料の免除手続き、各種給付金に関する手続きの期間と大まかなスケジュール、そして主な提出先を一覧で解説します。
産休・育休の手続きをスムーズに進めるためには、まず全体の流れを把握することが重要です。いつ、何をすべきか、どんな書類が必要になるのか、事前に理解しておくことで、担当者様の業務の負担を軽減し、従業員も安心して休業に入ることができます。
産前産後休業の主な手続き
従業員が産前産後休業を取得する際に、会社として対応が必要な主な手続きです。
| 手続き・届出名 | 概要 | 提出先 | 提出時期・期限 |
| 産前産後休業取得者申出書 | 産前産後期間中の社会保険料が全額免除されるための申請。 | 日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所) | 産前産後休業期間中に提出(従業員から申し出を受け次第速やかに) |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 出生した子どもを従業員の健康保険の被扶養者に入れるための届出。 | 加入している健康保険組合または日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所) | 事実発生(出生など)から原則5日以内など、速やかに |
| 出産手当金支給申請書 | 出産時の生活保障として給付金を受けるための申請。 | 加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ) | 産休終了日の翌日から2年以内(産休中から申請できる場合もあります) |
育児休業の主な手続き
従業員が育児休業を取得する際に、会社として対応が必要な主な手続きです。
| 手続き・届出名 | 概要 | 提出先 | 提出時期・期限 |
| 育児休業等取得者申出書 | 育児休業期間中の社会保険料免除を受けるための届出。 | 日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所) | 育児休業等開始年月日から育児休業等終了予定日の翌日の属する月の前月まで(原則、育休開始後速やかに) |
| 育児休業給付金支給申請書(及び受給資格確認票) | 育児休業期間中の生活保障として、雇用保険から給付金を受けるための申請。 | 管轄のハローワーク | 育児休業等開始年月日から育児休業等終了予定日の翌日の属する月の前月まで(原則、育休開始後速やかに) |
| 出生後休業支援給付金支給申請書 | 産後パパ育休(出生時育児休業)等を取得した際の育児支援として給付金を受けるための申請。 | 管轄のハローワーク | 出生時育児休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 出産育児一時金 | 出産費用の負担軽減のため、健康保険から一時金を受けるための制度案内・申請サポート。 | 加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)/医療機関等 | 出産日の翌日から2年以内(直接支払制度等を利用する場合は医療機関での手続きによる) |
育休明けの主な手続き
従業員が育児休業を終えて復職する際に、会社として対応が必要な主な手続きです。
| 手続き・届出名 | 概要 | 提出先 | 提出時期・期限 |
| 育児休業等終了届 | 社会保険料の免除を終了させるために提出する届出。 | 日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所) | 育児休業終了後、速やかに提出 |
従業員の産休・育休にともなう手続きは多岐にわたり、各申請には提出期限が設定されているものもあります。期限を過ぎると給付金の支給が遅れたり、社会保険料の免除が受けられなくなる可能性があるため、スケジュールを確認し、漏れがないようにタスク設定することが求められます。
煩雑なスケジュール管理の一助として、下記のツールをご活用ください。従業員の出産予定日を入力するだけで、主要な届出の申請推奨日を自動で算出できます。
【関連記事】
> 出産手当金・育児休業給付金の支給金額・期間自動計算ツール
手続きに不安がある場合や、人的リソースが限られている場合には、専門家である社会保険労務士(社労士) に依頼することも検討しましょう。 社労士クラウドでは、産休・育休の申請手続き代行をスポット(単発)でご依頼いただけます。 まずはお気軽にご相談ください。
産休(産前産後休業)および育休(育児休業)とは、従業員が出産や育児のために法律に基づいて取得できる休業制度です。産休と育休は労働基準法や育児・介護休業法に根拠を持ち、従業員の権利保護と仕事と育児の両立支援を目的としています。
企業は、従業員からの産休・育休の申し出を原則として拒むことはできません。性別にかかわらず、また、正社員だけでなく有期契約労働者やパートタイム労働者であっても、一定の要件を満たせばこれらの権利を行使できます。
企業が産休・育休制度を正しく理解し運用することは、法令遵守はもちろん、従業員の安心感を高め、ひいては企業の成長にも繋がる重要な取り組みです。
従業員が利用できる主な休業制度として、「産前産後休業」「育児休業」「出生時育児休業(産後パパ育休)」があります。それぞれの対象者、期間、申し出方法などを正しく理解し、従業員へ適切に案内できるようにしましょう。
産前産後休業(産休)
産前産後休業は、出産する女性従業員の母体保護を目的とした休業です。一般的に「産休」と呼ばれます。
| 項目 | 産前休業 | 産後休業 |
| 根拠法規 | 労働基準法第65条第1項 | 労働基準法第65条第2項 |
| 主な対象者 | 出産予定の全ての女性従業員 | 出産した全ての女性従業員 |
| 取得可能期間 | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間) | 出産日の翌日から8週間まで |
| 申出の要否 | 従業員からの請求が必要 | 従業員の請求なしに取得(就業させてはならない期間) |
| 就業の可否 | 休業中は就業不可 | 原則就業不可。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務については就業可能。 |
産前休業の取得は任意ですが、産後6週間は本人の希望があっても就業させることはできません(強制休業期間)。
育児休業(育休)
育児休業は、主に1歳未満の子を養育する男女従業員が、仕事と育児の両立を図るために取得できる休業です。「育休」と略されることもあります。
| 項目 | 育児休業 |
| 根拠法規 | 育児・介護休業法 (主に第2条、第5条~第9条など) |
| 主な対象者 | 原則として1歳未満の子どもを養育する男女従業員(日々雇用される者を除く)。有期契約労働者の場合は、別途取得要件あり。 |
| 取得可能期間 | 原則、子どもが1歳に達するまで(保育所に入所できない等の特定の事情がある場合は1歳6ヶ月または2歳まで延長可能)。 |
| 申出期限・方法 | 原則、休業開始予定日の1ヶ月前までに、書面等(企業が認める場合は電子メール等も可)で事業主に申し出る。 |
| 分割取得 | 2回まで分割取得可能。 |
父母ともに育児休業を取得する場合の特例(パパ・ママ育休プラス)など、柔軟な取得を促進する制度があります。
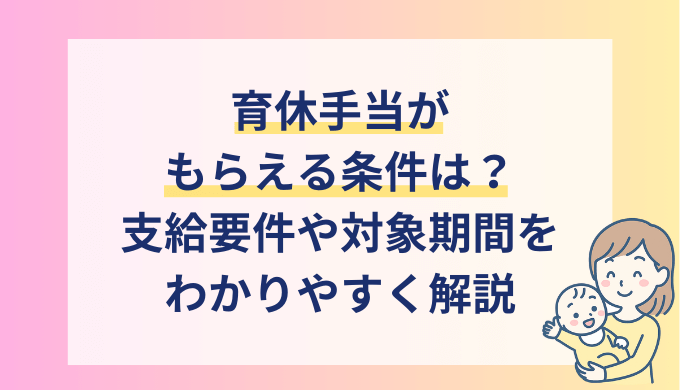 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
出生時育児休業(産後パパ育休)
出生時育児休業は、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして創設された制度で、主に男性の育児休業取得を促進することを目的としています。「産後パパ育休」とも呼ばれます。
| 項目 | 出生時育児休業(産後パパ育休) |
| 根拠法規 | 育児・介護休業法 (主に第9条の6など) |
| 主な対象者 | 子どもの出生後8週間以内に、産後休業をしていない男女従業員(主に男性従業員を想定)。有期契約労働者の場合は、別途取得要件あり。 |
| 取得可能期間 | 子どもの出生日または出産予定日のいずれか遅い方から出生後8週間以内に、4週間(28日)まで。 |
| 申出期限・方法 | 原則、休業開始予定日の2週間前までに、書面等(企業が認める場合は電子メール等も可)で事業主に申し出。労使協定で1ヶ月前までと定めることも可能。 |
| 分割取得 | 2回まで分割取得可能。初めにまとめて申し出る必要あり。 |
| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、従業員が合意した範囲で休業中に就業させることが可能(就業日数・時間には上限あり。事前に従業員に提示・同意が必要)。 |
出生時育児休業は、通常の育児休業とは別に取得できます。休業の申し出と同時に就業希望を申し出ることで、休業中の就業が可能になる場合があります。
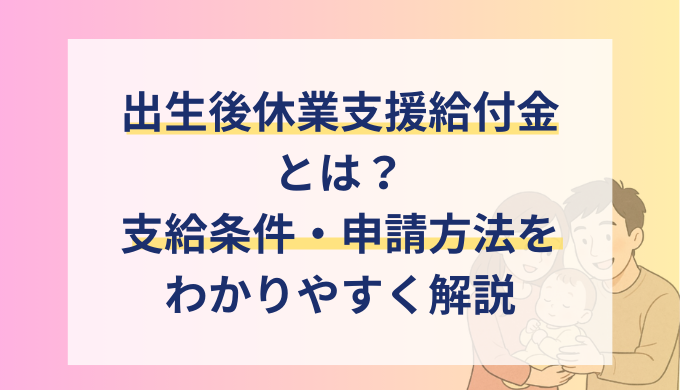 【2025年4月~】出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
【2025年4月~】出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
従業員から妊娠・出産の報告を受け、産休・育休の取得希望があった場合、会社は迅速かつ適切に対応する必要があります。
ここからは、従業員の妊娠報告から職場復帰までの流れに沿って、会社が行うべき具体的な手続きと対応をステップごとに詳しく解説します。
STEP1:従業員から妊娠報告を受けたら(産休開始前)
従業員から妊娠の報告を受けたら、会社として最初に行うべきことは、休業取得の意向確認と、産休・育休制度に関する情報提供です。
従業員が妊娠を報告した後の最初のステップでは、具体的に以下の2つの対応を行います。
① 従業員への初期対応と意向確認
② 産休・育休取得に向けた具体的な準備依頼
それぞれの対応について、詳しく見ていきましょう。
従業員から妊娠の報告を受けたら、まずは祝福の言葉を伝え、母子の健康を気遣う姿勢を示すことが大切です。その上で、産休・育休制度の概要を説明し、取得の意向を確認します。
【従業員に伝えるべき主な制度のポイント】
| * 利用できる休業制度の種類(産休、育休、産後パパ育休)とその対象者・期間の概要* 経済的支援(給付金、社会保険料免除)の概要* 社内の相談窓口 |
【従業員に確認すべき主な事項】
| * 出産予定日* 産前休業の開始希望日* 育児休業の取得希望の有無、および希望期間* (男性従業員の場合)出生時育児休業(産後パパ育休)の取得希望の有無* 休業中の連絡先と連絡方法* 現時点での復職の意向(予定日など)* その他、休業に関する不安な点など |
従業員から妊娠の報告を受けたら、まずは祝福の言葉を伝え、母子の健康を気遣う姿勢を示すことが大切です。その上で、産休・育従業員が産休・育休の取得を希望する場合、以下の具体的な準備を依頼し、必要な書類の提出を促します。
【従業員へ依頼・案内する主な事項】
| * 「産前産後休業届」(または企業所定の申出書)の提出を依頼* 母子健康手帳のコピー(出産予定日証明のため)の提出を依頼* 出産手当金支給申請書の準備と一部記入を依頼し、提出方法を案内(会社がサポートする場合)* 出産育児一時金の申請方法(直接支払制度等)に関する情報提供と本人の意思確認 * 通勤手当等の精算に関する案内(該当する場合)* 休業期間中の住民税の徴収方法に関する説明と本人の希望確認* 出産後の会社への報告を依頼(正確な出産日、子の氏名など)* (該当する場合)母性健康管理指導事項連絡カードの提出を依頼 |
ここまでに述べた初期対応と準備依頼を丁寧に行うことで、従業員は安心して休業の準備を進めることができ、会社側もその後の社会保険手続きや給付金申請などを円滑に進めるための基礎が整います。
STEP2:従業員が産休に入るとき(産休開始時)
従業員が実際に産前産後休業(産休)に入るタイミングでは、会社として行うべき主な手続きが2つあります。
- 社会保険料免除の申請(産前産後休業取得者申出書)
- 雇用保険関連の社内対応
特に、1の「社会保険料免除の申請」は、従業員・企業双方の経済的負担を軽減するために不可欠な手続きです。また、2の「雇用保険関連の社内対応」も、その後の育児休業給付金の申請等に繋がる重要な確認事項を含みます。
それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。
従業員が産休を取得する期間中は、健康保険および厚生年金保険の社会保険料が、被保険者(従業員)負担分・事業主負担分ともに免除されます。この免除を受けるためには、企業(事業主)が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。
この手続きは、産休期間中の従業員の経済的負担を軽減し、企業側のコスト削減にも繋がる重要なものです。提出を忘れると免除が受けられず、遡っての免除も原則として認められないため、従業員から産休開始の連絡を受けたら速やかに申請準備を進めましょう。
| 提出書類 | 産前産後休業取得者申出書 |
| 提出先 | 日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所) |
| 提出期限 | ・産前産後休業期間中(従業員が産休に入った後、速やかに) ・具体的には、従業員から「産前産後休業届」などにより休業開始の事実を確認した後に提出します。 |
| 免除期間 | 産前産後休業を開始した日の属する月から、終了した日(出産日が予定日後になった場合は、当初の出産予定日から起算して産後56日を経過する日)の翌日が属する月の前月まで。 例)5月10日に産休を開始し、7月5日に産休が終了した場合:5月分から6月分まで |
なお、この社会保険料の免除期間中も、被保険者資格は継続し、将来受け取る年金額の計算においては、保険料を納付したものとして扱われるため、従業員にとって不利益はありません。
産休期間中は、原則として雇用保険の被保険者資格は継続します。そのため、産休開始に伴って特別な雇用保険の手続きが必要になることは通常ありません。
ただし、会社としては以下の点を適切に管理・把握しておくことが重要です。
◯被保険者資格の継続確認
産休中も雇用保険の被保険者であることに変更はありません。給与計算システムなどで、被保険者資格を喪失するような誤った処理をしないよう注意が必要です。
◯育児休業給付金の準備
産休終了後に従業員が育児休業を取得する場合、育児休業給付金の申請が必要になります。その準備として、産休期間中の出勤状況や賃金支払状況を正確に記録・保管しておくことが求められます。
育児休業給付金の申請には、原則として休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就業した時間数が80時間以上の月)が12か月以上必要となるため、その確認の基礎となります。
産休と育児休業は連続して取得されることが多いため、産休開始時点から育児休業も見据えた情報管理を意識しておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
STEP3:従業員から出産の報告を受けたとき(産休中〜産休終了)
従業員が無事に出産を終え、その報告を受けたら、会社としてはまず祝福の言葉を伝えるとともに、出産日を確認し、産後休業の正確な終了日を確定させます。
そして健康保険関連の給付金申請のサポートや、子どもの健康保険加入などの手続きが主な対応となります。
このステップでは、主に以下の5つの対応について詳しく解説します。
- 出産後の社内確認と産休終了日の確定
- 健康保険の出産手当金の申請補助
- 健康保険の出産育児一時金の手続き案内
- 子の健康保険加入(被扶養者異動届)
- 扶養控除等申告書の追記
それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。
従業員から出産の報告を受けたら、会社としてまず取り組むべきは、正確な出産情報を把握し、それに基づいて産後休業の終了日を法的に確定することです。
具体的には、まず以下の情報を従業員から確認し、社内で適切に記録・共有します。
- 実際の出産日
- 出生した子の氏名、性別(後の健康保険の被扶養者手続きで必要になる)
- 母子の健康状態
上記情報に基づき、産前産後休業(産休) の正確な終了日を算出し、確定します。産後休業は、原則として出産日の翌日から8週間(56日間)です。
確定した産休終了日は、誤解が生じないよう、速やかに従業員本人へ書面等で明確に通知し、双方で日程を共有しておくことが大切です。
出産手当金は、健康保険の被保険者である従業員が、出産のために会社を休み、その休業期間中に会社から給与(報酬)の支払いを受けなかった場合、または受けた報酬が出産手当金の額よりも少なかった場合に、その差額を含めて支給される生活保障のための給付金です。
会社は、従業員がこの出産手当金をスムーズに受け取れるよう、申請の補助を行う大切な役割を担います。
【従業員への案内と必要書類の準備依頼】
従業員に対して、出産手当金の制度概要、申請の流れ、必要書類について改めて説明します。申請書(「健康保険出産手当金支給申請書」)は、通常、健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。会社で様式を準備し、従業員に渡しても良いでしょう。
従業員が記入する欄(被保険者情報、振込先口座など)と、医師または助産師が記入する欄(出産日や入院期間などの証明)、そして事業主が記入する欄(勤務状況や賃金支払状況の証明)があります。
【会社(事業主)による証明と申請代行または提出サポート】
従業員から記入済みの申請書と、医師または助産師の証明部分を受け取ったら、会社は事業主証明欄に必要事項(休業期間中の出勤状況、賃金支払状況など)を記入します。出勤簿や賃金台帳などの添付が求められる場合もあります。
完成した申請書は、従業員本人が提出することもできますが、多くの場合は会社が取りまとめて、加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ提出(郵送または電子申請)します。
| 提出書類 | ・健康保険出産手当金支給申請書(医師・助産師の証明、事業主の証明を含む) |
| 添付書類 | ・マイナンバーを記載する場合は、本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、通知カード+運転免許証など) ■場合により・療養担当者(医師・助産師)の意見書・賃金台帳や出勤簿の写し |
| 提出時期(提出期限) | 産休開始日の翌日から2年以内。一般的には、出産後、産休期間が終了する頃や、出産日が予定日からずれた場合はその期間が確定した後(産後56日を経過した後など)に申請手続きをまとめて行うことが多い。 |
| 提出先 | 会社が加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ) |
出産手当金は、産休中の従業員の生活を経済的に支える非常に重要な給付金です。会社としては、従業員への丁寧な情報提供と、迅速かつ正確な事務処理を心がけ、従業員が安心して休業し、出産・育児に臨めるようサポートしましょう。
出産育児一時金は、健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産した際に、出産費用の経済的負担を軽減するために支給される一時金です。1児につき原則50万円(2023年4月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)が支給されます。
この出産育児一時金の受け取り方には、主に「直接支払制度」と「受取代理制度」の2つの方法があり、多くの場合、医療機関が手続きを代行するため、会社が直接申請するケースは稀です。
会社の役割は、従業員へこれらの制度を説明し、スムーズに利用できるよう情報提供を行うことです。
◯直接支払制度
被保険者(従業員)が医療機関等の窓口で支払う出産費用について、出産育児一時金の支給額を上限として、健康保険組合等が医療機関等へ直接支払う制度です。従業員は、退院時に出産費用から一時金の額を差し引いた差額のみを支払います。
利用する場合は、従業員が医療機関等で合意文書を取り交わす必要があります。
◯受取代理制度
事前に健康保険組合等に申請することで、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度です。これにより、従業員は直接支払制度と同様に、窓口での支払いが差額のみで済みます。
この制度を利用できる医療機関は限られています。また、小規模な健康保険組合などで導入されている場合があります。
会社としては、従業員が出産前に上記2つの制度について医療機関に確認し、利用できる方法を選択できるようアドバイスすることが大切です。もし、これらの制度を利用せず、出産後に従業員自身が健康保険組合等に直接請求する場合は、会社が被保険者であることの証明などを求められることがあります。
従業員に子どもが生まれたら、その子どもを健康保険の被扶養者として加入させるための手続きが必要です。これにより、子どもは健康保険の給付(医療費の補助など)を受けることができます。
| 提出書類 | 健康保険被扶養者(異動)届 多くの場合、国民年金第3号被保険者の資格取得届も兼ねています(従業員の配偶者を扶養に入れる場合など)。 |
| 添付書類の例 | 出生の事実を証明する書類(住民票の写し、戸籍謄(抄)本など。ただし、マイナンバーを記載することで省略できる場合もあります) |
| 提出先 | 会社が加入している健康保険組合または日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所) |
| 提出時期 | 原則として、事実発生日(子どもの出生日)から5日以内。 |
健康保険被扶養者(異動)届の手続きが遅れると、子どもの保険証の発行が遅れ、医療機関を受診する際に一時的に医療費を全額自己負担しなければならない場合があるため、従業員から出産報告を受けたら、速やかに被扶養者異動届の準備と提出を進めましょう。
従業員に扶養する子どもが増えた場合、所得税の計算において扶養控除の対象となる可能性があります。その年の年末調整や、翌年以降の毎月の給与計算に反映させるため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容を更新する必要があります。
◯対応内容
従業員から出産の報告を受け、子が扶養親族に該当する場合、会社は従業員に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当欄(例:「控除対象扶養親族」の欄)に、出生した子どもの氏名、マイナンバー、続柄、生年月日などを追記してもらうよう案内します。
提出された申告書に基づき、会社は年末調整や月々の源泉徴収税額の計算を行います。
◯追記・提出のタイミング
原則として、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで、または、年の途中で扶養親族に異動があった場合には、その異動後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出(追記・更新)することになっています。
出産の場合は、事実が発生した後、次の給与計算や年末調整に間に合うように、従業員に速やかに追記・提出を依頼しましょう。
扶養控除は従業員の所得税額に影響するため、正確な情報を把握し、適切に処理することが重要です。
STEP4:従業員が育児休業に入るとき(育休開始時)
産前産後休業(産休)が終了し、従業員が引き続き育児休業(育休)に入る際には、会社として新たに行うべき主な手続きが4点あります。
この段階では、従業員からの育児休業の申し出を正式に受け付け、関連する通知を行うとともに、社会保険料の免除申請や雇用保険の育児休業給付金の初回申請などが主な業務となります。
また、男性従業員が取得する「産後パパ育休(出生時育児休業)」についても、会社側の適切な対応が求められます。 このステップでは、主に以下の4つの対応について詳しく解説します。
- 育児休業取得の申し出と通知
- 社会保険料免除の申請(育児休業等取得者申出書)
- 雇用保険の育児休業給付金申請(初回)
- 男性社員の産後パパ育休取得時の対応
それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。
従業員が育児休業を取得する際には、育児・介護休業法に基づき、原則として育休開始予定日の1ヶ月前までに、会社に対してその旨を申し出る必要があります。
会社はこの申し出を適切に受領し、法律に基づいた必要な通知を行う義務を負います。 従業員からは通常、「育児休業申出書」といった書面(企業が認める場合は電子メール等の電磁的方法も可)で申し出があります。
会社は、従業員から育児休業の申し出を受けた場合、または従業員の配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合には、速やかに(概ね2週間以内を目安に)その従業員に対して「育児休業取扱通知書」(またはそれに準ずる名称の書面)を交付しなければなりません。
この「育児休業取扱通知書」には、主に以下の事項を記載します。
- 育児休業の申し出を受けた旨
- 育児休業開始予定日および終了予定日
- 育児休業の申し出を拒む場合はその理由(法に定める正当な理由がある場合に限る)
- 育児休業期間中の待遇(賃金、社会保険料の取り扱いなど)
- 復職後の労働条件(配置、賃金など。変更がある場合はその内容)
- その他、育児休業に関する事項(育児休業給付金の申請についてなど)
育児休業期間中も、産休期間中と同様に、健康保険および厚生年金保険の社会保険料が、被保険者(従業員)負担分・事業主負担分ともに免除されます。この免除を受けるためには、企業(事業主)が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所)へ提出する必要があります。
産休に引き続き育児休業を取得する場合は、産休期間の社会保険料免除のための「産前産後休業取得者申出書」とは別に、改めてこの「育児休業等取得者申出書」の提出が必要となる点に注意が必要です。
| 提出書類 | 育児休業等取得者申出書 |
| 提出先 | 日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所) |
| 提出時期・期限 | 従業員が育児休業を開始した後、速やかに(原則として、育児休業等開始日の属する月から育児休業等終了予定日の翌日の属する月の前月までの間に提出)。 |
| 免除期間 | 育児休業等を開始した日の属する月から、終了した日の翌日が属する月の前月まで。 |
【注意点】
賞与にかかる保険料も、その賞与月の末日において育児休業等を取得している場合は免除対象となります(連続して1ヶ月を超える育児休業等を取得している場合に限る)。
育児休業の開始日と終了日が同一月内の場合は、その月の社会保険料は原則免除されませんが、その月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除対象となります(2022年10月施行)。
この手続きを確実に行うことで、従業員と企業双方の経済的負担が軽減されます。
育児休業期間中の従業員の生活を経済的に支えるため、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。この給付金を受け取るためには、初回の申請後も、原則として2ヶ月ごとにハローワークへ申請手続きを行う必要があります。
多くの場合、会社が従業員に代わって、これらの申請手続き(初回および2回目以降)を管轄のハローワークへ行います。まずは、初回の申請について見ていきましょう。
従業員が育児休業給付金を受給するためには、休業開始前の被保険者期間や育休中の就業日数制限など、一定の要件を満たしている必要がありますので、事前に確認が必要です。
| 提出書類 (初回申請時) | ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 |
| 提出書類 (2回目以降) | ・育児休業給付金支給申請書 (内容はハローワークから送付されるか、ダウンロードして作成) |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 (初回申請時) | 原則として育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで |
| 提出期限 (2回目以降) | ハローワークが指定する申請期間(通常、支給対象期間の末日の翌日から起算して10日以内など) |
育児休業給付金は、従業員にとって非常に重要な収入源となります。会社は、申請期限を守り、正確な情報に基づいて手続きを行う責任があります。
より詳しい申請方法や必要書類、2回目以降の手続きの流れについては、こちらの記事もご参照ください。
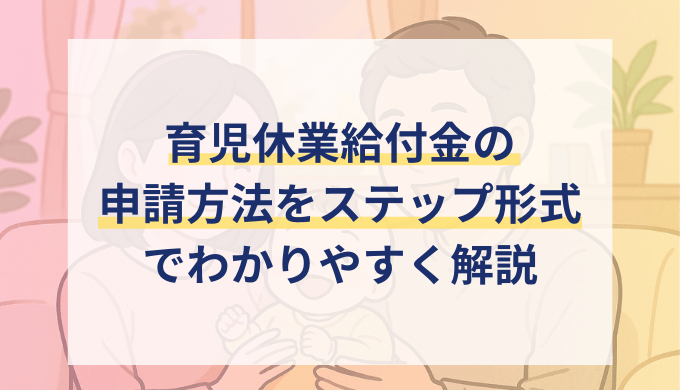 育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
男性従業員も、子の出生後8週間以内に最大4週間まで、「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得できます。これは通常の育児休業とは別に利用できる制度で、柔軟な育児参加を支援するものです。
会社としては、従業員から産後パパ育休の申し出があった場合、主に以下の対応が必要です。
- 申し出の受領と通知書の交付
- 社会保険料免除の手続き
- 出生時育児休業給付金の申請サポート
産後パパ育休期間中の就業は、労使協定と従業員の合意があれば一定の範囲で可能ですが、日数や時間に上限があるため、会社は適切な管理を行う必要があります。
産後パパ育休の詳しい制度内容や、出生時育児休業給付金、関連する出生後休業支援給付金については、以下の記事も併せてご確認ください。
STEP5:従業員が育休を延長するとき(育休延長申請)
育児休業は原則として子どもが1歳に達する日までですが、「保育所に入所できない」などのやむを得ない事情がある場合、従業員から育児休業の延長を希望されることがあります。
会社は、従業員からの延長申し出(原則、当初の育休終了予定日の2週間前まで)と、その理由が育児・介護休業法に定める延長事由に該当するかを証明書類(例:保育所の入所不承諾通知書など)に基づき確認し、承認した場合には、主に以下の2つの重要な延長手続きを行います。
- 社会保険料免除の期間延長手続き
- 育児休業給付金の支給期間延長手続き
それぞれの延長手続きについて、具体的に見ていきましょう。
育児休業期間が延長された場合、健康保険および厚生年金保険の社会保険料の免除期間も延長されます。
会社は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の「変更(延長)」に該当する箇所に記入し、延長後の育児休業期間を日本年金機構(管轄の事務センターまたは年金事務所)、または加入している健康保険組合へ速やかに提出します。
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 |
| 提出先 | 事務センター、もしくは管轄の年金事務所健康保険組合 |
| 提出期限 | 育休期間中(または育休終了日から起算して1ヶ月以内) |
なお、育児休業が1歳から1歳6ヶ月へ、さらに1歳6ヶ月から2歳へと段階的に延長される際には、それぞれの延長の段階でこの申出書の提出が必要になる点に注意しましょう。
育児休業給付金も、育児休業の延長が認められれば、延長された期間について引き続き支給を受けることができます。
| 提出書類 | 育児休業給付金支給申請書(延長用) |
| 主な添付書類 | 延長理由を証明する書類(例:保育所の入所不承諾通知書のコピーなど) |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | ハローワークが指定する申請期間(通常、延長後の支給対象期間ごと) |
育児休業の延長理由によって添付書類が異なる場合があるため、詳しくは管轄のハローワークに事前に確認することをおすすめします。
育児休業の延長は、従業員が仕事と育児を両立させる上で重要な選択肢です。会社としては、制度を正しく理解し、従業員からの申し出に対して適切かつ迅速に対応することが求められます。
STEP6:従業員が職場に復帰するとき(育休終了・復職時)
従業員の育児休業が終了し、いよいよ職場へ復帰する際には、会社としていくつかの重要な手続きが必要になります。
社会保険料の免除措置を終了させるための届出や、休業によって給与額に変動があった場合の社会保険料の標準報酬月額の改定、そして将来の年金額への配慮に関する特例措置の申出などが主なものです。
このステップでは、主に以下の3つの対応について詳しく解説します。
- 育児休業終了の届出(社会保険料免除終了)
- 給与・社会保険料の復旧(標準報酬月額変更届)
- 厚生年金養育期間標準報酬月額特例の申出
それぞれの対応について、具体的に見ていきましょう。
育児休業期間中に免除されていた健康保険・厚生年金保険の社会保険料は、育児休業が終了すると再び徴収が開始されます。
会社は、従業員の育児休業が終了した際に「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構(または健康保険組合)へ提出し、社会保険料の免除措置を終了させる手続きを行う必要があります。
この届出を忘れると、社会保険料の免除が不適切に継続してしまう可能性があるため、従業員の復職日を確認したら速やかに手続きを行いましょう。
| 提出書類 | 育児休業等取得者終了届 |
| 提出先 | 日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所)、または加入している健康保険組合 |
| 提出期限 | 従業員の育児休業が終了した後、速やかに |
また、前回のSTEP5で触れたように、産休期間が予定と異なり早期に終了した場合など、産休期間に関する変更があった場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出も必要になることがありますので、併せて確認しましょう。
育児休業から復帰した従業員が、育児のために短時間勤務制度などを利用し、その結果、復帰後の給与(標準報酬月額)が育休開始前と比べて大幅に変動する場合(通常2等級以上の差が生じる場合など)があります。
このような場合には、実際に支給される給与に見合った社会保険料額となるよう、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」(月額変更届)を提出し、標準報酬月額の改定を行うことができます。
この手続きは、育児休業終了後に、従業員が3歳未満の子を養育している場合に、通常の月額変更の条件(継続した3ヶ月間の各月の支払基礎日数が17日以上等)を満たさなくても、復帰した月から3ヶ月間の報酬の平均に基づき、4ヶ月目から標準報酬月額を改定できる特例(育児休業等終了時報酬月額変更届)です。
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(育児休業等終了時報酬月額変更届) |
| 提出先 | 日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所)、または加入している健康保険組合 |
| 提出時期・期限 | 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額に基づき、速やかに(通常、職場復帰から4ヶ月目) |
この手続きを行うことで、従業員の実態に即した社会保険料となり、手取り額への影響も考慮できます。ただし、標準報酬月額が下がると、将来の厚生年金額にも影響が出る可能性があるため、制度について従業員へ丁寧に説明することが望ましいです。
【関連記事】
> 社会保険の月額変更届(随時改定)とは?標準報酬月額の改定条件や手続き方法をわかりやすく解説!
> 標準報酬月額とは?決め方や計算方法、調べ方を社労士がわかりやすく解説(簡易計算ツール付き)
育児休業を取得したり、育児のために短時間勤務を選択したりすることで、厚生年金の標準報酬月額が低下した場合でも、子どもが3歳になるまでの間、将来の年金額を計算する際には、育休や短時間勤務を開始する前の高い標準報酬月額が保障される「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(養育特例)という制度があります。
この特例措置を受けるためには、従業員が会社を通じて「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。この申出は、従業員からの申し出に基づいて会社が行う手続きです。
| 提出書類 | 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 |
| 主な添付書類 | ・申出者と子の身分関係及び子の生年月日を確認できる書類(戸籍謄本または戸籍記載事項証明書、住民票の写しなど)・その他、事実発生日などを確認できる書類(申出期間の途中で退職した場合など) 提出先 |
| 提出先 | 日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所) |
| 提出時期・期限 | 養育を開始した日(または事実が発生した日)以後、速やかに(遡っての申出も可能ですが、時効があります) |
この特例は、育児のために働き方に変化があった従業員の将来の年金額への不利益を緩和するための重要な制度です。
対象となる従業員には、会社から制度を案内し、申出をサポートすることが望まれます。特に、前述の「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出して標準報酬月額が下がった従業員には、この養育特例の申出を併せて案内することが重要です。
【出産手当金と育児休業給付金の申請代行を全国スポット対応!】
社労士クラウドなら顧問料0円、業界最安値の料金で専任の社労士がスポットで申請代行!
- 複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減してコア業務にしたい
- 正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避したい
- 法改正への確実な対応がしたい
\ 顧問料0円で全国対応!/
> 社労士クラウドのスポット料金・報酬を確認する
産休・育休の手続きを進める中で、企業の人事・労務担当者の方から多く寄せられる質問や、判断に迷いやすいケースについて、Q&A形式で解説します。
産休・育休中に会社から業務連絡してもいい?
原則として、産休・育休は労働の義務が免除されている期間ですので、業務に関する指示や強制的な連絡は控えるべきです。
ただし、休業中の従業員の同意を得た上で、業務の引継ぎや復職後の円滑な業務再開のために必要最小限の連絡を取ることは、状況によって許容される場合があります。
例えば、社会保険手続きや給付金申請のために本人確認が必要な場合や、業務の大きな変更があり事前に情報共有しておいた方が本人の不利益にならない場合などです。
重要なのは、連絡の頻度や内容、方法について事前に従業員と話し合い、本人の意向を尊重することです。休業中の従業員が安心して休養に専念できるよう、会社として配慮ある対応を心がけましょう。
育休取得中の社員から早期復職したいと言われたら?
従業員から育児休業期間の途中で早期復職の申し出があった場合、会社は必ずしもその申し出に応じなければならない義務はありません。しかし、可能な範囲で従業員の希望に配慮することが望ましいでしょう。
育児休業の期間は、原則として従業員からの申し出に基づいて決定されます。一度決定した期間を短縮して復職するには、労使双方の合意が必要です。
会社としては、まず従業員の早期復職の理由や希望する復職日、復職後の勤務体制(短時間勤務の希望など)を丁寧にヒアリングします。
その上で、業務の状況や代替要員の配置などを考慮し、受け入れが可能かどうかを判断します。 受け入れが可能な場合は、復職日や労働条件について改めて書面で確認し合うとよいでしょう。
もし、業務の都合等で直ちに希望通りの早期復職が難しい場合でも、その理由を誠実に説明し、可能な時期や条件について話し合う姿勢が大切です。
育休中の社会保険料免除は会社負担分も免除?
育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、従業員負担分だけでなく、会社負担分も共に免除されます。
この免除を受けるためには、会社が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(または健康保険組合)へ提出する必要があります。申し出が受理されれば、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、社会保険料が免除されます。
免除期間中も、従業員の被保険者資格は継続し、将来の年金額の計算においては、保険料を納付したものとして扱われますので、従業員にとって不利益はありません。
産休・育休中の社員に賞与は支給すべき?
産休・育休中の従業員への賞与の支給については、法律で義務付けられているわけではなく、会社の就業規則や賃金規程、労使協約などの定めによります。
多くの企業では、賞与の算定対象期間中の勤務日数や業績への貢献度に応じて支給額を決定しています。産休・育休で長期間労務の提供がなかった場合、賞与が減額されたり、支給されないケースも一般的です。
重要なのは、就業規則等に賞与の支給基準(算定対象期間、出勤率の扱い、休職期間中の取り扱いなど)が明確に定められており、それが不利益な取り扱い(妊娠・出産・育休取得を理由とした不当な減額など)に該当しないことです。
従業員から問い合わせがあった場合には、自社の規程に基づいて、公平かつ客観的に説明できるように準備しておきましょう。
有期契約社員やパートタイム労働者の産休・育休の扱いは?
有期契約社員やパートタイム労働者であっても、産前産後休業は、雇用形態にかかわらず全ての女性労働者が取得できます。
育児休業については、以下の要件を全て満たす場合に取得可能です(2022年4月1日以降)。 ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(この要件は2022年4月1日より撤廃されましたが、労使協定により引き続き1年未満の労働者を対象外とすることは可能です。ただし、その場合でも日雇い労働者は対象外です。) ・子が1歳6ヶ月(保育所に入れない等の場合は2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
会社としては、有期契約社員やパートタイム労働者から産休・育休の申し出があった場合も、正社員と同様に、法律に基づき適切に対応する必要があります。取得要件の確認や、制度の説明を丁寧に行いましょう。
従業員が育休中に第2子を妊娠した場合はどうなる?
育児休業中に従業員が次の子どもを妊娠した場合、いくつかのケースが考えられますが、基本的には新たな産前産後休業や育児休業の権利が発生します。
まず、第1子の育児休業は、第2子の産前休業開始予定日の前日(または第2子を実際に出産した日など、産前休業に入れる状態になったとき)までとなります。
その後、第2子の産前産後休業が開始され、産後休業終了後には、改めて第2子のための育児休業を取得することができます。
第2子の育児休業給付金についても、受給要件を満たせば新たに受給資格が得られます。 会社としては、従業員から第2子妊娠の報告を受けたら、まず第1子の育児休業の終了日を確認し、次に第2子の産前産後休業および育児休業の取得意向、期間などを改めてヒアリングし、必要な手続きを進めることになります。
社会保険料の免除手続きなども、それぞれの休業に合わせて再度行う必要があります。
育休取得を申し出た従業員が、その後退職したいと言ってきた場合の対応は?
育児休業の申し出後に従業員から退職の申し出があった場合、会社としてはまず、退職の意思が固いものであるか、また、退職を希望する理由などを丁寧に確認することが大切です。
育児休業は、職場復帰を前提とした制度です。しかし、従業員が自らの意思で退職を希望する場合、会社はそれを不当に引き止めることはできません。
退職日が育児休業期間中になるのか、育児休業終了後になるのかによって、社会保険の手続きや育児休業給付金の取り扱いが異なる場合があります。
例えば、育児休業給付金は、原則として育児休業終了後の職場復帰を前提としているため、育休開始時点で退職が予定されている場合は支給対象外となる可能性があります。
会社としては、従業員の退職の意思を尊重しつつ、退職日や有給休暇の消化、社会保険の資格喪失手続き、貸与品の返却など、通常の退職時と同様の手続きを進めます。
ただし、育休取得を理由とした退職勧奨や不利益な取り扱いは法律で禁止されていますので、慎重な対応が求められます。
従業員の産休・育休は、企業にとって喜ばしい出来事であると同時に、会社側には多くの手続きが求められる期間でもあります。本記事では、従業員からの妊娠報告から始まり、産休・育休期間中の対応、そして職場復帰に至るまでの一連の会社手続きと、関連する制度について解説してきました。
具体的には、休業取得の意向確認、各種社会保険料の免除申請、出産手当金や育児休業給付金の申請サポート、そして復職時の手続きなど、会社が行うべきことは多岐にわたります。これらの手続きにはそれぞれ期限があり、正確な対応が不可欠です。
産休・育休制度を適切に運用することは、法令を遵守するだけでなく、従業員が安心して働き続けられる環境を提供し、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
しかし、特に初めて対応する担当者の方や、日々の業務で多忙な企業にとっては、これらの手続きを全て正確に、かつ期限内に完了させることは大きな負担となることも少なくありません。
もし、産休・育休に関する手続きの進め方に不安がある場合や、専門的な知識が必要だと感じる場面、あるいは人的リソースが限られている場合には、社労士のような専門家へ相談することも検討していきましょう。
な運営と従業員の安心につながります。5日を過ぎてしまった場合も、社労士の専門知識とサポートを受けることで、大きな問題に発展することなく、会社の安定した運営が可能になります。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|