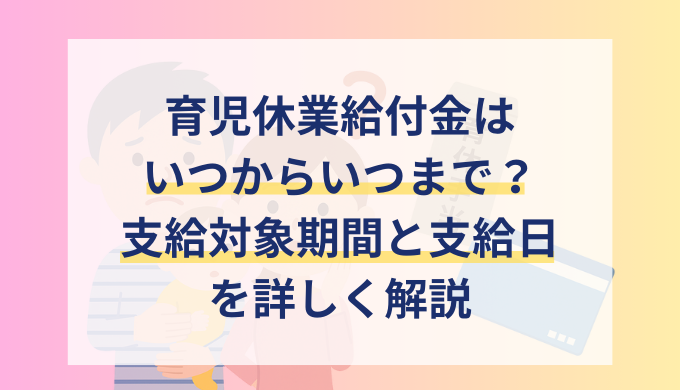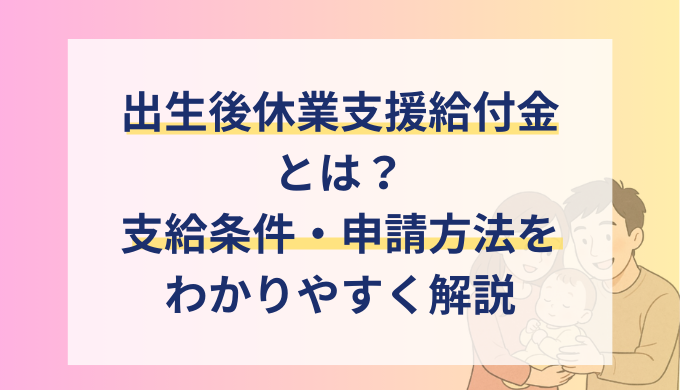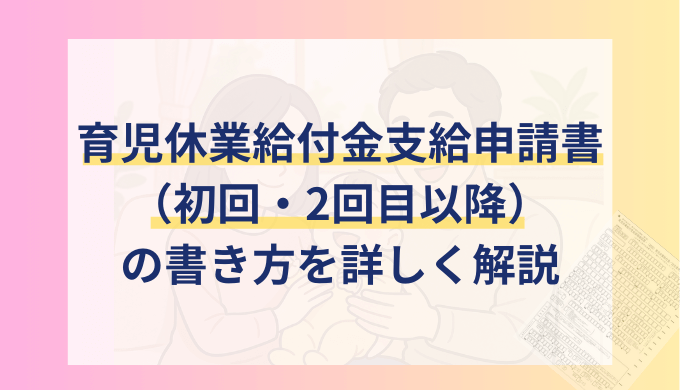育児休業給付金(育休手当)は、従業員の育児と仕事の両立を支える重要な制度ですが、「いつからいつまでもらえるの?」「支給日はいつになるの?」といった対象となる支給期間やタイミングに関する疑問は、特に初めて手続きを担当される方や設立間もない企業の担当者様にとって、分かりにくい点が多いのではないでしょうか。
育休手当の申請は原則として会社(事業主)側が行うため、正しい知識を身に着けておくことが必須。加えて、期間の延長ルールや2025年4月から始まった新制度(出生後休業支援給付金)もあり、最新の情報に基づいた対応が求められます。
この記事では、育児休業給付金の対象となる支給期間(開始・終了の原則から延長ケースまで)、支給日のスケジュール(初回や2回目以降の目安)について詳しく解説します。
従業員への適切な案内や、申請・スケジュール管理をスムーズに進めることができるように、正しい知識を身に着け、従業員の育休手当の給付をサポートしていきましょう。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業の産休・育休で会社が行う必要がある手続きを下記の記事でまとめています。
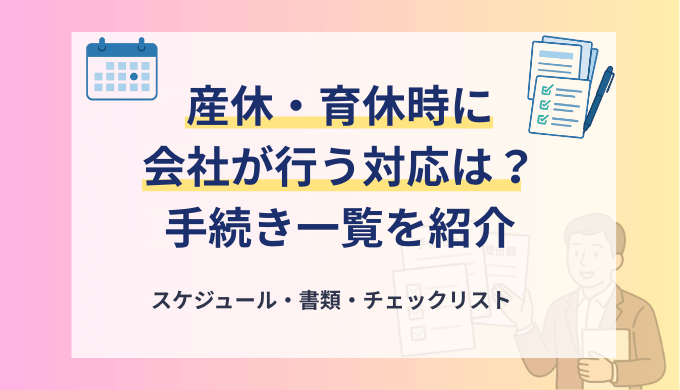 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2025年版】
育児休業給付金(育休手当)とは、従業員が子どもを養育するために育児休業を取得した際に、雇用保険から支給される給付金のことです。育児のために会社を休業する期間中、従業員の収入が大きく減少することを防ぎ、安心して子育てに専念できるよう生活を支援することを目的としています。
この給付金は、会社から支払われる給与とは異なり、一定の条件を満たせば、正社員だけでなく契約社員やパートタイマーなどの従業員も対象となります。また、母親だけでなく父親の取得も可能です。
企業の人事・労務担当者としては、従業員から育児休業の申し出があった際に、この制度の基本的な仕組み(いつからいつまでもらえるのか?支給日はいつなのか?)や、会社として対応すべき手続きの流れを理解しておくことが非常に重要になります。
2025年4月からは法改正による新制度も加わり、支給額や支給期間が変動するケースがあるため、最新の情報を把握しておくことも必要です。
まず育児休業給付金の対象となる従業員の支給条件と、支給金額の基本的な考え方について解説します。
支給条件と対象者
育児休業給付金を受け取るためには、育児休業を取得する従業員が雇用保険の被保険者であり、さらにいくつかの要件を満たす必要があります。
担当者は申請手続きを進める前に、該当する従業員(被保険者)がこれらの条件を満たしているかを確認することが不可欠です。
主に以下の要件をすべて満たす必要があります。
| ・1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者であること ・育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12か月以上あること ・育児休業期間中の就業日数が、1支給単位期間あたり10日(または就業時間80時間)以下であること |
【有期雇用労働者(契約社員・パートタイマーなど)の場合の追加要件】
期間を定めて雇用される従業員の場合は、上記の要件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
| ・養育する子どもが1歳6か月に達する日までに、その労働契約期間が満了することが明らかでないこと |
育休手当の条件や対象期間については下の記事で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい】
> 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
支給金額と計算方法
育児休業給付金の支給金額は、原則として育児休業 開始前の賃金(給与)を基にした計算式で算出され、雇用保険から支給されます。
基本的な考え方として、支給額は以下の計算式で算出され、育児休業(休業)期間によって給付率が異なります。
| 育児休業開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 181日目以降 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50% |
育休開始から約半年間は休業前賃金の約2/3、それ以降は休業前賃金の約半分が支給されるイメージです。
ここでいう「休業開始時賃金日額」とは、原則として育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った額を指します。
育児休業給付金について、担当者として最も正確に把握しておくべきことの一つが、「いつからいつまで」給付金が支給されるのか(支給対象期間)です。従業員への説明はもちろん、申請手続きや社会保険料免除の手続きにも関わるため、基本的なルールをしっかり理解しておく必要があります。
育児休業給付金は、原則、育児休業が開始した日から子どもが1歳の誕生日を迎える日の前日までが支給対象期間となります。ただし、支給が開始されるタイミングは母親と父親で異なり、また、保育所に入れないなどの特定の事情がある場合には、支給期間を延長することも可能です。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
【あわせて読みたい】
> 出産手当金・育児休業給付金の金額・期間の計算ツール
自動計算ツールを使うと、下記画像(4/1が出産日の場合)のように育児休業給付金の対象期間や支給金額を自動で算出することができます。
支給開始は産後休業終了後から
育児休業給付金の支給が開始されるタイミングは、育児休業(育休)が始まった日からです。ただし、この育児休業の開始日は、母親と父親で異なります。
通常、出産日の翌日から8週間は「産後休業」期間となり、この期間は原則として就業できません(※医師の許可があれば6週間後から就業可能)。育児休業は、この産後休業が終了した翌日から開始されます。したがって、育児休業給付金の支給対象期間も、産後休業終了の翌日からスタートします。
(例:4月1日に出産した場合、産後休業は5月27日まで。育児休業は5月28日から開始となり、給付金も5月28日からが対象。)
父親は、子どもの出生日(または配偶者の出産予定日)から育児休業を取得できます。そのため、育児休業を開始した日から、育児休業給付金の支給対象期間が始まります。 なお、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得した場合、その期間に対応する給付金は「出生時育児休業給付金」として支給されます。
通常の育児休業給付金とは別の扱いになる点に注意が必要です。
支給終了は原則子が1歳になる前日まで
育児休業給付金の支給対象期間が終了するのは、原則として、子どもが1歳の誕生日を迎える日の前日までです。
(例:子どもが2025年8月10日に生まれた場合、支給対象期間の終了日は2026年8月9日となります。)
ただし、これはあくまで原則です。
従業員が1歳の誕生日よりも前に育児休業を終えて職場復帰する場合は、その復帰日の前日までが支給対象期間となります。
支給期間を延長できるケース(1歳6ヶ月・2歳まで)
育児休業給付金の対象期間は、原則は子どもが1歳になる前日までですが、特定の事情がある場合には、育児休業の期間を延長し、それに伴って育児休業給付金の支給期間も延長することが認められています。
延長が認められる主なケースとしては、以下の2つのパターンがあります。
夫婦(両親)ともに育児休業を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、子どもが1歳2か月に達する日の前日まで支給期間を延長できます。
この「パパ・ママ育休プラス」制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者が、子どもが1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
「パパ・ママ育休プラス」は、例えば母親が先に1年間育休を取得し、その後父親が交代して2か月間取得するといった柔軟な取得を後押しするものです。
育児休業をしている従業員が、子どもが1歳になった後も職場復帰が困難な特定の理由がある場合、育児休業給付金の支給期間を延長することができます。
◯1歳6か月までの延長
子どもが1歳に達した日後の期間について、以下のいずれかの理由がある場合に申請できます。
- 保育所等への入所を希望し、申し込みを行っているが、当面入所できない場合
- 子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡、負傷、疾病、離婚等により養育が困難になった場合
◯2歳までの再延長
1歳6か月まで延長してもなお、上記の理由が解消されない場合には、子どもが2歳に達する日の前日まで、さらに期間を延長(再延長)することが可能です。
【延長申請の注意点と2025年4月1日からの変更点】
延長を希望する場合は、その都度、延長の申請手続きが必要です。特に保育所等への入所ができないことを理由とする場合、従来は市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」などの証明書類の提出が求められていました。
重要な変更点として、2025年4月1日以降は、この手続きが変更されています。
従来の入所不承諾通知書等に加え、市区町村への保育所等利用申込書の写しなども必要となっていますので、ご注意ください。手続きの詳細は、厚生労働省からの最新情報を必ず確認するようにしましょう。
【2025年4月開始の新制度】出生後休業支援給付金の支給期間
2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新しい制度が開始されました。この制度は、従来の育児休業給付金に上乗せされる形で支給されるもので、特に子どもの出生直後の期間における両親の育児休業取得を強力に支援するものです。
この新給付金が支給される対象期間は、以下の通りです。
| 子の出生後8週間以内に開始される育児休業(休業)のうち、最大28日間(4週間)分 |
この期間について、一定の条件(※)を満たすことで、従来の育児休業給付金(給付率 67%)に加えて、出生後休業支援給付金(給付率 13%相当)が支給されます。
これにより、合計の給付率が80%となり、育児休業(休業)期間中の社会保険料免除の効果と合わせると、休業前の手取り収入の実質10割相当が保障されることになります。
これは、従業員が収入の心配をせずに育児休業を取得しやすくするための画期的な改正です。
(※)新給付金の支給条件(両親ともに14日以上の休業取得など)や申請手続きの詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい】
> 出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
育児休業給付金の支給対象期間と並んで、担当者が従業員からよく質問を受けるのが「給付金はいつ振り込まれるのか?」という支給日や振込のタイミングです。育児休業中の従業員にとって、給付金は生活を支える重要な収入源となるため、支給の目安となるスケジュールを事前に把握し、説明できるようにしておくことが大切になります。
育児休業給付金は、原則として2か月に1度支給されますが、特に初回の支給は育休(休業)開始から時間がかかる場合があります。支給の基本的なサイクル、初回と2回目以降の支給時期の目安について具体的に解説します。
【あわせて読みたい】
> 出産手当金・育児休業給付金の金額・期間の計算ツール
自動計算ツールを使うと、下記画像(4/1が出産日の場合)のように育児休業給付金の支給日(振込日)のスケジュールを自動で算出することができます。
支給サイクル(2ヶ月に1度)
育児休業給付金の支給は、原則として2か月に1回、2か月分がまとめて行われます。
これは、育児休業給付金の申請が、原則として「支給単位期間」ごと、かつ2つの支給単位期間をまとめて行うことになっているためです。
「支給単位期間」とは、育児休業(休業)を開始した日から起算して1か月ごとの期間を指します(例:5月28日に休業開始なら、5/28~6/27、6/28~7/27が各支給単位期間)。
会社(事業主)は、この支給単位期間ごとに従業員の就業日数などを確認し、2つの支給単位期間が経過した後に、まとめてハローワークへ支給申請を行います。その申請に基づいて審査が行われ、支給が決定されるという流れです。
初回の支給日・支給時期の目安
従業員や担当者が最も気にすることの一つが、初回の育児休業給付金がいつ振り込まれるか、という点でしょう。
結論からお伝えすると、初回の給付金がいつ振り込まれるかは、会社がいつ支給申請を行ったかによって大きく変わります。申請は初回申請期間内(育休開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)に行う必要がありますが、その申請タイミングによってで実際の振込日が変動します。
これは、以下のプロセスを経るためです。
- 従業員が育児休業(休業)を開始する。
- 会社(担当者)が初回の申請に必要な書類(賃金月額証明書、受給資格確認票兼初回申請書など)を準備・作成する。
- 最初の2つの支給単位期間が経過するのを待つ。
- 会社がハローワークへ初回の支給申請を行う。
- ハローワークで申請内容の審査が行われる。
- 支給が決定され、指定された口座へ振込が行われる。
特に、会社での書類準備や申請タイミング、ハローワークでの審査にかかる時間によって、初回の支給日は変動します。従業員には、「育休(休業)が始まってすぐにもらえるわけではない」という点を事前に伝えておくことが、後の不安解消につながります。
下記画像のように育児休業給付金(初回)の申請は2025年4月1日が出産日の場合は、2025年7月28日から支給申請を行うことができます。
母親の場合、産後休業(出産翌日から8週間)が終了した翌日から育児休業が開始されます。そのため、初回の給付金が振り込まれるのは、一般的に出産日から数えて4~5か月後が目安となります。
◯ママのスケジュール
- 出産~産後休業終了:約2か月
- 育休開始~最初の2つの支給単位期間終了:約2か月
- 会社の申請準備~ハローワークの審査・振込:約1~2週間から1か月程度
下記画像は4/1に出産した場合の給付金支給のスケジュールです。
担当者としては、産後休業に入る前の面談などで、初回支給の目安時期を伝えておくとともに、申請に必要な書類(母子健康手帳の写しなど)の提出を早めに依頼しておくことが、スムーズな手続きのポイントです。
父親が子どもの出生直後から育児休業を取得する場合、産後休業がないため、母親のケースよりも早く初回の支給を受けられる可能性があります。目安としては、育児休業(休業)開始から2~3か月後程度と考えられます。
◯パパのスケジュール
- 育休開始~最初の2つの支給単位期間終了:約2か月
- 会社の申請準備~ハローワークの審査・振込:約1~2週間から1か月程度
下記画像は4/1から育児休業を取得した場合の給付金支給のスケジュールです。
ただし、これも会社(担当者)がいつ初回申請を行うかによって時期が変動します。男性従業員が育休を取得する場合も、早めに手続きを進めることが重要です。
2回目以降の支給タイミング・目安
初回の支給が無事に行われれば、2回目以降の支給は、比較的スムーズに進むことが多いです。
原則通り会社が2つの支給単位期間ごとに申請を行えば、前回の支給決定から約2か月後に、次の2か月分の給付金が振り込まれるというサイクルになります。ハローワークでの審査も、初回に比べると短期間で済む傾向があります。
下記画像は4/1に出産した場合の給付金支給のスケジュールです。
ただし、注意点もあります。
注意点1:会社の申請タイミング
会社(担当者)が支給申請を行うのが遅れると、当然ながら従業員への振込も遅れてしまいます。担当者は、各従業員の支給単位期間を把握し、期間経過後、速やかに申請するようスケジュール管理を行う必要があります。
注意点2:支給日の変動
支給日が毎月完全に固定されるわけではありません。会社の申請日やハローワークの処理状況、金融機関の営業日などによって、振込日が月によって多少前後する(バラバラになる)ことがあります。従業員から支給日について問い合わせがあった場合は、ハローワークから送付される「支給決定通知書」で確認できる旨を伝えるとよいでしょう。
育児休業給付金の支給を受けるためには、会社(事業主)がハローワークへ申請手続きを行う必要があります。
こちらでは、申請に必要な書類や提出時期・期限、申請から振込までの流れ、そして忘れずに行いたい社会保険料免除の手続きについて、担当者が押さえておくべきポイントを具体的に解説します。
申請に必要な書類と提出時期・期限
育児休業給付金の申請は、原則として会社(事業主)が従業員(被保険者)に代わって行います。初回の申請と2回目以降の申請で必要となる書類や提出時期が異なりますので、しっかり区別して準備を進めましょう。
初回の申請(受給資格の確認と最初の支給申請を兼ねる)には、主に以下の書類が必要です。
【会社(担当者)が作成・準備するもの】
| 必要申請書 | 内容 | 提出先 |
| 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 育休開始前の賃金額を証明する書類。通常、休業開始前6か月分の賃金台帳などを基に作成。 | ハローワーク |
| 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 | 受給資格の確認と初回の支給申請を同時に行うための申請書 | ハローワーク |
| 賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)の写しなど | 賃金月額証明書の記載内容や休業の事実を確認するための補足資料 | ハローワーク |
【従業員から提出してもらうもの】
| 必要申請書 | 内容 |
| 母子健康手帳の写しなど (場合によって)育児休業申出書の写しなど | 育児を行っている事実や出産日、子どもとの関係を確認できる書類。 |
【申請時期・提出期限】
| 初回申請 | |
| 提出可能時期 | 原則として、育児休業(休業)開始日から最初の2つの支給単位期間が経過した後。 |
| 提出期限 | 育児休業(休業)開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。 |
この期限を過ぎると、原則として最初の給付金が受けられなくなる可能性があります。会社として期限管理を徹底することが必須です。
| 2回目以降の申請 | |
| 提出可能時期 | 原則として、前回申請した支給単位期間の次の2つの支給単位期間ごとに申請します。 |
| 提出期限 | 対象となる支給単位期間が終了した後、速やかに提出することが推奨されます。明確な期限は定められていませんが、提出が遅れると支給も遅れます。 |
育児休業給付金支給申請書については下記で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい】
> 育児休業給付金支給申請書の書き方を記入例付きで解説!初回・2回目以降まで
育休手当の申請の流れ
育児休業給付金の申請から振込までは、一般的に以下のような流れで進みます。担当者はこの流れを把握し、各ステップで必要な対応をスムーズに行えるようにしましょう。
申請の流れは、大まかに「従業員からの申し出 → 支給要件確認 → 必要書類準備・申請書作成 → 初回申請 → 2回目以降の継続申請」となります。
【あわせて読みたい】
> 育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
初回申請時に合わせて行う社会保険料免除手続き
育児休業(休業)期間中は、従業員だけでなく会社(事業主)も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが免除される制度があります。
これは育児休業給付金の申請とは別途、手続きが必要ですので、絶対に忘れないようにしましょう。
| 手続き名 | 育児休業等取得者申出書 |
| 提出先 | 会社が加入している年金事務所または健康保険組合 |
| 提出時期 | 従業員が育児休業(休業)を開始した後、速やかに提出します。原則として、休業期間中または休業終了日の翌日から1か月以内に提出する必要があります |
この手続きを行うことで、育児休業を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除されます。給付金の初回申請を行うタイミングで、こちらの免除手続きも忘れずに行うように、担当者はスケジュール管理をすることが重要です。
前のセクションで解説した通り、育児休業給付金の支給、特に初回の振込までには一定の期間がかかります。しかし、会社(担当者)側の手続きの進め方次第で、支給がさらに遅れてしまう事態は避けることが可能です。従業員が安心して育休(休業)を取得できるよう、企業として確実かつ迅速な対応を心がけることが重要です。
ここでは、育児休業給付金を可能な限り早く、そして確実に従業員が受け取れるように、会社(担当者)がすべきこと、注意すべきポイントを3つの観点からご紹介します。
申請書類の準備と迅速な提出
育児休業給付金の支給をスムーズに進める上で最も重要なのは、必要な申請書類を正確に準備し、提出期限を守って迅速にハローワークへ提出することです。
申請書や賃金月額証明書などの書類に不備(記入漏れ、計算誤りなど)があると、ハローワークから差し戻され、修正や再提出が必要となり、支給が大幅に遅れる原因となります。特に賃金の計算などは正確に行い、添付書類(母子健康手帳の写しなど)の漏れがないか、提出前に必ず確認しましょう。
【チェックリスト:よくある申請書類の不備】
□ 申請書の記入漏れ・押印漏れ
□ 賃金月額証明書の賃金額や日数の計算誤り
□ 添付書類(母子手帳の写し、賃金台帳、出勤簿など)の不足・不鮮明
□ 従業員本人が記入すべき箇所が未記入
初回の申請は、育休(休業)開始日から4か月後の末日が提出期限ですが、期限ギリギリではなく、申請が可能になるタイミング(最初の2つの支給単位期間経過後)で、できる限り早く提出することが望ましいです。早く申請すれば、それだけ早くハローワークでの審査プロセスに進むことができます。
申請には従業員本人から提出してもらう書類もあります。担当者は、どの書類がいつまでに必要なのかを事前に従業員へ明確に伝え、早めに準備・提出してもらえるよう協力を依頼しましょう。
社内での申請スケジュール管理
育児休業給付金の申請は、初回だけでなく、2回目以降も原則として2か月ごとに行う必要があります。この2回目以降の申請を会社(担当者)が失念したり、遅れたりすると、その分従業員への支給も遅れてしまいます。確実な支給のためには、社内での申請スケジュール管理が不可欠です。
どの従業員がいつから育休(休業)に入り、次の申請タイミングがいつなのかを、担当者が常に把握できる体制を整えましょう。
- カレンダーやリマインダー機能を活用する。
- 育休取得者ごとの申請状況や次回予定日をまとめた管理表(Excelテンプレートなど)を作成・共有する。
- 担当者が複数いる場合は、責任の所在を明確にする。
会社の規模が大きくなり、複数の従業員が同時に育休を取得するようになると、管理はより複雑になります。従業員ごとに支給単位期間や申請時期が異なるため、個別にスケジュールを管理し、申請漏れがないように注意が必要です。
支給を早める工夫(1ヶ月ごとの申請も可能)
育児休業給付金は原則として2か月に1回の申請・支給ですが、従業員と会社(事業主)が合意すれば、1か月(1つの支給単位期間)ごとに申請し、支給を受けることも制度上は可能です。
従業員は、給付金を毎月受け取れるため、2か月ごとの支給よりも収入の波が小さくなり、生活の見通しが立てやすくなる可能性があります。
- 申請回数が倍になるため、会社(担当者)の事務負担は大幅に増加する
- 申請頻度が増えるだけで、ハローワークでの審査自体が早くなるわけではないため、初回の支給が大幅に早くなるわけでない
- 実施するには、事前に従業員の希望を確認し、会社として対応可能か(事務負担を考慮して)検討する必要がある
この方法は、従業員の経済的な不安が大きい場合などに検討する工夫の一つですが、会社側の負担も考慮し、慎重に判断することが求められます。
従業員から妊娠や育児休業取得の申し出があった場合、会社(担当者)が行うべき手続きや確認事項は多岐にわたります。育児休業給付金の申請だけでなく、社会保険料の免除手続きや復職時の対応など、一連の流れを把握しておくことが重要です。
ここでは、育休開始前から復職後までの期間において、担当者が対応すべき主な事項をチェックリスト形式でまとめました。このチェックリストを活用することで、手続きの漏れを防ぎ、円滑な業務遂行にお役立てください。
【① 育休開始前の対応事項】
- [ ] 従業員からの報告・意向確認:
- 妊娠の報告を受け、育児休業(産後パパ育休含む)の取得希望の有無、期間などの意向を確認します。
- [ ] 制度説明:
- 育児休業制度、育児休業給付金制度(支給期間、金額の目安、申請の流れ)、社会保険料免除制度について従業員に説明します。
- [ ] 育児休業申出書の受理:
- 従業員から「育児休業申出書」を提出してもらい、内容(休業開始予定日・終了予定日など)を確認します。原則、休業開始予定日の1か月前までに提出を受けます。
- [ ] 産前産後休業期間の確認(女性従業員の場合):
- 出産予定日を基に、産前産後休業の期間を確認します。
- [ ] 業務引継ぎのサポート:
- 休業期間中の業務の引継ぎがスムーズに進むよう、従業員や関係部署と連携し、計画を確認・サポートします。
- [ ] 休業中の連絡方法の確認:
- 休業期間中の会社からの連絡方法(メール、電話など)や頻度について、従業員の希望を確認します。
【② 育休開始時・休業中の対応事項】
- [ ] 社会保険料免除手続き:
- 育児休業(休業)開始後、速やかに「育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合へ提出します。(給付金とは別の手続きです!)
- [ ] 給付金:初回申請書類の準備:
- 初回の育児休業給付金申請に必要な書類(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書など)を準備・作成します。従業員から必要な書類(母子健康手帳の写し等)も提出してもらいます。
- [ ] 給付金:初回申請書の提出:
- 最初の2つの支給単位期間が経過した後、必要書類を揃えて管轄のハローワークへ提出します。(期限:休業開始日から4か月後の末日)
- [ ] 給付金:支給決定通知書の確認:
- ハローワークから「支給決定通知書」が届いたら内容を確認し、支給額や支給日の目安などを従業員へ連絡すると丁寧です。
- [ ] 給付金:2回目以降の定期申請:
- 原則として2か月ごとに、従業員の休業状況(就業日数など)を確認し、ハローワークへ支給申請を行います。申請が遅れると支給も遅れるため、スケジュール管理が重要です。
- [ ] (延長の場合)延長申請手続き:
- 従業員から期間延長の申し出があった場合、理由(保育所に入所できない等)を確認し、必要書類を揃えてハローワークへ延長の申請を行います。(2025年4月からの手続き変更にも注意)
- [ ] 休業中の定期連絡:
- 事前に取り決めた方法で、従業員と定期的に連絡を取り、状況確認や会社からの情報提供を行います(過度な連絡は控える)。
【③ 復職時・復職後の対応事項】
- [ ] 復職日の最終確認:
- 従業員と連絡を取り、復職日を最終確認します。
- [ ] 社会保険料免除終了の手続き:
- 育児休業が終了したら、「育児休業等取得者終了届」を年金事務所等へ提出します(※現在は多くの場合で提出不要となっていますが、会社の加入状況等により確認が必要です)。
- [ ] 社会保険料標準報酬月額の改定手続き:
- 復職後、時短勤務などで給与が下がった場合、従業員の申し出に基づき「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所等へ提出することで、社会保険料の負担が軽減される場合があります。
- [ ] 給付金:最終回の支給申請:
- 復職した期間を含む最後の支給単位期間について、育児休業給付金の支給申請を行います。
- [ ] 復職後の勤務条件の整備:
- 従業員が希望する場合、時短勤務などの制度利用に関する手続きを行います。
- [ ] 復職後面談の実施:
- 復職後の従業員と面談を行い、業務へのキャッチアップや両立支援について話し合います。
※このチェックリストは、育児休業に関する主な手続きを網羅することを目的とした一例です。会社の規定や従業員の個別の状況、最新の法令等により、必要な対応が異なる場合があります。詳細な手続きについては、必ず管轄のハローワークや年金事務所、または社労士にご確認ください。
育児休業給付金の支給日や支給期間については、従業員から様々な質問が寄せられることがあります。担当者として正確な情報を把握し、疑問に的確に回答できるようにしておくことは、従業員の不安解消と会社への信頼につながります。
ここでは、支給日や支給期間に関して特によくある質問とその回答をまとめました。
育児休業給付金の支給日がバラバラな理由は?
育児休業給付金の支給日は、毎月決まった日(例:毎月25日など)ではありません。振込日が月によって多少変動する(バラバラになる)主な理由は以下の通りです。
- 会社の申請タイミング: 給付金は原則として2か月ごとに申請しますが、会社がいつ申請手続きを行うかによって、審査開始のタイミングが変わるから。
- ハローワークの審査期間: 申請を受け付けたハローワークでの審査にかかる時間は、混雑状況などによって変動する可能性があるから。
- 金融機関の営業日: 支給決定後の振込処理日が土日祝日にあたる場合、実際の振込は翌営業日となるから。
多少のずれは通常起こりうることですが、あまりにも支給が遅れる場合は、申請状況を確認した方がよいでしょう。
育児休業給付金は復帰した月までもらえますか?
正確には、「復職日の前日まで」が育児休業給付金の支給対象期間となります。
例えば、5月15日に復職する場合、育児休業期間は5月14日までとなり、給付金も5月14日分までが支給されます。
最終回の支給申請では、復職した月(上記の例では5月)の休業日数(14日分)に基づいて支給額が計算され、支給されることになります。この最終回の申請は、復職後に会社(担当者)が行います。
育児休業給付金はいつ振り込まれるか確認する方法はありますか?
従業員が支給日を確認する最も確実な方法は、ハローワークから発行される「育児休業給付金支給決定通知書」を確認することです。
この通知書は、支給申請ごとに審査が行われ、支給が決定された際に発行され、支給額とともに支給予定日(振込予定日)が記載されています。通常、この通知書は会社宛てに送付されることが多いので、担当者は内容を確認し、従業員へ連絡すると丁寧です(場合によっては従業員へ直接送付されることもあります)。
支給決定通知書が届かない、または予定日を過ぎても振込がない場合は、会社(担当者)から管轄のハローワークへ申請状況を問い合わせてみましょう。
育児休業給付金の最終回が振り込まれない時の原因は?
最終回の育児休業給付金がなかなか振り込まれない場合、いくつかの原因が考えられます。
- 最終回の申請が未提出または遅延: 復職後、会社(担当者)が最終回の支給申請をハローワークへ提出し忘れている、または提出が遅れている。
- 申請書類の不備: 提出した最終回の申請書に記入漏れや誤りがあり、ハローワークで手続きが止まっている(差し戻されている)。
- 支給要件を満たさなかった: 最終の支給単位期間において、復職前に従業員が就業し、その日数や時間が上限(原則10日/80時間)を超過したため、不支給となった。
- 振込口座の変更・相違: 従業員が振込先の口座を変更したが、会社やハローワークへの届出がされていなかった。
- ハローワークでの処理遅延: 繁忙期などで審査や振込の手続きに通常より時間がかかっている。
担当者としては、まず最終回の申請が会社から確実に提出されているか、提出した書類に不備がなかったかを確認しましょう。ハローワークから不支給決定通知書などが届いていないかも併せて確認し、原因が不明な場合は、管轄のハローワークへ問い合わせるのが確実です。
この記事では、育児休業給付金(育休手当)について、特に担当者の方が押さえておくべき「いつからいつまで」という支給期間と、「いつ」振り込まれるのかという支給日・タイミングを中心に、制度の基礎知識から申請手続きの流れ、企業として注意すべき点などを解説してきました。
育児休業給付金は、従業員が安心して子育てに専念するために非常に重要な制度です。担当者として制度の内容を正しく理解し、手続きをスムーズに進めることは、従業員の不安を解消し、育児休業(休業)後の円滑な職場復帰を支援することにも繋がります。
育児休業に関する手続きは、特に初めて対応される担当者の方や、設立間もない企業にとっては、少し複雑に感じられる部分もあるかもしれません。しかし、基本的なルールや流れを把握しておけば、落ち着いて対応できるはずです。
もし、手続きに不安がある場合や、最新の法改正への対応、個別のケースについて確認したい場合は、厚生労働省やハローワークの情報を確認するとともに、専門家(社労士など)に相談することも有効な手段です。
ぜひ、この記事で得た知識を活用し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境づくりと、そのサポートにお役立てください。
育児休業給付金支給申請書に関する相談や申請を社労士がスポット代行
育児休業給付金支給申請書の作成や一連の申請手続きは、専門的な知識が求められ、記入項目も多く複雑です。「書き方は理解できたけれど、自社で正確にできるか不安…」「他のコア業務に集中したいので、手続きは専門家に任せたい」といったお悩みはありませんか?
そのような場合には、社労士に相談したり、申請の代行を依頼したりするのも有効な選択肢の一つです。
「社労士クラウド」は、顧問契約が不要で、必要な手続きだけを依頼できる『スポット契約』に特化した社労士サービスです。
「育児休業給付金の申請だけをお願いしたい」「申請書の内容チェックだけしてほしい」といったご要望にも、顧問料0円で柔軟に対応いたします。設立間もない企業様や、普段は自社で手続きしているけれど今回だけ不安がある、といった企業様にも多くご利用いただいています。
経験豊富な社労士が、最新の法改正にも対応しながら、正確かつ迅速な申請手続きをサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|