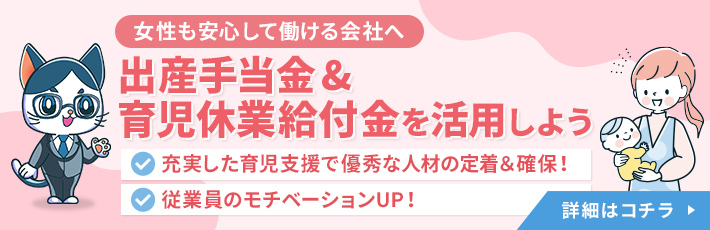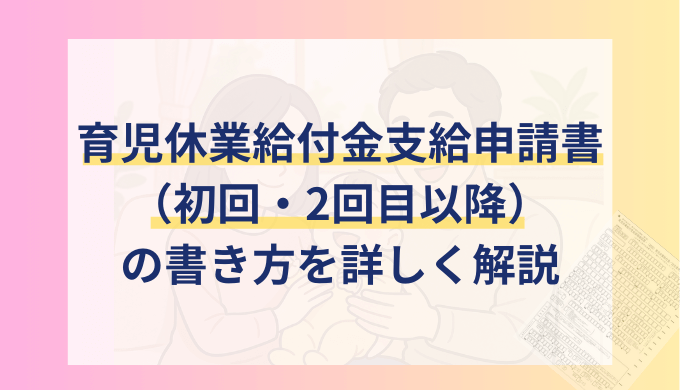育児休業給付金(育休手当)は、従業員の育児と仕事の両立を支える重要な制度ですが、その支給条件は複雑で、「うちの従業員は対象になる?」「雇用保険の加入期間はどれくらい必要?」「最新の条件はどう変わった?」といった疑問を持つ事業主や人事・労務担当者様も多いのではないでしょうか。
育児休業給付金の受給資格(もらえる条件)を正確に理解し、適切に対応することは、従業員の権利を守るだけでなく、育休取得に関するトラブルを未然に防ぐためにも不可欠です。
特に、雇用保険の加入期間の計算や、パート・契約社員といった有期雇用労働者の扱い、休業中の就業制限などは、間違いやすいポイントと言えます。
この記事では、育児休業給付金(育休手当)の基本的な制度概要から「もらえる条件(支給要件」、対象期間について、専門家の視点で詳しく解説しています。
さらに、対象外となるケース、2人目・3人目以降の注意点についても紹介しています。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
従業の産休・育休で会社が行う必要がある手続きを下記の記事でまとめています。
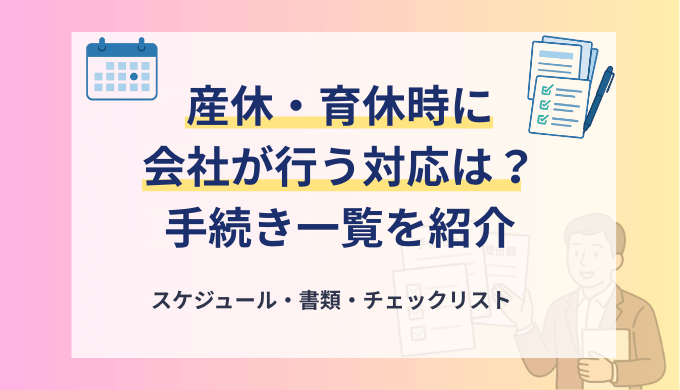 産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
産休・育休時の会社手続き一覧とスケジュール!提出書類やチェックリストつき【2026年版】
育児休業給付金(育休手当)は、従業員が仕事と育児を両立できるように支援する目的で雇用保険から支給される重要な制度です。
休業前の賃金の一定割合(原則として最初の6ヶ月は67%、それ以降は50%)が支給され、子育て世代の経済的負担を軽減します。支給額は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税はかからないのもポイントです。
この給付金は雇用保険の被保険者が対象となるため、パートタイマーや契約社員を含む従業員が、一定の支給要件を満たせば受給可能です。また、男性も女性も平等に対象となります。支給期間は原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入所できないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長が可能です。
2025年4月からは法改正による新制度も加わり、支給額や支給期間が変動するケースがあるため、最新の情報を把握しておくことが必要です。事業主や企業の担当者としては、従業員が育児休業を申し出た際に、この給付金制度の概要や受給要件を正確に理解し、適切な申請手続きと社内調整を進めることが求められます。
具体的には、
- 雇用保険の加入期間や就業実績などの支給要件を確認する
- 休業前賃金をもとにした支給額の目安を提示する
- 従業員が休業に入るタイミングや復帰予定日を確定させ、必要書類の準備や提出スケジュールを整える
といったステップが欠かせません。従業員への説明責任を果たし、スムーズな申請と職場復帰をサポートするためにも、育児休業給付金の基本的な仕組みをしっかりと押さえ、最新情報のアップデートを定期的に行いましょう。
このように、育児休業給付金は企業にとっても、人材の定着や従業員満足度向上につながる重要な制度です。事業主や企業担当者は、従業員からの質問や不安を解消できるように、正確な知識と丁寧な説明を心がけましょう。
育休中は社会保険料(厚生年金・健康保険)が免除に
育児休業中は、給与からの社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除されます。この制度は、育児休業給付金とは別の経済的支援策として大きなメリットとなります。
具体的には、育児休業等取得者申出書(新規・延長)を会社経由で年金事務所に提出することで、育児休業期間中の社会保険料が本人負担分も事業主負担分も全額免除されます。免除の期間は、育児休業を開始した月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
例えば、4月15日から11月20日まで育児休業を取得する場合、4月から11月までの8ヶ月間の社会保険料が免除されます。
この社会保険料免除には以下のメリットがあります。
- 育休中の家計負担が大幅に軽減される(給与の約15%相当)
- 免除期間中も年金受給資格の「加入期間」としてカウントされる
- 将来の年金額計算において不利にならない(標準報酬が下がらない)
ただし、会社側での申請手続きが必要なため、育児休業取得時に人事部門に確認することをおすすめします。また、免除は毎月の保険料についてであり、ボーナスからの天引きがある場合は、ボーナス時期と免除期間を確認する必要があります。
社会保険料の免除と育児休業給付金(67%/50%)を合わせると、育休中の手取り収入は休業前の約8割程度を確保できるケースが多く、経済的な不安を軽減しながら育児に専念できる環境が整備されています。
【2025年4月改正】新設された2つの給付金(出生後休業支援・育児時短就業)とは?
2025年(令和7年)4月1日より、育児休業に関連する雇用保険の給付金制度が拡充され、新たに以下の2つの給付金が創設されました。
従業員の育児と仕事の両立をさらに支援するための重要な改正です。
| 制度名称 | 主な目的・対象 | 概要(簡単な内容) |
| 出生後休業支援給付金 | 子の出生後早期(産後8週以内)の育児休業取得支援 | 育児休業給付金(67%)に13%相当額を上乗せ支給(最大28日)。額面80%支給で実質手取り10割相当に。 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育するための時短勤務支援 | 時短勤務中の賃金の10%相当額を支給。 |
これらの新制度は、従業員がより柔軟な働き方を選択しやすくなるよう後押しするものです。企業としては、制度内容を正確に理解し、対象となる従業員へ適切に情報提供を行うことが重要です。
特に「出生後休業支援給付金」は、従業員の育休取得意欲にも影響する可能性があります。詳しい支給要件や申請手続きについては、以下の記事で解説していますので、合わせてご確認ください。
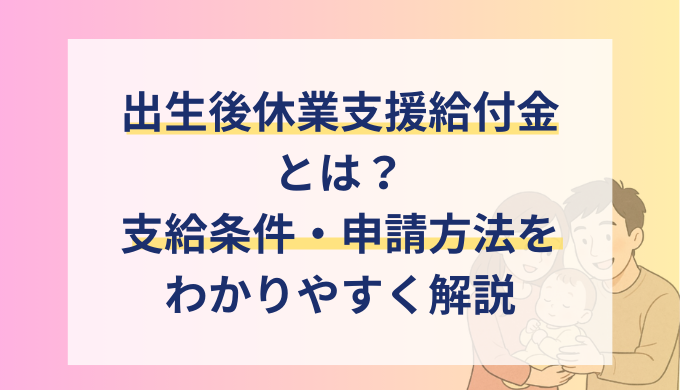 【2025年4月~】出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
【2025年4月~】出生後休業支援給付金とは?支給条件・申請方法を社労士がわかりやすく解説
育児休業給付金は、育児休業を取得するすべての従業員が自動的にもらえるわけではありません。受給するためには、雇用保険法で定められたいくつかの支給要件(条件)をすべて満たす必要があります。
事業主や企業の担当者様は、従業員から育休の申し出があった際、まず育児休業給付金の受給資格を満たしているかを確認することが、適切な手続きの第一歩となります。
ここでは、育児休業給付金を受け取るためにクリアすべき主な条件を一つずつ詳しく解説していきます。
特に、雇用保険の加入期間や有期雇用従業員の扱いなど、間違いやすいポイントもありますので、しっかりと内容を理解し、従業員への正確な説明や確認作業に役立ててください。
条件1:雇用保険の被保険者であること
まず大前提として、育児休業給付金は雇用保険制度から支給されるため、育児休業を開始する時点で従業員が雇用保険の被保険者であることが必須条件です。
雇用保険は、原則として労働者を一人でも雇用する事業所に適用され、一定の要件(週の所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みなど)を満たす従業員は加入義務があります。
正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員であっても、要件を満たせば被保険者となります。
【ポイント】
- 雇用保険に加入していない、または加入資格のない方(例:自営業者、法人の代表者・役員の一部など)は、育児休業を取得したとしても、育児休業給付金の支給対象にはなりません。
- 従業員の雇用保険加入状況は、入社時や雇用契約変更時に必ず確認し、適切に管理しておく必要があります。
条件2:1歳未満の子を養育するための育児休業であること
育児休業給付金の対象となるのは、原則として「1歳に満たない子」を養育するために取得する育児休業です。 ここでの「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。
この条件は、育児休業給付金が、特に出産後から1歳までの、子育てに手がかかる時期の休業を経済的に支援することを目的としているためです。
【ポイント】
- 対象となる子の年齢は、育児休業を開始する時点ではなく、休業期間中に1歳未満であることが基本です。
- 保育所に入所できない等の特定の理由がある場合は、子が1歳6か月、または最長で2歳に達するまで育児休業を延長でき、それに伴い給付金の支給期間も延長される可能性があります(延長条件の詳細は後述します)。
- 配偶者が専業主婦(夫)であるなど、家庭の状況に関わらず、従業員自身が主体的に養育するために休業するのであれば対象となります。
条件3:休業開始前の就業実績(雇用保険の加入期間)
育児休業を始める前の雇用保険加入期間が一定以上あるかという点が、育児休業給付金を受給するうえで重要な支給要件となります。
具体的には、「休業開始日前2年間」に、雇用保険に一定期間以上加入していたことを証明できなければなりません。
「転職して間もない」「入社して1年未満」という場合は、特にこの条件を満たせるかどうか注意が必要です。給付金は雇用保険の保険料を原資としているため、保険料をどの程度納めているか(= 被保険者期間)が重要視されます。
【原則的な要件】
育児休業開始日(※)の前2年間に、
1. 賃金支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)が11日以上の月(「完全月」と呼ぶ)
または
2. 1)の条件を満たさない月でも、就業時間が80時間以上ある月が、合計で12か月以上あること。
※産前産後休業を取得している場合は、その休業開始日、またはそれ以前の妊娠・出産等による休業開始日を起算点にして2年間を遡ります。
【賃金支払基礎日数とは】
給与計算の基礎となる日数のことで、月給制の従業員なら暦日数(30日や31日)、日給制の従業員なら実際に出勤した日数などが該当します。
【特例:判断期間の延長】
病気やケガ、家族の介護などのやむを得ない理由で30日以上連続して賃金が支払われなかった期間がある場合、その期間分を除いて最大4年まで遡って加入期間を確認できます。
一見、条件を満たさないように見える場合でも、この特例に該当するかハローワークに確認してみましょう。
条件4:育休中の就業日数・時間に制限があること
育児休業期間中でも完全に働けないわけではありませんが、「育児に専念するための休業」という制度の趣旨を踏まえ、就業日数や時間には明確な上限が設けられています。
この上限を超えて働いてしまうと、該当する月の育児休業給付金が支給されなくなるため、特に臨時的な業務依頼があった場合は、慎重に日数・時間を管理する必要があります。
【就業制限の具体的な基準】
- 1ヶ月(支給単位期間)あたりの就業日数が10日以下であること
- または、10日を超える場合でも総就業時間が80時間以下であること
【実務上の注意点】
- この制限は「1ヶ月(支給単位期間)ごと」に適用されます
- 特定の月だけ制限を超えた場合、その月の給付金のみが不支給となります
- 在宅ワークや短時間の一時的な出勤も「就業」としてカウントされます
- 賃金が発生する業務のみが対象(社内行事や研修への任意参加などは除外)
短期の仕事を引き受ける場合は、上限に余裕を持たせて計画することを
条件5:育休中の賃金支払いに制限があること
育児休業期間中に会社から賃金が支払われる場合、その金額によって育児休業給付金が減額されたり、場合によっては支給されなくなったりします。
育児休業給付金は休業中の所得保障を目的としているため、会社から十分な賃金が支払われる場合には、給付の必要性が低下すると考えられています。
【賃金支払いの制限ルール】
- 各支給単位期間において、
- 休業開始前の1か月あたりの賃金(休業開始時賃金月額)の80%(8割)以上の賃金が会社から支払われていないこと。
【具体的な影響】
- 会社から休業開始前賃金の80%以上が支払われた場合:その月の育児休業給付金は全額不支給
- 会社から一部賃金が支払われた場合(80%未満):賃金額に応じて給付金が段階的に減額
- 賞与(ボーナス)も支給時期によっては判定に含まれるため注意が必要
【実例】
休業前の月収が30万円だった場合、会社から月24万円(30万円×80%)以上の賃金が支払われると、その月の育児休業給付金は支給されません。月15万円の賃金が支払われる場合は、給付金が一部減額されます。
契約社員・パート等の追加条件
契約社員やパートタイマーなど、期間の定めのある労働契約(有期雇用契約)で働く従業員が育児休業給付金を受給するには、前述の条件に加えて追加要件があります。
これは育児休業制度が「職場復帰」を前提としているため、休業後も雇用が継続される見込みを確認するためのものです。
【有期雇用労働者の主な追加要件】
契約満了が明らかでないこと:
・養育する子が1歳6か月(延長時は2歳)に達するまでに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
【法改正による緩和措置】
- 以前は「同一事業主での1年以上の継続雇用」という条件がありましたが、2022年4月の法改正により撤廃されました
- 現在は、労使協定で除外対象として定められていない限り、入社1年未満の有期雇用労働者も育児休業の取得が可能です
- ただし、給付金の受給には他の条件(特に雇用保険加入期間の要件)を満たす必要があります
【実務上の判断ポイント】
- 「契約満了が明らかでない」とは、契約書に「更新しない」と明記されている場合や雇止めが確定している場合を除き、原則としてこの要件は満たされると考えられます
- 契約更新の有無が不明確な場合でも、直ちに要件を満たさないとは判断されません
- 判断に迷う場合は、管轄のハローワークに相談することをお勧めします
育児休業給付金は、前述した支給要件をすべて満たしていることが大前提ですが、たとえ要件を満たしているように見えても、特定の状況下では支給対象とならない、あるいは給付が受けられないケースが存在します。
対象外となる主なケースについても正しく理解し、従業員への説明や手続きの際に誤解が生じないよう注意が必要です。
ここでは、育児休業給付金が支給されない代表的なケースを3つご紹介します。自社の従業員が該当しないか、事前に確認しておきましょう。
ケース1:育休開始時点で退職予定がある場合
育児休業の開始時点で、既にその育児休業期間の終了後に退職することが決まっている従業員は、原則として育児休業給付金の支給対象となりません。
なぜなら、育児休業制度および育児休業給付金は、従業員が育児のために一時的に休業した後、最終的に元の職場へ復帰することを基本的な前提としているためです。休業開始前に退職が決まっている場合は、職場復帰の意思がないと判断され、制度の趣旨に合致しないため、給付の対象から外れます。
従業員から育児休業の申し出があった際に、休業後の復職意思を確認することが重要です。退職の意向が明確な場合は、給付金の対象外となる旨を説明する必要があります。
【注意点】
育児休業期間中にやむを得ない理由で退職することになった場合は、退職日までの期間については、他の支給要件を満たしていれば原則、給付金を受け取ることができます。しかし、当初から退職を予定している場合は対象外です。
ケース2:雇用保険に加入していない、または加入期間が不足している場合(転職直後など)
育児休業給付金は雇用保険制度の一部であるため、雇用保険に加入していない方や、加入していても必要な被保険者期間を満たしていない方は支給対象となりません。
【雇用保険に加入していないケース】
以下の方々は雇用保険制度の適用外となるため、育児休業給付金を受け取ることができません。
- 自営業者やフリーランスの方
- 法人の代表者や一部の役員(原則として労働者でないため)
- 雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間など)を満たさない短時間労働者
【加入期間が不足しているケース】
前述の「条件3:休業開始前の就業実績」で説明した要件(育休開始前2年間に被保険者期間が12か月以上)を満たせない場合も対象外となります。
特に注意が必要なのは「転職して間もない従業員」や「入社1年未満の従業員」のケースです。
このような場合、前の職場での加入期間と通算しても12か月に満たない可能性があります。また、前の職場を離職後に失業手当(基本手当)の受給資格決定を受けていると、その前の期間は通算されないため特に注意が必要です。
被保険者期間の計算方法や特例(判断期間の延長)については、「条件3」の解説を参照してください。判断に迷う場合は、ハローワークへの確認が確実です。
育休中に一定以上の賃金が支払われた、または働きすぎた場合(有給の扱い含む)
育児休業期間中に、会社から一定額以上の賃金が支払われたり、定められた日数・時間を超えて就労したりした場合は、その期間の育児休業給付金が支給されない、または減額されます。
育児休業はあくまで育児のための休業であり、給付金はその間の所得を補填するものです。そのため、会社からの十分な収入がある場合や、休業とは言えないほど働いている場合には、給付の必要性が低いと判断されます。
【賃金支払いによる影響】
- 各支給単位期間において、休業開始前の1か月あたりの賃金の80%以上の賃金が支払われた場合、その期間の給付金は全額不支給となります
- 80%未満であっても賃金が支払われた場合は、その額に応じて給付金が減額されます
【就労日数・時間による影響】
各支給単位期間において、就労日数が10日を超える場合(または就労時間が80時間を超える場合)、その期間の給付金は全額不支給となります
【有給休暇の取得と給付金】
- 育児休業期間中の有給休暇取得自体は、直ちに給付金対象外になるわけではありません
- ただし、有給休暇取得により支払われた賃金が休業前賃金の80%以上となれば、給付金は不支給となります
- また、有給休暇取得日が「就業した日」としてカウントされ、月10日または80時間を超えると不支給となる可能性があります
- 「育休中に有給を使うと絶対にもらえない」というのは誤解ですが、給付額に影響が出る可能性がある点は、従業員に説明しておく必要があります
育児休業給付金がいつからいつまで支給されるのか、その対象期間を正確に把握することは、従業員への説明や手続きにおいて非常に重要です。 原則となる期間に加え、特定の条件下では期間が延長されるケースもあります。
ここでは、育児休業給付金の基本的な支給対象期間と、期間が延長される主なパターンについて解説します。従業員の状況に合わせて適切な期間を案内できるよう、しっかりと確認しましょう。
原則の支給期間は子が1歳になるまで
育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日(実際には1歳の誕生日の前々日)まで支給されます。
具体的には、1歳の誕生日の前々日までが支給対象です。(休業終了日が月の途中になる場合は、その休業終了日までとなります。)
例えば、2024年6月1日に出産した場合、出産後56日(6月2日~7月27日)までは産後休業になり、2024年7月28日~2025年5月31日までが育児休業となります。
また、育児休業給付金は、実際に育児休業した日数を対象に支給されるので、任意で育児休業期間を短縮した場合、育児休業給付金の支給期間も短縮されることになります。
ただし、支給が開始される日は、母親と父親で異なる点に注意が必要です。
| 母親の場合 | 出産日後の産後休業期間(通常8週間)が終了した翌日から、子が1歳に達する日まで |
| 父親の場合 | 子の出生日(または出産予定日)から、子が1歳に達する日まで。(産後パパ育休(出生時育児休業)を取得する場合は、その休業とは別に通常の育児休業を開始した日からとなります。) |
(※)「1歳に達する日」とは、法律上、1歳の誕生日の前日を指します。
支給期間の延長条件(1歳6ヶ月・2歳まで/保育園に入れない等)
特定の状況下では、原則である「子が1歳になるまで」の期間を超えて、育児休業給付金の支給期間を延長することが可能です。これは、育児休業を延長せざるを得ない従業員の経済的支援を継続するための措置です。
延長は段階的に認められ、まず子が1歳6か月に達する日まで、さらに状況が変わらない場合は子が2歳に達する日まで、最大2段階で延長できます。
延長が認められる主な理由は以下の通りです。
1. 保育所等への入所ができない場合
子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間について、保育所等での保育を希望し申込みを行っているものの、当面その保育の実施が行われない場合に延長が認められます。
具体的には、1歳時点で入所できなければ1歳6か月まで、1歳6か月時点でも引き続き入所できなければ2歳まで延長可能です。
2. 子の養育を行う予定だった配偶者の状況変化
当初、子の養育を行う予定だった配偶者が、以下のいずれかの状況に該当し、子の養育を行うことが困難となった場合に延長が認められます。
- 死亡したとき
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、子の養育が困難になったとき
- 離婚その他の事情により、配偶者が子と別居することになったとき
- 配偶者が産前産後休業(※)を取得することになったとき
(※)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しない場合を指します。
3. その他(対象となる子が負傷・疾病等で要看護の場合など)
上記以外にも、延長対象となる子が負傷・疾病等で相当期間にわたり看護が必要となった場合や、新たな産前産後休業・育児休業・介護休業の取得により養育が困難となる場合など、個別の事情に応じて延長が認められるケースがあります。
【2歳までの再延長について】
上記1~3のいずれかの理由により、子が1歳6か月に達する日後も育児休業を延長する必要がある場合は、子が2歳に達する日までの間、さらに育児休業給付金の支給を受け続けることができます。
期間延長を希望する場合は、延長が必要になった時点(通常、子が1歳または1歳6か月に達した後の最初の支給申請と同時)で、改めて延長申請の手続きが必要です。
延長理由に応じて、「保育所入所不承諾通知書」や医師の診断書、住民票などの証明書類の提出が求められます。延長の判断基準や必要書類は個別のケースによって異なる場合があるため、必ず事前に管轄のハローワークに確認してください。
パパ・ママ育休プラス利用時の延長
「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、支給期間を子が1歳2か月に達する日まで延長できます。 これは、両親が協力して育児休業を取得することを奨励するための特例制度です。
この制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【パパ・ママ育休プラスの利用要件】
| 配偶者の育休取得 | 従業員本人が育児休業を取得しようとする時点で、その配偶者(※)が、子が1歳に達する日以前において育児休業を取得していること |
| 本人の育休開始時期 | 従業員本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること |
| 本人の育休開始時期 (配偶者との関係) | 従業員本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること |
(※)事実婚の配偶者も含まれます。
【制度活用のポイント】
| 支給延長期間 | この制度利用時の給付金支給期間は子が1歳2か月に達する日の前々日まで |
| 個人の上限は変わらない | 夫婦それぞれが取得できる育児休業期間の上限(産後休業期間含む)は、原則として1年間。この制度を利用しても、1人あたりの取得可能日数は延びません |
| 同時取得の扱い | 両親が同時に育児休業を取得している期間については、**原則としてパパ・ママ育休プラスの対象とはなりません。(通常の1歳までの期間として扱われます) |
【具体例】
この制度を活用することで、例えば、産後休業8週間を含めて子が1歳になるまで母親が育児休業を取得し、母親の復職と同時に、父親が子が1歳2か月になるまで育児休業を取得した場合、母親は産後休業の後から子が1歳になるまで、父親は子が1歳になってから1歳2か月に達するまでに、それぞれ育児休業給付金を受け取れます。
このように、夫婦で協力してより長く子育てに関わることが可能になります。
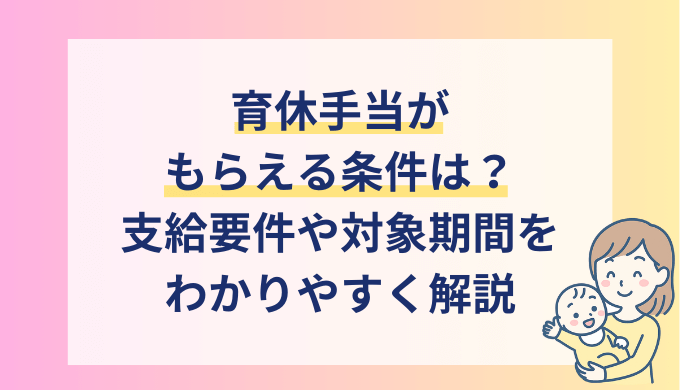 育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
育休手当(育児休業給付金)とは?もらえる条件や対象期間を詳しく解説
2人目、3人目以降の育児休業であっても、基本的な支給要件を満たせば育児休業給付金を再度受給することはできます。育児休業給付金は「子ども一人につき」支給される制度であるため、子どもごとに新たな受給権が発生します。
ただし、1人目の育休からの期間や復職状況などによって、特に注意すべき点がいくつか存在します。
特に「雇用保険の加入期間」や「賃金日額の算定」において、通常とは異なる扱いになる可能性があります。ここでは、基本的な考え方と、人事・労務担当者として押さえておきたい特有の注意点、よくある質問について解説します。
基本的な支給条件は同じ?再確認ポイント
2人目、3人目の育児休業であっても、適用される育児休業給付金の基本的な支給条件は、1人目の場合と変わりありません。
つまり、「育児休業給付金をもらえる条件と対象者」で解説した以下の条件を、2人目・3人目の子のための育児休業開始時点で改めて満たしている必要があります。
- 条件1:雇用保険の被保険者であること
- 条件2:原則1歳未満の子を養育するための育児休業であること
- 条件3:休業開始前の就業実績(雇用保険の加入期間)があること
- 条件4:育休中の就業日数・時間に制限があること
- 条件5:育休中の賃金支払いに制限があること
- (有期雇用の場合)契約社員・パート等の追加条件
これらの基本的な条件については、「育児休業給付金をもらえる条件と対象者」をご確認ください。
以下では、2人目以降のケースで特に注意が必要な点に絞って解説します。
注意点①:続けて育休に入る場合の「雇用保険の加入期間」はどう数える?
1人目の育児休業終了後、職場復帰せずに続けて2人目の産前産後休業・育児休業に入るケースでは、「条件3:休業開始前の就業実績(雇用保険の加入期間)」の計算に注意が必要です。
通常、この条件は「育児休業開始日前の2年間」に必要な被保険者期間(原則12か月以上)があるかを見ますが、1人目の育児休業期間中は賃金の支払いがないため、そのままでは期間要件を満たせない場合があります。
【基本的な考え方】
このようなケースでは、2人目の育児休業開始日を基準とするのではなく、1人目の育児休業を開始した(またはその前の産休等を開始した)時点を基準として、「過去2年間」の加入期間を再確認します。
つまり、1人目の育休を取得できた時点での加入期間が、2人目の育休でも(原則として)有効とみなされる形になります。
【特例措置】
ただし、上記の基本的な考え方でも要件を満たせない場合や、個別の状況によっては、さらに前の期間に遡って判断する特例が適用される可能性もあります。 判断に迷う場合は、必ず管轄のハローワークや社労士に確認してください。
注意点②:給付金の計算のもとになる「賃金」はいつのもの?
続けて育休に入る(復職期間がない)場合、2人目の育児休業給付金の支給額計算の基礎となる「休業開始時賃金日額」は、原則として1人目の育児休業給付金と同じ賃金額に基づいて算定されます。
育児休業給付金の額は、育児休業開始前の6か月間の賃金を基に計算されます。
1人目の育休から続けて2人目の育休に入る場合、その間には賃金支払い実績がないため、2人目の育休開始時点での賃金日額を新たに計算することはできません。
そのため、1人目の育休開始時に算定された賃金日額が、引き続き2人目の給付額計算にも用いられるのが原則的な扱いです。
【注意】
もし、1人目の育休後に一度職場復帰し、一定期間(原則6か月以上)働いてから2人目の育休に入る場合は、その復職後の賃金実績に基づいて、新たに賃金日額が計算され、給付額が変動する可能性があります。
注意点③:申請手続きで気をつけることは?(必要書類・タイミング)
2人目、3人目の育児休業給付金の申請手続きも、基本的には1人目と同様に、事業主(会社)を通じてハローワークに行います。 従業員から育児休業の申し出があったら、改めて申請書類を準備し、提出する必要があります。
【手続き上の主なポイント】
| 改めて申請が必要 | 1人目の受給資格が自動的に継続されるわけではありません。2人目の子の育児休業開始に合わせて、新たに受給資格確認と支給申請が必要。 |
| 提出書類提出書類 | 初回申請に必要な書類(受給資格確認票・初回支給申請書、賃金月額証明書、母子手帳の写し等)を基本的に再度提出。ただし、賃金月額証明書など一部書類は、賃金変動がない場合など特定の条件下で提出が省略できるケースもある。 |
| タイミング | 1人目の場合と同様、原則として育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに初回申請を行う。 |
注意点④:「育休の延長」と上の子の保育園利用の関係
「上の子(1人目)が保育園に入れなかった」という理由は、原則として、下の子(2人目)の育児休業給付金の支給期間延長の理由としては認められません。
育児休業給付金の延長(1歳6か月または2歳まで)が認められるのは、現在養育している子(=今回の場合は下の子)自身が保育所に入れない等の理由がある場合に限られます。
例)2人目の子の1歳の誕生日時点で、2人目の子自身が保育所に入所できない場合に延長が可能です。1人目の子の保育状況は、直接的な延長理由とはなりません。
Q&A:2人目・3人目育休に関するよくある質問
Q: 2人目・3人目の育休でも「パパ・ママ育休プラス」は使えますか?
2人目・3人目のお子さんであっても、配偶者が子が1歳に達する日以前に育休を取得しているなど、制度の利用要件を満たせば、支給期間を子が1歳2か月になるまで延長できます。
Q: 2人目の育休も、会社に改めて申し出る必要はありますか?
育児休業の取得は、法律上、子ごとに行うものです。2人目の子のための育児休業も、1人目と同様に、原則として休業開始予定日の1か月前までに会社(事業主)へ申し出る必要があります。育児休業給付金の申請とは別に、会社への育児休業申出の手続きを忘れないよう、従業員に案内してください。
Q: 1人目の育休から復職せずに続けて2人目の育休に入る場合、社会保険料の免除はどうなりますか?
2人目の育児休業についても、改めて事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することで、社会保険料の免除を引き続き受けることができます。免除期間は、2人目の子の育児休業を開始した月から、その休業が終了する予定日の翌日の属する月の前月までとなります。手続き漏れがないように注意が必要です。
育児休業給付金の支給金額は、原則として育児休業 開始前の賃金(給与)を基にした計算式で算出され、雇用保険から支給されます。
ここでは、育児休業給付金の基本的な計算式、2人目・3人目の場合の扱い、支給額の上限・下限、そして育休中に就労した場合の支給額調整について解説します。
基本の計算式(67%/50%ルール)
育児休業給付金の支給額は、「休業開始時賃金日額」に「支給日数」と「給付率」を掛けて算出されます。 給付率は、育児休業の期間によって2段階に設定されているのが特徴です(通称「67%/50%ルール」)。
支給額の基本的な計算方法は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」です。給付率は育児休業 開始からの期間によって異なり、具体的には以下の計算式で求められます。
| ・支給開始後180日目まで:支給額=賃金日額×休業日数×67%・支給開始後181日目以降:支給額=賃金日額×休業日数×50% |
休業開始時賃金日額とは、育休開始前6ヵ月間の賃金を180日で割った額です。
たとえば、育休開始前の6ヵ月間で120万円(月額20万円)の賃金を得ていた場合、休業開始時賃金日額は120万円÷180日=6,667円となり、1ヵ月の支給額は6,667円×30日×67%=13万4,000円となります。
6ヵ月以降の支給額は、6,667円×30日×50%=10万円となります。
月給20万円の人が満額で育児休業給付金をもらうと120万円を少し超えるくらいです
ただし、育児休業給付金の支給額には上限が設けられており、一定額を超えると、休業開始前賃金日額にかかわらず、一律上限額が支給されます。
2人目・3人目の場合の給付金額
2人目、3人目以降の育児休業で給付金を受ける場合も、基本的な計算方法は1人目の場合と同じです。 上記の計算式と67%/50%ルールが適用されます。
ただし、給付額の基礎となる「休業開始時賃金日額」の算定については注意が必要です。
◯1人目の育休から続けて2人目の育休に入る(復職しない)場合:
原則として、1人目の育休開始時に算定された賃金日額が、引き続き2人目の給付額計算にも用いられます。(詳細は「雇用保険から2人目、3人目の育休手当をもらえる条件と注意点」の注意点②をご参照ください。)
◯一度復職してから再度育休に入る場合:
復職後の賃金実績に基づいて、新たに賃金日額が算定され、給付額が変動する可能性があります。
上限額と下限額:もらえる金額には制限がある
育児休業給付金の支給額には、上限額と下限額が設けられています。 これは、雇用保険財政の健全性や、他の受給者との公平性を保つためです。
上限額と下限額は、計算の基礎となる「休業開始時賃金日額」と、1支給単位期間あたりの「支給額(月額)」の両方に設定されています。これらの金額は、毎年の賃金変動に合わせて、原則として毎年8月1日に見直されます。
【令和6年度(2024年8月1日~2025年7月31日)の上限額・下限額】 (※執筆時点(2025年4月)の情報。常に最新の情報をご確認ください。)
| 休業開始時賃金日額 | 上限:15,430円下限: 2,746円 |
| 支給額(月額)の上限 | 給付率67%の場合:310,143円給付率50%の場合:231,450円 |
つまり、休業開始前の賃金が非常に高い従業員であっても、上記の支給上限額を超える給付金を受け取ることはできません。逆に、賃金が低い場合でも、最低限の保障として下限額が設けられています(ただし、算出された賃金日額が下限額を下回る場合はその額となります)。
育児休業給付金や、産休中にもらえる出産手当金の具体的な金額や受給期間は、個別の状況によって異なります。以下のページでは、簡単な情報を入力するだけで、支給額や期間の目安をシミュレーションできますので、ぜひご活用ください。
【あわせて読みたい】
出産手当金・育児休業給付金の金額・期間の計算ツール
育児休業給付金の申請は、初回の手続きだけで完了するわけではなく、育児休業期間中は原則として2か月ごとに継続して申請する必要があります。そのため、初回と2回目以降では、それぞれ提出する書類や申請期限、申請の流れが異なります。
育児休業給付金の申請手続きは、基本的には以下の5つのステップで行われます。
【出産手当金と育児休業給付金の申請代行を全国スポット対応!】
社労士クラウドなら顧問料0円、業界最安値の料金で専任の社労士がスポットで申請代行!
- 複雑な賃金集計や書類作成の手間を大幅に削減してコア業務にしたい
- 正確な計算で過払いを防ぎ、追徴金等のリスク回避したい
- 法改正への確実な対応がしたい
\ 顧問料0円で全国対応!/
> 社労士クラウドのスポット料金・報酬を確認する
育児休業給付金の申請方法や必要書類については下記の記事で詳しくまとめています。
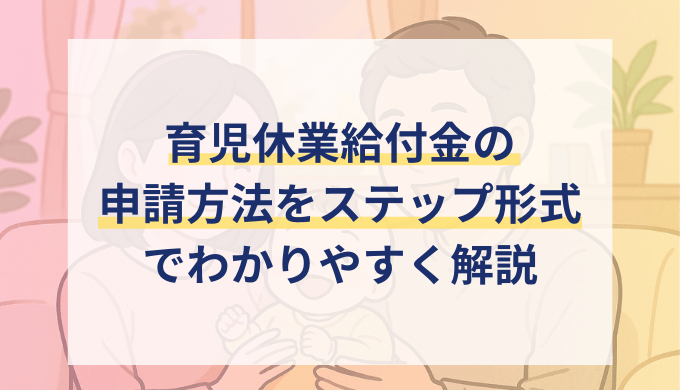 育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
育児休業給付金の申請方法を社労士が解説!必要書類や初回・2回目以降の手続きの流れまで
ここでは育児休業給付金(育休手当)のことで特に寄せられることが多い質問とその回答をまとめました。
手取り80%(実質10割)への引き上げはいつから?
いわゆる「手取り10割相当」への引き上げに関連する新しい給付金制度「出生後休業支援給付金」は、2025年(令和7年)4月1日から既に施行されています。
この「出生後休業支援給付金」は、一定の要件(※)を満たす場合に、通常の育児休業給付金(休業開始前賃金の67%)に加えて、休業開始前賃金の13%相当額が最大28日間上乗せして支給される制度です。 これにより、育児休業給付金と合わせて額面で最大80%が支給され、社会保険料の免除などを考慮すると実質的な手取り額が休業前の10割程度に相当することになります。
育児休業と産休(産前・産後休業)との違いは?
産休とは、出産するための準備期間と、出産後に身体を回復させる期間に休業できる制度です。産休は女性のみが取得できることが育児休業との大きな違いになります。
産休期間は、出産予定日の6週間前から出産後8週間までです。産前に関しては従業員が休業を申請した場合、労働させてはならないとしていますが、産後は本人からの申請に関係なく、休業させることが法律で義務付けられています。
ただし、産後6週間を過ぎて医師から許可が出た場合に限り、8週間を待たずに復職が可能です。
育休手当は、何ヶ月働いたらもらえる?
育児休業給付金(育休手当)をもらうためには、「何ヶ月働いたか」という単純な期間だけでなく、雇用保険の被保険者として認められる期間がどれだけあるかが重要になります。
具体的には、原則として育児休業を開始する日より前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業時間80時間以上の月)が通算して12か月以上必要です。
この「12か月」という要件を満たしていれば、例えば入社してから1年未満であっても、前職の期間を通算して受給できる可能性があります。
詳しい条件や計算方法、例外的な取り扱いについては、本記事の条件3:休業開始前の就業実績(雇用保険の加入期間)」で解説していますので、そちらをご参照ください。
育児休業給付金は転職後1年未満でももらえる?
転職後(または入社後)1年未満であっても、育児休業給付金をもらえる可能性はあります。
重要なのは、「入社してからの期間」ではなく、前述の「雇用保険の加入期間」の要件(原則、育休開始前2年間に被保険者期間が12か月以上)を満たしているかどうかです。
前職での雇用保険加入期間と現職での加入期間を通算して12か月以上あれば、入社後1年未満でも受給資格を満たす場合があります。(※ただし、前職退職後に失業手当の受給資格決定を受けていると通算できないなどの注意点があります。)
また、以前は有期雇用労働者について「入社1年以上の継続勤務」が育児休業取得の要件とされることがありましたが、法改正によりこの要件は撤廃されています(労使協定による一部例外を除く)。
したがって、転職直後や入社1年未満の従業員であっても、雇用保険の加入期間要件を中心に、他の支給要件を満たしているかを確認することが重要です。
育休中に会社を辞めたらどうなる?
育児休業給付金の受給中に会社を退職した場合、原則として退職日を含む支給単位期間までは、他の支給要件を満たしていれば給付金を受け取ることができます。 しかし、退職日の翌日以降は支給対象となりません。
育児休業給付金は、職場復帰を前提とした制度です。そのため、退職によって雇用保険の被保険者資格を喪失すると、それ以降の給付は行われません。
育児休業制度には休業の種類が2つあり、また休業そのものの要件と給付金の要件が別々に存在するなど、複雑に感じることが多いのが特徴です。
こうした複雑さを軽減し、従業員からの申し出に的確に対応するためにも、事業主の皆さまにはあらかじめ以下の内容を就業規則や育児休業規程に明記しておくことをおすすめします。
- 育児休業の対象となる従業員の範囲(雇用形態や勤続年数など)
- 取得手続きや変更手続きの方法・ルール(申し出期限、書面提出の要否など)
- 休業期間(原則期間・延長可能なケース、複数回取得のルールなど)
- 休業期間中の賃金支払の有無(無給・一部有給の扱い、社会保険料・雇用保険料の取扱いなど)
これらを事前に整理・周知しておけば、都度どう運用するか悩まなくても済み、従業員への周知漏れによるトラブルも予防できます。とりわけ、育児休業は従業員の取得権利に深く関わる制度ですので、書面化しておくことが企業にとっても安全策となります。
本記事では、育児休業給付金(育休手当)の制度概要、支給条件、対象期間、計算方法などを解説しました。この制度を正確に理解し適切に対応することが、従業員の取得権利に関するトラブル回避の第一歩です。
特に支給条件(雇用保険加入期間、休業中の就業・賃金制限等)、対象期間(原則1歳、延長条件、パパ・ママ育休プラス)、支給金額(計算方法、上限・下限、就労時調整)、そして対象外となるケースの把握は不可欠です。2人目・3人目以降や有期雇用従業員など、状況に応じた注意点も理解しておきましょう。
近年、法改正により「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」といった新制度も導入され、育休を取り巻く環境は大きく変化しています。
若い世代を中心に育休取得は「当たり前」の権利と捉えられており、育休が取得しやすい企業かどうかが、採用活動や人材定着にも直結する重要な経営課題となっています。育休取得状況の公表義務化なども進んでおり、企業側の積極的な姿勢が求められます。
育児休業制度は複雑であり、個別のケースで判断に迷う場合は、決して自己判断せず、管轄のハローワークや社労士といった専門家へ相談することも有効な手段です。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|