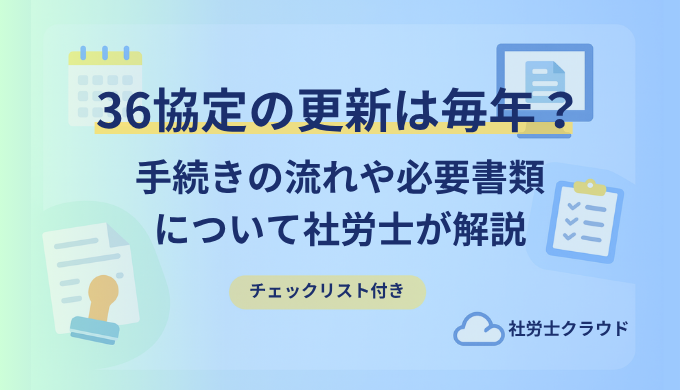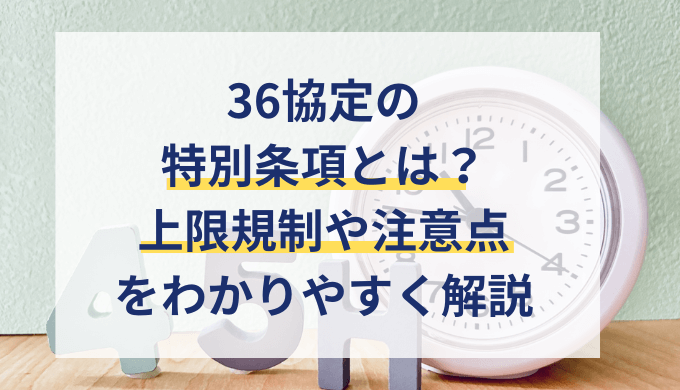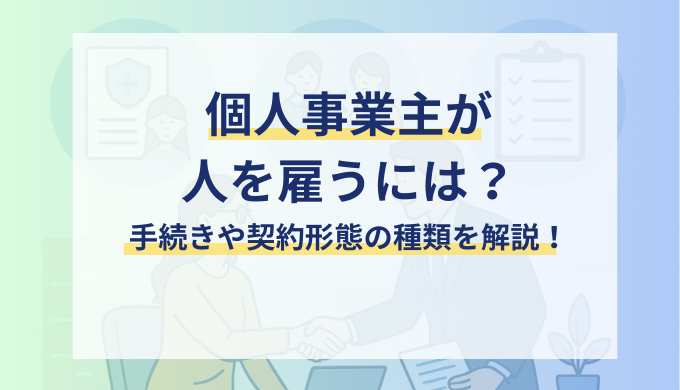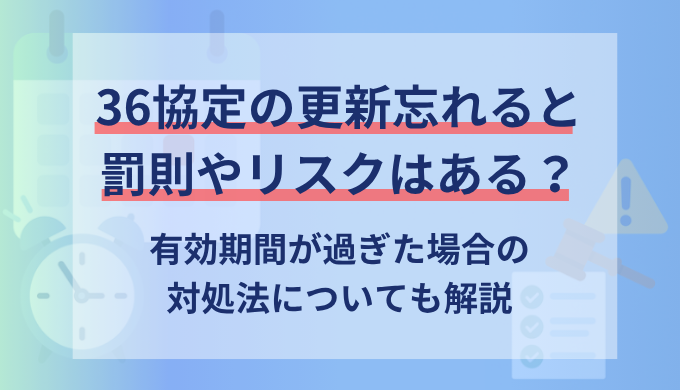事業の現場で残業や休日出勤が発生するなら、36協定の更新は毎年欠かせない手続きです。もし、うっかり更新を忘れたまま時間外労働や休日労働をさせると、法律違反となり罰則の対象になるだけでなく、企業の社会的信用を失うことにも繋がりかねません 。
まずは「いつまでに」「何を」「どこへ」届け出るかを正しく押さえることが重要です。
この記事では、36協定の更新が毎年必要な理由から、具体的な手続きの流れと必要書類、そして更新を忘れた場合の罰則やリスクまで、わかりやすく解説します。

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://sharoushi-cloud.com/社会保険手続きの自動販売機|全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】の運営者|懇切丁寧・当日申請・フリー価格・丸投げOK|3,000社以上の事業主様や顧問先の社保周りを解決されたい士業の先生にご利用頂いており、顧問契約も可能です|リピーター率8割以上
36協定の更新は、企業の労務管理において年に一度の重要な義務です。「去年と同じ内容だから…」と安易に考えていると、思わぬ法律違反に繋がりかねません。
まずは、なぜ36協定の更新が毎年必要なのか、その基本から正しく理解しておきましょう。
そもそも36協定とは?
36協定(サブロクきょうてい)とは、法律で定められた労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働(残業)や、法定休日の労働を従業員に命じるために、会社と労働者の代表者との間で締結する取り決めのことです 。
この取り決めは、労働基準法の第36条で定められていることから「36協定」と呼ばれています 。
重要なのは、この協定を労働基準監督署へ届け出て、はじめて法的な効力が生まれるという点です 。協定書を社内で作成しただけでは不十分で、届出のないまま残業を命じることは法律違反となり、罰則の対象となります。
協定には、対象期間(多くは1年)、時間外労働をさせる具体的な理由、延長できる時間の上限などを明記します。
例えば「決算期の繁忙対応のため、月45時間・年360時間の範囲で残業を命じることがある」といった形です。
残業や休日労働を適法に行うために、毎年内容をきちんと見直し、届け出ることが会社と従業員の双方を守ります。
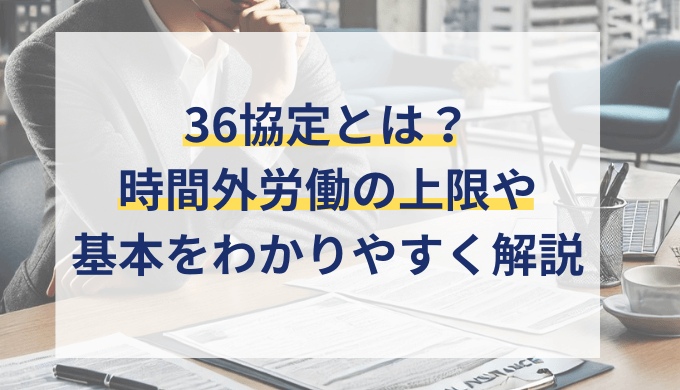 36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36(サブロク)協定とは?時間外労働の上限規制を基本からわかりやすく社労士が解説
36協定の更新が必要な理由
36協定を原則として毎年更新するのは、従業員の健康を守り、長時間労働が常態化することを防ぐという大切な目的があるからです 。
法律は、会社と従業員が定期的に労働時間の実態を点検し、合意内容を見直すことを求めています。これにより、協定内容が形骸化し、実態と合わなくなることを防いでいるのです 。
前年度の残業実績や組織変更、新しい業務の開始などを踏まえ、上限時間や対象業務の範囲が現状に適しているかを確認します。もし上限に近い残業が続いている部署があれば、業務の進め方や人員配置を見直すきっかけにもなります。
毎年の更新は、単なる形式的な手続きではありません。実態に合った、安全で無理のない働き方へと改善していくための重要な「点検の機会」なのです。
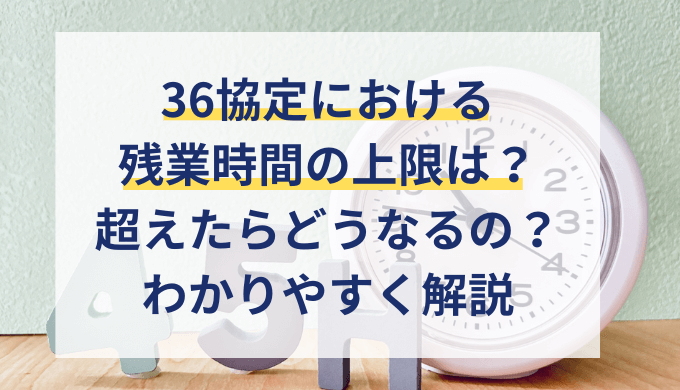 36協定における残業時間の上限(月45時間/年360時間)や超えたらどうなる?社労士が解説
36協定における残業時間の上限(月45時間/年360時間)や超えたらどうなる?社労士が解説
36協定の更新手続きの提出期限(いつから更新できるの?)
36協定の更新で最も注意すべきなのが「期限」です。協定の有効期間が満了する日(=新しい協定の効力が発生する日の前日)までに、労働基準監督署への届出を完了させる必要があります 。
36協定は、労働基準監督署に届け出て受理されて初めて法的な効力を持ちます 。そのため、 1日でも空白期間が生じると、その間の残業や休日労働はすべて違法となってしまいます 。
この「切れ目」を作らないために、有効期間が満了する1ヶ月前には更新手続きを開始するなど、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
特に、労働者代表の選出や内容の協議には時間がかかる場合があるため、早めに着手しましょう。
36協定の更新は、大きく分けて5つのステップで進めます。特に最初の「労働者代表の選出」は、協定全体の有効性を左右する最も重要なポイントです。
一つひとつの手順を確実に実行し、法律違反のリスクをなくしましょう。
まずは準備から!36協定の更新手続きに必要な書類一覧
36協定の更新手続きをスムーズに進めるには、最初に必要書類をそろえておくことが近道です。提出するものと社内で作成・保管するものを分けて整理しておきましょう。
| 書類の分類 | 書類名 | 主な用途と注意点 |
| 労働基準監督署へ提出 | 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) | 協定書の内容を転記して提出する正式な書類です。代表者の適格性チェック欄のチェック漏れや、対象期間の記載ミスは差し戻しの原因になりやすいため注意が必要です。 |
| 社内で作成・保管 | 36協定書(原本) | 会社と労働者代表で合意した内容の根拠となる文書です。届出書と兼用も可能ですが、その場合は労使双方の記名押印または署名が必要になります。 |
| 社内で作成・保管 | 労働者代表の選出記録 | 告知文、投票用紙、議事録など、「民主的な方法で公正に選んだ」という事実を示す証拠一式です。これが曖昧だと協定全体が無効になるリスクがあります。 |
| 社内で作成・保管 | 協議の経緯メモ(任意) | 打合せ日、参加者、決定事項などを簡潔に記録しておくと、後日の社内説明や監督署の調査対応がスムーズになります。 |
| 手続き後に保管 | 36協定届の控え(受理印または受付完了通知があるもの) | 届出が完了したことの証明であり、少なくとも3年間は保管する義務があります。紙とデータの両方で保存しておくと管理がしやすくなります。 |
必要な書類が確認できたところで、続けて、具体的な更新手続きの流れを5つのステップで見ていきましょう。
ステップ1:労働者代表の選出(不適正だと無効)
36協定の更新手続きで、最初に行うべき最も重要なステップが「労働者代表の選出」です。この代表者の選び方が正しくないと、締結した協定そのものが無効になってしまうため、細心の注意が必要です。
代表者は、パートやアルバイトを含む、事業場で働くすべての労働者の過半数を代表する人でなければなりません 。
選出にあたっては、投票や挙手、話し合い、Webアンケートなど、全員が参加できる民主的な方法で行う必要があります 。
会社が一方的に特定の人を指名したり、親睦会の代表などを自動的に選任したりすることは認められません 。
また、部長や工場長といった「管理監督者」は、経営側の立場にあるため労働者代表にはなれません 。
誰が、いつ、どのような方法で選ばれたのか、そのプロセスがわかるように告知文や議事録、投票結果などを記録としてきちんと保管しておくことが、協定の正当性を証明する上で極めて重要です 。
ステップ2:協定内容の協議(協定書)の作成
労働者代表が決まったら、会社と代表者とで協定内容を具体的に協議し、合意した内容を「協定書」として書面にまとめます。この話し合いは、会社が一方的に条件を押し付けるのではなく、労使双方が納得できる内容を目指すことが大切です 。
協定書には、主に以下の項目を具体的に明記する必要があります 。
- 協定の有効期間(通常は1年間)
- 時間外労働をさせる具体的な理由(「決算業務」「臨時の受注対応」など)
- 対象となる業務の種類と労働者数
- 延長できる時間の上限(原則として月45時間・年360時間)
- 休日労働をさせる日数や始業・終業時刻
前年度の内容を安易に流用するのではなく、現在の業務の実態や残業時間の実績に合わせて、毎年内容を慎重に検討しましょう。
もし、突発的な受注増や納期の逼迫など、やむを得ない事情でこの上限を超える可能性がある場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶこともできます。
特別条項を結ぶと上限を年720時間まで延長できますが、その分、従業員の健康を守るための措置を講じるなど、より厳しいルールが課せられます。
ステップ3:36協定届の作成(新様式2021年4月以降)
協議して作成した協定書の内容をもとに、厚生労働省が定める様式の「時間外労働・休日労働に関する協定届」(様式第9号など)を作成します 。
2021年4月1日から新様式での届出が必須となっているため、必ず最新の様式を使用してください 。新様式には、労働者代表が適正に選ばれたかを確認するチェックボックスが設けられており、このチェックは必須です 。
また、新様式では届出書への使用者の押印・署名は原則不要となりました 。ただし、この届出書を協定書と「兼ねる」場合は、労使双方の合意の証として記名押印または署名が必要になるため、注意が必要です 。
参照)時間外・休日労働に関する協定届(36協定届) | 厚生労働省
ステップ4:労働基準監督署への届出
作成した36協定届は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。窓口への持参、郵送、または政府の電子申請システム「e-Gov」を利用したオンライン申請が可能です 。
ここで最も重要なのは、36協定は、届出が受理されて初めて法的な効力を持つという点です 。
協定の有効期間が始まる日(起算日)の前日までに、必ず提出を完了させましょう。郵送や電子申請は便利ですが、処理日数を見込んで、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが大切です。
ステップ5:従業員への周知と協定書の保管
労働基準監督署へ届け出た後も、やるべきことがあります。締結した協定の内容は、事業所の見やすい場所への掲示、書面での交付、社内イントラネットへの掲載などの方法で、全従業員に周知する義務があります 。
この周知を怠ると、協定の有効性が認められない可能性もあります。また、届け出た協定書の控えや、代表選出の記録といった関連書類は、有効期間が満了した後も3年間保存しなければなりません。
更新のたびに「代表選出→協議→届出→周知→保存」の流れをチェックリスト化しておくと、担当者が変わっても確実な運用ができます。
「もし36協定の更新を忘れてしまったら…」と不安に思う担当者の方もいるかもしれません。
結論からお伝えすると、更新忘れのリスクは非常に大きく、会社の信用問題にも発展しかねません。
更新が切れている期間の残業や休日労働は、法の根拠がない違法な状態となります。もし更新忘れに気づいたら、直ちに時間外・休日労働を停止し、速やかに協定の再締結と届出を進めることが重要です。
ここでは、更新を忘れた場合にどのような罰則やリスクがあるのかを具体的に解説します。
36協定違反した場合の罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
36協定を届け出ずに法定労働時間を超える残業をさせたり、協定で定めた上限時間を超えて労働させたりした場合、労働基準法違反となります。
この場合、法律では「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という重い罰則が定められています 。これは単なる行政指導ではなく、刑事罰であるという点を認識しておく必要があります。
罰則の対象は、会社だけでなく、労務管理を直接担当する事業主や人事部長、工場長なども含まれる可能性があります 。また、更新切れの期間に発生した残業についても、割増賃金の支払い義務がなくなるわけではないため、未払いがないかどうかも確認が必要です。
36協定違反した場合のリスク(企業の信用失墜、労基署の対応)
罰則に加えて、企業経営に直接的なダメージを与える以下のようなリスクも存在します。
◯企業名の公表
違反が悪質であったり、労働基準監督署からの是正勧告に繰り返し従わなかったりした場合、厚生労働省のウェブサイトで企業名が公表されることがあります 。一度公表されると、その情報はインターネット上に残り続け、企業のブランドイメージを大きく損ないます。
◯事業運営への影響
企業名が公表されると、公共事業の入札参加資格が停止されたり、ハローワークでの求人が受理されなくなったりと、事業運営に直接的な支障をきたす可能性があります。
◯信用の失墜
「法令を守らない会社」というイメージは、取引先や金融機関、そして従業員からの信用を失うことに繋がります。優秀な人材の確保が難しくなったり、離職率が上がったりする原因にもなり得ます。
このように、違反が発覚すると、企業名公表という直接的なペナルティに留まらず、事業運営や社会的な信用といった、企業の存続に関わる部分にまで深刻な影響が及ぶ可能性があります。
被害を最小限に抑えるには、更新忘れに気づいた段階で原因を分析し、担当者の二重チェック体制や更新スケジュールの事前通知といった再発防止策を講じることが重要です。
「36協定違反はバレる?」監督署の調査実態
「少しくらいならバレないだろう」という考えは非常に危険です。労働基準監督署は、以下のような形で事業場への立入調査(臨検監督)を行う権限を持っています。
- 定期監督: 特定の業種や社会問題(例:長時間労働)などを対象に、計画的に行われる調査 。
- 申告監督: 従業員やその関係者からの通報(申告)に基づいて行われる調査 。
- 災害時監督: 労働災害が発生した際に、その原因を究明するために行われる調査 。
特に、従業員からの通報に基づく「申告監督」は、具体的な情報をもとに行われるため、違反が発覚する可能性が極めて高いと言えます。
調査では、タイムカードや賃金台帳、36協定届などの書類が厳しくチェックされ、矛盾があれば是正勧告が出されます 。
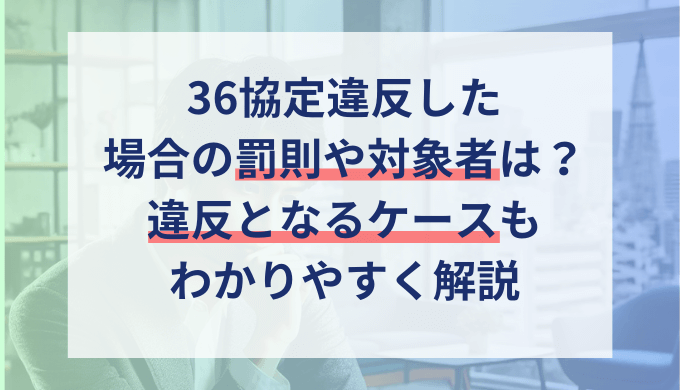 36協定に違反するとどうなる?罰則や発覚するケースを社労士が解説
36協定に違反するとどうなる?罰則や発覚するケースを社労士が解説
36協定の更新は、毎年繰り返す手続きだからこそ、無意識のうちに形骸化しやすいという落とし穴があります。「去年と同じでいいだろう」という安易な判断が、思わぬところで協定の無効や法律違反に繋がることも少なくありません。
ここでは、更新時に特に見落としがちな6つの重要チェックポイントを解説します。自社の運用が適切かどうか、この機会にぜひ点検してみてください。
労働者代表の選出プロセスは形骸化していないか
36協定の有効性を根底から揺るがすのが、労働者代表の選出プロセスの不備です。毎年更新するからといって、「去年と同じ人で」と自動的に再任するのは非常に危険です。
協定を更新する都度、改めて全労働者(パート・アルバイト含む)に「36協定締結のための代表者を選出する」という目的を明確に伝え、投票や挙手といった民主的な手続きで選出し直す必要があります 。もちろん、部長や工場長などの管理監督者は代表にはなれません 。
「いつ」「誰が」「どのような方法で」選ばれたのか、その客観的な証拠となる告知文や議事録、投票結果などの記録をきちんと保管しておくことが、協定の正当性を証明する上で不可欠です 。
協定内容は「去年のまま」で実態と一致しているか
前年度の協定内容をそのままコピー&ペーストで更新するのは、実務上のリスクを伴います。この1年で組織改編や部署名の変更、新たな業務の発生はなかったでしょうか。協定内容と実態が乖離していると、いざという時に協定が無効と判断される可能性があります。
前年度の時間外労働の実績データなどを参考に、対象となる従業員の範囲、時間外労働をさせる具体的な理由、延長時間の上限などが、現在の業務実態と一致しているか、毎年必ず見直しを行いましょう。恒常的に上限近い残業が発生している部署があれば、それは業務プロセスや人員配置を見直すサインかもしれません。
特別条項が常態化していないか?健康確保措置は機能しているか
臨時的・突発的な事情に対応するための「特別条項」が、毎月のように発動されている状態は「常態化」とみなされ、違法となります 。特別条項付き36協定を結ぶ場合、月45時間を超えることができるのは年に6ヶ月までという上限があります 。
前年度の発動回数や対象部署を振り返り、その理由が本当に「臨時的」であったかを検証することが重要です。
また、特別条項を適用する従業員に対しては、医師による面接指導や代休の付与といった「健康確保措置」を講じる義務があります 。協定に記載するだけでなく、その措置が実際に機能しているか(対象者が利用しやすい仕組みになっているか)まで点検・改善しましょう。
法改正・新様式の反映は最新ものへ対応しているか
労働関連の法律は頻繁に改正されます。古い様式の協定届を使い続けたり、最新の法改正の内容を反映していなかったりすると、届出が受理されない、あるいは協定が無効と見なされる可能性があります。
2021年4月以降は、労働者代表の適格性チェックボックスが追加された新様式での届出が必須です 。また、2024年4月からは建設業、自動車運転の業務、医師にも時間外労働の上限規制が適用されています 。
自社が該当するかどうかを含め、常に厚生労働省のウェブサイトなどで最新情報を確認し、それに準拠した協定内容と様式で届け出ることが不可欠です。
更新後の周知と証跡管理を徹底すること
協定を更新し、届け出ただけでは義務を果たしたことにはなりません。その内容を全従業員に周知する義務があります 。周知を怠ると、協定の効力そのものが認められない可能性があります。
事業所の見やすい場所への掲示、書面での交付、社内イントラネットへの掲載など、全従業員がいつでも内容を確認できる状態になっているか、改めて確認しましょう。
また、コンプライアンスの証明責任は企業側にあります。締結した協定書、受理印のある届出の控え、そして代表選出プロセスの記録は、法定の3年間、いつでも提示できるよう確実に保管・管理する体制を整えましょう。
有効期間の起算日とスケジュールの確認(切れ目防止)
36協定の有効期間に1日でも空白期間が生じると、その期間中に行われた時間外労働は全て違法となります。
例えば、3月31日で有効期間が満了する協定の更新手続きが遅れ、新しい協定の効力発生が4月2日になった場合、4月1日に行った全ての時間外労働は違法行為となってしまいます。
このような事態を防ぐため、有効期間が満了する少なくとも1ヶ月以上前から更新手続きを開始し、協定の開始日(起算日)までに労働基準監督署での受理が確実に完了するよう、余裕を持ったスケジュール管理を徹底することが重要です。
年間スケジュールに「36協定更新」をタスクとして組み込み、担当者を複数設定するなどの工夫で、更新漏れのリスクを減らせます。
36協定の更新手続きについては、多くの担当者が共通の疑問を持っています。ここでは、特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
有効期間は1年でないとダメ?起算日はいつ?
法律で有効期間が1年に限定されているわけではありません。しかし、労働者の健康確保と労働時間管理の観点から、行政は「有効期間は1年間とすることが望ましい」との見解を示しており、実務上の基本となっています 。
1年より長い期間を設定すると、労働時間の実態と協定内容が合わなくなるリスクがあり、労働基準監督署から指導を受ける可能性もあります 。
協定の開始日である「起算日」は、会社の事業年度や給与の締切日など、管理しやすい日を任意に設定できます。重要なのは、一度決めた起算日を基準に、毎年切れ目なく更新手続きを行うことです。スケジュールの詳細は「4-6. 有効期間の起算日とスケジュールの確認」も参考にしてください。
自動更新の条項は使える?
協定書に自動更新条項を設けること自体は可能ですが、実務上のメリットはほとんどなく、おすすめできません 。
たとえ自動更新条項があっても、更新の際には「労使双方から異議がなかったことを証明する書面」の添付を求められるケースが多く、結局は毎年同じような手間がかかります 。
むしろ、労働環境の変化や法改正を毎年見直すという法の趣旨に反し、協定が形骸化するリスクの方が大きいため、1年ごとに内容を協議し、再締結・再届出を行うのが最も確実で望ましい方法です。
複数の事業所がある場合は?(本社一括届出)
政府の電子申請システム「e-Gov」を利用する場合に限り、本社が一括して各事業場の36協定届を届け出ることが可能です 。
各事業場で個別に労使協定を締結した後、本社が必要書類(一括届出事業場一覧CSVなど)を添付して電子申請することで、事務負担を大幅に軽減できます 。
ただし、注意点が2つあります。第一に、届出は本社がまとめても、協定の「締結」そのものは各事業場で行う必要があること 。第二に、事業場名や所在地などの転記ミスが起こりやすいため、提出前のチェックが重要です。
新様式のポイントは?署名・押印は必要?
2021年4月から導入された新様式の最大のポイントは、労働者代表の適格性を確認するチェックボックスが新設されたことです 。ここを空欄のまま提出すると差し戻しの原因になります。
もう一つのポイントは、労働基準監督署へ提出する36協定届への使用者の押印・署名は原則不要になったことです 。
ただし、この届出書を社内で保管する協定書と「兼ねる」場合は、労使双方の合意の証として記名押印または署名が必要となるため、自社の運用方法に合わせて対応しましょう 。
36協定は、残業や休日労働を適法に行うための大前提となります。本記事で解説した、代表選出から協議、届出、周知・保存までの5つのステップを、毎年同じ手順で確実に実行できる体制を整えましょう。
更新が切れた状態での時間外・休日労働は法律違反にあたります。
罰則だけでなく、信用失墜や求人不受理など、事業運営におけるダメージも大きくなるため、協定の開始日前に受理されることを目標に、前倒しで進めることが重要です。
また、形骸化を避けるため、代表選出は毎年民主的に実施し、協定内容は前年度の実態に合わせて見直します。特別条項が常態化していないか、最新様式を使っているか、周知と証跡の3年保存はできているかも、必ず点検しましょう。
| ▼提出前の最終チェックリスト[ ] 代表者の適格性と選出記録は整っているか [ ] 期間・上限時間など届出書の記載に抜け漏れはないか [ ] 協定の開始日前に提出し、受理控えを取得できるか [ ] 協定内容の周知(掲示・配布など)は完了したか [ ] 関連書類(協定書、届出控え、選出記録など)の3年保存は設定したか |
もし、こうした手続きに不安がある、担当者がいない、差し戻しを避けたいといった場合は、専門家へ相談するのが最も確実です。
面倒な36協定の更新は「社労士クラウド」のスポット代行へ
「社労士クラウド」では、顧問契約は不要で、36協定の作成・届出といった手続きを1回から代行するスポットサービスを提供しています。
法改正に対応した正確な書類作成から電子申請まで、専門家が迅速に代行することで、事業主様や担当者様の負担を大幅に軽減します。さらに、毎年有効期限が切れる前に更新のご案内を無料で行っているため、「うっかり更新を忘れてしまった」というリスクもありません。
従業員が安心して働き続けられる体制づくりのために、ぜひ「社労士クラウド」の活用をご検討ください。

全国のあらゆる社会保険手続きと労務相談を
「顧問料なしのスポット」で代行するWebサービス【社労士クラウド】
懇切丁寧 ・当日申請・全国最安値価格| 3,000社以上の社会保険手続き実績|